浦上玉堂と琴
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
江戸期を代表する文人画家の浦上玉堂(一七四五~一八二〇、通称兵衛門、諱は弼、字君輔)と、明治の画家川合玉堂。まさかに、今もってこの二人の混同はあるまいが、岡山の支藩備中鴨方藩の中級武士であった玉堂は、中年以降武士を捨て、琴と丹青とをもって生きた。その遺作は、今は国宝に指定されるほどであるが、むしろその生前は、琴を酷愛した文人音楽家として有名であった。
この琴(きん、きんのこと。俗称七絃琴。現代中国語では古琴)というのは、世に言う普通の十三絃の箏(そう、そうのこと)ではなく、中国の文人が嗜む七絃の古琴であることは、多少とも中国学や江戸の文事を齧った者の間では周知の事柄であろう。
よく和漢の水墨画中に描かれた、いかにも訳有りげな高士や、それに伴う童子が細長い袋を抱えていたり、瀑布を前に岩に腰掛け、両膝に小さ琴を乗せている図柄、また君子四友という琴棊書画を題材とした画題などがあるので、大方は「ああ、あれか」と合点されるに違いない。
琴は、伝説の時代を起源とする中国最古の絃楽器である。以後、歴代の帝王や名だたる文人たちによって大切に引き継がれてきたが、その長い歴史の中で、儒の礼楽思想を根底に、遂次仏教さらには道教をも加味して、それまでの琴譜(減字譜)、演奏法、美学、製琴、製絃法などが整理され、混然一体、明代中期に至って「琴学」というジャンルに発展確立した。
中国の文人を憧憬した玉堂はこれらに倣って若い頃から琴に耽溺し、古今の琴書楽書を貪り読んだのだが、琴法は独学であったようである。しかし、江戸勤番の折り、文事仲間の井上金峨が後に幕府の医学館となった躋寿館館長の多紀藍渓と親しく、当時金峨は躋寿館の経営面を補佐していたので、その紹介をうけ、念願かなって玉堂は正式に琴学を藍渓に学ぶことになった。しかし、当時の藍渓は将軍家奥医師また、躋寿館との掛け持ちでお役目繁多。一方の玉堂は独学とはいえ既に一家をなした古楽家としての矜持もあり、その琴法授受は惜しくも二、三曲にして終わってしまった。
 「玉堂弾琴図」
『玉堂琴士集』寛政6(1794)年刊より
「玉堂弾琴図」
『玉堂琴士集』寛政6(1794)年刊より 『玉堂琴譜』(前集) 寛政3 (1791)年刊より
玉堂琴譜 備前玉堂先生著 讃岐 張元徽琹翁按
商音我駒
27
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第2話
東川琴門の逸材 多紀藍溪
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
浦上玉堂の琴の師、多紀藍溪(たきらんけい)(一七三一~一八〇一)、藍溪とはその号で、名は元悳(もとのり)、字仲明、幼名は金之助で、長じて安長、後に安元と改めた。
藍溪の遠祖は丹羽国の出で丹羽氏である。よってまま向柳原多紀氏の家系も丹羽氏を名乗る。父元孝も藍溪もそのまた後裔も、代々奥医師に任官した名家である。奥医師とは当時の医官の最高峰で、将軍のお脈を直接診ることができた。
安永五年法眼に叙せられ、寛政二年には法印となり広寿院と称し、後には永寿院と改院したため、人は藍溪を多紀永寿院と尊称した。多紀家の医塾躋寿館(せいじゅかん)の第二代目の館長でもある。寛政三(一七九一)年に躋寿館が幕府直轄の医学校となった経緯は、林家の昌平黌、後の昌平坂学問所に大略準ずる。
さて、藍溪の表向きは今でいう厚生労働大臣と日本医師会会長、東大医学部部長などを兼任したような文字通りの国手で、当時の日本医学界の頂点であった。
漸々多忙となる日々を送る館長の藍溪国手にしてみれば、躋寿館の経営万事を任し、学政の総理を委託していた井上金蛾の周旋によらばこそ、止む無く異色の画人玉堂に接したが、琴の正伝を得ぬまでも玉堂もまた蘭溪に劣らぬ酷しい琴癖を持つ人に知られた高士であって、一時は貴重な自己の時間を割いてまで、自家薬籠中の東皐心越禅師(後出)四伝の琴学を師承せんとしたこの玉堂に、如何なる気持ちで藍溪は対し初学八法を授けたのか、今となっては知る術もないが、筆者屡(しばしば)の実体験と重なり、非常に興味深い。
当初、家号を多紀氏と改称した中興の家祖元孝の五男坊として生まれた藍溪であったので、比較的安穏とした状態で、少年の頃から好きな琴を江戸第一の琴家小野田東川(一六八二~一七六三)の膝下で心行くまで学んでいたが、長ずるに及び東川門数百人の中でも能手と喧伝され、元服の後には東川門四天王の第一に挙げられる琴人となった。
東川は、門下中でもこの藍溪の才能を殊に外愛で慈しんでいたようで、東川は没するに際し、藍溪に東皐心越伝来の存古琴一面、鶴氅衣(かくしょうえ)、心越と竹洞二師子の肖像、さらには琴案を遣ったほどである。しかし、長兄は病に倒れ、次兄は父元孝の実家福嶋氏を嗣ぎ、三、四男は相次いで夭折したため、多紀氏第六代の正統を継ぐ羽目となり、「……多務劇職、絲桐に従事すること能ハす……」(『閑叟雑話』後出)となってしまった。
「蘭溪琴の師小野田東川像」
膝上に琴を抱くのが東川翁
『東都嘉慶花宴集稿』より 宝暦2(1752)年原刊 1991年東京琴社復刻
「鶴氅衣之図」
(明僧心越所製 小野田東川所蔵) 『蒹葭堂雑録』より 安政6 (1859)年原刊
「明僧心越製す所、小野田東川所蔵」と記されるので、蘭溪が東川から遣られた鶴氅衣(琴服)と重なる。
江戸の琴客は弾琴に際し、必ず鶴氅衣を着し、芙蓉巾を戴き、香を炊き、琴案上で正式に琴を弾じた。
※本稿中の図版で、とくに明記しないものは筆者所蔵
34
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第3話
絃外余響・甲州編
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
拙稿は漸次江戸の琴系譜を辿り、玉堂―藍溪―東川と溯行中であるが、閑話休題。
たまたま筆者の本誌新連載と号を同じうして、偶然にも「素封家渡邉青洲の書画・遺品展」が掲載紹介された。筆者はそれに先駆け特別展観をこれまた偶然に別誌上で知り、早速甲府駅前の山交まで出掛けた。その理由たるや次の独言であるが、私事に纏わるため、大方のご寛恕を乞わねばならぬ。
展覧会席上、渡邉青洲(一八四〇~一九一一、市川大門町初代町長)翁の三男陸三(一九〇二~一九八〇、英文学者)氏令夫人のまさ子刀自と約四半世紀ぶりに邂逅し、無沙汰を大いに詫びた訳であるが、筆者の未だ若かりし当時、江戸の琴学とその系譜を調査する中にも、甲府を中心に、『琴学発揮』(未刊)を著した山県大弐(一七二五~一七六七)関連の音楽文献を漁っていた。
大弐著の楽書ではないが、東大図書館で閲覧した琴譜に「青洲文庫」の蔵書印があり、青洲文庫の古目録にも数件の楽書とその中に確か『東皐琴譜』も混在した。文庫そのものは震災後全て東大に委譲済みで、この中の書籍を閲覧したと承知していたが、ここに渡邉青洲翁の見識を知り、機会があれば何時かは故の青洲文庫の故郷即ち、市川大門を尋ねたいと思っていた。
さらに以前の話で、昭和四十年代初め一九六〇年代半ば、筆者苦学中のこととて、とある日バイト先での雑談中に、「山県大弐の楽」との話題に及ぶや、別課主任の故今村富士子女史が、大弐先生のことをご存じの上、さらにご実家が甲府在の十日市場で、甲州の郷土史全般に明治末年の頃から熱心に取り組み、山県大弐研究の先達かつ権威であられた村松志孝(一八七四~一九七三、号蘆洲)翁ともご家族ぐるみでごく親しくされている事を伺った。
この志孝翁も市川大門の産で、女史の想い出中には、志孝翁はいたって健脚で、一日、川向こうの市川大門からわざわざ徒歩で十日市場のご実家まで「大弐先生の琴だ」と言って、琴箱をさも大事そうに抱えて来られ、持参した古い七絃琴を見せられたことを覚えておられると、筆者にお話し下さった。今にして思えば何と言う奇縁であったろう。そして、「機会をみてご紹介しましょう」といわれている内にも数年を経てしまい、昭和四十八年五月、惜しくも志孝翁は九十九歳で大往生され、直接その警骸に接する機会は永遠に失われてしまった。
『琴学発揮』 山県昌貞著
宝暦13(1763)年序
山県大弐は琴を小野田東川に学び、本書を著したが、未刊本で数本抄写本が伝わるのみである。自筆本は山梨県の文化財に指定されている。
奇しくも師の東川はこの年没し、大弐も4年後に刑場の露と消えた。世に謂う明和の疑獄である。
琴學發輝下 峡中 山縣昌貞著
知新
凡調絃法。當以文武絃應管色。乃爲得中聲。然今之管色。鳧鐘以下。皆當古律倍聲。故越平二管。必以子聲當之。或以宮商絃應中聲。依法調和。則皆得其正矣。唯黃鐘以宮商絃爲倍。文武絃爲中。不則小絃不勝其急也。但黃鐘與越平。緊縵頗殊。不
「村松志孝翁小照」壮年の頃
『甲州叢話』より 昭和11(1936)年刊
村松志孝は明治7年市川大門に生まれ、郷里の修斉学舎、英和学館、次いで東京の二松学舎で学んだ。著作は20種以上ある。
37
△目次TOP↑
秋月※山県大弐『琴学発揮』については次を参照:山縣大貳1763年『琴學發揮』
瘦蘭齋樂事異聞 第4話
絃外余響・甲州編 二
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
以前、筆者に琴の演奏を依頼され令夫人のご夫君が偶然にも甲府の柳葉氏で、『山県大弐』掲載琴の旧蔵者であった。該琴のことをお尋ねすると、「東京に避難させたため、却っ戦火に焼かれてしまった」とのこと。胴内墨書銘に「明和元年甲申六月京橋銀座四丁目柏屋長右衛門調製」とあったらしい。写真の琴は、漆されない(拭き漆のみ)日本でいうところの白木の素琴仕立てで、松村志孝翁縁のものと同一らしい。『琴学発揮』の序文には黒漆琴と明記するので、大弐先生はもう一面所蔵していたことになる。
その後今村女史は志孝翁の遺詩集『蘆洲詩集』や『甲州正気歌』などを八方手を尽くして入手され、筆者にご供与下さったばかりか、女史ご実兄でご当主の河西鉄之助氏にその経緯を説明され、氏のご協力を得てさらに紹介を受け、翁ご子息で鏡花の研究家村松定孝先生を尋ねたり、以降、余裕があれば随意に峡中峡南と飛び回ったもので、さらに念願叶って市川大門の萩苑草舎まで足を伸ばせば、渡邉陸三先生ご夫妻は一介の貧書生を心よく迎えて下さった。
萩苑草舎は、旧は桐華書屋という青洲翁の特別な離れ座敷であったが、戦後直ぐ(農地解放)に移築され、陸三先生ご夫妻がお住まいで欧米文学を研究しておられた。志孝翁ご親子は陸三先生とも大変昵懇で、しょっちゅうこの書屋に出入なされ、現在、萩苑草舎の苑に植わる桐樹も、志翁宅から移植したものだそうな。
次に『蘆州詩集』から、志孝翁と陸三先生ご一家とのご高誼と、志孝翁ご母堂の月琴に纏わる二詩をご紹介して、この懐古の扉を閉じよう。
渡邉雅契を訪う
承襲す桐華書屋の名
遷居するも塵外の鳥声清し
青洲愛好の遺品存す
追憶す風流高雅の情
家母遺愛の月琴に題す
母儀の庭訓厳に堪えず
円琴を弾じ得て能く恬を養う
追憶すれば清音猶耳に在り
温容髣髴として涙痕霧う
荻苑草舎では一宿一飯のご恩義に恐縮し、白鷹の超特急を特に美味しいと温顔を綻ばせた陸三先生に、携えた琴(七絃古琴)を旅の徒然に奏で、お慰めした想い出も懐かしい。現在また、九十歳に近いまさ子刀自の懐かしい土地訛りに連れられ、今は亡き今村(再婚され吉岡姓となられたが)女史とそのご一家の甲州弁も想起され、優しくも厳しい時日の流れに、唯々目頭が潤むばかり……。
 「山県大弐先生遺愛の琴と琵琶」
「山県大弐先生遺愛の琴と琵琶」町田柳塘著『山県大弐』 明治43(1910)年刊より
「月琴」
清朝中後期蘇州製
明治7(1874)年生まれの村松志孝の幼少時は、当然江戸の名残がそこかしこにあった時代で、翁のご母堂も折節月琴を嗜んだ。
幕末から明治中期にかけての月琴の爆発的な流行に伴い、初期には清楽(清朝の俗曲)のみ学んでいたものが、後期には日本の俗曲をも併奏するようになり、徐々に日本化した。
図版の月琴は、長崎に清楽を伝えた清朝中後期の文人江芸閣(こううんかく)愛用の名器。
「盧洲詩集内題」
昭和55(1980)村松家私家本
村松志孝は東京の二松学舎を卒ると芝に顕光閣という出版社を設立、著作活動に入り、帰郷後郷里に南陽学院を建学し、特に郷土の人材育成に力を尽くした。
32
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第5話
聖堂の秀才
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
本誌8月号「書道界ニュース」及び「論壇」の、水戸の咸章堂の記事に触発され、拙稿は早くも陋に迷い込む。元々樂事異聞(がくじいぶん)とは、筆者のこれまでの音楽生活を通しての、他愛のない聞き齧りであるからして、そう大手を振るって大道を闊歩するようなものでない。
水戸は、本邦琴学中興の祖東皐心越(とうこうしんえつ)禅師(一六三九~一六九五)終焉の地で、そのパトロン天下の副将軍徳川光圀(一六二八~一七〇〇)公のお膝下であるが、水戸に琴道の拓けたのは却って遅く、禅師遷化後の大分時を経た頃で、その末尾を飾るのが盲目の学徒・咸章堂主人岩田健文(一七六二~一八一四)である。
第2話で触れた小野田東川(一六八四~一七六三)は、当時としては至って長命な質で、数え年八十歳の長寿を全うし、正徳から宝暦年間にかけての凡そ六十年間の長きに亘り、特に後半生は市井(聖堂川向こうの駿河台)にあって琴を教授し続けたため、門弟は百千の多きを数えた。その功績は大で、後の明和から寛政期には、既に琴は文人のごく普通に嗜むものとされ、大凡(おおよそ)学者(学ぶ人の意)たるもので琴を学ばぬ者は皆無といった風潮であった。その内訳たるや大小名や武士、学者(儒者)、医師、絵師などが多く、巷間俗に
「壁上に琴なくんば人をして卑俗ならしむ」とまで言わしめたものである。
禅師三伝の小野田東川門下四天王以降の高足(こうそく)久保盅斎(一七三〇~一七八五)は、水戸藩士立原翠軒(一七四四~一八二三)の琴学の師である。宝暦十三(一七六三)年六月、二十歳の折に、翠軒は微禄ながら小石川水戸藩邸内の彰考館「江戸書揚場」雇いとなり、これを機に、東川亡き後の聖堂の盅斎に就いて琴学稽古を始めた。こうして後の彰考館総裁翠軒は心越派の琴系の一翼を担うこととなり、東川―盅斎から翠軒―健文へと一縷の琴系は水戸へ回帰し、大切に遺伝されたのである。
盅斎は、東讃同郷の大儒柴野栗山(一七三六~一八〇三)の生涯無二の親友で六つ違いの兄貴分。同じく高松藩儒後藤芝山(一七二〇~一七八二)門でも栗山の先輩格、また江戸の昌平黌の先輩でもあった。当時盅斎は林家聖堂付属の同黌学頭(舎監兼生徒会長、首席)という大秀才で、学者として理論上の「礼楽」に飽き足らず、「楽」を統ぶる琴に興味が至るは当然のこと、盅斎が宝暦年間東川晩年の琴門でも頭角を現したのは自然の成り行きと思える。ただ、栗山は琴学でこそ大成せずとも、なお生涯琴を身辺から離さなかった。
「故一橋府儒員盅斎久保仲通之碑銘」
『訓點栗山文集』より 明治39(1906)年 香川県丸亀中学校刊本
聖堂一の秀才で将来を嘱望された盅斎であったが、夙に故郷を離れ、累代采領地のない一橋藩儒となり、江戸で逝ったため、盅斎に関する遺された資料は皆無に近い。
弟子翠軒の秘蔵した遺稿や、知己栗山のこうした碑銘が現在唯一の導べとなる。
文淬武厲 中道而隕 其志弗畢
維爾祖時 闙闑渇才 惜哉爾生
不及祖時 若能相及 方面可試
寧止彫蟲 一夕百詩 詒厥孫謀
有訓在家 爾孫有立 維爾之功
故一橋府儒員盅齋久保仲通之碑銘
大君承統之初。白川源矦以親賢入輔。明良相遇。庶政維新。網羅賢才。幽側不遺。乃以庸劣鈍滞如邦彦。且蒙鉛割之選。辱非常之擢。駸駸中興。蓋百代之時也。邦彦旣拜命。首謁宗藩水戸公。公曰。使久保某在焉。其於國家如何。邦彦置對未了。泫然泣下。所謂某者。吾友仲通之諱也。邦彦與之爲同鄉。而又宦學朝夕共事十餘年。後雖宦跡時隔。未嘗十日無書也。是
「送柴子彦遊日光」 『霊園詩稿』より 久保盅斎遺稿再写本
久保盅斎、諱は泰享、字を仲通、初め二郎右衛門後に喜左衛門と称す。温斎・霊園とも号した。東讃高松の人である。
盅斎は琴弟子翠軒の14歳年長で、翠軒は琴学稽古以外にその人となりに感化され、また学問的にも多大な影響を受けた。師の詩文集を極力尊重するも宜なるかな。また盅斎も、翠軒を単なる門人とは見ず、後にはこれを友人と称したのである。
星摇南極外春满北堂前親族陪莚几兒孫執豆〓貞松懸瑞日慈竹蔟祥烟旨酒罍如涌喜殽盤鮮玉杯期萬福寶算祝千年且喜ー三遷後君家諸子賢
送柴子彦遊日光
野服非歸隠,此行為愛山。石南秋後落,巖桂月中攀。 襌榻談玄罷,琴容理由閒。知君丘壑興,囊裡且携還。
凝過淮陰故里
舊都春草遍駐馬淮陰城無復垂綸者徒聞撃
55
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第6話
盲目の琴客 岩田健文
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
聖堂の久保盅斎は一橋藩儒に迎えられるが、惜しくも五十五歳を一期に逝去する。然し、ここでは若き立原翠軒に琴系を繋ぎ、学灯をも灯したことが眼目となろう。
因に、盅斎と柴野栗山に先立ち昌平黌で学んだ後藤芝山(経書訓読の後藤点でも名高い)も東川琴門らしく、どうやらその紹介で盅斎と栗山江戸遊学を機に東川門に加わったようだが未だ確証がない。一方、栗山は昌平黌を出て京都で国学修行し、隣国阿波の藩儒を経て、晩年は江戸幕府に召されて聖堂の儒官となり、天下に範を垂れる大儒となったことはご承知の通りである。
水戸藩士立原蘭渓は下士ながら学を好み、活計のために塾を開いていた。翠軒はその男である。代々薬種商の岩田家の跡取りであった幼少の岩田健文(名は幸三郎、通称太郎衛門、健文と号す)も蘭渓塾に学び、次いで父に代わって業を継いだ翠軒にも学び、殊に心越派の琴を学ぶこととなる。
好学だが蒲柳の質の健文は、持病の眼疾が進行しつつも、翠軒の肝入りで二十歳で咸章堂を創てたが、果せる哉二十四歳の頃には全く光を失う。こうして、世にも類無き盲目の琴客が誕生することとなるのだが、江戸と言わず、中国にも瞽者の琴客は珍しく、恐らくは日本では岩田健文唯一人であろうか。この間、嫡子健文に代わり、長姉八十の女婿を岩田剛文として家業を分かち、健文は翠軒指導の元、番頭とともに専ら咸章堂の名の下、榻本事業の経営に苦心し、後に薬種事業は三男善吉(時純)をして担らせしめた。
健文は中途失明のため学問に支障を来したが、当道座には深入りせず、家業を振興しつつも、学問への憧憬を常に持ち続け、取り分け師の翠軒とは何事に拠らず万事相談の上、総てを綿密に謀り事業を進め、榻本の良版を彫刻し、善本を印刷して世に頒布し、却って学問に貢献せんとしたのである。
余暇があれば剛文や時純に書を朗誦させ、弾琴また清興に耽る。こうした健文の存在は遠近に知れ渡り、水戸行の文人で咸章堂を尋ね、健文との結交を願わぬ者はなかったほどと言われる。
元聖堂学頭(員生長とも)であった盅斎は志し半ばで逝ったが、その琴癖は見事に水戸の翠軒や健文に感染遺伝しては剛文や時純にまで琴法が伝わる。故に彼らは流祖たる東皐心越禅師を尊び、咸章堂の榻本中に『東皐心越書画帖』や禅師将来の董其昌の書を含ませたのである。
「久保盅斎詩幅」
湯島聖堂文会所蔵
極少な久保盅斎の資料中、「長久保子玉老兄の過り訪う、且つ柴子彦の述懐詩を示さる。因て次韻し謝し奉る」と題す五律がある。子玉は水戸藩儒長久保赤水で、盅斎に長ずること一回り上の先儒、柴子彦とは柴野栗山のことである。
詩の内容は琴事には及ばぬが、無二の親友栗山を気遣うこと日常起臥の中にあった盅斎なればこそ、その篤実な人柄が書体に滲み出る。
武尊歌大雅,餘韻筑坡東
豹隱深山裏,鶯遷春苑中
時名欽遲久,新識故情通
更喜傳隹句看
君存古風
右
長久保子玉老兄過訪且
因柴子彦見示其述
懐詩次韻奉谢
久保享拜
「岩田健文弾琴図」宮部等元画
岡沢慶三郎著『咸章堂岩田健文』より 昭和17(1942)年刊
江戸の著者は、当道座の官位を持てば当然僧形となるが、健文も瞽官を得たか、唯一手掛かりとなるこの弾琴図もまた僧形を写す。
瞽者が筝三絃を聴覚と触覚のみを頼りに習練したと違い、琴は左手と琴面の徽を正視しながら弾奏する。健文は少年の頃より琴を学んだため、完全に失明した後も弾琴に不自由せず、また何よりも、琴は当道座規制の埒外であった。
41
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第7話
心眼吹笛
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
水戸の咸章堂主人岩田健文の原稿と並行して、知人の伝で筆者に小規模なミュージカルの舞台上で二胡(中国の擦絃楽器)生演奏の役が舞い込んで来た。然もタイムリーに視覚障害者を中心とした話である。
たまたま舞台初日の前日に、FM東京の昼の生番組で弊小研究所(坂田古典音楽研究所)への取材があり、この舞台の宣伝もしておいたので、お聴きの向きもあられたのでは……。
大宮出身の青木陽子(劇中では鈴木耀子)さんという、天然痘の予防接種で六歳で失明した六一年生まれの頑張り屋の話を種にした脚本で、タイトルは「赤いハートと蒼い月」。彼女は名古屋の大学で通常の課程を終えてアメリカに留学し、さらに天津外国語学院在学中にその地の中国語コンクールに優勝し、卒業後にアジア視聴覚障害者協会を設立、同じく天津で盲人のための日本語訓練校開校して、以後、何人もの中国人を日本に送り込んでいるという。誠にバイタリティに富んだ女先生を中心とした、心温まる笑いと涙の物語りで、スタッフも俳優陣もそれなりの人選で、短期間に仕上げられた。原曲の作曲は演出家のご子息で、それをまた他の作曲家が編曲し、予算の関係であろう、録音したシンセサイザーと電子ピアノをベースに、私の二胡とフルートそれに中国の笛子(てきし)の三人が実演するという変則的な編成であった。筆者は稽古と本番四公演で十日間の拘束を強いられたが、然し、何とも得難い演奏経験をしたというのが実感であった。
就中、中国の笛子を吹いたのが、現在京都の盲学校に留学中の楊雪元君で、現実の青木さんの日本語学校OBで、劇中の范さんのモデル。もちろんこの舞台で初めてお会いした。
数年前の天津市内を設定した四合院中庭の舞台を中心に、二胡とフルートは正庁(四合院の正面、即ち舞台正面)扉の蔭に陣取り、伴奏の曲を演奏する。一方笛子は舞台袖で幕間にストーリー・テラーの役割を果たすのだ。
遅れて稽古に参加した楊君は、スタッフと劇中の曲を選曲し出す。ここで何分位こんなイメージで曲が欲しいとスタッフが提案すると、楊君は暫し考え、バッグの中からG調の大笛を徐(やお)ら取り出し、「梅花三弄」の序を吹き出す。また次の場面にはC調の曲笛で「姑蘇行」の序と行板、次には「孟姜女」を塤(けん)(古代の土笛)で吹く等々。斯く言う筆者も曾て学び、現在もよく演奏する曲目ばかりで、現代中国の若者がこうした古典ものを選んだのが嬉しく、思わず口を挟むと、楊君、筆者に就いてスタッフ予めの紹介があったものと見え、ちょうど楽屋の席も隣り合わせたのを幸、互いに心を開いて少し専門的な話をするや、直ぐに打ち解け十年の知り合いのようになってしまった。
彼は天津の盲学校在学中に、地元天津音楽院の先生に就いて笛子を本格的に習ったそうで、当然北派の榔笛を善くする。筆者もかなり古く(一九五八)から中国古典音楽を齧り、多少江南の曲笛をも学んだので、見知った先生連や音楽仲間の名前がポンポンと出てくる。揚げ句に稽古の合間に気楽な専家同士で、あの曲この曲と合奏して楽しみ、思わぬ稽古場の余禄を得てしまった。
楊君は盲人特有の警戒心の強さ、神経質さをおくびにも出さず、ユーモアと天津人の饒舌さで、楽屋内を一挙に和ませたが、京都の盲学校を終えたなら、関西の音楽大学声楽(テナー)で受験したいという。今までは彼は盲人社会の中でのみ音楽活動をして来たと言っていたが、今後機会を得て大きく羽ばたき活躍されるよう希望する。
自身がハンディを乗り越えるばかりか、人のために何かしたいと、晴眼者には無い心眼で蒼い月を見ることが出来る人達、併せて赤いハートを備えたこの潔い人達に、終幕後ではあるが満腔の力を込めた拍手を贈らずにはおれない。
「赤いハートと蒼い月」ポスター
9月30日(木)10月1日(金)・2日(土) 志木市民会館パルシティ
企画・製作(株)ジャパンコーポレーション
赤いハートと蒼い月
笑って!歌って!喧嘩し 私は、決してあきらめない!
[演出]瀬藤祝
[作]富川元文
[音楽監督]丸谷晴彦
[作曲]瀬藤幹
[美術]西山三郎
40
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第8話
琵琶交々1
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
元々琵琶は胡(ペルシャ系西域)の楽器であるところから、唐代には胡琴といわれていた。但し、現在での胡琴という呼称は、弓奏楽器の胡琴(二胡を含む)、及びその総称胡琴属をいうので注意を要する。本邦にも『胡琴教録』なる著者不詳の古楽書があって、琵琶の伝授に関する様々の記事を載せるが、書名の胡琴とは琵琶を指すこと無論であるし、実際、漢人ならずも吾人は今なお琵琶に強い西域趣味を感じるのである。
琵琶は中近東からシルクロードを経由して中国に入ったものが主流らしく、中国西方の新疆ウィグルの地には、琵琶が現在の形に固定するまでの類似形の古楽器がなお残存し、長棹四絃で無柱の火不思や、同じく二絃で長棹の忽雷があって、その音色に遙かなロマンをかき立てられるのだが、この忽雷には大小二種の大忽雷と小忽雷(図版左上)とがあり、清朝前期の著名な戯曲家孔尚任(一六四八~一七一八)は、齣中に白楽天の『琵琶行』を副説して案を起て、顧彩が填詞した伝奇小説『小忽雷』(図版右)の曲本に仕立て上げた。
事の序でに粗筋はといえば、時は唐の文宗帝(八二六~一八四〇在位)の頃、梁厚本という士人と鄭盈盈という娘の結ばれるまでの顛末と、名器小忽雷を廻る紆余曲折を絡ませた単純なものだが、因に、そのモデルとなった伝唐代製の楽器も幸いに故宮に現存する。
琵琶はさらに東伝して、中国から朝鮮半島を経由し、雅楽器として奈良時代に日本に齎来され、反対に西伝したものはアラビア系のウードとなり、またヨーロッパに伝わって中世のリュートともなった。
こうして琵琶の伝来した各国では重宝して、それぞれお国振りの楽器として変化発達させるに至り、日本に先行した朝鮮半島でも唐朝伝来の雅楽の唐琵琶(図版左下)から、新羅起源説の俗楽の郷琵琶(図版左下左)が派生したのである。
『楽学軌範』に記す。唐琵琶の項目に、「……擔環は銀或は豆錫を用い、擔條児は紅真絲を用う。……」とあり、図版にあるように、いにしえ朝鮮半島ではやはり唐琵琶は、カラフルなギターのストラップ同様に紐で肩から吊り、重さ対策、且つ西域時代馬上演奏の名残を止めていたのだ。
郷琵琶の項目には、「三国史に云う。郷琵琶は唐の制度と大同小異にして少しく異なり、また新羅に始まる。但何人の造る所か知らず。……」とある。この三国史とは『三国史記』のことで、新羅、高句麗、百済の事跡を記した朝鮮最古の歴史書である。
「小忽雷」 北京故宮博物院所蔵
楽器本体には篆書三字銘で「小忽雷」とあり、背面には「臣韓滉手製恭進、建中辛酉春」と十二字銘があるが、本図版では見えない。
建中辛酉は西暦781年で唐の徳宗(779~805在位)2年に中り、韓滉(723~787)がこの年の春、徳宗に献上したことが分かる。
第六齣「争琴起釁」挿図
『彙刻伝奇小説二十四種』より
孔尚任と夢鶴居士顧彩合作の『小忽雷』(暖紅室依味経書屋鈔本刊)は、左上図版の真物の小忽雷に触発された、実話を交えた創作である。
なお、「釁」字はキンの音で、仲違いの意味。骨董屋で見つけた名器小忽雷を廻り、これより争奪の悶着が始まる。
「唐琵琶」と「郷琵琶」
『楽学軌範』萬暦38(1610)年刊本、昭和8(1933)年京城帝国大学景印本より
『楽学軌範』は現存最古の韓国楽書で、古楽のバイブル。なお、李氏朝鮮時代には、中国明朝の年号をそのまま利用していたため、刊行年は光海君2年に中る。
40
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第9話
琵琶交々2
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
日本の琵琶では、正倉院御物及びそれに準ずる各家所蔵の名物を除けば、一般には雅楽中に使用されるものが一番古い形態を遺していて、これを明治以降楽琵琶(図版右)と呼び、他の民間伝承の琵琶と区別した。
私事で恐縮であるが、明治三(一八七〇)年の楽制改革までは、筆者の家系は代々京都でこの雅楽の琵琶の免許を連綿と司っていたため、その後も琵琶は家学として必修であったが、昭和の御代にはそれほど厳しくなく、却って筆者などは雅楽を疎んじ、また、一見単調な琵琶を嫌って様々な東西の音楽に走り、揚げ句は琴学に没頭したものである。
さて、この楽琵琶の本体は大変大きく、また胴体の主部が檀木(紫檀や花梨等比重の重い材)で構成され非常に重いため、平安朝のいと止ん事無き姫君や、繊細蒲柳の質の貴族子弟たちには楽琵琶は重過ぎたし、何よりも似つかわしくなかった。で、これを小さく簡便にし、演奏し易くしたものを小琵琶といい、当時は重宝され多少は流行したらしい。尤も、これとて重いことには変わりないのだが……。
その後、平氏滅亡後のことだが、この小琵琶の利便性に盲人音楽家が着目し、『平家物語』を語りながら改良小琵琶を携えて伴奏して諸国を歩いた。これを平曲(平家琵琶)といい、今でも名古屋と仙台には平曲の伝統が極々僅かだが残っている。
従って、雅楽の小琵琶と平曲の琵琶は基本的には同一だが、絃数は四絃、柱(ぢゅう、フレット)のみ四柱を平曲では五柱にした。勿論背景演目も違えば調絃法演奏法も違う。
楽琵琶はさて置き、平曲にも既に約八百年を越える歴史があり、この平家琵琶が以降の日本の伝統芸、特に民間芸能の各分野に直接間接を問わず与えた影響は、それこそ計り知れないものがあるのだが、近世に至り三絃(三味線)が渡来するや、大半の琵琶法師たちは、それまで平曲の「節」や「語り」の合いの手のみに終始し、限られた音程しか出せなかった琵琶の手を捨て、長棹で柱が無いため音律に制約がなく、如何なる旋律でも自由に弾きこなせる三絃を歓迎し、挙ってこれに宗旨変えしてしまった。
さらに面白いことには、法師(後には当道座、地歌箏曲界の瞽官の有資格者。即ち検校、勾当、座頭等)たちは、右手に慣れ親しんだ琵琶の撥(図版左上)だけは捨てずにそのままにし、左手に持つ楽器だけ、即ち琵三に持ち替え、さっさと仕える主人を変えてしまったことである。
「琵琶」
『正倉院の楽器』日本経済新聞社1967年刊より
正倉院に伝わる「木画紫檀琵琶・騎猟画」という琵琶で、全長は100cmもあり、小琵琶の生じた必要性も頷ける。
本連載第4話の図版「山県大弐先生遺愛の琵琶と琴」中にあるのが小琵琶で、長さ70cm程である。
「正倉院琵琶撥二種」 前掲『正倉院の楽器』より
現存最古の正倉院琵琶撥「紅牙撥鏤撥」と「紫檀金銀絵撥」。撥鏤の技法とは、牙を染色した後に文様を彫刻する方法である。
「平曲用琵琶撥図」
『平家正節』天保7(1836)年写本より
『平家正節』(へいけまぶし)は、安永5(1776)年、晴眼の平曲愛好者のために尾張の萩野検校が編纂後全国に流布し、以降の平曲定本となった。
40
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第10話
落日の煌めき1
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
アコーディオン(以下アコと略)をご存知であろう。些か乱暴であるが、この楽器のルーツは中国にあると言えば、誰しも吃驚なさるかも知れぬ。笙、篳篥(ひちりき)の音は日本の伝統的儀式に欠かせぬものだが、これとて中国から伝来したもの。楽器学上、笙はフリー・リード属に分類される。
大は小学校の教室にあったオルガン、アコ、バンドネオン。小は口琴、口で吹くハーモニカの類から、コサティーナその他数多の同属楽器が存在するが、詳しくは楽器事典にお任せするとし、進稿するにしよう。
コンサティーナは十九世紀初頭英国発明特許になる愛くるしい手風琴で、程なく完成したアコの利便性に完敗した、何とも儚げな楽器である。
渡邊節男(さだお)氏(ナベさん)は世界に通用したアコの名調律・修理士で、同ご夫妻苦心の渡邊楽器店が神田小川町の片隅に楚々としてあった。虎造ばりに、したやらあったというからは氏は既に鬼籍に入られたに他ならなく、筆者は縁あって英国宣教師からコンサティーナを教わったが、昭和四十(一九六五)年前後の東京にはコンサティーナのコの字もなく、修理すべく駿河台下の現都銀の一角にあった木造二階建て花卉鉢の囲むナベさんの店に飛び込み、無理やりお願いしたものである。ナベさんは飾り気のない気っ風のよい人で、古武士を彷彿とさせる面影の裡には他への思いやりを秘め、反面、自己や近しいご家族には至って厳しかろうと容易に推察された。その上大の苦労人であったが、その苦を顕さず、然も金銭に淡麗という一本気な人で、以後何かにつけお世話になり続けた。
大正十三年(一九二四)年五月一日、静岡県小笠の棚草に生まれ、昭和十一年、当時浅草鳥越にあった姉上の婚家先谷口楽器店に奉公する。同十六年に谷口は駿河台に移転。十九年には召集され館山航空隊に配属。戦後疎開していた義兄と谷口楽器店の再起を計ったそうな。二十五年ご結婚。店の順調を見届けた後、漸く三十三年に現在地の目の前で前記渡邊楽器店を独立開業し、現在に至った訳だが、惜しくも平成十六(二〇〇四)年十二月二十八日、四十五年間生涯現役の歴史に終止符を打たれた。
奇しくも筆者年上の生徒を二年前に失い、同じ十二月に場所も同じく三楽病院ヘナベさんを見舞ったのも束の間、その生徒住居隣が調律士ナべさんの葬儀場となった。享年八十歳。愛らしい店の前に佇み、何時も別れ際に寂しそうにしたナベさん。チャリンコを牽く姿ももう見えない。
「筆者愛用のコンサティーナ」
1850年代製の初期イングリッシュ式。
ロンドンのホィーツストン家は1750年創業になる老舗の音楽商社であったが、同家出身の著名な物理学者チャールズ・ホィーツストン(1802~1875)卿は、1827年、電信に使う電気抵抗のホィーツストン碍子(がいし)を発明して、後にサーの称号を賜った。
続く1829年、中国の笙にヒントを得てシンフォニウムを考案し特許を取得。1844年に更に特許を重ねた改良型イングリッシュ・コンサティーナは、瞬く間に全世界に普及したが、その後アコーディオンの完成度が高まるにつれ、次第に忘れ去られていった。
「33年前の渡邊節男氏と筆者」
昭和47(1972)年11月18日、駿河台下の全電通ホールにおける「第1回谷口アコーディオン・スクール発表演奏会」にゲスト出演後の、未だ青臭い筆者と、48、9歳壮年の気が充満しているナベさんとのスナップ。すると40代成り立ての頃のナべさんからずっと忘年の交わりを戴いていたことになる。
40
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第11話
落日の煌めき2
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
少年の頃の想い出に、誰しも恐らくは一度位はご経験があろうか。口で吹くハーモニカの銀色に輝く上下二枚の長いカバーを外すと、細長いスティール製の弁が現れ、左から右へ規則的に順に小さく並んでいる。この金属片の弁を漢語で簧と言い、略三千年の後にreedと英訳された。
一七七七年、中国清朝の笙が初めてヨーロッパに入り分解研究され、以降フリー・リードの楽器が模倣さ陸続と誕生したが、未だ全ヨーロッパ中のそうした試作中の楽器が殆ど玩具の域を脱せずにいた中、ロンドンのチャールズ・ホィーツストン卿は一八二一年頃から模索し始め、一八二九年にシンフォニウムと名付けいち早く特許を取得した。笙は直接口を付け、また指先で音孔を開閉するに対し、人間の息に代えて鞴の蛇腹に。指の代わりにボタン・アクションで音孔と接するタンポを開閉する、いわば欧州風手動笙である。
これが逐次改良されて一八四四年特許のコンサティーナとなる訳だが、この頃に四オクターブ近いクロマチックの音域を備え、然もハンディ、且つ音楽的要求を満たす高度な独奏に耐えうるリード楽器は皆無であったため、この画期的な楽器は一躍にして全世界の寵児となり、ベルリオーズの名著『近代管弦楽法』(一八四三年初刊)にまで採用された。
同様ドイツ、オーストリアを中心とした各地で、様々な手風琴が考案されては消えていったが、初期のドイツ系の各種アコーディオンはそれこそ稚拙なアイディアで幼稚なものばかり。複雑な音型には対応出来ず、民俗音楽内に久しく止まっていたが、二十世紀初頭前後に、現在の定形、即ちピアノ若しくはボタン式鍵盤と、左方120個のベースボタンを装備するや否や、コンサティーナよりも重く、多少持ち運びに不便ではあったが、世界はアコの独壇場となった。
その後コンサティーナの指使い(フィンガリング)も各種整理され、用途別によって使い分けられるようになったものの、惜しくもその流行もそこで、後続のアコーディオンその座を譲らざるを得なくなった。
こうした中、十九世紀末葉にウィーンで考案され、シュランメル音楽の全盛期に取り入れられて愛用されたのがヴィナー・ハーモニカで、小さな木箱に共鳴するリードの音が何とも心に優しく響くのだが、これもコンサティーナ同様衰退の一歩を辿り、今ではホイリゲやカフェハウスにいってもアコが代わりを占めていて、滅多に耳目にすることはない。
「笙」
中国清朝中葉製の笙。
ちょうど仏人ピエール・アミティオが1777年、初めて笙をヨーロッパに持ち帰った頃の笙。
「コンサティーナ」
ホィーツストン家の姻戚で、既に1840年代後半から特許使用権を得、ラケナルの商標で一時は世界のコンサティーナ製造界をホィーツストン社と二分したルイーズ・ラケナル社も、コンサティーナの世界的衰退と共に1936年に廃業した。
筆者愛用のラケナル社製コンサティーナ。右が最高器種エデオフォン、左が幻の名器トライアンフ。
「ウィーン式アコーディオン」
ウィーン伝統のヴィナー・ハーモニ力は、ツィー・ハルモニカ若しくはクノップフ・アコーデオンと呼ばれる。口で吹くハーモニカではなく、手で奏でるハーモニカ、またボタン式のアコーディオンと厳格に区別される属の一種である。
シュランメル音楽には欠かせぬが、英国のコンサティーナ同様既にして過去の楽器となってしまった。
39
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第12話
至福の音楽
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
前号でヴィナー・ハーモニカに就いて触れた条に、シュランメル(ン)というジャンルを掲げた。これは約百年少し前のウィーンで大流行した音楽で、その後も大衆音楽の代表格として愛好され続け、今もってウィーンっ子たる心の拠り所、いわば市民たちの魂の歌といったような位置付けにあるが、唯にウィーンのみならず貴重な世界の音楽遺産とされ、一時は厚いファン層に支えられたが、時代の趨勢か今や往時の盛況はない。
シュランメルは音楽一家で、父親のカスパーはクラリネットの名手、母アロイジヤは民謡歌手、息子二人の兄がヨハン(一八五〇~一八九三)、弟がヨーゼフ(一八五二~一八九五)である。兄弟は幼いときからヴァイオリンを習い、父と三重奏団を編成して、そこそこの評判を得ていたが、兄弟揃ってウィーンの高等音楽院に学び正規の音楽教育を受け、卒業後ヨハンは作曲家、弟はヴァイオリニストを生業としていた。
時は将にオーストリー・ハンガリー帝国末の爛熟退廃期で、欧州各国の国民運動は騰まり、一触即発、全欧州の支配者であるハプスブルグ王朝瓦解を目前にした時期であった。
当時新興の一般市民階級の嗜好する音楽は、ヨーゼフ・ランナーから既にシュトラウス一家の音楽に完全に移行していたが、これとは別にヨハン・シュランメルの通俗性に富んだ旋律は、先ずウィーン下街の庶民階級の人心を捉え、次いで一般市民、そうして知識階級及び皇室禁裏にまでと瞬く間にファン層を拡張して、音楽界を二分(ワグナーと)していたブラームスや、時代の寵児シュトラウス(兄弟)といったハイソな同業者をも虜にし、果てはルドルフ皇太子がシュランメルの大パトロンとなるや、この四重奏団は一躍ウィーン楽壇の人気を攫うこととなった。
オーストリー民族色濃い楽器編成と、各地の民謡を基盤にして作編曲された兄弟の旋律とが織りなすサウンド。また兄弟の作品ばかりでなく、その編成で自在に演奏される有名無名の古今の名曲の数々(シュランメルン)は、譬えようもなくウィーン的となり、一六〇〇年代から歌い継がれたヴィナーリート(ウィーン小唄)との相性も絶妙で、「ゲミュト」(好い加減)とか「エヒト」(これぞ)といった曖昧さと断定とを兼備したウィーン市民の心情を、将に音楽で代弁したもので、巷間俗に「木陰の下に極上のワインを傾け、シュランメルンに浸れば、これこそ人生の至福の時」と言われたものである。
「ヨハン・シュランメルとその四重奏団」
シュランメル最盛期の一齣で、最も有名な写真である。
テーブル左端の第一ヴァイオリン奏者が弟のヨーゼフ、次いで第二ヴァイオリンでバンドマスターの兄ヨハン。G管クラリネットのゲオルク・デンツァー。コントラギターのアントン・シュトローマイヤー。
筆者愛奏の「コントラ・ギターレ」
汎チロル一帯で用いられ、正式にはコントラ・ギターレ、別名シュランメル・ギターと呼ばれる。
この低音絃付きギターは、ヴィナー・ハーモニカやG管クラリネットとともにシュランメルンには不可欠の楽器で、その郷愁をそそる低音の独特な響きがシュランメルンを形成したといって過言ではない。なおG管クラリネットはとても小さなもので、ピックジュセ・ヘルツル(甘い小棒)との別名がある。
「坂田進一と法螺吹き楽団」
衰えたりとは言え、日本でも未だシュランメルのファンは多い。2002年5月5日、文京シビックホール「ウィーンの歌と音楽」演奏会にて。
中央の歌姫がコロラトゥーラ・ソプラノのヨーネンツ・エミさん、真後ろのハーモニカが音楽学者の高久暁氏、左端が極東に於けるシュランメル音楽提唱者の筆者。
44
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第13話
琴とウィーン式チター
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
敬愛したナベさんのことから、ついついウィーンの下街音楽まで話は弾んでしまった。そこで、コト?の序でにチターをご紹介しよう。というのも中国の琴(きん。拙稿第1~6話参照)が地続きで中央アジアを経てヨーロッパに渡り、チターとなったという説があるからで、筆者同様中国や江戸の文人を好むご同輩としてみれば、強ち無関係ではない。その証拠といっては何だが、上図版をご覧じろ。笙とコンサティーナの件も筆者のコジツケにはあらで、歴とした事実であるからして、……
折しも十九世紀初頭のウィーンを中心としたヨーロッパでは、小型ハープを机の上に寝かせ平面にして弾く簡単な子供用チターから、英米ではクロマ・ハープと呼ばれるアコード・チター、変種のギター・チター、ヴァイオリン・チターなどの開発が試みられていた。これら亜種の多いチター属ではあるが、現在普通にチターといえばコンツェルト・チターを指すように漸次進化発展してきた。
コンツェルト・チターは、琴と同様、左右の小指を除いた八指で演奏する。右の拇指にピックを嵌めて手前の旋律絃五絃を担当し、残りの食、中、名指で数十ある伴奏絃を弾き、左の拇指から名指にかけての四指が旋律を担当するという難儀な奏法である。旋律絃は五絃と変わらぬものの、伴奏の絃数に至っては当初二十五、六絃であったものが現代では四、五十絃前後に増えて、可成り高度で複雑な曲もこなせるようになった。
ウィーン式チターの調律は、旋律絃は c g g1 d1 a1 と変則的に並び、伴奏絃は as1 から下方に四度調絃で始まる。一方現在主流となったミュンヘン式は、旋律絃はヴィオラの a1 絃をダブらせたもの、伴奏絃は es1 から同様四度で始まる。
止まれ!それまでチター音楽と言えば日本では、ワルツ王ヨハン・シュトラウス二世(一八二五~一八九九)の傑作「ウィーンの森の物語」(一八六八)の有名な序章とコーダ部分、陽気なチロル民謡、またその地の家庭音楽などを仄聞するの感が否めなかったものだが、このチターを全世界に知らしめたのは、何と言っても英国の名匠キャロル・リード(一九〇六~一九七六)監督の功績で、彼は名画「第三の男」(一九四九)で大戦直後のウィーンの陰と負の部分を表現し、チターという民族楽器に焦点を当てたは良かったが、同時に、一介の街の楽士であったアントン・カラス(一九〇六~一九八五)を世界的な檜舞台に押し上げてしまった。
「チター弾奏図」
『ヴィナーチター・シューレ』カール・ウムラウフ著 1900年頃ライプチヒ刊より
一見すると如何にも琴を鼓しているかのようだが、ウィーン式チターを弾いている図である。
「中国笙とシンフォニウムの展開図」
本連載「第11話」中、1829年に中国笙からヒントを得てシンフォニウムを考案した際、ホィーツストンが特許申請時に提出した展開図。
「コンツェルト・チター」
十九世紀中葉ウィーン最高のチター工房アントン・キーンドルは、1895年迄の約50年間に何と5万台前後のチターを製作した。
そのキーンドル製作になる見事なウィーン式コンツェルト・チターである。この後、更に低音絃を増したアーム型のモダンなハープ型現代チターへと変化していく。
チター手前にあるは、右からピックと調律用のバー、それに埃取りの箒の三点セット。因みに埃取りは琴の必須アイテムでもある。
※本連載使用の図版中、所属を示さぬものは、筆者及びその研究所の所蔵。
48
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第14話
第三の男とカラス
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
Anton・karas は、カラーシュと発音するのが近く、愛称はトーニ。数多あるチター演奏家には、大御所ルディ・クナーブルや筆者同世代のクラウス・ヴァルトブルクといった正統派の名手等もあって、各々吾が厳しい鑑賞眼に堪え得たが、矢っ張りアントン・カラスが大好きである。どういう訳か、長年シュランメルで鍛えられ、毒? された我が身体髪膚及び音源探知諸器官は、この人の灰汁と澱の混じったウィーン下街風な演奏で無いと味気無いし物足りない。
で、カラスと言えば映画「第三の男」と主題曲「ハリー・ライム・テーマ」に直結するが、勿論オリジナルの作曲と演奏はカラス自身のサントラ版がベストで、少年の頃に馴染んだガイ・ロンバート楽団のダンス版フォックス・トロットも捨て難い。
全編を穿つサスペンス性と、ハリー・ライムのミステリアスな性格を十二分に暗示した例の冒頭半音階の旋律は、筆者やご同輩方の子供心に鮮烈に染み込んだもので、今に至るその影響力たるや、ちっとやそっとのものではなかろう。それらを見越してか、CMの背景に流れるテーマ曲に釣られ、自然とエビス・ビールに手が出てしまうのだから恐ろしい。
多少とも音楽を囓った方ならばお解りになろうが、アーノルド・シェーンベルク(一八七四~一九五一)の十二音技法を引き合いに出すまでもなく、元々ウィーン地方の音楽には十二音半音階を自由に駆使する伝統があり、この楽都に集散した膨大な旋律群は、オーストリー・ハンガリー帝国中の数多の民族、殊に全土に分布したチゴィネル系の音楽の影響を何処かしらに受けていて、卑近例を挙げるまでもなく、フリッツ・クライスラー(一八七五~一九六二)の「ウィーン奇想曲」前奏と主題、ウィーン小唄の傑作、アドルフ・ジーチンスキーの「我が夢の都ウィーン」の折り返し等枚挙するに暇ない。
そのカラスがホイリゲの一介のチター弾きであったのを、偶然キャロル・リードが目に(耳に)し、その才能を垣間見てしまったのが抑もの事の始まり。一介のチター弾きとは言え、元来カラスは音楽学校と音楽大学で長くピアノと楽長コースに学んだ正統派の音楽家で、家庭の事情でやむなく街の楽士となり、生活と学費を支えたチター弾きは世を忍ぶ仮の姿であった筈が、これを契機に終生チターを伴侶とする羽目となる。
嗚呼! 我が心の緒琴、愛しいチターは琴線に触れて鳴り止まず、カラス逝って已に廿年。
「第三の男」映画パンフレット
映画は1949年ロンドン・フィルムの制作になる。世界に先駆け先ずロンドンで封切られ、同年直ぐに第三回カンヌ映画祭のグランプリを獲得した。翌1950年にはアカデミー撮影賞を得たが、撮影現場のウィーンでは甚だ不評であったらしい。
日本では昭和27(1952)年の秋9月に日比谷で封切られ、その後現在に至る迄数え切れないほど上映されたが、右が記念すべき最初のパンフレット。左が昭和51(1976)年リバイバル版である。この他、寒斎にはカラスが来日した際の実写真や英和対訳シリーズ本等があったのだが、何処かに紛れ込み、この図版紹介には間に合いそうもない。
「アントン・カラス」(1906~1985)
映画の撮影は全てウィーンで行われた後、逆にカラスの音楽はロンドンで作曲、録音された。世界的にこの映画が大ヒットするや、カラスは一躍時代の寵児となったがため、ミスター・シンデレラとあだ名されてヤッカまれ、地元住民から総スカンを食った経緯がある。
37
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第15話
平氏縁の琴 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
この三月から五月にかけて「厳島神社国宝展」が上野の芸大美術館にて開催され、会期最終日の五月八日となって漸く重たい腰を持ち上げた。とは言っても何の事はない、我が湯島男坂下の新寓居兼小研究所からはチャリで一漕ぎの目と鼻の先である。
前々号とご紹介したように本来のチター属は台形箱型のものが多く、これに比してロング・チター属は琴や箏のように稍細長い胴体を持つ。
琴は音楽学ではロング・チター属に分類され、チャイニーズ・セブン・ストリングス・チターと訳すのが正しいが、碧眼の文人と異名を獲った吾がヴァン・グーリック(一九〇〇~一九六七)先生は、大著『琴道』の英訳にあたり、敢えて書名をロア・オブ・ザ・チャイニーズ・ルート(リュート)と意訳し、中世欧州の紳士たちがリュートに託した思いと、恰も中国文人の琴に対する姿勢とが一脈相通じたことに重きを置き、読者の題名を読む視点から、内面に存在する意識へと喚起を促した。
午前中ならば少しは余裕を持って鑑賞できるかしらんと思いの外、会場は既に大混雑していたため、早速目指す平重衡(一一五七~一一八五)遺愛と言われる琴に向かう。重衡卿は平清盛の五男坊、母は時子である。
現行の文化財保護法は一九五〇年からの施行で、少々回り諄いが重要文化財の中から、文化史的・学術的な価値の優れたものを文部科学大臣が特に指定したものを国宝という。この重衡卿の琴は今でこそ重文だが、改正以前の旧法では国宝であったと。
『厳島神社国宝展』図録では、「社伝では平重衡が所用したものといわれている。……重衡所用の伝承は信憑性を確認できないが、……」と解説子は暈(ぼ)かすが、逆に、重衡卿遺愛琴との口承社伝に拠る以外に、確認出来得る証左は全く無いものか。亦、製作期を平安時代(十二世紀)後期と推定するからは、和製と見做す其れなりの根拠も有ろうし、続く「法隆寺旧蔵の開元琴、正倉院宝物の金銀平文琴に継ぐ古作」との文脈は、概琴が日本現存第三番目の古琴と読めるが、此等を含め、野犬の遠吠えとならぬよう、何れ遺漏のことども等々連載中にご紹介せねばなるまい。
抑も、同社の神職棚守房顕の『房顕覚書』(一五八〇成書)に、「将又(はたまた)、天王寺ノ伶人蔦ノ坊、岡兵部少輔ノ父薗式部、東儀因幡守、細々(さいさい)下向アリ、然ル処二、京一ノ琴ナレハ、法華ト名ツクルヲ、銀子五百文ニモトメ下ス、当社末世ノ調法(重宝)ナリ、」とあるのがこの琴と言われた。
 伝平重衡卿遺愛「琴」重要文化財
伝平重衡卿遺愛「琴」重要文化財台風復興被災支援『厳島神社国宝展』図録2005年刊より
琴式は仲尼様。胴内墨書銘と琴銘も無いが、木質、琴式と漆の断文(紋)、作風からすれば、大約宋代初期制作のものに分類されよう。蓋し「唐圓宋偏」との大前提が造琴術史にあり、晩唐以前に遡ることは先ず無い。
文武を兼ねた重衡卿も、旧怨を抱く南都の衆徒により木津で斬首され、29歳の若さで弑(しい)されたが、この古琴伝説こそは卿の床しき一面を偲ぶ縁(よすが)となる。
厳島神社祀官で、社家奉行となった棚守房顕(一四九四~一五九〇)の記録が『房顕覚書』(本文末尾参照)で、社伝以外の概琴に関する神社側の唯一の文書である。元来棚守とは職名で、本姓は佐伯氏、又野坂を称した時もあり、以後棚守を姓とした。
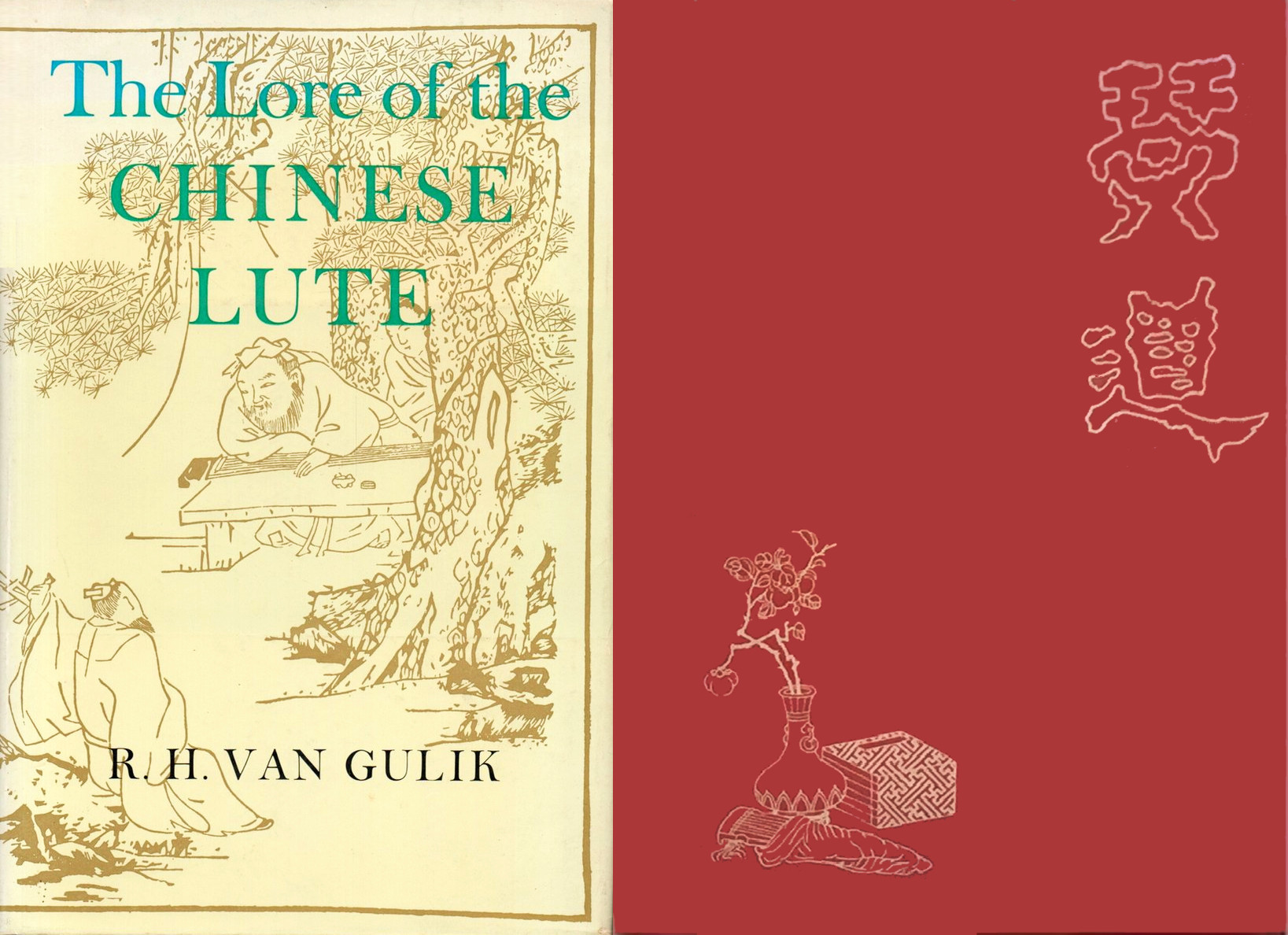 『琴道』初版(右)と改訂版(左)
『琴道』初版(右)と改訂版(左)右の初版は大戦中の1940年、改訂版はグーリック先生没後2年を経た戦後の1969年。両版とも東京刊で、上智大学出版会による一大叢書『モニュメンタ・ニッポニカ』に収められる。
先生著す処の琴説姉妹編には、他に『中国文人音楽とその日本への導入』及び『嵆康の琴賦』等がある。
琴道
The Lore of the CHINESE LUTE R.H.VAN GULIK
45
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第16話
平氏縁の琴 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
江戸の琴客浦上玉堂(本連載第1話参照)著『玉堂雑記』中「催馬楽を琴曲に被らせる説」に、「肥後国益城郡。菅米丸といふ所に。小松内大臣の宮あり。石室ありて。古琴蔵といひ伝ふ。」との、長兄重盛(一一三八~一一七九)脚の琴伝説を引き、次いで、「厳島神庫に重平(ママ)の琴蔵まる。予(※玉堂)上卿市正といふ神家にて観たり。六七百年の物断紋古りて。実に雷家などの製なるべし。平家の時。琴行はる。」とある。只、概琴はそれ以前の厳島の宝物信仰に因って既に世に知られてい、大の琴痴玉堂も重盛卿や重衡卿遺愛の平氏縁(ゆかり)の琴に着目し、年一度七月の虫干しを兼ねたご開帳に宮島まで詣でたらしい。『玉堂雑記』に遅れること約五十年、『厳島宝物図絵』巻之一琴の条には、「社伝ニ平重衡ノ愛玩シタマヘル琴ナルヨシイヒツタフ。棚守房顕記ニ、法華トイフ名物ノ琴ノコト見へタルハ、コレナルヘシ。」とあるが、通常琴背に書刻される琴銘「法華」は同図絵中にも現物にも見出せぬ。
大凡十五分、重衡卿遺愛の琴は典型的な宋琴の様式を備えた仲尼式で、五度目の対面をなし見惚れていたその間、よくある光景とて、次々と入れ替わる参観者の言を聞くともなしに聴けば、「コトだね、柱(ぢ)が無いけど何絃だろう」、「何の木だろう(漆塗りとは思わないらしい)、紫檀かな」、「これ弾けるの」、「音が出るのかな、聞ければいいのにね」、「螺鈿かな」(徽を見て)、「糸は何だろう」等の他愛ないものから、多少絃楽器に知識がありそうなものでは、「糸が繋いであるけど、これでいいのかな」(絶(き)れた糸を偶々結んだだけ)等々、各人各様の素朴な疑問に興味津々であったが、概琴は経年の小修理以外に、
一に、漆色差に数度の修復痕の確認は、門外漢でも解る事柄。茲でハタと専門家の眼を以てして更に解明した点が次の二以下である。
二に、幕末~明治期最後の大修理が行われた証拠に、断紋の消滅(百年以上経つと再度ひび割れる)した箇所がある。
三に、琴の岳と箏の龍角は似て非なるもので、意図する用途も異なる。概琴の岳は惜しくも完全に本来と違い、形状に誤りがある和製の後補(箏匠修理による龍角同型)である。
四に、絃と絃眼、軫(しん)と紐扣(にゅうこう)(絃眼を除き消耗品)も勿論後補である。
五の最後に、『図絵』中、岡田清の所見に引用する梅花断は実際には無く、有れば筆者同様に目睹した玉堂の見逃す筈も無かろうこと等々、平氏縁の二張の古琴に想いは駆け巡る。
『玉堂雑記』無刊記、寛政年間成書
概書は『玉堂琴譜』と一対をなす姉妹編で、いわば『玉堂琴譜』(前・後集)の虎の巻である。『玉堂琴譜』を精確に活用するにはこの雑記が必要で、その読解正否が鍵となる。
「内大臣神社」
平重盛が九州に落ち延びたという熊本県上益城郡の内大臣という元集落に小さな小松神社が遺る。そのご神体の重盛卿像である。
小さな社の裏手に石室があって、ここに玉堂が伝聞した重盛卿の古琴が納まると言う、何ともロマンを掻き立てる伝説がこの平家落人部落跡にある。
「琴面・琴底図」
『厳島宝物図絵』岡田清編述 天保12(1841)年刊より
山野峻峯斎描く挿図も仲尼様琴式である。仲尼とは孔子の字、琴を酷愛した孔子好みの琴式を言うのだ。
絃初の蜻蛉結びが乗る一番高い山の部分が「岳」、「軫」は調律用の糸巻き、「紐扣」は絃と診を結ぶ絹の綿糸の控えである。尚、本文中の玉堂例文にある「雷家」とは、唐代蜀の琴匠の家系で、よくヴァイオリンの名工ストラディヴァリウスに比されるものの、勿論ここでは単に名琴の譬えである。編者岡田清の所見には、「サレトモ、断紋ニヨリテオモフニ、玉堂カイヘルコトク、六七百年ノ物ナルコトハ疑ヒナシ。蛇腹牛毛ハ更ニモイハス、所々ニ梅花断モミユレハ、千年以上ノ物トイハンモ、オソラクハタカフへカラス。」とある。
37
△目次TOP↑
秋月※「平重衡七絃琴 看琴記」(投稿時刻 14th January 2012)をも参照
瘦蘭齋樂事異聞 第17話
琵琶の名手重衡卿
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
『参考源平盛衰記(じょうすいき)』にも一応、琴、箏の区別はあり、これを頼りに琴事を拾おうと寒斎『改訂史籍集覧』本を矯けば、三十九巻に「女柱(ぢ)立テ」と箏であって、やはり琴でないことが解る。以下、それ等を交えた重衡卿箏琵琶弾奏の場に至る経緯である。
ルビ及び()内筆者注。
「去二月七日虜レテヨリ以来。イマタ沐浴セス塵埃ヲ蒙ケルニ云々。(以上南都本。以下『盛衰記』本文)狩野介殿(源氏方頼朝配下の侍。名は宗茂)尋常ニコシラヘテ。御湯(風呂)ヒキ給へト申。中将(重衡卿)嬉シキ事カナ。道ノ程疲テ見苦カリツルニ。身浄メン事ノ嬉シサヨ。但今日ハ身ヲ浄メ。明日ハキ(斬)ランスルニヤト心細クソ思ハレケル。
一日湯ヒキ給程ニ。昼程ニ及テ二十許カト見ユル女ノ目結(めゆい)ノ帷(かたびら)ニ白キ裳(もすそ)着タリケルカ。湯殿ノ戸少開テ。左右ナク内ヘモ入ス。中将如何ナル人ソト問給。…略…。晩程二十四五許ナル美女ノ。地白ノ帷ニ染付の裳著タリケルカ。金物打タル楾(ばんぞう)ニ。新キ櫛取具シテ。髪ニ水懸梳(くしけずる)ナントシテ上奉ル。休所ニ入奉テ。暫有テ。(長門本には、「此二人ノ女湯アミテ中将ノ前ニ来テ何事モ」云々)、(何事でも仰せ付け下さい。との女の言に、重衡卿は頭を剃り僧形になりたい旨を告げるが、咎人を勝手に出家させられぬ。と言われ、卿も納得し黙してしまった。さて、)。
其夜ニ入テ。佐殿(源頼朝)狩野介ヲ召テ。三位中将ハ無双ノ能者(管絃の道の)ニシテオハシマス也。和君(狩野介)カ私ナル様ニテ琵琶弾セ奉レ。頼朝モ汝カ後園ニタゝスミテ聞ヘシト宣ケリ。
(狩野介館酒宴の場面)狩野介女ニ向テ。兎テモ角テモ御前(重衡)御徒然ヲ慰進セン料(ばかり)也。一声挙テ。今一度申サセ給へト云ケレハ。女兼テ心得タル事ナレハ。酌サシオキテ。(これより女は朗詠二首と今様念仏を歌い、次いで)、纐纈(きょうけち)(臈纈染め)ノ袋ニ入タル琵琶一面。錦ノ袋ニ入タル琴一面。女ノ前ニ置タリ。中将琵琶ヲ取寄見給フ。女柱立テ弾タリケリ。中将宣ケルハ。只今アソバス楽ヲハ。五章(常)楽(ごしょうらく)トコソ申習ハシテ侍レトモ。重衡カ耳ニハ後生楽トコソ聞侍レ。往生ノ急ツ(告)ケントテ。テンシュ子(ネ)チツゝ。妙音院殿(太政大臣藤原師長。琵琶の名手)ノ口伝ノ御弟子ニテオハシマセハ。皇麞(おうしょう)(楽曲名。また往生の掛詞)ノ急。撥音気高ク弾セラル。(夜は更け、障子を開けると灯が消え、これより名場面となる)。中将爪調へシテ。
灯暗数行虞氏涙。夜深四面楚歌声。
ト云朗詠ヲ二三遍シ給ケリ。」
『参考源平盛衰記』巻頭
『改訂史籍集覧』明治15(1882)年 近藤活版所刊
『平家物語』の原本は、鎌倉期の承久から仁治(1219?~1243)年間頃に成り、当初三巻であったが、読本と語り本(平曲)とに分かたれてそれぞれ順次脚色整理された。
読本には六巻の南都本、廿巻の長門本、更に潤色された四十八巻の『源平盛衰記』等の他に様々な異本が伝わる。
平重衡卿の前半生は『公卿補任』や『玉葉』等に窺えるのみで、詳しくは伝わらなく、後半生のみが『平家物語』等に管見される。
その各種異本を挙げた『参考源平盛衰記』(『改訂史籍集覧』所収)は、奇しくも琴道中興の祖東皐心越禅師と徳川光圀公との間を周旋し、惜しくも早逝した舜水門下の逸材今井魯斎の考訂本である。
參考源平盛衰記卷第一
常陽水戶府
魯齋今井弘濟將與甫 考訂
著軒內藤貞顯仲微甫 重校
平家繁昌 竝得長壽院導師事
祇園精舎ノ鐘ノ聲。諸行無常ノ響アリ。沙羅樹ノ花ノ色。盛者必衰ノ理ヲ顕ス。奢レル者モ久カラス。春夜夢ノ如シ。猛キ者モ終ニハ亡ヌ。風前ノ塵ニ同シ。
遠ク異朝ヲ訪ハ。夏ノ寒泥。秦ノ趙高。漢ノ王莽。梁ノ朱昇。唐ノ禄山。皆是舊主先皇ノ政ニモ随ハス。民間ノ愁。世ノ亂テモ知サリシカハ。久カラスシテ滅ニキ。
近ク我朝ヲ尋ヌルニ。承平ノ将門。天慶ノ純友。康和ノ義親。平治ノ信頼。侈レル心モ猛キ事モ。取々ニ有ケレトモ。マチカク入道太政大臣平清盛ト申ケル人ノ有様。伝聞コソ心モ詞モ及ハレ子。桓武天皇第五皇子一品式部卿葛原親王九代ノ後胤。讃岐守正盛孫。刑部卿忠盛嫡男ナリ。彼親王御子高見王。無官無位ニシテ失給ケリ。御子高望王ノ時。寛平元年五月十二日。始テ平姓ヲ賜テ。上総介ニ成給シヨリ以来。忽王氏出テ人臣ニ連ル。其子鎮守府將軍良望。後ニハ常陸大掾國香ト改ム。國香ヨリ貞盛、經衡、正度、正衡、正盛ニ至マテ。六代ハ諸國ノ受領タリトイへ共。イマタ殿上ノ仙籍をハユルサス。忠盛朝
「楽琵琶」
琵琶(本連載第8・9話参照)を始め、平氏の公達が管絃の道に勤しむ姿は、『平家物語』の随所にある。
重衡卿は琵琶大臣・雨大臣と綽名された妙音院相国藤原師長の愛弟子で、これまた絲竹の道の達人であったが、残念ながら重衡卿ご本人と琴そのものを直接結ぶ文献は現在無く、前号に触れた「法華」銘の琴が、則ち現存する厳島神社宝物の無銘の素琴と一致するや否やも曖昧模糊の彼方にある。ただ、少なくも「三位中将ハ無双ノ能者ニシテオハシマス也。」、との風評を背景に、源頼朝に言わせしめた、管絃、分けても琵琶の名手であったことは本文に拠っても事実であろう。
45
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第18話
紀州の琴僧古岳上人 甲
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
一代の清僧且つ琴痴の古岳幽真(一八一二~一八七六。法諱は茲観、翠山人と号す)は、紀州海草郡加茂谷丸田村の産で本姓大塚氏。性は高邁、豪放磊落、然も無欲であったと。妻帯せずも後嗣は古岳姓を名乗る。
幼少より真言に帰依し高野山不動院で修行。天保十(一八三九)年廿八歳で山を下って数年の後、紀ノ川を見下ろす絶景の地那賀郡藤崎に弁天堂を復興。傍らに古岳庵なる庵を営み、又、庵中の一室を挹翠山房と命名した。当時名だたる文人墨客が訪れては古岳の弾ずる琴を聴き、清遊に耽った由緒深きこの古岳庵も、昭和廿五(一九五〇)年九月三日、関西を襲ったジェーン台風の直撃を受けて崩壊し、惜しくも撤去された。
筆者は古岳上人の名を本邦琴学系譜上に夙に見出し、寒斎蔵の上人縁の琴書を始め、偶々地方紙での古岳に関する記事や、その他の文献を貽られもしていたが、何分遠隔の地のこととて、機が熟したのは漸く平成四(一九九二)年の年明け正月半ばの頃、愚門の存じ寄りを頼りの紀州でのフィールド・ワークに出た。
この愚門と言うのは、令姉妹お二人で、当時姉君高橋ゆりさんにヴァイオリン、妹君藤岡多恵さんにはチターを筆者がお教えしていた。ご実家が海草郡木之本村(現和歌山市木之本)の名家で、姉妹のご父君が理化学研究所でビタミンAの抽出に世界で初めて成功し、帝国学士院賞を得た高橋克己博士(一八九二~一九二五)。且つ、母方は五条の素封家で、有吉佐和子作の『助左右衛門四代記』や『紀ノ川』のモデルという次第。
古岳は、詩文を菅茶山と河合梅所、歌学を加納諸平、琴を鳥海雪堂に学び、諸学各々頗る蘊奥を極めたが、野山の律に犯す琴(音楽)を棄て切れず、やむなく高野下山の後、奥州から九州まで全国を行脚しながら山水を愛で、各地の名士と交遊した。常に木綿の墨染めを着し、首には頭陀袋を掛け琴を負ったその姿は、一見して乞食のようであったと伝わる。而して誰が知ろう、この琴こそ明の張季修作の古琴であったなどと……。
更にその交友には、三条実臣、岩倉具視、伊藤博文、伊達千広、陸奥宗光、森田節斎、頼山陽、倉田績、市川団十郎、河合小梅等の錚々たる顔触れが並び、以て尋常の僧でないことと、縉紳各家も善く彼の心底を見極めて交わったこと。併せて幕末有事の際、前記維新の元勲間を周旋、琴を携え密使として往来したとして何ら不思議ではない。拠って巻間勤王の僧とも呼ばれた所以である。
 「古岳上人弾琴図」冷泉為恭画
「古岳上人弾琴図」冷泉為恭画『冷泉為恭の生涯』逸木盛照著 昭和31(1956)年便利堂刊より
概肖像画は冷泉為恭(1823~1864)文久二(1862)年冬の作である。
是迄に筆者目睹の「古岳弾琴図」は三幅あったが、概ねこの為恭を臨模したもので、遠景に高野の峯々を置き、そこから発した紀ノ川が松樹下に弾琴する上人の足下に至り去るという構図であった。
古岳上人自作「琴」
黒漆素琴で琴式は鳳勢様。胴内墨書銘は無いが、幕末期古岳上人自製遺愛の琴で、琴箱上蓋裏面に古岳庵自署の文字が有り、庵の代物であったことが知れる。
尚、弊小研究所寒斎には上人自製の琴をもう一面所蔵する。日本で言う所の素琴(本連載第4話参照)で、仲尼様拭き漆仕上げ、琴総体の木地の木目が見える。連載第20話掲載予定の古岳家現蔵琴と関連がある。
「琴箱上蓋」 古岳庵自署の文字
雁足、軫(調律用の糸巻き)、紐扣も揃い、幕末当時、上人が張った琴糸の残缺も保存する。
43
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第19話
紀州の琴僧古岳上人 乙
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
天保の改革で幕府に嫌われ、江戸を逐われた稀代の名優七代目市川団十郎(一七九一~一八五九。五代海老蔵)の大阪公演中、古岳は楽屋を尋ね琴を聴かせて吃驚させ、以来昵懇となったとの逸話が伝わる。
団十郎は、既に天保三(一八三二)年の三月、八代目を息子に譲り五代目海老蔵を襲名。天保十三(一八四二)年の六月、江戸十里四方所払いとなった後は、幾たびも変名して中京、上方方面を巡業して廻っていたが、膾炙した特徴は直ぐにそれと知れ、浪速で古岳と会った時分も、民草は総ての事情を知りつつ、依然として七代目と愛称し贔屓して、絶大なる人気に毫も衰えは無かった。
この七代目は上人に、「望みのものを」との口約をしていたが、その機会も無く、とある日、上人は草庵を結びたいとの発心に、起草した庵の図面を団十郎に見せて謀った所、団十郎は快く喜捨を引き受け、上人安住の栖(後の古岳庵)を新築し、約定を果たし得たという。言わば団十郎は上人の大恩人でもあった訳だ。
詩歌の道はさて置き、古岳第一の琴師は鳥海雪堂(一七八二~一八五三)である。結果的にはこの雪堂数多の門下により、当時衰退の日本琴学は辛くも明治に継がれるが、同門の大先輩で、琴曲皆伝した讃岐産の浪速の儒、藤沢東畡(一七八三~一八六四)は「贈古岳上人序」で、
高野の古岳上人、書を読み詩を賦し、頗る風致有り。
嘗て予と同じく雪堂和尚に従い、琴曲を受け、錬磨数年妙境に至る。上人古琴一張を蔵す。明人張季修斲(※)する所。出入起居するに、須與たりとも側を離さず。蓋し有虞氏の南薫操を奏し、孔夫子の文王操を学ぶ。伝に之有り。而して上人の琴や、其の背に銘有りて、曰く蔵密と。是諸を易伝に取る。聖語なり。今上人琴曲に耽り、而して特に蔵密を愛するは、志(こころざし)古聖人の道に有る者の似(ごと)し。
野山に律有り。誦梵を節するの外、固く声音を用うるを禁ず。乃ち上人の律を犯すを謂て之を逐う。
上人古琴を負いて野山を出で、藤崎の山中に廬を結び、朝夕松風と与に相和す。
或いは曰う。雅俗を問わず、概ね声音を禁ず、野山の律は酷(はなはだ)しと。予則ち野山の更に酷しきを加え律せざることを憾む。上人をして浮屠氏(僧)を去らしむるのみか。
(『東畡先生文集巻之三 筆者訓 ※斲 木を切り、成形してものを造る意)
と、長年隣席同学した兄弟子の視点から古岳身辺の状況を具に伝えた。
七代目市川団十郎「自画賛」
岐阜県博物館特別展図録『七代目市川団十郎と国貞、国芳』より
この七代目が「歌舞伎十八番」を制定し、「東海道四谷怪談」を初演した、所謂江戸歌舞伎界の大立て者で、後に古岳幽真のパトロンとなった。
概図で自身特徴を描くよう、「目玉団十郎」と徒名され、絶大なる人気を博して庶民に親しまれたそうだ。
「弁天堂」
古岳幽真の復興した藤崎の弁天堂。
往時に比し水量が激減したとは言え、弁天堂の足下には蕩々たる紀ノ川が蛇行し、眼前には値千金の眺望が開けるという、正に絶好の立地の中、今以て御堂は鎮座まします。
「古岳堂」扁額 古岳家蔵
古岳庵縁の第一の扁額は、先ず徂徠筆の「古嶽」で、他に貫名海屋や頼山陽のものがあったとも。
写真の揮毫の主鷯巣幽人とは聞き慣れぬ雅号であるが、略上人と同時代を重ねた山田翠雨(1815~1875)その人である。翠雨は京都の産で、後藤松陰門に学び、後に家塾を開き多くの門弟を育てた。
森田節斎の「古岳庵記」に、「道人海内諸名家の書画を展じて曰く、是皆衲の親しく謁えて獲る所なり。」と豪語した上人ならでは、為書きも微笑ましい。
概額は徂徠筆「古嶽」とは異なること勿論だが、肝心の徂徠の額が前記ジェーン台風迄存在したや否やは定かで無い。
43
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第20話
紀州の琴僧古岳上人 丙
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
後の古岳幽真を育んだ生地加茂村丸田(下津町加茂郷丸田)は、和歌浦湾の南に位置する温暖の地。続く廿年間は峻厳の高野に在って修行し、下山後遊歴した上人は紀ノ川流域中第一の景勝地藤崎の地を選び、ここを終の住処と定め、七代目団十郎の喜捨を受け弁天堂を復興し、附帯する草庵を普請したことは既に述べた。
此の草庵の様子は、弁天堂傍らの老松樹下、瓦葺き(当初は藁葺き)建坪廿余坪であった(『ふるさとの誇り・那賀郡版』)というから、草庵とは言うものの規模は可成りのものであったようである。
此処に於いて歌作と琴書三昧に耽り、且つ又、此処を拠点に各地の風光を猟渉しつつ、後には寺子屋を開き近在の子弟を育て、其の膝下からは明治の自由民権運動で名高い児玉仲児、千田軍之助の両代議士他を排出したと言う。してみると、上人の後半生は琴と歌作三昧にのみ隠れた唯の世捨て人で無かった事も知れる。
雪堂琴門の兄弟子である藤沢東畡には、前掲「贈古岳上人序」の他に更に一編、次掲「古嶽庵記」(節斎と同題異文)なる上人の為にものした文章があって、共に東畡の並々ならぬ友情を示す筆意を以て貫かれる。
「古嶽庵記」
高埜の玆観上人風流にして読書を好む。時時吾が浪花の寓を来訪す。一日予に謂いて曰く、
我徂徠先生書する所の古嶽の二字を扁す。因って其の字を以て庵にせん。如何と。
余の曰く、先生は前輩の豪傑、実に古学を唱うる者、先生にして此の字有り、其の所を固くするなり。今上人此を以て号と為すは、抑も志の古学に有るや。
曰く、子誤りて之を聞く。学問の学に非ず、山岳の岳なりと。
曰く、岳や岳、山の大なる者古学問を以て山に譬うは、九仭一簀の言か。豈然らず。上人果たし能く其の功を虧(み)ず。亦将に其の大を成すか、善き哉号とするや、其の旃(せん)(人招きの旗)勉むべし。
上人乃ち之に頷き、而して其の牽強を腹笑するに似たり。
(『東畡先生文集』巻之四 筆者訓)
之にて高野修行中、其の鳥海雪堂の下、東畡と併に琴を学んでいた若き頃の上人は茲観と称していて、高野を下山、各地を遊歴した後に藤崎に庵を構える三十歳代、即ち、入手した茂卿の筆跡「古嶽」に感じ、之を東畡に商ってより初めて庵名とし、又同時に、之より以後は専ら古岳と自号(庵主は庵名を名乗る)したこと。更には、上人自ら「扁す」と日うよう、草創当時の庵には当然、碩儒荻生徂徠筆になる件の扁額が懸っていた事も併せ知られよう。
古岳詩文添削の師たる河合梅所の令室小梅女史の『小梅日記』(東洋文庫本)中、古岳の名が散見されること、嘉永年間から明治十年古岳の死去伝聞まで度々ある。就中、慶応三(一八六七)年九月八日の、
「古岳を二度迄呼びにやり候へ共りういん(留欽)にて不快、出来たらず。琴および自身の像、又は集めし書画皆持ちよこす。是は作日也。不快故心にまかせざれば、代に琴や像を上るとて、砂糖一箱又は茂助高野より持帰りたる松たけと柿を上るとの文、八塚へ来る。……」
や、亦森田節斎の「古岳庵記」の、
「道人頻りに(節斎に)巨觥(こう)(大盃)を侑(すす)め……、遂に大酔し眠りに就く。」
等に、上人可成りの左党と読めた。
「古岳弾琴図」部分古岳家蔵
筆者目睹の「古岳弾琴図」三幅の内、古岳家現蔵の図である。落款には霊水とある。
矢張り松樹下弾琴の構図で、明らかに為恭を臨模したもの。然も、三幅全図共少しく髭を蓄える。
46
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第21話
紀州の琴僧古岳上人 丁
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
古岳幽真の著作中、代表作である『空谷伝声集』の題箋は、和訓して「やまびこ集」と読むが正しいようだが、その書名には琴僧の名を恣にした古岳ならではの典拠が隠される。是非上図版の解説を読まれたい。
此の『空谷伝声集』の巻下に「山彦」と題す歌があり、呼べば答える山彦と琴法「罨(えん)」、即ち「空谷伝声勢」を重ね、書名としたかが知られる。紀州の風土に育まれた上人は、長じて高野の峻厳さに心身共に鍛錬され、後に藤崎の景勝を愛し終の栖とした。
さくらちるはるなつかしみ鶯に とへは答ふる山ひこのこゑ
又、同書巻中の「琴川居にて月前琴」と題す三首は、俄然、心越派の琴系譜に拘る筆者の興味をそそる。
幕末期江戸の杉浦出雲守(旗本世襲)邸には猶、家門中興の誉れ高き杉浦琴川の居室が残され、琴道の大先達を偲ぶ古岳がここを訪れたことが知れた。琴川君は東皐心越直伝の琴を伝え、『東皐琴譜』五巻を編纂した功績があるも、早逝し惜しまれた。
心あらは月にとへかし山水の ふかき手もいさ(いざ)おしへまし
ありあけのなこりなきまで琴ひかむ さし入る月を聞人にして
小萩さくかのやかたに琴とりて 露ちるよいの月をみるかな
又々同じく巻下には、「平井調庵琴師の七回忌に寄琴懐旧」とて、
吹風のおとさへかなしから(唐)琴の 秋のしらへは松にのこして
とあるため、古岳上人は前後二人の琴師に就学したと推察される。
更には、宮部美臣の「古岳上人の明の張季修か作たる琴をえ(得)られしをほ(祝)きて」との題に、
蜑(あま)すらも得かたき玉をいかにして かつ(潜)きあてゝむ唐琴浦
と、名宝に等しき古琴を得た喜びを、友人間に多少は吹聴していたらしい。
森田節斎(一八一一~一八六八)は大和五条産で、名は益、通称は謙蔵。節斎又山外節翁と別号した。聖堂と山陽、洞庵に学び、特に『孟子』、『史記』に通じた。この節斎は上人の嘱に応じ『古岳庵記』をものし、又、『空谷伝声集』の跋文に曰う。
近世の緇林(しりん)(仏教界)に風流を解する者の鮮(すくな)し。古岳上人已にして琴を以て天下に鳴る。又和歌及び漢歌を善くす。真に空谷の跫(きょう)音(あしおと、即ち琴法「罨」)か。今先に和歌集を刻す。漢歌の如きは、則ち将に他日を待ちて刻すべし。
慶応二年丙寅仲春
山外節斎居士 森田益題
於古岳庵山水奇絕処
「空谷伝声勢」
『太音大全集』明刊本より
琴法に「罨」なる左指法がある。
「空谷伝声勢」とは此の「罨」法の形容であって、先ず左手無名指(薬指)にて某絃指定の徽分を按じて、右手の某指で概絃を弾ずる。次いでその余韻のある内に、右手では弾ぜずに同絃の上徽を大指()で撃ち、軽い打音を得るのである。
これを「罨」と言い、その琴法の心(心象)は「空谷伝声勢」、即ち、その手法にて得た琴音は、山彦、谺のよう、然も静かに彼方と相呼応せねばならないと。
『空谷伝声集』古岳幽真著
無刊記 慶応末年頃刊
文久元(1861)年から慶応二(1866)年に及諸家の序跋を閲すれば、刊行に至る迄には凡そ五、六年程の時日を要したことが解る。勿論、自作歴年の詩歌選に及んでは殆ど半生以上の歳月に亘ろうが、上人の全作歌はとてものことで概書には収め切れぬ。
書は上中下の三巻仕立て。下巻の三分の二迄が古岳歴年の和歌で、春夏秋冬の四季題から雑詠に至り、巻末に諸大家の古岳に寄せた祝いの和歌と漢詩が掲載されるが、就中「古岳上人の弾琴を聴く」他が、関西を中心とする四十氏を超える当時一流の漢学者達により寄せられる。
35
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第22話
指ヶ谷残夢
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
再び閑話休題。
歳々年々人同じからずとか。本連載第10話で触れたナベさんこと故渡節男(さだお)氏の一周忌法要が、旧臘三日に白山下の心光寺でしめやかに行われ、ご親族以外の集った親しい顔触れの中に、アコ界の元老金子万久、売れっ子のコバこと小林靖宏、アコ研究家の渡辺芳也各氏等が見えた。
筆者は中学生まで、心光寺門前の肴町に上る元電車道(都電指ヶ谷停留所。旧中山道)を渡った崖上の西片町に住んでいたし、つい一年前迄は今の白山通り反対側の崖上の小石川伝通院脇の元表町に寓居したので、所の地理には詳しく、粗方の路地裏熟知すると言う自負があったが、近きに遠しの譬えか、日本琴学史上、未調査の江戸中期の画家、黒川亀玉の奥津城が確か此の心光寺にあった筈と、朧気の記憶裏のまま、参列した。
亀玉は享保十三(一七三二)年十月廿八日江戸の産。名は安定、字は子保。亀玉、松蘿館、商山と別号した。幼にして駒込吉祥寺の学寮で一日にして千枚の絵を描いたと言う神童で、狩野派の絵を学んだ後、長崎渡来の清人沈南蘋の画風を慕い写生派に転じ、書と棋及び琴法にも精通した「江戸漢画の祖」と目される文人だが、惜しくも宝暦六(一七五六)年の六月廿五日、廿五歳の若さで早逝した為、巷間の遺作は皆無に近い。
法要も済みナベさんの墓前に額ずくべく一同墓地へと向かう。渡邊家の墓石を正面にし、礼拝の順を待つともなくフト筆者の左手に触れた傍らの古びた墓銘を見れば、「商山処士亀玉原子保之墓」と。ゲッ!何とこれが目当ての黒川亀玉その人のもの。南無ナベさんの手引きに違い無い。その場は逸る心を抑え直来へ。改天、渡邊夫人の紹介を得、和尚に亀玉の調査を依頼したこと勿論である。
本連載第2話の挿図「藍渓琴の師小野田東川像」は、宝暦二(一七五二)年の暮春三月、千住在の旧甲良屋敷跡(幕府普請方棟梁甲良家。現千寿常東小学校校地)、当時は医師で本草学者の坂上玄台(田村藍水。一七一八~一七七六)の別墅で催された、東都嘉慶花宴集という雅会の記録図の一部分で、前後に書家三井親和(一七〇〇~一七八二)の題字と琴客小野田東川の碑文が布され、黒川亀玉描く所の挿図が中間にある。
日光水戸の両街道が交わる要衝の地、千住宿の甲良屋敷に水戸往還の途次滞在したのが、黄門光圀卿に庇護された中国曹洞宗第三十五世の正宗、且つ、後年日本琴学中興の祖と仰がれた東皐心越禅師である。
黒川亀玉自画像
『東都嘉慶花宴集稿』より
花宴集の挿図は当然、君子四友の琴碁書画を念頭に置き構成される。
其の内、爛柯の道に余念の無い三士の向こう側、案上に描きかけの竹画を置き、横向きに黒衣を着し、葛巾を被って画業に余念のない若者が、亀玉其の人である。
極簡単な線描画であるが、天才と謳われた亀玉自ら、急逝する四年前の廿一歳の己が姿を写生する。
現存する肖像は恐らくは是のみか。
黒川亀玉の墓
心光寺門前
寺の在る旧指ヶ谷町から山門前の旧中山道沿いに続く旧丸山福山町一帯は、明治末年より白山三業地なる花柳界として隆盛を誇った。
昭和の初期からは漸次不振となったが、昭和30年代の其の頃も灯は消えず、未だ夜毎に賑わう西片崖下の花街に何かしら心惹かれ、危うい思春期の筆者に対し、「絶対に崖下に遊びに行ってはならぬ!」と、家人は釘を刺したものだ。
48
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第23話
東都嘉慶樹
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
東皐心越襌師(一六三九~一六九五)は、清初の康熙十五(一六七六)年六月廿日に杭州湾から船主彭公尹の一番南京船に乗船、舟山普陀に数ヶ月寄錫し、翌日本の延宝五(一六七七)年正月十二日の夜間に長崎に入港した。(心越自筆『雑詩』より)
禅師の渡日するに際し、密かに持ち来たった杭州城内嘉慶坊の李の種を、留念の為に旧主甲良氏をして植栽せしめたと言う伝説が事の発端。
徳川光圀卿の庇護の下、禅師は天和元(一六八一)年の七月、小石川水戸藩上屋敷の朱舜水設計になる後楽園中の琴画亭傍らに匿われ、此処に三年弱仮寓した後、天和三(一六八三)年の四月、初めて水戸城北三の丸に入るべく千住を過ぎり、貞享三(一六八六年八月の家兄対面の長崎行、元禄八九(一六九四、五)年の箱根湯治への往復でと、都合五度程水戸往還の途次千住宿を通った。
唯、後記「嘉慶樹記」には、「故有りて、之を甲良氏の別墅に種(う)う。」とあり、同「会雲和亭記」では、「嘉慶坊の李子を以て、而して甲良氏をして之を種わしむ。」とあるのみで、何故に禅師将来の李の種子が甲良氏に渡ったのかは、玄台から伝え聞いた東川も詳しくは其の来歴を知らぬし、筆者も禅師自筆の記録や詩文集から其れらしきものを読み取れぬ。
ともあれ、甲良氏から坂上氏へと主替わりした凡そ八十年後の別墅では、多くの薬草に混じり此の間も李樹は成長し続け、年々白い花を咲かせては遠近の人士を楽しませていた。
是即ち江戸近郊評判の「東都嘉慶樹」で、其の心は、大明国の高僧東皐心越禅師将来の東都(江戸)に花咲く、杭州嘉慶坊(南宋都臨安)の李の子裔たる名樹と言う意である。
之に先立つ元文三(一七三八)年九月十八日、江戸城中に於いて八代将軍吉宗公の舞楽御覧あり、群臣の観覧も許され、心ある者は古楽を珍しく見聞して大いに感じたが、中でも琴は今の世に絶えていたものを、明僧心越が日本に投帰した時の伝を、勘定奉行杉浦内允蔵(正職)の家小野田嘉兵衛東川が学び取ったと言う。琴は中古に絶えていた業で、京都の伶人すら誰一人として知る者の無い為、吉宗公は理想とした礼楽整備からも、雅楽中の琴の復権を果たすべく伶人を京都から呼び寄せ、伝奏屋敷にて東川をして琴を教授させしめ、伝習も修了し伶人が御前演奏をしたと言う訳だ。(『有徳院殿御実記』)結果、主君杉浦琴川、殊に陪臣乍ら琴客たる東川の名は、是を機に全国の士人間に知られることとなる。
「東都嘉慶樹」
『東都嘉慶花宴集稿』1991年東京琴社復刊より
嘉慶樹の全体像を把握し易いよう、黒川亀玉の挿画五図中三図の版心を除去し、試みに樹影を接合してみた。
三井親和の題字及び東川の碑文図を足すと、全七枚の図となる。

「東都嘉慶樹」の碑
小野田東川撰文 千寿常東小学校
碑文は東川の「東都嘉慶樹記」の冒頭部分で、前号で禅師が「甲良屋敷に水戸往還の途次滞在した。」とは言ったものゝ、実は筆者にも禅師滞在の確証は無い。
拠って一概に禅師が水戸往還の途次千住に於て、留念の為直接甲良氏に与えたとばかりは言えぬのである。
44
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第24話
甲良屋敷と坂上玄台
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
琴客小野田東川は、嘗て東叡山寛永寺宮一品親王の推挙に由り将軍家の上聞に達し、上意を承けて平安朝従り中絶した雅楽中の琴の地位を復活、大いに面目を施したが十四年前の事。以来、東川の名は江戸以外の地にも広まり、心越派琴道の領袖として名実共に斯界を教導して来たが、齢七十の古稀を迎え漸く老境に入る。
頃は宝暦、旧甲良屋敷の新主坂上玄台と歓晤した東川。嘉慶樹の言い伝えと玄台の、「後の人淪滅せば跡と名と而して伝わらず。」との言に堪らず、「予原(も)と東皐開士、琴学の末弟たり。之を聴きて心地惑い怡(よろこ)ぶ。豈速やかに筆を採り得ざるに如かず。是(ここ)に兄が家を想えば、日後必ず嘉慶の事有るべし。豫(あらかじ)め以て之を祝さん。」と急遽「東都嘉慶樹記」をものする。
時に玄台三十四歳、町医の傍ら殊に人参に詳しい本草家として、此の後幕府小普請組支配の医員に登用されるが、元々玄台の出自は同じ小普請方棟梁大谷出雲の次男。総領は大谷南浦、三男は一橋奥坊主の大谷立佐と言う家系で、玄台は少時に町医田村宗宣の養子となり田村姓を冒し、亦、田村家は坂上田村麻呂を祖とした為、坂上姓をも併用していた。
日ならずして「東都嘉慶樹記」は碑に刻されるが、茲に面白いのは其の碑陰で、其処に刻まれる宛ら土豪の平城を想わせる園林図は、全体を江川を引き込む壕に囲まれ、更に中央の塀を象った方形の中に、門、カケイ(嘉慶)、相思松屋鋪(雲和亭と思しき)等とト書きが有り、其等の上に玄台の識語が彫り込まれる。
然も、別墅全体図と重なる旧甲良屋敷に関する識語は、午(南)の方角を右下に倒置する形で台座に布される為、正視する状態では読み難く文面は全く判読出来ぬが、首痛に堪得れば、主人玄台の次掲の語に因り、屋敷との関係は更に明々白々となる。
抑も此の地や、寛文十(一六七〇)年以来、(五字欠字恐らく第一代を謂う)宗清(甲良氏第三代)の別業なり。宗清老いて改名して曰く宗賀と。宗賀の子は曰く宗貫之の妹、牟久子と曰う。牟久子なるは、乃ち予が実の家母なり。是(ここ)を以て甲良氏の玄孫、匠五郎なる者、予に此の地を譲り、而して今又予の別墅と為すなり。夫れ地の縦横籔林の中、神社五位、故木三株有り。五位とは、稲荷二座、疱瘡神一座、弁財天堂、土神祠、是のみ。夫れ三珠樹とは、一に曰く千株松、一(二)に曰く相思松、三に日く東都嘉慶樹のみ。
宝暦二壬申(一七五二)暮春
坂上登玄台(田村藍水)謹識
「甲良屋敷跡」を眺む
写真中央、白く低いL字状に横たわる今日の千寿常東小学校。其の校庭に今猶「東都嘉慶樹」の碑は建つ。
「宗賀の子は曰く宗貫。」後の一字と、他の二字が不明な為、一日碑の調査をす可べく小学校へ向かう。
許可を得て校庭へ出れば、折しも休憩時間で、生徒数600名弱の嬌声と砂埃の舞う中、首を傾げ、字分の乾拓を採り、碑文の再調査に掛かる。
休憩も終わり、矢庭に閑散とした校庭に継いで現れた二年生。「今日は。」と可愛らしい挨拶を筆者に向かって投げ、碑の真後ろに在る苗圃で実習をし出す。此の二年生と引率の女教諭と数言を交わした筆者は、春光の中、思わぬ寛ぎと憩いの時を得て、穏やかな気持ちで帰途に就いた。
「旧甲良屋敷跡図」
李核を模し円形に象られた「東都嘉慶樹」碑陰(背面)の屋敷図。
之に因ると口型の園林の一辺は百間(182m)前後と記され、往時の甲良屋敷は、現在の小学校敷地よりも更に大きな一万坪余あった。との記述と符合する。
48
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第25話
東都嘉慶花宴集
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
宝暦二(一七五二)年三月、頃も好しとの坂上玄台の招きに、唯一東皐心越禅師の警咳を知る小野田東川と語らった風騒の士達は、静養中の成島錦江を誘い大川を舟で遡上する。
東川は禅師将来の琴服(鶴氅衣)を装い、携えた禅師遺愛の名琴「雲和」で「秋風辞」を鼓し、平復初は唐音を朗誦しつ、舟で江川づたいに別墅へ着岸。其の名も琴に由来する雲和亭に集い、花見を兼ね禅師を偲ぶ雅会「東都嘉慶花宴集」を催す。
花宴に於いて、東川の琴は言わずもがな、平復初(平賀源内説有り)は唐音、黒川亀玉は彩管を操り、亀玉の父嵩山は玄台実兄の大谷子秀と手談に興じ、又、多芸の士に遅れを取った錦江は酒を敵(あいて)とし、各々詩を賦し文思を練っては琴碁書画の世界を満喫し、更には日後、茗筵図録に魁る好事本『東都嘉慶花宴集稿』を纂し、書肆戸倉屋喜兵衛をして発見せしめ、同好に配し、又頒布した。
当日花宴に集った面々は、亭主の坂上玄台と主客小野田東川。次いで源柳園、関琴洞、成島錦江、平復初、玄子保(亀玉)と嵩山父子、東川琴門の寂堂空(新豊禅師)及び原虚室、谷子秀(大谷南浦)、内子尚(河内山宗俊)、山南澗等で、書家三井親和は所用で心ならずも不参加とある。
奥の茶坊主河内山宗俊は「雲和亭辞並序」(『花宴集稿』)、に曰う。
東都の東に、一園林有り。右は駅路に交わり、左は綾瀬に接し、亭は其の央に居す。亭の前後に三株樹有りて、其の一に曰く相思松、其の二に曰く千株松、其の三に曰く東都嘉慶樹と。江都の佳樹なりと云う。…
又、禅僧寂堂呑空は「会雲和亭記」(同『花宴集稿』)に記す。
此の李樹たるや、大凡七十余年なるか。花は姑洗仲呂の間に向かいて、其の心を発す。其の園なるや、大凡方百畝、自然にして琴の形勢を製す。之を能する者は、黙して之を識らん。蓋し、琴腹の中、姑洗を以て仲呂の界とし、以て天柱を立つ。其の柱は琴の心膂なり。其の西北の隅なる松樹は、千年の姿在る有り。以て地柱と為せば、無射をして応鍾の界たらしむ。…
辞に「右は駅路に交わり、」と有るよう、甲良屋敷の園林は街道に接し、厳重に警護された禅師も、此処で休息若しくは宿泊し、暫し憩われたやも知れぬ。とは筆者の勝手な想像。
止まれ!宝暦文雅の士が意識し劉希の絶唱、「洛陽城東桃李の花、飛び来たり飛び去って誰が家にか落つ。」とばかり、洛城嘉慶坊の名花と禅師との牽強附会は察するに余るが、筆者の知る限り禅師の前半生は江浙両省を一歩も離れず、禅師は洛城産と称する種を人に貽られたか、はたまた、杭州城坊の種を洛陽名花に肖(あやか)り凖(なぞら)え、美称したが真実に近かろう。
さはあれ、唐宋何れかの宮殿址の李子を禅師が実際に将来してもせずとも、斯く伝説となった東都嘉慶樹は少なくも百年近い歳月を千住邑に根付き、其の後も花を咲かせては江戸の市民を娯しませたことも事実。
扨、禅師の草花を詠じた詩文集『華叢』(外題「花木詩」未刊)には、次なる「李花」題の七絶が遺るが、
青李如珠喜不酸 崑崙遺産莫加鑚
但教結実花長発 豈謂無無根自盤
無論、後に東都嘉慶樹に成長する李子を直接詠ったものでも無し、亦、禅師は後々の風騒連が自分を出汁に花の宴を開いたこと等知る由も無い。劉翁の続けて詠う、「古人復た洛城の東に無く、今人還た対す落花の風。年々歳々花相似たり、…。」との例も虚しく、今日此の東都嘉慶樹の面影すら無いが、傍らの東川碑文は其の後の二百五十年間奇跡的に保存され、是等の経緯には些か疎いであろう千住宿末裔の子弟を今も見守り続ける。
「秋風辞」琴譜
『東皐琴譜正本』 2001年9月坂田進一編纂より
琴歌辞は人口に膾炙した漢の武帝作。琴譜は杉浦琴川の命で東川が自筆した明朝体浄書の稿本である。
東皐心越禅師は中国で学び自ら校訂した琴曲と、日本投帰後の自作の琴操とを併せた琴譜集上梓を果たせず遷化。門下の幕儒人見竹洞と麾下の大身杉浦出雲守が遺命を嗣ぐも刊行に至らず、禅師示寂後306年にして漸く全巻を整え、待望悲願の『東皐琴譜正本』を公刊するに至った。
62
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第26話
紀州の琴僧古岳上人 戊
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
道を返し更に古岳上人の跡を辿る。
古岳庵の記
乙丑之十二月望(陰暦十五日)。山外節翁(森田節斎自身の謂)扁舟に乗り、橋本駅従り紀川を下る。
舟の不二崎に至るや、乍ち琴音を聞く。翁之を異とし、舟を捨て岸に上り其の音に踪(したが)えば、則ち松林草庵中に在り。
翁王摩詰の詩を高吟して曰く、深林人知れず、明月来たって相照すと。
一道人戸を開け、大声に呼ばわりて曰く、詩を吟ずる者は、森田先生に非ずや。衲(どう)は古岳なり。先生を待つこと久しと。遂に強いて留め宿す。
明日道人再拝し請うて曰く、衲近ごろ異夢を感ず。夢神の衲に告げて曰く、当に天下の文人至り、汝が庵を記すことの有るべしと。先生の果たして至る。願わくは之を記せよと。
翁の曰く、記す者は記さん。記す可き無きは、何を以て之を記さんと。
道人海内諸名家の書画を展じて日く、是皆衲の親しく謁えて獲る所なり。以て記す可きにや。翁の曰く、書画は観つ可しと雖も、記するに足らざるなり。記す可き者は、其の風景に在るかと。
乃ち酒を置き欄に憑りて望む。飯盛龍門の諸峰は、雲煙中に出没隠見す。翁の文思は動き筆を援りて之を記せんと欲す。
須にして煙は消え雲は散じ、黛色滴らんと欲す。翁筆を擲ち、道人を顧みて嘆じて曰く、此の如き奇絶は、僕記する能はざるなりと。
道人頻りに巨胱を侑(すす)めて曰く、先生酔はざれば、則ち文を成さず、請う数杯を尽くせと。遂に大酔して眠りに就く。
半夜夢覚む。寒月檐を窺い、松影婆娑たり。渓流石に触れ、清音耳に徹す。翁の文思は復た動き、筆を援りて之を記さんと欲す。
忽然として水烟中に叫ぶ者の有り。響き裂帛の如くして、山谷皆応ず。翁の曰く、是何の声ぞと。道人の日く、老猿なりと。翁又筆を擲ち嘆じて曰く、此の如き清絶は、僕記す能はざるなりと。
道人の曰く、記する者に足らざれば、之を如何ともする無し。記す可き者の有りて、而して記せず。先生遂に記さざるかと。
翁黙然として語らず。道人乍ち膝拍ちて曰く、衲之を知んぬ、衲之を知んぬ。先生の之を記さざるは、乃ち之を記す所以なりと。
是に於いて琴を援りて弾ず。
翁破顔微笑して、復た扁舟に棹さして去る。
(『節斎遺稿』巻一筆者訓)
「古岳庵記稿本」森田節斎筆
節斎推敲の痕跡が多々認められる貴重な資料である。
当然、稿本は刊本『節斎遺稿』所収の「古岳庵記」(本文参照)とは異なる。例えば、2行目補足の添筆を省いて読むと、「舟至藤崎、琴音乍北岸松林中発、翁異之、招舟上岸。」とあり、更に読み足し推量するも、未だ刊本定稿には至らぬ以前の状態なのである。
古岳「短冊」
とるほこ(鉾)にくももなひ(靡)きて越の山 かり(雁)啼くよいの月をこそみれ
上人直筆の該冊は、『空谷伝声集』下巻では、歴代の英傑を題材にした中に、「不識庵」こと上杉謙信を詠じた歌として掲載される。
41
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第27話
紀州の琴僧古岳上人 己
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
珍かにも、順風満帆の筆勢を得たかに見えた拙稿は、前号森田節斎の「古岳庵の記」中にあった「狙」を追わんとて、忽ち雑踏に迷い込む。
彼の李謫仙はいみじくも、
両岸の猿声啼いて住まざるに
軽舟已に過ぐ万重の山
と絶唱。同様に上人も、斯くももの悲しい猿の断腸を題材とする歌を『空谷伝声集』中に度々詠じた。
月さえし小峡にさけぶ山狙の こゑもくれて小夜更けにけり
おや狙のこをよふこゑもかつそひて 小峡に氷る冬のよの月
俄然、前号「古岳庵の記」の記述とも符合し重なるではないか。狙は長臂猨(テナガザル)の意で、勿論日本には生息せず、日本猿を狙に見立てたポーズであることは、古人文学表現上の常套手段であると誰しもが認める所だが、敬愛した吾が琴道の先達高羅佩大人はこれに着目し、『長臂猨考』を著し、中国奥地にのみ生息した長臂猨が、何故日本の文人画に描かれ、又、詩文の題材となったかを考察する為、東京芝台の駐日オランダ王国大使館公邸の庭に長臂猨の一種ギボンを飼育し愛玩止まず、折々は肩に乗せたりして慈しんでいたが、時とすると近くの寺に逃げ込んだりするので、探し出すのが一苦労であったと。(御遺族談)
本題の古岳上人と琴に戻ろう。上人の分身とも言うべき琴だが、その詩歌中に玉堂詩ほど琴字は頻出させず、程良い抑制の中に上品さが薫る。
わかための冬の夜ころのしる人は 桐の火桶と琴となりけり
ゆくとしのを(惜)しミてとまるものならハ ななのをこと(緒琴)に弾もとめまし
又、恐らく冬雨降る自庵で詠じたと思われる歌に、
かきならす四のをことのかへす手も 乱てさむき雨の音かな
「四の緒のこと」とあるにより、上人は琵琶をも嗜んだことが知れる。
就いては屋上屋。平安中古の昔には絃楽器を総て「こと」と云った。
諸賢耳タコの「琴」は「きんのこと」で、絃が七本なので「七つ緒のこと」と言い、俗称は「七絃琴」。「箏」は「そうのこと」で、絃が十三本あるので「十三絃」。
「琵琶」も「びわのこと」と言い、絃が四本あるため「四緒のこと」。
等々と厳密に区別していたが、近世に至り却って混同してしまった。無論之は三味線伝来以前の話で、「しゃみのこと」、況してや「三緒のこと」とも言わぬし、「三絃琴」は幕末以降の創作楽器で別個に存在した。
「鳥海雪堂墨跡」
古岳上人琴学の師。鳥海雪堂の筆になる「松風和琴」の句。
廿八歳、天保十(1839)年に山を下りて丁度九年の後の嘉永元(1848)年の冬日。既に上人は古岳庵主、又紀州の琴人として名高い。此の上人の為に各家(主に雪堂琴門)の揮毫した『紅絲雅集巻』と題す巻子本の巻頭に置かれる。
「高羅佩とギボン」
オランダ王国大使館公邸の庭園でのスナップ。
一に、「猱」なる重要な琴左手法は、長臂猨(狙)木登りの際の動作を模して採られた琴技。二に、元来日本に生息せぬ長臂猨が、何故日本の南画に描かれたか。との二点がヴァン・グーリック(高羅佩)の飽くなき知識欲を刺激し、『長臂猨考』(英題「ギボン・イン・チャイナ」1967年ブリル社刊)が編纂されたと言って過言でない。ライデンのブリルは、オランダきっての古書肆を兼ねた出版社で、該書も亦若き先生の才能を見抜いた同社前老板の見識により、公刊された良心的出版物である。
筆者は老板のご厚意で楼上の書庫に入り、勇躍、其の数百年の蓄積中から貴重な数点を漁ったも懐かしい。
53
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第28話
ここに泉あり
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
四月四日、読むともなしに新聞紙上に映画プロデューサー市川喜一氏の死亡記事を認め、つい読み返したばかりの群馬交響楽団を題材とした『愛のシンフォニー』(丸山勝廣著一九八三年講談社刊)を暫し想起する。名画「ここに泉あり」をリアルタイムでご覧になったご同輩も多かろう。筆者が映画を観たのは未だ小学生の頃。新星映画社の作品で制作は岩崎晄。水木洋子の脚本、監督は巨匠今井正で、プロデュースが前記市川氏、昭和丗(一九五五)年二月封切りの再生日本の音楽映画の魁りで、主演は岡田英次、ヒロイン岸恵子は前作「君の名は」で既に国民的大女優。小林桂樹の他に錚々たる俳優陣が脇を固め、更には、日本近代音楽史上の山田耕筰の生出演も破天荒な事で、名場面の中にも、今でも筆者の脳裏に浮かぶのが次景の数々だ。
一に、岸恵子はピアニスト佐川かの子役で匂い立つような若さを見せたその恋人役岡田英次扮するコンサート・マスター速見明と、成瀬昌彦扮するヴァイオリン弾きが絡み衝突する場面で、竹村の「乙に絡むね!」と言う台詞がその後も耳に付いて離れず、今も時に脳裏を過ぎる。
二に、入団希望の少年が、速見にオーディション風にヴィバルディのイ短調コンチェルトの冒頭を弾かされるシーンでは、批評の仕様もないヴァイオリンに、一抹の不安を抱きながらも、それでも才能を信じているかのような、子煩悩の年老いた母親のさりげない演技が印象に残る。
三に、貧窮どん底の楽団生活に、軍楽隊出身の三井弘二扮するトランペッター丸屋と加藤大介扮するドラマー工藤が、飲み代を稼ぐ為にチンドン屋でアルバイトをする場面は凄かった。流石は今井正監督である。コンバスも弾いた(海軍は絃楽器も併習し、時に応じてオーケストラも編成出来る伝統があった)工藤は楽団のトラブルメーカーであつたが、それでも「帝国海軍軍楽隊」出身の軍人音楽家の矜持だけは失うまいと、チンドン屋の隊列の中で胸をピンと張って、軍楽隊仕込みの姿勢を崩さずに必死に大太鼓を叩くのである。
筆者の軍楽隊好きは一寸したもの。年長友人の旧陸海軍軍楽隊出身者の未だ多くが当時現役の中、海軍ファゴット出身で、労働者救済ホームに入り、ニコヨン(日雇い)生活をしていた猛者もいた。最後の軍楽隊長内藤清吾先生にも何度も直接お話を伺った経験もあり、こんな些細なシーンが筆者にはとても大きく映った。
斯く云う筆者も団塊の世代で、当時は多少富む者もそうでない者も、総じて暮らし向きは貧しく且つ慎ましいもので、音楽家ならずも「暮らしは低く、想いは高く。」との泰西の格言宜敷、国民の大半は貧困に喘ぎつ、も希望を失わずに生活していたこちとら庶民派の青少年が気張って音楽鑑賞等と言へば、一寸した名曲喫茶へ行き、大人振ってナケナシの大枚百円札を払い、ほろ苦い一杯の冷たくなったコーヒーを啜って何時間も粘り、紙片にリクエストを書いては之忍耐強く、何時間も曲順を待ったものだし、花の都東京と雖も当時音楽専用のホールは皆無で、日比谷公会堂以外には上野の文化会館も完成していなかったそんな時代、大編成のオーケストラを鑑賞しようとすればそれはそれは難儀な作業であったが、小編成のサロン音楽やダンスバンド、タンゴのオルケスタ等や楽隊からチンドン屋迄、現在と比すれば、却って東京には生の音が溢れ、身近に存在したように思う。
手廻し蓄音機も未だ健在で、流石に主流はラジオ付きの電蓄となったが、バリコンとコイル手作りのイヤホーンラジオで雑音だらけの短波放送を貪り聴き、猫眼のマジック・アイ付のハイファイラジオに吃驚した頃、悪童達は映画中の泉のように湧き出る旋律とシーンに酔い且つ涙した。
「ここに泉あり」
封切り時の映画パンフレットで、今や実物は貴重となったが、却って映画本編の廉価版はワンコインで鑑賞出来るのだから、時の経過
と事物の推移との因果関係は計り難い。
中央映画株式会社製作
独立映画株式会社配給
49
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第29話
紀州の琴僧古岳上人 庚
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
古岳上人自筆の「遺状」の控え(正本は消印せぬ)を読んで見れば、
山人滅後、弁天堂并びに古岳庵、山林田畑、楽器類、什物、悉く御房事に附属せしむ。当山は自分支配の為、已に御上従り御許容下し成されし村中分、勿論約定相違い無く候間、生涯安堵之有る可く候。
併し、山人積年骨を折りし中興、相調へ候供田什物ニ候得ば、随分大事ニ所持、後世に伝へ為す可く候。委曲縷々、記録之有る可く候。
因つて後日の為遺書を附属すること、件の如し。
文久二年辛戊九月二十一日
古岳庵開基 幽真 印
高野山 明王院建道御房
只今住于河内国加賀田社寺
平生覚悟の中に読経、弾琴していた上人は、持てる全てを野山の塔中明王院に寄託。更には、紀伊藩儒の倉田績(一八二七~一九一九)に依頼し、生前墓である寿蔵「古岳庵幽真墓」を明治八(一八七五)年建立、俗世後顧の憂いを絶ち切っていた。特筆した楽器類とは琴と琵琶である。
古岳上人の後裔古岳家にはそれでも猶、上人縁の遺品と数通の文書が遺されたが、張季修作の明琴「蔵密」は其の後主人と所在を替え、只今唯一家蔵される和製の素琴は、胴内墨書銘に、「天保五年甲午孟春、做愛山琴野之調菴 花押」とあり、前号掲載の和歌と同一人、琴師平井調菴の一八三四年正月手製の琴と知れる。
次なる古岳自用の「往来切手」は、
丑壬五月名手組大里正(大庄屋)
妹背佐次兵衛殿 持来
伊都郡 御代官所 被下候
往来切手 御印鑑
と、上人自筆になる外包みがあり、内の往来切手本紙には、
名手組池田姫門村 古岳庵
伊都御代官所 印
乙丑壬五月ヨリ
とある。この往来切手は現在のパスポート以上に重要で、諸国及び他藩との関門を通過するには不可欠であった。無論これ以前にも交付され、各所を経巡ったであろうが、この日付の乙丑壬五月は慶応改元直後の一八六五年の五月で、最後の切手と思われる。当然、維新後の明治政府が安定した時点では不必要となる。
既に文久二(一八六二)年の九月には文頭の遺書を認め、通交手形を所持し、琴を負い、心置きなく諸国を往来し、各地の風光を愛でつ、見聞を広め、又、各界著名の人士との旧交を温め、遂に明治九(一八七六)年の十一月五日享年六十五歳、納めの長途、遠い涅槃に向けて旅立った。
「古岳庵筆意図」田野村直入筆
嘗て、野山の律に反する琴を酷愛し、止むなく下山した形式を選んだ上人は、之を恨みず、何時でも高野山を見上げられる藤崎の地を撰び、此処に在って常に野山を仰慕して居た。
落花のかたのうちに、と題した次なる歌に、
花ちりて都こひしくなりにけり 草の庵ハ誰にゆつ(譲)らむ
と詠じ、本文冒頭にも有る様、遺言に高野の塔中に庵を寄託すると明記し、斯く安心立命の内に生前墓を建てそして逝ったのだから。…
小虎散人痴は、田野村直人(1814~1907)若年の画号である。
45
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第30話
東台琴客余聞 一 今泉也軒
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
 幕末の琴客井上竹逸の琴門に、岡倉天心の片腕として美術学校を創り、本邦美術をフェノロサと共に国内外に講じ、斯界を教導した今泉也軒(やけん)(一八五〇~一九三)が在った。
幕末の琴客井上竹逸の琴門に、岡倉天心の片腕として美術学校を創り、本邦美術をフェノロサと共に国内外に講じ、斯界を教導した今泉也軒(やけん)(一八五〇~一九三)が在った。也軒は、美術学者乍ら文人趣味を地で貫き、又一方では茶人、好古癖の人として著名であったが、殊に特記す可きは彼の師友で、琴に因って深く結縁された其の場面は概ね上野界隈に限られる為、筆者は便宜上是東台派(心越流)と括った。
也軒と拘わる東台派の第一は無論竹逸。二に美校の天心、三に博物局初代局長で東博初代館長の町田久成、四には妻鹿友樵の男松井友石である。
也軒は幼名亀太郎。文峯と初号し、也軒、後に無礙又常真居士と号したが、通常名の雄作を以て呼ばれる。嘉永三年六月十九日の生まれ、昭和六年一月廿八日逝去、享年八十二歳。
雄作は八丁堀組同心の家に生まれ、父の覚左右衛門元長は名同心として、通常与力から侮蔑された存在の同心中、覚左右衛門のみは「今泉のおじ「さん」と筆頭与力からも「さん付け」された(「今泉先生の生い立ち」原胤昭)実力の同心であったそうな。そんな父の膝下に育ち、少時より雄作は向学心に燃え、野田笛浦に学び書法を高林二峯に受けた。慶応の声を聞く十六歳で幕府昌平坂学問所に入学。当時の最高学府で学ぶ事となるが、昌平黌入学を機に琴学を井上竹逸に学び、四、五年にして大政奉還となり幕藩体制は瓦解する。
世は明治ご一新、解体された昌平黌どころの騒ぎではない。心機一転、築地居留地で英学を学び、更に横浜の英人の下で実習する。御用達小野組に迎えられ、真(まこと)新聞編集長となるも、此の間も琴学稽古は継続し、十年以上も竹逸門で錬磨し続けたのは、琴は余程雄作の性に合っていたのだ。因みに後に竹逸収蔵の名琴中の一面は割譲され、雄作の所蔵に帰した。
明治十(一八七七)年、大学南校(東大の前身)の仏語教師ジュリーの推薦で、フランス留学の途次インドにて梵語を学ぶ。前後するがリヨンで日本文学を教授し、偶々実業家で東洋美術館(現在国立東洋芸術博物館)々長のエミール・ギメ(一八三六~一九一八)の相識となり、乞われて同館客員教授となった。
明治十七(一八八四)年晴れて帰国。文部省学務局に出仕し、前記天心岡倉覚三と相識るに及び、協同し東京美術学校創立に尽力。後、京都美術工芸学校々長に転じ、帝室博物館美術部長、古社寺保存会委員、帝室技芸員等歴任した後、野に下り大倉集古館初代館長に転ずる等、縦横に活躍したのである。
今泉也軒書
也軒漢学の師野田笛浦(1799~1859)は、名は逸、字を子明と言い、13歳で寛政の三博士の一、古賀精里門に学び、丹後の田辺藩に仕えて儒者から執政、即ち家老職となった勤苦の秀才である。書の師高林二峯は、富堂(ふたを)と名乗った幕末を代表する江戸の書家で、継ぐる明治の書界に多大なる影響を与えた。
図版の書軸は自作の七絶書で、漢学の師笛浦の書体を彷彿とさせる。
落款には常真道人今泉雄作とあり、大正10(1921)年71歳の作である。
49
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第31話
東台琴客余聞 二 今泉也軒
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
微禄の八丁堀組同心乍らも、今泉也軒の父覚左衛門は酔叟、酔花居とす心の余裕を持つ茶人でもあった。其の膝下に育ち、当時の最高学府湯島の昌平黌で培った也軒の向学心は維新後の混乱期にも萎えず、堅忍不抜の精神で苦学した足跡は欧州や印度に迄及び、帰朝後の也軒が明治黎明期の本邦美術界に果たした功績は多大であるが、吾人は其の裏面に隠れ、表舞台からは見え難い本主題である「楽事」に眼を転ぜねばならぬ。
聖堂で学び初めた也軒こと雄作少年は、新たに広がるネットワークを得て、「学者たるもの琴を学ばずんばあらず、」と竹逸の門に辿り着いたのだ。そうして前号で「十年以上も竹逸門で錬磨し続けた」と其の琴学稽古に就いて触れたが、此は『奇人井上竹逸』と言う次なる文章から引用したに過ぎぬ。(全文は後出の予定)
「…略…翁が絵画に傑出した手腕を持つてゐたことなど知る者は殆どなかつた。翁は絵画に堪能であつた許りでなく、七絃琴の妙技に達してゐた。七絃琴は人も知る如く、舜五絃の琴を造り、文王一絃を増し、武王更に一絃を加へて七絃としたと云ふ、支那三千年来の楽器である。唐詩選に独坐幽篁裏、弾琴復長嘯とか、明朝有意抱琴来とか云ふ琴は此七絃琴
のことであつて、長さ三尺六寸、現今婦女子の間に専ら行はる、、十三絃の琴とは、余程趣きの異なった高尚なものである。翁は非常に此琴を愛して、常々不足勝の生活をしてゐながら、支那の銘ある立派な琴を十五六面も所持して楽んでゐた。実は吾輩(也軒)も琴曲の弟子として翁に私淑した一人であつた。翁遺愛の琴の一面は現に吾輩の手に伝つてゐる。吾輩が翁に師事したのは十六七の頃から二十七の歳、欧州に留学するまでの十年間であつた。…略…」。
也軒の恩人で大先輩の前博物局長町田石谷が上野で逝去する以前の明治廿三(一八九〇)年、世俗を辞し三井寺で剃髪するに際し、石谷は愛惜已まぬ「宋琴」一張のみを残し、他の琴は然る可く各々分散して処分し、又所蔵する琴書の大半は一括して軒に帰した為、明治中期から大正期の東京琴界に於いては、也軒所蔵する所の琴譜及び琴書が近代日本屈指のコレクションとなった。
当然ながら其の真価を知る也軒は是を私せず、又、実子の無い後を憂えて、大正四年(一九一五)年六十六歳の折、茶書・仏書・琴書と各々蓄年の貴重な蔵書を帝国図書館に寄贈した為散逸を免れ、九十年後の現在も猶我等後学を溢して余りある。
「正装の今泉也軒」
 前号図版の「七絶書幅」をものした頃、功成り名遂げ大礼服を装った今泉也軒。
前号図版の「七絶書幅」をものした頃、功成り名遂げ大礼服を装った今泉也軒。丁度大正10(1921)年72歳前後の姿を留める。
「常真居士寄贈」図書の印記
今泉也軒は、大正4年(1915)年の12月1日付を以て、茶書仏書と共に貴重な「琴譜」と「琴書」を、帝国図書館(上野図書館、現国際子ども図書館)に一括して寄託した。
右下の三顆「左琴右書」、「無礙庵」、「常真居士寄蔵」が也軒、二顆「今泉雄作氏寄贈本」と「大正…」が図書館。
該書は佐久間象山の琴師仁木三岳(旗本)自筆の『東皐琴譜』である。
40
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第32話
東台琴客余聞 三 今泉也軒
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
因みに、奇しくも新帝国図書館は旧薩摩上級藩士であった町田石谷が最晩年を過ごした薩藩縁の上野寛永中明応院の跡地に建設、明治丗九(一九〇六)年に竣工したのだが、建議許可の知らせだけは石谷の臨終に間に合い、せめてものとなった。
戦後の変遷で図書館は赤坂離宮へ移り、そして現在地の国会図書館となったが、筆者若輩の昭和四十年(一九六〇年代半ば)頃には也軒寄贈の琴書の存在は一般には未だ知られず、当時の国会図書館課長某氏のご厚意で、貴重書室管理下の「八三二函」として纏めて収蔵される事を知り、更には全書閲覧可の便宜を戴いた。
精査すれば和漢の琴書全数百部、その大半は石谷の旧蔵書で構成され、石谷の世俗を捨てる際に也軒に譲られたものと判明したが、也軒自らの蒐集書も少なくなく、中には日本のみならず中国でも海内の孤本とされ琴書も含まれる実に琴客垂涎の的の琴書群である。明治の初期を中心に、石谷と也軒二人程の見識と地位とを併せ持てばこそ、「さもありなん」、と頻りに筆者は点頭したものだ。
未だ也軒翁の義嫁ご存命中の事、筆者が往時に就いてお訊ねすると、「義父が音楽を嗜んだ事は余り記憶になく、楽器の類も遺品中には皆無です。」とのご返答が訝しかった事を記憶するが、前記琴書の用意周到の例もあり、深く参禅し悟入した也軒翁の事ゆえ、時宜を得た然る可き配所へ、と容易に推察されもした。
現在の筆者小研究所から旧東黒門町、広小路へと通じる御成道沿いに、丗年近い前迄筆者の良く通った廣田書店なる古書肆があり、何と故老板は也軒の実弟廣田金松氏。或る日のご遺族直の話に、「美術学校の帰途、雄作翁は二頭立ての馬車に乗り、折々気軽に立ち寄った。」等との話があった事を記憶する。通う中にも也軒翁の書を何点か都合して呉れた一が前々号図版の端正な書軸で、雄作少年が動乱の幕末期に高林二峯に学んだ書法は端正さを留め、維新後の書も翁の品格を見事に投影している。
同じ頃のとある一日、佐久間象山(一八一一~一八六四)の琴師仁木三岳(一七七一~一八四〇)の後裔をお訪ねした時、思い掛けず珍しい也軒の帝室技芸員の落款の入った「雛の図」を拝見するを得たし、更に筆者の若い頃、京都の三条辺りの古玩店の店先に、也軒翁の断簡が可成り纏まって出ていたのが眼に留まったが、○と縁の双方共が没かったに相違ない、今にして想えば何とも惜しい事をしたものだと後悔頻りである。
『仏説造像量度経』今泉雄作訓点
也軒欧州留学中の明治15(1882)年の2月、偶々英国オクスフォードに滞在中の真宗大谷派の学僧南條文雄に此の『仏説造像量度経』を借覧した。
前年南條はパリで清国公使館の楊仁山に該書原本を供与され、也軒は訓点と梵語を増補し、帰朝後直ぐさま明治17(1884)年版権免許を得、翌年10月出版したのである。
当時也軒は多くの文人が好んだ金杉村に住し、其の栖を無礙庵と称していたが、此の頃既に庵蔵の琴書は少なくないには大いなる事由が有る。
「也軒翁の墓碑」
墓は牛込天神下の交差点の近くにある矢来のお釈迦様として有名な一樹山宗柏寺にある。
也軒の著で広く世に知られたは『日本陶瓷史』及び『茶器の見方』等であるが、仏書の『釈迦像の研究』や次図の『仏説造像量度経』等もある。
也軒自身は参禅し深く悟入した人物だが、終の棲家は撰ばずに日蓮宗、同じく三帰依の弟子に変わりは無かろう。
39
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第33話
東台琴客余聞 四 井上竹逸
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
余談乍ら、池之端の横山大観の媒酌人は也軒雄作翁で、横道序でに、筆者中学の同級で近席の大変なシャンが、大観画伯の令孫横山操嬢であったし、ブラバン(吹奏楽部)取り巻きの一人で、何かしら懐かれて困惑していた下級生女子生徒の家が初音町交差点(旧本郷田町)の寺で、隣に未だ三流映画館が在って時折鑑賞(サボり)に行っていたが、何と、この寺に井上竹逸の墓(後出)があったのだから、奇縁恐るべし! …。
也軒琴学の師井上竹逸(一八一四~一八八六)は、幕末から明治に架けて活躍した琴客で、無論御同輩諸賢の知る処では無かろうが、然し、渡辺崋山門下の四天王に数えられる人と謂えば、其の名のみは記憶に残る御仁も或いは有るやも知れぬ。
竹逸、通称は玄(源)蔵、名は令徳、字は季蔵、竹逸と号した。例の元禄赤穂事件で加増され、世の憎まれ役となった梶川与惣兵衛(旗本千二百石)家幕末期の御用人である。竹逸は鳥海雪堂に琴、高島秋帆に砲術、渡辺崋山に絵画を学び、何れも優れた成績を修めたが、矜持高く然も性豪快、一旦意に決する処有らば自らの質をも顧みず、他の為に全力を尽くす。と言った江戸っ子侍でもあり、「生涯売り絵は描かぬ」、との信条を貫き通した為、初代黒川亀玉以上に巷間遺作は見聞せぬ。
旧幕臣中根香亭(一八三九~一九一三)は、下谷の文人仲間であった竹逸から借覧した琴書雑記『竹逸琴話』を基に、毎日新聞に「七絃琴の伝来」を連載し、明治中期の新興知識層(新聞購読者)に、幕末以降漸く忘れ去られようとした「琴」の紹介に文筆を以て務めたのである。
此の竹逸の琴門に、本邦明治美術界に名を留めた今泉無礙こと也軒雄作翁が在った事は前々号来御紹介の通りだが、偶々寒斎架蔵の『書画苑』一巻第三号(一九二〇年七月号)に、也軒が琴学の恩師竹逸の事を「奇人井上竹逸」との題で書いたを見い出したは、既に四十年近き以前の事。
一読して看れば、本来ならば地下に埋没して然るべき市井日常の一齣だが、也軒翁の筆忠実に援けられ、平成の御代に江戸の一琴客の気概を知らしむる為にも、茲に煩雑を厭わず全文をご紹介せずばなるまいし、此の小文を公刊し竹逸の逸事を遺した也軒翁の筆功も、我等琴客の心底に留めねばならぬ。也軒にしてみれ少年時代に海山より深い恩寵を受けたに、恩返しの機を逸したま帰国後暫くして世を去った恩師へのせめてもの返礼の意があったろう。
「今泉也軒伝」
松井友石著より『談琴』大正6年(1917)年 未刊本
浪速の儒医で、琴系を明治に繋いで功績の有る妻友樵(1826~1896)の男として生まれた友石(1857~1926)の事は後に述べようが、其の著『談琴』(二巻)は、本邦近代に於ける末尾を飾る最後の纏まったとも云える琴書で、此の要約版が同人の『琴話』(後述)で
ある。
就中、巻下「談余一」の「琴師略歴」に紹介されるのが、今泉也軒で、「…竹逸に琴を学び、十六曲を卒ふ。也軒琴書を多蔵し、心越齎来する所、及び心庵(町田石谷)蔵する所、皆也軒の書庫に帰す。近(ちかごろ)其の散逸を恐れ、諸(これ)を上野図書館に挙納すと云う。」と、也軒蔵の琴書に触れるが読めよう。
識蓄古琴十面扁其廬二十琴館學法于友樵明治三十年九月十五日寂年六十
今泉也軒
名彰字有常擁雄作又號文峰故幕府士精于鏖識慶應末學斧于竹邈平十六曲也軒多藏琴書心越竹簡來及心庵所藏皆歸于也軒書庫的恐其散逸譽納諸上野圖書館云
佐治謙堂
名自謙故佐倉藩士學琴于竹逸明治卅七年二月一日没年八十二
44
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第34話
東台琴客余聞 五 井上竹逸
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
旧臘イブ、旧奏楽堂での演奏会直前、月夜越しに眺めた旧上野図書館の甍の何と素晴らしかった事か。
然し、終演後芸術院脇に置いた貧乏音楽家の足チャリが無いではないか。茲十数年に亘り縦横無尽に吾が手足となって闊歩して呉れたに…。
音楽会での足、更なる追い打ちのチャリと一挙に両足を失い、止む無くナケナシを叩(はた)く。一両日して未曾有の冬嵐に祟られたが、打って変わった翌日の快晴に送られ心機一転、起死回生。琴客井上竹逸の事績を准わんとて御成街道を上り、其の儘韻松亭前へと出、真正面の東博、図書館、奏楽堂、そうして東漸院と知ってか知らずかチャリは軽快に走る。
東漸院では折良く庭内作務中ご住職筑土秀玄師の大黒様に事情を話し、幸いにも昔話を伺う事が出来た。
往時の寛永寺は寺領一万一千石余を誇り、就中、東漸院は権威ある表別当の一千三百七十石扶持として、徳川三代将軍家光公(一六〇四~一六五一)の大猷院殿御霊屋なる廟に到る参道に接し、廟には警護の山同心(寺侍・寺役人)が常駐し、東漸院は今に数等倍する寺域を持ったと。
廟域は今の東博(旧日光御門跡跡地)と両大師の間を抜け、忍岡中学校から今の鶯谷駅へ出る凌雲橋(旧鶯坂)左手に到り、大黒様の輿入れ後迄も茶屋の跡らしきものがあったと記憶されるので、次掲の「…上野東漸寺跡に設け、茗を売り客に待す。…」との記述は、幕末、彼の彰義隊と官軍の戦で寛永寺の大半が荒廃に帰した際、廟と東漸院との境が曖昧となり、どうやら其の後一般には此の廟域と東漸院寺域(東漸山)を混同して居た事が原因らしい。
友石『談琴』の井上竹逸の項には、「…曾て一茶店を上野東漸寺跡に設け、茗を売り客に待す。一椀の直(あたい)銅貨一釐、因って扁に曰く一林亭と。蓋し林と釐の邦音相近し。而して壁に古琴数面を懸け、客に請う者の有らば、則ち弾奏するを辞せず。嘗て旧主の駿州に在りて生計窮乏の状を聞き、大いに之を憂え、愛する所の琴を鬻ぎて、若干の金を得、直ちに往きて之を献ず。州人皆其の忠の厚きに感ずと云う。
明治十九年四月三日没す。年七十三。門人今泉也軒、佐治慊堂、青山碧山、其の遺音を継ぐ。」とある。
大猶院廟前から屏風坂(両大師橋)、旧下谷六間町(下寺町)へと続く塔中と、東台沿いに大きく迂回して鶯坂(凌雲橋)を含む山裾の部分を切り崩し、日本鉄道が明治十六(一八八三)年開業の鉄路とした。
「東漸院」と「鶯坂」
写真は無論現在の東漸院で、也軒の文中には、「…鶯坂上(今は切崩されて鉄道線路になつてゐる)の東漸院と云ふ寺を賃借して、一林亭と称し、矢張茶見世を経営してゐた。…」とある。
鶯谷駅は明治四五
(1912)年の開業。
鶯坂(新坂とも)を上って直ぐ左手が嘗て東山とも呼ばれた見晴台で、茲に昭和廿九(1954)年今の忍岡中学校が建設された。
下の写真(『台東区の学校』より)は明治四+(1907)頃の鶯坂で、右手岡上の建物がどうやら元の竹逸の茶店の名残らしい。
現在の「韻松亭」と「東京博物館」
韻松亭は明治八(1875)年に開業許可、因みに静養軒は九年である。本来官営の上野公園諸機関の原型は、既に明治六(1873)年、百年後の今日を見越した初代博物局長(東京帝室博物院院長)町田石谷畢生の建議で決まっていた。
48
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第35話
東台琴客余聞 六 井上竹逸
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
次に也軒筆の全文を掲載しよう。(改行の責は筆者にある。)
奇人井上竹逸
今泉 雄作
吾輩が井上竹逸翁と相知ったのは、翁が日暮里に在住してゐた頃のことである。
当時家は今の日暮里停車場附近にあつて、庭に吹き抜き井戸があつた。其の泉の流れ出る音に何とも云へぬ閑雅な趣きがあると云つて、其処に瀟洒な蝸廬を営んで、妻に茶屋を出させてゐた。
常に愛して猿を養ってゐたので、人呼んで猿茶屋と云ひ、翁自身も猿茶屋の爺さんを以つて納まつてゐたので、翁が絵画に傑出した手腕を持つてゐたことなど知る者は殆どなかつた。翁は絵画に堪能であった許りでなく、七絃琴の妙技に達してゐた。
七絃琴は人も知る如く、舜五絃の琴を造り、文王一絃を増し、武王更に一絃を加へて七絃としたと云ふ、支那三千年来の楽器である。唐詩選に独坐幽篁裏、弾琴復長嘯とか、明朝有意抱琴来とか云ふ琴は此七絃琴のことであつて、長さ三尺六寸、現今婦女子の間に専ら行はる、十三絃の琴とは、余程趣きの異なった高尚なものである。
翁は非常に此琴を愛して、常々不足勝の生活をしてゐながら、支那の銘ある立派な琴を十五六面も所持して楽んでゐた。
実は吾輩も琴曲の弟子として翁に私淑した一人であつた。翁遺愛の琴の一面は現に吾輩の手に伝つてゐる。吾輩が翁に師事したのは十六七の頃から二十七の歳、欧州に留学するまでの十年間であった。
其の間吾輩も随分熱心に研究するし翁も身を入れて教へられたが、吾輩が愈々欧州留学と決して其の暇乞に行くと翁は何時になく立腹して、予が琴曲の奥儀を伝へるものはお前一人のみと思つてゐたのに、今更世俗の名誉心に駆られて洋行するなどは沙汰の限りであると、碌々挨拶もして呉れなかつた、却々一徹な老人であった。
日暮里を引払って後、鶯坂上(今は切崩されて鉄道線路になつてゐる)の東漸院と云ふ寺を賃借して、一林亭と称し、矢張茶見世を経営してゐた。
其の後間もなく、鶯坂下に居を移したが、其の頃はもう大分貧乏して、書斎を建ては建てたが、雑作の障子を買ふことが出来ず、寒い頃などは、日中紙帳を釣って、其の中で琴や琵琶を弾いて、超然としてゐたことなどがあつた。翁は琴と共に平家琵琶を善くした。
(続)
「寛永寺図」延宝年間
『寛永寺』寛永寺教化部編より
此の図は江戸中期前の東叡山全図だが、基本的な塔中等の配置は彰義隊の戦闘迄変わらぬ。
幕末の琴客井上竹逸は崋山門下四天王に数えられる画家でもあるが、幕末から明治初期を代表する煎茶人としても著名である。
東台(上野東叡山、俗に上野の山)に於いて八橋売茶翁に倣い、前号御紹介の東漸院より賃借した「一林亭」なる茶店で、当時未だ一般に普及せぬ煎茶を、机上の空論ならぬよう客に一厘の廉価で供し、煎茶道と併せ、請う者があれば自己の琴道も実践していたのだが、「上野の花見其他」(『江戸時代文化』4月号第1巻第2号1927年刊参照)なる也軒筆の別稿に拠り、幕末期迄は山では一般には茶は禁じられていた事が解り、明治ご解禁となり、晴れて上野山での魁として竹逸が茶店で茶を振る舞うようになったのだ。
現「国際こども図書館」
東京博物館の左手の道沿い左が往時の上野図書館。文化財研究所を右に見て突き当たると徳川五代将軍綱吉公の常憲院廟前。右折し隣接する墓地の奥が現在の三代家光公大猷院殿廟で其の真下が鶯谷駅となる。
図書館は、東京図書館、帝国図書館、国会図書館上野分館と変遷を辿ったが、元々は寛永寺塔中明応院で、此処で元初代博物局長町田石谷は最晩年を過ごした。
石谷遺愛の琴書を始めとする茶・仏書群は部下で博物館東洋部長でもあった今泉也軒に譲渡、也軒は後に是を一括して帝国図書館に寄贈した。
41
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第36話
弘一法師「一輪明月」
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
弘一法師とは剃髪した李叔同(一八八〇~一九四二)の法名で、偶々本誌前号の「続・書人今昔」(89)に紹介された清末民初に活躍した芸術家で、後に厳格な律宗の僧となる。
此の弘一法師を題材とした「一輪明月」という初の伝記映画があり、実は斯く言う筆者も端役で出演する。製作は北京の国家広播電影総局。総監督陳家林、中国仏教協会後援で、現代中国のトップスター濮存昕が主役の李叔同、架空のヒロインである日本女性雪子を台湾の徐若暄が演じ、二〇〇三年にクランクインしたが、残念な事にフィルムは上海映画祭で試写の際には相当の評価を得たにも拘わらず、其の内容が余りに地味且つ真面目な為と、却って買い手が付かず、中国本土でも日本でも遂に上映されず終いであったが、幸いにもたった今(二月七日)、此の原稿執筆中に東京の中国大使館で試写会をすると言う朗報が有ったばかりだ。
李叔同は天津の名家に生まれ、上海の南洋公学で蔡元培(一八六八~一九四〇)等に学んだ後、明治卅八(一九〇五)年秋に来日。東京美術学校の留学生として専門の油彩の他、隣の音楽学校で本格的な音楽を聴講したり、又、当時日本の伝統的な旧劇系統から離脱した新劇(中国では話劇と言う)を実地に学び、五年後に帰国し、近代中国にいち早く是等を紹介した先駆者でもある。
映画のロケ地は杭州、上海、泉州等全て中国で行われ、上海郊外の松江の映画村のロケには筆者も参加し、美術学校での叔同直接の教官であっ黒田清輝大先生の役を賜ったが、全編は未だ鑑賞していなかった。
長い出番待ちには、存昕氏と共に長時間親しく語らい、彼は之の役に就くや、叔同の若さと後の窶(やつ)れを表現する為、苦労の末ダイエットし数kg痩せた話や、元来人間の精神性に興味を抱く性格である為、此の機に仏典を深く味読した事、更には、叔同も琴を学び、脚本中にも琴を少し弾く場面が有り、偶然にも筆者の親友である上海第一の古琴家龔一氏に就き、撮影の為に初学の指法を学んだと聴くに及び、両者共其の奇縁に驚きもし喜びもした。全てのロケが終了、打ち上げの飲み会後には、存昕氏自ら筆者の部屋を訪ねられ自分は北京に直帰する為、撮影の為龔一先生からお借りした高価な琴を、丁重に龔一氏にお返しして呉れと、大切な役を仰せ付かったのである。
と言う訳で、フィルムには痩身の存听氏迫真の演技と、太り気味の筆者が一寸だけ登場する羽目になる。
中国映画「一輪明月」パンフ
監督は巨匠陳家林、演出は路奇で、此の作品は中国2005年放送映像大賞で映画華表彰賞を受けた。
当初は、宣伝用のデモ版DVD(右)とDVDも極短期間のみ発売されたのだが、是も諸般の事情から直ぐに発売停止となってしまい、日本では鑑賞する手立てが全く途絶え、早くも幻の映画となってしまったかに思えたが、2007年初頭、正規に「弘一大師生誕百廿五周年」記念と銘打って、中国郵政省の記念切手とのみドッキングされたDVDが中国で限定発売された。
谨以此片献给中国近代文化艺术先驱一代大德高僧————弘一大师
林路奇談存昕
「弘一法師臨終前昼像」
弘一法師筆「般若心経」
1970年東京観音慈航会刊
日本でも一定の評価を得ていた李叔同の作品は、現実に斯く翻刻されて日本人にも紹介され、有る意味で良寛さんにも相通じた其の書体は弘一体と呼ばれ臨模され親しまれた。
金剛般若波羅蜜經
姚秦三试法師鴯摩羅
如是我聞。一時佛在
與衛國祇澍
國與大比丘眾千二
42
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第37話
東台琴客余聞 七 井上竹逸
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
当時前住の東漸院から大きな庭石を貰ったと云つて、貧乏のなかからひと工面して大勢の人足を雇ひ、気(木)遣り歌か何かで坂上から坂下まで大石を曳いたことなどがある。
又或時は尾州屋敷から出たと云ふ仏像を手に入れて来て、拝仏会と称し、友人知己を招いて貧中一夕の大宴会を開いたりした。翁は全く世俗の生活になど拘はつて居らなかった。翁の趣味は却々多方面で、琴、琵琶を弾ずるのみでなく、最も古銅器を愛し、可成収蔵してゐたが、貧乏義侠心の為に生前大抵は売り尽して了つた。
殊に旧主家の倒産没落を聞き、家財を売って其の急を救ったなど、云ふ逸事がある。旧主と云ふのは、幕府麾下の士で、忠臣蔵の芝居で有名な本蔵を出した、梶川与曽兵衛と云ふ武家である。
翁は決して並々の風流人ではなかつた。されば今日其の筆に成る絵画を観るに、到底凡俗画家の企て及ばざる異彩を認めることが出来る。翁は絵画を渡辺崋山に学んだ。然し恬淡清廉なる翁は、生前決して潤筆料を取つて揮毫すると云ふやうなことはなかった。只楽しみに書く、書いたものは深く是れを匣底に収めて敢て人に示さなかった。
死後長持を開いた所が、大小の絵画が山程出た。然もそれが皆無落款で、如何にも翁の面目躍如たらしめてゐた。其の無落款の画へ、偽筆書きの名人、鳥居敬助と云ふ男が翁の落款を入れて世に出したり、又狡猾な骨董屋が、竹田や崋山の名を署して売買したりしたので、洵に翁の画として世に伝はるものはないのである。
翁は明治十九年四月三日、七十三の寿を保つて永眠した。墓は本郷丸山大善寺にある。
翁には数人の子供があつた。長男は警官を奉職し、家督は末子の源三郎氏が継いでゐる。二男に西松、三男に申松と云ふ奇名を持った子供があつた。余り可笑しいから或時其の因縁を訊ねたら翁は真面目な顔をして、山王祭りの行列に一番に酉が渡り、二番に猿が渡るのをお前知らぬのかと云はれたには思はず哄笑を禁じ得なかった。翁の如きは全く天来の奇人、近世稀れなる仙骨の高士と云ふ可きであらう。
(以上)
鳴呼竹逸、何と清々しい人物であろうか。其の師にして筆者今泉也軒なる弟子が育ったのだからして、世の似非文人須く以て肝に銘ずべし。
「井上竹逸の墓」
筆者は東大農学部前の西片で中学生の頃迄育ち、杉並、信濃町、そして小石川、現在の湯島と転々としたが、小石川在の折りには旧丸山福山町の「福山アパート」に書斎を借りていた。是が木造三階建ての名物アパートで、子供の頃には未だ軍艦の様な偉容を誇っていたものである。
西片を下ると初音町の交差点の手前が昔の本郷田町(丸山福山)で、其処の寺に竹逸の墓があったのだが、寺は本郷台と小石川台地に挟まれた旧中山道に側した底地に在り、大雨の降る度に水が溢れる為、やむなく転地した経緯がある。
廿年もの後、又候隣町の小石川に舞い戻った折、佐久間象山の琴師仁木三岳の後裔を訪う可く、巣鴨のヤッチャ場附近のお宅を訊ねようとすある矢先、偶々通りすがった寺が、田町から移り軒を借りた記憶にある寺名で、約束の時間には未だ早く、ならばとフト山門を潜れば、何と何気に目前に嘗て見覚えのある竹逸の墓石が在るではないか。
「茶会に於る竹逸」
『楓川画集』大正9(1920)年刊より
琴客松井友石の岳父松井釣古(楓川亭)。幕末から明治期の東京煎茶道第一の大立者でもある。釣古が弘化から明治の初年に描いた書画帳に、慶応中尾張町静山楼での煎茶会に於ける竹逸等が写される。
惜しむらくは人物が特定されぬが、髷を引っかけた者の右側三人の内、チョン髭を蓄えた手前二人のどちらかが竹逸で、花は老梅とある。
48
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第38話
宋台琴客余聞 八 井上竹逸
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
竹逸琴士は画家たる一方で煎茶人としても著名で、幕末から明治初期の書画会や煎茶会に度々其の名を見出すし、自前の茶屋も持った。
竹の琴弟子今泉雄作少年こと後の也軒居士は聖堂で学ぶエリート、且つ審美眼鋭い青年で、尋常ならぬ奇人の真価を早くも見抜き、竹逸を師として仰ぎ十年も其の膝下に育まれたのだが、也軒が後年点茶人、或いは在家禅人として名を成すのも案外那辺に要因が有るやも知れぬ。…
竹逸の父親は忠輔方久と言い、矢張り幕臣梶川家譜代の執事で、其の父が嘉永三(一八五〇)年六月三日に六十九歳で身罷った時、竹逸が立派な墓を建て之を弔ったのだが、竹逸自身の没する際は、同じ墓石には「明治十九(一八八六)年四月三日寂滅」とのみ記し、実の息子に名すら刻させなかった江戸っ子気質。
聖堂で学び始めた雄作少年は、八丁堀から日暮里の竹逸翁の元へ琴学稽古に通い、熱心に琴を学んだ。
也軒の『奇人井上竹逸』には、「当時家は今の日暮里停車場附近にあつて、庭に吹き抜き井戸があつた。其の泉の流れ出る音に何とも云へぬ閑雅な趣きがあると云つて、其処に瀟酒な蝸廬を営んで、妻に茶屋を出させてゐた。」とあり、現在のJR日暮里駅の直ぐ近くに泉が流れ、茶屋の庭園には猿公が飼ってあったと言う。今にして想えば隔世の感頻りと言うもので、幕末は夢の昔の事だ。
之を引き払い、前述の東漸山で又茶屋を出し、又暫くして更に東漸山下直ぐの寛永寺領根岸に居を移した。其の頃はもう既に大分貧乏であったに、「前住の東漸院から大きな庭石を貰ったと云って、貧乏のなかからひと工面して大勢の人足を雇ひ、気(木)遣り歌か何かで坂上から坂下まで大石を曳いたことなどがある。」等々、例え世間的な名声とは無縁乍ら、貧中にも一等抜きん出た精神的傲りの内に日々を送った。
慶応四(一八六八)年五月十五日の上野戦争で過半を焼失した東叡山寛永寺。其の寺域の大半が復興せぬ儘に明治の御代を迎え、結果的に再建余力の無さを幸いに新政府は跡地を召し上げ、後に博物館や図書館を中心とした東京の一大教育文化施設群を建設するが、竹逸は栄枯盛衰と世の変遷とを身を以て体験し乍らも上野の山に拘り続け、茶を煮、琴を撫し、又丹青に耽り、世を眇に眺めつ、尚更此の東台を核とした浄域と娑婆とを跨ぐ桃源郷界隈に於いて清遊三昧に人生を締め括る。是亦有る意味では本懐を遂げたと言えよう。
井上竹逸「仙山楼閣」図
嘉永3(1850)年1月筆[筆者蔵]
前号御紹介の也軒筆『奇人井上竹逸』には、「…翁は絵画を渡辺崋山に学んだ。然し恬淡清廉なる翁は、生前決して潤筆料を取つて揮毫すると云ふやうなことはなかつた。只楽しみに書く、書いたものは深く是れを匣底に収めて敢て人に示さなかつた。
死後長持を開いた所が、大小の絵画が山程出た。然もそれが皆無落款で、如何にも翁の面目を躍如たらしめてゐた。其の無落款の画へ、偽筆書きの名人、鳥居敬助と云ふ男が、翁の落款を入れて世に出したり、又狡猾な骨董屋が、竹田や崋山の名を署して売買したりしたので、洵に翁の
画として世に伝はるものは勘ないのである。」…
と、専門の美術のみならず、一面古書画鑑定家でもある鑑識眼の鋭い也軒の云うよう、崋山門下四天王の一に挙げられる割りには、竹逸の遺作で世に伝わるものは殆ど沒い。
「仙山楼閣」図の小品乍ら極緻密な筆遣いに、崋山門下四天王の一たり、又、前述の也軒筆の実録に毫も誇張の無い事が知れようし、同画の落款には、「庚戌(嘉永3年)首春写祝 茂松琴師栄寿。竹逸々人。」、雅印には琴に因む伯牙高山流水の故事「峨々たる山、洋々たる流れ」から採った「峨洋」、下駄印には「竹逸」、とあり、琴仲間で師匠格の高島茂松の長寿を祝って献呈したが知れるが、同年晩夏には厳父忠輔が逝去する。
49
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第39話
東台琴客余聞 九 井上竹逸
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
上図、竹逸が琴弟子也軒に宛てた書簡中、流石の江戸っ子武士竹逸も、維新後間も無い時勢の波に弄され、縁を離れた多くの侍士同様、生業に苦労する様も垣間見え、聖堂で学んだ秀才周辺の元学友たる人脈を当て込んでの様々な工夫を窺わせよう。 (※改行と句読点は筆者)
先頃て途中二而度々 …略…
来ル十一月朔日より連月朔日十一日廿一日ト、浅草寺内花やしき六三ヤ方へ出張仕、拙画并七絃琴相催候間、何卒諸君子様方御光駕之様、偏ニ奉希候、尤かき手間聴聞料て只見次第也、それも煎茶可給候、申通り夕、より安くい相なり不申、
右段半君様より諸方へ風聴(※吹聴の意)し奉願上候、…略…
御光来奉約候、右篤願用斗ト、早々如件
壬月廿六日 竹逸拝
無碍大君様并 半橋大人樣方
明治新政府は従前の陰暦を太陽暦に改め、明治五(一八七二)年の十二月三日を以て陽暦の明治六(一八七三)年一月一日と制定した。
竹逸書簡の日付「壬月廿六日」の「壬月」との月名は元来無い。「壬」とは則ち「閏」の略字で「閏月」を表す事を鑑みれば、陰暦最後の閏月用例は明治三(一八七〇)年の閏十月であり、彼以前の閏月のある明治元(一八六八年の閏四月は、也軒は竹逸の下に在るも未だ聖堂在籍中の生徒で、「…来る十一月…」とも合致せず、元年説は成立しない。
で、明治三年竹逸は五十七、也軒は既に大君様と呼ばれる廿一歳の青年君子。「吾輩が翁に師事したのは十六七の頃から二十七の歳、欧州に留学するまでの十年間であった。其の間吾輩も随分熱心に研究するし翁も身を入れて教へられたが、…」と、正に也軒は竹逸膝下で琴学稽古に励んでいた頃、明治十(一八七七)年に洋行する七年も以前の事である。
寛政年間以降一時琴学の衰退した感の拭えぬ江戸であったが、嘉永年間に浪速から江戸に出向いた出羽の鳥海雪堂(一七八二~一八五三)が本郷周辺に出張り、琴を筆頭に初学を教授、最後には琴の門人で麾下の大身松平采女正の湯島天神下の屋敷に寄寓した結果、雪堂門に井上竹逸や片山賢(幕府御鷹匠同心)等が集い、東台(上野の山)を中核として切磋琢磨し合い、以後、江戸を引き擦りつも、新都東京の琴客は相互且つ頻繁に行き交う事となる。
晩年矢張り東台を核に活動した竹逸。茶目っ気も交えた此の書面に、江戸っ子侍の気概と辛苦を併せ見る。
「竹逸書簡」今泉無礙宛 東京都立中央図書館蔵
陸軍中将の渡邊刀水(1874~1965本名金造)は、退役後史学研究に没頭、近代名家の書簡を収集した。幸いにも本稿お誂え向きの竹逸書簡が此の「渡邊刀水旧蔵諸家書簡文庫」に収まる。
也軒の庵号無礙は一に無碍とも。宛名「得」字は碍の勘違い、本文中書簡の読み下しは前後の抜粋である。
寒斎蔵の竹逸の幅と書簡(各々ーの記憶)とを今回の原稿に間に合わせる可く本気で捜したのだが、此の数年間の止む無き三、四度移転の為終に見当たらず、幼時厳父から彼程言われた普段の整理整頓が苦手な儘、華甲の歳を迎えて了い、此の先どうも直りそうも無い。で、宿題として出てきた時にご紹介する、と言うことで一先ず御寛容を願おう。
そう、紅衣の後は、痩蘭斎改め濫字を用う可きか…。
往時の「花屋敷」
大正期絵葉書より
書簡中の花やしき六三屋は当然現存せずも、竹逸が丹青と琴、煎茶席に利用した頃の花屋敷の風合いは此の一葉に存し、明治の薫りを色濃く漂わせる往時をも偲ばるゝ。
但し、既にして鉄製の遊具らしきが認められる。
THE BEAUTIFUL FLOWER GORDEN.
HANAYASHIKI IN ASAKUSA PARK,
(大東京)四時行楽の人で賑わう
浅草公園花屋敷
Great Tokyo,
42
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第40話
東台琴客余聞 十 井上竹逸
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
上図『一絃琴』巻頭序言に、此の年七十歳の博識家で井上竹逸琴弟子の大槻如電(一八四五~一九三一)の日うを見れば、 ※()内筆者
「三絃(一中節)ヲ八世一中(都)に学び、四絃(平家琵琶)を福住検校に学び、七絃琴)を竹逸琴士に学ぶ、一絃(板琴)に至りてハ、徒らに須磨栞一巻を蔵するのみ、…」、
全く無関係と思われる当道座末期の福住検校と竹逸が、何と、明治の粋人学者大槻如電音曲の師匠格として繋がる奇遇が斯く明瞭に存する。
更に竹逸に至っては、「…鶯坂下に居を移したが、其の頃はもう大分貧乏して、書斎を建ては建てたが、雑作の障子を買ふことが出来ず、寒い頃などは、日中紙帳を釣って、其の中で琴や琵琶を弾いて、超然としてゐたことなどがあつた。翁は琴と共に平家琵琶を善くした。…」(『奇人井上竹逸』今泉也軒稿)等と、琴は兎にも角にも、貧中にも超然として平曲を嗜んで居たのである。
扨、既に言うよう、吾が井上竹逸は幕末期から明治初年に掛けての煎茶界でも名を馳せたが、琴以外の関連した古玩古書画の世界に於いても、相当程度の位置を占めて居た。
嘉永四(一八五一)年五月十三日、竹は地の利を活かし、琴師鳥海雪堂古稀祝いに寛永寺弁天堂貸席での書画会を主催、何より江戸の文人にとっての不忍池は小西湖に見立てた景勝の地でもあり、盛況裏に収めた。
茲に上図「和漢古物会」たる引き札が有る。西南役後の政情市井も稍安定した頃、同様異名の書画骨董会は全国各地で盛んに行われていたが、之を子細に見れば其の証左に足る。
「明治十二年五月十九日発意
席費一名二付五銭
和漢古物会
午前十一時より午後六時迄開筵
連月十九日柳橋万八楼において
和漢古書画古器物備高覧候二付
同好之諸君晴雨とも御来臨を希ふ
但各君御出品は当日午前九時限
御届可被下候事
幹事…略…、
鑑賞諸家臨席出品…略…、
同盟 …略…、」
欄外には、
「御名前次第不同御容捨ヲ願ふ
但御出品之節者(ハ)
必目録書御録可被下候事」
蛇足乍ら同盟とは同一目的で盟約する連判人の意で、畠山如心、高木法古、楓川亭釣古、樋口趨古等、晩年の竹逸の極親しい間柄の人物が名を連ね、無論、同盟筆頭に在る竹逸は、事実上の推進人の一人である。
『一絃琴』上田芳艸著
大正三(1914)年刊
如何にも雅致なる蔵書印は、象が珍奇なる玉を玩弄するを以て「富田珍蔵」と読ませる。
果たして掬す可き小本の旧蔵者は誰あろう、幕臣富田礫川の男で、真鍋豊平(1809~1899)の後を嗣ぎ第二代全国一絃琴総取締役と為った富田豊春(号渓蓮斎。1851~?)其の人、無論竹逸等の大後輩である。
豊春は清楽を筆頭に琵琶、三味線古曲、一絃琴等に幅広く通暁し、明治初期の音楽界を牽引した。
其の豊春の人と為りを示す愛蔵書は、小本と雖も唯に一絃琴界のみ為らず、書中、明治期邦楽の失われた地下断片資料が鏤められ、実にも稀覯本である。
和漢「古物会」引き札
丁度、同盟の筆頭井上竹逸の名が、中央上下の縦線最下部の左側に認められる。
明治十二(1879)年の五月十九日を皮切りに、以降、毎月十九日の午前十一時~午後六時迄、柳橋の貸席万八楼にて各々五銭の会費で「和漢古物会」は開かれたらしいが、果たして其の終焉を知らぬ。
品出席臨家諸賞鑑
木村二梅
松浦馬角斎
川式胤
横山月舎
市河万庵
柏木探古
シーボルト
永井盤谷
中井敬所
福田鳴彎
高須小梅
目賀田介菴
学古主人
長井十足
馬島谷雨
西村𠮷叟
市川團州
高島藍泉
岩瀬菊谭
佐藤祐誠
寺嶋梅幸
小磯前雪窓
井上松溪
野田成努
加藤仙昇
山内香溪
同盟
井上竹逸
畠山如心
羽島李郷
柏木彦兵衛
嘉木園
高木法古
玉川三二
梅田考古
村山陶遊
山口俊英
佐藤栄中
松林堂
樋口趨古
関根只楽
46
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第41話
福住檢校 井上竹逸
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
楽友薦田教授の御案内を承け、先六月十日両国在の江島杉山神社に参詣し、併せて「江島杉山神社御神宝所蔵品公開」を拝観する眼福を得た。
往時、此の神社を含む一帯約二千余坪は、当道座関東総禄屋敷を兼ね杉山検校の拝領屋敷跡で、検校は病弱であった第五代将軍徳川綱吉公(一六四六~一七〇一)の信任厚く、綱吉公の恩賞を取らせんとの御下問に、咄嗟に「一つ目が欲しう御座いまする。」と答え、本所「一つ目」の地元禄六(一六九三)年五月下賜されたと言う有名な逸話が伝わる。
此の一ヶ月後の同年六月には、平生遠路江ノ島弁財天迄定例の月詣りをしていた目の不自由な杉山検校の為、綱吉公は江ノ島往還の辛苦を慮邸内隣接の地に江ノ島弁財天迄をしてしまったと言う訳である。
諸記録等では知りつつも、初見する彼の有名な絵禄屋敷縁の平家琵琶「倚波」(寛政年間製)や「釣灯籠」、伝綱吉公筆になる「書幅」、「短冊」、『当道大記録』、等々、種々陳列される中にも、琵琶は当道座最末期の総緑検校であった福住検校(生没年不詳、前田流平家七代宗匠都名順賀一)遺愛の一面で、弁財天に報恩の為、文久二(一八六二)年に福住検校が奉納した物である事を知る。
偶々『当道大記録』享保年間(一七一六~一七三六)の記録には、「…職屋敷十老職(となる人々)の増加に伴い、之より後総禄検校の任期を三ヶ月とする、…」との記載があり、其の余りの目廻しさに一寸吃驚したものだが、而て見ると福住検校の総禄期間も三ヶ月という事になろう。
扨、斯く平曲を好んだ井上竹逸同様、嘗ての幕臣や津軽藩士等、実は、極一部ではあるが晴眼の武士が旧幕時代、既に平曲を学んでいた事実があり、是等が基石となり江戸の文人上りの人士間に明治初期から中期に架けての平曲趣味が興るが、麻岡検校の弟子の福住検校門下に大槻如電、如電の琴師が井上竹逸。青山晩翠、深川忍山、福地桜痴等の如き元武士達も皆一端の平曲愛好家であった。
無論、一般に晴眼者が元検校等に平曲を学べる様になったは、新政府明治四(一八七一年十一月の「盲官廃止令」の御布令で当道座が廃止され、警官制の庇護を失った検校や勾当等が困窮し、新たな生業の一助に止む無く寄席芸等に身を窶した、侍とても御同様の頃である。尤も、当道座の規範が無効になったからと、一挙に平曲愛好家が拡張される訳も無く、素養の有る者以外には相変わらず一般とは無縁の平曲であった。
「江島杉山神社」の参道より
該神社は人も知る、芸事の神でもある江ノ島弁財天を勧進してお祀りした一社と、鍼灸の神様と謳われた江戸中期の杉山和一総禄検校(1610~1694)を祭神とする両社より成り、来る平成22(2010)年には、御祭神杉山検校の生誕400年を迎える。其の為記念行事の一環として初めて「江島杉山神社御神宝所蔵品公開」が催された。
平家琵琶「倚波」(さゞなみ)
江島杉山神社蔵
琵琶箱の表蓋裏に書された福住検校の箱書きを読めば、()内筆者
「右の琵琶は則ち長田左太夫の作なり、寛政の頃京師二老(当道屋敷職官)松浦検校経瑞一秘蔵の後、薩州公之を蔵し、前の宗匠麻岡検校長歳一之を賜う、其の後先師予(杉山)に伝へ、予之を秘蔵する処、検校座中関東総禄職之命を蒙り、滞り無く勤務する所は、是則ち天女(江ノ島弁財天)の与う護りに応へ、其の報恩を謝徳する為、之を永く奉納し、神徳を仰ぐ也、 時に文久二年壬戌三月前田流平家宗匠総禄福住検校順賀一誌」と銘記してある。
42 △目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第42話
「普庵咒」夢境
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
「普庵(安)咒」、別名「釈談章」は、中国臨済宗第十三代法嗣普庵禅師の咒語を後人が模した作と伝えられる琴曲で、主に書斎で奏でられる文人音楽の「琴簫合奏」と言うジャンルに於いて好まれる演目である。
琴簫合奏とは、則ち琴と洞籍の二重奏で、勿論、琴とは俗称七絃琴の謂いである。之を例えるならば日本の箏と尺八の合奏を更に上品にしたものと思えばさして遠くない。
洞籍は日本の尺八に似た縦笛であが、琴と同じく書斎の楽器「竹友」として古くから文人達に愛玩珍重(「前赤壁賦」蘇東坡)され、特に琴と合奏する洞籍を「琴簫」と言い、一般の洞籍よりも細長く、音程も低く且つ繊細に製作される。琴が主体の琴簫合奏では抑制され従に徹する為、非常に吹奏の難易度が高い。
「普庵咒」は数多の琴譜集に採用されるが、就中、溥雪斎の伝譜は白眉とされ、筆者等も該版を愛用する。
朝まだきであろうか、靄の中から静かに聞こえてくる日課の看経の声。漸ては高潮し三昧境に到るも、何時しか又禅院は元以上の静けさに戻るのだ。無から有、有から無と景を叙述し、且つ反映した物体を心象(情)に移行する。漸く曲が終わり指を静かに降ろせば、未だ彼我と不可分な現実世界に戻った自己が其処に存在するのにうっすらと気付く。吾か蝶か、正に古刹に禅を聞く間に、恰も鑑賞する眼前の文人画の画面中に何時の間にやら自身が入り込み、画中にいる自己の眼から、鑑賞している自己の眼を是亦凝視するかの様だ。
明末清初の乱を避け杭州から中国曹洞宗第三十五世の正宗東皐心越禅師(一六三九~一六九五)が渡日し、其の遷化の後、幕儒人見竹洞と麾下の大身杉浦出雲守琴川に拠って編纂された『東皐琴譜』にも禅師自ら諧音した「釈談章」として所収される。
平安朝末から約六百年間途絶えていた本邦琴学は、禅師の東渡を切っ掛けに中興、後に江戸琴学の所謂心越派(流とも)が形成され、其の中心たる牛込の琴社へと系譜は続く。
東皐心越─人見竹洞─杉浦琴川─小野田東川─幸田子泉─児玉空空─新楽閑叟─山本徳甫─高倉雄偉…
禅師四伝で東川門最古参の幸田子泉(麾下の士。中根元圭門の著名な算学者)は、自らの琴系の釈氏伝来を常々不服に思い、『東皐琴譜』の「釈談章」を生涯弾ぜず、却って他譜を弾じたが、釈氏を軽んじるならば他譜の「釈談章」をも弾ぜぬ筈、自系を否定した事をも気付かぬ侭に、蛹状の心で師の東川より先立った。
杉浦琴川「釈談章」琴譜跋
『東皐琴譜正本』より
東皐心越禅師の遷化は元禄八(1695)年九月の晦日、人見竹洞も後三ヶ月にして没し、二師の遺志を継いだ杉浦琴川が幕職の間隙を縫って漸く『東皐琴譜』を整稿したのが宝永七(1710)年暮れの事。
琴川の自序は同年秋八月、「釈談章」跋文が同冬、琴川は惜しくも翌正月には急逝し、為に是亦刊行は頓挫。公刊は其の後の三百年を待たねばならぬ。
『東皐琴譜』が幻の琴譜と言われた所以である。
「溥雪斎小照」
1893-1966
雪斎は清朝の宗室で清末道光帝を祖父とする。本姓は愛親覚羅氏、漢名は溥、満州正藍の貴人である。
「溥雪斎対聯」
往時、宮中の皇族は皆文雅に親しみ書画と芸術を嗜む風習の有る中にも、雪斎は端正で品格の高い琴を奏し、兼ねて同様の書画をものした名家で、清末、民初から解放後までの長い間北京を中心に琴界と美術界を領導した。
北京郊外香山東麓の名刹碧雲寺で書した対聯である。
54
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第43話
祇園寺緑蔭
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
本連載中、本邦琴学中興の祖東皐心越禅師(一六三九~一六九五)を度々取り上げるが、去る九月一日、御住職小原宜弘老師のお招きで、禅師を開山とする水戸祇園寺へ赴いた。
如何に研究の為とは言い乍ら、筆者たるや祇園寺への往還は青年時代から此の四十年以上の間に数える事すら出来ぬ程だが、良く住職の御話しを伺へば、何でも茨城県曹洞宗青年会主催の伝統行事「緑蔭禅の集い」なる催し会場が祇園寺と決まり、参会者も百人を超えるが、既に三十四年回も続く泊まり込みの此の座禅会に、祇園寺の紹介をす可く筆者の琴を是非にと御住職の要望であった。
寿昌山祇園寺は、中国曹洞宗寿昌派第三十五世の正宗である東皐心越禅師を開山第一世とする。禅師は明末清初の乱を避け、杭州から舟山列島を経て長崎に上陸し、紆余曲折の後、最終的には天下の副将軍・水戸黄門徳川光圀卿の知遇を得、援けら元々此の地に在った岱宗山天徳寺へ入堂。禅師寂滅後に天徳寺を領内河和田へ移転させ、禅師を開山として新たに寿昌派の祇園寺を建立した。
日本寿昌派は光圀卿の庇護や東皐禅師の勧化に因って最盛期、其の末寺は三十数ヶ寺を数えるに到ったが、心越禅師亡き後、直接其の警咳に触
れた僧侶等の活躍した時代は兎も角、以後は漸々と衰退し、加へて幕末から明治初期の水戸藩の政争等で、さしもの祇園寺も無住となるまでに荒廃してしまい、末寺も大方は黄檗や日本の曹洞へと改宗してしまった。
明治期曹洞の傑僧浅野斧山は慶応二(一八六六)年名古屋の産。十四歳で尾張法持寺の天珠童拳に就き得度し後其の法嗣となり、将来を嘱望され明治三十五年曹洞宗大学林教授となる。同四十一年常陸管天寺駐錫中、曹洞宗本庁より荒廃した祇園寺の再建を命ぜられ、先ずは寺に遺る心越禅師の遺稿を整理編纂し、禅師と其の遺業とを世に再評価させしめんと急遽『覚世真経』と『東皐全集』を公刊し、祇園寺廿二世として寺の再興に尽力後、中伊豆最勝院に移り惜しくも翌明治四十五(一九一二)年六月一日道栄寺にて示寂するが、茲に斧山師の素志は引き継がれ、祇園寺は現住小原師と先住父子二代畢生の平成大改修の事業を今将に終わらんとし、心越禅師の遺墨集も編纂中。更には此の四月、杭州西湖に近い心越禅師前住の永福寺も重修成って一般に開放。祇園・永福両禅寺は尚一衣帯水、深い緑蔭に囲まれつ、開山を始め歴代住持の篤き想いを秘めて、時を同じうして漸く語り出さんとす。
「本堂での座禅道場」
今号の写真は下の「覚世真経」を除き、全て茨城県曹洞宗青年会のご提供に拠る。誌上を御借りして感謝申し上げる。
「記念撮影」
平成大改修中の祇園寺本堂前で、緑蔭に抱かれた参加者一同と共に
前列左から二人目筆者、小原住職、茨城県曹洞宗青年会会長小嶋弘道老師。
写真では見えぬが、左手前に黄門光圀卿の筆になる「寿昌開山心大和尚之塔」がある。
「小原宜弘老師」
9月1日当日、釈迦誕生から達磨大師、禅、曹洞宗、水戸と祗園寺と系統立てゝ訓話なさる小原老師。
右の幅が祇園寺に伝わる開山東皐心越禅師筆の自画頂相。
「琴と東皐琴譜を前にする筆者」
小原住職に次いで筆者が東皐心越禅師の伝えた琴系に就いて語り、『東皐琴譜』より数曲を演奏する。
「東皐心越禅師筆」
浅野斧山編『覚世真経』より明治44(1912)年3月刊
該経は『東皐全集』に先立ち刊行されたが其の原版は既に無く、享保15(1730)年8月再版に拠り活版とした。
右上の四顆が所謂「関羽七印」の一である。
勅封三累
伏魔大帝
神威遠鎮
天尊
42
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第44話
杭州金華山永福寺 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
 「東皐心越頂相自画讃」 水戸祇園寺蔵
「東皐心越頂相自画讃」 水戸祇園寺蔵二〇〇七年四月廿日、永福寺は元代の上下両院を模範に重修成って正式に一般に開放され、前号祇園寺に続き東皐心越禅師縁の二寺は目出度くも時を同じうして重修新装された。幾多の艱難の末、光圀卿の大翼の下水戸の天徳寺(後の祇園寺)に入堂した東皐心越禅師が中国に在って住職した杭州の名利永福寺は、霊隠寺の西約一キロ現在の区割りで言う所の杭州霊隠景区内に位置する。
筆者が知る頃の永福寺は極簡素な本堂と前庭ばかりの破れ寺で、飛来峰の鉄塔下に位置し、直前迄解放軍の電信隊が駐屯した痕跡が生々しく、通信機器の残骸等が残っていた。
東皐心越禅師(一六三九~一六九五)は渡日前、三十三歳で此の永福寺に入り五年間留錫し、其の間道名日々に高く江浙の地に響き渡ったと言われ、更に其の盛名を遠く長崎唐人五ヶ寺の一、興福寺四世の唐僧澄一(ちんい)が伝聞し、東皐心越禅師を後釜に据える可く長崎に招来した、と言うが事の発端である。
永福寺の山号は現在の中国では佚名された為通用せぬが、浅野斧山師編纂の『東皐全集』には山号を金華山と分明に記してあり、又『西湖遊覧志』と、『西湖漁唱』等には寺の沿革を記して次の様に云う。
劉宋文帝の元嘉(四二四~四五四)年代に、慧林法師が講じた大吉祥寺(青厳寺)を起源とし、南宋度宗(一二六四~一二七四在位)の母君隆国夫人喜捨に因り、咸淳九(一二七三)年其の規模を拡大し、碧色瑠璃の瓦を用い建立された…。
と。其の後元代に上下両院となり、明末清初に東皐心越禅師が住持した後の戦乱や長い歳月で徐々に荒廃し、開放中国の頃には、縮小された清末民国期の小さな本堂を残すのみで、誰しもが寺の故所を特定出来ずにいたが、筆者が何度か杭州に足を運ぶ内にも、東京の寒斎蔵民国廿三年刊『中国分省図』に永福寺が掲るを見出し、一九八五年春、上海滞在を利用し又ぞろ杭州に出掛けた迄は良いが、肝心の地図を音楽院に忘れてしまい、記憶を頼りに尋ね廻り、最後には上天竺迄辿り着いた。
すると其処の寺で何人か談笑して居り、当てずっぽで永福寺を尋ねてみれば、果たして誰も知らぬ。輪中の元中学校の教師だったという御仁が、ならば仏教協会で訊くが良かろうと、わざわざ法云弄の協会迄同道して下さったが、仏教協会でも誰も知らぬ。万策尽きて諦めかけると、誰やらが協会の雑役を務める唐パパ(当時八十歳前後)ならば、知っているかもしれぬと、目前の庭の畑で手入れ中の唐パパを探し出して呉れた。
すると何と「案ずるより…」、即座に知っていると答えたではないか。狂喜し彼の跡に従った事勿論である。今はもう無い光景、霊隠寺道に群れた土地っ子達の茶売り台を横目に脇道に逸れ、小川伝いに茶畑の小径を飛来峰へ向かって上ると、左右に小さな家庵が点在し、更に登れば苔生した破れ寺跡が在るではないか。
其処には本堂跡を利用して剣舞の先生や元々永福寺下の家庵で育った尼姑などが居られ、庭と本堂の境の玉垣には何と我が家の家紋と同じく、「輪違い」の紋が彫刻され、其の奇縁に驚いたものである。
後日、御世話になった方々を招き、細かな接待の席を当時解放路に在っ素菜館で開くと、元教師を始め、唐パパは素朴な如何にも心を込めた手作りの龍井茶と、元尼さんは永福寺に因んだ「福」字の玉を下さり、筆者の永福を祈念して呉れた。
既に亡い此の方々との淡くも清浄想い出を秘め、其の後廿年余りの中で永福寺再建の機運が騰まり、此の度永福寺は旧来にも増して立派に重修されたと言う訳である。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第45話
杭州金華山永福寺 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
日中国交正常化三十五周年と言う事で、二〇〇七年は両国で様々な催しと文化交流が行われ、杭州では四月十九〜廿二日「天籟雲和・第一回国際東皋心越古琴交流会」という催しが東皋心越禅師が嘗て住持した永福寺と、更に是等に因み杭州最新の音楽ホール紅星大劇場ホールで心越禅師記念の琴会や討論会が行われた。
東皋心越禅師が日本に渡り三百三十年が経過した事。又、永福寺の約六十年ぶりの重修完成を祝い、更に是等に因み、禅師に縁の深い日本人音楽家として筆者も招待された。
中国曹洞宗寿昌派第三十五世の正宗東皋心越禅師は、日本では主に「近世日本琴学中興の祖」、「篆刻」、又「詩文」及び「書画」、特に「隷書」善くした文人僧侶として知られる。
禅師は浙江省の金華府婺郡浦陽の蒋家の次男に生まれ、俗名は蒋興儔、母は陳氏で、両親が二子目を欲し永福寺の観音に祈願して禅師を授かった為、八歳の成長を待って俗叔の蘭石霊公により蘇州の報恩寺で剃髪して仏門に入り、以後浙江を中心に各地に師を求め仏道に精進し、更に参禅の余暇に詩文はもとより、琴碁書画篆刻に到る迄、凡そ君子たるもの必須の教養全般を修めたが、此の間には明末の文学史上に残る著名な文人との交流もあったようである。
禅師の東渡の条は既に御紹介済み。江戸期日本の仏者や特に学者間で明末文人の活きた雛形として禅師は尊重され、又、師を称して「僧中に真儒有り」と彼らに言わしめた程の傑物で、貴顕から庶民に至る迄の多様な日本人に崇め慕われたのである。
筆者は家学の関係で三歳から和洋の音楽の初等教育を受け、丁度音楽の中等教育を受けていた十一歳の一九五八年に、戦後初の「中国歌舞団」の来日東京公演があった。其の頃既に将来作曲家兼ヴァイオリニストたらんと懸命に学んでいたが、初めて聴く生の中国古典音楽と、取り分け其の時に演奏された琴曲の音色と其の内容の精神的深さに圧倒され、是を学ぼうと決心した。学ぶ其の中、日本にも琴の伝統が有ったことを知り、特に東皐心越禅師の伝えた琴派・心越流も研究するようになり、前条杭州の永福寺が約数年前に発見された経緯に深く関わるのである。
禅師に纏わる逸話で著名なものは、徳川光圀公の師、「金沢八景」の選者、水戸の目薬「北斗香」の製法を伝えた、「関羽七印の一」の将来者で庶民の絶大な人気を博す等々、今も多く遣り、宮内庁には心越禅師将来の琴が今も四面保存されている。
「永福寺大雄宝殿」
上院にある大雄宝殿で、右に見えるのが「中日仏教センター」となり、東皐心越禅師を記念した日中の仏学研究所となる。
「杭州西湖図」
中国分省図より。民国23(1934)年、商務印書館刊。地図の一番左側稍少し上に、永福寺の在処が見えようか。
「筆者知音の龔一先生と」
元上海民族楽団団長で、国家第一級演奏家の称号を持つ古琴家の大先生も、筆者とは裸同士で付き合う兄貴分で、交流会後の息抜き、西湖遊覧船上での一齣である。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第46話
魏氏明楽 元
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
巷間、江戸期伝来の中国音楽を「明清楽(みんしんがく)」と俗に言い習わすが、少しく日本音楽を学んだ御仁ならば、「明楽(みんがく)」と「清楽(しんがく)」は、其の成り立ちと背景のみならず、曲趣も楽器編成も違う全く別種の音楽である。と言う事は良くご存じの事柄と拝察する。
此の四~六月に姫路文学館で「姫路城主酒井宗雅の夢」展が企画され、為に筆者も担がれて鈍重の腰を上げねばならぬが、之には、姫路藩最後の宗主たる酒井家初祖の酒井雅楽守(忠恭(ただずみ)侯。一七一〇~一七七二)が魏氏伝の明楽に痛く感動してより、以下歴代藩主が是を保護した。と言う歴史があるからに他ならない。
「明楽」の謂いは勿論明朝伝来の音楽と言う事であるが、其の伝来は一に、明の遺臣魏氏家伝のものと、二の他伝のものとがあり、通常魏氏伝のものを便宜上「魏氏明楽」と呼び、他伝をも唯に「明楽」と呼ぶが、実用上専門家でも明確な区別は出来かね、普通に「明楽」と言えば大抵は此の「魏氏明楽」を指すのである。
然うして明楽の内容はと問われれば、唐宋の名詩詞に旋律を附した楽や孔子釈奠(せきてん)の楽、又、仏教音楽等が整然と整い、酒井侯は明楽を知り魏氏四世の君山と相知るに及び、之を藩楽に採り入れんと藩士の師に君山を招聘するのだが、撫や苦心して老臣等を説き伏せた事であったろう。
長崎魏家の初祖魏之琰(しえん)(一六一七~一六八九、字は双侯、号は爾潜、通称九官)は明朝に仕えた士人で、福建省福州府福清県の人である。若くして郷里を離れ、安南と東京(トンキン)そして長崎と、三国を股に主に白糸交易で成功して巨財を成し、明末の崇禎年間(一六四〇年前後)を中心に、東京と長崎間を往来し交互に滞留していたが、寛文六(一六六六)年以降は長崎に定住し、同十二(一六七二)年に官許を得て正式に帰化。其の後長崎奉行の特別の計らいで、
「延宝七未(一六七九)年、御奉行所牛込忠左衛門様より、格別の御懇命を以て、九官元卜明官之者故、其侭明服相用候様との御事ニて、倅共元服被仰付、地名を以て苗字に相定、魏高(次男)を鉅鹿清左衛門、魏貴(三男)を清兵衛と相改、御祝儀の為、九官黄金五版、二子に御脇差壱腰、大判壱枚つつ下し置かれ、…」(鉅鹿家・魏氏『由緒書』)
と、魏氏の大元の籍貫が趙(河北が省)の鉅鹿(きょろく)郡であった事から、帰化に際して九官は魏姓の侭にし、二代目からは日本名の鉅鹿(おおが)姓を名乗らせ、以後代々世襲で唐大通事(とうだいつうじ)の「福州話」担当官に任官させたのである。
『洋峨楽譜』見返し
聚奎堂書院刊 明治17(1884)年7月
元来「明清楽」とは、明やら清やらの中国渡りの音楽の総称であって、明清楽という統一されたジャンルが有った訳では無い。
『洋峨楽譜』目次
先入された明楽は別個に一家を成していたが、後の清の俗曲の大流行に因り、明楽家は疎か、明楽譜までが清楽曲集に収拾され、辛うじて生き長らえたのであるからして、当然、明楽も矜持を捨てゝ清楽器を用いて俗曲風に演奏された事、勿論である。
『洋峨楽譜』全94曲中、図版中の「宮中楽」から「風中柳」までの12曲が明楽曲である。
「小重山」明楽手抄譜『魏氏楽歌譜集』より
【右図】刊本『魏氏楽譜』とは異なる伝の、是又江戸中期の『魏氏楽譜』であるが、刊本は歌詞のみ印刷されて譜は一切無い。伝習を尊ぶが故に、師からの指示で工尺譜(こうせきふ)は記された為である。本例は唱歌、龍笛、巣笙、瑟、小鼓の各譜が記された師匠級の実用した総譜で、遺例は非常に珍しい。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第47話
魏氏明楽 亮
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
明楽を伝来した魏家の初祖双侯は、明末崇禎年間末期(一六四〇年前後)を中心に、東京と長崎間を往来して交互に寄留していたが、既に正保四(一六四七)年には、崇福寺の最有力な大檀越となっていた。
抑も此の崇福寺は長崎寄留の福建省福州人の為に寛永十二(一六三五)年に創建された寺で、福州寺又昔は支那寺とも、伽藍が赤い為に赤寺とも言われたが、寺の梵鐘を寄進するに際して、四人の大檀越の中の最年少三十一歳であり乍ら、双侯は百五十両という最高額を寄付している程の実力者であったのである。
魏家に関する代々の覚書『由緒書』に、
「…其後、明季之勢不任、心底日本之御国風を慕ひ、寛文六(一六六六)年来朝仕り、同十二子年右二子、并召仕魏熹共々四人長崎住居御免、…」
とあり、清の康熙五(一六六六)年、我が寛文六年以来、双侯一家主従四人妻の武氏は無く、使用人は別計)は長崎に居住していたが、六年後の寛文十二(一六七二)年、双侯五十六歳の時に至り初めて、
「…寛文十二年、清人魏九官等帰化シテ長崎ニ居ラン事ヲ乞フ、之ヲ許ス、…」(『続皇朝史略』)
官許を得て帰化し、正式に長崎に定住するようになったのである。同じく『由緒書』に、
「…延宝七未(一六七九)年、御奉行所牛込忠左衛門様より、格別の御懇命を以て、九官元卜明官之者故、其侭明服相用候様との御事ニて、作共元服被仰付、地名を以て苗字に相定、魏高を鉅鹿清左衛門、魏貴を清兵衛と相改、為御祝儀、九官黄金五版、二子に御脇差壱腰、大判壱枚つ、被下置、…」
とあり、長崎奉行牛込忠左衛門勝登の特別の計らいで、
「…九官元ト明官之者故、其侭明服相用候様、…」
と、魏双侯は中国士人に対する処遇で、魏氏のままに置き、
「…魏高を鉅鹿清左衛門、魏貴を清兵衛と相改…」
と、魏氏の本貫が趙(河北)の鉅鹿(きょろく)郡であったため、息子二人の代か日本名の鉅鹿(おおが)姓を名乗らせた経緯も判明するのである。
扨、魏家の初祖となった双侯は白糸交易に携わる傍ら、明の宗室朱氏載堉(一五三六~一六一二)の音楽や廟堂の音楽に精通し、更に明末清初、双侯が頻繁に往来した安南や東京は未だ中国(漢字)文化圏であった事からも、音楽に堪能な双侯は、中国伝来の音楽や、各地の音楽にも興味を持った事と思われる。
「…翌丑年御願申上候而上京仕、不図も於内裏明楽を奏し、御酒御菓子抔頂戴仕、冥加至極難有仕合奉存候、…」(『由緒書』)
双侯帰化翌年の延宝元(一六七三)年五十七歳の折、允許を得て京の都へ上り、内裏に於いて明楽を演奏し、御酒、御菓子などを拝領したと有り、斯うした縁も有って京都に多少の人脈が出来たものと思われるが、唯此の時は魏氏三代の明規や四世に当た君山は未だ在せず、双侯は魏氏二代となった弟の貴こと永昭(一六六一~一七三八)や、その兄で別家した高こと永時(一六五〇~一七一九)に連なる一族郎党を牽き連れて演奏したのであるからして、当然君山は偕に演奏したことにはならぬが、此の明楽演奏は都の管絃好きな人士の記憶に残る画期的な出来事で有った様で、為に是が百年の後、都で家伝の明楽を広める事となる四代魏君山上京の重要な伏線となったのである。
「明服衣巾図」『魏氏楽器図』より
『魏氏楽器図』は、安永9(1780)年6月、魏双侯明楽四代目の継承者である魏君山の門人・筒井景周の篇、京都の奎文館の発行になる『魏氏楽譜』と姉妹編の楽器図及び手引き書で、言うなれば「魏氏明楽」を読み解く為の必須の虎の巻である。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第48話
魏氏明楽 利
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
魏之第四世の魏皓こと鉅鹿(おおが)子明(一七二八~一七七四。幼名富五郎、諱は規貞)は特に音楽に才能があり、又、自負もあつて明和の初年、家学の明楽を伝えんと京都に出て、通り名を民部、君山と号して活躍した。魏家も之琰以来すでに百年を超え四代目ともなり、子明はこの音楽が魏家一族中でも段々と風化し、
「幼きより音律を解し、其の家其の技の妙を悉く究めざるなし、其の伝の博まらざることを聞き、一旦飄然として西のかた京師に遊び、之を同好に授く」(「君山先生伝」)
本来は廟堂にこそ用いられるべき雅正かつ貴重な音楽が、当時長崎一地方の魏氏の家庭音楽としてのみ伝えられている現状に飽き足らず、眈々と機会を伺っていたのである。
そこで魏氏三代・明規(?~一七六九)の嫡男である子明は、弟で第四子の太左衛門規康(後の道流)に一先ず家を任せ、曾祖父・之痰がかつて内裏で明楽を演奏した折りの多少の伝を頼り、子明自身の都で是非とも一花咲かせたいとの強い願望と、並々ならぬ自負心とを持って勇躍京の都へ上ったのである。
「凡そ京に居すること殆ど十余年」と「君山先生伝」にもあるように、この上京は子明三十代半ばの宝暦の末から明和の初め、即ち一七六四年前後の頃では無かったかと筆者は推定する。
京の都で子明は名を民部と改め君山と号し、新生君山こと鉅鹿民部は不退転の意志をもって暫く辛抱する内に、幸いにも筒井景周、芥川思堂、岡崎廬門を始め何人かの有力な門弟も出来、最終的には百人もの弟子に恵まれたのである。亦、姫路藩主の酒井侯(後出)というパトロンも現れ、魏氏伝の明楽は一躍活況をきたし知名度を得るに至る。
其の頃の姿を写した上図を見れば、如何にも自信に満ちた風貌の君山先生である。彼が楽器を持った従者を従え、京の都を闊歩する様が彷彿と裏に浮かび上がる。
芥川思堂(一七四四~一八〇七。京都の人で越前・鯖江藩儒。名は元澄、通称左民、字は子泉、思堂は号)による『魏氏楽器図』引言に言う。
「拙に至り、愚に至るに、加うる以て病多し、音を為す何物をも、律を為す何物をも知らず、晩に君山魏子に従いて其の伝うる所の楽を学ぶ、伊(た)だ吾が暇に、未だ甞て此れに従事せず、
浪華の筒景周、先に已に魏子入室の弟子と為り、諸楽器、阮(げん)など悉く之を善くし、且つ楽器を模擬し、而して之を造りて諸を蔵す、其の家に肆習すること有年、故に余と懇ろに交うを以てす、
余は江南に家すなり、游息の餘、花辰月夕、船を江上に放ち、君と諸友、白(あした)に浮かべて大飲唱歌し、迭(かたみ)に起こる絲管を並べて奏さば、陶々乎として、其の楽の(この間[只且・シショ〕の字あるも助字にして意なし)声音は嗟(なげ)くが若く、以て已むべからず、
易に曰く、缶を鼓して而して歌はざれば、則ち大耋(だいてつ)のみ之を嗟くと、
詩に曰く、何ぞ日々に瑟を鼓し、且つ以て喜楽し、且つ以て日を永くせざると、君に其の意有るか、
楽器図の拳は蓋し魏子没して其の伝の泯(ほろ)び絶うることを恐る、故に之が伝を為し、
之が器を図し、之を上木し、之を同好に公にす、信じて古を好む者と謂うべし、師受の義を忘れざる者と謂うべきなり、
嗚呼魏子、而して其の之を何と謂うか知ることの有るか、予をして言を題せしむ、
謝すに敏からざれば、則ち述回するべからず、君と相得るの状を以て篇に列すと云う、
安永九年庚子夏六月
平安 思堂芥元澄書浪華江浜寓居」
「君山魏先生肖像」
『魏氏楽器図』安永九(1780)年刊 観瀾亭版より
君山は京都に於いては高弟や門人、又理解者とパトロンにまで恵まれ、京阪の地に在った凡そ十余年の内の大半は比較的順風満帆に明楽を伝授して過ごすが、パトロンである姫路侯に先逝され、已む無く故郷長崎に帰り失意の中に病死する事となる。
像肖生先魏山君
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第49話
魏氏明楽 貞
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
前稿中、芥川思堂自ら引言中に言うよう、通常少年期の志学よりは遅く、恐らくは二十代末頃に思堂は明楽を学んだようだが、自身謙遜する以上には余り熱心に学ばなかったことが解る。思堂は師の君山より十六歳年下であるから、君山の再晩年すなわち四十五、六歳頃の弟子と看做すことができる。
思堂が儒者として君山に明楽を学んだ時、すでに筒井景周は同門の大先輩として存在し、其の後に思堂は景周と親しくなったが、之と交際する中にも景周は一般の門人とは異い諸楽器や阮などの演奏法に通じ、其の上各種楽器を模作して已に明楽の専門家然としている。そんな景周の人柄と学識に思堂は驚きと尊敬の念を抱いていた様子が窺え、後年『魏氏楽器図』上梓の際には、文末にあるよう、喜んで「引言」の依頼に応じたのである。
思堂の引言は現役の儒者という事もあり、典拠を駆使した文辞も巧みに、後半『周易』の「離」から、また『詩経』国風から「蟋蟀」(コオロギ)
の例を引く。
筒井景周(生没年不祥)については現在のところ、名は郁、景周と号し、君山の高弟、且つ師の亡き後その衣鉢を継いで門人と結社し、『魏氏楽器図』を刊行し明楽の普及を図った大阪の人とのみ伝わる。
次に筒井景周の「君山先生伝」(『魏氏楽器図』巻末)を読んでみよう。
「君山先生伝
先生姓は魏、名は晧、字は子明、君山と号す。其の先趙の鉅鹿郡に住すを以て鉅鹿氏と為す。
四世の祖、双侯字之は、明朝の仕人なり。朱明氏の楽に通じ、崇禎中、楽器を抱くて乱を避け、遂に吾が肥前長崎に来りて家し、伝習して先生に至る。
先生幼きより音律を解し、其の家其の技の妙を悉く究めざるなし。
其の伝の博まらざることを聞き、一旦飄然として西のかた京師に遊び、之を同好に授く。人の稍明楽なるもの有ることを知り、一時翕然とし名籍の声甚だし。
凡そ京に居すること殆ど十余年。其の従いて学ぶ者、先後百余人、筠圃宮氏之が魁たり。其の名諸王公卿に達す。
近衛相公、之を別殿に召し、先生を師とし門人数十人、而して合奏す。相公大いに之を賞し、数々の褒賜有り、公卿の間に、声名益々興る。
東本願法主、之を枳穀別殿に召し、船を苑池に浮かべて之を奏す。冷泉
為村卿亦坐に在り、和歌を作りて之を賞賜す。
後、姫路侯聞きて之を招き、大いに之を嘆美す。即ち賓礼を以て先生を留めて学び、悉く楽器舞衣を製し、且つ諸近臣をして之を習わせしむ。一時の風靡、将に大行せんとす。
侯の幾も無くして即世す。先生意を失して帰る。後病に罹り、遂に楽器を携へて長崎に帰り、安永甲午の冬、家に終る。
遺言し之を京師の門人に託して日く、吾死せば則ち楽の其の殆どは混びんか、若し吾が志しに続く者の有らば、亦遺恨無しと。その諸弟も亦善く家楽を伝う。
門人結社して遺業を紹(つ)ぐ者、数十人、余も亦末列に厠(まじ)る。
明楽の伝うる所に、凡そ八調あり。其の器、管に四、絃に三、考撃に四、其の詞曲に凡そ二百余。先生没して門人其の伝を得る者、僅かに百余曲。且つ古詩の雅楽有り、聖廟の釈菜楽有り、是其の大較なり。
余先生に親炙すること已に久しく、後世煙滅し、其の由を知る無からんことを恐れ、旧聞を回輯し、録して先生の伝を為し、并に楽器図を著し、以て同好に公にすと云う。
安永九年庚子夏五月
浪華 筒井郁景周謹撰」
「坐楽式」『魏氏楽器図』より
一般に魏氏明楽の演奏スタイルには二種有り、是は其の「坐楽式」である。十一人の楽器と同じく十一人の唱歌、合計二十一人の合奏だが、剛直な武士が左右二列に対面する演奏と唱歌斉唱を想像されたい。
橙花陪診
瑟
月琴全
大鼓
小鼓唱歌
雲会
下坐
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第50話
魏氏明楽 春
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
長崎の魏家では家祖・之琰以来、家学の明朝士人の音楽を、代々伝え絶せぬように温存してきた。然し乍ら其の音楽は合奏を主体としたもので、二、三の人数では本領を発揮するどころか、却って真味は半減するばかりである。
昔の大家族制度を想定しても、魏氏二代を継いだ弟の貴こと永昭は元文三(一七三八)年、其の兄の高こと永時は享保四(一七一九)年まで生存したが、一族郎党から女子や小人を差し引いて、演奏可能男子を十人乃至二十数人を揃えるのは、かなり難しい事と推定され、是等が少なくも特別な場合を除き、明楽の演奏を公開せずに百年間余り秘して来た要因の一つと思われる。又、記録は遣らぬが君山直接の音楽の師は、二代の永昭と三代明規の二人と推定される。
鉅鹿子明は家伝の音楽や楽器を持って京都に上り、民部と名乗り君山と号して魏家父祖伝来の音楽普及に勉めた結果徐々に門弟も定着、其の成果も有り安永元(一七七二)年には近衛相公の命に依り、京都河原御殿に於い大勢の貴人が招かれ、泉水に船を浮かべ其の中で明楽を演奏したのである。
「先生を師とし門人数十人、而し合奏す」
「筠圃(いんぼ)宮氏之が魁たり、其の名諸王公卿に達す」
と「君山先生伝」に有り、是等の斡旋は君山高弟の一人、宮崎筠圃(一七一七~一七七四)の引きに困った事が判る。
当日出席した有栖川宮(一六七二年高松宮から改称)は、
珍しなその品多き物の音の 調べにそへてうたふ唐うた
と詠じ、初めて見聞きする魏氏伝来の明楽に実際の唐風を垣間見、亦此の御殿に招かれ同席したか、若しくは之を伝聞したか、別に東本願寺法主が君山師弟を枳殻(きこく)別殿に召し、船苑池に浮かべて明楽を奏させたのである。
更に和歌の師範で冷泉家中興の祖・大納言為村(一七一二~一七七四)卿は、
歌をうたふ唐声唐ころも 唐人ならで唐めける船
絲竹にあはす唐歌唐ころも 唐人ならで唐めける船
と詠み、その唐風三昧の中に演奏された明楽を絶賛したのである。『由緒書』には、此の事を次の様に記す。
「堂上様方従り厚く蒙御懇命、既二安永元辰年、於河原御殿御泉水、舩楽を奏候節、先年九官上京之節、於内裡、明楽を奏候儀、其御記録にも有之由、近衛関白様御意被為遊候、都而本朝にて明楽流行仕候儀ハ、民部より弘り申候、則其節頂戴仕候御詠歌、
有栖川宮様
珎しなその品多き物の音の 調へにへてうたふからうた
冷泉為村
糸竹に阿はすからうた唐衣 唐人ならで唐免ける舟
右民部儀も、晩年ニハ当所(長崎)に帰郷致、寿を以終申候」
『由緒書』では河原御殿での明楽と、東本願寺枳穀殿における明楽演奏の記事が混同して居る様子にも取れるが、「君山先生伝」では別記されて居る。
又、最後の「寿を以終申候」とは、長崎奉行所を通じ幕府(お上)に差し出す公式文書では、唐通事の家系安泰の為「病死」の語は禁句で有ったのである。
姫路文学館から白亜の姫路城を望む
漆喰の白さ故姫路城は又一名白鷺城とも呼ばれる。幕末に至る迄、此の天下の名城に於いて魏氏明楽は屢々演奏されて居た。
筆者と東京琴社絲竹班に依る魏氏明楽演奏(半隊編成)
此の四月末、宇治の黄檗山内万寿院に於いて、筆者を首班として江戸の文人音楽演奏と煎茶席とが催され、翌二十七日には本前号で予告された姫路の文学館で、「魏氏明楽と姫路」と題したレクチャー・コンサートが二度開催された。恐らくは廃藩置県後、表面的には初めて姫路城下に於いて明楽が演奏された事になろうか。
姫路酒井家が愛した異国の音色一明楽一
講師:坂田氏(坂田古典音楽研究所)演奏:東京琴社絲竹班
△目次TOP↑
連載50回記念企画 痩蘭齊樂事異問
瘦蘭齋樂事異聞50回の歩み
月刊書道界編集部編(かっこ内編集部。主な内容、登場人物など)
2004年
5月号浦上玉堂と琴(浦上玉堂)
6月号東川琴門の逸材多紀藍溪(多紀藍溪/小野田東川)
7月号絃外余響・甲州編(「素封家渡邉青洲の書画・遺品展」/松村志孝)
8月号絃外余響・甲州編二(松村志孝)
9月号聖堂の秀才(久保盅斎/小野田東川)
10月号盲目の琴客岩田健文(岩田健文)
11月号心眼吹笛(舞台「赤いハートと蒼い月」と楊雪元さん)
12月号琵琶交々1(琵琶の歴史と伝播)
2005年
1月号琵琶交々2(琵琶と三味線)
2月号落日の煌めき1(アコーディオン/渡邊節男さん)
3月号落日の煌めき2(笙/コンサティーナ/ヴィナー・ハーモニカ)
4月号至福の音楽(ウィーンのシュランメル一家四重奏団)
5月号琴とウィーン式チター(チター)
6月号第三の男とカラス(チター奏者アントン・カラス)
7月号平氏縁の琴上(平重衡遺愛の琴/ヴァン・グーリック)
8月号平氏縁の琴下(平重盛遺愛の琴)
9月号琵琶の名手重衡卿(『参考源平盛衰記』より重衡卿箏琵琶弾奏)
10月号紀州の琴僧古岳上人甲(古岳上人(幽真)出自略歴)
11月号紀州の琴僧古岳上人乙(七代目市川団十郎/藤沢東畯「贈古岳上人序」)
12月号紀州の琴僧古岳上人(終の栖の草庵で/藤沢東咳「古嶽庵記」)2006年
2006年
1月号紀州の琴僧古岳上人丁(古岳幽真著『空谷伝声集』/森田節斎)
2月号指ヶ谷残夢(渡邊節男さん一周忌法要/黒川亀玉)
3月号東都嘉慶樹(東皐心越禅師将来の名樹/小野田東川)
4月号甲良屋敷と坂上玄台(小野田東川/甲良屋敷/坂上玄台)
5月号東都嘉慶花宴集(東皐心越禅師を偲ぶ花宴)
6月号紀州の琴僧古岳上人戊(森田節斎「古岳庵の記」)
7月号紀州の琴僧古岳上人己(テナガザル考/ヴァン・グーリック)
8月号ここに泉あり(映画「ここに泉あり」の音楽世界)
9月号紀州の琴僧古岳上人庚(古岳上人「遺状」)
10月号東台琴客余聞一今泉也軒(今泉也軒(雄作)出自略歴)
11月号東台琴客余聞二今泉也軒(近代屈指、琴譜琴書の今泉コレクション/町田石谷)
12月号東台琴客余聞三今泉也軒(町田石谷/也軒翁墓碑)
2007年
1月号東台琴客余聞四井上竹逸(井上竹逸出自略歴/中根香亭)
2月号東台琴客余聞五井上竹逸(竹逸事蹟探訪・東漸院)
3月号東台琴客余聞六井上竹逸(今泉也軒筆「奇人井上竹逸」全文・前)
4月号弘一大師「一輪明月」(李叔同/映画「一輪明月」)
5月号東台琴客余聞七井上竹逸(今泉也軒筆「奇人井上竹逸」全文・後)
6月号東台琴客余聞八井上竹逸(煎茶人竹逸/今泉也軒)
7月号東台琴客余聞九井上竹逸(也軒宛竹逸書簡)
8月号東台琴客余聞十井上竹逸(上田芳艸「一絃琴」/竹逸主催鳥海雪堂古稀祝いの書画会)
9月号福住検校井上竹逸(福住検校/江島杉山神社参詣)
10月号「普庵咒」夢境(琴曲「釈談章」/洞籍/東皐心越禅師/幸田子泉)
11月号祇園寺緑蔭(水戸祇園寺「緑蔭禅の集い」/東皐心越禅師/浅野斧山)12月号杭州金華山永福寺上(永福寺重修新装/東皐心越禅師)
2008年
1月号杭州金華山永福寺下(天籟雲和・第一回国際東皋心越古琴交流会/東皐心越禪師)
2月号魏氏明楽元(明楽由来/酒井雅楽守忠恭/魏之琰)
3月号魏氏明楽亮(魏家代々覚書『由緒書』)
4月号魏氏明利(鉅鹿子明(君山)/芥川思堂)
5月号魏氏明楽貞(芥川思堂/筒井景周「君山先生伝」)
6月号魏氏明楽春(魏家/鉅鹿子明(君山)/京都で絶賛された魏氏明楽/姫路で明楽演奏)
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第51話
魏氏明楽姫路侯と明楽 夏
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
君山と門弟による河原御殿と東本願寺枳穀殿における二度の明楽演奏は、京都人士の耳目を驚かせるには十分で、此の二つのデモンストレーションを機に、魏氏明楽は京都ばかりか周辺の藩でも評判となり理解者や弟子が増える事となるが、更には是等の明楽演奏の様子を又聞きした姫路藩酒井家初代酒井忠恭(ただずみ、一七一〇~一七七二)侯が大いに関心を示し、此の後、君山最大のパトロンとなる。
「後、姫路侯聞きて之を招き、大いに之を嘆美し、即ち賓礼を以て先生を留めて学ぶ、悉く楽器舞衣を製し、且つ諸近臣をして之を習わせしむ、一時の風靡、将に大行せんとす」(「君山先生伝」)
忠恭は大坂城代を経て幕府中枢の老中首座を勤め、前橋藩から姫路藩に転封し姫路酒井家第一代となり、諸文芸を擁護した事でも知られる開明的な名君で、藩の儀式に此の魏氏明楽を用い、以後歴代藩主もこれを踏襲したのである。
忠恭に就いての姫路側の記録『六臣譚筆』では、
「…舞楽なども、楽人東儀播磨守を聘して諮り、明楽を創めた。」
「忠恭は、殊に多趣味で…明楽、蹴鞠、茶、…その他に及んだ。」
「…明楽は当時未だ諸家にはなかったが、忠恭は猪狩律斎等を召し抱へ、中根導惇をして専ら楽府の肝煎をなさしめ、家中の子供等を召し、舞の稽古をさせた。…」(『姫路城史』)
とある。
余談だが、同じく『六臣譚筆』に、魏氏四代を兄君山から譲られ唐大通事となった四男坊の弟・太佐衛門規康が、姫路藩お抱えの明楽の師となった君山のもとを訪れた際、お覚えも目出度く屢々忠恭侯に召された事が、
「忠恭、長崎大通詞に百挺備射を観覧せしむ」
と同じく『姫路城史』に記され、君山と規康は仲の良い兄弟であった事も判明する。
又、二代藩主となる酒井忠以(ただざね、俳号宗雅。一七五六~一七九〇)は、実は忠恭の孫であったが早逝した父忠仰に代わり忠恭の養嗣子となり、十八歳で家督を継ぎ、先逝した養父共々明楽を奨励したが、是又三十八歳で早世してしまう。
以降、漸次君山と直接警咳を接し学んだ藩士の減少する中にも、歴代の藩主の庇護の下、先細りしつつも明楽は演奏され続け、姫路藩では幕末までこの伝統は守られるのである。
尚、姫路藩には楽隊なるものが有った。明治二(一八六九)年改正の『姫路藩知行取調帳』(『姫路城史』)「寄合」の中に「楽隊」が記載され、楽隊取締支配十二人扶持が六名、五十八人扶持が二十九名の都合三十五人の氏名が列記される。
人数としては丁度舞を入れた明楽の編成にピッタリ符合するが、此の楽隊が明楽の為のものか、将又如何なるものかは明記されぬし、更に文政十一(一八二八)年の冬十月、四十年前の江戸藩邸における明楽お披露目の家臣中と、該楽隊中で姓が重なる者は僅かに二名のみで、今後この楽隊と明楽との関わりは精査の必要がある。
「万寿院」での琴会
姫路文学館での魏氏明楽の演奏に先立つ四月廿六日、宇治の黄檗山万福寺山内万寿院に於ける江戸の文人音楽を実地に再現した「琴会」の一齣。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第52話
大雄寺 牡丹コンサート
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
五月十一日、筆者は黒羽の曹洞の名刹大雄寺に於ける音楽会に独奏者として招かれ、寺に因む琴(きん)(七絃古琴)と二胡(胡琴)の独奏を果たす可く、雨中只管、那須塩原へ向け新幹線車中の人と為る。
約百年前の明治中期には已に大雄寺の境内は至る所牡丹が咲き誇る名勝として遠近に知られ、爾来、今日に至る迄歴代の御住職が丹精を凝め牡丹の花を実際に眺めつ音楽を鑑賞せんものと、「牡丹コンサート」は今回で九回目を数えると云うが、何とも雅致と詩情に満ち溢れる催しである。
寺名を正しくは黒羽山久遠(くおん)院大雄寺(だいおう)と称し、室町期の応永十一(一四〇四)年の創建だが焼失した為、時の大名黒羽藩第十代藩主大関忠増に依り現在地に再建されたのが文安五(一四四八)年の事。従って山門、本堂も庫裡も、鐘楼も禅堂、東司、浴堂等を繋ぐ回廊何れも全て茅葺きと言う非常に珍しい造りで、六百年前の当時の姿を留めると云う本堂正面の縁側から御本尊に向かい演奏したのだが、一度では入りきらぬ為、百人の定員を二度に分ち御聴き願う。
寺に因むとは、抑此の音楽会は同じく曹洞宗の水戸・祇園寺御住職小原宜弘老師から該寺倉沢良裕老師宛の御推薦に依り、三百三十余年前、東皐心越禅師が水戸から那須、日光へと周遊した折り、此の大雄寺にも立寄り錫を留めた事に端を発する遠因と、本連載第43~45話「祇園寺緑蔭」一連に御紹介した経緯が有るからである。
水戸の岱宗山天徳寺に全国から千七百余人の善知識が参集し、三百年来未曾有の開堂式を心越禅師が行ったのは元禄五(一六七六)年の初冬十月六日の事。
心越禅師の「心月山長渓寺十景」「十景後跋」には、「是の年癸酉殷秋、那須温泉の行有り」と有るので、翌年の元禄六(一六七七)年七月、那須の温泉に立寄り、此の「心月山長渓寺十景」や藤田氏「風永堂詩・序」等をものする途次、此処大雄寺へも寄錫し、其の際禅師が「達磨図」、「龍乗観音像」、「梅図」、「竹図」や二葉の扁額「学無為」、「霊鷲」を揮毫した。
初見する心越を日本に招いた長崎興福寺四世の「澄一道亮頂相」(新蔵?)等の他、
祇園寺第三世の蘭山道昶(らんざんどうちょう)(一六四九~一七四二)に関する二点で、
日本黄檗の祖・隠元隆琦(一五九二~一六七三)の『三籟集』を蘭山が翻刻した和刻本や、黒羽藩家老の風野勝長(?~一七四五)「向陽亭十二景并序」詩巻中に遺る蘭山の詩偈等、折から寺内の集古館で展観中であった「黄檗墨蹟展」での眼福を授かり満腹する。
此処大雄寺には黄檗初期の渡来僧の遺品が多い事で、一時期隠元禅師の黄檗宗に属し、明け暮れ明音での看経に寺は包まれて居た事に筆者はハタと気付くが、
更には、数々の寺宝が有る中に、杉渡戸(すぎわたど)(現黒磯)産の孤高の絵師・高久靄崖(一七九六~一八四三)作のものを第一とするが、何と筆者のシュランメル仲間(本稿第12話参照)で音楽学者の高久暁氏が其の直系だと云う。実に「因果は廻る水車」の様相を来す。
此の音楽会の為、祇園寺の座禅会の皆さんも態々水戸からバスを仕立て、大挙して来訪された事も有り難く、昨年の「緑蔭禅の集い」で御会いした御顔も多数雑じる。
午前中の第一回が開かれる頃には晴れ間が兆し、満山の木立露を含み、厭が上にも緑苔の色濃く冴え、山内の静寂は王維の名句「空山人を見ず、但聞く人語の響くを」(「輞川二十景」鹿柴)の情景も斯やと計りに彷彿させる。斯く静謐と冷気の被う中、倉沢老師が光圀公と東皐心越との逸話(加藤拙堂)や寺との関わりを披露され、次いで筆者の弾ずる明朝成化二年製の是又六百年近い歳月を経た名琴「霜鐘」の枯淡な音色で、心越禅師が中国で学び日本に将来した「秋風辞」や、渡日後宋人の詞に自らが諧音作曲した「安排曲」、和歌に諧音手付けした「山桜」等を弾じ終わり、拙い二胡に持ち換え伴奏者小西祐子嬢との演奏が始まるや否や、何処からか笛らしき音がするではないか。怪訝に思い乍らも演奏を続ける中に、漸く事情が飲み込めたのだが、何と突如音楽会に闖入した演奏家は誰有ろう鳶(とんび)氏であった。楽の音の響きに釣られてか、将又領域を侵す外敵と勘違いしたか、二胡を奏でれば彼も又「ピーヒョロ、ピーピーヒョロローー」と頻りに啼き出すのだ。暫し啼き声の止むを俟とうとしたが、「是も又一興」と更に拉絃すれば、彼も亦同様に高潮して啼き応えるのだ。中空と地上との阿吽の一齣が暫し続き、吾が「胡弓」(中国での古名は胡琴)と鳶氏の「呼吸」が図らずも合奏と為り、自然界に己も彼も共に生かされて居ると云う事を、音を通じて改めて実感する貴重な体験を得た。
「茅葺きの本堂」
「コンサート前景」
「本堂から内庭を望む」
「コンサート後、鐘楼を背景に大雄寺倉沢良裕老師を囲み座禅会スタッフと」
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第53話
書く像先生 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
覚三とは岡倉天心の通名でもあるが、本稿では下總覚三、後に皖一と改めた教育音楽家兼作曲家を御紹介する。
通常、下總の姓は「しもうさ」と発音され、又御自身の随筆集『歌ごよみ』(一九五四年音楽の友社刊)の「発音」と云う随筆には、出自に関する問いに、
「先生の御国は東北ですか。東京からいえば東北でしょうか、埼玉です。下総という姓は珍しいですね。ええたぶん昔先祖が下総の国から出たのでしょうね、私の郷里から茨城県の古河町というところまで、僅か一里そこそこなのですが、たぶんそのあたりから渡って来たのでしょう、そこは下総古河町といいますから姓氏録という書物を見ると下総という姓はかん武(ママ)平氏千葉氏の族となっていますが私の先が平家だか源氏だかわかったものではありません。でも昔は士族だったのですか。なあに、百姓です。祖母も母も手打ちうどんをつくって卸売をしていました。それから父は小学校の教員でした。下という姓は明治維新の時分に勝手につけたらしいです。私の部落に四五軒同姓のものがありますが、お寺の過去帳を繰って見ますとみんな昔の名は姓なしで、吉蔵だとか、嘉吉だとか藤兵衛だとかなっています」
とあり、地名は「しもふさ」とも記したが、先生の英字署名には
「shimosa」とあり、以来、我等音楽人は「しもおさ」と読む仕来りである。後に病気勝ちであった愛妻千代子夫人の伸枝との改名に伴い、先生も以後「皖一」と名乗られるが、生来大なる筆記癖を持ち、日常も其の両手から鉛筆と五線譜ノートを離さず、絶えず何かしらを筆記していた為、覚三ならぬ「書く像」と揶揄された。
先生の作品で遍く世に知られる曲は、「たなばたさま」(ささの葉さらさら〉、「はなび」〈ドンとなった花火だきれいだな〉、「野菊」〈遠い山から吹いてくる〉、「電車ごっこ」〈うんてんしゅはきみだしゃしょうはぼくだ〉等の主として童謡や唱歌であるが、残念乍ら時代と共に忘却され往くも浮き世の定め。無論、是以外の多くの芸術歌曲や管絃楽曲の事とて言わずもがなの事だが、著作権協会に登録された曲だけでも千二百を数え、別に全国の校歌は八百以上、歌や社歌に至っては千曲を超える甚だしき曲数が遺るので、読者中にも先生作の校歌や社歌で少年から青春時代を過ごされた御同輩が必ずや居られる筈である。
筆者等の学生時代は先生の没後間も無い頃の事で直接の御指導は無かったもの、皆下總皖一著の『和声学』を縫いたもので、先生の師であドイツ近代の大作曲家パウル・ヒンデミット(一八九五~一九六三)直伝の和声学や作曲法を学生達は当面の指標としたものだが、既に華甲を過ぎた筆者に計らずも先生の顕彰会からの御声掛りで、其の遺作群の再評価をせよとの大役を仰せ遣い、ならば手始めに近在の中・高校の吹奏楽部に先生の曲を演奏させようでは、と云う提案をしたが、偶々夏期は全国吹奏楽コンクール等の行事と重なり、言出しっぺの責で吾がアウフシュナイダー・カベレが八月八日の旧奏楽堂での「下總皖一と星祭~生誕一一〇年記念コンサート」に急遽助演と云う事になり、先生の遺作で普段演奏機会の少ない、ベルリン留学中の一九三三年夏、アイヒェンドルフの詩に作曲した歌曲〈Nachts〉(邦題「夜」)と、サロンオーケストラのための作品、〈円舞曲・童唄を主題として〉、我等の世代には殊に懐かしい、〈ハイケンスのセレナード〉を不肖筆者の編曲で演奏する事になった。
下總皖一先生(1898~1962)
『下總皖一生誕90年』1988年同編集委員会編より
明治卅一年三月卅一日、埼玉県北埼玉郡原道村大字砂原の産で、原道村尋常小学校から、父君吉之丞氏が校長であった隣町の栗橋尋常高等小学校を経て埼玉県立師範学校に進み、其処で音楽、殊に教育音楽を学ぶ可きを痛感し、更に卒業後に上野の音楽学校の師範科で勉強し直し、主席で卒業、奨学金を得るに至るのだが、先生の遺された随筆や作曲群を見るに付け、多感な少年時代を過ごした郷土に育まれた自然を愛する繊細さと、生きとし活ける草木や小動物等に注がれる細やかな愛情に満ちあふれて居る。
下總皖一先生生家
36
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第54話
書く像先生 中
下總皖一 生誕一一〇周年記念コンサート
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
下總皖一は歴とした作曲家で、半世紀以前の筆者中学時代の音楽では、日本を代表する作曲家として滝廉太郎、山田耕筰、信時潔、中山晋平、弘田龍太郎、成田為三、宮城道雄、下總皖一、本居長世、藤井清水のたった十人の代表格の中に入って居た大家である。
然し何と言っても下總の真骨頂は数少ない音楽教師の為の真の教師であって、師範学校の音楽系で育った先生にしてみれば、東京音楽学校の師範科は最適、且つ当然帰結する処であった。何となれば、当時の音楽学校は何よりも明治以降の欧米文化に追随せんが為の悲願を遂行せんとの、日本全国の初等音楽教育普及の為の官立教員養成所面の色彩が強く、当然の事、真の音楽家や演奏家を育成する事よりも、如何なる鄙の地にも唱歌教育を普遍させんとの一大急務が先行したからに他ならぬ。
偖、和声学や対位法に些か弱かった当時の日本洋楽界の期待を背にして作曲法研究の目的で先生がドイツに官費留学したのは昭和七(一九三二)年三月の事。二年半後の九年九月に帰朝後、東京音楽学校に戻り講師となるも、同年十二月に助教授となり、作曲科教授に任命されるは八年後の昭和十七(一九四二)年の三月であるが、皮肉な事にも是等が戦後に先生が学校を逐われる要因となり、且つは彼の忌まわしい枢軸国ドイツとの提携感を払拭し、オーストリアやドイツ後期ロマン派との命脈を継ぐ大時代的な教授陣を断ち切り、代わって日本新生の顔たらんとするフランス近代音楽派を主軸として欧米化して学校を蘇生させ、更には師範の育成よりも本来の音楽家を育てる方向に文部省と学校側の方針が転じた事にある。
「下總皖一と星祭~生誕一一〇年記念コンサート」と銘打った八月八日の音楽会は、下總先生の代表作で世に遍く知られた〈たなばたさま〉に因み、星祭と夜の曲を中心に選曲され、吾がカペレは先生の遺作中、殊に通常演奏機会の無いであろう歌曲の〈Nachts〉(邦題「夜」)と他二曲を御紹介した。
「夜」は、皖一先生が一九三三年に文部省在外研究員としてベルリン高等音楽学校留学中に習作したもので、歌詞はドイツ後期ロマン派の詩人で異例の長名を持つヨーゼフ・カール・ベネディクト・フライヘル・フォン・アイヒェンドルフ(一七八八~一八五七)作の同名の原詩で、東京帝大卒の詩人で先生と親交のあった江南文三(一八八七~一九四六)の邦訳歌詞が附く。無論、作曲学の指導教官はドイツ近代音楽史上に燦然と輝く大作曲家パウル・ヒンデミット(一八九五~一九六三)で、其の影響と添削の痕跡を色濃く残す貴重な作品でもあるが、先生の没後其の弟子達が協力して出版した『下總皖一作品撰集』(下總皖一作品撰集刊行会編、一九八〇年音楽の友社刊)には採られぬ為、一般的な知名度は低いが、上図の様に当時の良心的な東京の楽譜出版社・共益商社書店に依り『下總皖一作曲独唱小曲集』として大貫松三画伯の装幀画で昭和十(一九三五)年に已に刊行されては居た。
もう一曲筆者が撰んだのは、皖一先生が東京音楽学校に戻り作曲科教授となった二年後の作品で、敗戦前の昭和十九(一九四四)年六月廿九日、時局柄倉卒の間に完成させたサロン・オーケストラ(室内管弦楽)の為の〈円舞曲〉(童唄を主題として)と云う曲である。
此の曲は副題にも有る通り、各地に残る童唄の〈ほたるこい〉、〈子守唄〉等をモチーフ(動機)として書かれたもので、小品乍らも日本の伝統的な旋律や和声を研究し、実際に其の作品に活かし続けた先生ならではの管弦楽法と和声応用の結実であり、如何にも興味深い。
『下總皖一作曲独唱小曲集』第五集
下總は昭和9(1934)年の秋9月に独逸から帰国するが、其の作品は直ぐ様東京の楽譜出版商・共益商社書店に依り、留学中の習作を含めた歌曲集『下總皖一作曲独唱小曲集 第1~5集』として大貫松三画伯(1905~1982)の木版装幀画で飾られ、翌10(1935)年の春から刊行され、同年末の12月には第5集が出て全編完結した。
「夜」は第4集に収められる。
下總皖一作曲 独唱小曲集 第五集
1.Bel der Wiegen 子守唄
2.Fuchs und Bar 狐と熊
東京 共益商社書店
42
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第55話
書く像先生 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
愚門で月琴を学ぶ才媛・ハーピストの大村典子姉が、筆者と下總皖一先生の顕彰会(中島睦雄会長)橋渡しの労を取られたが抑の発端で、無論、拙稿は其の余勢を借りての異聞である。
前々号で触れた下總先生の名字の読みに関する記憶に、碩儒新井白石の稀書『昔日余杖』中、
「宝永改元の七月、東関洪水下総(ヲサ)国鴨大河とも溢れて武蔵所領の北伐に海に等しく、…」
と態々其処丈ルビを振った事を何気に想起し、白石在世の頃(一六五七~一七二五)には已に「しもをさ」と読み癖の有った証左を認めた。
扨、下總先生の随筆『歌ごよみ』中に左記の一節「ベビーオルガン」が有る。
「私はその村の小学校には六年までしか行かなかった。そして隣村を一つ越えた小さな町の学校へ二年間通った。その学校は私の父が平教員から校長まで通して、三十年もつとめた学校だったので、私の姉も兄も高等科になると毎日一里半の道を歩いて、通ったのである。…略…その学校には私の村のオルガンよりももっと小さい、外からふみ板の針金が見えるベビーオルガン一台しかなかった。…略…町にお祭りがある時、よく、私は祖母と二人で学校の小使いさんにおよばれして、小使室へ泊めて貰った。オル
ガンは昼の間は教員室に置いてあって一切いじらせないが、小使室に泊った夜は誰に遠慮もなくぶーぶー鳴らす事が出来た。何という嬉しさがらんとした校舎に響きわたるベビーオルガンの音を、私はいつまでもいつまでも楽しんだのである。勿論すらすらなど鳴ってはくれないけれど、耳と片手の指でさぐりさぐり鳴らすのである。
ある時県の師範学校の卒業間際の人たちが三四十人参観に見えた事があった。その参観人たちが私たちの授業を参観しながらいっしょに唱歌を歌ってくれた事が私はとてもうれしかった。そして翌年、私はその師範の生徒となったが、オルガンはいじらせてもらえなかった。ちょっといじって上級生から手ひどく叱られた。やむなく、冬休み、夏休みに小学校へ行ってベビーオルガンを鳴らしてはひそかに喜んだ。やがて一年生が終わり、二年生を過ぎて、三年になった時、漸く楽器使用が許された。私はむさぼるようにオルガンを鳴らした。右の手と左の手と違う動きをするのが実に難しかったが、それも過ぎて片手だけで二つの音や三つの音を同時に出す魔術師のように思えた事も、だんだん自分でも出来るようになると、もううれしくてたまらなかった。…略…師範学校にはいって、はじめピアノというものの形を見せて貰い、音をきかせて貰ったけれど、自分の手で鳴らすなどという事は夢にも思えない。…略…私自身も上級生になり、ピアノも許されるようになった時でも、お祭りの夜ベビーオルガンを鳴らした喜びにはとうてい比ぶべきもなかった。」
今にして思えば、師範学校の下級生時代に自由にオルガンが弾けたなら、先生の鍵盤の作品が…とも推量されるが、今更言っても詮無い事。兎もあれ、先生の音楽修行は此処いらから始まったのだからして、筆者等が音楽を学び始めた頃とは比較にならぬ程大器晩成型であるが、ソコは気骨溢れる明治生まれの日本男児の事とて、短期間の学業と修練で凝縮された或る程度の専門性を身に帯び、更に現今の平凡愚鈍且つ怠惰の性を生まれ乍らに身に纏った筆者等とは是亦比べられぬ程の社会貢献を為したのだから、唯々頭が下がろう。
つい先程、筆者はさいたま新都心で「日本の胡弓」という講演をして来たばかり。又、栗橋や隣市古河は下總先生少時縁の地でもある。本年度茨城県開催の「国民文化祭」の分会地古河では、愚生と稿頭大村女史との「日本の胡弓とグランド・ハープ」なる世にも珍らかなる演奏が要請される為、下總先生の曲を演目に加えて見よう。
下総皖一著『歌ごよみ』 1954年音楽の友社刊
38
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第56話
江文也
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
思いも掛けず、本誌編集子が一〇月号「今月の本棚」欄で筆者校注になる江文也著『上代支那正楽考』(平凡社東洋文庫774)を取り上げて下さったので、茲に改めて江文也の事を御紹介して見よう。
筆者は本年四月に三省堂『超級クラウン中日辞典』の音楽語彙や図版の訂正と、別項目を執筆した直後、翌五月には該正楽考の刊行となるが、演奏、講演、教学との間隙を縫い此の為推敲を重ねた事と、詩集『北京銘』も翻刻に際し寒斎架蔵の原本を用い、尚、引用された白文は現代人には難しいとて、老爺?心から読者に便なる様にと、云わずも良い事を言った為、原典を具に当たり、読み下し文の作成迄をも買って出て了った。全く後悔先に立たずだ。然も筆未だ苦学生の頃、恩師・田邊尚雄(一八八三~一九八四)老先生直々の御薦めを戴き読了した本とて、一入思い入れも強い本の事でもあり、更には其の当時、江文也は未だ中国に存命中であった等、様々な事を想起させ、不肖無才が出来るたった一つの土俵入りと、田邊老先生への万分の一の恩返しの意も有ったのだ。
江文也の本貫は福建の永定で客家人である。日本統治下の台湾に生まれ、日本に学んだ中国文化圏人、否、彼の内に潜む華人の裔として流れる血液中のDNAが、ゆくりなくも日本の一地方、信州上田のメソジスト教会で西洋音楽と出会うことにより開花し始める。それまで日本人風に育っていた著者自身でも感知せぬ無意識の中に、騒ぎ蠢く中華の血が目覚め、いざ北京の都に往って生活し始めたことで静かなざわめきは一転してまさに沸騰せんとするのだ。
少時廈門で日本語教育を受け、継いで信州の上田で青年期を過ごし、其の後上京して東京の電気学校に在籍しつ傍ら音楽を学んで居た。初めは声楽家として活躍するが、徐々に作曲方面の才能に目醒め、課外に音楽学校の東京出張所(戦後の付属高校)であったお茶の水分校の予科で山田耕筰(一八八六~一九六五)等に学び、次第に頭角を現すようになり、折しもベルリンオリンピック芸術部門の作曲に応募し、『台湾の舞曲』で東洋人として初めて四等に入賞した事に因り、一躍日本ばかりか欧米の楽壇からも注目されるようになる。無論、山田や当時一流の他の日本人作曲家も同時に応募したが、誰一人として入賞作は無かったのである。
文也が最初に北京と上海を訪れたのは一九三四年から三七年に掛けて東洋歴訪中のロシアの作曲家アレクサンドル・チェレプニン(一八九九~一九七七)の誘いにより、一九三六年六月の中国旅行に同行しての事だが、筆者の推論に違わず文也は中国の持つ底力に圧倒され、余程其の印象が強烈で忘れ難い物で有ったか、一九三八年に北京師範学校の教授に招聘されるや、渡りに舟とばかりに喜び勇んで北京へ渡り、而して自らの足で中国大地を直に踏んで実際に生活を始めるや否や、見る物聞く物全て中国一辺倒とばかりに、中国文化に傾倒し出すのである。
文也自身の孔子像が五、六年前迄は旧態依然としたものであったが、師範学校の教授となり、新天地北京の孔子廟で遠くて近い中華民族の祖が演奏もし、亦聞きもしたであろう古代中国の楽に、先ず演奏家、継いで作曲家、日本の文化人、更に中国人としての文也が着眼正視せざるを得ない運命的な出会いに、以後、視点を変えて孔子と音楽に強く関心を寄せる様になり、改めて其れ迄の孔子像を構築し直したのである。
江文也小照(東洋文庫より)(本名・文彬1910~1983)
『台湾の舞曲』初版
1936年東京白眉出版社刊
BUNYA KOH
Formosan Dance Dance Formosan
Tanz Formosa Op.1
PIANO SOLO
江文也作品一 臺清の舞曲 ピアノ獨奏
HAKUBI EDITION TOKYO 1936
46
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第57話
少年の眼
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
小雨の降る小さな波止場に降り立ち、数歩歩み掛けるや否や、澄んだ大きな眼が筆者と対峙した。其の少年はブルーの雨合羽を羽織り、左手に小さな蜜柑が十個計り入ったビニール袋を手にし、右手で余り強くもなく筆者の袖を掴んだまま離さぬように「十円、十円で良いよ!」と頻りに声を掛ける。
此所は中国広西省の桂林郊外の漓江畔の竹江埠頭から遊覧船で三十日弱三時間ばかり行った処、冠岩の下の十年程前に開けた最大の鍾乳洞への入り口に在る小さな渡し場での一齣。百人乗り位の大型三層の遊覧船が小さな波止場に接岸するのは大凡一時間に一、二隻程だろうか、一日に千人以上は訪れるであろう遠来の観光客中の一人として筆者を捉え、目をつけた其の刹那の機を逃すまいと、直ぐ目前の山への上り口の石段へ向かおうとする方向へ一緒に着いて来るではないか。実に必死である。
扨、都会等で一歩表へ出れば本物の物乞い、多くは乳飲み子を抱え、窶れ汚れ切った母親が他の子供と共に、一旦カモを見つけると中々離して呉れず、一度掴んだ袖は離さぬ様に必死で、富裕に見える中国人迄もが其の標的と、似た様な風景は何十年も以前から中国では極々当たり前の出来事で、然も何処へ行っても有る事。今更決して驚くことでは無いし、現実に数え切れない程遭遇して居て、平常ならば柳に風と見て見ぬ振りをしスッとやり過ごすのだが、然し今回丈は何処かで違ったものかし知らん。良く見れば、恐らくは十歳前後の年齢であろうか、其の少年の足は雨の中裸足で、だからか却って洗ったように綺麗であったし、名ばかりの合羽だが是も雨の為、さして汚れて居ない。
此の少年の眼を見つめる中に、不意に何故とは無く自らの過去を見た様な不思議な感覚が沸き起こり、自分の子供の頃と重なってかとても胸が疼くのだ。其の内に今年十九歳を迎え、未だ人生の何物を掴み得ないで煩悶する豚児の幼い頃、未だ挫折を知らぬ頃の愛らしい瞳の色とも重なって来るでは無いか。稍諦めたものか、少年は一度手を離すが、他の客も同様に相手とならず、又しても筆者を対象として来て、今度は半額の「全部で五円で良い」と焦り出した。
一体に桂林付近は柑橘類の多産地域で、何も遊覧途中で買わずも、美味しくて安い品物は市内に戻って普通の物を買えば良いのだ、と今度も相手にせずに、成る可く手荒にならぬ様に少年の手を振り払い、漸く難関を突破して階段を登り掛けると、直ぐに石段の折り返しの踊り場で閊えた前列の人を待つ暫しの間に、客が絶えた波止場に少年がポツンと佇む姿が眼に入った。と堪らず眼下の少年に呼び掛ける声が極自然に出て了ったのである。咄嗟の事とて事情が読み込めぬ侭、筆者を認めた少年は蜜柑が売れるものと喜び勇んで駆け上がって来るが、コチトラの前途に蜜柑は邪魔な物なので、ポケットに有った小銭を掴み、少年の掌に握らせ、「蜜柑は要らぬのだ」と云うと、漸く其の意図を察した彼は、千金の重みを込めて「有り難う」と小さな声をホット漏らした。云って見れば唯其れ丈の事、然し、此の後少年の眼は記憶に刺さった侭、度々筆者を悩せるに違い無い。
「漓江煙雨」
小雨に煙る漓江船上に在る筆者等は、古の画中の人と重なって暫し陶然とする中にも、冠岩鍾乳洞へと向かう。
「去り際の渡し場」
少年の去った後で、心無しか寂しさが漂う。写真中央左手の白く映る石段手摺の、左・右と上がった右側の踊り場が其所であった。2008年10月26日
38
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第58話
繰縵一半 如一昨夢 1 王鉄錘先生
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
前号少年云々の記事は、昨秋十月廿五日、写真に有る様「高山流水・漓江秋夜」なるコンサートが中国桂林市の国賓館「榕湖飯店」の礼堂で開かれた翌日の出来事で、音楽会は愚門で琴を学ぶ画家の李女史が博士号を取得した事を記念し、晴れて故郷に錦をと云う訳で、桂林博物館に於ける展覧会の開幕を祝う為企画され、北派笛子の大師で国家一級演奏家の称号を持つ王鉄錘師と筆者二人に依る演奏会。因みに榕とはガジュマルで桂林の古称を榕城とも云う。
此処に唐突感を免れぬが、昨年末を以て新宿コマ劇場が閉鎖されると聞き及び、今号拙稿の伏線となる出来事を想起する。
忘れもせぬ丁度五十年前の一九五八年の春、未だ少年だった筆者にとって其の後の一生涯を決定す音楽との出会いが有り、軈ては稿頭へと繋がる成り行きとなる。本連載第四五話で既に触れた様、抑、筆者は家学の関係から和洋の楽を幼少から学んで居て、小学校高学年の頃には一端に、将来は作曲家兼ヴァイオリニストたらんとして曲想モチーフのノートを持ち歩き、秋山六郎兵衛の名訳でヘッセの『孤独な魂』等を貪り読んだりしたもので、主人公クーンと自分を重ねる何ともマセ餓鬼であったが、一面では御他聞に漏れず悪童仲間と蔓んでは、大流行の銅線のコイルを巻きバリコンを繋いだ丈の粗末なゲルマラジオを自作し、練習後の夜間寝乍ら海外の短波放送等を貪り聴き、中でも北京放送の古典音楽の番組を良く聴いて居て何かしら強く惹かれて居た。
其んな折一九五七年の初夏、父に前年暮れに落慶した新宿の大劇場にサーカス見物に連れて行かれたが、翌年に戦後初の中国歌舞団の来日公演が有る事を知り、四月十日を待ち改めて生の中国音楽を聴く事が出来た。只管洋楽と邦楽の世界の入り口付近で彷徨って居た少年に、中国の音楽の魅力を知らしめる契機となった場こそがコマ劇場であり、少年の筆者は甚く感動したものである。其の後成長するに従い音響に稍劣る同劇場への足は次第に遠のく事になるが、茲に特筆す可き因縁が又しても絡む。何と二胡の生徒K姉から思いも掛けずチケットを戴き、本年大晦の最終公演でコマ劇場最後の瞬間を看取る事になろうとは!演目は「年忘れにっぽんの歌」である。
偖、中国歌舞団の演目は古典音楽から革命物迄の文字通り歌や踊りが雑多に入り混じった出し物で、就中筆者の興味を惹いたのが琴曲と琴籍合奏であり、是を機会に筆者は以降五十年以上も琴学に呑めり込む事となるが、此れは続稿に譲るとして暫く置き、当時の日本は中国と正式な国交が無かったが、新中国は数年前から「百花斉放百家争鳴」のスローガンの下、怒濤の様に躍進する様々な情報が日本でも報道され、少年乍其れ等に翻弄影響され唯々吃驚して居た。戦後十三年にして初、然も国交の無い国からの歌舞団とあって日本公演は終始友好的に大成功を収めるかに見えたが、豈謀らん世に好事魔多しとか、東京から関西、而して長崎と巡業して居た五月二日、長崎に於いて不逞の輩が中国の国旗「五星紅旗」を引きずり降ろした上、剰え国旗を踏みにじり、然も科料五百円の軽犯罪法で釈放されるや、時の岸内閣の大外交問題に発展し、揚句は五月九日には対日貿易も即時中止されるは、歌舞団も十九日に帰国するはで、三年近い貿易の断絶の後、田中内閣迄もの長期間、日中国交正常化に至らなかった一大要因となる。
王師と筆者に依る「琴簫合奏」
「王鉄錘・坂田進一中日友好音楽演奏会 謹李博士東瀛作品展開幕音楽演奏会」2008年10月25日
※琴簫合奏に就いては第50話参照
46
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第59話
繰縵一半 如一昨夢 2 査阜西先生
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
中国歌舞団の団長は音楽家協会会長の呂驥。副団長は査阜西で当時の音楽家協会副会長を兼ね、又、後の民航の創立者の一人で中国航空界のパイオニアもあったが、何よりも古琴家として著名であった人。而して下の写真にも有る様、洞簫と笛子等が若手演奏家の王鉄錘である。以上長くなったが此処迄が前置きで、此の五十年間に纏わる経緯を、以下甲斐摘み御紹介する事となる。
査阜西先生は湖南永順の産で原貫は江西の修文である。一八九五年十一月七日出生。〇八年から一〇年家庭教師の夏伯琴に琴歌、舅の栄漱石に民歌、昆曲、洞蕭や笛子を学び、一一年から一二年に湖南大庸県の名琴家龔光表の門人田義明、龔嶧暉等に就き琴歌を、一三年に南昌の中学に入るや、琴の歴史と文献を中心に其の理論を学び、二〇年から二四年に掛けて漸く上海及び長沙等の地で、沈草農、顧勁秋、彭址卿等の名家と交わり、琴曲を学ぶ様になる。其の後の三四年には上海の琴の為の結社「今虞琴社」を創立したが、日中戦争や中国内戦を経て、四五年には米国に航空界の為の視察行をした折り、業務とは別に然も精力的に講演や小演奏会を通し、琴を逸早く米国の識者に紹介した功績が有る。五三年中国音楽家協会常務理事に推され、五六年には北京の中央音楽学院民族音楽系主任に任命された。勿論、一九五八年歌舞団来日時にも江戸の琴学資料を短時間で蒐集したのである。此の時のプログラムは流石に四散し、保存して居ないが、査・王両先生の琴簫合奏「梅花三弄」は、少年の耳と記憶の底に確りと残り未だに新しい。
歌舞団来日年は丁度尺貫法切替の年と重なり、大抵は開けっ放しであった街の商店で、古新聞の紙袋に入れて渡された商品を、「百目下さい」
とか、「二斤お願い」。又、竹の物差しで尺寸で計って慣れ親しんで居たものを、学校の先生から「今度から使用してはならぬ」と言われて戸惑った頃である。其の後筆者の成長するに伴い、コマへも何度か行く事となるが、概して出し物は軽演劇が多かった為、ソ連のオケや中国雑技等の他は足が遠のき、無論東京文化会館等は未だ建設されず、クラシックは専ら日比谷公会堂であったか、是チケットは高価でそう度々は行けぬ為、丁度コマ劇場前の広場に面しての二階にコンサートホール?な音楽喫茶が有り、音楽不良少年は学校帰りにチョイト寄道しては、タンゴやら室内オケ等で通俗曲をリクエストし、未知の新曲を仕入れたりし、又足を延ばして近くの歌声「カチューシャ」等へも通ったものだ。
厳父は筆者を建築か数学畑へ進ませたかった様で、少時の内は「其れも良いか」と何とはなく思っていたが、目覚めた自我が確定するに従い、猛反対を押切り、高校から音楽を専門とし、茨の道が始まるのである。
「開演前の一齣」2008年10月25日
開演前の一時、榕湖飯店礼堂の人影の無い玄関ホールに於いて無心に吹笛に興じる王鉄錘先生と筆者。
「来日時の琴簫合奏練習」1958年4月
古琴家査阜西(1895~1976)先生と、未だ25歳の王鉄錘(1932~)師との舞台本番に備えての琴簫合奏(第50話参照)練習風景である。
44
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第60話
繰縵一半 如一昨夢 3 査阜西先生
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
戦後初の中国歌舞団来日公演に就いては、プログラムを保存して居らぬ今となっては判然としない事も多いが、確か毎日新聞社の招聘で訪日実現した事もあり、閑暇に委せて紙上に其の周辺を探索すれば、何と当時未だ少年の筆者では気付かぬ事項が多々有った。中にも五月七日四時からの歓迎レセプションは圧巻で、是又今に比すれば日本側接待の顔触れも豪華絢爛。学芸畑から梅原龍三郎、田邊尚雄(※後に吾が生涯の師と為る)、石井漠、杉村春子、清元寿兵衛、藤原義江等。歓迎側は委員長が久保田万太郎、他に日中文化交流協会会長の中島健蔵、日中友好協会会長内山完造、工藤毎日新聞編輯主幹、其の他千人以上の有識者が集い歌舞団の面々を歓迎した事からも、之が如何に世間の大関心事で有ったかが知れよう。無論、此のレセプションに未だ少年で有っても無くても、何の道筆者なぞは招待され様筈も無いが、後年筆者と直接拘りの生じた中国音楽家を列記して見れば、少なくも中国音楽を志した成果は有ろうか。
来日歌舞団呂驥団長(一九〇九~二〇〇二)は、原名を呂展青と云い、元々は作曲家且つ楽理家を兼ねた人で、筆者も何度か御会いしたが、五十年以上も中国音楽家協会の首席を務めた方。惜しくも〇二年の一月五日に北京で逝く。
査阜西副団長は該団最長老で已に六四歳であったが、中国総人口十億以上の芸術家を代表する人民代表(国会議員)であり、琴では日本の人間国宝に相当した名家。中共建国以来、前清以上に中央から大切に保護整理された古琴が文革に因り「四弊の一」とされるや、其の嵐の中で翻弄され、北京っ子の作家老舎も研究所々長の楊蔭瀏も査老も逝って了った。
笛子演奏家の王鉄錘師はモスクワで開催された「世界青年学生平和友好祭」第四、第五回の連続優勝したという才能の持ち主で、而して笛子を以て「吹破天」(天をも吹破る)と渾名された程の名人を父に持つ鳶鷹の親子で、中央歌舞団(現在の中央民族楽団)の独奏者である。
一九五八年の三月三十一日夜、第一陣三十五名が羽田着後赤坂プリンスホテルに投宿し、五月三日に公演プログラム発表。第二陣の呂団長以下三十名の後続部隊は、BOAC機がカルカッタで機体整備の為遅れて、四日の午後七時半に羽田着、漸く合流して六十五名全員が揃い、翌五日同ホテルでの記者会見。七日には日本側主催の歓迎レセプションでは、折柄満開の桜花の下、新橋物産展に来京中の佐渡おけさ連や、平良リエさんの沖縄舞踊を楽しんだ後、其の晩一行は浅草国際劇場で松竹歌劇団「東京踊り」を鑑賞し、東京の春を満喫する。十日から廿日迄が新宿コマ劇場に於ける東京公演で、三日にはプログラムABC(次号)が発表されるが、既にパリやロンドン等で上演した好評を博した出し物(上図記事参照)ばかりで、来日以降「舞踏班」、「合唱班」、「楽団」と夫々別れて稽古していた各班も、八日の夜からはコマ劇場に於いて本格的な訪日公演の合同舞台稽古に入った。
「中国歌舞団と各国の反響」
勧進元の毎日新聞は1958年4月2日夕刊で、〈パリを酔わせ、狂わせた〉と迄、其の欧州各国での大反響を謳った。
昭和33年(1958年)4月2日(水曜日)
パリを酔わせ狂わせた。中国歌舞団と各国の反響
スイス公演に南北米から観客
「弾到梅花月満琴」1936年
解放前の鎮湖と号した若き頃、陵園花圃に於い満開の梅花の下、弾琴に耽る名琴家査阜西先生。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第61話
高羅佩先生のことゞも 一
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
 拙稿は現在、半世紀前の回顧に浸って居るが、暫し閑話休題、今年の話題から書き起して見よう。
拙稿は現在、半世紀前の回顧に浸って居るが、暫し閑話休題、今年の話題から書き起して見よう。「痩蘭斎樂事異聞」を愛読下さる諸賢には、高羅佩(こうらはい)の大名は已に御馴染みで、日中の中国学界のみか欧米に迄令名を轟かせたオランダの碩学R・H・ヴァン・グーリック(一九一〇~一九六七)の華名である事は先刻御承知の事と存ずる。高羅佩は吾等琴界のみか斯学界の大先達でもあり、拙稿には多出する為、詳伝は措置き、以下、其の高先生が日本の琴学に興味を持つに至る重要な契機へと繋がろうか。
筆者は此の二月、柏在の中国の音楽学者孫玄齡(中国戯曲)先生から「孫伯醇(そんはくじゅん)文人画展」の御案内を受け、孫先生の奉職する同じく柏の麗澤大学キャンパスの一角で、静謐の環境中に御遺作を鑑賞し得た。実は筆者は伯醇先生の御令孫が玄齡教授である事は夙に承知して居り、予てより若しも斯様な企てが有れば、御一報を御願いして居たのである。覧に因んだ孫教授の記念講演「孫伯醇の文人画」も盛況裏に行われ、百名近い聴講者で教室は活況を呈した。
扨、高羅佩は幼き頃陸軍中将であった父君の駐屯地インドで過ごした為、産まれ乍らにして東洋に親しみ、長じて国際法を学ぶもライデン大学でインド、チベット学等に惹かれ、其の後ユトレヒト大学で日本や中国等の研究で博士号を取得した。外交官としては仏、黎、日、中、米の各国に勤務した経験を持ち、在東京の大使館員仲間として知り合うや、忽ち肝胆相照らす友となったのが孫伯醇である。
孫伯醇。名は混(しょく)、簡道人と号し、傍ら文事を薄くした北京の人で、晩清から昭和にかけ活躍した中国外交官である。其の原貫は安徽省寿県(春秋戦国の楚の都)の学者の家の出で、古くは寿州と云った故地は古来多くの文人を輩出した事で有名だが、事実、伯醇の大叔父、即ち父五雲の叔父孫家鼐(そんかだい)(一八二七~一九〇九)は咸豊の状元で、光緒年間の工部・礼部・吏部尚書等、又、京師大学堂(北京大学の前身)初代の管学大臣(学長)、更には光緒帝の教育掛等を歴任した清末切っての大官である。
斯様な家風に育まれた伯醇は、幼少期こそ家塾に学ぶもの、未だ開花の名残を色濃く留める明治の卅八(一九〇五)年、已に東京に留学し、東京同文書院から転じて暁星中学を卒業し、同四十四(一九〇九)年に一時帰国するも、大正元(一九一二)年に再来日、法政大学を卒業する。大正七(一九一八)年には、新中華民国を代表する文化人で中国共産党の創立者でもある陳独秀(一八七九~一九四二)の推挙で北京大学文学部講師となり、同十一(一九二二)年の東京に於ける山東会議の通訳を契機に、同十三(一九二四)年に外交部秘書官となり、昭和五(一九三○)年駐日公使館二等書記官、同十四(一九三九)年に一等書記官、翌年には参事官に累進し、同十七(一九四二)年に退官する迄外交畑一筋の半生を歩んだ。
当然、大戦中は対日折衝に担(あた)って居たが、終戦後も帰国する事無く其の侭日本に留まり、日本の外務省研修所の講師を始め、外交文書調査室、湯島聖堂、学習院、都立大、東京外語大等の講師等を歴任したのである。
「大礼服着用の高羅佩先生」
駐日オランダ王国大使任官時(筆者蔵)
「孫伯醇先生小照」(1891~1973)(孫玄齡氏提供)
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第62話
高羅佩先生のことゞも 二
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
元来文人的資質の強かった孫伯醇は、青年期に革命的文学集団「南社」に参加し、文士の蘇曼殊(一八八四~一九一八。邦名は河井宗之助で父は日本人)等と交わり詩作に励んだり、学業と勤務の余暇に、北京画壇領袖の陳師曽(一八七六~一九二八)、北平芸術専門学校の王夢白(一八八八~一九三四)、北京女子師範学校の汪采白(一八八七~一九四〇)等の著名画家と交わり、其の影響下に絵画を学び始めたりと、従来大半の中国知識人と同じく、実質では文官の辿る可き伝統的王道を歩み乍ら、胸中には進取の精神と六芸への憧憬を併せ抱きつ、東支那海を幾度も往来したのである。斯様な伯醇をして、清末民初の最後の外交実務と文人的な一面とを実践し得た、大きく二種の人生を歩んだ人と言っても良かろうと思う。
伯醇の遺稿となった『ある中国人の回想』に、羅佩の歿後直ぐに物し口頭文が載るので御紹介して見よう。尚、文は無論伯醇の明治仕込みの東京弁、文中の()内部分は本稿筆者の補注である。
高羅佩先生
高羅佩先生(R.H.van Gulik)は、最近亡くなったオランダ大使である。
第二次大戦前、私は中国大使館にいたが、高羅佩先生を中国大使館の漢籍の先生として推薦した。先生は中国語も日本語もお手の物であったからである。手紙も両国語で自由に書かれた。先生は二十八歳で、「馬頭観音」の研究で、オランダにおいて学位(博士号)を得られた。西洋人で東洋のことを研究する者は、皆中国語と日本語を学ぶから、先生も勿論そうであった。
先生はまだ独身のころ日本に来られた。私の日記によれば、一九三六年の除夜にオランダ大使館に行き、先生と一席を共にしている。私は、その後ときどきオランダ大使館に行き、泊まったりしたが、そういうときには、漢籍の中の疑問点について話し合ったりするのが、大変に楽しみであった。そのころ研究したものに、葉徳輝が中国で出版した『雙梅景闇叢書』(清末葉徳輝の編で房中書をも含み、羅佩編著の『秘戯図考』や『花営集錦』
等の下敷となった)などがある。当時オランダ領であったインドネシアのものなども、よく一緒に食べた。戦争中は中国におられ、外交団が南京から重慶に遷ったので、先生も重慶に行かれた。そこで中国婦人と結婚され、のちにまた日本に来られた。婦人は張之洞の娘の娘(水世芳嬢、外交団秘書)である。
先生は十三経、廿四史などの書物もそろえておられ、大使になられたのちに、「学問ができなくて困る。」と言っておられた。
オランダで亡くなったときは、まだ五十七歳で、癌であったが、本人は癌と知っておられながら、家族にはついに知らせなかったということである。これは偉いことである。(続)
 『ある中国人の回想』孫伯醇文集(1969年東京美術刊)
『ある中国人の回想』孫伯醇文集(1969年東京美術刊)当時已に容態の芳しく無かった伯醇に代わり、お茶大の中山時子先生(現名誉教授)が中心となり、其れ迄の彼の短編や新たな口頭筆記等を加え文集として編纂した。其の中山女史が筆者青年期の中国語の先生で、今以て薫陶戴いて居る老師である。
「負喧」孫伯醇(1958年画)
手札版絵葉書である。画題は〈喧しに堪えられぬ〉の意であろうが、「辰乃ち戌の誤」とは賛にあらず、干支の誤記を指す。又、落款「聴蛙館」が画題を解く鍵で、冬期には蛙声の響き渡る書斎。斯く一葉を以てしても伯醇の如何にもエスプリに富んだ洒落者であった事が判明しよう。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第63話
高羅佩先生のことゞも 三
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
高先生は中国の琴も研究されていた。中国の琴は、孔子のときにすでにあって、日本にも伝わって(奈良朝に朝鮮半島経由で雅楽器と併に伝来した)いたが、日清戦争後、日本では国内の中国の文物を全て廃棄(無論誇張である)したために、現在の日本ではほとんどみられないのであるが、高羅佩先生はこの琴にも秀(ひい)でておられたのである。私は、骨董屋で、寛政年間に日本で作った琴(琴銘「秋淵」)偶然(六本木界隈で)みつけて、先生に贈ったことがある。高先生がどこで琴を習われたかというと、独身時代、北京におられたころに、葉鶴伏先生について、けいこされたのであるが、面白いことに、その葉先生の家は、私の家(孫家)のとなりであったのである。のちに高先生と知合ってから、雑談中にこのことがわかって、二人で興味深く思ったものであった。
先生は琴の譜を、中国のも日本のもいろいろと集めておられたが、とくに、長崎に来て、琴を教えて(徳川光圀公の庇護で江戸は小石川後楽園に仮住まいした三年弱の間である)いた明代の僧、心越の琴譜を全部買いとられ(一部分のみ)、また、その書も収集しておられた。湯島聖堂(当時、聖堂斯文会内に書籍文物流通会が在り、古籍と古玩を扱っていた)にも、心越の書があると、せっせと購入しておられた。
中国の知識人は、書斎に琴や書を備えていた。琴と書とは「琴書」(左琴右書)という成語になっている。私の祖父も書斎に琴を置いていたが、父になると、もうそういうことへの理解はなかった。琴の歴史は中国では古い。晉の陶淵明の無絃琴(若し琴中の趣きを知らば、何ぞ絃上の声を労せん)の話もあるし、論語にも出てくる。論語の時代から清に至るまであるのである。三千年来、形なども少しも変わっていない。
高先生の書斎の名は「尊明閣」(次号図版参照)という。「明朝を尊ぶ」という意味である。私が書いたものだが、それを朝鮮の人に頼んで彫ってもらい、私には拓本を下さった。また、先生は江戸時代の官版(湯島聖堂・昌平黌の校閲で一七九九年から一八六七年に掛けて公刊された百九十九種の膨大な量の版本叢書。一八四六年の江戸大火で聖堂の書庫と版木が焼失した為、一九〇九年から民間で再版したものが『昌平叢書』である)を全部集めておられた。私は二つぐらいしか持っていないが。とにかく、東洋の学問、文物を深く愛された方である。(続)
此処で読者諸賢は、誇り高い年長者、然も古典に造詣の深い伯醇が、羅佩に対しては送って敬語を用いて回想して居る事に気付かれた事と思うが、先を急ぐ。該書『ある中国人の回想』では、伯醇が羅佩に贈った詩が続くが、行間の都合で次号で御紹介しよう。
高羅佩琴学の恩師は清朝旗人の葉詩夢(しょうしぼう)(一八六三~一九三七)で、本姓葉赫那喇(エホナラ)氏、初名を仏尼音布(フニインプ)と云い、諱を潛、初めの字は荷汀、後の字を鶴伏、斎号から詩夢斎、又、六琴斎居士と号した。清の大学士文荘公葉瑞麟の第三子であったが、中華民国成立後は琴に隠れ、復世に出る事が無かった。著す所は若干有るも皆公刊せず、全て手抄本にて伝わる。
羅佩が詩夢先生に就いて琴の稽古をしたのは『琴道』公刊の年と同じき一九三六年(秋月※①)の秋九月の事で、公務の余暇を得て北京隆福寺裏手の小宅に通い、約一箇月間に琴学の初歩を学んだ。
 「詩夢斎遺影」
「詩夢斎遺影」『書苑』第二巻第六号1938年6月三省堂発行より
「詩夢斎宛羅佩献呈の辞」
『琴道』1936年刊初版本より(秋月※②)
This essay is
respectfully dedicated to the memory
of my first teacher of the Lute
Yeh Shih-meng
葉詩夢
(obiit 1937 aetate 74)
a gifted musician
and
a great gentleman
△目次TOP↑
秋月※①1936年『琴道』はまだ公刊されていない:
1936年秋高羅佩の第1次北京行において、初めて琴を葉詩夢から習う。
1938年 Monumenta Nipponica, Vol. 1, No. 2 (Jul., 1938)から1940年まで The Lore of the Chinese Lute を4回に分け連載公刊。1950年同誌に「補遺と訂正」公刊。
1940年『琴道』単行本公刊
秋月※②1936年は1940年の誤り(第15話参照)。英文献辞に1937年逝去の葉詩夢に捧ぐとあるように、1936年時点では未公刊なのは明らか。
瘦蘭齋樂事異聞 第64話
高羅佩先生のことゞも 四
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
今号は高羅佩先生に敬意を表すべ行間に多少の余裕があるため、拙稿連載の附録として稿末に「略年譜」を加えることとした。
羅佩は外交官としてデビューしてほどなく、すでに東洋問題のエキスパート、また中国・日本文化研究の世界的権威として著名な存在となっていたが、そもそもの斯方に踏み入る契機は、少時、父君のコレクショ中の中国陶磁器に漢字を見出して興味を抱いてよりのことである。十六歳の折りにはオランダ・ロッテルダムの中華街で中国語を学び、これより後、東洋の文化により深く関心を示すようになり、結果的には殊にジャパノロジーとシノワズリーに深く耽溺することとなる。
ライデンで学士、ユトレヒト大学で博士号を取得した年に外務省官僚入りし満州へ。東京では戦時中の一時、大使館中へ軟禁され外部との接触を絶たれるも、さしたる不便はなかったようで、戦後その体験を日本人に一言も愚痴らなかった。東西諸国での外交官任務の傍ら、北京では前清旗人の葉詩夢から正統派の琴を学び、戦前から琴書画の諸芸に精通する碧眼の文人と異名を獲ていて、当時日本の漢学畑では誰一人として知らぬ者はおらぬほどの重鎮であり、琴学や中国学の著作群は既に学界内において高い評価を受けていた。
さらに高羅佩の旺盛な探究心は止まることを知らず、艶なる方面や長臂援(手長猿)、果ては蝸牛(羅佩発見の新種ギューリック・マイマイ。※英語の発音ではこう呼ぶ)等、生物学の範囲にまでおよぶが、『長臂考』附録のソノシートには、羅佩が大使館官邸内で飼っていた愛猿の啼声があり、そのころ漢詩講座で高名な石川忠久先生にテープに起こしたものを筆者が呈したところ、李白の「両岸の猿声啼いて住(や)まざるに…」に引かれる「猿声の断腸とは、との詩興を解するに大いに役立つ」と歓喜なさり、犬の遠吠えにも似た啼声を盛んにラジオ講座で流されていたものだ。
羅佩はさらに、『武則天四大奇案』(一八九〇刊通行本)にヒントを得、積年温存した中国の公案小説『狄公奇案』を、江戸川乱歩(一八九四~一九六五)の助言を得て飛躍的に構成度を高め、一九四九年に凸版印刷で刷り、東京とニューヨークでそれぞれ頒布したのである。
これを、新たに知り合った魚返善雄(一九一〇~一九六六)により、一九五一年講談社版『迷路の殺人』として邦訳するや、これを機に以来「狄公案シリーズ」(Judge Dee Mystery)は高先生の歿後もヒットし続け、且つ販売実績を上げながら今も重版され、同様に全世界の言語に翻訳されて、愛読者数は確実に増え続けていることでも、その人気度は解ろうものだが、もともとは神保町の古書肆の二代目老板故山本敬太郎氏から、高先生は乱歩翁に紹介され、これが縁で羅佩は長年温存してきた中国の公案ものを翻案した、日本の所謂探偵小説に手を染めることとなったという経緯がある。
こうした高先生の遺業と、各方面に及ぶ私家版そのものを纏めんものと、これまでに何度か全集刊行の全てがあったのだが、余りにも広範囲に渉る内容のゆえに、専門家それぞれが連携するに至らず、惜しくも全集は現在までも刊行されぬままである。
残念ながら当時青年であった筆者と高先生とのご縁は全くもって淡いもので、二、三度程しかお会いする機会は無かったものの、一度だけ芝の駐日オランダ王国大使館にお呼ばれすると、「中和琴室」や「集義斎」と名付けられた書斎があり、和漢の書籍がビッシリ並び積められ、その一隅には先生著書専用の棚があって、探偵小説から未成年には垂涎?の妖しく艶なる方面のものの他に、さらに明清版の琴書や和刻の明清楽譜も多く架蔵されていた。
余談であるが、その後英国大手のK社から先生の遺品が競売に賭けられ、コロンビアとライデンの二大学に落札され、かつて筆者が実地調査し、目賭したライデンでは、次頁写真のような先生生前の書斎風に近い様子が模されていて、見覚えのある琴譜や明清楽譜もあって、ひどく安心したことと、懐かしさの込上げてきたことを想起する。
以来、高大人のこうした著作群に触発され、若僧の筆者は山本書店主とも懇意にしていただいていたこともあり、大抵の高先生の琴書以外の著作をも早くに架蔵していたが、残念ながら当時一番最新刊の沼野越子訳『黄金の殺人」(一九六五年東都書房刊)だけは如何しても入手することができず、訳者に直接お願いすべく八方手を尽くしたがすべては徒労に終ってしまい、連絡の方法もないままでいた。
さあ『ある中国人の回想』に戻り、曾て孫伯醇のために弾琴した高羅佩への返礼詩を次掲しよう。但し、白文のままご紹介したいのだが時節柄そうもいかぬ。
聴高羅佩鼓琴
高羅佩の琴を鼓するを聴く
高侯胸次満貯書
高侯は胸次に満に書を貯へ
与我論交常淡如
我との交を論ずれば常に淡如なり
夜闌置酒招名月
夜開にして置酒し名月を招けば
寒光流汞盈前除
寒光流汞(こう)前除に盈つ
於時人静万籟空
時に人静かにして万籟空しく
正襟為我撫孤桐
襟を正し我が為に孤桐を撫す
松風颯颯泉琤琤
松風颯颯として泉錚錚
玲玲玉佩下青穹
玲玲たる玉佩は青穹に下る
九泉唳鶴龍吟水
九泉の唳鶴龍水に吟じ
霜華満天来清鐘
霜華天に満ち清鐘を来たらしむ
嗚呼古楽零落向千載
鳴呼古楽零落して千載に向(なんなん)とし
雅道凄凉余琴在
雅道凄凉として余琴在るに
可憐俗耳乱筝笛
憐れむべし俗耳は箏笛に乱る
忍使随和悶光彩
忍(むご)くも随和して光彩を悶(とざ)しめ
主人玉立何昂藏
主人玉立すること何ぞ昂蔵たる
雙瞳澄碧涵秋光
瞳澄碧にして秋光を涵う
平生愛琴入骨髓
平生琴を愛すること骨髄に入り
百金脫手収散亡
百金手を脱して散亡を収む
非唯諳操縵
唯に操縵を諳ずるのみに非ず
亦能窮古今
亦能く古今を窮む
於今青春勤著述
今より青春著述に勤め
要使〇〇識雅音
○○をして雅音を識らしめんと要(ほっ)す
続く
大使館内「集義斎にて読書に耽る羅佩」
明代を愛しその文物を尊んだ羅佩は、大使館内の書斎の一に「集義斎」、「尊明閣」や、琴房「中和琴室」と名付け、公務の傍ら、それこそ和漢の蔵書万巻中に身をおき、文人趣味を満喫していた。写真左、丸穴の墩と琴案の上の愛琴がお解りになろうか。
『詩梦斎琴簫譜』
清光緒年間葉鶴伏稿本(坂田古典音楽研究所蔵)
琴と簫とは文人の雅友にして、君子たる者の書斎中、「左琴右書」および「竹友」の簫は欠く可からざる器とされる。
高羅佩の琴師で、この両者を善くした葉詩夢の自用箋が「詩梦斎琴簫譜」で、自らの琴やら簫やらに関わる譜及び内容とを記した意であり、彼の著述筆記した琴書の類は総じて「詩梦斎琴簫譜」で、別に同名の著書があるわけではない。該譜は弊小研究所秘蔵中の『東皐禅師集刊』とともに白眉である。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第65話
高羅佩先生のことゞも 五
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
劣悪な情況下にあった重慶で一〇○部のみ私家版で梓行された図版の高羅佩編著『明末義僧・東皐禅師集刊』の書には、献呈にまつわる以下の面白い逸話が伝わる。
台湾の蒋介石総統(一八八七~一九七五)は生前すべてのものの一番に拘泥し、たとえ最高のものであっても二番目に贈られることを嫌っていた。蒋総統に本書を献呈すべくその事情を知った羅佩は、やむなく第一番として総統に贈って喜ばれたのだが、しかし実は、東皐心越を開山とする祇園寺にこそ、いの一番を贈るべきとかねて編纂の段階から羅佩は胆に銘じていたので、戦後再度日本に着任するやいち早く祇園寺に詣で、初志を貫き正真正銘の一番を献呈した。よって該書の通番一番は世の中に二部存在することになる。因みに小研究所架蔵書は二番である。
さて、『ある中国人の回想』の編集は中山時子老師を主編とし、本多浄道(きよみ)、故太田愛子と故三浦いと子の四先生と申し上げたが、この稿をものするに際し、前号でご紹介した孫伯醇の詩中、積年の疑問であった結句の不明二字を、実際に編集を担当された中山老師に満開の桜花の下、「大泉公館」で久し振りにお会いし直接お訊きすれば、「当時伯醇先生は已にお具合が悪く、他に編集に携わっていた本多先生へも、貴君(筆者)の質問を機に再度お訊ねしてみれば、良く記憶されていて、〔出版に際し当時、伯醇先生にその結句の不明点をお尋ねしたが、先生自筆の詩稿も乱れ、すでに自作の結句が解らぬ状態であった。〕とのお答えが寄せられた。」とのこと。急遽数日後の午后、葉桜と八重桜とを見比べながら、中山老師と大西姉(中山師門下)と約定同道し、療養中の本多先生をお見舞いすべく礫川台の宗慶浄院へと向かう途次、倩(つらつら)これら一連の経緯を思えば、伯醇先生未だご在世のこととて、何よりも先生が不明点をそのままとし、上梓されたことに四十年間も気付かぬ自分の迂闊さを恥ずる。
この前日に本多先生は退院され、さらにお加減が勝れぬ由、そのため直接面会は叶わず、大黒様の「本堂の二、三階は墓域ですので」とのお言葉に甘え、ご案内していただいたそこに、フト何気に数年前に文学座の芝居で数ヶ月間ご一緒に仕事をし北村和夫(一九二七~二〇〇七。五月六日享年満八十歳)氏の墓標があるではないか。確か氏との共通演目は二つで、「オランダ影絵」と「風の中の蝶たち」であった。無論、筆者はその音楽作曲担当。特に後者は山田風太郎原作の『明治波涛歌』をアレンジ、和物を熟知された戊井市郎氏の演出で、音楽も大変凝った要求が出された面白い演し物だったが、再演の機はなかった。故人の戒名は「紫光院響誉蓮台和傘居士」とあった。
『明末義僧・東皐禅師集刊』
高羅佩著1944年7月重慶商務印書館刊
高羅佩先生記念「坂田進一琴演奏会」
1994年12月1日東京は芝の駐日オランダ王国大使公邸において、三笠宮両殿下と欧州列国の大使ご夫妻がた、ヴァン・デン・ベルク大使ご夫妻以下、高先生縁のお客様を前にして、講演と演奏中の筆者。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第66話
高羅佩先生のことゞも 六
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
一九六七年十一月二十四日に高羅佩が歿して後、最も充実した「高羅佩先生記念会」一連の行事は一九九八年の十二月一日に行われ、筆者の「琴演奏会」も同日の夜、オランダ王国駐日大使公邸で開催された。その重文級公邸は、名建築家・ジェームズ・マクドナルド・ガーディナー(一八五七~一九二五)設計になるが、工期半ばの彼の死により、弟子の上林敬吉(一八八九~一九六四)が引き継ぎ、一九二八年に完成した元はオランダ王国駐日公使館であった。大戦終結後この公使館は大使館となり、さらに現在の大使館本館竣工を機に大使公邸となった経緯がある。
羅佩は外交官駆出しのころからこの公使館に陣取って往古の文人風書斎(第六四話写真参照)を構え『琴道』その他を執筆したが、ある時、京都の古本屋から購入した古い版木で、自らが刷った春宮画『花営集錦』などを、書斎?兼執務室にロープを渡し、そこに刷りたての絵を干す、あまりに大っぴらな辺りを憚らぬ所業を時の大使が見兼ね、失笑して苦言を呈したという逸話が遺る。
そんな高羅佩先生の警咳に触れ、直接関わり合った諸先生方も大方はご高齢に達しているので、先生に纏わるエピソード等は出来得る限り早急に纏めねばなるまいが、幸いに筆者の周辺には極親密であった方々が未だ数人おられる。
わが良友で華語の名通弁として知られる平田敦子姐が平成の始めころの浅草寺における「重陽琴会」を催す時分に、「この度随行している元オランダ公使夫人とそのご友人を、珍らかな貴琴会にお誘いしても宜しいか」との打診が有った。「その方々は琴をご存知なのですか」と訝れば、「充分に承知しておられる」と宣うではないか。
筆者が主宰する東京琴社では毎年二度だけ「琴会」を開催し、一は清明琴会であるが已に廃止し、弐は重陽琴会で、平成改元このかた浅草寺の伝法院で「重陽琴会」のみ公開していて、ならばと浅草にお招きした。会後、直接お会いしてみれば、元駐日オランダ王国公使デ・フリース夫人に随伴されておられたご婦人が、何と長年尋ね求めた訳者の沼野越子女史で、偶然の邂逅に驚喜しつつお話しすれば、すでに照山姓に復姓されていたためと、その探し当てられなかった訳をようやく知った次第。以下、孫伯醇が高羅佩に贈った琴にまつわる詩の補足に戻ろう。
かつて筆者は浄土宗の名刹無量山伝通院寿経寺脇、小石川表町の幸田露伴(一八六七~一九四七)故宅の蝸牛庵近くに久しく住したため、伝通院の鐘の音は朝夕枕頭に親しみ、時折は寺の写経会に加わったり、境内は日常に憩った場である。宗慶寺(元々は伝宝院とも伝通院とも)は了誉聖冏(一三四一~一四二〇)が伝通院に魁て開いた草庵であるため、吉水山伝宝院は伝通院と創建年次を同じくすると謂う。
高羅佩記念「坂田進一琴演奏会」の後、三笠宮両殿下とヴァン・デン・ベルク大使ご夫妻と。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第67話
高羅佩先生のことゞも 七
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
目下道草を喰いながらも、忘れずに隻眸では孫伯醇の羅佩宛詩の続きなおも追っている。
小石川は唐風粧(からふうめか)して礫川(れきせん)ともいい、礫はこいし、つぶての意で、また小さな石が沢山で幾千もの意があり、そのために地名となった小石川なる河川は別名千川(せんかわ)とも呼ばれる。今も暗渠で覆せた上の通りの名を千川通りと呼ぶほどである。寺はその通りを少し登った礫川台の下方傾斜地に位置し、了誉上人が創建した応永廿二(一四一五)年の往古、吉水(よしみず)と命名した名泉が境内にあり、山号を吉水山としたが、最初の寺名の伝宝院を、徳川家康公の側室茶阿(阿茶ともの局の墓所を同寺とした元和七(一六二一)年六月十二日を機に、局の戒名「朝覚院殿貞誉宗慶大禅定尼」に因み宗慶寺と改めたと。
吉水は極楽水(みず)とて次のような因縁がある。『江戸名所記』に、
「極楽之井
小石川吉水の極楽の井は、そのかみ、伝通院の開山了誉上人、よし水の寺におはせし時に、龍女かたちをあらはして上人にまみえたてまつり、仏法のふかきむねをもとめしかば、上人すなはち弥陀の本願他力の実義即相無相事理倶頓の要方をねんごろにしめしたまふに、龍女すなはち即悟無生の理にかなひ菩薩戒の血脈をうけ、その報恩としてこの名水を出して奉りけり、このゆえに極楽の井と名づく。」
との霊験を謳われたが、その後は環境が変わり、明治期には露伴の『琴のそら音』に次掲する一変した極楽水に関する記述がある。
「極楽水はいやに陰気なところである。近頃は両側へ長家が建つたので昔ほど淋しくはないが、その長家が左右共関然とし空家のように見えるのは余り気持のいいものではない。貧民に活動はつき物である。働いておらぬ貧民は、貧民たる本性を遺失して生きたものとは認められぬ。余が通り抜ける極楽水の貧民は打てども蘇る景色なきまでに静かである。…実際死んでいるのだろう。」
とあり、曾ては雨が降れば泥濘になる礫川に沿ってはそれ形に可成り賑わしい貧民窟が続いていたものだが、寺域が遷った後の極楽井の泉の周囲には、曰く有りげなヒッソリとした貧民達の窠があったらしい。
更に宗慶寺で筆者の興味を惹いたのが「珂北野口先生之碑」なる詩人野口雨情(委細後稿)の叔父で、大恩人の野口珂北(一八四八~一九〇五)の碑が門前にあったことである。
珂北の本名は勝一といい、珂北仙史と名乗り後に北厳とも号した。本憲政史上初期の代議士で、衆議院で辣腕を揮ったが、特筆すべきは文事を善くし、東洋絵画会を結成、『東洋絵画叢誌』を発刊、「茨城日々新聞」をも創刊した。遺墨こそ少ないが書も絵も嗜み、著書は多数、中でも『国会議員品定』、『征露戦史』、『画法自在』、又「西山山荘記碑」の撰文や、少年向けには『水戸義烈両公』も著す等々、今で謂うマルチ人間のハシリであった。
続く
「宗慶寺にて」
高羅佩令夫人・水世芳女史の良き友で、筆者若年のころの中国語の恩師でもある中山時子先生と。
「極楽水の碑」
「珂北野口先生之碑」
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第68話
高羅佩先生のことゞも 八
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
今号では再度高羅佩の心友孫伯醇に焦点を当ててみよう。
羅佩の知己となった伯醇の詩文集『ある中国人の回想』は、なお現在でも比較的入手しやすい通行本である。就中、伯醇先生の明治仕込みの日本語は、単純明快かつ歯切れの良い東京弁で、もちろん語り手が一外国人であることなど読者には毛頭感じさせない。
中国では中国事情に通じる外国人への褒め言葉の一つに「中国通」があり、時として筆者などもその対照となり、何かしら面映い念を抱くことがあるが、これはどちらかというと、半可通に対し「ホー!よくご存知で?」的な使い方をされるので注意を要する。しかし、こと伯醇や羅佩両先生のような方々に対して、そんな心配はそれこそ無用で、その身体こそ外つ国産であるが、思いや習慣に至っては日本人以上に日本的なのである。
日常筆まめ、かつ琴と対話した羅佩に比し、伯醇はその深き思いを絵画に託することが多く、遺作の詩文もあまり多くないため、この意味からも『ある中国人の回想』という遺文集は貴重な記録となろうが、たまたま雑誌『言語生活』に伯醇を交え対談があるので、さあ、三者三様その筋金入りの東京弁を抜粋してご紹介してみる。
「外人は日本語をどう見ているか」
この座談会は日本語で行われた。ブリンクリーさんも孫さんも、日本
語が大変お上手である。日本人以上に自由自在に、実に自由自在に日本語をあやつられる。
幼時に日本語を覚えた
—略―
魚 小学校もこちらで……。
ブ ええ、暁星小学校です。
魚 そうしますと、孫先生と同窓ですね。
孫 ええ、先輩です。
魚 孫先生は……。
孫 ぼくの方はずっと遅いんで、明治三十八年の卒業ですから、(ブリンクリー氏に)三十二年に卒業されたんでしょう。
ブ ええ、
魚 教育はお小さい時に日本で受けられたので……。
孫 それは一応中国で四書五経を読んで、それから日本に来てまた小学一年からやったんです。
魚 四書五経を読んで小学校の読本をおやりになったのは珍しいですね。孫 二重人格です。(笑)
ブ 先生はそうおっしゃいますがね、私が日本語を習ったのは、日本の読本を右の方に置いて、同時に漢文をやったもんでございますよ。日清戦争の時分のお話でございますが……。もっとも私のはむずかしい漢文ではなく日本式のもので「日本外史」「十八史略」。
孫 えらいもんだ。
—略―
今の学生にむずかしい東洋古典
魚 今、孫先生は学習院で中国語を教えておられますが、文法を教えていらっしゃいますか。
孫 やっていません。初歩のものは一切おことわりしているんです。それから古詩などは返点つけて漢文読みにし現代の言葉に直して、それを講釈するんです。
(続)
『言語生活』No.49 昭和30(1955)年10月号
国立国語研究所監修 筑摩書房発行
同雑誌の巻頭を飾る12頁におよぶ紙上座談会だが、表紙には掲載されない。
出席者は編集部員を除く、立正大学教授で英文学のロナルド・ブリンクリー、学習院講師の孫伯諄。司会は東大講師の魚返善雄で、この三名いずれも当時を代表する日本通であった。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第69話
重修永福寺
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
この十一月半ば、水戸祇園寺の浙江省浦江ツアーに参加するを得た。同行者は同寺ご住職小原宜弘老師とご子息、湊檀家総代と各檀家方。茨城県下曹洞宗寺院の僧侶方、かくいう筆者と元篆刻美術館館長の松村と古美術研究家高田両氏、杭州仏学院の殷先生と添乗スタッフの総勢二十名弱であった。
祇園寺開山の東皐心越禅師が明浙江金華府婺(ぶ)郡浦陽(その後の区画整理で、禅師生地である実際の浦陽は、いまは蘭渓市管轄となっている)の出身であることから、現在の浙江省義烏市浦江県にある名勝仙華山中の道観の境内中に「心越記念堂」が建てられ、今回、その前庭に小原ご住職の筆になる「伝衣鉢」の石碑建碑が、雨の中厳かに執行されたという訳である。
この前日には杭州の名刹霊隠寺に隣接して重修なった永福寺において、もうひとつの目的である祇園寺住職と永福寺住職の歴史的会見が行われ、東皐心越禅師が杭州湾を船出してより三百三十三年を経て初めて点と線
が合致し、ここに尊い仏縁が結縁され、これより祇園永福の二寺が協同して東皐心越禅師の顕彰と研究を行おうとの決意を新たしたことである。
次いで境内の音楽堂(東皐心越禅師が琴を弾かれたことを記念したホール)で記念の琴会がもたれ、祇園寺側を代表して筆者の歌で東皐禅師作曲の「安排曲」、永福寺の管院(副住職)念順法師ので陶淵明の「帰去来の辞」(東皐琴譜にも収録されるが、南京の成公亮打譜による)と、仏曲「普安呪」を急遽その場で、念順師の琴と筆者の簫とで琴簫合奏で演奏したが、聴衆はツアーの一行と、永福寺側スタッフと、上海からの我が友数人とさらにその友人たちであった。
憶えば、筆者が日本の琴道の重要性に気付き初めたまだ学生のころ、そう五十年前にも近いころか、その間、東皐心越を中興の祖とする江戸の琴客の事蹟を調べ、高羅佩に出会い、また祇園寺を訪ね、さらには杭州の永福寺址発見等々、走馬灯のように想起され感慨も一人であったが、私独りでさえそうならば、当然そこに集った人々それぞれの人生において、ここに至るまでの各人各様の道程には、これまた一個の劇や本などのネタには事欠かないこと明らかである。
霊隠寺と永福寺は新たに共通のチケットで拝観料を収める。しかも、通常の五等日でも少なくも一日一万人ほど善男善女が訪れるという。すでに永福寺では中国本土ばかりか、香港や台湾の信者もあってその信奉も篤く、今後、東皐心越禅師の足跡をたどり、この禅師縁の二寺の交流を通して、明末清初の日中の仏教交流がさらに明らかにされ、仏縁が大いに広まることであろう。
さらに、筆者にとって有り難いことには、本連載でもご紹介した幻の琴譜『東皐琴譜正本』の中国版の復刻の意義を認め、永福寺が全面的に協力してくださることである。二〇〇一年の九月三十日、奇しくも東皐心越禅師の御忌三百六年当日、琴社創立三十一年を記念してこの琴譜を出版することができたが、日本側で完売したため、以来中国音楽界、ことに琴界からの切望に何年間もお応えすることが出来なかったのである。
「祇園・永福両寺住職の邂逅」
2009年11月15日永福寺内心越記念堂にて
右側が永福寺月真法師、左側が祇園寺小原老師。後方は東皐心越禅師頂相。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第70話
重修永福寺 続
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
旧臘半ば、上海音楽学院において近代の名琴家張子謙(一八九九~一九九一)先生を記念する「記念古琴大師張子謙誕辰一百一十周年」なる会が催され、たったの二日間であったが、筆者もその門下最後尾に連なる一人として急遽これに参加した。
十七日は報到(登録)で、少数だが筆者を含み音楽院ほど近くのホテルに国内外からの名家が参集し、十八日午前には音楽院におけるシンポジウムと、午後は「古琴大師張子謙誕辰一百一十周年記念音楽会」が開催され、夜間は大宴会と、その後の茶会とで深夜まで内容の濃い会は大層賑わった。
張子謙先生は揚州の産で、八歳で私塾に入り、十一歳で孫紹陶先生に就き広陵派の琴を学んだ。結婚後に天津、二八年には上海に移り、当時の名琴家たちと交わるが、張先生共著の『今虞琴刊』(一九三七年五月刊)中の「琴人題名録」には、
姓名・張益昌、別字斎名・子謙、双蕉琴館、年齢男女・三十八男、籍貫・江蘇儀徴、家世職業・農商、住址及通訊処・揚州東関街二百八十一号、上海浦東春江路公茂塩桟
とあり、原貫は儀徴の人らしい。
筆者は一九五八年から琴学に志し、暗中模索の中にも七〇年に東京琴社を興し、八〇年代はじめに上海の龔一先生と文通を始めた。この張先生の「芸術生活七十五周年」の記念会に今虞琴社の要請で上海に出て、初心に戻り筆者は張老先生や他師に就いて琴を学び、陳重先生に就いて絲竹や洞簫を学び、また高志遠先生に随行して上海市内の主要な絲竹会に出入りを許されて実地に絲竹を学んだりしていたが、それらの合間にも、上海音楽院を拠点として杭州まで度々フィールドワークに出かけ、前号でご紹介したように、杭州の永福寺をようやく発見する。
その後の仏教協会などの多大な尽力で今日、永福寺は重修となった訳だが、そのころの上海琴界では、いまの中国では琴を学ぶもの等しくが認識している、近世日本琴学中興の祖となった東皐心越禅師などのことなどは、上海図書館に『東皐琴譜』の不全本が所蔵されていることを知っていればよい程度の方で、筆者が杭州くんだりで血眼になって心越縁の寺を探索しているのを、「フーン、物好きだな」と大方は冷静に観ていたのである。
上:「上海音楽学院にて」
2009年12月18日
纪念古琴大师张子谦诞辰一百一十周年研讨会留念
上海音乐学院2009.12.18
左:「揚州広陵琴社雅集」
中央前面左側の柱に凭れるのが若きころの張子謙先生で、そのすぐ右が査阜西先生である。
下:「永福寺俯瞰図」
寺域は画面よりさらに広く、図はまだ左側の山門へと続く。
永福寺參拜交通方案
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第71話
重修永福寺 続々
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
ところがである。杭州行から三十年近くなった現在、当時は一見なんでもないようなそれらのごく小さな一つ一つが結集してきたではないか。しかもその形となったものをみてみれば、いやはや何とも大きな成果となればなるもので、今や永福寺は地下の東皐心越禅師でさえびっくりするであろうほどの宋代の寺域を規範とした一大伽藍を備えた寺院とはなり、さらに今までは同禅師の遺品など中国には何一つなかったものが、ホンの少しづつではあるが、遺墨や関係の仏書なども寺では蒐集し始めているし、また心越の日本に齎した最大の貢献『東皐琴譜』の復刻なども実際に計画されるようになったのであるからして、他の先学たちのそれぞれの微々たる努力は報われもし、こうして現実に形となって眼前に存在しているのである。
これらのことを通して筆者は多くを学んだ。一個の力ではまったく不可能とも思えることに対して、地道な積み重ねを怠らずに、目標点を見失わず努力していけば、必ずや思いを同じくする同志が現れ(たとえ同時代ではなくも)もし、またそれらの小さな力が結集して細い糸が縒られて太い絲となり、やがては多絃となって琴に張られ、霊妙な音楽を奏でるようになることをである。
ここに唐突ながら、長々と前述した東皐心越禅師の影響例の実際を少しばかりご紹介する。禅師の東渡以降、特に江戸の士人たちの土壌に蒔いた文人的種子はごく少量小粒のものであったが、如何にもその後の収穫量は大きく、また着実なものとなった実例中の佳話である。
そんな一例として、天明から寛政年間(一七八一~一八〇一)にかけて、牛込の琴社(東皐心越禅師を流祖とする江戸琴派の結社。主に近在の旗本やご家人が集った)は、現在の大久保通りと神楽坂の交差点角にある安養寺や近くの行願寺(神楽坂が花柳界となる契機となった元の寺だが、現在はない)などで「琴会」を開き、田安徳川家の文学・児玉空空(一七三四~一八一一)の迎噉閣のメンバーを中心に「牛門社」(牛門琴社とも)として研鑽しあい、それぞれが弾琴し、さらに余裕があれば詩を賦し、書画を認め、文学を語り、絲竹を奏し、飲食をともにしたりと、定期的に雅会を開催していた。
ややあって牛門琴社の内容も充実し出してきたため、寛政元(一七八九)年、琴社の重鎮で幕府の御徒目付たる新楽間叟(一七六四~一八二七)が琴社のために改めて起草した「琴会の約」がある。北宋の司馬光(一〇一九~一〇八六)の故事を規範としたものだが、これを読めばこれがただに琴を弾き合う会ではなく、東皐心越の齎来した浙派の琴学が、明代士人の復古精神を汲取り伝えたものであって、よくこれと日本の武士階級が呼応しあい、さらに消化したものであったということが解ろう。以下本文は次号でご紹介しよう。
「天籟雲和」
現永福寺住職月真法師筆
雲和天籟とも。まま琴銘に多用され、東皐心越禅師が好んだ語でもある。
「天籟雲和
坂田仁者鑑之
己丑秋永福月真」
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第72話
重修永福寺 牛込琴会の約
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
「琴会の約」
昔、司馬温公とそのグループは、真率の会という、ありのままで飾り気のないサロンを催した。精白しない穀物と濁り酒を数杯お代わりするだけの会であったが、なんと昔の賢者というものの心の用い方は、見習うべきはなかろうか。富貴にあっても節度倹約を守り、俗を真似て贅沢にならぬようにしたのだ。
今、琴社の面々も互いに約束して、この先例に倣おう。我々は清貧であって、贅沢や上辺を飾ることなど出来ないからだ。こうするの外、やむを得ぬところから発足したのと、真率の心とは図らずも一致するのである。
古い習慣に従って、条例を左記のように定めよう。
一つ、これに集う人は琴社のメンバーとするが、招かざる客でも甚だしく俗物でなければ構わない。但し、身分を鼻にかけたり、金権を誇り、また文学を解さないような人物は同席させない。
一つ、集う日は一月に一度、乃至二度とするが、公務繁多でない日としよう。風雨の日でもこれを決行する。午前十時ころに集い、午後六時ころ解散する。夜は泊まらないようにする。約束に遅れた者も、来会出来なかった者も、どちらも罰しない。
一つ、集う所は、牛込御門外の安養寺である。差し障りがあって会場を変更する時は、必ず寺院とか別荘とする。人込み、喧噪の場所を避けるためである。
一つ、集いに用意するものは、茶菓子少々と琴二面、それに琴案と椅子二脚。その他、当日余力のある者で、酒肴やおやつを差し入れるについては、一向に構わない。
一つ、集いでは、琴を弾く他に、詩を賦し書を朗読し、字を書き絵を描き、また詞曲を歌い、絲竹を演奏するも、各々その好む所に従ってする。ただ、多人数が集えば、話し声はうるさくなり易い。経書、史書を語り、世俗を否定するも反対しないが、出世に関する話しと、下世話な話題だけは許さない。
規約が出来て空空先生に申し上げると、「よかろう」とおっしゃったが、「お客ばかりで主人役がないな、質素は良いが、誰が接待するのか」とのご下問。メンバーがお答えするには、「毎回輪番で二人を選び、幹事の任に担らせたいと思いますが、如何なものでしょうか」と。先生が「よし」と仰せになったので、常連を別に列記してみる。
己酉花記陰曆二月十五日
同社名二十七人
新楽 定誌
…以下略
(筆者稿「神楽坂ニュース」第一五九号より)
「琴会約」
寛政元(1789)年新楽間叟起草
立原杏所後写本 国会図書館蔵
水戸藩士立原翠軒の男杏所(1786~1840)の筆写になる。
杏所の琴系は、東皐心越→人見竹洞→杉浦琴川→小野田東川→久保盅斎→立原翠軒→杏所、となる。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第73話
重修永福寺 続又続
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
こうした和漢の先人琴客に勇気付けられた筆者は、『東皐琴譜正本』に継ぎ、江戸期の文人音楽として一時武士の間に流行した「明楽」の楽譜と論との集成『明楽大全』、および今日中国の二胡に圧されてしまった感の日本伝統の『胡弓名曲集』を完成されるべく、残余の時間を充てなんとしているが、閑話休題、ここに唐突ながら以下の話しをご紹介したい。
わが青春期の愛読書『菜根譚』がある。明末の洪自誠(生没年不祥)編の儒仏道ないまぜの書で、いわば心学風の警句三五七編よりなるものだが、就中、加藤咄堂(一八七〇~一九四九)の『菜根譚講話』が面白く、四十五年経った今もって胸中深く秘蔵している。
書中、「無寒暑の公案」、「去来自由」とて、「心は明鏡の如く、花来れば花現じ、鳥来れば鳥現じ、来るに任せて少しも影を留めない。それを我々凡人は影を留めて執着し続けるものだから、そこに迷いが生ずる」というような話に、原坦山和尚と東皐心越禅師の逸話が続き、如何にも禅師の巷間における知名度を物語っている。
風、疎竹より来たり、風、過ぎて、竹、声を留めず、
雁、寒潭を渡りて、雁、去って、潭、影を留めず、故に、
君子、事、来たつて、心、始めて現はれ、事、去って、心、随って空し。
…略…
心越禅師の心膽
東皐心越禅師といふ人は支那から日本に来られた高僧で、非常に胆力の座つた御方で、容易に驚くといふ事がないといふので、水戸黄門光圀が、或る時その心越禅師がどの位の心が定まって居るかと試さうとして、自分の屋敷に招いて御馳走をして、大きな杯で酒を出し、今、禅師がその大杯を両手に挙げて酒を飲まふとせられる一刹那に、次の間に大砲を準備して置いて、ズドンと一発打ち放った。大抵の者ならば吃驚して杯を落すか、酒を零す所でありますが、心越禅師は、その酒がピリツとも動かず、グット飲み乾し「有難く頂戴致しました」と平然として居られる。しかし、人を招いておいて隣の部屋で大砲を打つなぞといふことは失礼なことでありますから、光圀が「禅師、只今は失礼仕った」といはれた。成程、武家で大砲を打つのは当然だから別段斟酌するには及ばぬと云はれたのに不思議はない。さて返杯といふことになつて光圀は其の杯を取られた。今度は大砲を打ち出す心配もないから安心して飲まふとせらる一刹那に、禅師は腹の底から出るやうな声で「ガアツ」と大喝せられた。光圀は不意に杯を取り落して「禅師、何をなさる」といふと、禅師は「棒喝は禅家の慣ひ、別に御斟酌は仕りません」とやられた。棒を振廻したり喝と警覚するのは禅宗の常套手段だから別に斟酌は致しませんといはれたといふ有名な話があります。この禅師の態度は即ち事に当つて始めて心現はれ、事去つて心空しきものがあります。斯る境涯に至るならば、話は元へ返りますが暑いの寒いのといふやうな所を通り越して無寒暑の処に到る。否、無寒暑どころではない、無生死の処に至り、生きる死ぬるを超越した所に心を落着けて行き得るのであります。即ち来れば現じ、去れば影を留めず、生死を生死に任す。さあそこまで参りますと、心を鏡のやうにする、其の鏡といふことに執着することもなくならねばならぬのであります。
(『菜根譚講話』)
「永福寺僧侶による梵唄」
2007年4月19日杭州永福禅寺音楽堂にて
解放後60年を経て再建された永福寺は、2005年4月に正式に対外的に門戸を開き、以来、念経の声が日夜広大な寺院内外に響く。再度この梵唄が戦乱によって途絶えることのないように祈るのみである。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第74話
九連環 一
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
今号で少し琴と東皐心越禅師を離れ、多少は馴染みのあろうかという清楽の話しをしてみよう。
外来音楽中、西洋の切支丹音楽については、また稿を改めてご紹介することとしようが、日本に根付いた最古の音楽は雅楽であることは諸賢ご承知の通りで、これは朝鮮半島を経由して齎せられた。次いで古いものは江戸期伝来の三種の中国文人音楽で、琴学と明楽、さらにやや遅れての清楽である。
「清楽(しんがく)」とは清朝中国南方系の俗曲群を呼称する日本における分類名で、その内容は古謡から民歌民謡、戯曲(芝居音楽)、曲芸(浪花節のような歌いもの)流行歌、俗謡、童謡などを包合した多岐にわたるもので、幅広い曲種を含んだものだが、その主核をなすものは一体に小曲が多いため、清朝中葉以降のこれらが流行した当時の中国では、庶民の間ではもちろん楽譜などは必要とされず、みな空で聞き覚えて唱っていたのである。
徳川幕府唯一の貿易港であった長崎と往来し寄留した中国商人の中には、かなりの大店の主人もあってその知性と見識を誇り、いっぱしの文人気取りの老板もあったりしたものだが、さらには商務を離れて北京の落第生などと自称する旅游目当てで物見遊山の輩もあり、唐館を中心とするその内外に居を構え、日夜文事と遊興にのみ耽る手合いもあったのである。
幕吏「唐通事」家系の先祖はすべて初期の長崎貿易に携った華僑で、その子孫は出身地毎に異なる方言を一子相伝で学び、小通事見習いから大通事にいたる長い修行期間を経て、北京・南京官話をはじめ、福州、泉州、杭州、寧波などの各方言を学び、貿易業務から政治情勢、文化、学問などの中国と関わりのある一切を取り仕切って、はなはだ公権と学力の両刀を兼備したものであった。
個々の名は煩雑ゆえ避けるが、役目柄唐通事は唐館居留のこうした清客から学んだ月琴などを、さらに華語や詩歌また俗文学などを学ぼうとする日本人門下生中の楽才のあろうかというものに伝え、その門人が日本各地に分散して清楽流行の下地がなったわけで、昨今テレビの大河ドラマで話題の龍馬の妻おりょうが、そのころ流行していた月琴をわざわざ長崎に習いにいくという件もあるほどだ。
清楽流行の魁曲はいくつか挙げることができるが、とりわけ「九連環」の一曲が目覚ましく、これによって清楽が一躍日本全土に拡散されたといって過言ではない。
鈴木鼓村(一八七五~一九三一)は軍人あがりの音楽家で、中学教師をし、一時は京極流という復古新派の箏曲の家元となり、また後に那智俊宣と名乗り大和絵師となったほどの奇才であるが、誰もが無関心であった日本音楽史を初めて系統だてた人として特筆される。
その『鼓村襍記』(遺稿集)に、この九連環についての記述がある。
(続く)
「九連環」
本来の九連環とは玩具で、古来ある知恵の輪の一種である。
「九連環」工尺譜
『亀齢軒月琴譜』1832年序より 亀齢軒斗遠編
一名『亀齢琴譜』また『花月琴譜』ともいい、天保三年序をもつ刊行された日本月琴譜の嚆矢であるが、よくよく見れば『魏氏楽譜』版本と同様、元刷りに楽譜はなく、正式な伝授の際に学習者が工尺譜を書き込み使用した。
月琴詞
一越調
泿華 龜齢軒斗遠著
九連環 一曰指情歌
看看兮賜奴的連雙手拿
來解不解
九連環九卟九連環
他做夫妻他門是个男男子漢了也也呦
九連環 鳳陽調 筭命曲 龜齡琴雷
40
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第75話
九連環 二
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
鈴木鼓村の本名は映雄であるが、生地の磐城国亘理郡小堤村は後に小鼓村とも呼ばれたため、鼓村と自号したのである。その遺稿集『鼓村襍記』(雨田光平編一九四四年古賀書店刊)には九連環を評して、
…また外邦輸入の俗謡が追々日本化されたり、詮索して見ると却々面白い。彼の近年流行つて一時盛んであた「サノサ節」などは、そのもとは誰でも知つてゐる清楽の「九連環」であるが、あれが昔支那から長崎に入つて、軈(やが)て意味の通じない「カンカンノー節」となつて流行り出したのは慥か嘉永安政の頃と聞いてゐる。
とある。
片山賢(さかし。一七九八~一八五三)は、江戸は雑司が谷幕府御鷹屋敷に属した御鷹匠同心で、今日では幕末期を代表する江戸の蔵書家、また筆記癖の人として知られている。この賢は中年の三十三歳ころより心越派の琴に興味を抱き多少は学んでいたが、四十年近く勤めた御鷹匠同心を退いて、賢の男椿助(後の幕府御軍艦取調役組頭、御勘定組頭)に家督を譲った晩年のころ、浪速より琴師鳥海雪堂が江戸へ下り、駒込本郷湯島と転々とするうちにも琴と書を教授したため、ようやく念願かなって琴と書三昧に耽るのだが、惜しいかな、時すでに遅し。日夕、敬愛親炙した雪堂を五年にして失い、賢もその後を追うかのように僅か二ヶ月で没してしまう。
まさにその賢がまだ青年御鷹匠同心として江戸を闊歩していたころ、ちょうど全国的に「九連環」が流行し、これから派生した「かんかんのう」が江戸にもおよび、文政四(一八二一)年の三月から五月ころには大流行したとみえ、ご府内各所でその一座が興行していたようである。
数え二十六歳の折、生来音曲好きな賢のことである。ちょうど四月には見習同心から御鷹匠同心に格上げとなり、片山家の家督(参拾俵二人扶持)を正式に嗣いだ時期と重なり、さらには結婚する一年前のこととて、彼の人生中でもなべてが順風満帆のころである。御役目の途次に三月には深川八幡で、五月には両国回向院境内で、唐人踊り「かんかんのう」を偶然に見物し、この図をスケッチしたのである。
賢をも含め、幕臣といえども当時大半の下級武士たちは生活のため副業をもち、趣味と実益を兼ねた絵画や書道、また学問などに精を出したはまだしも良いほうである。
賢の実家も養家もが先祖以来、画学や随筆日記を善くしたので、賢も青少年期から幕臣大岡雲峰(一七六五~一八四八)や岡田閑林(一七七五~一八四九)などに就いて画を学んでいて、崋山のようにセミプロの画家とはならなかったものの、片山家に伝えた「お守草子」などにはかなりの筆跡がうかがえるのであるが、その筆記癖の面白さゆえ、拙稿連載中、この賢氏には向後もたびたび顔を出していただくことになる。
唐人踊り「かんかんのう」
片山賢が江戸の街で見た唐人踊りのスケッチで、もちろん楽手と踊り手は日本人である。
「おとりてハミなかきいろのい志やうに、かきいろ頭巾をかふれり」と三人の踊り手が、面白おかしく手振り足振りするなか、「はやしかたハ、皆くろき衣装也」と、四人の楽手それぞれは、太鼓・三味線(三絃子)・鼓(胡)弓、および三角鈴(トライアングル)で「九連環」で伴奏している様子である。
50
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第76話
九連環 三
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
前号片山賢のスケッチのキャプションは、「おとりてハミなかきいろのい志やうに、[くろき]頭巾をかふれり」が正しく、「…[かきいろの]頭巾をかふれり…」 [傍点]の部分は間違いである。チャンと読んではいるのに、思い込みで意志とは別に手だけが動いてしまうことが多く、どうも粗忽でいけない。ここに謹んでお詫び申し上げる。
この「九連環」から派生した「かんかんのう」につき、大田南畝(一七四九~一八二三)が文政四(一八二一)年六月に詠じたものが『あやめ草』に載り、
文晁の画がけるかんかんおどり、
かんかんの 踊をみても
本つめの むかしの人の 名こそわすれね
文晁の故妻幹々といふ、唐画をよくせり
とある。谷文晁の亡妻は「幹々」といい唐絵をよくしたが、その絵を想い、これに寄せた南畝の題と讃である。(現在不明)
同じく、ちょうど片山賢が見た「唐人踊り」も、文政四年の春からのあまりの流行振りにお上の禁忌に触れ、唐人踊り「かんかんのう」は、翌五年の春には禁令となってしまうが、「九連環」の一般的な歌辞は、
カンカンエー スウヌテキウレンクワン
看看兮 賜奴的九連環
キウヤキウレンクワン ショワンシュナーライ キヤイポーキヤイ
九呀九連環 双手拿来 解不解
ナアバタヲルクワ クワポードワンリヤウ エエユウ
拿把刀児割 割不断了 也也呦
というもので、当時はルビ通りにカナで唐音(とういん)で唱っていたが、これは戦後の一時期にあった「なんとか英語」擬きのしろものにも似たような、アメリカのジャズやポップスを、カタカナ米語そのままの発音で唱った他愛無いものである。
こうして「九連環」が大流行するうちにも、これを本歌としてだんだんと日本的な手が加えられたり、庶民の間で口真似られたりするうち、大別して二種の系譜に分かれるようになるのだが、その一種がすなわち「かんかんのう」系統で、文士が面白がって「九連環」の歌辞をもじり、これがそのうちに庶民階層でモテハヤされるや、いくつか替歌が生まれるが、その大概は本歌とは似て非なるメロディーに乗せ、おおむね歌詞のナンセンスを楽しんだだけのことで、そこは世界に冠たる江戸っ子のこと。唐音はチンプンカンプンってな調子で、落語「ラクダ」の「かんかんのう」にも登場する、その歌辞の例を挙げれば、
カンカンノウ キウレンス
キュウハ キュウレンス
サンショナラエ サアイホウ
ニイカンサン インピンタイ
ヤメアンロ メンコンフホウテ
シイカンサン モエモントワエ ピイホウ ピイホウ
や、「カンカンノウ、キウレンス、キュヤキュデキュー…」など多種生じて、かえって筆者などには本歌の唐音よりも難解なものでさえあるが、もとより、これらはチンプンカンであればこそ、江戸っ子連が面白がっ歌辞を、無粋にもいちいち典拠を挙げたり、漢語を当てはめようなどとは、それこそが全くナンセンスである。
片山賢筆「お守草紙」から
ちんこたん(椿助さん)
てつけなたんなよ
(手をつけなさんなよ)
ぺんぺんひくかや
(三味線弾きたいかい)
ちまさん(一族の幼女の名)
このねんねへ(この人形に)
ぼうくんなよ(坊に下さいな)
ねんねこよう
ちいやいよう
図中、ぺんぺんを弾くのが「ちんこたん」、すなわち賢の男椿助で、こうした父の慈愛のこもった台詞と自筆の草紙などで育まれ、家祖伝来の御鷹匠同心の役を継ぐも、その後、幕末多事の際には幕府御軍艦取調役組頭、また御勘定組頭となり国事に奔走した
51
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第77話
九連環 四
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
寒斎蔵の『清朝俗歌訳』(天保八年著未刊本)という奇なる本には、「九連環」を邦訳して、
一、見よ見よ、われに沿いし九連くわん、きうとハ九ツくさりのゆびわの事よ、もろ手かけても不解とかれぬ、小かたな取て、われともはなれぬ、エ、なんとしやう
三、河わたろうとておるのハ、いもがふね、妹とハいもとの乗れる舟、かれと遠くはなれねと、かねて両門とざしたり、さして逢れぬ、エ、なんとしやう
と、清楽を正式に学んだ者は、その「知恵の輪」がなかなか解けぬと同じように、これに若い男女の愛の絆と願いをかけていたことを知っていたのだ。
以下は、清楽「九連環」の日本化した「カンカンのう」の続きである。
神田アのふ 急火ですう
半鐘なるベエ 西風逃げさんせ
一家は大がい焼けたんべ
めんくがわるくて心配さ…
など、ここまで来ると一種芸術的でさえある。
もう一種が「法界節」の系統で、九連環の旋律をそのまま利用したものである。
これは「九連環」歌辞の第一節二句目の末にある歌詞「解不解(キヤイポーキヤイ)」から来たもので、その「不解」の唐音のルビ「ぽーきゃい」が、序々に「法界」と訛ったことによるものだが、法界坊(一七五一~一八二九)が広めたからとの一節もあるものの、「九連環」の大流行よりも少し先行するので合わない。
この「法界節」系統の特徴は、唐音を面白おかしく真似ただけのナンセンスな歌ではなく、まったく日本の歌として換骨奪胎してあるため違和感がないばかりか、お座敷系の端唄・俗曲として立派に独歩した上、新作の替歌を作ることも斯様に流行し、その唄本まで出版された証左が上図である。
多くの場合、法界節の楽器編成はもちろん月琴を主体としたもので、三味線や日本の胡弓、尺八などで簡単な伴奏をしていたが、中には正式に清楽を学んだものが演奏するかなり本格的なものなどもあったようで、まれには清楽器の胡琴や清笛などと和漢混交のものもあったのである。
ただ、法界節の一座とて、親方夫婦と二、三人の少女などで編成された小規模な旅回りの一座が、全国津々浦々を廻り、この法界節を広めたまでは良かったのだが、旅中の生活苦のため、この少女たちに春を売らせることが定型化し、法界節すなわち…、ということになり、揚句はお上から法界節の一座を組むこと自体が禁止され、法界節そのものも庶民からは旅廻りの芝居などより一段と低く位置付けされるようになってしまい、やがては下火となってしまったのである。就中、比較的有名な歌詞が以下であるが、よほど低俗化したものとなっている。
○一日も早く年明けぬしの側
縞の着物に糯子の帯 ホーカイ
○今朝斗りゃ鳴くな鶏まだ夜は明けぬ 早く返すも人に依る ホーカイ
「旅巡業の法界節屋一行」
法界節の唄本二種で、その表紙には『三曲合奏法界節新文句』とあり、明治29(1896)年6月、浅草の国華堂こと山崎暁三郎の発行と、『流行・三曲・法界節』は、同年の9月、日本橋の東雲堂こと鈴木武二郎の発行である。
仔細に見れば、いずれも手甲脚絆に菅笠姿の娘三人、また書生二人と女性が一人、それぞれ楽器を手にし、紅灯点々とする花街で、一は月琴、尺八、瑤琴(金属絃の箏を立て弾く)、一は同じく月琴に尺八と胡琴を奏で、流し歩く情景である。
38
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第78話
東台琴客余聞 十一 松井友石
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
ここしばらくは九連環を唱ったため、その旋律がしばらくは頭から去りそうもないが、払拭しつつもまたぞろ江戸の琴事に戻ろうか。
ただ、これから本題とする松井友石翁までの距離は案外と近いものの、筆者個人の想い出が彼処に鬱積し過ぎ、そこへ辿り着くまでの寄り道はかなり迂遠、かつヨタも入ろうが、これも大方の青春の想い出や往事の力道山のプロレスの大逆転、また昨今の韓流ドラマの筋立てと同じく、試練があればあるほど、我慢した分だけその後の喜びも増そうというものか…。
西片生まれのわが従前の侘び住居は、伝通院脇の旧表町にあったことは耳タコ。そのころの話しで、角の露伴の蝸牛庵を折れ、沢蔵司から小石川の善光寺坂を下り柳町の商店街を抜ければ白山通りだ。
一方、コンニャク閻魔の方から、小石川ドン突きの昔風な大亜堂書店からそのまま言問通りを遡行し旧初音町。江戸っ子武士かつ画家で琴客の井上竹逸の菩提寺のあった田町を左手に見て唐橋を潜り、東大農学部朱舜水終焉の碑をさらに下って不忍通りを過ぎり、谷中の藝大裏手方面に緩やかに登る坂が、同名の谷中善光寺坂である。
この坂の手前に畏友根津の「鉄兵」ことY兄の店が昨年まであった。兄はその若きころ藝大で学んだ、長唄三味線の故菊岡裕晃先生門下の逸材である。この音校の裏手下にあたる店を、わが学生時代に利用しようにもまだそこにはなく、本郷薬師の裏手、菊坂の長泉寺(東皐心越禅師が逗留した)の下手に店はあって、筆者は菊坂を日夕上下していたわりに店の印象はなかった。というより、貧書生で右往左往したそのころには、居酒屋の看板とて無縁であったのだ。
その後大分の時を経て、根津の店で音楽集団(客演演奏家をした時期がある)の打上や、自身の小さなライブをしたようなこともあったが、自分が湯島に移った今日のように、頻繁にご厄介になるとはとてものこと想像もつかぬなか、今夏、店は後述する千駄木に新開店した。
根津交差点から最初の信号機のある四つ角に煎餅の大黒屋があり、ちょうどその角を左折する道が暗渠となっていて、今も昔ながらに「藍染川」(その先は谷戸(たにと)川)という小さな小川が下水となって流れているはずである。幕末から大正の半ばころまでは、この小川を利用する多くの染め物業に携る職人が川の周辺に暮らし、しかもその大半は極貧であったと。昭和三十年代ころの筆者の少年期にもそんな印象が強かったように記憶するが、小川を暗渠としたのは大正から昭和の初期にかけてのことで、しかも一度きにではないらしい。
この四つ角を過ぎてほぼ真っつぐに道なりに行くと、道(川)は九十九曲りとなるため、通称「へび道」と呼ばれ、これを抜けると「よみせ通り」となり、目下その先で新「鉄兵」は背水の陣を布く。
前「鉄兵」から善光寺坂をちょいと上ると曹洞禅の望湖山玉林寺だ。その創建は徳川家康公の江戸入城の翌年、天正十九(一五九一)年にかかり、天王寺(もと感応寺)、大行寺に次ぐ谷中屈指の古刹で、本堂裏手には都指定の天然記念物の椎の大木があり、参道に続く右手の小路が「お稽古横丁」となり、ここらで三味線の音が聞こえるようなら、もうシメタものである。
谷中「玉林寺」門前から
藍染川(現在暗渠)の源流が湯島方角に位置する不忍池。その小高い傾斜に立地する玉林寺からは、往昔不忍池が見渡せたのだ。それゆえこの寺に深く帰依したという徳川三代将軍家光(1604~1651)公が、寺から池を眺望し絶賛したという故事に因み、望湖山と号したと肯点しようが、創建時すでに山号はあったはずである。
「不忍池」
蓮花の盛り七月、湯島から上野東叡山を望む。池は太古の江戸湾の名残で、往事は琵琶湖に模して造営され、杭州の西湖に準えて小西湖ともいう。玉林寺のある谷中は写真の左手奥の方向にあたる。
54
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第79話
東台琴客余聞 十二 松井友石
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
偶々今年の七月のこと。前号でご紹介した新「鉄兵」楼上に坐せば、なにやら隣席の客人たちが大層賑やかである。そのうちにも、お互いに声を掛け合えば、何とこれが玉林寺の若和尚を中心とした、何でも目出たい席だということが判明?し、その後は例の如く打ち解け過ぎ、お定まりのハチャメチャとなった次第。
心越流琴派江戸の残党、ことに上野界隈の事跡を調査するうちにも、東京遷都後の最後に位置する琴客松井友石に担ることとなり、確か昭和五十九年ころであったか、未だご存命(平成元年四月没)であった友石翁のご長女松井きつ(橘とも)刀自にアポをとり、渋谷駅近くのビル階上のご自宅をお訪ねし、聞き取りや友石翁のご遺品を拝見した。きつ刀自は山脇女学校を退職されて久しく、ついで渋谷で幼稚園を経営され園長職を長く勤められたが、これもとうに引退されていた。
 きつ刀自の尊父松井友石(一八五七~一九二六)名は廉、別号石翁、字司直は、実父は浪花の医儒で、なかでも琴を最も善くした妻鹿友樵(一八二六~一八九六)の男である。
きつ刀自の尊父松井友石(一八五七~一九二六)名は廉、別号石翁、字司直は、実父は浪花の医儒で、なかでも琴を最も善くした妻鹿友樵(一八二六~一八九六)の男である。父の膝下に諸学と琴を学び、十才で詩を善くし、十五才で郷校で助教を勤めたという。生母の没したを機に十七才で家を異母妹に譲り、もと丹波篠山藩儒の渡邊弗措(一八一八~一八八五)に従学し、傍ら医術を修め国学を講じ、また小学校の助手となって糊口を凌ぎ修学費用の足しとしていたが、廉青年十九歳の冬、自ら感ずる所あり、笈を負い東京に游学せんと助手を辞したのである。
これより以前、摂津南豊島村六ヶ村村長の小畑萬次郎(一八五五~一九三六。号松坡、友樵琴門)と義兄弟の約を結び、東遊の志を語れば、松坡は大にこれに賛同し、資金と旅装までも提供してくれた。
明治十二(一八七九)年十二月のこと、汽船に身を投じ横浜に着港するやいなや、早くも小盗に遇い、衣装金品を悉く奪い盗られ、嚢中僅に五十銭を剰すのみと。
ようよう東京に到り、さきに谷中一乗寺の学僧となって修行中の異父兄尾藤勝運(後の谷中大行寺の住職)師を頼ってこれに投ずれば、五十嵐宝俊住職もよく廉を歓待してくれたという。(小伝続く)
以下次号へというわけだが、ここまでの友石こと廉の履歴を閲すれば、なかなかの硬骨漢で、しかも努力家にして勉強家の像が浮かび上がる。
しかするうち、この駄文を纏めんものと古い資料を捜索すれば、松井家と筆者との接点の一「弾琴儀」なる断片が偶然にもあった。
友石・松井 廉先生記念
「弾琴儀」
乙亥四月十五日 於・谷中「玉林寺」
琴家・坂田進一
一、琴曲「平沙落雁」『琴学叢書』
二、琴歌「秋風辞」 『東皐琴譜』
三、琴歌「山櫻」 『東皐琴譜』
その後きつ刀自の計らいにより友石の男清(~一九五〇。号友山、林学士)の女婿故松井安信(一九二二~二〇〇六。北大教授)先生からご連絡いただいたことがきっかけで、こうした内輪の法要にお招きに預かったというわけだ。
ちょうど四月は友石翁ときつ刀自ご親子の没月とて、ご両人の法事を兼ねたその日、庫裡の書院での弾琴が終わり、安信先生らに見送られて参道を後にしたことを記憶するが、乙亥四月はちょうど平成七(一九九五)年のことで、もうすでにあれから十五年もの歳月が流れたことになる。
谷中坂町・玉林寺「寺額」
今や谷中も寺の周囲はすっかり街中に様変わり。大樹に沿って奥深い参道を行けば、寺額は本堂正玄関にあって有縁無縁を問わず、訪なう人々を静謐な禅機に誘(いざな)う。
玉林寺墓地「松井家墓標」
本堂左手脇から墓地へ抜ける石段を数段登り、すぐの右手に松井家歴代の奥津城が鎮座まします。
36
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第80話
東台琴客余聞 十三 松井友石
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
東游当初の明治十二(一八七九)の暮、早くも生き馬の目を抜くよう横浜で身包みを剥がれ、しばらく谷中に身を置くこととなった妻鹿廉こと後の松井友石、この後、東京最後の琴客の一人たるべく天理は動きゆく。
薩藩遣英留学生で博物局長、初代東京博物館長の町田久成(一八三八~一八九七。号石谷、従四位勲三等三井寺大僧正、友樵琴門)と豪商奥三郎兵衛(一八三六~一八九七。号蘭田、衆議院議員、友樵門)は友石の実父友樵門下で学んだ旧知の間柄で、この顛末を仄聞した久成は数日にして友石をその邸内に迎えて住まわせ、翌年の四月には町田、奥の両氏相談の上、師を選んで三筋町の小永井小舟(一八二九~一八八八)の濠西精舎に入門させた。
時に小舟の門生藤井重兵衛こと名優中村宗十郎(一八三五~一八八九)は、かつて友樵に書法を学んだため、友石の入塾を聞き夜具一組を贈りこれを祝したという。
師の小舟は早くも友石の才を看破して直ちに助手の任を託し、爾来常にその側に置き愛育した。その恩義に報うべく濠西精舎のため大いに尽力した友石は、遂には塾頭に挙げられ、師の講義録『論語講義』を数人の高弟と共に口述筆記、これは後の明治十八(一八八五)年の七月に公刊される。
学教大いに進む中にも、濠西精舎を出て、なお友石は足れりとせず斯文学会に入学することとなる。
斯文学会は幕藩体制瓦解後に前昌平黌に法をとった学校で、この斯文学会が改組され、後に現在の湯島聖堂斯文会になるため、ちょうど明治初期の渾沌たるその歴史の狭間に直接学んだ生徒として、この友石の若きころを通して、その経緯を多少とも解明できる貴重な人物ともなるのであるが、これらは別項で…。
湯島聖堂旧昌平黌出身で、同学会の教頭かつ日本初の文学博士となっ重野成斎(名は安繹。一八二七~一九一〇)は、友石の先師渡辺弗措が昌平黌で詩文の添削をした後輩でもある。その成斎が教授に担り、友石はその厳格な膝下におかれて、その第一期上等生となった。
斯文学会は、会長を有栖川宮熾仁(一八三五~一八九五)親王殿下、副会長は谷干城(一八三七~一九一一)子爵、教頭が重野博士という錚々たる人材に恵まれ、ために校規ははなはだ厳格であったというが、友石は学ぶこと久しからずしてここでも舎長を命ぜられ、学校の試験に際しては、常に優等を取った秀才で、かく諸学科尽く百点満点を取ったのは、友石の他、前後に人なしという。
明治十九(一八八六)年七月、同黌を晴れて卒業できた者は僅かに三人のみにして、この卒業生の嚆矢となり、会長有栖川殿下が親しく臨し卒業式を挙げられた。
廉はすでに学校を卒業し、人はみな勇躍その官途に出るを勧めたが、友石の曰く、「余は已に天爵(天の定めた爵位)を以て自任す。豈に人後(人のひそみに倣って)に従い、人爵(人界の定める官位)を望まんや」と遂に肯かずと。その抱負の人間に非ざる壮大さが知られよう。
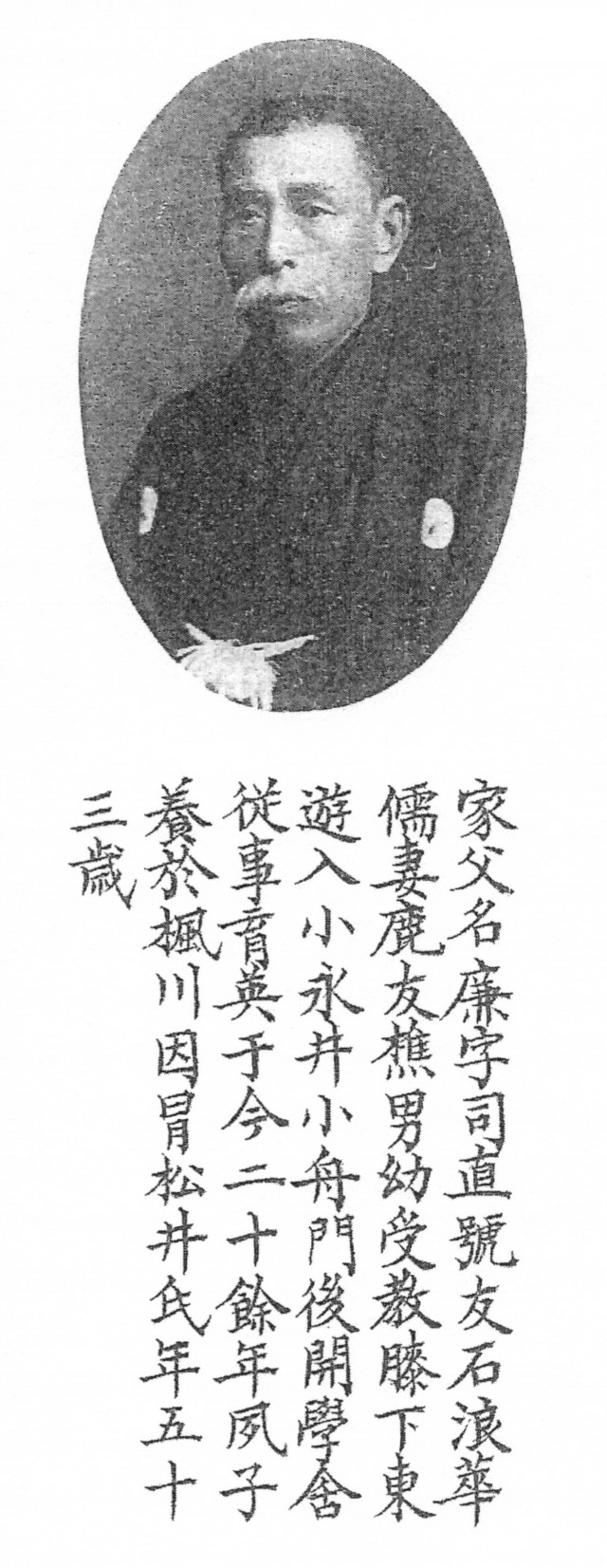 「松井友石翁小照」
「松井友石翁小照」『瓊琚餘韵』大正元(1912)年刊 私家版 松井清編より
長い学業を了えた妻鹿廉は官界には出ず、後に甲津学舎を開く在野の教育者としての道を選んだ。
家父名廉字司直號友石。浪華儒妻鹿友樵男。
幼受教膝下。東遊入小永井小舟門。後開學舎從事育英于今二十餘年。
夙子養於楓川。因冐松井氏年五十三歳
38
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第81話
寺島応養と浦上玉堂 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
この十月はじめ、金沢文化振興財団のお招きで、市内大手町に現存する武家屋敷「寺島蔵人邸」での講演と演奏に出向いた。
加賀前田家の家臣寺島応養(一七七七~一八三七)は、名を兢、静斎また乾泉と号し、通称を蔵人、字を応養といった、直言剛毅の性かつ書画を善くした文人肌の人で、三十二歳も年長の浦上玉堂(一七四五~一八二〇)が応養の名を聞き慕って立ち寄った当時は、藩の馬廻役目付四百五十石取り中級藩士であった。
文化五(一八〇八)年の秋、一代の琴痴・浦上玉堂は飛騨における田中大秀(一七七七~一八四七)らとの清遊を楽しんだ後、越後を経て、会津藩の礼楽整備のために仕官させた次男坊の浦上秋琴(一七八五~一八七一)のもとを尋ねる途次、金沢城下の応養邸を訪れ、応養の周旋のもと約百日間も金沢に滞在し交流したのだ。
幕末明治期の同郷加賀出身の漢学黒本稼堂(名は植。一八五八~一九三六)は、金沢四高や京都師範で令名を馳せた名物教師だが、熊本の第五高等学校の教授として奉職中、同僚となった夏目漱石と親しくし、『坊ちゃん』中の「山嵐」のモデルとなったことでさらに有名である。
その稼堂の編纂命名した応養の遺文集『静斎翁遺文』なる翻刻書があり、就中、応養と玉堂との交流の記録を金府に知らしめた。
一方、府内の和菓子老舗「森八」第十二代当主の森下晴嶽こと八左衛門(一八六一~一九四三)は、実業家としても幅広く活躍し、金沢電機を創設し、石川県下では金沢に電灯初めて点したり、さらには七尾湾の開拓事業や鉄道敷設をも行うような人ながら、また、篤志家としての一面をもった仁義の人で、この晴嶽がつとに応養の絵画と人となりを慕って私淑し、東京に在住していた大正八(一九一九)年に『応養画譜』の出版を志して以来、京都師範に稼堂を訪ね、共同して資料編纂に数年従事し、郷里と東都を往復すること十数次、応養の遺墨を蒐集すること四十数幅に及び、いよいよ出版せんとしたが、折悪しくも同十二(一九二三三)年九月一日の関東大震災
で罹災し、東京の家も資料もすべて灰燼に帰してしまった。
その後の数年間、家産と事業の復興に刻苦勉励した結果、いつしか出版の志しは疎かとなったように見えたが、豈謀らん、家道もようやく復したその晩年、郷里金沢に戻ったを機に、再度遺墨六十余幅を得て、これに稼堂の校訂した遺文集を併せ、晴嶽七十四歳昭和九年の八月下旬、晴れて『応養画譜』を私家版ながらも公刊したのである。時に応養没し正に百年忌にあたり、稼堂の提案で晴嶽と数人、応養の足跡を辿らんとその配流された能登島まで旅行(『寺島蔵人配所記』)したのである。そんな稀覯本『応養画譜』を、そのご遺族で寺島邸を保存、傍らこれに勤務されるT女史から献呈され、復路東京への機上で読んだところ、「何事草紙」と仮題された文中に以下のようにあった。
「伊藤仁斎の常に口ずさみし今様とて、浦上玉堂の語りし、
玉堂はもと奥州会津の人、故ありて京師に出て、常に琴を弾じ、深く酒を好みて書画を能くす、予が家に宿する二十日計なり、寉氅衣を着し、髪をつかねて笄を指し、早起酒を飲み、琴を弾ず、夫より詩を作り、書画を楽む、其の清雅他に比するものあらず、(続)
寺島邸内「玉琴の間」
四畳ほどの一見茶室風だが、実は応養が玉堂が弾琴するために特別に設えた「琴房」で、特徴ある漆喰製の「折上げ天上」は琴響を計算した上といわれる。
ここで202年前に玉堂自身が、21年前の1989年6月放映のNHK「国宝への旅」では筆者が弾琴した。
『静斎翁遺文』黒本稼堂編
昭和9(1934)年森下晴嶽私家版
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第82話
寺島応養と浦上玉堂 中
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
附言、玉堂、名を失す、姓は紀氏、備前の人なり、後に京師に住す、元明の古法を学て、筆力超凡、毫も街気なし、玉堂常に其子春琴の画を評して針箱画と云、其見想ふべし、文政三年九月没、年七十六、今会津の人とするは、誤聞にや、吾聞く、玉堂の北遊せし時は、翁が許をとひ、宿を乞はんとの心構なりしかども、武士の家に旅人を留むること国禁なれば、宿料はこの方よりして進じ可申候故に、尾張町の住吉屋を宿と定め、その筋へも届出て、此方へ御出被成候様にと申聞されければ、その言に随ひて住吉屋にむかひけるに、宿の方よりも、翁方へ問合せ、さし支なき旨をきって、然後宿をかしし由、それより玉堂日々寺島方へかよひ、優遊雅談、凡百日ばかりも滞在したりと、森翁の話、是も吾が家に宿する二十日ばかりとあるは、宿賃は翁より払はれて、日日通ひぬれば、かく書かれたるにや、
人はとがむと、とがめじ、
人はいかると、いからじ、
怒と欲とをすてて、こそ、
常に心は楽しけれ、
是誰人の作ぞ、河南の程子伯淳、…以下略」
と、応養邸にての玉堂とその宿に関することなどが略記されていた。
文中の太字は本文、稼堂の附言前の細字割り書きはどちらも応養の筆になり、稼堂の欄外注はこの部分にはなく、これこそが応養本人が記録した金沢における玉堂との交流を具体的に示した証左となり、爾後延々引用され続けてきた出典であることを初めて知った。
無論、玉堂の産地は備前。ちなみに住吉屋はその後に改築されているが、応養邸からは徒歩で五分ほどのところに現存する。そして文末にある「河南云々」は、文意からして次項の文頭に置かれるべきものであろう。
さて、この応養筆記の冒頭部分「伊藤仁斎の常に口ずさみし今様とて、浦上玉堂の語りし、…」により、これまで金沢の郷土史家たちは、玉堂の吟じた「今様」は、伊藤仁斎の作?かと誤認していたらしいが、実際に玉堂の愛奏した今様とは、実は蕃山了介(熊沢蕃山。一六一九~一六九一)作歌のものを指すのが正しく、却ってこの記事により蕃山作歌の今様を、仁斎(一六二七~一七○五)が日常愛誦していたことと解るのは、玉堂が精魂を傾けた畢生の著『玉堂琴譜』(前集。一七九三年刊)所収の「今様」に、
人は咎むと咎めじ
人は怒ると怒らじ
怒りと欲を捨ててこそ
常に心は楽しめ
とあり、前記した応養の筆記とは多少歌辞に魯魚の差があるものの、さらに同『玉堂琴譜』再本の見返しには書肆によるキャッチコピーがあって、「近き頃備の熊沢老人、越天楽(今様)の歌を作りて婦女子の戒めとせり、鳴呼美哉、今先生(玉堂)も亦老人(蕃山)の意によりてみん」とあるからによる。
近代の小説家吉川英治(一八九二~一九六二)の『玉堂琴士』(吉川英治短編集一)には、前掲『玉堂琴譜』所収の今様が効果的に使用され、流石に筆墨に慣れ親しんだ吉川ならでの文体は、虚実を綯い交ぜにしながらも、実際の玉堂像を髣髴とさせるに足る文章となっている。
(続)
今様「人者」の琴譜同『玉堂琴譜』より
『玉堂琴譜』(前集)
寛政3(1791)年玉樹堂・芸香堂
原刊本原題箋は『玉堂先生琴譜』、内題は『玉堂蔵書琴譜』で、後の増刷本と版元を異にする別本がある。
初版原刊本は、玉堂自捺の「玉堂文房十八友之一」なる印影がその証左となり、また、未刊稿本の『玉堂琴譜後集』が準備されたため、これに対し琴譜刊本は『玉堂詩集』(前後集)にならい、便宜上「琴譜前集」といわれる。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第83話
寺島応養と浦上玉堂 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
玉堂が、金沢の応養のもとを訪ねるに先立つこと一年前、文化四(一八〇七)年の冬、男春琴(一七七九~一八四六)のよき友田能村竹田(一七七七~一八三五)と、大坂の持明院で四十日間も起居をともにし、日夕竹田は玉堂実際の琴音を間近に聴き、『竹田荘詩話』(一八一〇稿)に、微細な技にこそ触れぬもの、「玉堂老人」なる率直な印象評を遺す。
玉堂老先生は六十を越えてまだ童顔。歌う声はまろやかですべるよう。歯はところどころ抜け落ちてはいるものの、発音もハッキリしている。酒が一番の好物で、酔えば小詩(絶句から短い律詩まで)を賦し、いつも〔琴〕字を用いるのだ。そうして小品の山水画を描きだすのだが、それは皺擦法〔詳しくは『林泉高致集』参照〕に心力をつくしたものである。こうした詩も画も従来の詩画法のしきたりを度外視したものだが、大変に趣の優れたものである。(原漢文)
玉堂は数えで六十歳、音曲好きで箏曲や三絃をよく鑑賞していた竹田は三十歳。これ以後竹田は玉堂と忘年の交わりを結ぶが、玉堂が文政三(一八二〇)年に没して後、十三年を経て成書した『竹田荘師友画録』にも同じく「玉堂老人」なる記事を遺している。
玉堂老人、備前の人、奇士なり、予一日閑坐するに、一片紙の突然に到る有り、迺ち書して曰く、子能く来りて我が琴を聴くや否やと、又書して曰く、玉堂老人の字は、殊に古怪にして俗を絶つと、此を詳らかにせば、則ち紀春琴の尊父なり、白髪童顔、鶴氅衣を服し、琴を拾いて昂然として往来す、之を望めば其の常人ならざるを知るなり、後に同じく坂府の持明院に寓し、最も親しみ善くす、毎朝早起し、室を払い香を焚きて琴を鼓す、卯飲すること三爵、常に曰く、若し天子に音律を考正せよとの勅有らば、我必ず其力を致し焉に与ること有らんと、
とあるよう、玉堂は豪語したのであるから、もってその古楽家たる自信のほどをうかがえる。一方『玉堂雑記』(寛政年間刊)では、
或ハ催馬楽廃りぬれハ。其伝る人なくして。うたひ得がたしなどいひて。予がうたへるを聞て。疑をおこすものあり。
此道に深く志。古書に考へ求めば千載絶たる緒も継ざらんやハ。
とある。
蛇足ながら、玉堂故郷の大先達能沢蕃山は天下の逸材であったが、惜しくもその活躍の場に恵まれず、ついには幕府の禁忌に触れて古河藩に終身御預となり、あたら空しく世を終えた。このことが廻り廻って寺島応の境遇と重なるのは偶然ではなさそうだが、そうした蕃山自身の心境を投影したもう一首の「今様」が遺る。
雲の懸かるは月のため
風の散らすは花のため
雲と風とのありてこそ
月と花とは尊けれ
爾後余談 寺島応養には四歳年長の実兄惠和(まさかず)(一七七三~一八〇一)、幼名己之助、通称右門があった。この兄は文武に長け、中でも弓と歌道および算術を善くし、画号を孤嘯亭と称した才人であった(系図)と。
もと原氏から兄弟して寺島氏へ入籍し、寛政三(一七九一)年に家名を継ぎ御馬廻組頭支配役となり、同六年に御表小将(小姓)組役を仰せ付けられ、同十三年の主君前田治脩(はるなが)侯の御供として扈従した江戸で、急病のためわずか二十九歳の若さで逝去し、急遽本郷上屋敷下の講安寺で荼毘に付され、葬式した後金府に帰り、改めて埋葬されたのである。
旧加賀藩江戸上屋敷跡はそのまま旧東京帝国大学の敷地となり、今次の大戦では米軍の爆撃目標から意図的に外され、故に全東京の焼土と化した中にも、大学の周辺は寺をも含めて奇跡的に戦災を免れた。
弊研究所から湯島の切り通しを渡り、鴎外の『雁』の舞台となった無縁坂に側し、講(江)安寺の土蔵造りの本堂は、ほぼ往事の姿を留める。
金沢よりの帰途、小松空港での待ち合いでのこと。前方のテレビをフト見上げると、何とそこに見慣れた顔と手があるではないか。アレッと思ううち、寺島邸の前栽からのアングルが聴衆の姿に移ったので、その日に取材にきたNHK放映のものと合点したが、折悪しくも、機内持ち込みのため明初製の古琴を抱えていたため、気付いた周囲の旅客の視線が集中し、恥ずかしいやら冷汗が出るやらで散々であった。
「講安寺前景」
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第84話
東台琴客余聞十四 松井友石
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
偶々、奥蘭田の妻鹿廉こと友石に松井氏に女婿たるを薦めれば、意外にも友石は快諾し、十二月には婚儀を挙げた。松井氏は清水屋と称す骨董舗で、かつ楓川亭釣古と号した煎茶と挿花の大家。以て都下に名声甚だ高く、苟も当時の書画骨董、茶花を弄する者で、楓川の名を知らざるものなしという。
友石もまた能く楓川の人と為りを知った所以であろうが、新たに岳父となる楓川は頗る侠気あり、ひとえに友石を迎えるため、「自ら骨董を商うは君子の業にあらず」と信じ、おのれ一代を以ての業を改めんと欲し、女婿となる友石にはこれを求めなかった男子漢でもある。友石ご長女のきつ(青楓)女史の生前、こうした楓川についての逸話を、筆者は直接うかがうをえたが、なかにも印象深かったのが以下の数話で、たしかに友石先生後半生の天の布石とも思えるため、冗漫を承知でここにご紹介したい。
○友石岳父の楓川亭鈞古若きころの逸話と、謂れの仏壇
その昔、江戸城の奥深く紅葉山を源流とする紅葉川(楓川)があり、東流して大鋸町を経、新場川に合流東海道と交差する近くに、かつて紅葉川に架かっていた中橋のみが残り、その橋の名が辺り一帯の通称となっていた。
文政天保のころ、その中橋のたもとに主を加賀屋清兵衛、通称「加賀清」なる骨董舗があり、諸侯および旗本連を顧客とし、また市川米庵、椿椿山など多くの文人墨客と交友があって、その旧紅葉川畔にあるに因み、米庵がこれに唐風めかし「楓川亭」と名付けた。
加賀清の人となりは風流にして温雅、仕入れのためしばしば京阪の地を訪れていたが、ことに高遊外売茶翁の煎茶式を好み、これを関東に紹介せんものと、往還の道中にも茶具を陳べ、別に雅法を案じて煎茶式を人々に教え広めたので、風騒の士人たちは挙ってその門に連なり、ようやく江戸の煎茶が盛んになったという訳である。
おりしも幕閣首座の水野忠邦による天保の改革の最中。奢侈と金銀珠玉などの売買を厳禁され、奉行所の与力同心以下、捕方手下におよぶまで血眼で都下を詮索するも、誰一人としてこれを犯すものはなかったという。
加賀清の商品の多くはこの禁忌に触れるため、無論、清兵衛も用心に用心を重ねていたが、ある日突然、山城河岸八官町の名主と名乗る客が訪れ、「この度手前の娘の婚儀に、ぜひ銀瓶が必要のため、枉げて秘密裏にお譲り願いたい」という。「ご禁制品ゆえ、固くお断り申し上げます」と辞退するも、続けて曰く、「われら両人のみが知り、他人の知るなし。売れば罪となり、買ってもまた免れぬが、手前は決して他言はしませぬ」と、切に請いてやまない。客と清兵衛は面識もあり、かつ名主役であるを信用し、ついにその言に従ってしまった。しかしてこれが悪吏の計であって、その術策に陥り、ついには商品はおろか、家も土地もお上に没収され、さらには所払いとなってしまったのである。
天保十四(一八四三)年九月、水野が失脚し改革中止の後には赦され、従前近くの南鞘町に小店を出すものの、失意のうちに安政二(一八五五)年となり、加賀屋清兵衛は没する。時に加賀清には二人の丁稚小僧があり、一を兼吉、二が長兵衛で、主人清兵衛の薫陶よろしく、古器物の鑑定と茶儀を仕込まれていた。(続)
友石岳父「松井長兵衛小照」
友石夫人「松井文子小照」
松井長兵衛の女、小楓と号す。少にして日尾竹園に学ぶ。
38
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第85話
東台琴客余聞 十五 松井友石
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
兼吉は年長のゆえ、清兵衛歿後に加賀清の小店を継ぐが、故あって骨董を廃業し、心機一転、新たに赤坂門外に蕎麦屋を開業する。その際、加賀清の恩義を忘れず、楓川亭に因み店名を「楓庵」と屋号するのである。余談ながら、この安政年間兼吉創業の楓庵は今も続き、現在六代目のご当主がその暖簾を守っている。
しかして年若の小僧長兵衛こそが後の楓川亭釣古翁で、琴客松井友石の岳父その人となるのだが、それはこの先数十年後のこと。
加賀清の没したは、長兵衛十七歳のことで、長兵衛の父松井某の先は佐々木氏で、江戸の諸侯邸に出入して諸事を弁じ、しかして長兵衛とはその長子であるをいう。
兼吉は店を継ぎ、長兵衛は出て、改めて四世川上宗寿(号仙渓。一八一〇~一八七五)に茶儀を学ぶこと一年。加賀清遺族の許しをえて亡き主人の「清」字をいただき、小さな道具屋「清水屋」を新たに開き、以後これを生業とする。時に長兵衛二十歳のことである。
とある日六十歳ばかりの老人が来り、「拙者は信州産のものなるが、子に先立たれ、前月には妻をも亡くし、この上独居し寂しく江戸に在っても楽しまず。老い先を故郷信州で過ごさんがため、不要の家財道具一切を売り路銀にあてるに、乃公に委せたい」という。
長兵衛時に貧しく、これを一人で買う能わず。同業の中彦と共謀して二人で買い付けることとした。
行けば家は八丁堀代官屋敷(通りの通称)の入り組んだ路地にもの寂しくあり、家内の東西(品物)を一括して見積れば、およそ値金八両ほどである。老人もこれを可とし、そこで道具一切を買取って中彦と折半したのである。
さて翌日のことである。長兵衛が引き取った道具中に、煤煙で燻され、宛ら墨のように真っ黒な古い仏龕(仏壇に同じ。筆者も、きつ刀自宅にて実際に見聞した)があり、その埃を払い、掃除せんものとその抽出しを開ければ底に何やらある。試みに出せばゴソッと落ち、開いて見れば、あに謀らん、燦然と輝く黄金十八両(現在の貨幣価値に換算して約二百万円以上)ではないか。
吃驚した長兵衛は直ぐさま返却せんものと、息せき切って老人の家に至るも、すでに老人は去ってその在処を知られず。
さらに八方手を尽くし探索すれば、ようやく小柳町(神田須田町あたり)の居酒屋に探りあて、然々の由を語り金子を差出せば、老人の暫し沈思黙考して曰く、「恐らくはこれ、亡妻の密かに不慮に備えて蔵したるものならん。然るに、われ故郷に帰すればまた生計の思いなく、昨日得たところの八両で路銀も凡て足らん。金子は天の乃公に与えたもうたもので、宜しくその方に帰すべし」と恬談としたものである。
当時、町方内で決せざる事があれば家主に謀る定法。まず旧家主にこの経緯を告げると、善処すべく家主は長兵衛と中彦を伴い、往って老人に
懇々と諭すも、固辞して肯んぜず、曰く「すでに老いたるわが身に用うる所なし」と。
ここに至って万策尽き、家主は乃ち長兵衛をして金子を受けさせしめ、長兵衛もまたこれを私せずに中彦と折半したのである。
(続)
「蘭田弄笛之図」松井楓川亭 戯画
妻鹿廉こと友石少時からの恩人奥蘭田は、厳父妻鹿友樵門下の逸材ながらいたって風雅の士で、煎茶人としても高名であった。
江戸在の夏の夕べ、茶友の楓川亭と舟に茶具を載せ、茶を喫し名月を鑑賞せんものと墨江に繰り出す。時もよし、涼風に臨み蘭田の弄笛一声。すると蘆葦に潜む蚊の群が紛然と襲いかかり、如何せん禦ぎようもなく、清風名月を後目に、いましも退却寸前の情景である。
40
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第86話
東台琴客余聞 十六 松井友石
田邊尚雄 1
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
このところ畏友薦田教授とともに芸大の院生たちと『音楽見聞録』なる、田邊尚雄(一八八三~一九八四)の音楽備忘録ような書物を講読している。すると何とそこに松井友石の名があるではないか、異境であたかも旧知に遭ったような心持ちとなり、何だか嬉しくも懐かしい。
田邊先生は物理学の先学で、かつ音楽学者としてその名を知られ、日本や西洋ばかりか東洋音楽全般にわたり造詣が深かったが、筆者一方の専門とする中国古典および琴学と和漢の律学も殊のほか精しかった。で、四十数年前のこと、当時先生はすでに八十歳を越えたご老体ながらこの後百一歳の長寿を全うされ、教壇にこそ立たれなくなったが、日夕執筆活動に勤しまれ、筆者の学生時代から先生晩年のおよそ二十年ほどは直接その警咳に触れ、何かといってはお世話になったというわけである。
この田邊老先生(以下老先生と略す)の『音楽見聞録』書き出しの日付は大正九(一九二〇)年からで、その内容は明治当時の音楽各界、雅楽から洋楽にいたる幅広い第一線の著名人たちから、老先生(当時は青年教師)がさまざまな音楽に関する話題を直接聴き取りをしたメモであるが、この聞書集は秘蔵のネタ本でもあり、いかに短文といえども、汲めども尽きせぬ泉となって、大変貴重な当時の音楽情報を提供してくれるのだ。
琴事に関する部分の本文を示せば以下の通りで、先ずは(十六)条の全文、誤字は筆者が正した。
田邊尚雄 編輯
『音楽見聞録』第壱集 十丁より
(十六)〔七絃琴の曲〕
支那の琴の中の面白き曲 (予の聞きたるもの)
「掻首問天」 漢明妃作曲
「平沙落雁」 明ノ頃ノ曲力、
「釈談章」
「搗衣」 唐潘廷堅
以上支那留学生
(琴ノ上手)羅紀氏演奏。
[七絃琴の曲〕七絃琴とは、「琴」の俗称であることはすでにお話した通りで、太古の昔から歴代の帝王やら聖賢たちが大切にしたため、後には「中華の粋」とまでいわれ、楽器というよりも「聖器」として和漢両国で尊重され、明治十六年生まれの老先生もその如くに聞きもし、また学びもしたのである。
その生前、筆者に「自分は特に琴が好きで、若いころに中国人留学生からこれを学んだ」というほどの老先生は大なる琴癖の持主で、一九七〇年の自著『中国・朝鮮音楽調査紀行』(音楽之友社刊)中、ちょうどこの裏付けとなる記載があるので、そのままに引用する。
私は明治四十年(一九〇七)七月に東大を卒業して、その翌年春から早稲田中学校の数学と物理学の教師となった。そのころ中国(清朝)は政治の大革新を行い日本へ優秀な青年多数を留学生として派遣せしめたが、国立の東大(旧帝国大学)では関係が面倒なのでこれらの多数の留学生を受け入れず、そこで彼らは一括し早稲田大学に学ぶ
ことになり、とくに清国留学生部というのを設けてその教育に当ることになり、私はその中の物理学の講義を受持つことになった。
……
(続く)
田邊尚雄小照
紫綬褒章受章の昭和30年(1957)年11月、功成り名遂げた老先生七十四歳。炯眼の裏には温情が潜む。
『音楽見聞録』第壱集(1920~)未刊稿本
ひところは洋楽の大田黒(元雄)、東洋の田邊と、その著書の多さに外野が喧しかったものだが、老先生には洋楽ものの著作も多い。
31
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第87話
東台琴客余聞 十七 松井友石
田邊尚雄 2
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
早稲田大学の清国留学生部の授業を持ってから、はからずも彼らから不思議な尊敬を受けるようになり、彼らの中の有志が私の宅に遊びにくるようになったが、その中で琴(七絃琴、今は古琴と呼ぶ)を奏する者がおり、私にいろいろ聞かせてくれた。
琴は君子が身から離さないといわれる位に中国のインテリ階級の人は
これを尊敬している楽器であるが、今(明治末期から大正時代)は中国でも、これを奏する人はきわめて稀であるという。私はこの青年から琴の奏法を学ぼうと思い、彼らの宿所を訪れることにした。
当時彼らの十名ぐらいの仲間が高田馬場の駅の近くの大きな下宿屋に居住していた。私はこの下宿屋に何回も通って琴の奏法を学んだ。『平沙落雁』などという曲を学んだのである。
私がこの琴を身につけたことは後に中国を旅行するようになっていたるところで私が琴を身につけているということで、君子として尊敬されたことは、私の中国旅行に大いにプラスとなった。しかし、この青年の琴はあまり上手ではないというので、私はぜひ中国に渡ってさらに上手な人の琴を聞きたいと思ったのである。
明治四十一(一九〇八)年の春以降、早大の「清国留学生部」に来ていた羅紀氏(青年よりも成人が多かった)を師匠にしたのであるから、田邊老先生は清末当時の中国伝を学んだということ、早大は早稲田、清人の下宿は馬場、老先生のお宅は老松町と至便である。
引き続き校註の真似事をしてみようが、現今「支那」の字を無意識にも使用すれば、騒動となりそうだが、(十六)条原文のままをお伝えするため、しばらくのご容赦を願いあげる。冒頭支那の琴の中の面白き曲(予の聞きたるもの)とは、老先生自身が直接聴いた中国の琴曲中、面白いと感じた曲をいい、当時まだ健在であった日本流の琴曲ではないことを暗に仄めかしている。
『音楽見聞録』では、通番や条目に使用する()と、話し手を示す条末の()以外、本文中にある()内は老先生自身の補語や評価で、条末の敬称の多くは「氏」に統一していて、条末に羅紀氏の弾琴を老先生が実際に聞いたことをいい、また同時に曲名と作者を聞いて記録したのである。
「掻首問天」(そうしゅもんてん)
別題を「屈子天問」、また「秋塞吟」ともいう。楚の屈原が天に問うたという伝説を典拠とする。査阜西編『存見古琴曲譜輯覧』(一九五八)では「漢王墻作」とする。墻の字は昭君で、後に明妃、明君といわれる。ゆえに誤記ではない。
「平沙落雁」(へいさらくがん)
北宋「瀟湘八景」中の同名の題をヒントに琴曲となる。情から景へと移趣する琴曲中の白眉とされ、多くの明代の琴譜集には必ず採られる。『東皐琴譜正本』(一七一一序 二〇〇一復刻)にも収まるが、ここでは当時の中国伝流である。
「釈談章」(しゃくだんしょう)
別題を「普安咒」ともいう。琴曲中の仏曲である(本連載第4話参照)。普安禅師の作と伝わり、ゆえに普安呪とされる。梵語の漢訳が琴譜に附されている。『東皐琴譜正本』にも所収される。
「搗衣」(とうい)
唐代の清商大曲中にすでに曲名としてあるが、琴曲としては現行する山東派の流れの琴譜が多い。李白の「子夜呉歌」中の「萬戸衣を搗つの声…」と、遠く戦場にある良人思慕の情は、鑑賞の手助けとなろう。唐の翰林院学士・潘廷堅、字叔聞の作とされる。
(続)
「田邊尚雄書斎」(『田邊尚雄自叙伝』より)
戦時中の落合田邊邸である。
机案に対しては古人約定の通り「左琴右書」となる。
該琴には護軫の欠落が見られ、他に敔(ぎょ)あり玄琴あり、また楽・薩摩の双琵琶、白柱には一絃琴、さらに三絃子にトンコリ、田邊考案の玲琴等々の楽器が見える。
31
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第88話
東台琴客余聞 十八 松井友石
田邊尚雄 3
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
当時、未だ東皐心越禅師の遺響である日本独自の琴派・心越流がなお健在であったが、以上が明治四十一(一九〇八)年田邊老先生自身が直接聞き、面白き曲と思った琴曲のメモであり、こうした『音楽見聞録』一巻の(十六条により、以下のようなおおよその経緯が判明する。
四十数年以前のこと、老先生は筆者に向かい、「自分は特に琴が好きで、若いころに中国人留学生からこれを学んだ」というほどの大なる琴癖の持主、かつ日常にも君子人たりたいと心がけた生粋の明治のインテリである。
物理学者また音楽学者として自立する以前から琴を意識し、生前坂田に清国留学生で確か四川人から「平沙落雁」まで学んだといい、何度か坂田の弾琴を聴いた折には、後記する北京の想い出などが胸中去来したことと思われるが、一九八四年三月五日の田邊の逝去に伴い、坂田が田邊の幅広い音楽分野の中でも重要な位置を占めた「中国古典音楽」の薫陶をうけた門弟を代表して、告別式と東洋音楽学会葬で「漁樵問答」と、田邊の若き日に学んだ想い出の「平沙落雁」を献楽させていただいた。
これらと、明治四十一年の春以降、早大の「清国留学生部」の講師を勤めていた田邊が、四川の留学生羅紀氏(成人が多かった)を師とし、清末当時の中国伝を学んだことと、該(十六)条が符合することとなる。
田邊の著『中国・朝鮮音楽調査紀行』(一九七〇年音楽之友社刊)に、ちょうどこれを裏付けする記載があるので引用してみよう。
私は明治四十年(一九〇七)七月に東大を卒業して、その翌年春から早稲田中学校の数学と物理学の教師となった。
そのころ中国(清朝)は政治の大革新を行い日本へ優秀な青年多数を留学生として派遣せしめたが、国立の東大(旧帝国大学)では関係が面倒なのでこれらの多数の留学生を受け入れず、そこで彼らは一括して早稲田大学に学ぶことになり、とくに清国留学生部というのを設けてその教育に当ることになり、私はその中の物理学の講義を受持つことになった。 …略…
早稲田大学の清国留学生部の授業を持ってから、はからずも彼らから不思議な尊敬を受けるようになり、彼らの中の有志が私の宅に遊びにくるようになったが、その中で琴(七絃琴、今は古琴と呼ぶ)を奏する者がおり、私にいろいろ聞かせてくれた。
琴は君子が身から放(離)さないといわれる位に中国のインテリ階級の人はこれを尊敬している楽器であるが、今(明治末期から大正時代)は中国でも、これを奏する人はきわめて稀であるという。私はこの青年から琴の奏法を学ぼうと思い、彼らの宿所を訪れることにした。
当時彼らの十名ぐらいの仲間が高田馬場の駅の近くの大きな下宿屋に居住していた。
私はこの下宿屋に何回も通って琴の奏法を学んだ。『平沙落雁』などという曲を学んだのである。
私がこの琴を身につけたことは後に中国を旅行するようになっていたるところで私が琴を身につけているということで、君子として尊敬されたことは、私の中国旅行に大いにプラスとなった。しかし、この青年の琴はあまり上手ではないというので、私はぜひ中国に渡ってさらに上手な人の琴を聞きたいと思ったのである。 p220~
ここに注目すべきは、「琴はすなわち中国の君子の楽器である」といい、それを馬場の下宿屋に何回も通い、日本のインテリである自分はその中国本場の琴を学んだことにより、己がその趣きを知る君子人として形成され、なおかつ、後日それが中国各地のインテリたちとの交遊の場において実際に通用し、証明されたと強調することである。
ここに田邊の自意識中に琴を至上化する「琴癖」が形成されたことがみえ、文中の中国を人生という言葉に置き換えれば、田邊は「自分は中国の琴を学んだ日本の君子人である」と、最晩年にいたるまでそのように自負していたことが知られよう。
ともあれ、こうした経緯から明治四十一(一九〇八)年の春以降、清国留学生蘿紀氏から琴を学び、実際に「平沙落雁」まで学んだという、これらは前記一応の証左をえたが、学ぶについては自用の琴がなければならず、おそらくはこの初学時には田邊は琴をもたず、その際は羅氏の琴一張を交代使用したことで、ぜひとも自用の琴を早急にと欲したはずであり、これが「見聞録」(十七)条への伏線となって、〔七絃琴の売価〕などへと繋がることになるが、そこに拙稿現題の松井友石の名が牽かれ、その辱知富田渓蓮(豊春)が連なることを加味すれば、同じ琴事ながら、また前十六条とは少しく内容に差があり、さらには該条によって日本の琴派心越流に係る事柄など、さまざまな経緯が判明することになろうが、先ずはその原文である。
(十七)〔七絃琴の売価〕
日本橋の漢学者松井氏所蔵の琴の内、文政十二年越後の百一居士(素人の手製)の品は価七円にして譲りてもよろしき由申越あり。
又京橋大鋸町呦々堂小池氏の売品中に価弐拾参円の唐琴あり。朱漆塗、薄霞の銘あり。仲士珍蔵、凡そ三百年以前のものなり。音極めて宜し。 〔一絃琴家、富田豊春氏談〕
「琴癖」とは、琴(きん、きんのこと、俗称七絃琴。現代中国語では古琴)をこよなく愛好する意の語で、口語や俗語に詳しい中国文学者柴田天馬(一八七二~一九六三)はこれを「ことずき」と訳し、また、琴癖をもった著名人物の具体例としては碧眼の文人と異名をとったヴァン・グーリック(一九一〇~一九六七)の名を挙げられるが、田邊とほぼ同時代を生きた内田百閒(一八八九~一九七一)が、宮城道雄(一八九四~一九五六)に就いて箏を嗜んだことからくる「箏好き」(百閒著『無絃琴』参照)とは好対照で、自ずか別義で似て非なるものがある。この琴癖の語中に明治知識人のもつ中華思想至上主義の内在することを深く心に留めねばならない。しかして該(十七)条は、幕末明治大正の大先輩で著名な音曲家・富田豊春こと渓蓮からの聞き書きで、田邊との年齢差は三十二歳である。
(続)
「田邊尚雄小照」(『田邊尚雄自叙伝』)より
ちょうど清国留学生から琴を学んだころの田邊青年教師である。その風貌には明治知識人の気概が横溢している。
「故田邊尚雄先生東洋音楽学会葬」式次第
1984年3月23日於信濃町・千日谷会堂
故田邉尚雄先生東洋音楽学会葬次第
一、奏楽 吉備「菅搔」(レコード)
一、参列者着席 奏楽 小野雅楽会
一、御遺骨安置 奏楽 同
一、開式の辞
一、奏楽 御神楽「阿知女作法」(レコード)
一、黙祷
一、献楽 三曲「残月」 正派邦楽会
琵琶「先帝入水」(壇の浦より) 鶴田錦史
弾琴「平沙落雁」 坂田進一
一、故人の演奏と声
新日本音楽「薤露調」(レコード)
最後の御挨拶(白寿祝賀会より)
一、式辞 葬儀委員長 吉川英史
一、弔辞 文化庁長官 鈴木勲
日本放送協会会長 川原正人
重要無形文化財保持者 宮城喜代子
門弟代表 岸辺成雄
一、弔電
一、献花 奏楽 小野雅楽会
葬儀委員長 吉川英史
喪主 田邊秀雄・路子
文化庁長官 鈴木勲
日本放送協会会長 川原正人
重要無形文化財保持者 宮城喜代子
葬儀副委員長 岸辺成雄
葬儀副委員長 金田一春彦
親族
一、葬儀委員代表挨拶 金田一春彦
一、葬儀終了の辞
一、告別式 献花
奏楽 雅楽「盤涉調白柱」 小野雅楽会
沖縄音楽「十七八節」(レコード)
京極流箏曲「紅梅」(レコード)
韓国宗廟祭礼「熙文」(レコード)
新内「新内流し」 新内協会
雅楽「盤渉調千秋楽」 小野雅楽会
一、喪主挨拶
三、御遺骨お見送り
29
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第89話
東台琴客余聞 十九 松井友石
田邊尚雄 4
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
(十七)条文中の大鋸町は「おがちょう」と読み、その辺りから京橋一帯にかけては、現在もギャラリーや名だたる骨董舗が檐を連ね、中にも小池呦々堂とは当時一流の目利きで、その交遊に友石の岳父松井楓川や富田渓蓮などがあり、看板も『詩経』の「鹿鳴」から採る見識で、鹿が「ミュウミュウ」と鳴くように嘉賓が集う、すなわち文人がそのように集い、佳品を漁り求めることにかけていた。
前号までの裏付けを田邊自身の著書中にさらに補強すれば、あに計らん、『田邊尚雄自叙伝(大正・昭和編)』(一九八二邦楽社)中、以下の記述では多少ニュアンスが異なる。
支那留学生部 …略…
ところが音響学の説明に当り、音階、音律の説明に、洋楽と比較して中国の三分損益から五声十二律の説明、漢の京房の候気の法から六十律、銭楽之の三百六十律に及んだ。
これは中国人でも殆ど知らぬこと(当時私の専門研究分野であった)で、初めて自国の音律について知った(当時中国人は自国の音楽を排して洋楽のみに夢中になっていた)ので驚きは甚だしく、従って私に対する尊敬は異常なもので、急に私の家を訪れる者が多くなった。その中に馬藻裕という立派な上品な青年がいた。日本語がよくできないので話は多く筆談であったが、帰国する前に中国音律の研究書である清の陳澧の著で『声律通考』という書を寄贈してくれた。これは私の研究に大いに役立った。
…略…
このように私は中国の留学生と懇意になる機会を得たが、大正に入って清朝が倒れて国民政府になってからも、留学生とは往復していた。彼らの多くは高田馬場の一宿舎に集まっていたが、その中で琴(古琴)を弾く者がいて、私は屢々この宿舎を訪れて琴を聞かせてもらい、その説明も聞いた。「平沙落雁」その他の名曲もよく聞いた。
かように琴についての知識をよく身につけていたので、大正十二年に中国に旅行したときも、私が琴をよく知っているので上流社会から大いに歓迎された。(中国では古来、琴は君子の身につけるものとなっている)。 P61
田邊は克明に日常の出来事を日記につけていて、眼の良さを坂田に示すために、「極小な細字も、眼鏡なしで読めるし、書けるのです」と、療養所の病室において図らずも日記を一瞬間見せられる機会があったことを覚えている。そのため、田邊は往事の事項、また日時や固有名称など、具体的かつ詳細に引用することが容易かったのだが、多くの資料は自宅書斎にあり、編集者の外部での校正とでは齟齬が生じやすく、誤字や誤記の訂正もままならないことが多かったようである。
百年前に田邊が聴いたこの四曲は現在でも重要なレパートリーとして遣り、留学生羅氏の十八番であったことは想像に難くないが、田邊は少なくも何度か鑑賞しているはずで、「もっと(別な名曲をも)聴きたい」、さらには田邊が「中国へ行きたい」と願うようになる重要な動機となって次項引用文と結びつくこととなるのだが、『田邊尚雄自叙伝(明治編)』(一九八一邦楽社)では、ただ一人「清国留学生、藍経惟君」の写真が付され、その裏書きには藍君自筆で、
謹贈、田邊先生足下、支那四川綏定府渠県、藍経惟、年二十六歳、己酉年八月中旬、 P60
とあり、干支もちょうど明治四十二(一九〇九)年にあたるので、前記羅氏とこの藍君と同一人物では、とは拙速には断定し難いものの、今となっては直に田邊に確かめる術もない。あるいは羅氏も藍氏も同じく四川同郷の出身であったかも知れない。
早大の清国留学生部はその翌年の明治四十三(一九一〇)年には廃止されたが、田邊の言葉によれば、「大正に入って清朝が倒れて国民政府になってからも、留学生とは往復していた。」とありさらなる検証を要す。蛇足ながら、藍経惟は帰国後に郷土の教育のために尽力し、四川綏定府渠県、現在の四川省達州市渠県にある、もと渠県学堂(現四川省重点中学・渠県中学)の創立者としていまなおその地で尊敬されているという人物である。
(続)
「藍経惟小照」
26
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第90話
東台琴客余聞 二十 松井友石
田邊尚雄 5
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
だが、田邊はいったんは本心であったろう(琴ノ上手)の前言を翻し、「この青年の琴はあまり上手ではないというので、」と、一つには羅氏本人の謙譲の語を真にうけ、「私はぜひ中国に渡ってさらに上手な人の琴を聞きたいと思ったのである。」と思い、またひとつには、田邊の学生中、東大物理学教室の中村清二(一八六九~一九六〇。後に教授)の「日本支那楽律考」の論文を読み、その中村から『律呂新書』および『律原発揮』を貸与され、和漢の律学に興味を持ち始めたところへ、さらに早大の清国留学生馬裕藻(一八七八~一九四五。後の北京大学文学部長)が一年間の留学を終えるに際し、田邊に『声律通考』を贈呈したこととも重なり、
「日本支那楽律考」中村清二
『律呂新書』宋・蔡元定撰
『律原発揮』日本・中根元圭著
『声律通考』清・陳禮撰
などの律学書の影響で、音楽を学ぶ音響物理学者として研究を深めよう
との二つめの理由となり、田邊は「さらにいろいろ多くの律書を入手したいと思い、中国へぜひ行きたいと心に誓うようになった。」のである。
中華民国へ
こうした願いから数えてちょうど十五年後の大正十二(一九二三)年の四月、念願かなって中国本土で琴の名人の演奏を聞くことができ、かつ大量の古楽書をも購入することができることになる。
以下はその証左たる『中国・朝鮮音楽調査紀行』からの引用である。
四月十六日
夕刻東京発、十八日朝長崎着、十九日朝九時ころ揚子江口、正午上海郵船埠頭着。 …略…
[五月十六日]
午前に北京唯一の琴の名手馮汝玖大人が来宅され、 …略…
[五月十七日]
宗人府の中西音楽会へ行く。
…略… 別室で李士奎氏の琴曲『長門怨』を聞き、 …略…
[五月十八日]
…略… 夕刻、ともに前門外の馮汝玖大人邸の招宴に行く。馮汝玖大人は蒙蔵院僉(せん)事(蒙古とチベットの知事)という重職にあったが、今は老いて閑職にある。富豪でかつ立派な学者である。音楽を好み古楽を研究し、著書も多い。
ことに古琴をよくする。食前に私の持参した雅楽のレコードをやり、後に馮大人自作の古箏などを拝見し、それから馮大人の書斎で、馮大人は琴をとって『秋塞吟』を奏する。この曲は黄鐘均商調である。
やがて宴が始まる。 …略…
私はこの夜の楽しさを賀して「嘉辰令月観無極、万歳千秋楽未央」の朗詠をうたってこれに返礼した。馮大人は再び琴をとって『良宵引』の曲を弾じた。このようにして互いに律を論じ、楽を談じて夜更けるを知らなかった。
別れに臨んで馮大人の曰く、「伯牙ありとも鍾子期無くんば、何ぞ楽をなさんや。今日の中国は俗楽に耽り、高尚なる君子の楽たる琴に耳を貸す者はほとんどいない。今日君に遇うて初めて鍾子期を得たが、われ伯牙の才に及ばざるを恥ず」と。私はこれに答えて「私は過日漢陽において弾琴台を訪い伯牙の高徳を慕うていたが、今日大人に遇うて伯牙に接するが如くに思う。しかし我に鍾子期の明が無いのを憾みとする」と。傍らにあり歎じて曰く「否々、今日われわれはここに伯牙と鍾子期が相会するを見たり。善哉善哉」と。
とにかくわれわれは、互いに高雅な音楽のために力を合せて、易経にいわゆる「作楽崇徳」(楽を作して徳を崇める)のために努力をなそうと相約して、馮大人邸を出たのは夜半十二時であった。
(続)
「作楽崇徳」田邊尚雄書1969年
「作楽崇徳」とは、『易経』「坤下震上・雷地豫」を出典とする、「先王もって楽を作(つく)り徳を崇(たっと)び、殷(さか)んにこれを上帝に薦め、もって祖考を配す」なる成語だが、「楽を作(な)し(学び、演奏する)、徳を(たか)る」と転読することが多く、田邊はこれを日常座右の銘とし、人に乞われることがあれば好んでこれを墨書、かくいう筆者の苦学生のころ揮毫してくださった。
ちなみに田邊の雅号は「天山」である。ともあれ、本文中のこうした馮水との文人的応酬で、田邊は日本の君子人たる素志の一つを具現化できたこ
ことになろうか。
作樂崇德
昭和四十四年四月二十五日
坂田進一君
田邊尚雄
31
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第91話
東台琴客余聞 二十一 松井友石
田邊尚雄 6
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
それ以来しばらく馮大人とはたえず相文通を続け、私が古琴を所持していることを知って、ときどき琴の絃糸などを贈って来られた。
…略…
五月二十一日朝、奉天発釜山行の満鉄列車に乗り、そのまま朝鮮を通過して釜山に着いた。 …略…
私のトランクは中国の古書で一ぱいで、別に問題はなく、東京へ帰ったのは五月二十五日であった。 (同p225~)
馮水(?~一九四二後?)は原名を汝玖、『歴代琴人伝』(一九六五年刊油印本、中央音楽学院中国音楽研究所)では汝玠に作る。原貫は浙江省桐郷の医学名家の出で、字を若海、また叔瑩といい、楽中最も琴を善くし当時の退役高官である。
田邊が「著書も多い」というように、馮水は医書の他に『変徽定位考』、『琴均等調絃』、『白石道人琴曲古怨釈』などのいわゆる「馮氏楽書四種」を含む名著をものしたが、とくに後(次項「新中国へ」)に田邊が中国で聴いて大感激した琴曲「広陵散」の原譜、その一種を同氏が模刻した『広陵散譜』は近代中国の名だたる琴家がこぞって求め、これによって六朝嵆康伝説の「広陵散」が打譜され現代に蘇ったという名譜でもある。
この北京では、日本公使館参事官の有田八郎(一八八四~一九六五。後の貴族院および衆議院両議員)の接待のもとにあり、その太い人脈を通して多才な中国著名人と会見することができたのだが、田邊の二つめの素志である楽書を大量に購入するという目的を果たしたことはいうまでもない。
この夜宴で田邊が朗詠した「嘉辰令月観無極、万歳千秋楽未央」は、『和漢朗詠集』(一〇一八ころ成書)に所収される朗詠歌としては最もポピュラーなものである。
田邊の記録によれば、田邊と馮水こと汝玖はこの後も文通を続け、田邊が琴を所蔵することを知って喜んだ馮大人からは琴絲などが送られたようであるが、この絲が田邊の所蔵した琴に実用され張られたかは、今後の遺愛琴実見の機会に検証しよう。ただ、遺憾ながらもこの会見後に日中戦は次第に激しさを増し、馮水ほどのもと大官の生存でさえ一九四二年まではたどれるものの、その没年すら不詳となってしまった。
新中国へ
次なる記録は、戦後に田邊が中国旅行した際のもので、(十六)条に関連する箇所を、同じく『中国・朝鮮音楽調査行』中から引用する。
昭和三十一(一九五六)年の九月、田邊は戦後初の「日本文化人中国訪問団」団長として中国旅行に参加する。田邊自身、「つまり観光旅行にすぎない、したがって音楽調査のための旅行ではないから…」と断りつつ、『中国・朝鮮音楽調査行』中へ所収されたものである。
その当時は中国と直接国交がないため、香港経由で広州から入国した。この旅行中は終始国賓待遇の特別なものであり、北京滞在中の十月八日の午後から、民族音楽研究所と文芸家連合会共催による「中国古典音楽「演奏会」が開催されて大歓迎された。席上、琴に関する演目の記述を挙げれば以下のようである。
(続)
『広陵散譜』馮水編1927年刊
廣陵散譜
慢商調
廣陵散
開指
『中国音楽史』田邊尚雄著 陳泉中訳
田邊の多くの著作中、唯一日本での「著作一覧」に漏れがちな『中国音楽史』(1937年上海商務印書館初版、陳泉中訳)があり、その理由は却って日本訳がないためだが、書中、ことに琴の部分は重要視される。
1932年1月の上海事変で日本軍により爆撃破壊された市内の商務印書館である。しかし、館主張菊生(1867~1959。名は元済)の英断により幾多の猛反対を押し切り、仇国日本人の著作でありながら伊東忠太の『中国建築史』同様その真価を認められ、該書は「中国文化史叢書」40冊中の第二輯として収められ、鄭覲文『中国音楽史』(1929年刊)に続く古典的名著として、漢字文化圏でいまなお引用されることを忘れてはならない。
19
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第92話
喫茶と音楽 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
閑話休題。
しばし東台を離れ山下へ、休憩すべく池之端から湯島方面へ戻り、以下例のごとく筆者近場での異聞である。必定雑朴な内容となろうが、如何せん諸事混載のため、はなはだ恐縮ながら時系列など多少の端折りをお許し願いたい。ただ、ここにも続稿中の松井友石と岳父楓川亭釣古翁が見え隠れすることとはあいなる。
筆者の喫茶癖は煎茶を含む日本茶に始まり、紅茶と中国茶各種、これに多少の点茶と珈琲などが加わるが、概して最後の珈琲を飲む機会が一等少ないのは、かなり主張性の強いその薫りが苦手なためで、よほどでない限り珈琲を飲むことは少ない。
湯島天神男坂下の陋巷に弊小研究所(体のいい倉庫)はあり、町内の通り一筋隔てた昌平通りに面して葡萄パンと珈琲兼売のMがある。この数年、この店の階下で時折筆者の小さなライブを開いている。
何の変哲もない狭い店内(顧客S氏の設計)は、それでもスペイン風の鱗壁があしらわれ、筆者はこれをあたかもウィーン街角のカフェハウスに見立て、バックに流れるジャズを聞くともなしに、ガラス越しに映る人の波、隣席との他愛ない雑談と、ある意味で日本的な珈琲を飲むひと時を一服の清涼剤として、浮世を忘れもし、時には直視したりもする。
いまはない、畏友故林功幸氏の神楽坂下「パウワウ」は珈琲通の間でも名高い店で、筆者はそこでもしばしばシュランメル(本連載第12話)演奏の機会を提供され、看板後には林氏とビールやワインなどで夜が更けるまで楽しんだものだ。
シュランメルはホイリゲと不可分の至福の音楽とされ、夜のワインとは絶妙の関係にある。その反面、昼、すなわち午前や午後どちらかの一刻大抵の市民が過ごすカフェハウスで、ホイップした生クリームをいれヴィナーカフェー(実はウィーンにはなく、エスプレッソに生クリームをいれたものが近い)とも相性がよく、事実、ホイリゲやカフェハウスで聴くシュランメルは、衰えたりといえどもウィーン下街の国民的伝統音楽として今もって健在である。
改天、天神下からチャリで黒門小学校を過(よぎ)りものの二分、もと御成街道の中央通りを右折すると、そこにこジャレたS電気のビルがあり、片隅に「日本最初の喫茶店[可否茶館]跡地」との標識と簡単な説明板がある。
明治二十一(一八八八)年四月十三日の読売新聞社会部長石橋思案(一八六七~一九二七)のものした新聞広告文に、
「遠からん者は鐵道馬車に乗って来たまへ、近くは鳥渡寄って一杯を喫したまへ、抑下谷西黒門町二番地(警察署)隣へ新築せしは、可否茶館と云ツバ、廣く歐米の華麗に我國の優美を加減し、此處に商ふ珈琲の美味なる、思はず腮を置き忘れん事疑ひ無し、館中別に文房室更衣室あるは、内外の遊戯場を整へ、マツタ内外の新聞雜誌縦覧勝手次第にて、其價廉なる只よりも安し、咲き揃ふ花は上野か浅草へ、歩を運はせらる。紳士貴女、幸に來臨忝ふして、當館の可否を品評し給へかしと、館主に代りて鶯里の思案外史敬つて白す、定價カヒー一椀金一錢半、同牛乳入金貳錢」 (筆者句読)
とあり、以下因果は巡る。
可否茶館の創業者鄭永慶(一八五九~一八九五)は、代々長崎の唐通事(とうつうじ)(中国方言の通訳と諸役を兼ねた世襲の役人で、大小通事を核として職分化された帰化明人の家系)の家系に生まれ、同じく唐通事の鄭家に養われた。養父鄭永寧(一八二九~一八九七)は、小通事過人役から維新後に清国弁理公使を勤め、また第一級の資料『訳詞統譜』の跋文をものしてその名を遺す名士で、明治初めの姓氏改正にあたり、鄭永寧は改姓を時の外務卿沢宣嘉に諮ったところ、「足下本来ノ鄭コソ無類好カラメ」と諭され、爾来、鄭姓で通したという気骨漢。そんな鄭家二千坪の大邸宅跡の一郭が、いまのS電気のビルとなる。
広告文を起草した石橋思案は雨香、文山とも号し、通称を助三郎といい、奇しくも鄭永慶と同じく長崎を出自としたため、郷里の思案橋(明治期石造となる)に因み、「石橋を叩いて渡る」との諧謔の意を込めて号としたほどの人であるが、奇しくもこれまた代々オランダ通詞の家系に育った人である。
鄭永慶は養父の任地北京に育ち、明治七(一八七四)年ころ長兄永昌(次男とも。後の天津総領事)とともに米国のエール大学に学んだが、病のため卒業をまたずに単身帰国。米国留学仲間の駒井重格(後に高等商業、現一橋大校長)が校長となった岡山中学師範(もとの池田学校。変則)の教頭として請われ赴任した。
たまたま生徒に倉敷の人で慶応末年生まれの秋山定輔(一八六八~一九五〇)があり、その困苦を見かねて岡山の永慶宅に引き取り寄宿させたが、ほどなく駒井も永慶も東京に戻って大蔵省に入ることとなり、永慶の勧めで秋山も同行。下谷(上野)西黒門町の鄭家の学僕となり、苦学して大学予備門に通い、紆余曲折の後、帝大法科で石橋思案(後に文科)と学年違いの同窓となるのだが、これはさておき、ために秋山は永慶をその生涯中只一人の師また先生として仰ぎ慕い、成人の後には刎頸(ふんけい)の友として交わったのだ。さらに珈琲が媒(なかだち)となり、その同郷と学友のため、可否の広告を思案が草すのは後のこととなる。
中・仏・米語に長けた永慶は、大蔵省では主に仏文と仏語の件案を担当したが、しばらくするうち駒井らに惜しまれつつもこれを辞してしまう。在職しても学位がなく官界では頭角を顕わせぬ理由からであった。東京で永慶は結婚し、男子が生まれるも夫人が肺を長患いし、永慶必死の看病のもと没してしまう。
「乳飲児を抱くて男の手一つ、見るに堪へない気の毒な有様だった。」と秋山が述懐するほどであったが、亡妻実家のたっての願いでその令妹を後添いに迎えると、幸い賢夫人で内助の功あり、さらに男子二人に恵まれて周囲も喜んだのもつかのま、またしても肺病で没し、なさぬ仲の養父永寧邸は子だくさん、しかも当時その家を本妻同様に実質上切り盛りしたのは、吉原お職あがりの「お勝さん」なる人で、いきおい永慶一家は孤立せざるをえなかった。
さりとてそのまま商人とは成りきれずいたところ、たまたま鄭家邸は火災に遭遇し焼失したため、すでに家を出て池之端に下宿していた秋山が跡地での学校経営を勧めたが、永慶は想い出にある中国の茶館と米国のコーヒーショップを折衷し、かつ幾ばくかのインテリジェンスと娯楽性をかねた喫茶店を構想し、その跡地に苦心して開店したのだ。
規模は「二百坪の敷地に五間と八間の二階建ての木造洋館であった。」で、設備は前記思案のキャッチコピーにある通りである。
しかしいかにも時期尚早であった。いまだ鹿鳴館全盛のころである。一般客を相手に「きつねうどん」が一銭のところ、秋山ら帝大生の熱心な勧誘運動のなか、珈琲の可否を暗に問うべく可否茶館と名付けたまではよかったが、世人はこの不思議な飲み物一杯に一銭五厘を出せまいとばかり、たちまち経営不振に陥り、永慶はその穴埋めをせんものと素人ながら相場に手を出し失敗。いったんは秋山の忠告を容れて止めるとは誓ったものの、欠損を填めようとまたぞろ大損をしてしまうのである。 (続)
「在りし日のパウワウ」石井瑞穂画
たまたま入稿最終日、友人のご夫人が閉店後にスケッチしたものがあるときき、観ればイメージピッタリ、急遽お願いして掲載許可をえた。
2004.5-17 パウワウ mizuho.l
「鄭永慶と秋山定輔」
『秋山定輔』桜田倶楽部編より
右が秋山定輔、中央が永慶。
秋山は帝大卒業後に大蔵省会計検査院の高等官試補となったが、慈母幾野の急逝を機にこれを一年ほどで辞して野に下り、藩閥制打倒を標語に掲げ、26歳で「二六新報」を創刊。後に35歳で衆議院議員となる。ちなみに「二六」とは「二六時中」一日中の意とある。
27
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第93話
喫茶と音楽 中
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
永慶と秋山定輔の師弟愛から発した友情は、すでに刎頸の友の交わりと化し、「可否茶館」を軸にさらに深まる。もと師で恩人でもある永慶に対する秋山の無償の愛は、これを知る者の胸を打たずにはおかぬが、なおその顛末を完結させねばならぬ。中国茶館のイメージを珈琲ハウスに重ね、喫茶の習慣を通し多少の文化的な空間を東京に提供せんと開店したのは明治二十一(一八八八)年四月三日のこと。しかし赤字続きで同二十四(一八九一)年には早くも倒産し、万策尽きて借金に借金を重ね、やむなく永慶は養家黒門町二千坪の地所までも担保にしてしまう。しかもその土地は自分名義ではないのだ。義理ある養家と家族を裏切り、一時はピストル自殺までも考えたが、様子のおかしさに気付いた秋山に諄々と諭されようやく止まる。
秋山と相談の結果、永慶古馴染みの米国に渡り再起を図ることとし、ついては前住のサンフランシスコやエール大学のあるニューヘブンでは顔が知れていると、行先をシアトルとし、秋山が高等官三月分の月給を担保に金貸しから百五十円を借り、ひとまずはバンクーバーまでの三等切符を五十円で購入したものの、さてここからが難儀で、住所も戸籍もなければ正規の旅券を申請できず、偽名を西村鶴吉として国禁を犯して旅券なしで密航することとした。
横浜で一泊、秋山と別れを惜しみつつ出航しようとの矢先、臨検で旅券の提示を求められて危うく逃れ、永慶一人はその足で神戸に逃れた。神戸にはそのころ出稼ぎ人の旅券を扱う店があり、その手にかかればかなり曖昧な人でも米国へ渡航できるとかねて秋山は聞いていたのである。高額な切符は目減りし払戻しされたものの、この横浜からの密航計画の一齣は失敗のうちに終った。
一方、永慶の家出した後の鄭家の騒ぎといったら一通りでない。東京へ戻った秋山は、「事情を知るであろう、永慶と共謀して金を使った」と詰問され、永慶を引留めんがため居所を教えろと責められたが、「先生はすでに横浜から発って航海中です」とシラを切り、さらに永慶にかわり改めて秋山が逐一事情を打ち明け、「先生も前非を悔い、前途に非常な決心をして米国へ渡った。罪は罪とし、先生の現在の心情を諒解してやっていただきたい」と懇願したため、事件の波紋は甚大ながら、さすがもと唐通事一族のこと、終には永慶の運命と境遇とに却って同情を寄せたという。明治二十五(一八二九)年末のことである。
それからひと月ほど後、永慶から神戸で仮名西村鶴吉の偽造旅券を入手、ようやくバンクーバー行きに乗船出航したとの手紙と電報があった。その船が一日横浜に碇泊すると秋山が迎えに出れば、坊主頭に髭を落とし、青いボロの垢染みた菜っ葉服姿にやつした永慶のあまりの変貌ぶりである。秋山は胸潰れる思いでその場に抱擁し、思い切り泣き叫びたい心持ちであったと。明日の出航まで海岸近くの宿でのその後の物語に、両者一睡もせずに語り明かす。こうして別れてからしばらくは音沙汰もなく、またこちらから尋ねる術もなくいるうち、ある日シアトルから安着と居所の簡単な通知に、皿洗いをしていてとても疲れがちとあり、ようやく安堵して秋山はこれに長い返信を認めたが、さらにその後一年ほどしてシアトルから帰国した古谷某という人が秋山を訪ね、永慶の死の消息をもたらした。あいにく秋山は旅行中であったが、これを知るにおよび、愕然として天と神とを恨むが、やがて考え直し「人の精神や功徳は、死とともに滅びることはなく、必ずや輪廻となって永慶三人の遺子に幸福をもたらすであろう」と、念じかつ信じたのである。
以上、本邦喫茶店の嚆矢が唐通事家系の鄭永慶の住居下谷西黒門町(現松坂屋の斜め前)に開いた可否茶館で、その店内における音楽活動の記録こそ遺されていないが、おそらくは永慶の念頭には少年期に北京の茶館で聞いたさまざまな音曲や、いまだ挫折を知らぬ米国での楽しい学生時代のカフェーで聞いた音楽が常にあったであろうことは否めない。
その少しき以前、幕府の医官曽谷(そだに)長春(一八〇六~一八四七)、諱を俊乂(しゅんがい)通称長春があり、彼も長崎を通して音楽と出会った人となる。
長春は文政九(一八二六)年、父曽谷長順の家督を継ぎ天保五年には医学館の世話役手伝兼寄合医師取締となるが、長春はこれに先立ち、長崎における医術修行のかたわら唐館にて清人金琴江に清楽を学び、江戸は柳原の幕府「医学館」まぢかの拝領屋敷に帰り、隣町下谷黒門町の絵師平井均卿の二人の娘、平井連山(一七九八~一八八六)と梅園に長崎仕込みの清楽を教えたのである。
長春の清楽同門に奥州の人遠山荷塘(一七九五~一八三一)があり、荷塘は長崎崇福寺で黄檗僧として修行したが、同じく金琴江から清楽を学び、還俗して遠山荷塘と名乗り長春と共に二人して江戸に戻り、荷塘は大工町に住し唐音と清楽を教授したことで、この両者をして江戸に清楽流行の苗圃(びょうほ)が整ったわけだが、惜しくも長春は連山を遺し四十一歳で、遠山荷塘も三十七歳でと相ついで早逝してしまう。
時は清楽の定着期の時代と重なり、そこで計らずも長春の高弟であった連山に焦点があたることとなる。
連山とはその号、俗名はれんである。幼きより書画管絃の道を好み、書を篠崎小竹、画を父に学んで善くし、妹梅園と並び「江戸の女画仙」と称された天才で、画を父均卿に、長唄、清元、富本、箏曲などさまざまな音曲を学び、天保年間には長春の門で清楽を学ぶが、師の長春に長ずること八歳の愛弟子れんは、音楽的才能と経験は医官の長春より数等優れていて、師から一を聞き十を悟るといった天才であったため、師の長春が早世した後は、江戸第一の清楽教授として喧伝され、音楽書画をもって千代田城西の丸、薩摩、土佐、芸州などの各藩に出入りした。
安政元(一八五四)年、二十五歳年下の妹梅園(一八二三~一八九八)とともに大阪の内平野町に移り清・邦楽の普及に尽くした結果、門弟数百千を得て、さらに妹梅園と計り、これより姉妹東西に並立し、もって斯道を大いに奨励せんと、明治十二(一八七九)年四月梅園は東帰した。
こうしたわが国で清楽と呼称されるジャンルは、幕末に主として清朝の南方の俗曲が長崎に伝わったもので、洋楽の未だ普及せない一時は邦楽と折半するまでに隆盛となったのだが、ことに唐もの数奇の文人が好んだ煎茶趣味と相俟ち、煎茶席中の音楽席では唐渡りの音楽として、日本人の中国趣味にはたまらないほどピッタリと嵌まったものである。その上、唐渡りそのままの派手な極彩色でなく、ある程度日本的な侘び寂びによって贅肉を削ぎ落とされて品よく洗練されつつあった日本の煎茶席中にあり、また一入格別な雰囲気をもたらすものとして、もはや煎茶席には欠くべからざる音楽とされていたのである。
その後、惜しくも日清の役を機に清楽はようやく衰退するも、大正から昭和の初期までは、まだまだ煎茶席中の清楽には根強い人気があった。
(続)
「鄭永慶墓」 谷中霊園
鄭永慶の原墓は米国シアトルにあり、後に遺族の手で日本に分葬された。
その墓碑銘により、永慶は明治28(1895)年7月17日にワシントン州シアトルにて37歳、前妻の姉菅寿(俗名とし。墓碑銘には夢梅院月窓清節大姉とある)は明治19年3月13日に22歳、また、後添えの妹菅徳(とく)は同23年の8月3日、同じく22歳で逝ったことが解った。
「秋山定輔小照」(1868~1950)
鄭永慶に助けられた秋山少年は、苦学の後帝大を卒え高等官吏となるも、恩人であり師かつ最愛の友人の永慶は米国へ旅立ち、秋山の手の届かぬ地で先立った。失意の秋山は「二六新報」発行に邁進し、日本における孫文の良き理解者、さらに衆議院議員としても活躍し、その波乱の生涯を終えた。
「平井連山小照」
清楽名家平井連山の若きころ、さすがお江戸は下谷黒門町育ちの粋な容姿である。
美人平井姉妹の音楽や書画を人々は先を争うように求めたが、母娘ほど歳の離れた後の長原梅園は、連山女史の先逝した後の明治25(1892)年3月、読売新聞紙上「女流名家投票」で見事日本音楽家の部第一位の栄冠に輝き、姉に続く日本第一の女流清楽家となった。
連山・梅園姉妹共作「蕙菊扇面」
21
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第94話
喫茶と音楽 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
今でこそ、われわれはさも当然のように日常喫茶の習慣をもつようになったが、もともとは晩唐留学僧が宋初の茶種を帰国に際して持ち帰り、これを禅余の清涼剤また薬餌として用いていた。
禅語「喫茶去」の転用はさておき、爾来、各界さまざまな茶葉とその煎法が工夫されたが、それらは概ね上つ方の世界でのことであり、その上茶葉は高価なもので、濁酒を除いては一般庶民にはただの白湯(さゆ)などがあればまだしもであった。
戦国期を経て千利休らにより日本式の点茶式が確立して武家社会や富裕商人層に蔓延し、はたまた江戸初期には中国から黄檗の隠元隆琦の僧徒らの福建茶、やや遅れて曹洞の東皐心越(本連載第23~25、43~45話)らが杭州の緑茶をと、各禅流の規範である「清規(しんぎ)」を離れた明末江南以南の茶法をもたらすが、それらは未だ唐の陸羽以来の伝統的な上投法で、湯水に茶葉をいれて煮ていたものが主である。
京都では黄檗僧を還俗した高遊外売茶翁が煎茶趣味を巷間に鼓吹し、また長崎唐館出入りの来泊清人は江・浙・閩三省の出が多く、ために唐館ではこれまた日常喫茶の風習があり、就中、文事に通じ清楽(しんがく)を伝え、また茶事をも伝えた蘇州の江芸閣(こううんかく)(江稼圃の弟)や福州の傅士然らが茶や書画を嗜む傍ら清楽を善くし、士然は『茶具図譜』を長崎に紹介するなど、こうした唐館出入りの清人直伝の文事や清楽、また唐様茶儀を学ぼうと、日本の文人や好事家たちは挙って唐通事の伝を頼った。
これらのことが契機となり、以来、当時の日本式と南派工夫茶の茶儀や、幕末明治初期にかけて玉露が完成するなど徐々に合体し、現今の煎茶に似た、すなわち茶葉を急須にいれて湯を注ぐ下投法が主流となり、漸次唐様の総合芸として発展していく。
幕末にこの煎茶儀を東都に紹介した一人が加賀屋清兵衛で、松井友石の岳父松井楓川亭の旧主となる。また石田月香は嘉永年間飛鳥山下に江戸初の茶園を営み、その大路に沿っ茶店を開き、茶園の中に別亭を築いて雅客を延き、長崎仕込みの清楽三昧に耽(『香亭蔵艸』参照)ったのである。
その門下には若きころそこに寄寓し清楽の神髄を学んだ鏑木渓庵や、煎茶で名高い幕臣川勝蓬仙などがあるという次第だが、詳細は前書に譲り加賀清の件を略して再引用する。
「文政天保のころ、…加賀清なる骨董商がいた。人となり風流にして温雅、仕入れのためしばしば京阪の地を訪れていたが、ことに高遊外売茶翁の煎茶式を好み、これを関東に紹介せんものと、往還の道中にも茶具を陳べ、別に雅法を案じて煎茶式を人々に教え広めたので、風騒の士人たちは挙ってその門に連なり、ようやく江戸の煎茶が盛んになったという訳である。」(本連載第88話)
当初、各種煎茶器具は、舶載された前記『茶具図譜』が好事家により筆写され、さらにこれを田能村竹田が和刻し、流布しだしてより広く全国の煎茶家が影響され、これを参考に意匠を凝らして唐物屋を通して宜興などへ発注し、これらは古渡(こわた)りとして珍重されたが、無論日本独自の茶具製作もあり、さらに後の明治末から昭和にかけて輸入されたものは新渡(しんと)と区別され、いまとなってはなべて貴重なものとなる。
一方、明末の閩風を色濃く遺した台湾では、明治二十八(一八九五)年から日本の統治下におかれたため、却って福建工夫茶に日本の煎茶式を採り入れた茶儀を創成し、さらに二十世紀末葉にこれを大陸が模倣して現在に至るが、これらのことからしても、和漢の茶儀、こと煎茶に関しては各時代における日中両国は常に相互の影響を与えあっているのだ。
茶席の音楽に関しては、幕末、ちょうど煎茶に「道」字が付帯するころ、煎茶席における音楽席が珍重され出し、そこでは専ら唐音(とういん)で唱われ清楽がもてはやされ、やや由緒ある古楽器が展観されたりもしたが、これは主に清朝南方の俗曲と楽器群で、長崎の唐通事などを媒介に漸次全国に拡散流行し、明治の初中期には邦楽と二分するほどの一大勢力となっていたのである。
「初期「清楽」隆盛のほどは前述の通りだが、明治五(一八七二)年八月から同六年四月にかけての学制発布以来の初等音楽普及期と日清戦争などの要因が重なり、清楽そのものは衰退し始める。しかし、その後は形を変え、さらに明治三十年代に「九連環」(本連載第74~77話)から派生し日本化した「法界節」が大流行すると演歌直接のルーツとなるなど、衰えつつも主要な清楽器の月琴や清笛、さらに胡琴(胡弓)などにより、日本の俗曲が昭和の日中事変ころまでは演奏され続け、現在の二胡ブームの先鞭となるのである。
眼を現在の大陸に転ずれば、大分と生活は豊かになり、南北とも喫茶して当前の風となったが、戦前の緑茶一斤に数月分の報酬をはたいた時代はともかく、解放後の人民の茶は、北京では専ら廉価な茉莉花茶(ジャスミンの花で茶葉を香り付けする)一辺倒であったし、江南の上海や杭州でも真空パックは普及せず、緑茶は黄茶色に変色したものと思っていて、また両市とも水質が悪く、我慢してこうした茶葉で飲用していた。
そのころ、古くからの上海の茶館や旧劇場の大方は映画館となり、その後はディスコなどに転用されたが、近年、それも高価な茶葉を好む傾向と相俟って、茶館も本来の形式に復古しつつ、茶を飲みながら地方劇のサワリや漫才やら曲芸(日本でいう浪曲や浄瑠璃)、また江南絲竹などの品のよい音楽を聴かせ営業するところも回復し定着してきた。
拙稿「喫茶と音楽」創業者の鄭永慶が少時北京で味わった茶館の諸芸、青年期米国でのコーヒーハウスなどを体験した上での「可否茶館」開業は、ある意味でこうした洋の東西の茶館を融合させたもので、たかだか一杯の茶にまつわる話ながら、総合文化発信基点としての「本邦初の喫茶店」は、いかにも奥深く、また貴重な文化遺産であったことが解ろう。また、これらに有形無形で関与した帰化明人の末裔である唐通事たちと唐館に寄留した多くの来舶清人、黄檗の隠元や中国曹洞の心越ら渡来僧の徒、茶や音楽、詩文や書画篆刻を巡る人々等々。これら「四芸」に関する日本の文人数奇者たちにとっての至宝であった中華文化のエッセンスは、百年単位の年月で巡り巡り、いまも連綿と継承されつつあるのだ。ただ、その多くは近代文明の狭間に隠れぎみで、せっかく卑近の場にありながらも、現代人たちには見えにくいこともまた事実である。
以上、ひとまず「喫茶と音楽」の項を終えるにあたり、拙稿の各回各話は一応の主題と副題からなるものの、糾える縄の如く、往々にして別回と関連しつつ、さらに曳牽しようとする。この稿意を読者諸賢が了とせらるれば幸いこの上もない。
「江芸閣弄月琴図」
『観世居月琴譜』1860年刊より
江芸閣(生没年不詳)は蘇州の産で諱は辛夷、号を大水、字を芸閣といった。山陽、星厳、竹田その他、当時の日本文壇一流の人物らと交わり、彼らに影響を与えた清客文人の一人である。
芸閣は唐船々主(実務は番頭一任)で、嘉慶18(1813)年以後しばしば来泊して長崎の唐館に寄留し、馴染みの芸妓袖扇との間に八太郎という男子までもうけたという。
道光4(1824)年の暮秋、すなわち文政7年9月ころに描かれた「弄月琴図」により、そのころの芸閣はすでに壮年期を過ぎた老齢であったことが知ら
れる。
昭和『明笛独習』
全音楽譜出版社刊
明治中期を経て清楽そのものは衰退し始めるが、昭和の日中事変ころまで、月琴や清笛(一般には明笛と混同した)、胡琴などの主要清楽楽器は使用され続け、日本の俗曲や民謡などが演奏されるようになる。
標準 明笛獨習
東京,全音樂譜出版社会行
「江芸閣手沢の月琴」
該月琴は本連載第4話ですでにご紹介したもので、江芸閣が若年より愛用した名器であるが、近世日本音楽史上における清楽の伝来、さらには現存する清朝前期製の楽器として重要な原資料となる。
月琴裏面には、上部に「蘇州城西門街」を示す紙印記と、中央右には頼山陽が芸閣にあてた「月琴詩」が彫られ、左に芸閣の自讃刻記がある。
37
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第95話
良寛さんの琴譜
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
大雪の翌日、愛チャリで文字通り倒けつ転びつ、久しぶりに北の丸の公文書館に出向き、かたがた神保町馴染みの古書店へと思いつつ、道すがら懇意の古玩店へ立ち寄ったと思われたい。
例のごとく心越や玉堂の積もる話から始まり、たまたま良寛さんや出雲崎の話題におよぶや否や、老板M氏自らものされたという『良寛文人の書』なる大著を献呈され、「ここをごろうじろ」と、示された箇所に「閑適の境地」なる一節があった。
閑適――この言葉こそ文人の文人たる境地を指し、最も好まれるものではないだろうか。『白氏文集』(巻五)「閑適」の第一に収まる「常楽里閑居詩」を小野道長が書したものが重要文化財に指定されて、前田育徳会に蔵されている。その冒頭
帝都名利場。鶏鳴無安居。
獨有懶慢者。日高頭未梳。
帝都は名利の場、鶏鳴いて安居する無し。
濁り懶慢の者有り、日高くして頭未だ梳らず。
で始まる部分に「獨り懶慢の者有り」怠け者がいるのである。生涯身を立つるに懶い、良寛の詩に出てくる怠け者がここにもいるのである。
文人の条件、琴棋書画に照らしてみれば、良寛の親友の山岸楽斎が唐琴の達人で、「生涯懶立身」の詩に琴の譜を付けてくれている。良寛も楽斎もその譜を見ただけで音色を想像出来たことだろう。他に亀田鵬斎や五適社・中江杜徵、新楽閑叟もやってきた。いずれも琴棋書画を愛した人たちである。とにかく出雲崎には文人が多く集まったようである。…
老板M氏は古玩のなかでもことに「古硯」の目利きであるが、筆者にいわせればこれなどは世を忍ぶ仮の姿であり、もとを正せば大学で日本文学を専攻された学究の徒であり、しかも地モッチ魂で、こと新潟に関わる文人への思い入れは、人後に落ちざる強烈なものがあるのだから…。
もっとも、「坊主なのか、文人なのか、乞食なのか」、などと訊かれたところで、当の良寛さんも大いに返答に窮したことであろうし、そう思って改めて見るM氏も、なんだか捕らえ所のない大人物に見えてくるから不思議である。
この「閑適・閑居」なる語句が、ある意味で「怠け者」と解釈でき、実際にこの人生上においてそう捉えられる時空間を体験できれば、なるほど少しは文人的な世界も理解できるようにもなろうかというものだが、実は、すでに廃刊(休刊といったが)となった『文人の眼』なる隔月刊誌の連載に、ここにいう「良寛さんの「琴譜」を取り上げたことがあり、その残像があまりに強く残っているからして、ここで資料が検索できずば、実に惜しいのである。
ヤヤッ、あったあった!。
山岸楽斎が、良寛さんの『草堂集』にある「雑詩」という人口に膾した同名の五言律詩「生涯懶立身」に諧音(作曲)した琴譜は、ごく深遠な琴の旋律にのせて唐音で唄われるが、両人の淡い交情を偲ばせるには充分である。
そういえば、一昨年で辞した新宿住友ビルにあるAカルチャーセンタで講師をしていた時、琴のもと門下生に遭えば、なんと楽斎と良寛の琴譜の話しをするではないか。しかもその数年後、同じビル内に「良寛展」のポスターの掲示があり。ビックリしてその由を聞けば、これも知り合いの出雲崎の0氏(杜徵琴台の持主で白雪羔本舗主人)の企画で、急遽同ビルでの開催に至ったというのである。まったくもって、この世の点と線は、どこでどう変わるのか、すでに閑居する身には皆目見当がつかない。
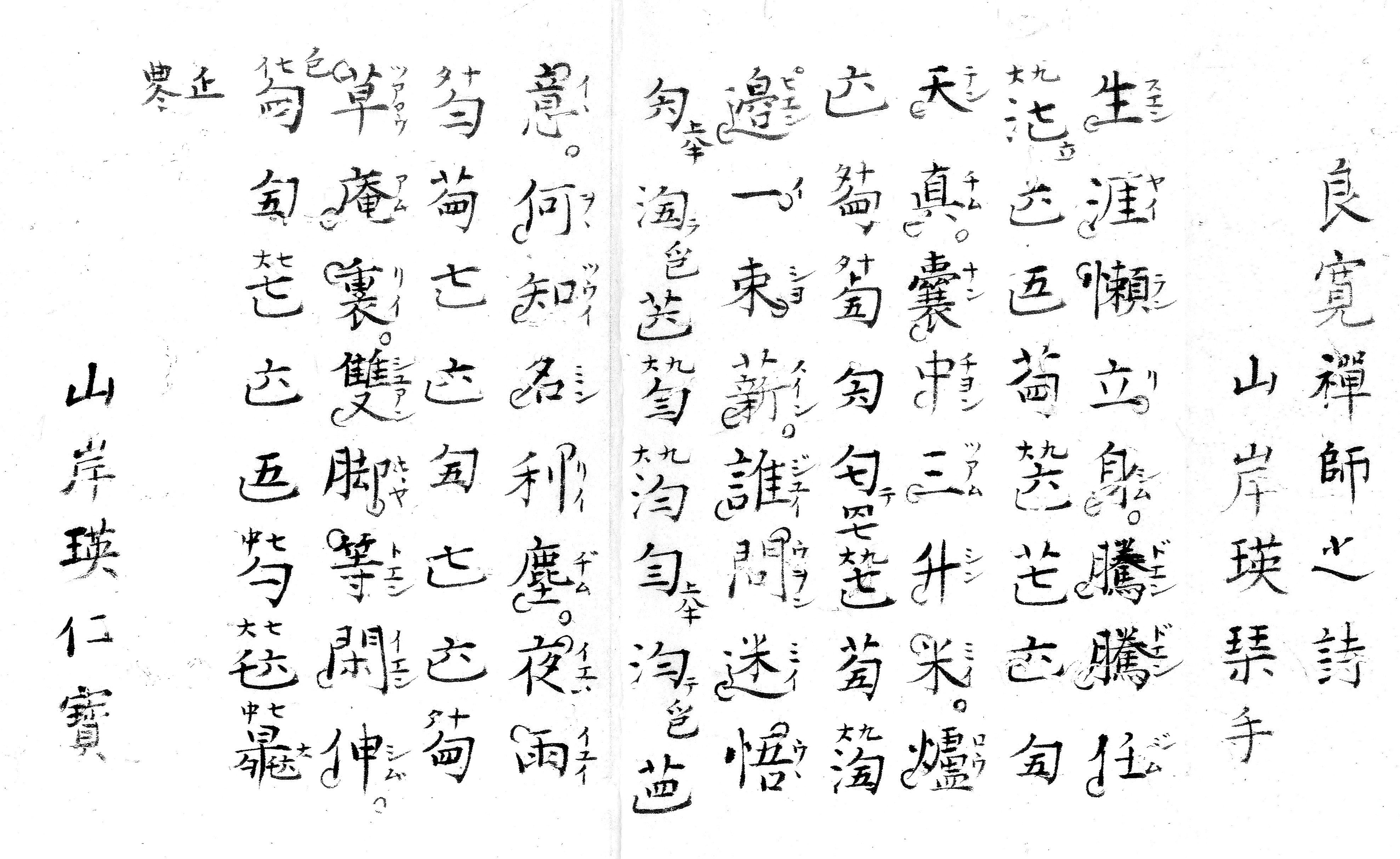 良寛さん作詩「琴歌」『楽斎琴譜』より
良寛さん作詩「琴歌」『楽斎琴譜』より越後和納村(現新潟市西蒲区和納)の医者で、琴ばかりか歌道も善くした山岸楽斎(1783~1850)は、良寛(1758~1831)さん25歳年下の忘年の友である。幼名を寛治、通称利左衛門、諱を瑛、字を元瑛といい、仁宝、楽斎と号した。斎号を鳴琴堂といった。
若き楽斎は京師で医術修行をし、その遺愛琴は楽斎48歳のときに入手した琴で、同じく京都で活躍していた美濃産の儒医児島鳳林(1778~1835)の天保元(1830)年の作であるため、恐らくは鳳林の琴門と推察されるが、これは考証を要す。
26
△目次TOP↑
秋月※M氏:萬羽啓吾 萬羽軒
0氏:大黒屋4代目小黒孝一、5代目小黒淳
瘦蘭齋樂事異聞 第96話
東台琴客余聞 二十二 松井友石
田邊尚雄 7
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
引き続き、田邊老先生の「琴癖」にまつわる話しである。
〔十月八日〕(筆注・北京)
(一)古琴『長門怨』 査阜西
(二)古琴曲『広陵散』 管平湖
(三)琴と洞籍『梅花三弄』 傅(正=溥)雪斎、査阜西…略…
このうちまず第一に驚嘆感激したのは、管平湖老人による古琴曲『広陵散』の演奏である。この曲は昔晋の時竹林の七賢の一人稽康が鬼神から伝授されたという。ちょうどイタリアのタルティーニが、夢で鬼神から授けられたというヴァイオリンの難曲『悪魔のソナタ』に比肩される難曲で、目にもとまらぬ速さのフラジオレット(ハーモニックス)の連続奏法などは、稀世の名人でなければ到底なし得ないところである。今では管平湖氏以外では、広い中国中でもほかにこのように立派に演奏し得る人はないとのことである。私はとくにこの演奏をレコードに録音したものを、今でも大切に保存して当時をしのんでいる。 …略…
古琴の楽譜集三冊をもらって五時ころ帰館した。
〔十月十三日〕(筆注・四川)午後は民族学院の歌舞団に行き、…略…つぎに専門家の古琴「流水」(四川派の奏法はハルモニックスをひじょうに多く用いる)を聞き、…略…
〔十月三十日〕(筆注・上海)…略…午後一時半、中央音楽学院華東分院(俗に上海音楽学院と呼んでいる。中央音楽学院の本院は天津にあり)より迎えが来て、…略…校内の参観を終って、私と秀雄のために講堂で演奏会を開いてくれた。曲目は、
(一)琴簫合奏『梅花三弄』……
琴は呉振平 簫は王巽之 …略…(以上『田邊尚雄自叙伝』P428~より)
かくのごとく田邊老先生は、戦後初の北京訪問において、溥雪斎(一八九三~一九六六)、管平湖(一八九七~一九六七)、さらには査阜西(一八五九~一九七六)など、名実共にその当時一流の古琴家三氏の演奏を間近に聴き感激するという、ようやく四十八年前に抱いた素志を成就させたのである。(一)の査阜西その人は本連載第98話でふれた。(二)管平湖ときに五十九歳。田邊は持ち帰った『広陵散』SP盤を終世愛聴し講演の際に使用した。その名盤を筆者は度々聴かされた。(三)の溥雪斎(第42話)は前清の宗室である。
特筆すべきは、この日本文化人訪中団の成功により、二年後の昭和三十三(一九五八)年の二月には、答礼としての新中国成立後初の「中国歌舞団」の訪日公演が実現することとなり、査阜西を団長とし、日本側の接待は田邊らが分担して、因果は廻り、この歌舞団訪日こそが坂田が初めて琴を学ぶ契機となり、後に田邊を師と仰ぐことへと繋がる。
「古琴の楽譜集三冊をもらって」云々は、この月ちょうど中央音楽学院音楽研究所で復刻した明版の琴譜集『神奇秘譜』三冊本が出版されたばかりであった。
(続)
【右】「中国歌舞団」節目単 1958年2月
連載中に頻出する「中国歌舞団」訪日公演時のプログラムを、寒斎反古の山中からようやく見つけだす。しかして筆者の現在あることと拙稿異聞の各回は、一見、何の関係も脈絡もないような出来事の連鎖だが、結果的にはそれらのすべてが見えぬムーサの手によって結ばれていることを痛感する。
【下】「広陵散」琴譜 『神奇秘譜』1956年10月復刻版
該譜1425年の原本は、版行された琴譜中、現存最古のものとなる。解放後、党の方針により中央音楽学院の民族音楽研究所では、各地に点在保存される琴学資料を調査し、整理して内部用少部数だが陸続と刊行、復刻しつつあった。中国音楽界のそんな動向中、民族音楽研究所で復刻された該譜の発行部数はたった1055部のみで、たちまち品切れとなる。後にこの復刻版をもとにして、現在まで三、四度も重版された。
24
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第97話
東台琴客余聞 二十三 松井友石
田邊尚雄 8
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
『音楽見聞録』第壱集十七条は、楽界の古老富田豊春から田邊が直接聞き取りした一条で、ここにようやく友石と田邊が繋がり、日本の心越派琴事に関することとなる。第88話との重複を厭わず原文を掲載する。
(十七)〔七絃琴の売価〕
日本橋の漢学者松井氏所蔵の琴の内、文政十二年越後の百一居士(素人の手製)の品は価七円にして譲りてもよろしき由申越あり。
又京橋大鋸町呦々堂小池氏の売品中に価弐拾参円の唐琴あり。朱漆塗、薄霞の銘あり。仲士珍蔵、凡そ三百年以前のものなり。音極めて宜し
〔一絃琴家、富田豊春氏談〕
《〔七絃琴の売価〕》
原義では琴の製作年代の古いものを「古琴」といい、その場合、美術的骨董的価値の高いものを暗示する。現代中国語における他の絃楽器と区別するための造語「古琴」とは自ずから別義である。
古来、琴は学者文人必須の器であったため、名琴や謂れのある琴(著名な文人の所有した)など付加価値により、現在におけるヴァイオリンの名器と同様、もしくはそれ以上に高価であった。
筆者の学んだ若きころ、中国における価格は、一般的で可もなく不可もない明琴(明代中期に琴学が大成され、それにつれて製琴法も確定したため、明琴が後世におけるひとつの標準となった)は、数十~数百元(当時の日本円で数千円~数万円)であったが、五十年後の二〇〇三年十一月に、中国における「琴」および「琴の文化」が世界遺産に登録されるやいなや、これを契機に中国ばかりか世界的に古琴学習熱がフィーバーし、非常に琴の価格が高騰してしまった。前記のような一般的な明琴でも数十万~数百万元(日本円で数百万~数千万円)となり、二〇一○年末の北京のオークションにかかった宋琴は、欧米をも含めた楽器の価格としては歴史上過去最高額の十七億円(日本円に換算して)で落札され話題となったほどである。
《日本橋の漢学者松井氏》
これこそ連載中の松井友石を指す文字で、当時友石は日本橋小網町で私学「甲津学舎」を経営していた。田邊―富田―松井と人脈は連鎖し繋がる。
《百一居士》
百一とは児島鳳林(一七七八~一八三五)をいう。美濃国更地村の産で、田邊の記録(富田豊春談?)した越後は聞き違い、もしくは富田の記憶違いである。
名は祺、字は子禎、鳳林また百一と号す。琴百面を製作し、各々に一面づつ提供せんものと結願、ゆえに百一と号した。そのため和製の琴としては巷間最も遺例が多く、百面結願後に百一とするは誤りである。百一は京都の儒医皆川淇園(一七三四~一八〇七)門生で、琴を浦上玉堂(一七四五~一八二〇)や勢伝(心越派伊勢伝)を永田蘿道に学び、とくに製琴を善くした琴客であった。著に木活字自刻本『琴譜』(内容は『東皐琴譜』)などがある。
《(素人の手製)》
児島百一の製琴を志した当初の文化年間初期のころのものこそ、試行錯誤し模索中のものであったが、数十面製して経験を積んだ以後は斲琴(たくきん)術もほぼ確定し、文化末年から文政年間にかけて製作したものには、和製の琴としてはかなりの水準に達したものもままある。田邊の聞き書きで文政十二(一八二九)年作の「(素人の手製)」といった琴は、後期の作例に属し、この田邊の評価は、百一の琴界と製琴における正当な位置を把握しえずにいたことを示す語であり、妥当ではない。
琴客と自負したものにはまま数面の琴を所蔵し、通常は初学に和製を用い、師匠クラスとなれば中華製の古琴を渇望した。友石も数面所蔵したが、就中第一の名琴に無銘の「宋琴」があり、これはもと東博初代館長の町田石谷(一八三八~一八九七)の愛惜してやまなかった遺愛琴で、石谷が仏門に帰依するときにもこの一面だけは手放しえなかった。その琴を後に友石の手に託し、松井友石はこれを莫逆の友で恩人の小畑松坡へ委ねたのである。
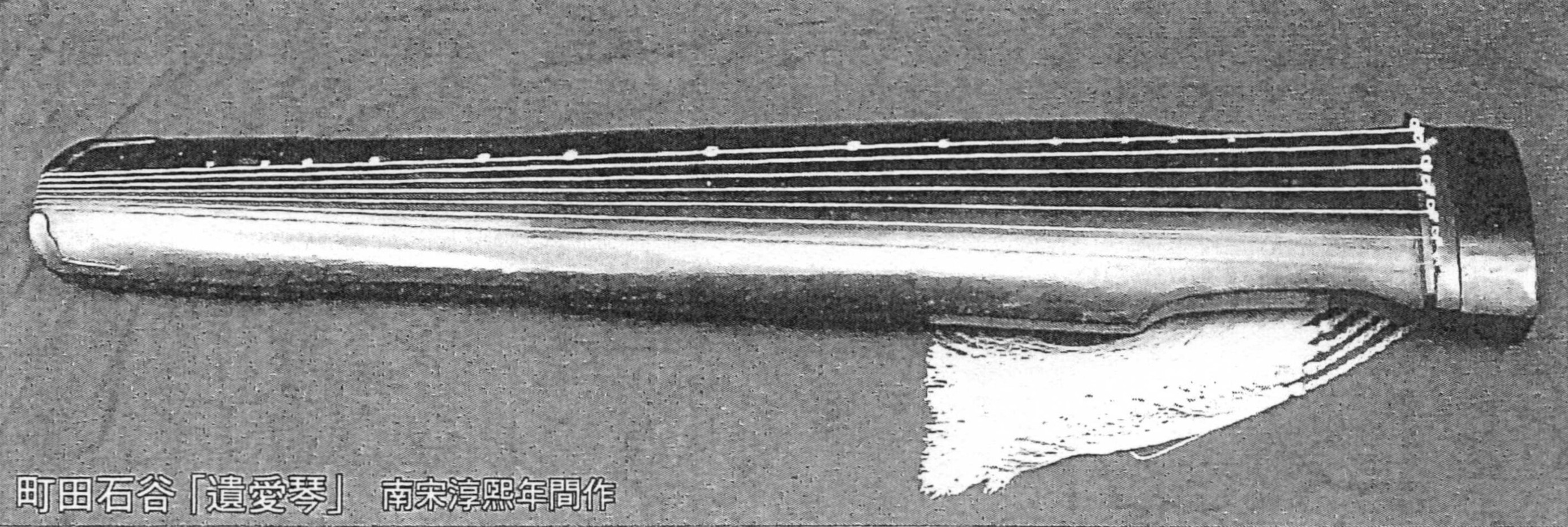 町田石谷―松井友石―小畑松坡―小畑松雲―小畑元三―坂田進一へと伝承されている。
町田石谷―松井友石―小畑松坡―小畑松雲―小畑元三―坂田進一へと伝承されている。なお、大方の琴客は中華製の古琴を得たいと切望(一例・浦上玉堂の「霊和」通称玉堂琴は、長子秋琴が借金四十両のカタにした)したが、明琴などは非常に高価で叶わず、大抵は和製の琴で百一ほか定評あるものを実用していたのである。
この記事で七円(明治初期の貨幣価値ではおおよそ江戸期の七両弱に相当するが、大正期はその半額以下となる。大正六、七年ころの教員の給与は十五円)と、随分と安価であったのは、商人を通さぬ良心的譲渡価格を示したからこそと思える。
句末の「譲りてもよろしき由申越あり」とは、一体誰を指しての言かを考察すれば、当然、インタビューアである田邊に対する友石のものであろうし、ならば琴を求めた田邊の依頼があってのことと解釈できる。田邊が学琴とここに到るまでの諸経緯などに大いに啓発され、自身が自用の琴、それも比較的良質な琴を求めるよう心がけていたところ、たまたま大先輩の富田に相談すると、松井友石所蔵の琴を割譲してもよいとの話しが出た、ということになる。ただ、これは成立しなかったものとみえ、後に田邊の男秀雄(一九一三~二〇一〇)が京都市芸大へ寄贈した楽器群を調査した限りでは、田邊親子の琴は二面遺るものの、この十七条にいう富田周旋の二面とは異なるのである。
ちなみに田邊老先生生前ご自慢の琴は、銀座云々(後述)でのいわくつきのもので、安藤朴翁(一六二七~一七〇二)遺愛で、元禄以前の貞享二(一六八五)年の作になり、東皐心越禅師の東渡以後、琴の第二次流行期嚆矢の和製としては最古に属する琴である。以下「胴内墨書銘」および「付けたり」である。
貞享乙丑四月做霊開琴造焉、平安隠士安藤朴翁玩蔵、
朴翁名定為通称新五郎丹波人、仕伏見宮元禄十五年八月没、年七十六、
《〔一絃琴家、富田豊春氏談〕》
一絃琴の全国総取締となった真鍋豊平(一八〇九~一八九九)に父礫川ともども学び、豊春と称し跡目を継ぎ二代総取締となる。鏑木渓庵門下逸材の清楽家渓蓮としても高名で、また江戸の古曲や俗曲などにも精しい音曲家として、明治から大正期の音雑誌などにも多数寄稿している。こうした富田豊春の交友は広く、楽友の他に友石や中根香亭など文人雅客もあり、また田邊尚雄のような音楽学者もあった。渓蓮自身も清楽の延長線上で琴にも興味をもち、清版『松風閣琴譜』などを所蔵していたし、大正九(一九二〇)年ころまでは現役で活躍していて、この田邊の取材面談に応じたものと思われるが、惜しむらくは関東大震災以後その終わるところを知らぬ。
(続)
 「松井友石小照」(1857~1926)
「松井友石小照」(1857~1926)本姓妻鹿氏、名は廉、字司直、友石と号す。大坂の儒医妻鹿友樵(1826〜1896)の男。
かく心越派正式の弾琴の際には、必ず琴服「鶴氅衣」をまとった。
児島百一斷琴例「黑漆仲尼様琴」
本文と同年の作が、たまたま筆者蔵琴中の一面にあるので参考に供す。
胴内墨書銘に、「文政十二年己丑仲冬、新造濃州鳳林艸堂」(1829年陰11月)とある。
「富田渓蓮小照」
(1851~没年不詳)
幕臣富田礫川(1816~1874)の男で名は寛である。豊春(とよはる)とは一絃琴における雅号で、清楽時および平素は蓮また渓蓮斎と名乗った。中根香亭(1839~1913)の辱知である。嘉永四年江戸は小石川の生まれで、徳川慶喜公の静岡転封にともない、後に浜松に住んだ。
41
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第98話
東台琴客余聞 二十四 松井友石
田邊尚雄 9
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
こうした琴癖を仲介とした知識人との縁がさらに田邊の周辺に構築されてゆき、後年の田邊をして「琴をともに語りあえる君子人」と、いかにも誇らしげにいわしめる伏線となったことがよく解る。ここでその田邊の琴癖なるものの変遷を整理羅列してみよう。
一、「琴の存在を知る」(推定)古典からの知識を初等教育また経書中に得、初めて琴の存在を漠然と知る。
二、「琴を聞く」(推定)富田渓蓮など周辺の友を通じ、次項三、以前に日本の琴歌を聞く。
三、「琴の初学」明治末、清国留学生の琴を聞き、またその学生から琴(清末蜀派伝)の初学および「平沙落雁」を習う。
四、「琴を得る」前記の諸経緯から琴を得る。(最終的に二面遺る)
五、「琴友を得る」琴を通し、琴癖を持つ内外の同好の士と知り合う。
六、「琴書を学ぶ」弾琴からは遠ざかり、徐々に琴書に重きをおく。
七、「琴を聴き、その美学を語る」鍾子期(伝説では琴の名聴き役だが、子期も弾琴の名手という設定)役に徹し、著書や講演で琴についての哲学的な美学を語る。
八、「琴との一体化」公職引退後の長き晩年の田邊の老成期を経て、『名人伝』(中島敦)ならぬ人琴(音楽)一体化する。
しかしてこれらの証左となるのが田邊自身のいう以下の記事となる。
○琴は君子が身から離さないといわれる位に中国のインテリ階級の人はこれを尊敬している楽器であるが、今は中国でもこれを奏する人はきわめて稀であるという。···略…私がこの琴を身につけたことは後に中国を旅行するようになっていたるところで私が琴を身につけているということで、君子として尊敬されたことは、私の中国旅行に大いにプラスとなった。(明治〜大正)
○それ以来しばらく馮大人とはたえず相文通を続け、私が古琴を所持していることを知って、ときどき琴の絃糸などを贈って来られた。(戦前)
〇及至周代、礼楽之思想極盛、对於音楽、専作道徳的解釈。認琴為最優秀者、以之為君子之器、於是琴之解釈甚多。…略…
此中已加入後世五行之説。要之琴之為器、実為代表中国人道德理想者。(田邊『中国音楽史』P102~3)
次に(十七)条を補足すべく附言として、松井友石著の『談琴』より引用する。
【談琴価】古琴已希。其価自貴。昔者晋嵇康売東陽旧業以購一琴。唐陳子昂以千緡市一琴。明李敬欲以百萬銭購雷琴。鬻者尚不肯。王逢年販焦尾琴以貿城南田数頃。玲瓏琴以千金市之。霹靂琴賜内帑千金。…略…
【町田石谷】名久成称民部号心庵。薩摩人。為博物局長又為元老院議官。後剃髮住三井寺任僧正。博学有鑑識。古琴蓄十面扁曰十琴仙館。
学弾法于友樵。明治三十年九月十五日寂年六十。
町田石谷(一八三八~一八九七)は、友石実父の妻友樵琴門で、東京における松井友石の恩人かつ身元引受人で初代博物局長にして博物館館長。琴癖に加えて全国の古美術を統括する役職からも、一般に比せば古琴を得やすい立場にあり、明治初期には宋の蘇東坡(一〇三六~一一〇一)を慕い倣って十二面の琴を蔵し、後に二面を割譲して十琴仙館主人と名乗った。(続)
『談琴』松井友石著(右表紙/左「談琴盛衰」冒頭)
1917年 上下二巻未刊稿本
心越流琴派の終焉を危惧した友石畢生の著作は近代日本琴書の結実で、稿本と控えの二本のみ伝わる。
田邊は富田渓蓮を通して、かく内面を秘めた友石との接点がせっかくありながら、惜しくも日本の主流である心越派の琴学を学ぶには至らなかった。
談琴上 友石松井廉著
彈琴盛衰
明陳衍曰。古事無傳於後者有數種。劍法嘯砭舞彈碁。予曰。是亦不必傳者。
不可不必傳。而今不傳者爲琴道。蔡邕曰。伏羲氏作琴以修身理性。予曰。堯舜禹湯文武皆求治於琴。不獨南薰之操也。孔子行住坐臥。未曾斯須去琴。或臨河而彈。或憑車而鼓陳蔡之厄絃歌之聲不绝。弟子三千人亦琴瑟以涵養德性不獨孔門第子。當時士大夫無不皆然記曰。士無故不徹琴瑟。詩云。琴瑟在御。莫不静好。而其所彈奏所
35
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第99話
東台琴客余聞 二十五 松井友石
田邊尚雄 10
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
町田石谷(久成)は、幕末遣英留学を終えた後、上野戦争で焦土と化した東台を憂え、跡地を一大教育文化施設の場とした功労者だが、世俗一切の名誉を棄て三井寺に入った。ただ、その生涯において最も愛した名琴だけはどうしても手離せず、最終的には松井友石が見込まれその名琴を託されたという、その顛末記でもある「宋琴記」は、石谷や友石との関わりを記念し、湯島聖堂斯文会の機関誌『斯文』に所収された。
「宋琴記」
…略…
心庵上人(町田久成)高雅之士也。嘗官於朝勲位並高。一朝桂冠帰仏。世間一切事物棄而不顧。而独不能離乎琴。飛錫東西必以琴從。明治某年、上人在大坂。使人齎琴来告曰。衲之愛惜此琴。而不能離者。恐託不得其人也。今聞子欲著琴書。故以相遺。庶幾乎託得其人矣。予受而観之。…略…
鳴呼七百年久興亡治乱滄桑変遷。此琴独不損不毀。以伝于我国。似有数存者。上人之愛惜之不亦宜乎。顧予不徳僅解琴中之趣。焉得膺其託。然予之与上人於義。為父執於琴曲為同学。又嘗久寄寓于上人之廬。
交誼極厚。其賜豈可以不徳哉。乃受而宝之。且記其所以。…略…
(松井友石著『談琴』より)(秋月※)
◯補記
以上、ことに田邊に関わる部分は、畏友M教授の還暦記念論集『中國學藝聚華』に寄稿した「清末の琴曲のおよぼした、ある明治人の琴癖の一端」という拙稿を連載用小齣に書き改めたものであるため、多分に読みにくいものであったことを改めてお詫びせねばならない。
ただ、かくも短文の二条目ではあったが、田邊の一般には知られざる癖が克明に浮き出され、これを大いに再認識させられる結果となり、あわせて「音楽見聞録」初巻の一端を繙くにつれ、しばし明治末大正初期の楽事における点と線の摂理に遠く想いを馳せることができた。
常に君子人たらんと欲していた田邊が、一種その憧憬にも似た琴癖を内に秘めていたことは、その戦前の北京における馮汝玖(国民党幹部)とのやりとりを通しても明確に知られ、これほど琴を好んだ田邊の初学は明治四十一(一九〇八)年のことと解った。たまたま清末当時の琴を学んだが、留学生を通してのことでもあり、極めずにはおかぬ質の田邊にしてみれば、さらなる高みを目指し、名手の伝をと願ったことは当然帰結するところであった。しかし中国調査行にはさらに十五年間の歳月を俟たねばならず、また実際の学琴熱はこの時期に冷めて断念。以後は音楽学者として聞(聴)くに徹したものと思われるのは、田邊の遺愛琴二面の調製が、学んだ百年以前とほとんど変わらぬ状態にあること、それ自体がその証左だろう。
翻って当時の日本では、なお心越派の琴流がありながら、「大厦のまさに顛(たお)れんとするに、よく一木の支えるところに非ず」と、松井友石をはじめ数名の琴客がかろうじて孤塁を死守していた、まさに一流の断絃する大正期を迎えようとしていた時期でもある。並の知識人を自負するものならいざ知らず、田邊ほどの教養と琴癖を併せ持ち、心越派の貴重さを認識し、かつ富田豊春などを通して日本最後の琴客の五指に挙げられる松井友石との接点をもつ機会がありながら、あえて日本流を学ばなかったのは何故か。この時流における琴系譜を正当に読みとり、弾法はさておき、学者としていま一歩踏み込んで心越派の全体像を把握しても良かったのではと、田邊老先生の亡きあと切歯扼腕した筆者である。(続)
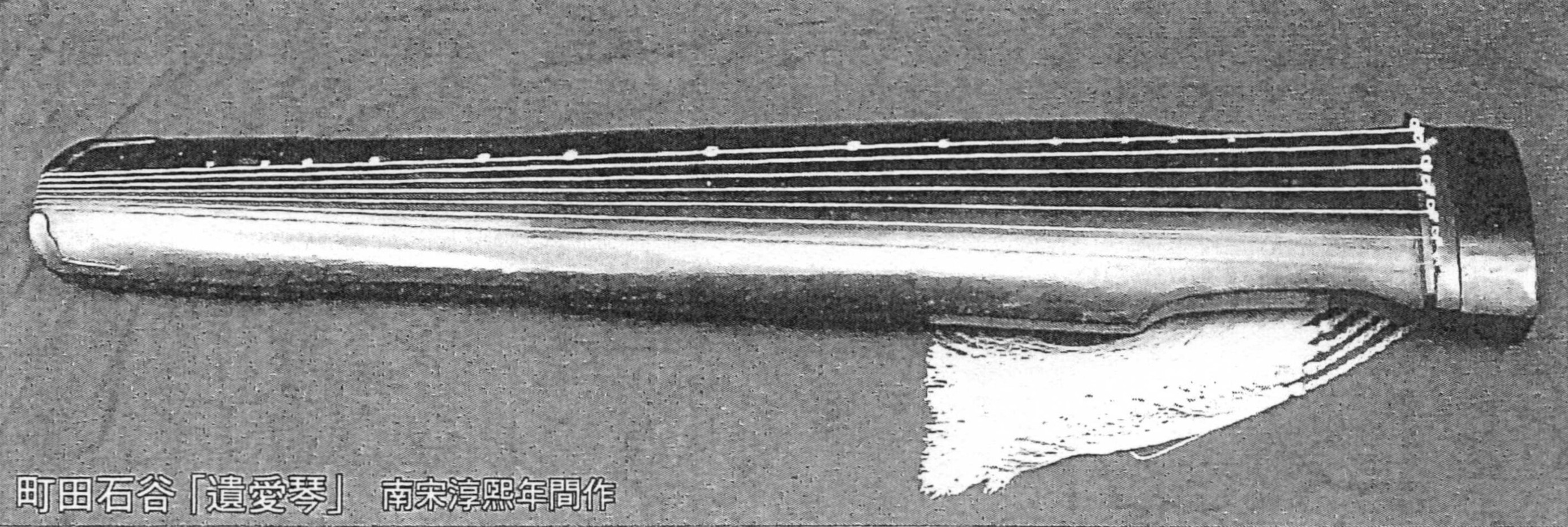 町田石谷「遺愛琴」 南宋淳煕年間作
町田石谷「遺愛琴」 南宋淳煕年間作松井友石が石谷の遺愛琴を託されたのは明治の末つかた、すでに百数十年以前のこと。冰絃を撫せばたちまち、八百有余年間のさまざまな出来事を古琴は語りだす。(秋月※)
31
△目次TOP↑
秋月※町田石谷遺愛宋琴については第97話なども参照
「宋琴記」の「焉」「為父執」など句点の解釈が異なるため、参考に全文読み下し(稗田浩雄『近世琴學史攷』1390頁)を下記にあげる:
宋琴記
「琴は禁也、淫を禁じ邪を閑する所以也。是れ古の君子を以って琴瑟身から離さず以って徳性を養い義に導く。方に後世身雅操廃れ正撃絶ゆ。其の器有りと雖も、其の趣を解し其の音を知る者鮮(すくな)し。
心庵上人(原注・町田久成)高雅の士也。甞って朝に官し勲位並びに高けれども、一朝桂冠し(辞し)佛に帰し、世間一切の事物を棄て顧みず、濁り琴を離す能はず。東西に飛錫するに必ず琴を以って従ふ。明治某年、上人大阪に在り。人をして琴を齎し来らしむ。告げて曰く、衲の此の琴を愛惜し離す能はざるは託すに其の人を得ざるを恐れば也。今、子は琴書を著せんと欲すと聞けり。故に以って相遺すを庶幾(こいねが)ふ。託するに其の人を得るか。予受けこれを観る。
鳳額より龍齦に至る長さ三尺六寸、中翅、濶(ひろ)七寸、蛇紋極めて古く漆光は人を照らす。歎に曰く、淳熙巳酉(十六年1189年)劉日新斲ると。按ずるに淳熙巳酉は朱晦庵始めて召され君子列朝廷の時、未だ劉日新の何たるか詳からず。
其れ君子か小人か。小人なれば豈に能此の雅器を斲り其の清音を弄せん、君子なれば則ち晦庵の徒か象山(陸象山)の徒か。此の琴或いは晦庵の堂に升り、又は象山の膝に横はり持敬主静の説、此の琴以って発明に資せざるかを知らん。未亡び、元と為り明と為り清と為り、而して此の琴もた轉す。幾たびか主を易(か)へ或は文山(文天祥)の有と為り、或は疊山(謝枋得)の有と為り、或いは邵菴、陽明(王陽明)の有と為るか、皆、未だ知るべからざる也。
鳴呼、七百年の興亡治乱滄桑変遷し而して此の琴獨り損れず毀せず以って畫我が国に傅る。数存有るは上人の愛情に似、亦宜しからざるか。顧するに予不徳、僅かに琴中の趣を解するのみ、其の託を得膺す。然れども予の上人と義に於いて父執とし、琴曲に於いて同学と為す。又嘗って久しく上人の廬に寄寓し、交誼極めて厚し。其の賜豈に不徳を以って辞すべき哉。乃ち受けこれ寶とし且つ其の所以を記す
。 夜深く静坐し弦を撫し三弄す。清音瞭瞭、指間に溢る。有るは虞氏の音か、宓子賤の音か、此の琴は其の必ず以って予を起しむ有るを知る也。」(松井友石『談琴』下、談餘三下)
瘦蘭齋樂事異聞 第100話
東台琴客余聞 二十六 松井友石
田邊尚雄 11
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
田邊は明治十六(一八八三)年八月十六日東京市四谷区西信濃町に生まれ、昭和五十九(一九八四)年五月三日に東京杉並の救世軍病院(もと救世軍杉並療養所)で没した。百歳と八ヶ月あまりの長命であった。
この田邊とは養家の姓で、本姓は本岡、実父本岡龍雄の実妹つね(叔母)が後の養母にあたり、父龍雄の父、すなわち尚雄の祖父正吉の実兄田邊久之丞(伯祖父)の息子貞吉(父の従兄)が尚雄の養父となる。
実父の龍雄は旧沼津藩(菊間藩へ)御祐筆方を勤めた士族で、学制発布後は東京市の小学校(不明)の教師をして、実母の旧姓は石井で、名をふみ(富美とも表記。一八五九~一八九二)といい、これも東京市芝の鞆絵小学校の唱歌教員をしていた。
こうした田邊の小伝はいくつかあるものの、拙稿で必要とするその幼少期の音楽体験とその展開は、実母の影響を多大にうけたことが直接の動機であり、自身が語るものがその後の経緯なども含めていっとう的を射たものであるため、他を棄てこれ本人の履歴としてご紹介する。
序 …略…
本文中にも述べてある通り、私の実母は和(箏曲、長唄、哥沢、二絃琴等)漢(月琴、その他の明清楽)洋(オルガン、ヴァイオリン、声楽)の音楽に精通し、私が小学校の頃は、母は東京市の唱歌教員をしてゐた。従つて私は生れ出でから母の懐に抱かれつ、常に日本と支那と西洋の音楽に身を浸して育つて来たのであつた。
…略…
しかるに私が九歳の時に母は急病で死んで、私は実父の妹の縁付いてゐる田辺貞吉住友家顧問、住友銀行初代総支配人の養子となり、大阪の天王寺中学校を経て、東京の第一高等学校に入り、続いて東京帝国大学理学部に入り同時に東京音楽学校の選科に入って音響学及び音響心理学、西洋音楽の研究などをやってゐた間は無事だったが、大学を出てから日本音楽の研究に入って、長唄やら常磐津やら哥沢などをやり、踊も花柳流から山村流などに夢中になり、屢々教員の職を放擲して舞台に出たりなどした。
ある時舞台で公衆の面前に所作事を踊ったりしたので、養父の勘気を蒙り、「道楽をするために学校に入れたのではない」と大いに叱られた。父が七十歳に達して一切の実業界から隠退して六甲山下の住吉に余生を送るに至つた時、盛んな隠退祝ひの宴を催した。その時、大阪毎日新聞社長の故本山彦一翁は、父に精神的の祝品を贈呈しようと申し入れ、新聞社の名を以つて私に講演を依頼された。私は新聞社で講演をするのかと思つて大阪に行くと、本山翁は自分と一緒に来てくれと言はれ、私が本山翁と同車して行った先は、住吉のわが父の宅で、多くの関西紳士の集まった祝宴の席上で、父の前に本山翁の紹介辞で、私は日本音楽の成立とその性格について、約一時間の講演をした。
この講演によって父の勘気を許され、爾来私は安心してこの道楽を継続することが出来た。その時、恩師長岡半太郎先生は私を導いて財団法人敬明会から研究補助を得せしめられ、同会としては最高額の金壱万円の研究費を支給され、以来、台湾に五回、蕃界に三回、朝鮮に六回、満蒙に四回、支那に三回、その他南洋各島、樺太、琉球群島を始めとし、普く東洋各地を跋渉して、その歌や踊りに耽溺した。
昭和四年、この東洋音楽の研究に対して思ひ掛けなく帝国学士院賞を授与され、畏くも宮中豊明殿に召されて、陛下より賜餐の光栄に浴したとき、私の道楽をして茲に至らしめ実母、養父、本山翁、及び諸先生の霊前に涙禁じ得ざるものがあった。その時ある人は、私に「世の中には勉強して覚められた人は多いが、道楽して賞められた人は珍しい」と評したが、私もやはりそんな気がした。従って今更急に学者らしい顔をして見たところで一向似合はない。やはり「道楽して賞められた男」として一生を終る方が私には似合はしい気がする。…略…
私は本年満七十歳になったので、知己の方々から本年春に盛大な古稀祝ひをしてもらった。その時、私の訓んだ歌を茲に記して、この序を終りたい。
古稀の祝ひに
学に生き、芸に遊びて七十年
楽しき道は尚ほ半ばなり
勲位なく、学位も持たず金もなし
ただ七十年、極楽の夢
昭和二十八年七月 天山田邊尚雄識
『音楽粋史』(一九五三年日本出版協同株式会社刊)P1~4より
この「古稀の祝ひに」とある件は、当然田邊には学位があり、研究資金にも事欠かず、学士院賞や後には紫綬褒章や勲四等を叙勲したので、学者のポーズであること無論である。
また、『続音楽粋史』(初名『音楽一代』一九五四年同社刊)P201冒頭に置かれた「序」は、田邊自身が語るその長い音楽学究生活に入る直接の要因となった原体験であり、この音楽好きの血統譜は、
第一、実母本岡ふみー(一八五九~一八九二)
第二、田邊自身(一八八三~一九八四)
第三、田邊の男秀雄(一九一三~二〇一〇)
と継承され、その献呈の辞には「この書を私の長男音楽三世田辺秀雄に贈る」としたほどである。
自他ともに「学楽」を司ることを許し許され、また数多の最高学府の教壇に立ち、何万という学生たちや多くの音楽家、また大衆に向かって啓蒙し得た田邊には、それらに伴う当然の義務があったろうし、思いがそこに到れば無論なし得たはずである。他の一絃琴や琵琶などのように琴もこれを教導なし得ていれば、その後の日本琴学の道も異なった方向へ導かれ、あるいは系譜も断絶せずにあったかも知れない。しかしこれらはすべて坂田の欲目である。
いったい田邊は本当の意味で琴が好きだったのか?、ただ単に知識人のステイタスシンボルとしてこれを識らねば恥辱と考えたのではないか、たまたま機会があってこれを学んだのではないか、などなど老先生の歿後にフト感じ抱いた坂田の素朴な疑問であったが、この校註に担り、改めて田邊の琴癖を考証してみて、こうした積年の「何故、貴重な日本の心越派を支持されなかったのか」という疑問が払拭されるようである。
本註4頁(二〇一一年九月号)の「支那留学生(琴ノ上手)羅紀氏」の部分を反芻していただきたい。
これほどの琴癖を秘めながら田邊は心越流を学ばず、初学の師として留学生を選び、なおその後も日本流を支持し得なかったのは、それが多分に学者としての立場を離れた侵し難い個人の趣味の域のことで、当時の日本流には厭きたらず、ましてや自らが学んだ留学生の琴にも距離をおいてしまうという、さらなる田邊の持つ上昇志向により、「ますます本場の琴曲に傾倒し興味を感ずるようになった」のである。研究者としては充分すぎるほど恵まれた境遇にあった田邊ではあったが、如何せん、琴を知ったそのころはいまだ巣立ったばかりの教師の域にあり、その後、学者として田邊が自立し社会的に形成されていく過程に従い、琴に限っては和漢二者択一のうち、ことに中国を中心に強く興味を抱くようになっていったのだと、しかも年齢を重ねるうちに、大方の過去にあった和漢の知識人と同じ轍をふみ、琴を弾かずに語る(ことのできる)人となっていったのだと…。
欲目とは単なる仮定に過ぎず、しかして歴史に仮定はあり得ず、事後に悔やむことの多いは衆生の性である。歴史は往々にして非情にして無常ながら、有情と体感し得るのは人であり、ましてや本来無機質な音響の連続を音楽として感じ得るのもまた人である。だがそれは単に音楽家には限らぬということを胆に銘じる。
တ
以上、松井友石と関連し、ここしばらくは田邊尚雄琴癖の一端をたどってきたが、次号よりひとまず田邊を離れ、またぞろ陋巻を散策しよう。
「田邊と玲琴」
昭和2(1927)年8月16日 東京放送局(JOAK)にて
玲琴は、はじめ追分節の伴奏用にと田邊が考案し、楽友の見砂知障(号東楽。追分節の名人で、東京キューパンボーイズを率いた見砂直照の父。姓名判断をも善くした)によって大正10(1921)年ころ製作され、田中正平博士が名付けた胡弓の一種。
なお、田邊愛用の筆名・禎一は見砂の命名である。
25
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞
田邊尚雄 年譜 坂田進一編
年次 年齡 ○履歴
○国内外の出来事
■明治
16(1883)年当歳○8.16父本岡龍雄、母ふみの次男(実兄は玉樹)として東京市四谷区西信濃町9番地で誕生
○11.鹿鳴館開館12.ブラームス交響曲第3番初演
17(1884)年満1歳※父本岡龍雄はもと沼津(のちの菊間藩へ転封)藩士で御祐筆方、維新後は東京某小学校教師
○5.日本鉄道上野高崎間開通○6.不忍池競馬場開設7.華族令制定
20(1887)年4歳母ふみ(旧姓石井)は東京市立芝鞆絵小学校の唱歌教員で和漢洋の音楽に通じた
○10.音楽取調掛を東京音楽学校と改称(通称上野音楽学校※以下本年譜では音校と略す)
22(1889)年6歳○このころ四谷祥山寺の三銭(※自叙伝では半銭)学校へ通う
○2.帝国憲法発布◯7.東海道線全線開通
23(1890)年7歳〇4.上野公園第三回内国博覧会を父と兄と見物〇三銭学校を退学四谷小学校入学
○5.音校開校◯7.第1回衆議院議員選挙
25(1892)年9歳○7.3母ふみ没し小石川伝通院光雲寺に埋葬○8.新橋から神
戸三ノ宮の父龍雄の妹つねの婚家先田邊貞吉家へ9.兵庫県尋常師範学校付属小学校尋常4年生に転入
○12.チャイコフスキー胡桃割り人形初演
27(1894)年11歳○このころから土蔵にあった養父となる貞吉の蔵書を片端か6.音校が東京高等師範学校付属音
ら筆記しだし、これが田邊終世の筆記癖のもととなる
28(1895)年12歳3.兵庫県尋常師範学校付属小学校の高等2年生を修了
楽学校に格下げ8.1日清戦争両国宣戦布告
月中学に入学のため大阪西区江戸堀へ移る◎田邊貞吉(住友銀行初代頭取)と養子縁組し次男(義兄は壮吉)となる(実際の届出はM35.9.6)○大阪府第一尋常中学校入学音楽教師は宮内省楽師出の多梅稚(Vn、鉄道唱歌作曲者)
3.30日清休戦条約4.17日清講和条約調印(5.8発効)9.英国から救世軍渡来
29(1896)年13歳3.中学1年を修了〇南区南綿屋町に転居○大阪府第五尋常2.プッチーニのラ・ボエーム初演
中学校へ転校秋季遠足は池田、三田行
○12.スーザ星条旗よ永遠なれ作曲
30(1897)年14歳○褒美に養父からヴァイオリンを与えられそれより独学○校6.東京大学を東京帝国大学と改称
友会で家弓熊助の薩摩琵琶を聴き琵琶楽に惹かれる
31(1898)年15歳4年合同の修学旅行は紀伊で河内金剛山、大和五條、紀ノ9.オーストリア皇后エリザベート
川沿いに和歌山行
暗殺10.日本美術院設立
32(1899)年16歳4.第五尋常中学校は大阪府第五中学校と改称(のちの天王寺4.音校は東京高等師範学校附属を
中学校)
離れ東京音楽学校として再独立
33(1900)年17歳〇従姉小川てる子に恋心を抱く○3.第五中学校卒業5.高校○6.義和団の乱7.ツェッペリン号
入学で8年振り東京の神田小川町の実家本岡家へ〇実兄玉樹初飛行
の手引きで宮内省楽師多忠基にヴァイオリンを習う〇7.第一
高等学校入試落第○受験ため牛込横寺町梧陰塾入寮○正則英語学校と東京物理学校へも通う
34(1901)年18歳○新春塾門内の離屋に移り受験に備える◎7.第一高等学校合※一高在学中の校長は狩野亮吉
格○同月梧陰塾を退寮大阪東区島町宅へ帰り準備〇多忠基が辞め、ひき続き宮内省楽師大村恕三郎にヴァイオリンを習う
○9.上京一高第二部理科を志望○寄宿舎は中寮4号室
35(1902)年19歳◯一高音楽部結成○西寮へ移る
36(1903)年20歳春に大村恕三郎大阪音楽学校に移る◎4.神田一ツ橋救世軍
裏手の音校選科ヴァイオリン科で石野巍、頼母木駒子らに就
本格的に学ぶ5.22田邊が親身にヴァイオリンを指導した
一高1年生藤村操が華厳の滝に投身◯8.寄宿舎を出男子5人で本郷西片町10番地で共同生活
○1.八甲田山遭難2.清国纏足禁止
8.初の私大早稲田大学開校
6.日比谷公園開園12.ライト兄弟動力初飛行成功
37(1904)年21歳7.第一高等学校卒業◎9.無試験で東京帝国大学理科大学理2.8日露戦争勃発
論物理学科入学○ヴァイオリン選科での田邊の成績良につき、
音校管弦楽団員に抜擢お雇い外人教師アウグスト・ユンケルのもと第二ヴァイオリン第三席となる(M41.3まで)
38(1905)年22歳4.音校兼務の宣教師ノエル・ペリにつき1年3ヶ月間和声9.5日露戦争講和
学と作曲法を学ぶ◯9.小石川原町へ転居
227
39(1906)年23歳○毎日夜2時まで大学の勉強、3時間就寝、5時起床、2時間3.上野に帝国図書館4.鉄道国有
法施行◯新宿御苑開園
ヴァイオリン練習○マムシの生干しを天井に吊るし毎日2寸つけ焼きにして食べ乗り切る○友人中島六郎が牛込新小川町に新設した音楽講習所でヴァイオリン科講師に
40(1907)年24歳○卒業論文「管楽器の音響学的研究」7.東大首席卒業○芝高輪の養父別荘に転居◎同月長岡教授に田中正平博士を紹介され、邦楽研究所研究生となり約3年間各種の邦楽舞踊を習う
○同月多忙のため音校選科を退学◎同月東京帝大大学院に進み長岡半太郎教授の推薦で音響学を専攻(3年間)、文学部心理学科聴講生として元良勇次郎博士の研究室などで学ぶ○東大研究室の中村清二の影響で日本と中国の楽律に興味をもち中国行を意識する10.東洋音楽学校講師となり音響学と音楽史を担当(S10)
41(1908)年25歳4.美音倶楽部結成7.築地に移転○早稲田中学、早稲田高等
予備校、早稲田大学清国留学生部の講師(T7.3退)その縁で
留学生羅紀より琴の初伝を高田馬場の宿舎で授かる
○4.救世軍万国総督ブース大将来日
6年間に改正〇小学校義務教育
9.音校に邦楽調査掛を設置
11.清朝光緒帝と西大后崩御
12.宣統帝愛新覚羅溥儀即位
42(1909)年26歳7.豊国銀行頭取の長女村井八重子と結婚○牛込矢来町に新○10.伊藤博文ハルピン駅で暗殺
居を構える
43(1910)年27歳○春に矢来町から小石川区雑司ヶ谷町に転居○清楽家富田渓8.日韓併合
蓮と知り合う〇8.音校邦楽調査掛調査員(M43.11辞任)
45(1912)年29歳
○1.中華民国成立2.宣統帝退位
○4.渋沢栄一らの募金で仲御徒町に救世軍病院完成7.30大正改元
■大正
2(1913)年30歳2.27長男秀雄誕生◯東京盲学校嘱託講師として音楽理論と○5.ストラビンスキー春の祭典初演
音楽史を講義(S39.3退)
3(1914)年31歳○東北帝国大学理学部臨時音響学講師○宮内省楽師薗兼秋
7.第一次大戦勃発12.東京駅開業
○小石川区老松町に転居
よび大原重朝伯爵、重明父子より雅楽の実技を習う11.20長女美津子誕生
4(1915)年32歳
6(1917)年34歳
8(1919)年36歳
9(1920)年37歳
9.30夜半風速42mの台風に遭う〇大阪毎日新聞社社長本山彦一の口添えで養父が田邊の研究が自由にできるよう下落合に新居を贈呈、11月に完成し終の住処となる
4.宮内省雅楽練習所音楽理論、音楽史講師(4年間)
1.財団法人啓明会より東洋音楽研究のため研究費1万円を支給(4年間)○4.東久邇宮殿下に音楽論ご進講○吉備楽を学ぶ(3年間)○11.正倉院御物楽器の音律調査および宮内省蔵の楽器調査研究
10(1921)年38歳3.北白川宮殿下に音楽ご進講4.朝鮮李王職の雅楽を調査研究○12.文部省邦楽調査委員〇同月音校に邦楽科として、能
·
楽箏曲長唄の三科設立の可能性と具体的方法を審議、その成績を議会に提出
11(1922)年39歳○このころ日本胡弓を改良した玲琴を考案4.台湾総督府の援助で台湾全土の生蕃音楽および福建アモイ系の南音の調査
○5.朝香宮殿下に音楽論ご進講○久邇宮良子女王殿下(昭和皇后陛下)に音楽論ご進講ο7.琉球および八重山諸島の音楽調査(2ヶ月)
○ザックス・ホルンボステル楽器分類法提唱
08.のちの甲子園野球大会始まる
2.ニューヨークでディキシーランドジャズ初のレコーディング
○5.中華民国五四運動
1.国際連盟成立日本加盟○2.最初
5.上野公園で初メーデの箱根駅伝〇
○4.メートル法公布尺貫法と併用
○7.上海で中国共産党第一次全国代表大会開催
11.オスマントルコ滅亡
12.ソビエト連邦成立
12(1923)年40歳1.文部省社会教育課より民衆娯楽調査委員○4.国学院大学
教授○5.中国音楽調査行(2ヶ月)7.佐渡の音楽調査◯8.
太アイヌ、ギリヤーク、オロッコの音楽調査
9.1関東大震災
10.トルコ共和国成立
13(1924)年41歳7.伊豆大島の音楽調査○宮内省御物管理委員として宮中楽1.皇太子裕仁親王ご成婚、上野公
器の調査
14(1925)年42歳3.考案中の玲琴が見砂知障の製作で完成○3.日本初の仮放送で宮城道雄の箏と吉田清風の尺八田邊の笙を放送、本放送以後は全国で放送○4.秩父宮殿下に雅楽論ご進講5.高松宮殿下に雅楽論ご進講
園と動物園下賜O7.甲子園球場完成
11.救世軍病院を買収し懸案の環状線鉄路(現山手線)となる
15(1926)年43歳
◎12.25昭和改元
■昭和
2(1927)年44歳○宮城道雄、中島雅楽之都、中尾都山、町田佳声らと成和音○2.JOAKはじめてオペラのカバレリ
楽会を組織、新日本音楽の興隆に励み、全国演奏旅行
4(1929)年46歳
4.26帝国学士院賞受賞
5(1930)年47歳
4.東京帝大文学部講師(定年まで)日本音楽史
6(1931)年48歳
11.日本邦楽学校講師(S18年廃校)
7(1932)年49歳
4.賀陽宮殿下に音楽論ご進講
9(1934)年51歳
10(1935)年52歳
4.明治大学文芸科講師
11(1936)年53歳
7.東洋音楽学会設立初代会長となる
ア・ルスティカーナを放送
○東京市ドン(午砲)廃しサイレンに
○1.梅蘭芳来日○9.ドイツ総選挙でナチ党躍進
○4.音校作曲科新設
○10.東京市35区制定
5.音校講師8.南洋庁嘱託で南洋諸島の音楽舞踊の調査研3.満洲国執政溥儀皇帝に究
○4.溥儀来日○11.ホルンボステル没
○1.シャリアピン来日○6.音校に邦楽科新設○テレフンケン円盤型録音器
12(1937)年54歳8.第7回世界教育会議音盤教育委員ο9.日本大学芸術科講〇7.支那事変勃発
師(S16.9辞)
14(1939)年56歳12.文部省演劇映画音楽改善委員
15(1940)年57歳○満洲国政府の委嘱で満洲音楽調査
○6.男子長髪女子パーマネント禁止
○9.電音NHK型円盤型録音器完成
○9.日独伊三国同盟
16(1941)年58歳4.文部省聴覚訓練準備調査委員○9.文部省国民精神文化研○12.8日米開戦
究所の嘱託音楽研究員拝命
18(1943)年60歳○還暦○9.法政大学講師
19(1944)年61歳11.4妻八重子急逝
20(1945)年62歳
21(1946)年63歳
22(1947)年64歳○早稲田大学講師(S30.3)
○1.「前線へ送る夕」放送開始
○6.市から東京都となる
○8.グアム日本軍全滅
○8.15大東亜戦争終結
○11.3日本国憲法公布
○5.3日本国憲法施行3M社磁気録
音テープ発売※翌48.LPレコード開発
24(1949)年66歳○4.武蔵野音楽大学教授(S44.7)○東京電機大学講師(S39.3)○8.20下谷の広徳寺で朱舜水将来の明琴を調査
○5.新制東京芸術大学発足
25(1950)年67歳
○12.文化財専門審議委員(S40.3)
27(1952)年69歳31(1956)年73歳
○4.東京学芸大学講師(S40.3)
○3.最後の卒業式をもって音校廃止
32(1957)年74歳
○11.紫綬褒章受章
○1.南極越冬隊初上陸○12.溥儀の姪慧星(学習院大生)天城山心中
○9.日本文化人訪中団団長として1ヶ月半中国音楽旅行
○6.朝鮮戦争勃発
○12.カストロがキューバでゲリラ戦
33(1958)年75歳
○31年訪中団の答礼として戦後初の中国歌舞団訪日が実現し主たる接待役となる
◎5.左記歌舞団が長崎国旗事件で急遽帰国、S47.9国交正常化まで断絶
35(1960)年77歳○4.正派音楽院講師◯8.鹿児島で薩摩・盲僧琵琶調査
○9.カラーテレビ本放送
38(1963)年80歳
○傘寿○08.熊本にて肥後琵琶調査○12.東洋音楽学会が九学会連合に加盟その顧問となる
○11.ケネディ大統領暗殺
39(1964)年81歳
○10.関節炎で自宅療養
○4.海外観光渡航年1度自由化
40(1965)年82歳
○4.都立広尾病院に入院〇11.3勲四等旭日章叙勲
○3.淀橋浄水場廃止○フィリップス社互換性を条件にカセット特許無償公開
42(1967)年84歳○11.救世軍杉並療養所(翌年同ブース記念病院と改称)へ
○5.中国文化大革命はじまる
44(1969)年86歳○9.任意団体東洋音楽学会が社団法人化初代会長に
○1東大安田講堂攻防戦
46(1971)年88歳○米寿
○2.アポロ14号月面に
56(1981)年98歳○6.赤坂プリンスホテルにて白寿(数え)の祝賀会○11.3文化功労者に認定
○2.有楽町日本劇場閉館
57(1982)年99歳○白寿
○8.フィリップス社世界初CD製作
58(1983)年100歳○百賀○音楽学上の功績者に対し東洋音楽学会が田邊尚雄賞を新設
○9.国立能楽堂開堂
59(1984)年101歳○3.5救世軍ブース記念病院で没す○3.23信濃町千日谷会堂にて東洋音楽学会葬
○4.大阪国立文楽劇場開場
2012年7月7日
28
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第101話
国宝『碣石調幽蘭第五』 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
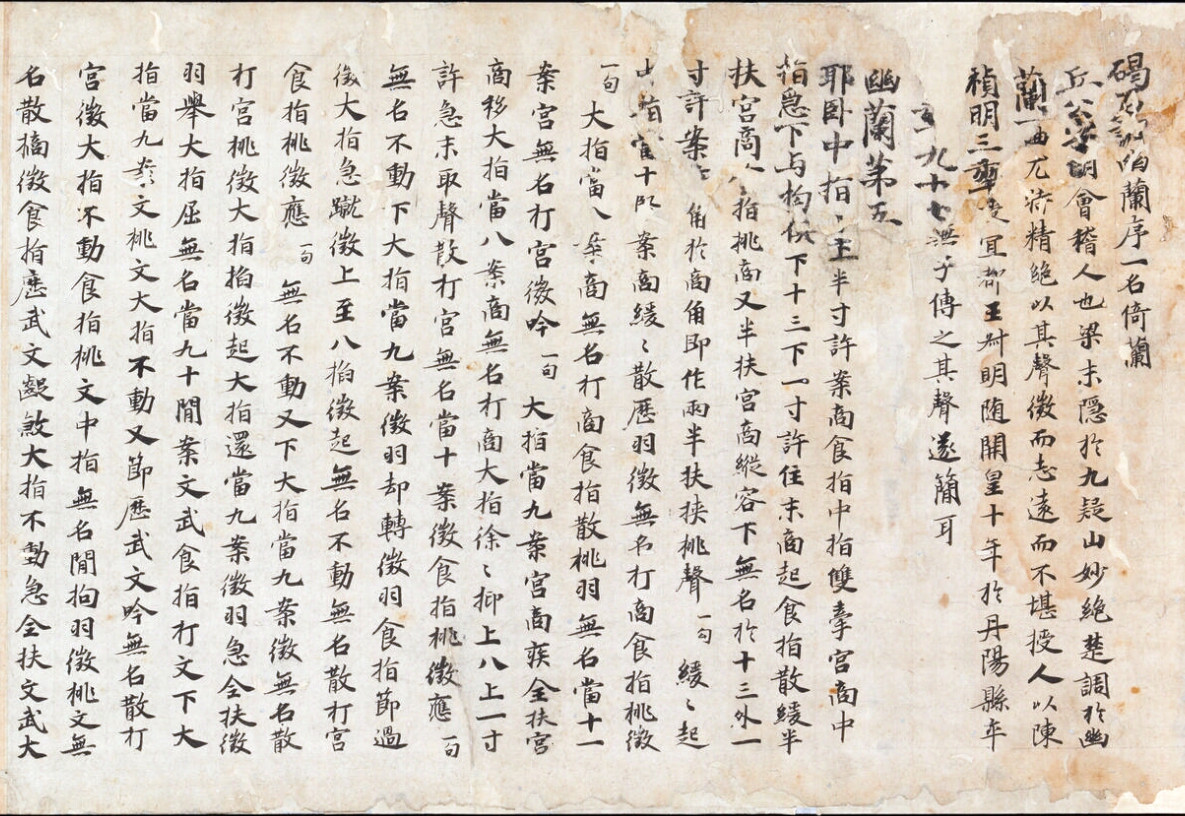 いにしえ、和漢の文人たちがこよなく愛した楽器が「琴」(きん。俗称七絃琴)であり、そのための専門の楽譜が「琴譜」(きんぷ)である。
いにしえ、和漢の文人たちがこよなく愛した楽器が「琴」(きん。俗称七絃琴)であり、そのための専門の楽譜が「琴譜」(きんぷ)である。その琴譜には二種類あり、一種は隋唐以前の琴譜で弾奏法やテンポ、また楽想などを文言文の文字で綴った「文字譜」といい、もう一種が、初唐の趙耶利(五三九~六三九)が発明して以来、現在までも変らぬいわゆる「減字譜」といわれるもので、漢字の字画をいったんバラバラにし、必要に応じて再合成し組み合わせて意味をもたせる現通行の「琴譜」で、約一千年間以上使用され続けている。
ここに『碣石調幽蘭第五』、通称「幽蘭」なる六朝の伝譜で唐人手抄本一巻「文字譜」の琴譜があり、何と!日本の国宝となって、いまは上野の東京国立博物館が所蔵している。
世界的に見ても国宝の楽譜などはまず少ないであろうが、さて、これが琴譜であるからには琴を演奏するための楽譜であること無論であるが、ではいったい単なる琴譜が何故に国宝に指定されたのであろうか。
中国にもない現存最古の琴譜であることがその第一。第二が現存する世界で唯一の「文字譜」であること。第三が書風からの観点で、唐代流行の楷書で均整のとれた斉筆で筆力の強い書風であるため、これが書写された時期を初唐と推定できる根拠となり、また巻首の残闕を補った筆跡も同一風で唐人の書とみられる。
幕末、福山藩医の医家森枳園(一八〇七~一八八五)編纂の『経籍訪古志』に収録され、ついで清末の黎庶昌(一八三七~一八九七)の『古逸叢書』に入り、広く世に、といっても中国国内に知られるようになったのだが、『経籍訪古志』に模刻図版はなく、『古逸叢書』の準拠した「幽蘭」種本も、実は原譜ではないのは、左掲の事由による。
黎庶昌は初代駐日清国公使の何如璋(同治の進士。一八三八~一八九一)に続き第二代公使を勤め、その後再赴任して第四代となったが、その折、中国では逸書とされた古籍で日本にのみ残る善本を模刻し、日本で印刷刊行した叢書こそが『古逸叢書』で、その二十四巻に「幽蘭」を収めたのだが、惜しくもこれは原譜ではなく、幕府の医官で考証学者の小島宝素(一七九七~一八四九)自らが臨模した抄本「宝素堂版」と呼ばれるものを模刻したもので、中華民国から人民中国一九八〇年代までの引用の大半は、この『古逸叢書』版をさらに影印したものである。
初代公使の何如璋、二代黎庶昌の幕僚でやはり同治の挙人・楊守敬(一八三九~一九一五)も日本で逸書を蒐め、この宝素堂蔵書を一括入手して中国へ帰国するが、その後の国共内紛を経て、現在、旧宝素堂蔵書はあらかた台湾の故宮博物院に納まっている。
さて、礼楽を重んじ、楽に通じた大儒・荻生徂徠(一六六六~一七二八)が、奈良南都楽家の狛氏から門外不出一子相伝の真物の「幽蘭譜」を借覧し、この難解な琴の文字譜に訓点を附し、さらには右手法には文字の右側に傍線、左手法には左側に傍線を引いて一目瞭然とし、『碣石調幽蘭』と題し、『琴左右手法』、『琴手法図』、『調琴法』、さらには和文で『琴学大意抄』なる一連の琴書を著したのは享保七(一七二二)年四月で、前記華人に先がけること百年以上も前のこと。その後心越流であるかないかにかかわらず、江戸の琴客たちは等しくこれらの写本を座右にし、遥か遠く六朝の琴音を偲んだもので、当時の写本がまま巷間に流布する。
狛家を離れた真物の「幽蘭譜」は紆余曲折を経た後、幕末京都の名物和尚和田智満(一八三五~一九一○)が神光院住職時代に入手し、一時は知人間の自慢の種であったものを、のちに東博に長期寄託、昭和の御代に改めて東博が購入し、その所蔵となったという経緯がある。(続)
荻生徂徠著『琴手法図』より「挑」
『碣石調幽蘭第五』の原譜は東京国立博物館公開のアーカイブで閲覧できるため、徂徠の『幽蘭譜』を参考に供するとしよう。
通常『幽蘭譜』は、巻末に『琴左右手法』、『琴手法図』、『調琴法』の三種を併せて合本としてある。
31
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第102話
荻生徂徠『幽蘭譜』 中
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
「琴譜」が日本の国宝に指定され、しかも本連載に見えつ隠れつする副題「東台琴客異聞」そのまま、東京国立博物館が現蔵すると前置きした。
『碣石調幽蘭第五』略称「幽蘭」は、六朝梁末の弾琴の名手丘公の伝譜で唐人手鈔の写譜である。
この原巻本の内容はというと、「幽蘭」(倚蘭とも)についての序文、本文に相当する弾法を文言文で書した文字譜があり、巻末には曲名が列挙してあるので、当時弾かれていたであろう琴曲も解る。
「楚調」、「千金調」、「胡調」、
「感神調」、「楚明光」、「鳳帰林」、
「白雪」、「易水」、「幽蘭」、「遊春」、
「緑水」、「幽居」、「坐愁」、「秋思」、
「長清」、「短清」、「長測」、「短測」、
以下略…、
と、最後の「楚妃歎」までの全五十九曲の曲名があり、本文「碣石調幽蘭第五」のみは、題下の註に「此ノ弄、宜シク緩ニ消息シテ之ヲ弾ズベシ」とあるので、往古はこれをユッタリと弾いていたことなども解る。
この原譜を借覧した大儒荻生徂徠がこれに訓点を施し、左記四種の短編琴書とを合册してより、一般、といっても直接の徂徠門高弟や、蘐園(けんえん)学派を通じて一部の学者間に知られるようになり、後には江戸の琴客たちが挙って手写するようになったことはすでにご紹介した。
以下、徂徠『幽蘭譜』巻末の「目録」である。 (筆者句読)
目録
一 幽蘭譜 一册
右左ニ朱引(しゅびき)イタシ、左手右手分明ニ見へ申候様ニ仕候。左右手法ト手法図御考合セ申候得ハ、大形相知レ可申候。
一 琴左右手法 一冊
先手被差下候琴指法、前後致混雑故、左手右手分ケ、重複ヲ除キ相認申候。
一 琴手法図 一册
右ノ左右手法、縛図ニイタシ候。
一 調琴法 一通
是ハ琴ノシラヘヤウニ候。
已上。 物部茂卿
それから、徂徠の琴学関係の著述中、識者にいっとう歓迎されたのが『琴学大意抄』で、これを書き上げたのが享保七(一七二二)年四月二十八日のこと。
「幽蘭」に触発されてより、琴の大意を一般にしらしめんものと、琴学の初歩から説きはじめ、これを本邦にのみ遣された「雅楽」と関連づけ、さらには「礼楽」そのものにまで学者の興味を牽引しようと意図した一連の啓蒙書の一つでもあった。
ちなみに、江戸期通行本の『徂徠全集』などに収録されず、上梓もされなかった琴書を含む徂徠自著の「楽書」は、一部の高弟のみが閲覧・抄写を許され、一般の門人には楽書は秘されていたふしがある。
また、昭和期刊行の二大「徂徠全集」にも、楽書の収録は一部もないまま、しかも未刊で終わった。
「琴学大意抄目録」
一 琴ノ起リノ事
一 琴ノ名義ノ事
一 琴ヲ弾セシノ事
一 琴匠ノ事
一 琴ノ名所ノ事
一 軫ノ事
一 徽ノ事
一 絃ノ事
一 一琴ノ調様ノ事
一 琴七絃十三徽ノ定位ノ事
一 三ノ声ノ事
一 指ノ名ノ事
一 右指法ノ事
一 左指法ノ事
一 譜ノ文字ノ事
一 琴ノ廃レタル故ノ事
附 品舷
(続)
 「順八逆六図」
「順八逆六図」荻生徂徠著『琴学大意抄』
享保7(1722)年4月成稿より
21
△目次TOP↑
秋月※荻生徂徠著『琴学大意抄』については次を参照:「琴の調様の事」「琴七絃十三徽の定位の事」のデジタルテキスト
瘦蘭齋樂事異聞 第103話
荻生徂徠『幽蘭譜』 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
東京国立博物館現蔵の国宝「碣石調幽蘭第五」は、狛家の手を離れ、流転したのち、明治期に京都神光院中興の和田智萬和尚個人の所蔵となったと前述したよう、収集癖をもつ和尚はもともと別なものを欲したが、かわりに該譜を手に入れたため、当時の琴客・楽家ともに垂涎の的であった「幽蘭譜」を、琴客でもなく、まして音楽に趣味があったわけでもない和尚が一コレクターとして入手したことから、友人たちの顰蹙を大いに買ったと伝わる。無論、遠い明治の話しである。
図版冒頭部分「序」の五行を読んでみる。
碣石調幽蘭の序一名は倚蘭。
「碣石調」
調名である。なになに調という意で、特定の楽曲を弾くためには、何調で演奏するのか、またそのためには琴の七絃をどんな調絃にせねばならないということで、洋楽ならばハ長調とかニ短調の曲をどん調絃で、ということになる。
本邦古人は琴曲「幽蘭」における碣石調は不詳としながらも、「碣」と「乞」が音通で「キ」、「石」と「食」が「シ」であるところから「乞食調」(大乞食調とも)と捉え、さらに「大食調」(大石調とも)にあてた。
徂徠も、
「幽蘭ノ譜ヲ碣石調トアルヲ、今ノ乞食調の事ナリト考ヘタルモ、奏調ヲ合セミレハ明カナリ、故ニ今奏調ノ五調ノ図ヲモ左ニ出スナリ、幽蘭譜ノ抄ニモ。縵角調ノ奏調ヲ、朱ニテカタハラニシルシヲクナリ、云々」
として、大食調は基音が「黄鐘商」であるから、日本十二律(下から順に高く)の、
「黄鐘(A)・盤渉(B)・上無(C#)・壱越(D)・平調(E)・下無(F#)・鳧鐘(G#)の七音」
ABC#DEF#G# 1234567
としたので、一見すればそのまま七絃順に対応するようにも錯覚するが、実は十三徽に割りふったもののため、五声の音階になおせば、
宮絃を黄鐘(A)、商絃を盤渉(B)、角絃を上無(C#)、徴絃を平調(E)、羽絃を下無(F#)、文絃を黄鐘(a)、武絃を盤渉(b)
ABC#EF#ab 1235612
に調絃するのである。
()内音名は筆者が現在の洋楽に相当させたもの、「奏調」とは、またの連載中にご紹介するとしよう。
「幽蘭」
琴の曲名である。白居易の七絶「聴幽蘭」にも、「琴中の古曲は是れ幽蘭」とある。
「一名倚蘭」
『琴操』十二操中に「倚蘭操」がみえる。
次ぐる「序」は丘公の小伝となる。「丘公字八明、会稽ノ人也。梁ノ末ニ九疑山ニ隠ル。楚調ニ妙絶ナリ。幽蘭ノ一曲ニ於テ、尤モ特ニ精絶ナリ。其ノ声微ニシテ志遠キヲ以テ、而シテ人ニ授ルニ堪へズ、陳ノ禎明三年ヲ以テ、宣都王叔明ニ授ケ、随(ママ)ノ開皇十年、丹陽県ニ於テ卒ス。時ニ年九十七。子ノ之ヲ伝ル無シ、其ノ声遂ニ簡ナルノミ。」
真物「幽蘭譜」冒頭上部本紙の欠損は激しく、とくに「丘」字以下の三字と続く部分は、寒斎の徂徠本などでは、「丘公子明、会稽人也」とある。図例の真物では、
「丘公字明、会稽人也」と解るものの、写真図版では本紙と補填紙、また虫損との区別が判然としない。
「会稽」
春秋時代のに越王勾践と呉王夫差との故事、「会稽の恥」で知られる地である。
「梁」 六朝期南朝の梁。
「九疑山」
湖南永州にあり、伝説の帝王舜を葬った地で、のちの世にこの九疑を慕い隠れた琴客がある。
「楚調ニ妙絶ナリ。幽蘭ノ一曲ニ於テ、尤モ特ニ精絶ナリ。」
徂徠曰く、「琴ノ調ニ五調アリ、瑟調、平調、清調、楚調、側調ノ五ツナリ、…漢ノ代ヨリ六朝マテ、琴ノミニ限ラス、楽ミナコノ五調の外ニ出テス」と。ならば、前記の大食調がすなわち楚調ととれようが、古代の琴において常用した調絃法五調のうちの一が楚調で、その楚調で弾かれる幽蘭の曲に、とくに丘公は秀でていた。
「陳」六朝の一。
「禎明三年」西暦五八九年。
「宣都王叔明」
宣都の王叔明ではなく、宣都の王・陳叔明。陳の宣帝の第六子・叔明、字は子昭(五六二~六一四)のことで、呉の興長(現在の浙江長興)の人である。ちなみに、江戸初期にわが国に投化した陳元(一五八七~一六七一)は、この陳明九十三世の末流であったという。
「随」隋朝。
「開皇十年」隋朝最初の年号で西暦五九〇年。
「丹陽県」
秦代の曲阿県が雲陽県となり、唐代天宝元(七四二)年に丹陽県(現在は丹陽市)と改められたので、本譜の書写は唐人の手になり、その年代は天宝元年以降とされる一大根拠となる重要な語句である。
序末の「簡」徂徠の話では「すくなきことなり」とするが、ここは素直に「おおまか」、「おろそか」ととり、丘公が逝き、叔明一人が幽蘭を伝えていたが、これも絶えて、いまでは幽蘭の秘曲(あっても)は、その水準に達しない「おおまかな」ものばかりとなってしまったとの意で、続く本文概要はまたの機会に…。
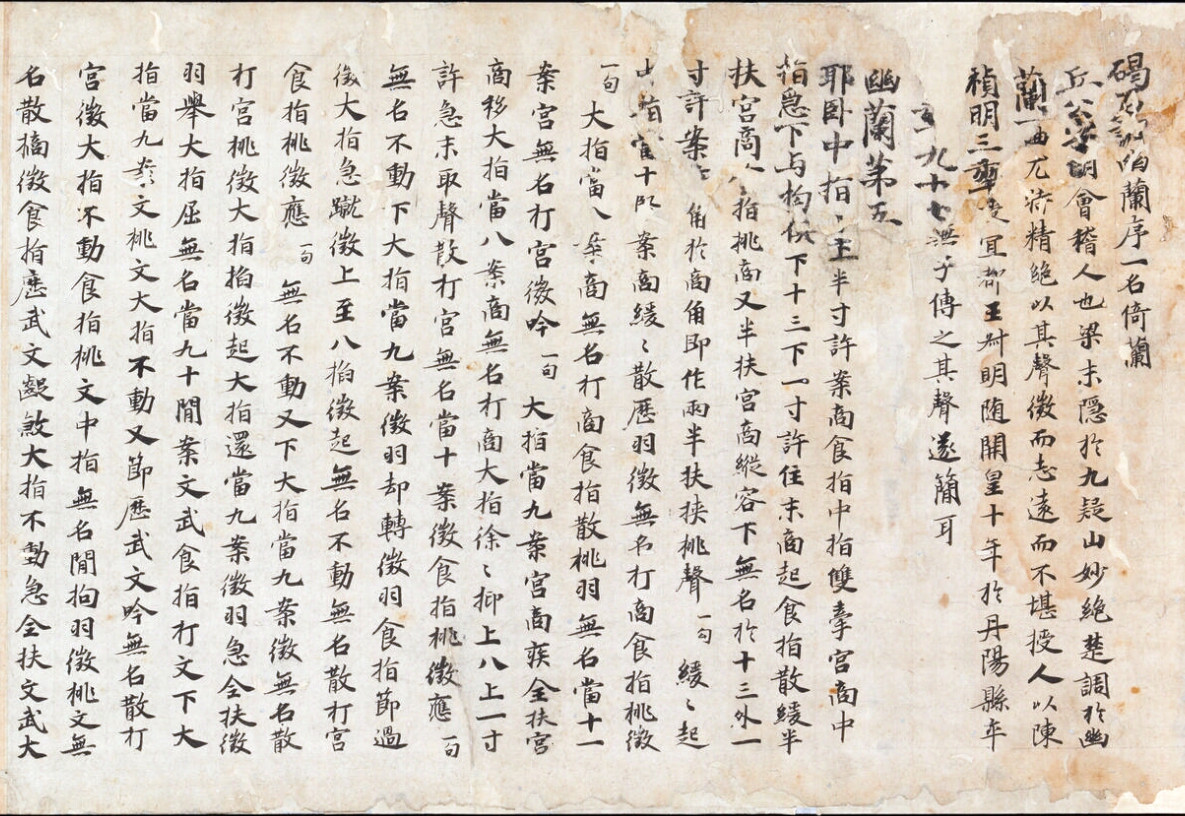 国宝「碣石調幽蘭第五」(部分) 唐時代 東京国立博物館蔵
国宝「碣石調幽蘭第五」(部分) 唐時代 東京国立博物館蔵(展示:2013年1月2日~2月24日東洋館8室)
しばらく耐震補強工事で休館中だった東博・東洋館が、来春一月二日に新装開館する由。其処でおりよくも、拙稿連載中の『碣石調幽蘭第五』が展示されると漏れうかがい、読者諸賢におかれては、会期中ぜひとも真物を肉眼で鑑賞の上、お確かめいただきたい。
1月5日(土)14:00~於・旧東京音楽学校奏楽堂
坂田進一先生出演新春音楽会「シュランメルとウィーン小唄」の招待券を6組12名様に。応募方法はp.90参照
21
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第104話
浦上玉堂雑感 一
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
百話を超えた拙稿。これひとえに読者諸賢と編集子の忍耐の賜物と改めて感謝する次第だが、沈思すれば書界の方々には、さぞかし読みにくく、かつ独りよがりな拙文の連続であろうかと頻りと自省するものの、ただ筆者にすれば他愛ない「楽事」の反芻とて、その禿びた筆先はまたぞろ楽界、古怪の代表・玉堂故居の彼方へとしばし歩まんとする。
浦上玉堂(一七四五~一八二〇、以下玉堂と略。本連載1話参照)は江戸期文人画家として、後にブルーノ・タウト(一八八〇~一九三八)により紹介されたことで世界的にも知られるようになったが、実はその本質は、中国文人を憧憬し、模倣しながら咀嚼して成り立った、より日本的な文人を代表する人物でもある。
だが、ここではなによりも君子四芸中の筆頭である琴を生命とした古楽家であったことを忘れてはならない。こうした玉堂の音楽方面は幕末以来の一時期、忘れられていたのだが、明治このかた玉堂の絵画が改めて注目されだし、それが前記したタウトなどに引き継がれ、以降、現代にまで絵画再認識の研究は連綿と続けられている。
ただ、玉堂自筆が落款によく用いた「玉堂琴士」として、世の識者たちには認識されはしたものの、だからといい、玉堂の本質である実際の音楽的考証(多少はあったが、大半は初歩的なもの)が実際になされたかというと、これまではほとんどされず(できず)に、長い歳月、一部の玉堂愛好家や美術史家たちのイメージの産物として琴韻は一人歩きし、語り続けられてきた感があることもまた否めない事実である。
まだ筆者年軽のころ、中国琴学を経てすでに日本の琴学に興味をもち、画人玉堂以前にその本質である琴人玉堂を本邦琴学系譜中に認め、また、ヴァン・グーリックの大著『琴道』や、新楽閑叟の『絲桐談』、中根香亭の『七絃琴の伝来』などの江戸琴学の基本文献はもちろんのこと、『玉堂琴譜』、『玉堂雑記』、『猶龍譚概』等々を貪り読んだもので、当時、画人玉堂の本質はやはり琴客であるとの認識も新たにしたことであった。
筆者自らが『玉堂琴譜』を研究して音にする以外、玉堂の琴音らしきものを聴けたのは、雑誌『古美術』第三十号(一九七〇年三彩社刊)附録のソノシートによるもので、その演奏者は当時東大駒場の比較文化研究室に留学中であった香港の張世彬氏で、音楽史家岸辺成雄先生指導の下で博士号を取得したが、その師弟ご両氏ともにいまは亡い。
シート収録曲は、『玉堂琴譜』所収の「伊勢海」と「我駒」、それと中国琴曲定番の「陽関三畳」とで、玉堂愛好家や美術史家は、はじめて聞く玉堂の琴音ということもあって、この演奏のソノシートは一時かなりの評判となったものである。
ただ惜しむらく、玉堂の音楽は雅楽中の郢曲(えいきよく)(日本の国風曲)と密接に関わっていて、『玉堂雑記』にもあるように、その演奏にあたっては古楽や雅楽を深く研究熟知せねばならなく、「陽関三畳」は数ある琴曲中の定番とて、張世彬氏の演奏もそつがなく無難なものの、肝心な曲は玉堂の「伊勢海」と「我駒」である。
 明琴「霊和」(『古美術』第30号1970年刊より)
明琴「霊和」(『古美術』第30号1970年刊より)浦上玉堂が35歳で入手したいわゆる「玉堂琴」である。右が琴面で左側が琴背、琴式は「連珠式(様とも)」に分類される。
正式な銘は「霊和」だが、命名した前所蔵者の印記「玉堂清韵」(韵=韻)より採り玉堂は自号としたことが解ろう。以後は玉堂琴士と称しこの古琴を生涯の伴侶としたのだ。
1970年に筆者も鑑賞したが、惜しいかなそれ以降42年、現在までも行方は杳として不明である。
27
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第105話
浦上玉堂雑感 二
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
たとえば三百年前の大バッハの埋もれた作品を演奏しようとする。当然ながらわれわれは楽器と楽譜を媒体とし、これを芸術的に再現しようと苦心するわけだが、こと楽譜に限っていえば、大時代的な自筆原譜の書き癖はさておき、浄書統一した五線譜から印刷された楽譜を、音楽家はその通りそのままに弾けばよい。しかし、こと和漢の琴曲の場合のみは、事情は大きく異なるのである。
琴譜(きんぷ)はもともと拍節を表記しない伝統がある。で、琴譜は遺るがすでに失伝忘却されてしまった琴曲を再現するには、これに「打譜」という作業で新たに妥当性のあるリズムをつけ、眠れる音楽を蘇生させるという重要な過程を経なければならない。浦上玉堂が多紀藍渓(連載第2話)に就いて一時学んだ、江戸琴派の主流心越派のテクスト『東皐琴譜』を現在演奏するに際しても、この打譜を無視するわけにはいかないのだ。
ただし、『玉堂琴譜』所収の琴曲は純然たる玉堂の作曲ではなく、先行する平安朝「催馬楽(さいばら)」遺譜である箏譜『仁智要録』と、琵琶譜『三五要録』を参考に、玉堂が「琴」の手付け、すなわち琴のパート譜としたもので、合奏を前提に作られてあるため、逆に二譜とピタッと合うこと、それこそがもともと玉堂の意図したところで、わざわざ打譜しなくもよいわけだが、だからといって、すでに催馬楽が廃れた今日となっては、『仁智要録』と『三五要録』の譜をそのまま演奏すること自体、豊富な経験の上に綿密な考証を要すること無論である。
幸い拍子に関しては、『玉堂琴譜』は朝鮮古来の「井間譜」に倣った升目で拍節を表記し、より正確度大を期してある。升内の拍子を指定された緩急いずれかの「雨垂れ拍子」で読め、との玉堂のアイデアで、乗りの良いリズム感は払拭し、極限まで待って待って拍子を打つようにするのが、雅楽郢曲伝統の拍子感である。
『玉堂雑記』なる楽書がある。実は『玉堂琴譜』を読み解くため「虎の巻」で、この『玉堂雑記』なくしては玉堂の琴曲は解明できぬと断言できるが、内容は、玉堂の古楽学習と、「催馬楽被琴曲説」、「琴に三調ある事」などの重要事項が示された訳鍵である。公刊部数が少なく、さらには現存少ない稀覯本で無刊記だが、内容により『玉堂琴譜』を上梓した寛政三(一七九一)年後、数年内の刊行と解る。
この『玉堂雑記』により、前に公刊した『玉堂琴譜』を直ぐさま補足せんものとかなり苦心したとみえ、玉堂の自筆稿本をみれば多くの添削痕跡が遺る。かく玉堂は多くの古楽書上で得た智識を翻案実施して得た結果、満を持して自らが意図し理想とした催馬楽に託した琴の手を、門人や識者、パトロンたちに齟齬なく伝えようとしたのである。
……博雅三位。其子信明。催馬楽の琵琶譜を作り。就中妙音院相国の仁智三五の譜を作り給へる。古譜を纂せるのミならず。大なる功にて不朽のたまものなり。弼竊(ひつひそか)に仁智三五箏琵琶の譜に依て。玉堂琴譜を作る[世に行ハる]顰(ひそみ)に傚ふと云べきのミ。実に妙音院相国の著述にて。尊伝すべきことならずや。三代房中の遺声漢秦古楽の雅音。及唐朝の燕楽。詞余の奏法。今尚皇国に存ずといふも可なり。……
と、『玉堂雑記』(図版)に玉堂自ら単純明解に語る事実を、美術界は百年間も等閑にしたことが、玉堂本来の琴音をいたずらに美化し、その後の長い年月を想像上の音楽としてしまった要因ではある…。
なお、引用文中の妙音院相国とは藤原師長(もろなが。一一三九~一一九二)、弼とは玉堂その人である。
『玉堂雑記』部分 無刊記 浦上玉堂著
21
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第106話
シュランメル残照
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
雑踏を避けチョイト寄り道である。
注連もとれぬ正月五日、新春音楽会と銘打ち、上野の杜のなか旧奏楽堂で、心暖まるウィーン下街の伝統音楽─シュランメルとウィーン小唄(十二話参照)と題する一場のコンサートを催したところ、「この冬一番の寒さ」にもかかわらず、大勢の聴衆が来場され、なかには『書道界』愛読者の姿もチラホラした。
その演目中に、われらトキオ・シュランメル楽団テーマ曲でもある、弟のヨーゼフ・シュランメル(一八五二~一八九五)が作曲した「ヴィンドボーナ」という曲がある。ヴィンドボーナとはローマ帝国時代のウィーンの古名である。歌詞は当時高名な歌手兼詩人のカール・シュミッテル(一八四九~一八九七)が書いたウィーン讃歌で、その内容はといえば、
神に祝福されし都ヴィンドボーナ
われらの心のよりどころ
オーストリーの真珠ウィーンよ
この地上に比ぶべきもの都なし…
という他愛ないもの。概してウィーン小唄などでは、自分が生まれ育ち、現在住む街を愛するあまり、こんな風に臆面もなく双手を挙げて讃美してしまうのだが、世界中なべての都を抱える国々は、それが古い都であってもなくても、それぞれ江戸っ子同様、手前味噌となってしまうもので、なに、ウィーン子とてもまた一頻りその気が強いだけなのである。なお「冬一番の木枯らし」とはヴインドボーナの別意である。
毎度いうよう、ウィーン庶民を代表する名物は洗濯女と辻馬車。これらの仕事に携わる人々がシュランメル音楽第一の支持層で、ついで新興市民、貴族、皇室へと支持層は広がったわけだが、なんといってもシュランメルはその庶民サイドの音楽で、彼らの強い味方であったことが筆者の眼目とするところである。
一方、ウィーン小唄の元祖といわれる「愛しのアウグスティン」(「お星が光るぴかぴか」の元歌)が十七世紀後半から歌い継がれ、これについで時事を織り交ぜ、庶民の哀歓、恋愛そして郷土愛を詠った小唄などが相ついで流行しだすのである。
十八~十九世紀にかけ、ハプスブルグ家の宏大な領地にまたがる汎チロル地方で愛用されていたハープやG管クラリネット(甘い小棒)、コントラ・ギターレまたヴィナー・ハルモニカなど、民族楽器ともいっていい特徴あるそれらが、すでにウィーン小唄と相性のいい伴奏楽器として定着化していたが、やや遅れてシュランメル(器楽)が流行するに従い、ウィーン小唄の伴奏はシュランメルの編成に集約包括され、ウィー小唄と兼用されるようになり、以後シュランメルとウィーン小唄とは不可分かつ表裏一体の関係が生じ、必ずペアで演奏されるようになったのである。
今じゃ俺らも六十歳になり
馭者台に座りはや四十年
馬車は似合いの連れ合いなのサ
墓場までも一緒に行こう
奔れ奔れ構わず四つ角でも
駆け足で行くんだ
立ち止まっちゃダメだぞ
誰でも一度はきっとやって来る
最後の引っ越しも
フィアッカー(辻馬車)で行こう
墓石に書いてくれ 誰にも解るよう
<リフレイン〉
自慢じゃないが ウィーン生まれ
他にない この俺らは
風のように軽やかな 生粋のウィーン子なのサ
タララ ララララララ ラララララ………(「辻馬車のうた」)
今回、シュランメル定番曲以外、とくに力を入れたのは筆者が新たに編曲した日本もの二曲と拙作で、せめてもの東京っ子の歯ぎしりである。
一、宮城道雄「春の海」
二、下絵皖一「夜」
三、坂田進一「双蝶の別れ」(続)
「旧奏楽堂ステージにて」
旧東京音楽学校奏楽堂は明治23(1890)年創建になり、かの滝廉太郎(1879~1893)は、15歳の少年で入学した明治27年からこの同じステージに立った。
左から筆者、奇蹟の美声と定評のあるソプラノの山田英津子さん、ウィーンもの伴奏の達人児玉ゆかりさん、少壮の学者丸山貴士君、高久暁教授。倉卒の撮影で画素も面相も低い?が、なぜかシュランメルの余情にはピッタリである。
55
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第107話
シュランメル残照 続
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
宮城道雄がシュランメル編成で「春の海」を書いたことはなく、筆者の編曲版があるだけのこと。さらに正月五日プログラム中の宮城小伝には魯魚亥豕と年次の誤りが多いため、ここに訂正させていただく。
シュランメル兄弟がウィーン楽壇の寵児として、なべての市民にもてはやされていたころのことである。
明治二十七(一八九四)年四月七日、後の天才的箏曲家宮城道雄(~一九五六。本姓菅)が神戸三宮居留地で、父菅国治郎と母アサの長男として生まれた。生後二百日で眼疾を患い、五歳のときに有馬で約一年間治療中、母は家出し父は再婚する。
明治三十五(一九〇二)年九歳で完全なる失明を宣告され、神戸水木通に祖母と同居しつつ、同年六月か九州系地歌箏曲を二代中島検校、二代目亡き後は同三代中島検校のもとで修業し、三年後の十二歳で箏と三絃の皆伝を受け、中菅道雄の芸名を許されて師匠の代稽古格となった。
この年、渡鮮していた父が暴徒に襲われ重傷を負い療養していたのを機に、明治四十(一九〇七)年の九月、道雄十四歳で仁川に渡り、健気にも箏と尺八を教授しつつ一家の家計を担ったのである。
十六歳で処女作「水の変態」を発表し、夏にはこれを時の朝鮮総督伊藤博文の前で演奏するも、十月に博文はハルピン駅頭で暗殺される。
十七歳で仁川から京城に活動拠点を移した。すでに当道座の官位は明治四(一八七一)年に廃止されていたが、互助団体と改組した当道会において大正元(一九一二)年十九歳で検校となり、同二(一九一三)年喜多仲子と結婚。仲子の生家宮城家を再興し、これを機に宮城姓を名乗る。十二月に内地を旅行し、翌三年に神戸の恩師のもとで未修曲を習い、三月に京城に戻る。
大正五(一九一六)五月、二十三歳で大検校に昇格。翌六年、熊本の長谷検校のもとで三絃を再修業し、いったん京城に戻り、四月に東京へ進出。麹町に借家するも妻仲子が帝大附属病院にて四十歳で急逝する。
翌大正七(一九一八)年の一月、市ヶ谷田町に転居し、吉村貞子と再婚。同八(一九一九)年五月に本郷の中央会堂(教会)で念願の第一回の作品発表会を開き、作曲家としてデビューする。
彼の作曲になる「春の海」は、いまでは正月に欠かせない定番曲として人口に膾炙しているが、昭和五(一九三〇)年、新春宮中歌会始の勅題「海辺の巌」をヒントに、曲想は失明以前に住んだことのある、父国治郎生家のあった広島県福山市鞆の浦を回想して得たものである。
前年にこの勅題が発表されるやすぐ作曲にとりかかり、昭和四(一九二九)年の十二月に完成。同時に日比谷公会堂で、宮城の箏と吉田清風(一八九一~一九五〇)の尺八で初演。この同じコンビで昭和五年の八月に録音した尺八版のレコードは六年のお正月にあわせて発売されたが、田邊尚雄(本連載86~100参照)や本居長世、町田嘉章らとの折からの新日本音楽運動などの勃興期と相俟って、順調に売れ行きを伸ばした。
こうした背景によりフアン層は広がり、その需要からも「春の海」の楽譜は、直後の昭和六(一九三一)年九月に大日本家庭音楽会から出版され、その後にも龍吟社や白水社の五線譜版があるが、ただ家庭音楽会版附録の尺八と箏の五線譜対訳版は誤植が多く、しかもおどろくことに初版以来八十年を経た今日にいたるまで訂正されていない事実がある。
「春の海」ハーモニカ譜坂田進一編曲
箏のパートをコントラ・ギターに移せばそのまま「春の海」のシュランメル版となるわけではなく、箏を模したギターを主としつつも、伝統を加味した新日本音楽として特徴づけるため、他のヴァイオリン、ハーモニカなどのパートは、ヘテロフォニック(単旋律の主題に、異なる旋律を一斉に重ねる手法)に処理し、しかもあくまでシュランメル風にアレンジせねばならない。
ちなみにハーモニカには二種あり、正しくは手のハーモニカ、口のハーモニカと分類される。いわずもがな、シュランメルでは手のハーモニカとなる。
32
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第108話
高士中根香亭先生 一
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
中根香亭(一八三九~一九一三)
 江戸は下谷長者町(現御徒町と秋葉原の中間)に生まれ育ったチャキチャキの江戸っ子武士である。
江戸は下谷長者町(現御徒町と秋葉原の中間)に生まれ育ったチャキチャキの江戸っ子武士である。幕末動乱期は幕臣の軍人として陸軍に、また一時は海軍に籍を置き諸処に奮戦したが、時に利あらず、徳川宗主の静岡藩転封に従い、沼津兵学校の教授となる。
ご一新以降は陸軍参謀局、また文部省に出仕し、致仕して後は野に下り編輯主幹として活躍した。
さらに世俗を絶ち、諸国を経巡り、詩文・随筆をものする隠逸の文人としての一面も知られる。
こうした香亭の業績と博覧強記ぶり、ことに高潔な人となりは明治期文壇や識者の間で喧伝(後の森銑三は香亭の詩文を高士の文学と称した)されたが、なによりも最後まで武士(もののふ)の矜持を崩さず、その気高さを貫き通した頑固一徹な高士である。
明治初期、新制日本陸軍内では、全兵士必読の教科書『兵要日本地理小誌』の著者・中根の本名で普く知れわたったが、自身が多くを語らぬため、まとまった伝記類がいまに少なく、したがって巷間の雑誌記事には誤謬が多く、また訂正もない。
そこで香亭自らが易簀(えきさく)時のために用意した次掲の「香亭自叙伝」、および自著中の断片と尺牘など、すべ他の筆によらぬ筆跡からこれらを手繰り寄せ、併せて本稿筆者の聞き及びなど、想い出すまま、気のつくままに「楽事」を中心に試みたおおよそが本稿である。前後、重複する部分がままあるも、平にご寛恕いただきたい。
「香亭自叙伝」(香亭口述筆記)
某名は淑、字は君艾。小字は造酒、香亭と号す。本姓は曽根、其の第二子なり。
天保十年二月十二日江戸に生まれ、幼にして中根氏に養はる。二尊我を視ること猶生む所のごとし。
長じて武技を好み、傍ら書を読む。学に師伝なく、百行修めず。唯二尊に事へて終始違ふことなきのみ。
幕府の季に仕へて監曹(かちめつけ)となり、歩兵指揮官に遷る。
明治元年徳川公に従ひて駿河に移り、沼津兵学校教授となる。
五年徴されて陸軍参謀局に出仕し、尋いで陸軍少佐に任ぜらる。
八年の冬病に罹り幾(ほと)んど起たず、因て職を辞す。
居ること五六年、文部省奏任編輯官となり、又数年にして罷め去る。
是れより復た世に出でず、日に文筆を弄して以て自ら楽しむ。
著書若干巻あり、皆観るに足らざるなり。
妻西村氏男彪並びに先だちて没す。是こに於て以謂(おも)へらく、天吾が家を絶てり。強ひて後を建つべからざるなりと。
晩節家を捨て、江湖の間に浪遊す。
最後に岳陽の興津に至り就居す。
偶病を得、大正二年一月二十日溢焉(こうえん)として逝く。
行年七十五、同地松林の中に於て火滅す。
遺命して骨を留めず、敢て怪を行ふに非ず、其の好む所に従ふなり。
右は、死期を悟った香亭が門人伏見道太を枕辺に呼び、口頭で筆記させ、その日付をさらに道太が補った本連載全編を通しての基本資料となるもので、これを本稿筆者が改行句読し、一部の送り仮名を改め(以降の引用例文も同じ)たものである。
また、左記の杵村小雅に答えた香亭尺牘中に、通行する小伝の誤謬を訂正したものがある。
某(それがし)、小名(おさなな)を造酒(みき)といへり。二男なるを以て、宅にて造酒二郎と呼びたることもありしかど、実は二字名なり。畸人伝に幹の字に作りたるは誤れり。
漢学は同書に僕、誰やらの門人の如く記したるは違へり。
僕十七八の頃、羽倉簡堂翁の塾に半年計り通ひたれど、其頃翁は聾を病みて応対も出来ざる程なりき。
其他浪人儒者生野臨犀の講席にも参じたれど、此人は安積艮斎が狂生と呼び居たる程の人物にて、人の師たる器には非ざりき。
朝川家は親類なれど遠方なりし為、是又一字も教へを受けず。
故に世間の学者違ひて、同門の友といふ者一人もなし。大要は有志の友三四人と会読・輪講・作文等をなして、互に切磨したるなり。
是実は聖堂流の学問の(を)を嫌ひし為め、斯様な(に)窮屈なる学問をしたるなり。今思へば愚の至りなり。
詩は十五六歳の頃より、大沼枕山の隣家に移り住みたる故、門人には非ざれど、益を得たること甚だ多し。是等は誤つて門人といひても辞せざるなり。
右の如く、漢学は総て独習なる故、固陋は免れざれど、明師に就かざりしより、自然力を用ふること多かりし為、今日にても書を読むことのみは、余程常人より上手なる様に自信し居るなり。呵々。……。
【名乗り字】
雅号の「香亭(こうてい)」については、今人に「きょうてい」と読むものもあるがその根拠はなく、香亭が没した家主の後裔と隣家の郷土史家は「こうてい」であると明言した。筆者つらつら思うには、一に、葬殮(そうれん)に際し人が担ったり、象に載せたりする香炉を納める小さな亭(四阿型)をいい、二は、李白「清平調」で知られた「沈香亭」が根拠であろうか。
名は淑(きよし)、字は君艾(くんがい)(きみか、とも)。幼名は造酒(みき)と読み、迷花(書)室主人、香亭迂人と好んで自称する。
迷花書室は東台の陰、根岸に構えた五十畝もある香亭庵名で、後に転宅する駒込曙町の書斎名でもある。
※筆者のうろ覚えである。その根拠を示せといわれるとはなはだ覚束ないが、この根岸旧居跡地こそが、中村不折が大正三年から住んだ、今日の「台東区立書道博物館」であると。
【出生】
天保十年二月十二日、下谷長者町で儒者の曽根氏の次男に生まれ、七歳にして下谷御徒町の幕臣御徒士の中根氏に養われる。
実父は儒者の曾根得斎(字は縄卿、諱は直)、実母は碩儒朝川善庵の娘で、香亭はその善庵の外孫にあたる。
香亭の少時とそれ以前、天保年間を中心に、下谷界隈にはキラ星のごとく著名な文人や学者、また芸術家連が点在したことを、香亭は記憶するまま『香亭雅談』に記した。
【武術】
幼にして剣術・心形刀流を江戸四大道場の一、下谷御徒町の伊庭秀業(代々軍兵衛を襲名す)の練武館に学び、馬術を稽古するも、安政年間に脚気を患ったを機(しお)に、武道専心の生き方を廃する。
【学歴】
儒学は清水純斎、羽倉簡堂、生野臨犀に就くもみな続かず、以後は定師に就かず、専ら姑君(養父の姉)恒(号小娥)の強い感化で、勉学自修に励み、併せて開成所へ通い、英学を友人の乙骨太郎乙、小林弥三郎、薗鑑三郎、石橋好一らに学ぶ。
(続)
「中根香亭小照」
明治7(1874)年写(『香亭蔵草』より)
香亭36歳の姿を写し裏面には、
「右某小照、明治甲戌在浪華所写、後十余年児彪命工、複写之。丙戌寒露節、香亭迂人中根淑」とあり、先逝した男児彪が、撮影12年後の明治19(1886)年、新暦9月に複写させたものであることが解る。
「一絃琴私説序」(未刊本)中根香亭著
中根香亭の著作中に、『一絃琴私説』と『一絃通史』の二書があり、後者のみ『香亭遺文』に所収される。
詳細は後述しようが、朝日新聞記者上田芳艸こと芳一郎は自著『一絃琴』を編むにあたり、斯界の大先達香亭に刺を通じ、「琴人伝」との名目で取材申し込みをした。香亭と彼の門人木村架空は、芳艸の人物に不信感を抱きつつも、一等高みの見地から、自筆稿本『一絃琴私説』を芳艸に貸与(郵送)してしまう。
案の定、香亭没後の翌年、『一絃琴』は出版され、その巻頭に、「中根香亭筆跡」(生前本書の為に起草せる序文の原稿)と偽り、かく「一絃琴私説序」を盗作したのである。
中根香亭筆蹟(生前本書の爲に起草せる序文の原稿)
序
八音之於耳。各有特長。而絲最切於人。據史舜彈五絃之琴。歌南風之詩。至周加文武二絃。千載不易永為定式焉。一絃琴長短形状。與此畧等。蓋其支流。以其簡素不華。幽人隱士好弄之。以故歷不甚顯也。我國古昔不閒有是物。前今百五六十年。浪華人以此度雜曲。漸行乎世。自是大小名手选出。而時有隆替矣。方艸上田君好文學。旁撫一絃琴。近者集古今士人中専従事於斯者姓名。探究其郷貫履歷。以作之傳。且附以歌曲及其註釋。名曰琴志。書
39
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第109話
高士中根香亭先生 二
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
本『書道界』ご愛読者諸賢に対し、拙稿連載がはたして有益なものか否かは、ご専門の立場それぞれで受取り方は異なろうが、浮生の出来事は糾える縄の如きものである。少なくも今回の記事は、一部好事家相手の江戸学擬きではなく、もとより知ったかぶりのものでもない。ただ、文人必須の「琴碁書画」中から読者の興趣ある事を提供共有し、かつて存在した一人の高士の生き様を知っていただきたいばかりからである。
で、予て傾倒する中根香亭先生についての雑考は長丁場となろうが、最後までお付合いくださるよう、ここに願い上げる次第である。
【迷花書室】
筆者寒斎は、名ばかりのさして広くもない仕事場兼練習場である。蔵書?巻を超え、そこへ古譜やら古楽器などが所狭しと居候し、常用せぬものは、さらに湯島切り通し下の貸倉庫と、本郷三丁目駅隣の、界隈で現存する一番古いとされるレトロなエチソウビル(越前屋惣兵衛の略)一角の分室に分散させてある。筆者うろ覚えで、香亭の迷花書室跡地こそ、たしか香亭の没後、書に深く傾倒した洋画家の中村不折(一八六六~一九四三)が購入した旧居であったと記憶し、それが台東区立書道博物館となったと前号で申し上げたが、他の資料を捜索中、なんとその証左が偶然、かつ速やかに愚眼に迷い込んだにはビックリ。一転してここに事実としてご紹介できることとあいなった。
香亭生涯を通じての書斎・迷花書室は、下谷仲徒士町・金杉村・本郷駒込曙町と、都合三度かわった。東台、すなわち東叡山寛永寺のあ上野台(地)の下北部が台ノ下で、同じく下谷とは湯島(本郷台地)や東台(上野台地)下の谷間の意で、江戸開府以前からの地名であり、根岸とは、上野台地の根っこ、音無川(石神井用水)の岸辺をいう。
正保三(一六四六)年、金杉村は寛永寺領となり、村の南は字根岸となり、時は過ぎて明治改元(一八六の九月、江戸は東京(とうけい)府となる。七年後の明治八(一八七五)年冬、病をえた香亭は陸軍参謀局を辞め、翌九(一八七六)年から時をかけ準備し、下谷仲徒士(御徒町四丁目から下谷最北端の東京府北豊嶋郡金杉村一八五番地の園田居へ移行する。
この土地は日本橋新右衛門町の質商太田惣吉から入手したもので、「官を辞しては田園生活に帰す」を理想とした古来の文人に倣い、三十八歳で念願をかなえたわけである。
草廬を営み、草花を愛でつつ、晴耕雨読の文筆活動を続け、新たに文部省奏任編輯官をも拝命した香亭は、金杉の書室に在ることほぼ十年。この間、明治十六(一八八三)年七月には草廬の南側間近に日本鉄道の鉄路が敷設されたため、騒音が読書筆耕の大きな妨げとなるが、かえって鉄道開業当時、上野駅と王子駅間にいまだ駅はなく、香亭は草廬から徒歩、または人力車で上野まで出てから鉄道を利用していた。
明治二十二(一八八九)年五月の市町村制施行で、金杉村の住所が東京市下谷区上根岸一二五番地と改正されるころには、年々押し寄せる開化の波を避け、すでに香亭は本郷区駒込曙町十六番地に転居しているが、これはずっと後のことである。
まずは稿をすすめるべく、迷花書室図を参照しつつ、香亭がこよなく愛でた書室とは、如何なる草の廬であったかを垣間みてみよう。
迷花書室記
古の君子には (以下書室の由来)
必ず好む所あり
而して其の好みを為すなり各同じからず
孔孟は仁義を好み
老荘は道徳を好む
申韓は刑名を好み
此れより以て往く (志向に邁進す)
韓柳の文に於ける
李杜の詩に於ける
王羲之張旭の書に於ける
劉伶畢卓の酒に於ける
白香山蘇東坡の伎楽と諧謔とに於ける(以上古人例)
人は偏を以て為さざれば
則ち以てを為すの他無し(興趣なんば閑悪に奔る)
臭味同じからざればなり
吾が性は花を好む (香亭の癖は)
一井一木愛惜措かず
嚢(さきに)は城北市井中に家す (下谷)
園は僅かに数十弓 (一弓は八尺)
花を養う地なし (庭が狭い)
故に東台の山 (上野の花)
墨陀の堤 (隅田の花)
花開けば必ず訪れ
雨にもまた往く
皆これを笑うも
余独りこれを楽しみて顧みざるなり
乙亥の冬 (明治八年暮)
疾を獲て官を辞し (陸軍参謀局)
因りて地を東台の陰に購い
移りて居す (下谷から金杉村へ)
園の大(ひろ)さ五十畝可(ばか)り(約五千m2)
南は山坡に対し (上野台地)
西は水田を臨む (書室の西側)
東北は村落に寄り (金杉村落)
松柏鬱茂す
老桜柯を交え (柯は枝)
其の間に仮山二と小流一あり
以て高低湾曲の勢を取る (以上地上景)
春風初めて至れば
梅杏桃李海棠桜花 (植栽景)
妍を争い麗を競う
二十四番 (節気)
次を逐うて開き落つ (次々に)
是(ここ)に於て余は欣然として喜び
怡然として楽しむ
日夕花の下に飲み
吟詠懐(おもい)を暢(の)ぶ
適(たまたま)李青蓮の月に酔いて (李白)
頻(しきり)に聖に中あた()り花に迷いては
君に事(つか)えざるの句に感有り(以上「清平調」と玄宗皇帝)
困りて其の室に名づけて
迷花書室と曰う
客の我に謂いて曰く
李句は花に先んじ君は後(おく)る
語意に弊有り
取るべからずと
余の曰く 然らず
君に事える者
未だ必ずしも尽く忠ならず
君に事えざる者も
未だ必ずしも尽く不忠ならず
忠と不忠とは人にありて
事える事えざるとにあらざる也
且つ夫れ迷と好みともに相依る
則ち之を好みて同せず
迷いて亦同せず
而して色に迷う者は身を傷め
名に迷う者は性を失し
利に迷う者は人を損ず
未だ花に迷いて
我と人とを害する者を聞かず
世の堂名を選ぶ者
或は実境を取り
或は仮想を取る
或は仁義道徳
或は礼楽刑政
或は詩文
或は琴酒と
唯其の欲する所をもってす
而して我は吾が好む所に従わん (陶淵明)
客は頭を掉(ふる)いて服せず
我も竟(つい)に之を悛(あらた)めず
筆者訓読および()内注
(『香亭蔵草』)
「迷花書室図」中根香亭画
明治19年刊『香亭雅談』より
香亭が金杉村根岸で営んだ草廬・迷花書室(屋)の写真がないものかと八方手を尽くしたが、まてよ、そういえば該書室図ならば『香亭雅談』巻頭にあるではないかと想いだした。
「迷花書室図
丙戌夏日、雅談の刻成りて、此を作し、以て序に代う。香亭」
けだし香亭の筆にも誇張があって当然で、文人画は景から情へとイメージの推移りを第一義とする。
上野の山を臨む松柏に囲まれた草廬には、二つの築山と橋(小川)があり、平屋の書室は母屋と分たれる。草廬の実景を心象化した筆意である。
画癖については改めてふれよう。
37
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第110話
高士中根香亭先生 三
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
春の一日、閑を見いだし、男坂下から湯島天神裏門坂通りをチャリで東へと、JR御徒町駅のガードを潜って左折し、これを真っつぐに上野駅正面口を金杉通りから言問通り、寛永寺陸橋を越えれば根岸である。
香亭の旧草廬周辺を一巡し、もとのタヌキ小路沿いで、折から家作の手入れをなさる老年のご夫婦に、「この路地はいまもタヌキ小路といいますか?」とうかがえば、「聞いたこともない」という。「では、何年ほどこちらにお住まいになりますか?」との問いに、「昭和二十年からだから、七十年近くになります」とのことで、謝して辞す。
書道博物館に駐輪し、受付姉を通し主任学芸員N氏を煩わせて簡単なご説明をうけ、館内出陳の書をザット鑑賞しながら、内庭の移築した迷花書室があったであろうところの写真を数枚撮り、暫しの感慨に耽る。
ついで小路を隔てた目前の子規庵に寄れば、まず手始めにビデオを視せられる。材料のない時期に復元したという座敷内は却って真物と紛うばかりで、その佇まいにあらぬ錯覚をおこしながらも庭をみやり、チョイトばかり明治の気分に浸る。
帰路、香亭草廬の水田であったところ、すなわちうぐいす小路の先の、しかも敷地内であったところに、小体でいかにも根岸閑人の侘び住まい風な茅屋が遺っているのにはビックリ。往時を彷彿とさせる佇まいに心惹かれつつ、愛車を押しやり高架を渡り線路を越せば、もうそこは御隠殿の坂で、辺りは谷中墓地となる。ただ、そこは天王寺の墓地にはあらず、寛永寺管轄の墓地で、ついこの先には本連載第2話の主人公・鄭永慶(可否茶館主)の分墓がある。
ついでに初代博物館館長の町田石谷の墓のある津梁院に寄り、桜木町から藝大を横目に、護国院、上野高校と、一気に暗闇坂を下ればもう不忍池(小西湖)畔で、根岸からゆっくり十五分もすればハヤ湯島である。
【天王寺】
香亭の生まれ育った長者町、御徒士町、上野も金杉村も日夕親しんだ街のなべてが下谷で、心身を育んだ形成基盤であるがゆえに、香亭戯筆に東台の天王寺界隈を題材とした『天王寺大懺悔』がある。
世にいう谷中天王寺は護国山尊重院天王寺といい、昭和三十二(一九五七)年の七月、放火心中事件で焼失した五重塔で知られる寺で、下図の塔がそれである。
長耀山感応寺は、文永十一(一二七四)年、日蓮聖人の弟子日源が創建した名刹である。
後にこの感応寺は、徳川家光公とその乳母春日局、家康公亡き後その側室であった英勝院の庇護のもと、約三万坪を下賜され徳川家の祈祷所となったが、さらにこれを元禄十一(一六九八)年、幕命で日蓮宗から天台宗に改宗させ、天保四(一八三三)年に天王寺と改号した。
小説のはしがき(明治十九年陰暦十月)に香亭自らが述懐する。
枕べのさうじ(障子)開きて、ふと向ひのかたを打見やれば、上野天王寺の山かげなる、木々の梢、いみじう染めつくしてげり、
春の花夏の緑きのふのごと思ひしを、名残の影もとめず、秋の色さへ老いまさりて見ゆれ、
とばかり、香亭は台ノ下の草廬から東台を眺めて暮らす。しかもそこは仏縁深く通い慣れたところでもある。
されど移りゆくものは四の時(四季)のみかは、山のあなたこなたにみちみちたる墓のぬしも、世にありしかぎりは、冨みて驕れるも、貧しくて諂へるも、才を恃みて人を凌げるも、頑にて、あらぬ道にまどへるもあるめれど、若きものは終に老い、生けるものはかならず死ぬることわりにて、しばらくも止めがたきは人の身なりけり、
一度苔の下に埋もるる身となりて、仏の御あかしに暗きころを照らされんには、生前の事ども思ひ起して、悔い愧ぢろはんふしも多かりぬべし、…
引用文()内筆者
明治六(一八七三)年七月、新政府は朱引内(しゅびきうち)(東京府中心部)の埋葬を禁止するが、土葬の神道派らの反対で火葬禁止令が布告され、同七年九月には天王寺(もと感応寺)墓地の一部を没収した谷中墓地をはじめ、雑司ヶ谷や染井・亀戸・青山(はじめ神葬墓地)の五箇所を東京府最初の公共墓地とする。しかし仏徒ら火葬を習慣とする者の猛反対で八年五月には前の火葬禁止令が解かれ、以来ようやく東京府での土葬は法度となるが、それでも人口の増加に伴い、十年もせぬうちに公共墓地は満杯となってしまう。
なお、香亭が該小説を書いた年、明治二十年末の人口は内閣統計局推計(昭和五年)では、全国人口が三八七〇万三千人で死亡率が一九七%の七六万一千人。東京府の人口が一五九万一千人と、香亭の目算よりは大分多いが、
…東京中の頭数を百萬人と見積つて、毎年二萬ぐらゐづつ、片の付くのは当り前、…
ざ(さ)れば上野の乾なる、天王寺の墓地を開きしより、僅か十年にも足らぬ間に、大小高卑長短方円、思ひ思ひの墓じるし、処せきまで立て並べ、積鬼といつては小むづかしいが、亡者どうし押し合って、火ともしごろの湯屋のありさま、鉢合せやら尻ぶつけやら、其の混雑いはん方なし、…
先年政府より、東京朱引内へは、以来土葬相ならずとの達しあつて、此の地が共同の墓地となりしより、朱引内に菩提所のあるものは勿論、其の外のものまで詰め込んで、かく死人稠密に相成ったが、…
と同書にいう。
上野から金杉村へは、御隠殿の坂が至近であるが、根津から天王寺、芋坂(いまの日暮里駅近く)へもあり、『天王寺大懺悔』本文には、
…うしろの村に住んで居て、いつもおそく茲を通る、小寺苦斎が、先刻塔(谷中五重塔)の前で、知つたものに行き逢ふて話すに、今から用事があつて、駒込まで往くが、帰りはおそくなるといつて居った、…
と小寺苦斎(香亭の筆名)の名をかり、別に東台に上らずに、仲徒士町から下寺(したでら)町、坂本町と奥州街道裏道(金杉通り)など、日常利用して香亭は往復していた。
こうした迷花書室における間居閒適の情景を詠った五律があり、これを読めば百三十年ほど以前の香亭の気持ちに多少なりとも近づけようか。
根岸閒居(『香亭蔵草』より)
朝去紅塵境
朝に去る紅塵の境
暮移台寺陰
暮に移る台寺の陰
酒廉因地僻
酒の廉(やす)きは地の僻なるに困り
鳥宿為花深
鳥は宿りて花の深きところをなす
時学桑麻事
時に桑麻の事を学び
殆為麋鹿心
殆ど麋鹿(びろく)の心をなす
都才距一里
都を距つこと才(わずか)に一里
有此好山林
此の好山林有り
下谷の巷間に生まれ、少年から青年まで過ごした自分である。
そうした人生の前半期から、暮れとは多少大仰だが、中年を迎えたいま、ここ台ノ下に転居した。
そこは辺鄙なところであるがゆえに物価が安く、ことに好きな酒などにいたってはなおさらである。
鳥が花の咲き乱れる樹々の奥深い時に安心して憩うようなここで、自分は晴耕雨読し、時には農事一般の真似事をしたりする。
官を辞したいまでこそ、はじめて麋(ヘラジカ)が湄(みぎわ)(麋(び)と音通、音無川)に群れ遊ぶ心境がわかるのだ。
※「朝纓初解佐江濱、麋鹿心知自有羣」(唐・許渾「出関」)
しかも都会から離れること僅か一里にも満たぬところに、こんなに素晴らしい別天地があるのだから…。
『天王寺大懺悔(てんわうじおほさんげ)』表紙
小寺苦斎著 明治20年4月金港堂刊
「迷花書室敷地」
明治21年「東京実測図」より
草廬には大邸宅ならずも家人のための母屋のほか、主人の書斎と居室および園林と圃田が必需である。
金杉村185番地が家人居住の母屋で、ここに現在書道博物館が建ち、該地図発行時はちょうど香亭駒込転宅期の前後と重なる。
184番地が香亭書斎と居室跡、無番の北側が園林、西側が水田となる。
100番地は明治5(1872)年に本郷から移転した旧加賀藩主前田侯邸の敷地で、図の左上から斜めの直線が日本鉄道奥州線。その鉄路とX状に交わる道が、谷中墓地から崖を下り金杉(上根岸)へ出る御隠殿の坂(いまの鴬谷駅近く※)。X字左部の墓地標示が谷中村字天王寺前である。
31
△目次TOP↑
秋月※鴬谷駅→日暮里駅?
瘦蘭齋樂事異聞 第111話
高士中根香亭先生 四
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
前号初校後、この二年分のデータをそっくり紛失してしまい、十回分以上余裕のあった香亭の原稿も、他の連載や書きためた論文数十本も、デスクトップ上の多くの資料もウソのようにすべて水泡に帰し、あろうことかバックアップもしていない。
こんな○○をカモとする世界のアキバに弊所は至近で、悪徳と本物の業者の見分けをつけがたいほどデータ復旧業者はより取りだが、五ヶ所ほど駆け廻ったものの、どうしても回復蘇生させることはできなかった。
はてさて、古来ナクした子ほど善くできたものとのお定まりながら、記憶はすでにボヤケ、筆は逡巡するばかりでいかにも覚束ない。しかしすでに渡し場を離れている。ひ弱な櫓漕ぎではあるが、どうにか向こう岸までたどり着かねばなるまいテ。ということで、主題とは着かず離れず、肩すかしの記事となりそうだが、諸般にめげずにまたぞろ根岸に参る。
書道博物館およびうぐいす横町の周りを徘徊するも、こたびは上海の友人・Y君(三仏右)と連れの僧D君(左)で、Y君は杭州仏学院の老師、これまたD君は飛行場のある浦東に、現在一大伽藍を建設中の老師で、コチトラは忘れているが、ン十年前に上海音楽院で愚生と会っているという。そういえば童顔をそのまま少年にすれば、何がしかの面影があるようなないような。だがそんな有縁だからといって、筆者が信心深い仏教徒であろうはずもない…。
この日、寒斎中の古楽資料をザッと見た後、不忍池(三仏キャプ中の堀氏造営になると。唐風粧して小西湖という)畔を抜けて東台に上り、清水堂から西郷サン、大仏などお定まりのコースを引きずり廻したが、せっかく筆者の引率だからと、芸大でK教官の許可を得て「清元」の授業を参観すれば、さすが音楽を長く嗜む二人である。教官の指導と邦楽の繊細さに頻りに感心し、目をパチクリしながらも、慣れぬ正座にシビレを切らしていた。ちなみに、いかに僧侶とはいえ、中国僧に正座の習慣はない。
アダシ物語りのツイデである。
(どこぞの国と違い)中国の僧侶は妻帯せず、魚・肉は食せず、モチ般若湯などは論外中の論外であるので、食事接待は気遣わねばならず、その点、藝大裏手の古馴染みの「愛玉子(オーギョーチ)」はなんら問題もなくホットする。
この日は彼らの興趣を第一に尊重し、ここいら東台にマツワル筆者の関心事項には目を瞑るものの、何とY君が書博へ行きたいというのを好都合に、そのまま谷中の墓地から御隠殿の坂を下り、香亭旧居跡を横目に真っつぐならば、目指す中食は彼らには仏供ともいうべき「笹の雪」。
食後、豆腐屋の下足待ちでご一緒した女性客三人組が、「この近辺でどこを見たらよいでしょうか」と訊くので、「ならば書道博物館」と一押しご同道すれば、門前の子規庵へサラワレ、われらのみ「唐代の書」展を開催中の書道博物館に入る。
筆者引率という意味では奇遇ともいえよう。Y君は前号既出のN主任学芸員女史とかつて一緒の仕事に関わったらしく、懐旧談ひと頻りの後、女史の筆者に曰く、「中村不折が大正四年、ここに転居する以前のお蔵新発見され、この内庭に移設する工事がすでに始まっています」というので、庭に目をやれば、小さな大谷石のお蔵が、もうそこに組まれつつあるではない
か。
「新旧御隠殿の坂」
野趣ゆたかな根岸を愛した香亭。その草廬跡の目と鼻の先にある小さな薬師寺堂祠が御隠殿の跡で、往時上野の宮様が通われる坂だから御隠殿の坂といった。
ふた筋の左側奥、電車が見える方が本来の旧坂で、鉄道敷設時に踏切に、後の昭和3(1928)年ころの架橋時に踏切は寸断されていまは渡れず、右側が跨橋の御隠殿坂橋となる。
「三仏」
二君ともかくも大仏さまに酷似すれば仏者冥利につきようもの。
そもそも寛永8(1668)年、澤庵禅師の友越後村上藩主堀直寄居士が戦士鎮魂のため釈迦如来漆喰像を寄進したのが上野大仏のはじめで、やがて金仏となり仏殿も喜捨されたが度々焼失損傷し、関東大震災後、壊れた大仏は寛永寺が保管していたが、その後の再建運動もふるわぬまま頓挫し、いまに至る。
30
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第112話
高士中根香亭先生 五
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
『書道界』七月号、書道博物館「江戸ワールド」なる展覧会案内文に、
…幕末、慶応二年(一八六六)生まれの不折にしてみれば江戸時代は近しく、大正四年に移り住んだ自邸(今の台東区立書道博物館)の敷地の一部は元禄年間に造られた御隠殿の跡地で、庭は古い石灯籠とともに元禄の趣を残し、木戸門には良寛の木額が掲げられていた。居宅は明治の建築だが部屋には池大雅や佐久間象山らの書画幅を掛けていたという。…
とあり、中村不折宅の「敷地の一部は御隠殿の跡地で、…」とのこと。
根岸薬師寺堂近辺にあった御隠殿敷地はもともと三千余坪(約一万㎡)といい、これを百m四方に換算し、さらに変形すれば、不折宅の約一千㎡、さらに旧主香亭の迷花書室約五千㎡ 五十m四方の変形がもとの御隠殿地と重なり、どうやら見えぬ絲に手繰られるようである。どちらにしても香亭先生とも関わることで、これも縁かと、しばし御隠殿について探るべく少ない記録を整理してみれば、いかにも不分明なことに気づくであろう。
一、輪王寺宮御隠殿以外にも、全国各地に秘された御隠殿の名称があること
二、御隠殿には隠居御殿の意と、秘隠する意の御隠し御殿たる別意があること
三、はじめは輪王寺宮日光参詣道中の御休息所を御隠殿といい、浅草寺本坊の伝法院をあてたこと
四、後に輪王寺宮の無聊を慰めるための隠居御殿「御隠殿」を役宅と別置したこと
など、いかにも紛らわしい。
一品法親王、三山管領宮(日光山輪王寺、比叡山延暦寺、東叡山寛永寺)などの天台宗座主をも兼務し、東台に常錫した歴代輪王寺宮は、必ず京都の宮家と皇子から選ばれ、朝廷の院宣で輪王寺宮の称号を与えられ、万が一京都で倒幕運動が興り天皇が倒されれば、輪王寺宮を天皇に擁立し、徳川家が朝敵とならぬようとの幕府の深慮遠謀で、傀儡とはいえ宮は将軍に継ぐ重い存在であった。
御隠殿については、幕府普請奉行編纂『御府内沿革図書』宝暦三(一七五三)七月の条に、
上野の宮の隠居御殿なりき。古図に御隠居所とのみ記したるもあり。宝暦三年七月杉崎の地四反一畝買上られ。造営なりて壮麗を極め。常に宮家の遊園なりき…
とあり、御隠殿のあった金杉村は、
御打入の後は、御料所なりしが、正保三年、東叡山領となり、次第に町地出来て、金杉上町下町と唱ふ、 …略…
南は下谷御箪笥町、坂本裏町、坂本町、東叡山構内なり、西は谷中本村、及び上野御隠殿なり、この御隠殿地は、村内字杉崎と唱え、四段一畝二十四歩の畑地なりしが、宝暦三年七月中、御買上げ今の如く、上野の内、御隠殿地となれり、…(『北豊島郡誌』東京府刊より)
とあるよう、まず金杉村が正保三(一六四六)年東叡山領地になり、後の宝暦三(一七五三)年の七月に、村内字杉崎の入会地四段(反と同義)一畝二十四歩(約四千余㎡)が改めて買い上げられ、御隠殿の土地とされたのである。ちなみに冒頭句の御打入とは、神君家康公の天正十八(一五九〇)年八月一日の江戸入府をいい、御料所は幕府直轄地をいう。
「台ノ下日光御門跡様界隈」
文政11(1828)年成子刊 須原屋茂兵衛版『分間江戸大絵図』より
やんごとない宮様を憚り、御殿を表立たぬよう秘隠するのが御隠殿たる別意で、その証左に、図中央左の感応寺と日光御門跡様に挟まれた御隠殿の当然あるべきところは「タハタ」(田畑)と記されるのみである。
別に「日光御門跡(様)」役宅は、台ノ下の寛永寺領内坂本村の永称寺隣接地などに分散された。
20
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第113話
「藝に遊ぶ」 會津八一と宮城道雄の琴癖 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
正月、旧奏楽堂演目でのシュメー版「春の海」以来の宮城道雄の話題で、しばしの閑話休題としよう。
七月初め、久しぶりに神楽坂上の安養寺近くの出版クラブへ上がる地蔵坂の途中で愚生のライヴがあった。この安養寺は、向いにあった行願寺とともに、寛政年間牛込琴社が定例の琴会を催した寺として知られる。
筆者は数年前まで、毘沙門さんでの町内会イベントや、すでにいまはない珈琲の名店「パウワウ」楼上で、年に数度は小さな和洋のライヴを催し、時には牛込琴社をテーマにした音楽会なども取り上げていたが、街の顔役であった故主人H氏の周辺には多くの人が集まり、そんな仲間の一人が、今年になって地蔵坂の途中に瀟洒な多目的喫茶店を開いた、その二回目ライヴ上でのことである。
席上、近くの宮城会館に勤務する古い友人I君が、世界的な箏曲家の宮城道雄(一八九四~一九五六)が、かつて歌人で書家の會津八一に宛てた書簡のコピーを持参し、
「宮城は書中で琴を部屋に置くと徳がおちるというが、琴界にそんな伝聞があるか、よく解らんから教えてほしい、なおかつ読んでくれ」
と曰う。「琴で徳がおちる」とは筆者も初耳のことで、ハテと痼りをのこしたまま開演前にザッと眼を通して二次会を終えて帰宅したが、なんだか気になり、深夜に改めてこれを読んでみれば、案に違わず、
…琴を自分の部屋にかけておくと徳が崇くなるとも云われ…
とあるではないか。
三十年前、愚門で琴、宮城宗家と藝大で箏曲を学んだ嬢から、当時宮城遺愛の「琴」があることを聞き、その和製のを見聞したこともあったので、人には知られぬが、宮城もまた琴箏とその精神性の異同をよく理解した上で、古来の文人同様「壁上に琴なくんば人をして卑俗ならしむ」とばかり、机のすぐ脇の柱に琴を置いた人と、当時は合点した。
一方、八一の琴癖は夙に知られ、その要因は、自身の中国古典への強い憧憬と、養女の一人蘭子が道雄直門の箏曲家であったことから、これまた八一も江戸製の「琴」を数面所蔵し、琴書までも架蔵していたが、ただし、この一事をもって実際に琴を弾ずる人とはいえず、大写しの写真などを見ても右手の爪はほとんどないので、古来の学者同様、琴癖のみに終始した人と思われたのである。
以下は『教育新聞』昨二〇一二年九月十七日付「円卓」欄より、愚稿の写しである。
「芸に遊ぶ」
芸には二種ある。古義は学芸で、経書や礼楽などを学ぶことの芸。現義の芸術で、音楽や美術などをいう芸である。
現在通行の「芸(げい)」は正字「藝(げい)」の中画を削った古くからの略字だが、別に同画の「芸(うん)」という本字があり、義は〈においぐさ、かおりぐさ〉すなわち香草をいう。そのため、芸大混同を避けていまでも正式には東京藝術大学であるし、逆に古書肆・芸艸堂(うんそうどう)の看板も現役である。ちなみに中国簡体字では「艹」に音通の「乙」を足して表記し「イー」と発音する。
さて、大分の以前、たしか新宿の中村屋楼上での演奏時であったか、秋艸道人こと会津八一(1881~1956)揮毫の「游(遊に同じ)「藝」という文字が眼にとまり、支配人に尋ねると「わかりかねます」との答えであった。
八一の書した芸とは、〈六芸(りくげい)〉礼儀、〈楽〉音楽、〈射〉武技、〈御〉車馬、〈書〉詩文、〈数〉数学を指し、遊蕩などを想起させる現代語でマイナスイージの強い遊芸の意でないこと無論で、「道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に遊ぶ」(『論語』述而編)を典拠とし、「六芸に遊ぶ」と男子(君子・士大夫)たるもの必須の条件をいった。しかし、そうした流れを多少とも汲むであろう?代耕を気どる現代文人たちには、なぜか高等遊民なる造語がピッタリあてはまり、ことさら真義の遊芸との区別は不要だ。
八一は歌人・書家として名をなしたが、文人趣味の延長から楽(がく)に興味を抱き、後にはひとかどの琴癖を気どっていたところ、ある晩、神楽坂の露天で一張の琴を見いだし、それこそ安価に購めて、本郷の琳瑯閣あたりで『琴学入門』や『琴山琴録』などの琴書を購入、「以譜為師(ふをもってしとなす)」とばかり自学していたのだ。
後年、筆者はこの琴や琴譜、別に購入した和製の琴など二、三面を調査する機会があったが、とくに前記神楽坂云々の琴は、案に相違して満甲断文の名琴であり、しかも宋代のものと鑑定するにいたった。
こうした琴(きん。俗称七絃琴)は、今でも琴碁書画の筆頭に挙げられる和漢文人たちのステイタス・シンボルだが、往古は君子四友やら四芸といって、書斎に一張の琴が懸からねば、主人の徳を疑われかねない、というような文人の欠くべからざるアイテムであり、陶淵明を出汁に無絃琴もまかり通った。
琴士・作編曲家 坂田進一
ご承知のよう生前の八一は早大文学部で美術史を講じていたので、大学からほど遠からぬ神楽坂は日頃彼の馴染んだ町で、よく散歩していた。
ある日、八一が神楽坂の夜店をヒヤカシ中のことである。何気に見やれば、ナンと屋台に琴があるではないか。秋艸道人と称した書家でもあり、中国文学に精しく、かつ審美眼をも兼ね備え、「琴碁書画」を地でいくいっぱしの文人を気取っていた彼である。本郷の琳瑯閣あたりで琴書を求め、さらに江戸製の琴をも数面所蔵するほどの琴癖を持っていたので、その琴が名品であることを一目で見破り、聞けば、なんでも店のオヤジは「変わったコトらしいが、これまたよくわからないから安くする」という。驚喜してこれを購入したこと無論である。
記念館調査時では、琴面はやや扁平で比較的胴の薄い典型的な宋琴であった。
「會津八一旧蔵漆琴一面」
年代「宋代製」
琴式「仲尼式」
琴銘「孤鶩飛霞」 鶩(ボク)
旧藏印「南京周奭書屋」人物不詳※
奭(セキ・カクはさかんの意)
漆色「生うるし溜め塗色」
断文「氷裂小蛇腹」補修痕あり
附「清代製共箱」
(続)
【上右】「藝に遊ぶ」フライヤー
2013年4月~6月 新潟會津八一記念館にて
會津八一の養女蘭(蘭子とも)が宮城道雄門下であったことから、八一と宮城は互いの存在を認めていたが、宮城は昭和25(1950)年11月18~19日の新潟演奏ツアーの際にはじめて八一の自宅を訪れて面談し、かねての「琴」に対する質問などをしたそうな。写真左の箏を弾くのが宮城、すぐ隣で喰いいるように覗き込むのが會津である。
平成25年春企画
名曲「春の海」の作曲家・宮城道雄生誕120年記念
藝に遊ぶ 會津八一と宮城道雄
平成25年4月5日[金]~6月30日[日]
午前9時~午後5時
[休館日]月曜日(ただし4月27日5月6日、5月7日(火)観覧料一般500円・大学生300円・高校生200円・小中学生100円 主催新潟市會津八一記念館
【上左】「芸に遊ぶ」
2012年9月17日 『教育新聞』「円卓」欄より
日本琴学の延長線上から、筆者は数年前に新潟の會津八一記念館で八一旧蔵の琴の簡単な調査をしたことがある。また昨年秋、教師のための新聞『教育新聞』の一面コラム「円卓」欄に、奇しくも偶然「芸に遊ぶ」という八一の琴癖についてごく簡単に触れたことで、こたびの展覧会フライヤーを見てその内容の酷似したことに驚き、よって本文中に愚稿を転載させていただく。
21
△目次TOP↑
秋月※周奭(生卒年不详),字允升,号敛斋,湘乡人。南宋学者。
乾道(1165—1173)间举人,受业张栻于岳麓书院。尝与张栻[shì]论学。栻问: “天与太极何如?”奭曰: “天可言配,太极不可言合。天,形体也; 太极,性也。惟圣人能尽性,人极所以立。”栻以为然,并题其亭曰“敛斋”。不信鬼神之说。
《皇极经世节要》,清朱彝尊《经义考》著录。《四库全书》存目著录。
《鬼神说》,张栻为之作书后,称湘乡周奭考鬼神之说,凡夫子之所尝言,见于《易》《礼》、《鲁礼》者悉集之。上及于濂溪周子,下及于诸家门人,凡有涉于此者,合为一编,以与朋友讲求其故。
瘦蘭齋樂事異聞 第114話
「藝に遊ぶ」 會津八一と宮城道雄の琴癖 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
以下は、I君の持参した會津記念館に遺る宮城の八一宛て礼状のコピ―を筆者が読み直したものである。
内容は重なるが、昭和二十五(一九五〇)年十一月半ばの新潟演奏ツアーで、宮城が古町の會津宅で八一と面談した際に「琴につき質問」し、また揮毫に対する礼状で、道雄夫人貞子(一八八九~一九六八)の代筆は女手ながらかなりの能筆である。
日ましに厳しいお寒さとなりました。
さて先頃御地へ伺いました節々、いろ(お世話になりまして難有たう存じました。
殊に先生にはじめてお会いした事ハ、大変嬉しく感じました。
又、この度結構な書をかいて頂きまして、わか者に読ましましたき、お作の「湍る水」は、耳のみで生活をしてゐる私にハ、一人ふかく感じられました。
又、琴の文に就いてはいろ(と御解説を頂き、よくわかりました。
「実は七絃琴を自分の部屋にかけておくと、徳が崇くなるとも云われて居りますので、私も机のすぐそばの柱に琴をかけて居ります。」それと今度の文によって、邪念を捨て、芸道に一層精進したいと思ひます。
中村屋にお恒りのよしをきまして、電話を致しましたが、鎌倉にお出でになつて居られた様子でありましたので、誠にくおくればせ乍ら、厚く御礼を申し上げます。
お寒さのおりから、
くれもお大事に。
宮城
會津八一先生
(句読改行仮名漢字変換「」筆者責)
宮城は新潟において、八一の養女で箏の門人(藝大生)でもある蘭子から、かねてより聞いていた八一とはじめて会見し、席上、八一がツアーに先立つ八月一日に宮城のために献呈した「琴銘」について解説をうけ、日ごろ疑問に思う琴事についてなど、腹蔵なく訊きもしたのだ。
蛇足だが書面中の「湍(はや)る水」とは、宮城は八一のために自作の「瀬音」や「水の変態」を弾いたに違いない。だからこそこれに感じた八一が宮城のために揮毫した書と推測されるが、さすがは人知れぬ苦労と努力を重ねた上になり、世界に通用した宮城道雄である。短文中にその人となりを伝える文面は、読むものをして自ずと頭(こうべ)を下げせしむることになろう。
偶然とは偶然である。書簡末尾の新宿中村屋の創業者は相馬愛三(一八七〇~一九五四)と黒光(一八七六~一九五五)夫妻で、この夫妻は八一ら多くの文化人に活動の場を提供したパトロンとして著名であり、八一筆の「游藝」はその答礼として貴賓室に掲げられたもので、後々筆者が目賭した経緯が前号記事となる。
次に八一書の「琴銘」について、これは後漢の碩学李尤の「銘」で、尤は六度にわたり洛陽南宮の蔵書庫「東観閣」における校書(書物校訂)に馬融(七九~一六六)とともに参画した大学者八人中の一人として『後漢書』に名が載るものの、惜しくもその伝は不詳である。ただ彼の「琴銘」は正倉院御物の「金銀平文琴」(図版)の装飾にあるため、この琴銘は日本の琴客間では古くから知られてい、八一の語る蘊蓄に宮城は耳を傾け、深く感銘をうけたのである。
「琴銘」李尤
 琴之在音蕩滌耶心
琴之在音蕩滌耶心琴はこれ音にありて耶心を蕩滌す
雖有正性其感亦深
正性ありと雖もその感もまた深し
存雅却鄭浮侈是禁
雅を存し鄭を却け浮侈是を禁ずれば
條暢和正樂而不淫
條暢和正楽しみて淫せず
こちとら凡人に十方を見晴るかす術があろうはずもなく、該展覧会の閉幕した直後のI君の知らせは遅きに失し残念であったが、多少なりともこうした琴事に繋がる催しがあることはまことに悦ばしいかぎりだ。
李尤「琴銘」會津八一書 宮城記念館所蔵
宮城記念館のご好意により、本誌掲載を快諾いただいた。誌上を借りて厚く御礼申し上げます。
20
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第115話
高士中根香亭先生 六
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
中根香亭が金杉の迷花書室を去って七年後の明治二十七(一八九四)年の二月のこと、うぐいす横町迷花書室跡対面に住いした陸羯南(一八五七~一九〇七。日本新聞社主兼主筆)隣宅の上根岸八十八番地加賀屋敷別邸宅地内に、俳人正岡子規(一八六七~一九〇二)が転居してくる。
おそらくは、子規も羯南などからかつて対面にいた旧主香亭のその人となりを聴いていたに違いないが、一年後の翌明治二十八(一八九五)年、無人のまま住む人もない真向かいの迷花書室跡に、子規がそぞろ感じて詠んだと思しき五絶がある。
根岸僑居雜詠四首之一
隣家有花樹
隣家に花樹あり
獨見艸生庭
独り見る草の庭に生ずるを
終日繙書卷
終日書巻けば
猶憐両鬢青
なお両髪の青きを憐れむが如し
以下はしばし香亭を離れて、お向いの新人子規と森鴎外(一八六二~一九二二)との友情についてである。
同年四月二十八日のこと、子規はこの根岸の寓宅から志願し、従軍記者として第二軍近衛師団に属して中国戦線へと赴く。
行かば我れ筆の花散る所まで
とばかり、遼東半島の金城に上陸すれば、折よくもかねてより文壇上で面識のあった、金州城の第二軍近衛師団兵站部一等軍医正として先に赴任していた鴎外がいたが、すでに戦闘は終結していて、子規上陸の二日後には日清講和条約が締結された。
一村は杏と柳ばかりかな
古寺や戦のあとの朧月
戦のあとにすくなき燕かな
鴎外に挨拶し帰国の途につくと、もともと子規は病身を引き摺っての従軍行である。船中で喀血した後は寝たきりとなってしまう。しかし、異域のしかも戦場で邂逅した両人は胸襟を開いて親交を温めたことで、深い友情が芽生え、翌明治二十九(一八九六)年正月、根岸での「句会」に鴎外を招いてからは、以後鴎外は子規庵を頻繁に訪れ、その交友は鴎外が小倉に転勤する明治三十二年まで続き、鴎外も香亭書室跡をたびたび目にしていたのである。
漱石や虚子に対しては脾睨視した子規も、五歳年長の鴎外に対しては、弟分としての節を守り先逝した。
明治三十(一八九七年八月二十七日、子規「根岸雑詠ノ内」の句に、
凧あくる子守女や御院田
「御院田」(御隠殿の意 ※筆註)
人の庭のものとはなりぬ月の松
などと、もと御隠殿庭内にあって庶民は拝めなかった名松も、いまは人手にわたったとの根岸懐古である。
こうした子規庵には森鴎外、夏目漱石、伊藤左千夫、高浜虚子や中村不折など、当時の文壇の錚々たるメンバーが集い、しばしば句会や歌会を開催し、文学談義に耽るようになるが、一足先に根岸を去った迷花書室の旧主香亭はその一時代前のいわば旧弊な文士。惜しくも子規のサロンとはその後も接点がなかった。
子規はうぐいす横丁を愛し、
加賀様を大家に持つて梅の花
梅もたぬ根岸の家はなかりけり
根岸にて梅なき宿と尋ね来よ
下谷区の根岸の奥の風涼し
夏の月此の横町も琴の音
同じく『発句を拾うの記』には、
…我は名もなき梅を人知れらぬ野辺に訪はんと同宿の虚子をそそのかして薄曇る空に柴の戸を出づ
梅の中に紅梅咲くや上根岸
松青く梅白し誰が柴の戸ぞ
板塀や梅の根岸の幾曲り
と根岸の景を慈しみ詠んだ。
「迷花書室跡」
現在の書道博物館をも含む、しかも、もとの迷路花書室の一画に現在建つ個人のお宅である。
いかにも香亭先生がいまにも戸を開けてフコッと出てきそうな、往時の根岸文人宅を彷彿とさせる佇まいで、この路地に面した右側の先にいまの子規庵はある。
27
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第116話
高士中根香亭先生 七 香亭と小西湖秘話 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
元来、香亭と鴎外は没交渉であるから誤解なきよう。奇しくも相前後して上根岸から駒込へと移りゆく。ただそれだけのことだが、つけても消えたディスクのデータは詩人のそれに勝るとも?で、筆者の想いは日ごとに増すばかり…、未練ではある。
太古江戸湾の名残が不忍池で、森鴎外がベルリン留学を終え、同郷津和野の親類で、徳川慶喜公の側近から明治政府高官へと上り詰めた西周(一八二九~一八九七)の仲立で、海軍中将赤松則良の長女登志子と結婚するのが明治二十二(一八八九)年三月。夏に上根岸の通称文士村の子規や香亭旧迷花書室至近の地から、上野花園町(現池之端三丁目の「水月ホテル鴎外荘」)の赤松家の持ち家に移り、新婚蜜月の裏に『舞姫』の他二編を執筆して明治文壇に確たる基盤を築くも、ほどなく妻登志子と離別し、長男於菟を連れ翌年、本郷駒込千駄木に転居し約一年間暮らした家が、十三年後には夏目漱石の借家となり、『我が輩は猫である』を執筆した家として有名になる。
明治二十五(一八九二)年八月、二十九歳での博士号取得を契機に、翌年一月、同町内団子坂上に移る家が以後六十歳で没するまでの鴎外終の住処で、当時この坂上二階の書斎からは遥か江戸湾が見渡せたため、これを「観潮楼」と名付けたことで、ようやく冒頭不忍池(小西湖)へと結びつく。
大分前置きが長くなったが、愚稿前号までは、謹厳実直そのものでいかにも石部金吉のような印象の香亭先生を追うが、いやいや若きころから意外にも軽妙洒脱、純情可憐?な側面もあったようで、今号からはそんな部分でしばらくホットしようとの企みである。
香亭の原文を損なう筆者の意訳であるが、意あるところを汲取あれ。
蔦姫伝 (『香亭蔵草』)
余自移岳陽に移りしより
晩年の興津かと思いきや沼津兵学校
耳に歌を聞かざること四年
そこでの教官時代は任務繁多
壬申の夏再び東京に移り
明治五(一八七二)年三十三歳
兵学校は陸軍兵学寮と統合東京へ
故人とともに小西湖上に飲む
旧友との不忍池畔での酒席上
伎楽を召して酒を佐く
芸者をあげれば
伎中に蔦姫なるあり
お蔦さんなる美形が目にとまる
年は十八、九
年のころは十八、九
我がため墨水閒鴎の詞を唱う
業平ゆかりの小唄を唱うので
余之に戯れて曰く
これをからかって
女(なんじ)は知るや 吾が前身はこれ五公にあるを
貴姐は知るか われの前身はこれ五公であるを
※五公は、唐宋期に南海に島流しされた忠臣五人。唐の宰相李德裕、宋の宰相李綱、趙鼎、宋の大学士李光と胡銓の故事をふまえ、わが菅公に比す。すなわち旧幕遺臣たる自身をこれに準えた、酒の上での言辞。
答へて曰く何ぞ知らざる
よく承知し存じあげております
児(わらわ)はこれ 小町の後身なるを
ならば妾(わらわ)は小野小町の生まれ変わりとお判りに
頃之姫問曰公何処館
しばらくして 旦那さまどちらにお住まいと訊かれ
余逈指湯陵菅祠日
かなたの湯島天神を指し
夫巍然者便是
あの高台にあるのがそうだよ
抑女亦何居
ならば貴姐はどこに居るのかな
姫直指湖中天女廟曰是
ただちに池中の弁天堂を指し あれなるがそうですと
余竊歎其機警不讓蘇小妹焉
わが胸中はその機智の 蘇小妹に劣らないのに驚くばかり
※宋代の名臣蘇洵の娘蘇小妹は生来賢く、宰相王安石が息子の嫁に乞うが、蘇洵は承知せず才人秦少游に嫁がせる。はたして新婚初夜、小妹は新郎にわざと詩文や対句の難問を出し、解けなければ共に寝ないと。少游は小妹の兄の蘇東坡の助けをかり、ようやく難問を解き、晴れて新婚の寝室に入ることができたという仮構。
後屢相見於酒席間
その後たびたび酒席で逢ううちにも
始得悉其為人
徐々にその生い立ちを知るにいたる
姫姓松本名縫
姓は松本 名は縫
生於湖西七軒里
池之端七軒町の産で
幼喪恃怙養於匠家
幼くして両親を失い大工の養女に
已長倩盼美姿
成長すれば
口元目元すずしく美しい
略知文字
初等教育を終える
先是家翁匠破產
それ以前に養父は身代を潰し
以養翁嫗
そのため老齢の両親を養う
而其才情秀拔
彼女はずば抜けた才気と情けにみちた心意気をもち
能知人賢庸蓋天性也
人の賢愚が解るように 生まれつき聡い
居ること数年
そんな暮らしぶりで何年かいるうち
或人欲納以為妾
身請けして妾としようとの人が現れる
姫日吾本士家之子
痩せても枯れても私はもと武士の娘
寧貧而妻
貧乏でも妻となりたく
不富而妾
いくら金持ちでも妾奉公は厭
翁嫗不可
しかし養父母はこれをよしとせず
納幣有期
結納金は期限つき
※前借の返済に充てる。妾を入れるため結納(納幣)の形を仮にとる。前数夕逢之
数日まえの晩彼女と出会えば
顔色彫悴如有所思
顔色が優れず何やら沈みがち
怪而問之
不思議に思いどうしたのかと訊ねると
乃調絃歌曰
三絃をとり根を締めて唄う
邂逅相遇愧我思切
偶然にも巡り会い 互いにこうしてお逢いするうち
妾の思いはつのるばかり
腸断郎笛
郎君の洞簫(尺八)は はらわたを断つようで
※香亭は一節切(ひとよぎり)をも善くした。漢語では尺八を洞簫といいかえる。
唯留一節因嗚咽
ただ一節聴くだけで泣ける
於是余知相逢止此日
そこではじめてこの日を限りに もうくなることに気づき
叙別而去
こまごまとした別れを述べて帰る
後不復相見也
その後また相見えることもないのだ
(続)
「小西湖畔から弁天堂を臨む」
寛永2(1625)年、徳川家光公は天海僧正座主として比叡山延暦寺に倣い、上野は東台に東叡山寛永寺を建立、不忍池を琵琶湖の竹生島に見立てて弁天堂を建てたが、さらに後の江戸から明治の文人連は池を唐風粧し杭州の西湖に見立てて小西湖と呼んでは好んで詩歌に詠んだ。
「(東台)慶応元年図」
山崎有信編『彰義隊戦史』明治43(1910)年刊より
なるほど、いまでも池之端から続く東台上には霊隠寺ならぬ寛永寺、池中には大分後代の昭和4(1929)年の造営になるが、蘇堤や白堤もどきの堤もあれば、またなによりも蓮や桜花、水鳥目当ての行楽の人波は今昔絶えることはない。
南印右の埒外辺で香亭は生まれ、左下御隠殿跡辺に明治初期に移る。中期以降はそこらに子規や鴎外また不折があり、西印下部が本文中の松本縫の生まれた池之端七軒町となる。
39
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第117話
高士中根香亭先生 八 香亭と小西湖秘話 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
中子日。千中求一。美人不可得也。萬中求一。才人不可得也。況兼其才与美者乎。今姫併有之。而為命太薄。何天之於彼而嗇於此耶。雖然姫一婦人耳。不足深惜也。嗚呼不足深惜也。
中子(香亭)曰く。千中に一を求めて。美人得るべからざるなり。萬中に一を求めて。才人得るべからざるなり。況んや其の才と美とを兼ぬる者においておや。
今姫は併せてこれあり。而して命のはなはだ薄きをなすは。何ぞ天の彼に与え而して之にするや。然りと雖も姫も一婦人たるのみ。深く借しむに足らざるなり。鳴呼深く惜むに足らざるなり。
舞台は香亭が洟垂れ小僧のころから走り回った下谷池之端周辺で、その後、幕末諸戦に破れて徳川家は大政奉還。宗主慶喜公の駿府転封に従い香亭は静岡藩、沼津兵学校の教官などを経て、新東京に戻るのが明治五(一八七二)年、該文はその花も実もある三十三歳のころの作となる。
沼津兵学校教官は概ね継続して陸軍中佐に任官して陸軍に配属されたが、香亭は陸軍参謀局付で一階級下がって少佐(後に物議をかもす)に、それでも馬卒付で乗馬待遇である。
はからずもそうした中での酒席で知り合った解語の花は、聴けば池之端七軒町生まれの薄倖ながらも当意即妙の美人である。同じき鴎外の『雁』を引き合いに出すまでもなく、至近に神田講武所、同柳原、同明神下、湯島同朋町、下谷仲町など花街のある中、仲町は格式も高く、小西湖や東台目当ての粋人が多かった。
その下谷芸者の中に咲いたお蔦(松本縫)さんなる一輪の花は、もと武士の家に生まれるも、幼にして両親ともになくしたため、大工の養女となり小学校に通っていたが、これに先立ち養家が破産して、芸者となり老いたる養父母を養っていた。
その聡明さと美貌、さらには気っ風の良さと人情味に溢れた人柄は、すぐに香亭のお気に入りとなり、その後しばしば顔を会わせるようになるが、何年かのうち、彼女を見初め身請けして妾にという人が出現する。
さあ、痩せても枯れても武家に生まれたお蔦さんである。「貧乏でも正妻ならばともかく、妾奉公はいやでござんす」と突っぱねてはみたものの、養父はその結納金を借金の充てにしようと、大恩ある養女の話に耳をかさずこの話を進めてしまうため、悩んだ挙げ句お蔦さんは香亭にそれとなく相談するのだが、生憎香亭にその高額を肩代わりする余力もなく、さりとて最愛の糟糠の妻を無視し、まして妾は否というお蔦さんをさらに妾にすることもできず…。わが江戸っ子武士の成れの果ての香亭先生、この非情なる現実を目前にしてただ坐視せざるをえず、悔し紛れに美姫といえども単なる一女性だ、「深く惜しむに足らざるなり、鳴呼、深く惜しむに足らざるなり」
と文末に重ねたのは、無論、これを深く惜しんで余りあるからのこと。
後日譚である。
閏怨 (同『香亭蔵草』)
郎隔千山萬水
郎は隔つ千山万水
妾悲一日三秋
妾は悲しむ一日三秋
何応為比翼鳥
何れまさに比翼の鳥となり
連理枝頭解愁
連理の枝頭に愁を解くべし
かくしてこの六絶こそ、この経緯以後を語るものとお解りになろうし、いわずもがな起承の句は、いまは手の届かぬ人を想う香亭、一日千秋思慕の情を寄せているであろうお縫さんのことで、如何にも哀れを誘う。
「もと動物園停車場から七軒町へ至る都電軌道跡」
右側の坂角が五条天神、上れば花園神社、韻松亭から博物館へと続く。
当然、香亭在世時に上野線や動坂線の市電(後の都電)はまだないが、筆者の学生当時、左側落葉の積もる道を都電20番と40番が上野広小路→上野公園七軒町へと抜け、動坂→護国寺方面へ行った軌道跡と記憶する。惜しくも昭和46(1971)年の3月から翌年11月にかけ廃線となった。
20
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第118話
高士中根香亭先生 九 香亭と岸上質軒
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
小研究所は湯島男坂下の陋巷にあり、明治に遡れば同じ坂下に岸上質軒(一八六〇~一九〇七)がいた。
香亭の退隠前は大書肆金港堂編集主幹として、殊に後生有為の学生諸君を益するところ多大であったことが知られるが、同様の質軒も当時の出版最大手の博文館にあり功績のあった人で、『太陽』、『江戸会誌』や、『近古文芸・温知叢書』、『内外古今逸話文庫』などを編集しては『中学世界』、『婦女雑誌』他の有力雑誌に寄稿もし、また自ら『通俗徳川十五代史』他数十編におよぶ著述もあるという文士で、ことさら意識せずも自然と大先達の香亭先生に私淑敬慕するに至ったわけである。
ちょうど寒斎にこの『明治畸人伝』があり、長文だが希少な香亭伝記を補足するものとしてここにご紹介しよう。ただ、香亭自らも折に触れ言及するように、この記事とても眉に水気を要する部分があり、注意せねばならないこと無論である。
「中根香亭先生」 岸上質軒
兵要日本地理小誌(※筆者註)
予が少年の頃、「兵要日本地理小誌」といふものを見て、愛読殆ど手を釈(お)く能はざる程であった。三冊ものであったかと思ふ。併し今は紛失して、よくは分らぬ。
当時中村敬宇先生の「西国立志編」、福沢諭吉先生の「西洋事情」、内田正雄先生の「輿地誌略」など、共に、諸生必読の書といふ有様で、何れも洛陽の紙価を貴からしめた。従つて世間を益した事も尠少(せんせう)でなかつたと謂ふ事である。
此(この)「兵要日本地理小誌」の著者が、即ち中根淑といふ先生であったことは、常に記憶に存していた。
迷花書室
其後予は明治二十五六年の頃、先生を駒込曙町の迷花書室に訪問した。
予の訪問したのは、或(ある)古書に就て、教を乞ふ為であった。書斎だか居間だかに通った。室内には幾多の書籍が置かれてあったが、何となく整然として居る中に、几上窓下、一の装飾といふべきものはなかつた。孔雀の羽に香炉、一輪挿の花瓶など、謂ふ俗気は微塵もなかった。併し先生は古書画器玩などに対する趣味は、十分に有つて居られたさうである。それは後に述べる事とする。
香亭雅談
先生は自身の履歴などを人に談(はな)すことは、嫌ださうで、余り詳しい事を知つて居る人は少いが、先生自著の『香亭雅談』を見ると、その出処進退の概畧は彷彿することが出来る。
香亭は其号である。之を骨子として、先生の知人から聞いた所の逸話を加味して、本編を綴ったのである。去年の夏の頃、東京日日新聞に出た、「明治逸士伝」といふ物の中に先生の伝があつた。
当時先生は行脚(※このときの香亭詩集が『行脚非詩集』)から一寸帰られて、此新聞を見て、事実もあるが、大分間違もある。第一幼名を幹三郎とあるが、幹は幹だが、三郎ではない、幼名も半分違って居る位だから、伝中の事実も先ず此様(こん)な割合だらうと謂つて哄笑されたさうである。
曽根得斎
先生は江戸の儒者曽根得斎といふ人の子で、母は有名なる朝川善庵の女(むすめ)である。
得斎は名は直、字は縄卿と日(い)つて、諸子百家の学に通じ、殊に経済の学に長じて居られたが、頗る卓犖不拘(たくらくふこう)(※卓越して拘泥しないこと)とい性質であったさうで、其一例を挙ぐれば、或時家人は皆外出して、独り家僕と家に居られたが、家僕も亦茶を買ひに出た。折しも知人平松といふ家から、檞葉餅(かしはもち)を贈って来た所が、平松氏の僕が、再三戸外で呼んでも、応といふのみで、取次に出て来る者がない。
(続)
「明治畸人伝」 1906年博文館刊
文芸倶楽部第12巻第6号
明治39(1906)年4月、質軒が没する一年ほど前の発兌になる『明治畸人伝』で、かなりの稀覯本である。
就中、これに先立つ明治25、6(1892~3)年、質軒が根岸から本郷曙町に移った香亭最後の「迷花書室」訪問記を核とした記事となる。
33
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第119話
高士中根香亭先生 十 香亭と岸上質軒 二
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
前号に続き質軒が聞き書きした香亭小伝を参照する。蛇足ながら、文頭のルビは下僕の意であるにご注意。
(承前)
僕(ぼく)は拠ころなく戸を明けて内を覗くと、得斎先生几に凭つて頻に書を読んで居られたが、平松氏の僕を見て、今日は家内残らず留守じや。又次に来て呉れと曰はれる。
僕は御入物を拝借して、移して参りませうと曰って、台所で盆に移して帰らうとするを、得斎先生は喚びかけて、贈られたは何じゃと問はる僕は柏餅でといへば、それは何よりじゃ、今茶も来るから此処に持つて来て呉れと謂はれたさうである。
泥鼈(すっぽん)奇談
先生の外祖父朝川善庵は、当時の大儒者であつて、謹厳方正の人であつたが、此先生に頗る滑稽談がある。
少年の折、長崎に漫遊された帰路に、太宰府に立寄られたが、途中で泥鼈を買って、さて旅宿に着かれて、主人を呼んで料理せんことを命ぜられた所が、主人は低頭平身して、
「今日は天満宮の御祭日で、一切殺生は出来ませんので」といふので先生も、成る程さうか、と薦で泥鼈を包んだまぁ、臥床の側に置いて、眠に就かれた。すると夜半頃になると、泥鼈は薦を咬破って、座敷中爬ひ廻つて、夜着も布団も、泥まみれにして仕舞った。
善庵先生だけに、特に面白いのであるが、その後十返舎一九此の事を聞いて、例の「膝栗毛」中の弥次喜多泥鼈に咬まる、一段の趣向とはしたのだ。
撃剣歌
香亭先生の齢は、藤本藤蔭君の談に、依田学海翁より四つばかり下であるから、今年は六十九であらうとの事である。さうすれば、天保九年戊戌の生である。
さうして幼年の折り、幕府の徒士中根氏の養子となった。
義父は忉雲(とううん)と号して、尺八の名人で、桜井柏亭などといふ人と社を結んで、毎月一回吹奏会を開かれたさうで、当時先生は酒茶の間に周旋されたさうである。
筆者曰く、香亭の晩年、尺八に傾倒するのはこうした追憶にもよろう。 然るに少年時代には、豪宕にして、甚だ剣術を好まれ、「撃剣歌」一篇を作られた。
擊剣歌
文能治内武威外。両道相待四海泰。
吾邦古来最右武。一片昆刀用亦大。
誰道劍是一人敵。畢竟斯語属冥頑。
請見高祖提三尺。戡定区夏及夷蛮。
剣乎剣乎君須学。護身鎮国二華岳。
潜龍躍兮出於掌。流星閃兮発於握。
魑魅罔両皆逃避。爽気払空清如濯。
君不聞
剣之動静有陰陽。陰陽各各提三網。
陰曰背孥掠与刺。陽曰左右又中央。
六綱錯綜遞変化。千闘万格不可量。
一刀疾乎電。再刀急乎霰。
三刀復四刀。刀刀応機変
格長縮斫腰。譲短伸割額。
不問刀利鈍。只審刀順逆。
鳴呼勝負
之機在此不在彼。彼是須見非邪是。
一団浩気能不餒。雖千万人吾徃矣。
なるほど、そういえば香亭は少時から巷内にあった江戸四大道場の一、伊庭軍兵衛の「練武館」に通いつめ剣術オタクで、軍兵衛の子息八郎とは終生を誓った友でもある。該詩は宋の欧陽脩「日本刀歌」などを意識した作ではあろうが、そればかりではないことがよく解ろうし、そんな少年が以後、次項「小娥女史」に諭されてようやく書籍に親しむようになったのである。
小娥女史
中根氏には其頃一人の名媛が居られた。尤も既に老人ではあったが、名を恒、字を小娥とれて、先代鐵翁といふ人の長女であつた。
才色双全ともいふべき人であつたので、諸方から婚姻を申し込む者が、多くあったが、小娥女史は皆之を斥けて、終身孤潔自ら守られた。
さうして妙齢の折に、ある諸侯の奥方ら宮仕をして、二十年も居られたが、奥方が身まかられてから、家に帰って終られた。
常に俳諧を嗜んで「色即是空」と刻した小印を用ゐられたさうである。又深く仏乗を嗜んで、毎夜三更の頃まで、経巻を誦まれたさうだ。
香亭先生の少年の時は、例の武芸が好きで、学問は嫌であつたさうだが、小娥女史の訓戒其宜しきを得たのと、清水純斎といふ儒者の誘掖とで終に十分学問をされたのである。
先生の少時、女史は衣類数箱を売つて、数十部の書籍を購ひ、十分に勉学せしめられ、又毎夜経を誦む時は、先生も其燈火に即いて書を読み、文を作らるる事であったさうだが、之に就ても一の面白い談がある。
或夜二人の間に儒仏の異同論が始まつて、先生は盛に仏を排撃された。すると女史は莞爾として、成ほど儒は善からうが、独立が出来ぬ、毎夜仏の灯光を借りて居るではないかと謂はれたので、思はず大笑をしたとの事だ。
其温然春風の如き間に、独立心を吹込まれた女史の庭訓は他日大に力あつたと思はれる。されば女史の身まかられた時、先生の作られた挽詩は、如何にも哀悼の情を写してある。
憶小娥女史
憶昨燈前我侍君。君修仏典我稿文。
今宵我在君何去。此旧燈前広半分。
欲写哀詞恭上君。神愴筆渋不成文。
幽明雖隔恩情厚。依例灯光一半分。
重複を厭わずに次にいおうとするのが、香亭の詩についてである。
養家中根氏が下谷長者町(いまの御徒町あたり)から下谷三昧橋畔に移転すると、隣家が一代の詩宗大沼枕山の家であったことから、香亭少年は門弟然として頻繁にその塾に出入りし、また枕山翁も詩会などがあると香亭一人を伴って出席したほど親密の間柄で、定師をもたずに刻苦勉励した香亭は、後にこのことだけは、すなわち枕山の門弟といっても差し支えないと誇ったのである。
又清水純斎といふ先生は、芳野金陵の外弟で、鵬斎の子亀田綾瀬の門人で、幼少の折から頗る穎悟であつて書法も優れて居つたさうで、白髭神社の前やも木母寺の境内にある碑は、何も其幼時の筆であるさうだ。純斎の事は後に言ふが、斯る堅姑良師の薫陶を受けられた事も、先生の美質を成すに於て力あったであらう。
下谷から根岸
先生の生家曽根氏の家は下谷長者町に在った。即ち其処で生れられたので、養家中根氏の宅は御徒町であつたが、先生が十五六歳の頃、三味橋の畔に先考と共に移られた。
南の隣は詩人大沼枕山の宅で、其又南は書家高橋単山が居つた。(続)
【上】「杵村小雅宛尺牘」『香亭遺文』より
本連載中、杵村小雅のことは改めてご紹介することになろうが、該尺牘は香亭が毎日新聞に連載した「七絃琴の伝来」を通じて知り合い、生涯の友となった伯耆米子町第五代町長杵村源二(治とも)郎宛て、明治24年5月21日付のものである。
「…に入れ候。此頃年来書捨たる反古の中に、少見るべき所あるものを取集め、随筆やうの物に致さうと存じ、序文の代りに
かきよせし落葉も今はすてかねつ
タへの月の影とおもへは
是は少し自まんの積り、ちと御誉被下度、扨御尋之破天…、」(句読筆者)
【下】香亭画「水墨山水」図
香亭の山水は当時の識者間ではある程度の人気があったが、ご承知のように売り絵でないため、接点がない人物は、ほとんど所蔵すること不可能であった。
蔵者はやはり明治から昭和にかけての文士岩田僊太郎のものである。
29
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第120話
高士中根香亭先生 十 香亭と岸上質軒 三
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
このところ、少ない香亭小伝の補足がてら質軒の対談を主とした記事を読んでいるが、多弁でない香亭先生のこととて、質軒も対話だけに得た材料ばかりでないこと勿論で、もっぱら当時すでに刊行されていた『香亭雅談』や、『行脚非詩集』などのネタ本によりこの項を補った、そんな様子が随所に見られよう。
さて、香亭少年は下谷長者町の実家に育ち、その後、隣町御徒町の中根家に養子となり、ちょうど香亭十五六の多感な少年時代にその養家が同じく下谷の三味橋畔に移った、というあたりから話は続く。
先生が十五六歳の頃、三味橋の畔に先考と共に移られた。南の隣は詩人大沼枕山の宅で、其又南は書家高斎単山が居つた。三昧橋を東に行つた所の和泉町には国学者前田夏蔭と、画家長谷川雪隕が居た。夏蔭は今の前田健次郎君の先考である。後に塩谷宕陰先生が、橋北に住まほれた。其近傍に画家鈴木鵞湖が居た。先生の内室は、少時鵞湖の宅の北隣に居られたので、鵞湖とは善く識つて居られたさうだ。他日先生が画に妙を得られたのも、これらが因縁をなしたのかも知れぬ。
これも質軒がいうように『香亭雅談』から抜き書き引用した記事であるが、鵞湖との交友から画を会得し善くしたのは、実は後の香亭内室であるし、俗に三枚橋といった東台山下の三橋と、ここにいう三昧橋とは同じ忍川に架かる橋ながら、本来まったくの別物で、小西湖こと不忍池に通じた忍川は今は地中にあってその面影もなく、もと川畔の汁粉屋にその名を残す橋とは別なのである。
右の談の中に、三味橋といふことがある。始めて『香亭雅談』を読んだ時は、香亭先生が物ずきに、斯様字を嵌められた者であらうと思つた。これは上野広小路に架つて居る、三橋だの、三枚橋だのと謂つて居る所の橋である。併し最初は橋が、今の様に三つ駢んで居たのではない。自分の棲んで居る所の附近の土地の、歴史や沿革を調べるのは、学者の通有性である。右にもある通り前田家は夏蔭、夏繁(健次郎)二代此地に住んで居られる。さるに依て、今の夏繁翁も、頗る下谷区の地理歴史を調べて居られる。曾て江戸会の演説で聴いたことがあるが、
「広小路の橋は、三味橋と書くべきである。其故は今も忍川の傍に、薬師の堂がある。古くは常念仏をした。その前に架つて居る橋であるから、念仏三昧橋といふ意で、三昧橋と称へたのである。」
大意は斯様な事だと思った。さすれば香亭先生が、三昧の字を用ゐられたのも、杜撰ではなかったのである。
其後根岸の里に移られてから、又近傍に住んで居た所の名家の故居を調べられたが、大島蓼太、北村筠庭、平田篤胤、山崎美成、原念斎、寺門静軒などの住んで居た所は、最早分らず、亀田鵬斎は石稲荷の社前に住んで居たが、子の綾瀬の時に、外に移ったさうだ。抱一上人の家は、鵬斎の故宅と極近かったさうで、その雨華庵といふ者も、此頃まで存在して居つた。石稲荷の幟は抱一の書で、一字の大きさ一尺五寸四方、頗る美事な出来であるさうだ。
京洛の游
先生年二十五(文久二年なるべし)、初めて京都に行かれた。路に琵琶湖を過りて、旭将軍を弔はれた詩がある。それは、
函谷渭水旧城池。秦皇雄略萬世期。
項家一矩忽焦土。咸陽民靡有孑遺。
我取関中誰敢拒。漢王可虜帝可移。
百戦百勝抜山力。却憐垓下不利時。
時不利兮騅不逝。四面楚歌奈虞姫。
男児運尽只知死。捲土重来我愧為。
之を朗吟すれば、気骨稜々たる風丰が躍出する如くである。
次項が香亭の善くした一絃琴の話で、その師たる豊平翁のこととなるのだが、この豊平が全国一絃琴取締の金看板をおしいただき、各地を経巡って琴を教授したことから、麦飯真人以来振るわなかった一絃琴は復興することとなり、いわば豊平は斯道中興の祖となる。
その名跡を継いで第二代の総取締となるのが、本連載中にもたびたび名の出る富田豊春こと渓蓮斎というわけで、香亭の新聞掲載に触発され琴(七絃琴)を学ぶ決意をした、伯耆米子第五代町長の杵村小雅は、その後香亭が没するまでの長期間、淡くも濃い交友を保ち続けた数少ない知己で、香亭の斡旋で豊春の所蔵する琴譜を借覧したりしていた。
琴東す
先生は又韻事に於て多趣味である。其大阪に遊ばれた時、真鍋豊平、号を蓁斎といふ人があつた。和歌の上手で、又一絃琴の名人であった。伊予の人で四十余歳で京畿の間に来て、遂に大阪に居を卜して一絃琴の教授をして居つた。先生も客遊の折から就て学ばれた。
上達が早いので、蓁斎も熱心に誘導した。それで二年ばかりの間には、名手を凌ぐばかりに成ったが、其時江戸に帰らる事となったので、蓁斎は、「琴が東に往く」と曰つて、一笑されたさうだ。中根香亭去って、京阪また一絃琴の名手なしとの意である。僅々二年間の修業で、斯く上達することは、天稟に得る所がなくてはならぬ。『香亭雅談』の記す所に拠ると、先生は其時江戸に帰って、一年ばかりにして、復た西上された。因て蓁斎の宅を訪問したが、不在であつて、既にして伏見の変があったので、急に江戸に帰ったといふ事がある。して見ると大阪で、初めて蓁斎に琴を学ばれたのは、文久三年の頃である。
其後は全く音信不通であつて、其後七年ほどたって、復た大阪に行かれた時、蓁斎の故居を尋ねられたが、更に踪跡が分らなかつたといふ事である。
以下は香亭を師と仰いで親交のあった酒田の素封家本間光美、光輝、光弥の三代の祖父子は、香亭の没後、その原稿を惜しみ義捐金を拠出して『香亭蔵草』を出版し、香亭を広く知らしめようとした。その書中から質軒は「真鍋蓁斎翁伝」の引用し、また香亭から直接聞取りもしたのだ。
蓁斎先生の一絃琴譜一巻、嘉永元年上梓す。曲数十余章に過ぎず、慶応元年第二巻成る、中に名曲多し、余向に親しく「須賀」の曲を先生に受く、佳曲なり。此巻之を逸す、怪むべきなり。今春(明治十九年)以来、臂を患ひて久しく琴を廃す、古人云、三日弾ぜざれば手荊棘を生ずと、但しこの心幸に未だ茅塞せず、因て其譜を作り、以て巻末に附す、其伝を失ふを恐る也。(原漢文)
右は『香亭雅談』中の一節であるが、その故旧に厚く、又文芸に尽さるる一端が分る。
一絃琴の曲は色色あるが、先生は「明石」、「須賀」、「枯尾花」、「歳之尾」、「歌恋慕」の五曲を尤も好まるるさうだ。「明石」は在原行平の須磨謫居の意を述べられたもの、「須賀」は菅の根の長きを以て、人寿の長久に比したるもの、「枯尾花」は宮人伊勢の作、「歳の尾」は歌人凡河内躬恒の作で、共に「古今集」の巻末に出て居るさうだ。又「歌恋慕」は元は箏曲から出た者ださうだ。
(続)
『行脚非詩集』
明治38年刊 中根香亭著
香亭の著書には私家版の配布本があり、巷間流布せないものもままある。本詩集は、下谷根岸の鉄道開通による喧噪を嫌った香亭が、本郷曙町に移転した後の迷花旧廬名で、明治38(1905)年の4月に出版したもので、その書名の謂れは、改め本連載中に触れることとなるため、ここには略す。
行脚非詩集小文及级歌附 全
「真鍋豊平八十歲自画」部分
香亭の「真鍋蓁斎翁伝」によれば、豊平は文化6(1809)年の生まれ、明治32(1899)年の4月に91歳没であるから、この図は明治21(1888)年の風貌を伝える作となる。
「須磨の枝折」慶応元年刊
本文中の一絃琴譜第二巻である。
なお拙稿中、出所と蔵者を明記せぬ資料は弊小研究所蔵
21
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第121話
高士中根香亭先生 十二 真鍋蓁斎翁伝(一)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
若きころ大阪で真鍋豊平翁に学んだ一絃琴。師の人柄も一絃琴の世界もよほど香亭の性質に適ったのであろう、わずか二年の滞在中にその蘊奥を極め、師の衣鉢を継ぐものとして期待されたが、香亭は東帰せねばならず、師の豊平はこれを惜しんで「琴東(ひんがし)す」と慨嘆したのである。
真鍋蓁斎翁伝
蓁斎翁姓真鍋。名豊平。以文化六年生於伊予宇摩郡上野村。父名河内。世為近邑北野村天満宮祠官。郡中有官地。備中倉敷代官管之。隔歳一巡。至則館其家為例。是以河内嘗自節用以新其堂。
会常陸人杉隈南。以画遊其地。
河内使隈南画堂之板扉。隈南揮大筆。写一大墨梅。
時翁方成童。在傍観之。指一枝日。此枝不似梅。隈南性剛峭。怫然作色。叱日。凱児何知。我而名手。何以至如許僻土。河内為謝之。色始釈。
因留数日。時弄一絃琴而楽。翁傾耳細聴。請而学之。節奏鏘然。隈南喜日。孺子妙於音律。可教也。乃尽伝其所知而去。
然当時一絃琴。曲数甚鮮。不過三須磨今様須賀等三四曲。於是翁自製新曲。且簡箏曲中名譜。以一摸十三。経二十余年。終大成之矣。是時翁年三十八。有四女子。而以父尚在堂。乃負琴西遊。遍経九州。往来山陰山陽之間而還。
已而復東遊。至伊勢拝大廟。帰途過京師。謁権中将千種有功。有功一見大喜。強留之。而伏見奉行内藤正縄学翁琴。亦勧居京師。於是翁感其知遇。竟絶帰志焉。居数年。有功薨。正縄解職東帰。而先是河内已没。翁長女迎婿承其家。
於是決居大阪。集門人子女。授琴与歌以為生業。此時新古曲数。大凡及四十余篇矣。
明治五年。与門人町田久成相携至東京。遊房総諸州。已西帰。
為広田神社祠官。十二年罷帰。
十五年遊土佐。遂至於郷里。
止数月。
明年回大阪。然数歳以来。以其居所不一。門人多散。加之齡逼大耄。漸病聾。不能復弁音。於是乃廃琴。専以倭歌為業。
翁最長長歌。年来所作。積至四千余首之多。嘗親書写之。上皇后陛下。為其所嘉納焉。翁大悦曰。吾一生光栄莫過此。
三十二年四月九日臥病。十三日溘焉而逝。享年九十一。葬大阪下寺町遊行寺。諡曰足彦命。
(改行筆者)
以上が『香亭蔵草』に収録せられた「真鍋蓁斎翁伝」原文であるが、かく香亭の音楽癖が見え隠れしたを機に、烏滸がましくも筆者自らの「楽縁」とも照らし合わせ、この行間を借りてここに再考したい。
古来多くの楽縁は人智を超えた存在であり、蓁斎と隈南しかり、香亭と斎もしかり。出会うそれまでは異なる人生を歩んでいた二者間の足跡「点と線」が合致し、「音魂」が琴線に触れ、相互に「教」と「学」を発願し、さらなる両者の努力と工夫の積み重ねにより成就するのであって、学んだ回数や年数、ましてや曲数などによらぬこと無論で、読者諸賢も各々六藝中専門分野の異なりこそあれ、これこそご同輩の原体験に重なるであろうと推量せらるる。伊予上野村の人真鍋豊平自身の左掲する書簡によれば、常陸の画師杉隈南こと杉浦桐邨から一絃琴を学んだのは二十歳、すなわち文政十二(一八二九)年のこと、僅かに学んだ二曲をもとに自身が努力を重ね、後に大輪を開花させたことが解ろう。
豊平は後には全国一絃琴総取締役となり、諸国に大凡二千人ちかくの門人を抱えるほどの大家となった人だが、明治十五(一八八二)年の初夏、蓁斎こと豊平が柴田花守(一八〇九~一八九〇)宛てた返書には、その略歴が一目できる興味深い内容が書かれているので、ぜひともこれを全文紹介せねばならない。
なお、豊平と同時代に一絃琴を善くした花守は、旧肥前小城藩士出の国学者かつ神道家であり、長崎にてシーボルトにも学んだ人だが、花守が長崎遊学中、料亭「花月」において、端唄の名曲「春雨」を作ったことで、向きには知られる人である。
()内註、改行と句読点は筆者責
六月十八日御認出の尊書大坂に着の処、拙者同月二十八日出船、土佐国より招待にて着船、大坂より尊書土佐国に相達し候て拝見仕候。
先以御健壮之由奉賀候、二に小子事も無事にて日日稽古仕候間、御安心可被下候。
扨一絃琴相伝来段御尋により巨細に申上る事左の如し。
小子二十歳の時常陸人杉隈南と名乗、伊予に遊歴の画師弊村に逗留の時、須磨と今様の二曲を習ひ申候が、先小子の始也。尤此人は外に江戸歌の鰹売りを引き候得共、是は三味線より移したる物にて、至て六ヶ敷候。其人の所持の琴と申すは、只一枚板のみにて何も錺は無、蘆管と唱へる物は竹也。柱も竹の節を用ひ、右の手の親指先爪にて引候事也。
其人は伊勢の人に習ひたる由申候。暫く有て、小子九州遊歴に琴を抱いて参り、八カ国を廻る内、其処にて右の二曲を教え、二月に出で十月の末に帰国仕候。
其後承り候得ば、右画工杉浦桐邨と名乗り九州中国を遊歴し候事、巨細他人より承り申候得ば、一名二号の事也。
其後小子三十六年前に国元出立、中国より北通りを京に出伊勢に至り、二月より七月迄志州と伊勢の両国に逗留。
足代弘訓翁の元に至り、一絃琴の由来を聞に、河内国駒ケ谷と申す処の寺僧、麦飯道人と申す僧が始めたりと云。
足代此僧処に若き時遊歴の節、此寺に止り巨細に聞くにより、其僧に伊勢の人が伝り、右画人先生に教へたる事明白也。
小子の弾る曲は、嘉永元年迄に十二曲に相成候に付、須磨の枝折と号し蔵版致、慶応元年に二十五曲を増し、二編と号けて蔵版致、追追彫刻に及、只今にては前後編五十曲に相成り候也。
自作の歌は、万葉集、古事記、古今集抔の長歌に手附致し候事、諸国にて法師又三味線に達したる人に示談して手附致事也。
○尤五段、六段、七段、八段、九段、乱れなどは、十三琴の手より出したれば、合奏するに一も不替。
○琴龍額の処を十三の記(徽)と定め候事、小子の工夫、其儀は、糸の音色にて也。
龍尾の処は、ヲツ(乙)の音、十三(徽)の処は極カン(甲)也。十三絃の音に合して、龍額の処の極カン十三の印と定め候事也。
尤も右隈南より伝はりし時は十二の調子也。
只今は、一二の間に別に△形の印を加へ、十三処と相成候事也。
今様の楽の調に不合御咎うべ(むべ)也。拙者の弾す処は、何れの楽人と合奏致し候ても、程能く合せ申候。
(続)
『須磨の枝折』第一編 豊平跋
須磨琴は一弦十二徽、其の形、龍、日月、星辰、陰陽五行を象り、兼備せざる無し。余は其の故を温め、新たに之を製し、同好の君子に遍く告げて云う。
ひとすちにこころこめたる琴なれは
千代のしらへも たえしとそおもふ
嘉永元年四月 伊予国人 蓁真鍋豊平誌
(上)「一絃琴図」
嘉永元(1848)年刊『須磨の枝折』第一編より
図は、豊平の改良した一絃琴の形で、基本的には現在まで大差なく伝わる。
豊平に就いて学んだ一絃琴を香亭は終生座右に置き、人生の徒然を慰めたばかりか、豊平作の琴曲に歌辞を提供した。
(下)「(一絃)琴規定目」同『須磨の枝折』
ただ、安政(1856)年に出されたこの触書の写しを読めば、あの香亭がよくもこの細目に肯んじたものかと不思議に思うが、さにあらず、後記する豊平から香亭へ宛てた尺牘で明らかとなろう。
琴規定目
一 彈琹必可置琴譜杓机前
一 去琴机而勿弹琴 弹琴必可着袴
一 去琴机直勿置於席上 必勿跨越琴上
一 琹譜之外勿彈雜曲
一 琴之製作勿妄改
一 雖秘曲皆傳之輩不受祖家及師範家之免状者不許他傳
一 不受琴譜者堅不許彈琴
一 不受秘曲印鑑者不許弾其曲
右八箇條堅不可違背者也
安政三丙辰十二月
正親町殿
一絃琴教諭取締役所
真鍋豐平
27
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第122話
高士中根香亭先生 十三 真鍋蓁翁伝(二)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
承前
御承知の通り越天楽に合す様に弾する時は、あまり調子長くゆるやか過て不面白、依て只世間に歌ふ今様に、自然と相成候事、只今全国中の門人千八百人にも及べば、悉く直して廻る分にも不至事、御遥察可被下、右先生は親指爪にて弾し候得共、自由に弾じがたく、依て肥後阿蘇宮地逗留中に思付、蘆管の短きを入指ゆびにさし弾じ候間、琴(箏)にも三味線にも劣りしこと、更に無之候。
扨、又三十年已前、京都の芭蕉堂に防州の百古と申す者、琴を弾くと承り、度々訪ひけれども一度も不聞候。定めて御書中の人にて御座候。其後国に下り病死せしと承り候。右桐邨後に承り候得ば、仙台伊達東五郎殿の藩なりしが、病気に付き三年の暇を願ひ、諸国遊歴す日数満候に付、国元より使者帰国の道、大坂八軒屋の宿屋にて、死去致したると承り申候。右先生何方にてか女房を持ちけるが、其後家弘蘆芳とか申す印刻師の女房に成り、右桐邨の石碑建立すと諸先生へ頼み勧化致したりと聞けど、小子方には不参申し候。
○土佐国には五十人計り門人御座候へ共、一度も下り不申、大流行に付、去月迎への参り、土佐に引越し、先づ八月中旬迄当地逗留の積り。
夫より一先旧里の伊予国に下り、当冬ならでは大坂に帰国は六ヶ敷と存候。
書外後便申上候也。
七月二十一日
土佐国香美郡野市村大石円方にて
真鍋豊平
花守先生
暑中御養生専一奉祈候也
右書簡は辛亥八月富田渓蓮、花守が女森増穂子を牛込若松町の宅に訪ひ、親しく写し取りたるものなり。
百古の姓は河村。たびたび拙稿に登場する富田渓蓮は当時ならびなき清楽大家で、森田女はその門下のやはり清楽家として名高き人であった。
○同上
一筆啓上仕候。
漸秋冷相催候処、尊兄益御勇猛に被成御起居と奉賀候。
次に小子無事に相暮申候、御休心可被下候。
扨、此度御著の雅談書拝見仕、始て御無事御様子を承知仕、大に驚き萬慶過之奉寿候也。
二十余年の昔、天満寓居を十二月暮に御訪ひ被下、来春早く上京に於ては、先此度は永き御別れに相成んと、家内諸共其後悲み不絶、今年迄御無事を不知罪を御高免可被下候。
小子事、明治五年の冬十月、サツマ人門人町田久成と申す人に被伴、上東仕、カサマ人加藤有隣と申す人に被頼、安房上総下総三ヶ国の説教被頼、回在して十二月末東京帰り、明治六年正月教部省に出で、摂津国西宮在官幣社広田神社の祢宜を被命、二月八日東京出立帰国仕、十二年迄相勤候。
官社人減の時より大坂に帰り、不相変歌と琴とを家業に仕、明治十四年に四国土佐国より招き付、七月より十月迄土佐にて稽古、夫より故郷の伊予に帰り、十五年四月迄、伊予国松山より東二十里の間説教仕、四月末に帰郷仕、今日迄無事に相暮し、八十歳の齢に至り申也。此段御安心可被下候。
扨、富田忠右衛門殿は東京へ帰りし後、以書状御訪ひ被下候故、上東の砌に御尋申候処、駿州御在住を承候。東京より帰路御尋申、一宿仕候て永く御物語仕候。 (続)
前便は豊平の花守宛てを渓蓮が写したもの、○同上以下が香亭宛の尺牘だが、幕末の動乱期を経、互いに生死の安否を気遣っていた師弟、とくに、真鍋家をあげての香亭に対する厚情が文面に横溢するし、町田石谷や加藤桜老など豊平周辺の著名人士も判明しよう。
「高士独絃琴調軫図」
大島秋琴著 万延元(1860)年刊『観世居一絃琴譜』より
著者の大島秋琴は名は克、不如睡斎・王克と名乗った。江戸の人だが、諸国を経巡り、長崎では清人に就いて清楽を修め、広島で本文中にある河村百古に一絃琴を学び、また勢南の津で辱知となる隅田子行(陶々居)と出会い、本書を上梓した。
小虎散人寫
25
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第123話
高士中根香亭先生 十四 真鍋藤斎翁伝(三)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
承前
前稿末、真鍋豊平の香亭宛て尺牘に、「サツマ門人町田久成に被伴、上東仕、カサマ人加藤有隣に被頼、…」と遺ることから、幕末薩藩の遣英使節で、帰国後、初代博物局長となる町田石谷(一八三八~一八九七)に伴われ、豊平は浪花から江戸に下ったこと、および石谷が妻鹿友樵に就いて琴(七絃)を学ぶと同時に、一絃琴の豊平門でもあったこと、さらに豊平は、常陸笠間藩儒の加藤桜老(一八一一~一八八四)の依頼により、本来の神職として主に現在の千葉県下で仕えた後、西宮の名社広田神社の祢宜を仰せつかったことなども判明する。
この桜老は、かの岡倉天心の学問の師としても知られる人で、儒学に精しいこと当然だが、神道および礼楽にも通じ、かつ雅楽や琴(七絃)などの音楽を嗜み、天心に琴の初学を教えた人でもある。余談ながら筆者前居の小石川(礫川)同町内で、ご子孫は箏曲など教えておられた。かく幕末から明治・大正期の東台、すなわち上野の相関図、石谷・天心・無礙こと今泉雄作とその師井上竹逸・松井友石・青山碧山など、これらすべては琴を通じた人脈である。
其後御遠行にて後を不知、且君御在坂之節、多人数の御馴染人門人も沢(山)に有之候に、御一新之後は、只の御一人も御尋の人無、只富田氏一人也。貴は元より永き御別れと存候事故、御尋無之筈に存居候処、御無事之由、誠以て大慶無此上。是より御互に以文通、相替蒙御懇命度、先は昨夜御存命を承知仕候。
今朝事なれ共、愚作を入御覧候間、御笑納可否被下候。就而は家内も宜敷申上候也。天満居住の時、国元三番目の孫を養子に引取り、女房を持せ、当年十歳の曾孫男子一人御座候。国元にては娘四人の中、一人死去、跡三人は無事也。右四人の娘の産し孫十一人、孫の産みし曾孫十八人に至り、家繁盛は無此上候得共、何れも困窮家にて、夫のみ困り入申候也。
あなかしく。
豊平は慨嘆する。御一新以前は豊平の一絃琴門人も沢山いたが、明治の御代には富田渓蓮(一八五一~?)ただ一人となってしまうからだ。
はじめ渓蓮の父礫川幕臣)が豊平の門人となり一絃琴を学んでいたが、後には父子ともども学ぶことになり、父が没した後も楽を好む渓蓮は廃さずにこれを続けたため、後に豊平から全国一絃琴取締第二代目の名跡を譲られ、その結果、大正年間の一時には渓蓮の門人はほぼ一千名に達するまでに挽回したのだが、時代の波とともに漸々と衰退の途をたどり、惜しくもまたもとの一握りの閑人の弄ぶ楽器となってしまう。
しかもこのころから男性の手を離れだし、戦後に復活はしたものの、一絃琴はまったくといっていいほど女性の専用物と変化してしまう。
文人音楽をはじめ、煎茶その他の文人藝といわれる藝術世界を男性の手に奪還(失礼)、復権させ、せめても男女同権平等のものとしたいと願うのは、筆者ばかりではなかろうが、ここで確認しておかねばならぬのは、香亭は琴(七絃)を嗜まず、一絃琴を好んだということである。
読者諸賢には「琴」も「一絃琴」も、ただ単に絃楽器の一種と認識されようが、いやいやどうして、一絃琴は本来、七絃琴の絲の真ん中に位置する第四絃をイメージし、そこからあらゆる虚飾を取り去って創作された日本独自の楽器というばかりではなく、単純であるが故にこそ、ただ一筋の絃に心を委ね、ひたすら森羅万象の宇宙観を描きうる秀れた楽器で、それこそ香亭が好んで然るべきものであったからである。
(続)
香亭作「後月」
明治32(1899)年刊
徳弘太舞著『清虚洞一絃琴譜』より
香亭作歌、一絃琴曲の一首「後月」は、蘇軾の「後赤壁賦」を題材
としたもので「後の月」と読ませ、中根貞の名で発表している。
26
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第124話
高士中根香亭先生 十五 香亭と杵村小雅(一)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
承前
暫し真鍋蓁斎を離れ、琴(きん。俗称七絃琴)の話題へと移るが、これも一絃琴繋がりの異聞に他ならぬ。
香亭在世当時の文人墨客たちは、古代聖賢が親しんだ聖器であることから、琴をなお「先王の遺音」と譬え、「琴碁書画」の一等として尊んだが、香亭にとっての一絃琴はさらに琴に勝るとも劣らぬもの。
ここに伯耆米子第五代町長の杵村小雅(名は悳。一八六二~一九四四)があり、どうにかして琴の正伝を得たいものと切望していたが果たせずにいた。それは、米子対岸の美保関突端近くに美保神社があり、古くからここを通過する多くの廻船が、海上航路の無事を祈願し、ご祭神ゑびすさまに鳴りものを奉納する慣しから、中に琴があったことにもよる。しかし、幕末以降明治このかた琴道は日に日に廃れいき、漢学者の矜持も凋落するなかで、世は一日も早く欧米に比肩すべく、一見、閑人の弄す琴どころの騒ぎではなかったからである。
東台から下谷金杉へ通ずる新坂下に、香亭古なじみで文人仲間の大先達井上竹逸(一八一四~一八八六。本連載第3~4話参照)がいて、徒然に撫す琴を何度となく聴いていた香亭である。もともと一絃琴は琴から派生した楽器であることから、琴の伝統にまで興味を抱いていた。明治十九年の四月に竹逸が七十三歳で没した際、遺愛の古琴は道具屋、書籍は古本屋に払われていたものを、三者共通の友である堀越愛古が八方手を尽くして探し出し買い戻した。
すると、その中に琴事の手控え『竹逸琴話』があり、これを香亭が愛古から借覧して手を加え、危うく近代化の浪に圧され世から忘れ去られようとする琴と、一代の奇人竹逸とその著を惜しむ意で、さらに整理だてて明治新興知識人である新聞読者層を対照に、同二十三(一八九○)年六月から『横浜毎日新聞』に連載したものが「七絃琴の伝来」である。
その記事を見た杵村小雅は驚喜し、すぐさま手代をして東京の香亭に刺を通じ、琴を学びたい旨を伝言したことから、以後、香亭が没する大正二(一九一三)年一月二十日までの二十三年間弱の歳月、東都、後には岳陽興津から伯耆と二百余里を相隔て、主に通信を手だてとした香亭と小雅の淡い交友が始まる。
新聞連載の記憶もまだ新しい明治二十三年八月二日。香亭から小雅宛て二度目の返書は、琴を嗜まぬことの念押しと、小雅の琴に対する不要気負いをたしなめる条や、小雅が玉堂自作の琴を所蔵したことからの、玉堂評を含んだいかにも親切心に満ちた内容で、結果的にこれを機に小雅は香亭に心酔し、琴ならぬ心の師として終生仰ぐことになるのだが、筆者十六歳いまだ高校生の折り、この『香亭遺文』中の小雅への応酬書簡群を味読してからは、これまた琴を学ぶ者への箴言とも警句ともとれ、それからはある意、筆者自身も香亭をして時空を超えた師として迎え入れ、以来、努めて自らを律するようにしてきたようなわけなのである。
本文中()内句読註筆者責
再度の御通信、去る三十日夜展読いたし候。
七絃琴に付先般来小生へ御属望之処、前便小生琴学を解せざる旨申上候に付御失望とのこと、御遺憾奉察候。乍併幸ひ浪華に友樵先生あつて、其道を御尋ね相成、兼ての御本懐に副ひ欣喜の至也。
小生が緒言中、学海翁浪華にて云と記したるは、即ち此先生に有之、翁は彼の老人二張(三張、三友草廬)の名琴を所蔵の由承りたるが、此人今尚世
にありや無しやと申し候ひしが、高書に拠れば猶健在の様子、可賀可祝。
尊兄には七絃琴御執心に付、須磨琴(一絃琴)八雲琴(二絃琴)は先ず見合すとの御趣、是は老兄自ら奇癖と仰せ候が、此癖所大に佳なり。
凡そ琴碁書画の類は、痴とか迂とかいふべき処なくて成るものに非ず。假ひ小道といふと雖も、国会議員(町長)の片手間仕事に成るものとは覚えず。迂癖の尊ぶべきことは、沈芥舟学画篇既によくこれを弁じたり。
小生取摘て論じ置きたきは、尊書先王の遺音云々の事なり。心越が七絃の伝来には彼此其道を貶すやうなることを述ぶるは其趣意ならぬゆゑ決して弁ぜざるも、周漢に伝へたる先王の楽は、五胡の乱以来漸く廃れ、唐に至りては殆ど其道絶えたり。
一証をいはば、今の唐楽を御覧あれ(高麗楽も同様 ※香亭註)。琴を用ひずして羯鼓を用ふるに非ずや。羯鼓はもと中国の楽器に非ず。されど玄宗喜んでこれを用ひしより、琴は遂に楽器の中に列せず、全体の楽曲已に斯くの如し。楽器中を押し出されたる琴のみ、如何で能く先王の遺音を保存するを得べしや。明の代には楽器中へ琴を加へたれど、唯其形ばかりを存して一向に用をなさずと聞けり。
扨、明代隠士など伝ふる所の琴は音声短促にして古の物に非ざることは、先儒物徂徠先生既に申置(『琴学大意抄』)かれたり。畢竟心越伝ふる所は唯夫だけの上にて尊ぶことは小生決して異論なきも、是を古賢聖王の遺物と揚言するは心服せざる処に有之候。併是は下手の長談議ゆゑ先ず大抵にして、余は識者の公論に任すべし。
漢音邦人の耳に入り難き意を申述べたるは、至て俗論に近く候へども、披蓑執釣板歌天地(ピイソヲチテヤウハンコウテエンティ)何の味ひかある
空空蘭室の徒は浦上玉堂を琴を知らざるものの様にひたれど、小生は是又一個の名士と思ひ、伝中(『七絃琴の伝来』中)の言葉も幾許か斟酌したり。何を以て名士とすとなれば、高論にもある如く、催馬楽やうなものなどを絃に上す才ありて、独り披蓑執釣の巣窟(天明寛政当時の琴界)を株守せざるを以てなり。方今はやりで申さば、玉堂は保守主義ならで改新主義を取たる人なり。此両主義何れも宜しけれども、唯今共に極端に走りたくなし。 …以下略
天明寛政期における江戸琴界には二つの琴社があり、拮抗して琴学の帷を下ろしていた。
一方は牛込の琴社で、御三卿徳川田安家の文学児玉空々を領袖とし、幕臣を中心としたちょっとお固い感じのする派。また浅草真龍寺の琴社は釈胤こと蘭室上人を仰ぐ琴派で、諸藩江戸勤番の武士や反官学派を中心とする比較的穏健派であったが、そうした社中連の下した多くの浦上玉堂評は、重複を厭わずに挙げれば、その大方は牛込琴社の幹部新楽閑叟(一七六四~一八二七)の『絲桐談』(未刊)の語を踏襲したものである。
浦上兵右衛門、玉堂琴を得て法印(多紀藍渓)に就て調絃及び南薫操なと受くといふ、然共僅に二、三曲にして未熟と見へ、今玉堂か鼓するを見れハ、指法節奏いささかも似す、惟譜字を解する事を得たる故、自ら我邦の歌(催馬楽)を此器(琴)に合せ弾くことにしたり、
(続)
「杵村小雅小照」
香亭の新聞記事が契機となり、琴道を学ぶ宿志が叶った小雅晩年の撫琴する姿である。
恵与されたもとの写真があるのだが見当たらず、やむなく『斯文』106号中の拙稿から転載させていただく。
「蓬莱僊境之図」井上竹逸筆
竹逸は十七歳で渡辺崋山の門に入り、後に四天王に挙げられたほどの画人でもあるが、売画を嫌ったため、いたってその遺作の少ないことはすでに連載中に述べた。
「歳次文久癸亥夏五写於仙谷山中」との讃で、1863年の初夏、長崎もしくは駿府への東海道往還の途次、箱根仙谷山にて描いた景であろうが、朝まだき山並の向こうに昇る日輪は、幕末、国事多難の際の竹逸壮年の心象
を反映して意味深ではある。
25
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第125話
高士中根香亭先生 十六 香亭と杵村小雅(二)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
承前
玉堂がものしたところの水墨は、今日では国宝・重文指定されるほどだが、いみじくも玉堂琴士と名乗り揮毫した玉堂の琴士たるその所以は、琴韻なくして語れぬこと無論である。
書画は作者の没後にも遺りやすいが、すでにして生前からその作品の水準には定評あった浦上玉堂である。一方、時間藝術である音楽作品を評価するには、実際に自分の耳で聴いて判断するよりほかはなく、しかも音楽に疎く、学ぶこともなく、さらに興趣もなければ良否の判断すらつかない。そうした風潮、しかも少ない資料の中で、香亭は玉堂の評価されにくい音楽家部分の真価を、すでに百二十年もの以前に見抜いていた。その香亭と縁あって、師とも畏兄とも慕った杵村源二(次)郎は、諱を悳(すなお)、藤源と名乗り、字は与卿、小雅と号した。
文久元年(一説二年)伯耆国会見郡米子町日野町の産で、幼少より漢学を修め、三十八歳の若さで米子第五代町長となった君子人である。
ちなみに、この小雅が大坂の妻鹿友樵(ゆうしょう)のもとに琴学稽古に通ったのは、新聞連載の完結した明治二十三年から同二十九年までの六年(一八九〇~九六)間のことであった。
聖堂附属の昌平黌が御一新で廃絶後、明治十三(一八八〇)年にこれを踏襲した文学会が創立され、大正七(一九一八)年に斯文会として新生改組された翌八年、五十七歳の小雅も引続き新会員となった。
後に関東大震災で全焼した聖堂は、昭和十(一九三五)年の三月、明末貢士朱舜水将来の孔子像が皇室から下賜され、四月には官民挙って復興聖堂竣工式と孔子像鎮斎式が盛大に行なわれ、小雅もはるばるこれに参加したのである。聖堂および附属の建築物はこの機に国に献納されたが、この一連の祭典に感激し、また自らの春秋を悟った小雅は、愛琴「小雅」を聖堂に納めることに決し、翌年十一月に無事献納したのである。
これより以前、小雅は陶潜ばりに「吾れ五斗米のために腰を折る能わず」とばかり、わずか一年足らずで米子町長をあっさりと辞任し、その後、糊口をすすぐために古玩店を営んだこともある。といったもともと数寄者の立場から蒐集した書画骨董のなかには、古い琴もあったのだろう。玉堂自作の琴ばかりか、図版の「小雅琴」の他に三面、都合四面の琴を所蔵していたのである。
以下は、かつての筆者フィールドワーク・ノートから玉堂琴部分抜粋。
杵村小雅旧蔵「玉堂自製琴」
琴式列子様(雷琴式)
無銘
黒漆 無断紋
胴內墨書銘
寬政卯季小春造于玉堂中
琴士 印 弼
※列子様は『雷琴記』からの模倣式で、俗に「雷琴様」と呼ばれる琴式は、玉堂模作中、もっとも遺例の多い琴式である。琴箱が遺るが蓋を佚し、そこに「伝浦上玉堂先生愛用〔万木澄幽陰〕」との墨書があったらしい。詳細不明。現山陰歴史館蔵。(続)
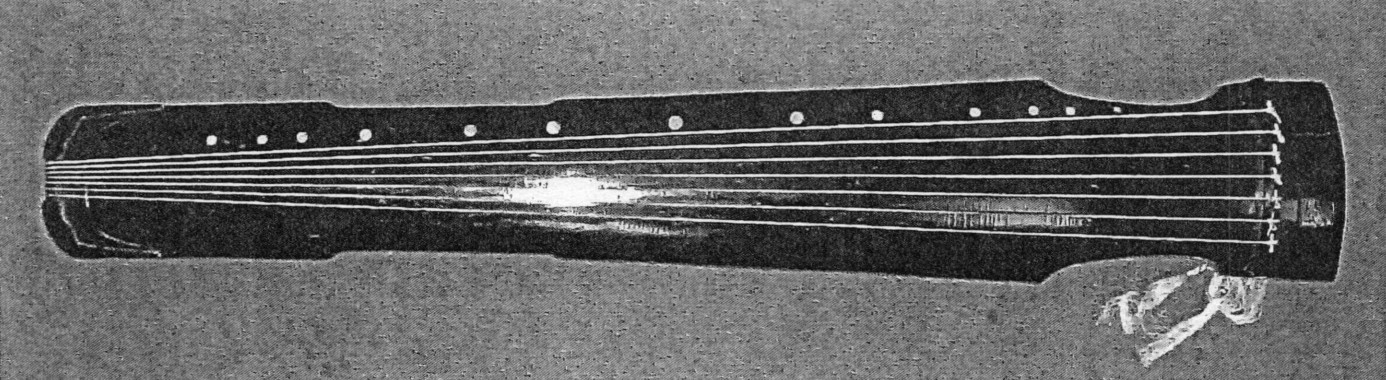 明琴「小雅」湯島聖堂・斯文会蔵
明琴「小雅」湯島聖堂・斯文会蔵琴式・仲尼様/琴銘・小雅/軫雁・古白玉/黒漆・琴面大蛇腹断/
琴匣墨書「昭和丙子十一月吉日 古桐恭献大成殿 聊表平生仰慕心 山陰米城小雅琴士藤愿謹書 印 印」
明琴「献納目録状」湯島聖堂蔵
「聖堂の琴(一)」坂田進一稿
『斯文』第106号(昌平黌創建200年・斯文会創立80年記念号1998参照)
献納品
一 古琴一張
右 聖堂江献納致し候也
昭和十一年十一月三日
斯文会員 杵村源二郎
斯文会会長徳川家達殿
27
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第126話
高士中根香亭先生 十七 香亭と杵村小雅(三)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
承前
浦上玉堂楽道の真骨頂を伝える主著『玉堂琴譜』前・後集(後集は未刊)は、平安朝の遺譜である箏譜『仁智要録』と、琵琶譜『三五要録』を土台とし、これに玉堂が理想とした琴の手附を新たに施した、催馬楽を中核とする琴譜である。
その姉妹編『玉堂雑記』は、『玉堂琴譜』をなぜに上梓したのか、また催馬楽の成立と変遷などを織り交ぜ、数多の古楽書による裏付けにより考証する過程で、いかにこれを理論づけ正しく復元したかをいう、いわば虎の巻であるが、この二編によってこそ、玉堂の意図した催馬楽の世界が実現したといって過言でない。その『玉堂雑記』にいう。
本文中()内句読註筆者責
…いまの神楽。つぎにハ。我国風俗催馬楽とておろおろ(部分的に)のこりたる事どもなり。楽といふハから国の歌ハ詩なり。この朝のすなワち神楽。風俗。催馬楽の詞なり。かやうにたゑたゑなるから国の歌のこわふりをうつしまねびたるを。楽とハいふなり。なほく吹ものハ。笛の調子。ひき物(絃楽器)ハ箏の撥合比巴(琵琶)の手揃などいふ。皆其器ものにつきたることなれど。其手などにも猶其伝ありけり。此朝につたワりきて。其歌ハつたワらず。音曲ばかりつたワりきたるとや。纔に其声に付たるほどの事だにも。すたれゆく。世の末心ぽそくかなしと云々
さらに条を改めて玉堂のいうには、
○延喜のおほん世にやありけむ。藤原忠房朝臣に 詔して。催馬楽を作らせ給ひ。
孝道抄云。延喜二十年。依勅定左近中将藤原忠房朝臣作催馬楽譜云々。貞治二年十一月廿一日於仙洞御所撰歌楽。御抄或秘抄中有此事云々。又一条左大臣殿令造之由。見治国鈔。
朝廷の御宴享にも用ひ給ふ。(催馬楽は)所謂詩の国風にして。其声ハ元三代の古国より伝来れる楽曲。房中の遺声なるべし。
仁智要録題下の注。其他古き楽書に。某の楽奏ハ。某の催馬楽と同音なりといへども。唐土の楽に
皇国の詞を被らせて。うたへるなれバ也。
そのかみ漢土より楽を伝へ来にけんに。其歌をも習来るべけれど。
皇国の人の耳に親しからねバ。いとさやぎて聞えつるほどに。
皇国のふりにあらざれハ。教としがたかるへし。たゞ彼国のふりをのミ擬鼓(古)する。琴(箏)柱に膠する類とやいはまし。
と。
さてと、香亭が玉堂を引き合いに出したのを機にかくは寄り道となったもので、ここに右顧左眄するようだが、またぞろ、香亭から小雅へ宛懇切丁寧で慈愛に満ちた書簡内容の旧路へと戻ってみれば、香亭が一絃琴を善くしたことは言するまでもなく、一時の琴への執心から、香亭を人生の師と仰いだことで、結果的に小雅は人間としてばかりか、望外のいかに多くの琴事に繋がる事項を教えられ益したことか。
そうした個々の例を、我々後生は、小雅宛の書簡中に星の煌めくがごとくに認めることができるし、さらに読者をして香亭の慈眼下に自ずと置きかえざるをえないこととはなるのだが、それにしても香亭先生の博覧強記ぶりと禅機に支えられた心胆には、さすがの現代人も時空を超えてしばしば驚かされることであろう。
近作御尋ねに預りしが、御覧に入れ候程のものもなし。旧作なれど、前文の楽に関係したる詩有之候間、左に記し申候。
博物舘中簫鼓鳴
碩人成列舞秋晴
衣冠尚見唐時制
雅頌長伝漢代名
詩絶譜存知曲古
文多武少憶時平
桑間濮上聾儂久
両耳慙難受大声
東台下に生まれ育ち、徳川氏の瓦解を渦中の人として目の当たりに体験、そうして下谷根岸から日夕東台を抜けて明治新政府にも仕えた香亭である。縁あって明治十五(一八八二)年三月の上野博物館の開館式にでも出席したものか、そこで舞楽公演があったものと見え、七律は一見その晴れがましい内容を詠うようだが、尾には、世俗に塗れて楽を聞きすぎた自分、すなわち巷間一処士で耳の不自由なものには、そんな大音響で演じられる立派な演目は、は相応しくなく、聞いても理解できないと。無論、香亭胸中は旧幕の士人である。台上における過ぐる年の戦火と新博物館とを憶えば、うたた寂寥、胸中少なからず去来するものがあったのである。
博物局(館)基盤とその成就は、旧薩藩士町田石谷(一八三八~一八九七)こと久成(ひさすみ)畢生の事業であった。この人物についてはさらに詳しく稿を改める必要があるが、石谷は東台琴客の一派を荷なう重要な構成員でもあった人で、手塩にかけ完成させた博物館初代館長をただ一年で逐われ、その機に剃髪、諦観して愛琴を松井友石に委ね三井寺に入ってしまった。最晩年は東台へ戻り、静かに博物館周辺を見守りながら、韻松亭の女将に看取られて慫慂として逝ったとある。
香亭がこの七律をものしたころは、いまだ石谷の博物局長もしくは館長職のころと重なるころで、旧弊な文士然とした野に下った前者と、一流の官吏から左遷された後者のことである。恐らくは香亭と石谷との接点は多々あったと推察はされるものの、惜しいかな、その根拠と証左はいま曖昧模糊のうちにある。
左の一首は貴地に関係あるもの故、御覧に入れ候。
おきつ風 八重の汐路を吹越て 波の花さく 船の上の山
何れも可然御粲政下れ度候。小生著書数多有之候様、御聞及の趣なれど左程無之、山県大臣が題名を附けられたる兵要日本地理小誌は拙作にて、世に地理書なき時ゆゑ、随分骨を折り候ひしが、方今は他に良書沢山出来申候。文典(日本文典)も十五六年前の作にて、只今見れば誤謬だらけ也。近年都の花といふ小説雑誌へ謡文評釈を載せ居候間、御閑暇の節、同雑誌御覧を乞ふ。此他五六年前上木の香亭雅談二冊、近日呈上致すべし。是は奇人伝畸行伝などになき風雅話しを集めたるものにて、他書より取来らぬ所が、ちと自慢に御座候。此外大著などは全く無之。
心越肖像模写御依頼承知致候。至て簡筆なれど、雅閑の節、緩く写取送上可仕候。
○鶏卵料として郵便切手御恵送、度々返上も失礼に付、難有拝収仕官候。
時属酷暑、高履御安重是祈
八月二日(明治二十三年) 中根 淑
杵村樣
研北
こうした書簡中、往々にして見られる香亭一流の人生哲学や物事の見方、また事物に拘泥せず、高ぶらず、飾り気のないサッパリとした江戸っ子気質は、ことに当時在野の学者や知識人たちの共感をも呼び起こし、一定の支持を得ていたことも大いに頷けるし、共感もできよう。(続)
『香亭雅談』明治19(1886)年 金港堂刊
陸軍省『兵要日本地理小誌』明治5(1875)年初版は、兵要教科書の性格上から著者の名は伏されたが、後に香亭の名を一躍高からしめたのが、本文中小雅宛てに約された該書で、その前後が香亭の筆が一等乗った時期である。
【右】琴銘「小雅」 湯島聖堂斯文会蔵
明琴の背に小篆刻された琴銘には、漆の断文がないことか
ら杵村小雅の蔵に帰した後のものと知れる。
25
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第127話
高士中根香亭先生 十八 羽倉簡堂
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
香亭の生まれ育った下谷御徒町(長者町)に、時の老中水野忠邦の天保の改革に際し、その才をかわれ幕府御納戸頭を勤めた碩学羽倉簡堂(一七九〇~一八六二)があった。簡堂の名は用九(もろちか)、字を子乾、通称を外記、また簡堂、天則、可也、蓬翁、小四海堂などと号した。
父の羽倉秘救(やすもり)は麾下の士で、各地の代官を歴任し、ために簡堂は浪速の任地で生まれた。
古賀精里門に学び、齋藤拙堂、篠崎小竹らと交わり、父の転任で豊後に下って広瀬淡窓の咸宜園に学んだが、秘の逝去にともない、文化五(一八〇八)年に家督を相続し、代官として武蔵、上野、下野、房総、駿河などの各地を歴任し、天保九(一八三八)年には伊豆七島を巡検し、『南汎録』を著すなど、広く天下の情状に通じた実学者で、各地の人脈に通じ、また交友の広かった人物である。
翌年五月の蕃社の獄に際し、友人渡辺崋山ら尚歯会の連中とともに連座。御目付鳥居耀蔵に糾弾されたが、水野忠邦の庇護により、江川坦庵と簡堂らは危うく難を逃れた。忠邦が失脚し天保の改革頓挫後、簡堂は下野し巷間帷を下していたのである。
香亭青年十八九のころ俄然目覚め、初めて文を学ぶ志を立てたものの、良師友に恵まれず、そこで念いあぐね、とある日町内の簡堂翁を訪ねたのである。すると、すでに齡七十の翁は案に相違し、
子、文を好むか。(香亭青年よ)
老父、敢えて子を欺かず。
文は自ら做すにあるのみ。
師を待ちて後、(師に頼り)
必ず浚工するにはあらざるなり。
と曰うではないか。
香亭は厚く翁のその言を信じ、退きて後自ら勉め、それから『孟子』、『荘子』、『春秋左氏伝』、『国語』、『史記』などの各書を熟読し、また『唐宋八家文』を暗誦し、誦してこれを思い、思いてはこれを倣い、熟習することを続けた。そうすると、未だ古文の深奥はよく理解できないものの、その意を写し言を載するに、本当に難なく覚えることができ、翁が去って久しいが、その日うことが正しかったのを実感したのであった。
(『作文要訣』自序)
その一方で、香亭から杵村小雅へ宛てた気のおけない書簡には、
僕十七八の頃、羽倉簡堂翁の塾に半年斗り通ひたれど、其頃翁は聾病みて応対も出来ざる程なりき。
とあり、多少ニュアンスの違いこそあれ、簡堂との話もただ一日間のことではなく、一応は簡堂塾に半年ほどの短時日ではあるが在籍したこと、そのときすでに簡堂は不自由な身体であったことが知られる。
わが国学制のいまだ整備されぬ以前の天保(一八三〇~四三)年間寺子屋の普及は頂点に達し、全国各地にその数一万七千に及んだという。旧文部省の調査では、明治二十(一八八七)年ころまでは幕末期と変化なく、男子で五~六十%、女子で三十%というから、そうした影響もあってか、黎明期陸海軍兵士の識字率はあまり低くはないが、一般兵士の教育は学校教育の先行代行でもあり、明治新政府としては全兵士の質を高めることは急務かつ悲願で、そのための必須教科書の一が、陸軍大輔(大臣相当)山県有朋命名するところの中根香亭著『兵要日本地理小誌』であったいうわけなのである。
この『兵要日本地理小誌』を除いた明治十年代ころまでの香亭の主著に、『日本小文典』、『日本文典』、『慶安小史』、『独学日本地理書』、『筆法小学』、『作文要訣』などがあり、さらに香亭間近の友人との共著の形をとったものや序文なども多くある。そうした中からすでに本連載においてもいくつか取り上げたが、さらにその辺りを散策してみようか。御一新の以前、早くも英学を乙骨太郎乙、小林弥三郎、薗鑑三郎、石橋好一らに学び、かつ幕府開成所に通うなど、開明的な一面をあわせもちながら、世の推移を見つめる慧眼と、さらに儒仏で修得した無常観と禅機とを併察し、自己の身を以て体現しようとしていた香亭である。
徳川家宗主の静岡移封にともない、明治元(一八六八)年十二月に「沼津兵学校」が開校され、その二等教授に任命された中根香亭。たびたび言を重ねるが、その胸中はいまだ幕臣のままである。
沼津兵学校は同三年に陸軍兵学寮の所轄となり、同五年には兵学寮と統合され、沼津の教授連は階級に応じてそのまま新陸軍の少佐や中佐に任ぜられた。香亭は新政府の陸軍少佐となり、静岡を離れて東京の陸軍参謀局に出仕し、そこで『兵要日本地理小誌』(同五年初版)を伏名で編纂することになるが、該書は版を重ね、黎明期日本陸軍で育った兵士の間に香亭の名は普く知れ渡った。
なぜならば、旧幕期の兵卒は概ね旧各藩の下級士族が主体であったが、明治六(一八七三)年の徴兵令で国民皆兵制となるや、創成期陸軍の徴兵した新兵の大半は農家の二三男となり、さらにほとんどは故郷の田畑を離れることあたわず、生地の近郷近在を知るのみで他郷を知らず、そんな新兵たちに近代日本地誌の概要を知らしむることを急いだのである。また、徴兵令と文部省の学制はほぼ同時期の発布であり、そうした農家出身者の中に寺子屋経験者があればこそ、当然のこと学校卒業者は皆無という中で、新兵の地理学習に果たした『兵要日本地理小誌』の実益は多大であり、除隊後の新日本国民地理感の基盤となり、除隊したもと兵士の青年たちには貴重な知的財産となったのである。
一転、この『兵要日本地理小誌』に次いで人口に膾炙したのが『香亭雅談』である。『兵要日本地理小誌』とはまったく正反対の文字に遊ぶ明治中期の教養人士を対象としたもので、彼ら必読の文雅の書とされたが、かく両極の人士からも敬愛されるようになったのがわが香亭先生である。
香亭自らの巻頭言から、著者その意としたところをなぞってみよう。
雅は俗の反りなり。
談は雅を以て名づく、
その俗ならざることを知ればなり。
然らば雅俗とは猶白黒のごとし。
物の黒からざるは、
未だ必ずしも皆白からず。
矧(いわん)や雅の俗と、
俗の雅とは与に形迹相類し、
誠に弁じ易からず。
昔、九方皐馬を相て、その精を得、
而してその粗を忘れ、
その内に在りてはその外を忘れ、
牝牡黄驪を言わずと。
及ぶこと能わざると雖も、
吾庶わくは之を学ばん。
と、この小序文末に『列子』より引く「外見にとらわれず、事物の本質を見なければならぬ」意こそが、香亭の自著に命名した所以である。
さらには、該書の点者の責を担っ依田学海(一八三四~一九〇九)が、香亭のために書いた跋文をご紹介すればなお補足できるであろう。
『作文要訣』見返し
中根淑著
明治11(1878)年
迷花書室私家版
木上月二十年一十治明
中根淑著
作文要訣
迷花書室薏蔵
下谷「羽倉簡堂邸」
近吾堂版『江戸切絵図』 嘉永3(1850)年刊より
通常、こうした地図の根拠は上木数年前のものである。
絵図中央列の上部◎印が香亭の生家曽根氏で、すぐ下印が養家中根氏、羽倉邸は中央列の右下印となる。
ちょうどこの三家を含む一帯は後に上野から秋葉原貨物駅の引込み線上となり、現在は山手線高架下で、JR御徒町駅が曽根氏の上辺となる。
中根香亭画「俳聖芭蕉翁小像」
木村架空著
明治29(1896)年中央堂刊本より
『新釈奥のほそ道』初版本の巻頭を飾る挿絵は、微細な雲母を散らした和紙を用いた木版画仕立で、いかにも凝ったものだが、心なしか芭蕉行脚姿のそれは、香亭自己の姿を投影させたものに見える。
33
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第128話
高士中根香亭先生 十九 木村架空
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
香亭の仲の良い兄貴分格で、『香亭雅談』の評点と跋文をものした依田学海(一八三四~一九〇九)は、下総佐倉藩の上士依田貞剛の次男に生まれ、藩校「成徳書院」に学んだ後上京し、東京商法会議所の書記官となり、さらに文部省に出仕し、ま音楽学校の前身である音楽取調掛に任命された。森鴎外の漢学の師でもあり、漢学者たるほか、文芸評論、文士、戯作など多方面で活躍した人である。幼名は幸造と信造。通称を七郎、右衛門次郎。諱は朝宗(ともむね)。字の百川を後に本名とし、学海また柳蔭と号した。主著に『学海画夢』、『新評戯曲十種』、『譚海』などがある。
なお、跋の原白文を読み易くするため、句読を点ち、改行し()の註を加えたは筆者の責にある。
香亭雅談跋
児童戯甲俯其手、
乙以指摘之。(つねりっこ)
甲忍痛又摘乙手。
層累重畳更代相摘、
高如其身乃止。
謂之鼬戯(いたちごっこ)
禅家初機降相对遂不相下、
互相弁難。
高者益加其高、
邃者益加其邃、(邃=奥深い)
各自謂彼所見浅近耳。(あさはか)
不若我之高且邃不去甲乙、
相摘更代層累、
是亦一場見戲矣。
余不解禅理、
而友人中根香亭頗好之。
毎相語動不相合。(意見が一致せず)
頃読其著雅談、(雅談を読むと)
稍有及此理者。(やや理があるか)
余益不服、(否、まだまだ…)
遂書鼬戲以質之。
若夫書中叙事精細写古人処、
鬚眉活現、文気益高、久情益邃。
余則爱手在下風矣。
明治十九年二月
学海居士 依田百川識
学海の日うには、ただ、児戯に喩えてはみたものの、貴君の活人筆に、あたかも古人の動くさまを眼前にみるようで、己の手掌(機心)は貴君の下位にあるであろう…、と負けず嫌いの学海にいわしめたものである。
すでに述べたごとく、香亭の書斎「迷花書室」は下谷金杉村にあった小荘園で、これは、もとの「御隠殿」三千余坪の一画にあたる。ちょうど現在の書道博物館を含む辺り一帯の千五百坪あまりが香亭の土地であり、無論、故林家三平師の祖父も中村不折画伯も、鉄路が開通して喧噪の地となったことを嫌った香亭が、この荘園を手放した後に分割分譲されてからの話である。
この他、香亭は明治中期までに和文、漢文に関する教科書などを多数ものしていたが、おおむね自身が編集長を勤めた金港堂発兌を中心とす教育書であった。
さて、かく雅俗両極の人士から敬愛された香亭先生。香亭間近の友人との共著も多く、その一例としてはじめ香亭に私淑し、後に忘年の友となった木村架空こと正三郎がある。
この架空は牛込仲町に住み、当時翻訳と俳句研究をしていた著名の出版人であるが、香亭の句を読み、その評文を香亭に送ったことから文通に発展し、それを契機に香亭を師とも友人とも慕いはじめたのは、かの杵村小雅と同様ではあるが、東京を拠点とした架空は地の利を活かし、平生、何是となく駒込の迷花書屋、後には興津の香亭仮寓を頻繁に訪れては、互いに好きな一絃琴やら尺八の研究みたようなことをしたり、俳書や翻訳、文学一般、また世間四方山の話を語りあっていたが、香亭最晩年の没するその枕頭に侍り、『香亭蔵草出版及び中根先生易簀前後の事』という先生寂滅の瞬間を共にした人でもあるが、惜しくも小伝は煙没している。
明治二十五(一八九二)年の極月、その交友のはじまったころと思しき香亭から架空宛の返書があるが、文面からは、若輩に香亭はその心のうちを読まれたことを嫌わず、かえって好ましく思っていることがわかる。
拝啓。拙文御評隲(ひょうしつ)被下難有、只今謝書可認存居候矢先へ、尊翰飛来、即時捧誦いたし候。
高文おもしろおかしきに比すれば、誠に小乗門、無知の輩を成仏させる外、何の効能もなし。但し、つまらぬおふみ様でも、幾許か意を用ひたる所なきにあらず。然るを尊評にて、だいぶ種を見顕されたる様な塩梅、恐喜交々、胸に集り申し候。
先の評者は○○○○の教授、随分天狗の先生なるが、之を作る手は知らざれ共、之を観る目は後に附て居るやう也。定めて御一覧はありしなるべし。世の中の大先生といふもの、大方此類かと思へば、甚歎はしき様なものの、其替りに素人に如何なる英雄あるかも計られず、左様に考来れば、世はこはい様な、こはからぬ様な変なものに御座候。
夫等は拝芝にて細に可論。但々高評著々竅に中り、大に満足致候間、右御礼書中を可以、此病人御尋被下難有。去廿四日より牛乳少々づ通り候様になり候間、最早追々快き方に向ひ可申と存候。過日は大取込に御匆々申上、心ならず萬々奉謝候。
猶御全家万福御迎歳是祈。
臘月三十日 淑拝
架空才弟
文 幃
度々の一筆啓上、話が段々入組候様なれど、今一度意中申述候。
授衣の時節がら、思はず着物で評したれど、決して甘酒屋を以て視たるに非ず。実際云々、是は書き様が宜しからざりしなるべし。こんな処に実際も屎もいらぬこと、只不二のてつぺんでも、浮世のうき雲は免れ難しとの意也。
やれ衣の二句めは、めのこ勘定にも致さゞるが、口の内で字数が合つて居る様な心地致し、夫には心付かで、却而詞に調ふらぬ処でもあるかと、乙な方に首を突っ込申候御陰にて、大疵を療治仕候。言葉は無論、御高説の驚きなせそに従ひ可申也。
古来字余りの歌は沢山にあれど、字足らずはいろは歌と是のみといへば、少し価値もあるやうなれど、心附けられても、まだ知らぬとは、自分ながらあきれたる話に御座候。
此頃蕉翁の御宮とやらんが棟上式を挙行したる時、俳人が時雨といふ題で咏じたとか申句を、新聞にて一見いたし、
初時雨冬木の蔭を宿にして
と顰に傚ひ候が、味知らずの境界、句になるやならずや、無我夢中、物になりさうなら、御筆削被下度候、余談海の如し。
何れも拝晤に申残候不宣。
十月十七日(明治二十六年)淑拝
架空詞友
※架空曰く 先生の初時雨の句は、深川冬木町に、花の本神社とか何とかいふ、芭蕉のお宮の出来たる年の吟なり
『香亭雅談』巻上より
欄外、依田学海の評点部および、香亭の巻頭言(前号参照)
【香亭雅談卷上
俗自其嗜好者
摩海日所謂雅雅俗之友也談以雅名知其不俗
「言之彼以為雅。此以為俗同
其不俗也然雅俗櫛白黑也物之不黑者未必皆印緋雅之桜興俗之雅形迹類不易辨也昔者九方
與同好者道不可與不同好者
臯相馬得而忘其祖在其内而忘忘其外不言牝牡黄驪雖不能及吾庶學之癸未抄迷花室主人、
古人自題其肖像者甚多資辭雖非莫謙傲之
別言出於己口有不可揜者焉如石丈山源白石賴山陽自賛可以觀也吾亦嘗使寫真自書
香亭雅談卷下終
『香亭雅談』巻下より依田学海跋文部分
明治年19(1886)年2月
本文参照
『頭書 保元物語』
中根香亭著 明治24(1891)年刊
巻頭におかれた香亭手跡の「はうけむものかた里」
27
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第129話
高士中根香亭先生 二十 木村架空(二)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
引続き、香亭とその忘年の友木村架空のことである。
鉄路の喧噪音から逃れるため、すでに香亭が下谷金杉から本郷曙町に移ってからの交友に始まる。
架空は香亭の迷花書室を屢々訪れては、好きな一絃琴やら尺八の調査、また文学一般、四方山の話などを解って語りあえる、いうなれば益友であり、その架空に宛てた香亭の書翰を通読すれば、多少やんちゃな愚弟に例えられよう杵村小雅のそれとは、かなり内容の違いが認められる。
架空に対しては、どちらかというとかなり磊落かつ意味深なものが多く、その多々斟酌せずとも通ずる応酬の端々に、さぞ香亭の心中、莞爾とするものがあったであろうこと、そこに、江戸の文雅の粋人が遊びに興ずるようなものが感ぜられるのである。
昨日之天気は食はせもの、何やらまだ湿暖を帯居候様存候。両書度々之往復、話は遂に港へこぎ込、愈面白くは相成候へども、最早大抵日和を見計ひ、是等で帆を揚げ可申也。
但し最後の口上、今一応申述候。
字足らず一件と見ればの例を以、御救ひ下され候へば、どうやら別に韻致もありさうに聞ゆれど、是は実以、前便に申たる通り、間抜より生じたる大失策、一晒(しん)に附し候より外無之、併御注意により創口も癒え、どうかかうか健康らしく見え候は仕合之至也。
初時雨の句、至極おもしろしとの尊評、且翁の夏木立と照応致す迄、御覧被下たるは、近頃分外の幸福也。然るに一昨日、故の尺(振八)氏の養子披露にて、亀清楼(柳橋)に招かれ、角田竹冷(真平)同席なりし故、不二登山の話致したるに、同人も先年登山したること有之趣、因て其節の旬なりとて、
「友だちの笠着て無事にふじ詣で」
といふ句を聞かせ候より、透さず初時雨の拙吟を話し、可否を問ひたる処、時雨が既に冬の季なるに、冬といふ詞ありては、僅きり詰めたる十七字中に、遊びがあつて締らずとの評、成程夫もさうかと閉口仕候。元々不案内之事ゆゑ、諸君之評次第、自分には少しも分り不申候ことのはの高作、拝吟右返しとにはあらねど、
ふみかさね言葉の林分行て 未だ見ぬ道をしるぞ嬉しき
鸚鵡返しのやうなもの、是もやは急場しのぎの類なるべし。余は面布を期し茲に明叙せず。 不備
旧重九後一日
(明治二十六年十月十九日)
淑
架空詞宗
文 壇
「春江泛舟」中根香亭戯画
明治6(1873)年
沼津兵学校が明治5年に陸軍兵学寮に統合された翌年冬、倉卒の間にでも描いたのであろうが、幕末の動乱期を身を以て経験した香亭である。御一新への淡い期待と、閑居への憧れが画面に横溢して読める。
28
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第130話
高士中根香亭先生 廿一 木村架空(三)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
更科山とよぶべかりけりふりはへて来しかひもあり信濃なる
拙稿はこの香亭先生副題のもと、連載はもはや二一回を数えるが、その一八の折り、架空著『新釈奥のほそ道』を例に出した。
香亭にしても架空にとってもある一面、芭蕉の超俗性と飄逸さを帯びその生きざまと旅癖が彼らの一大指針となり、ことに香亭の場合には、その前半生においては幕府軍人お役目としての旅。後半生においては旅そのものが目的となる旅で、実際にも精神上においても旅をし続けた人といえようか。
書肆金港堂の編輯主幹として活躍し、多くの文人学者を世に引き出し知らしめた功績もある香亭である。明治も半ば過ぎてからの業務繁多の合間には書堂を抜け出しては、全国各地を馳せ巡ってその烟霞癖を満喫していたのである。
拝啓、今度そろ神に取りつかれ、突然信濃地方へ遊歴いたし、昨夜旧暦の十六夜に乗じ、姨捨山へ登り申候。
をば捨てといふ名はゆゆし 今よりは
さらしな山の秋の夜の月
此度の漫遊は、是が第一の風流なり。
帰京後たつぷり御話申上ぐべし。
屋代停車場にて筆を借りて書す。
(明治二十七年十月十六日)
中根 淑
木村正三郎 様
今度之旅は僅に一週間なりしが、妙義へ登山、善光寺へ後生参りいたし、夫より直江津へ出掛申候。
尊著奥の細道を羽黒の俳諧興行まで閲し、俄に此旅行を企て候故、
越後路は先になりけり あとの雁
とやり申候。
扨、帰途川中島古戦場を訪ひ、夫からとうとう例の姨捨へ赴きたるわけ也。同地は唯今にては歌の名所といはんよりは、寧発旬の名所と相成居申候。門前にも芭蕉翁面影塚と書したる竪石有之。別紙は旅宿で写したる画也。そこで直に写したるに非ざれば、少しは相違もあらんが、先ず此様な処に御座候。其中拝宇、委しく御話し可仕故に、一々絵解不仕候。匆々不二。
十月二十三日(明治二十七年)
淑 拝
架空俳宗
文 几
前便の日付と後便のいう「僅に一週間なりしが、」を比べるとなんだか違和感があるが、わざわざ再度同一方向へ出直したとは考えにくいので、多めの一週間ほどをざっといったものでろうか。ともかく、このころは香亭の烟霞癖に盛んに火が点いたものとみえるのである。
芭蕉は貞享五(一六八八)年の八月に木曽路を経て姨捨山へ行き、「更科紀行」を書き、翌年三月から「奥の細道」への吟行へと出たのである。
本日はおつくりした西施と相成、己等は是も一興と存ずれども、子供や大道商人は気の毒に御座候。
偖、奥の細道中、句解御削正の分寄せられ拝見仕候。注文簡潔にて申ぶん無之、海棠睡未足の典故は、先達て閲読之節、添へようかとも思ひたれど、西施に楊貴妃を持て来るにも及ぶまじと差扣へたる也。
然るに美人の眠りをいはれなく持ち出した様に思ふものもあらんかとの老婆心、今度書きそへ申候。
(続)
「『夏木立二編』表紙 中根淑編
明治23年(1890)年4月 金港堂刊
大手書肆の金港堂は、明治21(1888)年に、山田美妙(1868~1910)を編輯主幹に、短編小説集『夏木立』を発刊し評判となったが、美妙の去った後、香亭はその跡をも継いで主幹となり二編を出したのである。
36
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第131話
高士中根香亭先生 廿二 金港堂原亮三郎と上海商務印書館
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
(承前)
然るに美人の眠りをいはれなく持ち出した様に思ふものもあらんかとの老婆心、今度書きそへ申候。御取捨は貴意に一任す。韻府には楊太真外伝にある趣記したり。
前月末染井にて御懇意の野村に逢ひ候故、越前地方にて白山の見ゆる塩梅を尋ねたるに、尊註の通りゆゑ、あの処は十分安心なり。奥浄るりの事、慥に存採叢書と覚居たるに、同書中にはなしとは閉口也。水戸の彰考館に一本あるのを取りたること記しあるをさへ記憶せり。書名は何とありしか今一応御検閲有之度存候。高吟三首拝唱。「涙煮え入る」如何に悲しくとも、古き仏などには通用致さず妙く。
此程例の沼津兵学校を創立したる阿部氏の病気を亀戸村迄たづねに参り、刷け次手に梅荘を訪ひ、
草廬三顧
雪より白き梅の花
とやり申候。いつも素人、迚も商売人にはなれ不申、御一晒可被下候。
(明治二十八年二月十一日) 淑
架空詞伯 玉机
架空名は正三郎。香亭中年からの忘年の友で、香亭寂滅の枕頭に侍り、その瞬間を共有したほどの人だが、牛込中町(現宮城道雄邸と中町図書館の中間)住で、大日本図書株式会社に勤務し、一絃琴を善くしたと伝わるのみで、惜しくも架空詳伝は煙没し他に知る由もない。
さて、以下は香亭の文才に惚れ、これを金港堂へと誘った同社主の原亮三郎(一八四八~一九一九)のこと。
原は美濃の福寿村の産、代々ところの大名主で旧名を伊藤寿三郎といった。十六歳にして父の跡目を継ぎ、明治元(一八六八)年に新東京に出て駅逓寮雇吏、同六(一八七三)年には神奈川県吏となったが、香亭が沼津から東都に移籍したころは、未だ原との接点はなさそうである。
壬申歳。復帰東京」。 與友人飲於湖上。
故園春色億曾遊
一醉小西湖上楼
忽見佳人翻袖舞
風光不減旧揚州
原は明治八(一八七五)年に横浜に書肆金港堂を創業し、翌九年には都下中枢の日本橋へと進出。折からの学校創成期と相まって金港堂は数年にして教科書出版では業界屈指の業績を収め、さらに文部卿森有礼の勧めで編輯所を開設し、同二十一(一八八八)年三宅米吉を主筆に雑誌「文」を創刊。次いで文芸誌「都の花」を創刊するなど、山田美妙や中根香亭を招聘し重用していた。
明治二十(一八八七)年、推されて東京書籍出版営業組合初代頭取および第九十五国立銀行頭取となり、二十五(一八九二)年二月の第二回衆議院議員総選挙では岐阜県から選出されて当選、以後は教育行政通の人として知られるようになるが、翌二十六(一八九三)年に「金港堂書「籍株式会社」と改組し、当時の日本における四大出版社の一に数えられるまでになり、同三十四(一九〇一)年の一年間に「教育界」、「文芸界」、「少年界」、「少女界」などの七大雑誌を刊行する社勢であった。
過る日清戦役で敗戦した清国は折しも近代化を急務とし、光緒二十八(一九〇二)年わが明治三十五年、はじめて全土に近代学校設立の勅旨「壬寅学制」を発布、ために原はそれらの学校で使用されはじめられるであろう膨大な量の教科書に着目し、上海最大の印刷工場と出版部門をもった商務印書館を射程距離にいれた。
商務印書館の前身はこれより以前咸豊十(一八六〇)年の末、寧波か上海に移転した美華書館(アメリカ長老[派]教会印刷所)で、米英ミッションの『聖書』をはじめとする宣教師間の会報雑誌および、キリスト教トラクトや、『英字指南』、『心算啓蒙』、『五大洲図説』、『地理略説』などの教会学校教科書、また『万国薬方』、『格物質学』、『代形合参』、『八線備旨』などの自然科学書などを発行していた。
その美華書館で働いていた長老教会信者の夏瑞芳・鮑咸恩・鮑咸昌・高鳳池ら四人の中国人植字工が独立し、あらたに共同出資して設立した小さな印刷所が、商業簿記などを印刷していたことが社名を「商務印書」と表記した由来で、光緒十八(一八九二)年二月に長老教会と自社の発展、および中国近代化を三大指針として創業された出版社なのである。
光緒同年の進士に挙げられた張菊生(一八六七~一九五九。名は元済、字は筱斎)は、同二十四(一八九八)年四月(旧暦六月)の戊戌変法後に北京の学堂を罷免され、上海の南洋公学(現上海交通大学)の訳書院院長に転じていたが、光緒二十七(一九〇二)年から世の趨勢に鑑み、商務印書館でも菊生が翻訳を担当することとなったものの、欧米の近代的著述を中国に紹介する重要性と刊行量の多さから、碩学蔡元培(一八六八~一九四〇)を新たに翻訳所所長に聘き、菊生自らは新教科書を編纂しつつ、その後の長きにわたって商務印書館の経営に担ったのである。
※蛇足だが奇しくも菊生も原と同様、解放後の一九四九年に第一期全国人民代表大会代表(日本の国会議員に相当)に選出されている。
一方日本では、明治五(一八七二)年の学制発布と同十二年の教育令が施行徹底されて以降の原と香亭を含む金港堂幹部は、いずれは小学校教科書出版の縮小化傾向を視野に、新たな経営方針を模索していたが、その一つとして隣の大清国という新市場に活路を見出そうというそんな矢先、ちょうど原の実妹(三女とも)のミサオが山本条太郎(一八六七~一九三六)に嫁いでいて、兄亮三郎のために口添えしたの
である。
山本条太郎は越前藩士の男に生まれ、後に満鉄総裁、衆議院議員に五度も当選し、また実業人茶道界の重鎮となった立志伝中の人で、当時は三井物産の上海支店にあり、彼の斡旋によって商務印書館と金港堂との日清合弁企業が実現するわけである。明治三十六(一九〇三)年十月のこと、満を持して原亮三郎は社員を引連れて渡清。合議のすえ、資本金二十万元を、日清双方十万元ずつ折半して対等に出資することで、ここに有限公司「商務印書館」が正式に発足することとなった。
さて、近代的教育書が国の基盤となる必要性を誰よりも身をもって経験してきた原である。その最重要性を知る原の資本金で商務印書館の経営は安定充実し、先輩格金港堂の出版編集とその近代的な印刷製本技術を学んだ印書館は、当然の結果として目覚ましい発展を遂げるが、合弁成果はそれだけにとどまらず、原が新たな試みとして小学校用の新定国語教科書を出版させたところ、その読みが的中し、需要が全国の六割以上にもなって、以後、中国全土の教科書販売は商務印書館の独占するところとなり、さらに「東方雑誌」や「教育雑誌」などの雑誌類、創作や翻訳ものなどの企画もつぎつぎと成功し、日ならずして商務印書館は東洋一の出版社へと成長していく。その良心的出版物に育まれた後の中国指導者の数は計り知れない。
「爆撃直後の商務印書館と東方図書館」
1932年1月29日『百科全書』
第一次上海事変において日本軍により爆撃され全壊した上海宝山路の商務印書館本社と同館付属の東方図書館(左側。蔵書30万冊)。
『中国音楽史』田邊尚雄著 陳泉中訳
1937年初版上海商務印書館刊
知る人ぞ知る。その後復興を遂げた該商務印書館が果たした学術的貢献度は中国近代史に特筆されるが、館主張菊生は創立時に原と金港堂からうけた恩誼を忘れず、爆撃した敵国日本人の著作ながらも、本連載91にすでに紹介したよう、田邊尚雄の『中国音楽史』や、伊東忠太の『中国建築史』の真価を心眼を曇らせずに評価した。
31
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第132話
高士中根香亭先生 廿三 原亮三郎(二)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
中根香亭の卓越した文才と博識を見抜き、これを新金港堂の編輯主幹に迎えた社主原亮三郎である。
また一面では、維新を体験した旧幕臣あがりの文士たちにありがちな、悲憤慷慨型とは一線を画す香亭の禅機に溢れ自若とした人柄を高く評価し、この人ならば癖の多い作家連を束ね、俯瞰かつ制御・育成できるであろうとの原の人選は見事的中し、事実、金港堂の教科書群は他に一頭抜きん出た需要で全国多くの各種学校に採用され、さらに文学面においても逍遥や四迷など新人中堅作家を育む温床ともなり、その結果、多くの新規読者を獲得し、金港堂は大会社へと拡大成長していくのである。
後年、香亭が公私の役すべてを退いて一介の処士となり、興津に隠棲してからも上下を超えた原との交誼は継続し、当時、下谷龍泉在の原を、興津で慰労せんとしたまさに明治四十三(一九一〇)年初夏のこと、あいにく八月上旬の東都一帯の長雨で、九日には大川(隅田川)が決壊し、とくに浅草をはじめとする下町が未曾有の大水害に襲われてしまった。
草啓、俄に冷気相催候へ共、不相変御起居御安静なりや奈何。
先般御近傍の洪水御案じ申上候処、幸御無難の由につき、大に休意仕候ひき。
併ながら被害の者、御救助等にて定めて御賢労の儀と奉察候。
此程新聞紙を閲し候へば、尊宅を以て貧民の施療所に充てられ候との件記しあり。いつもながら御高徳感服の至りに奉存候。
扨、今暑中清見寺を掛けて御来遊るべきの処、御都合により秋まで御延引相成候趣なりしが、追時候も体に可なる相成候へば、尊夫人御同伴にて御発相成候ては如何や。当地旅館にては東海ホテルと申すが他の旅亭よりも宜しく、且清見寺へは一丁もなき程にて、極々接近御都合も善からんと存ぜられ候。
御来過日限相分り、一寸御報下され候へば、老夫参り、座敷向取極め候は甚容易なること、御隔意なく御下命下されたく候。右貴意を得たく、一筆如此御座候。
公私御用向き尽くべからず候へ共、御憤発にて御出掛け相成候様、呉々も御勧め奉申上候。
尊夫人へは別段書状を呈せず候へども、此意伝へさせられ、必ず以て御同行奉待候。
他事一々申陳べず候。草々頓首。
秋分前一日 淑 拝
龍泉原先觉
侍 史 (句読筆者責)
文中洪水の条に、原が自邸を開放してまで恤教活動に励むさまに、
「いつもながら御高徳感服の至りに奉存候。」
と香亭は敬服しつつ、いったんは反古となった興津行を再度勧誘するのである。
ここで閑話休題、以下余談である。
原は立志の人にありがちな篤行の人なるがゆえの反面性も強く、いまでは廃れてしまった花柳界華やかなりしころを謳歌した人でもある。
何と、原の囲ったその人は誰あろう、安政七(一八六〇)年一月、遣米使節団の正使として咸林丸で海舟翁と渡米したことで知られる、麾下二千石の大身新見正興の愛娘であったが、御一新後に没落、新橋の蓬莱屋から愛子(一八六六ころ〜一八八八)の名で伯爵柳原前光に落籍(ひか)された薄倖の美人で、後の歌人白蓮女史の実母となり、若くして逝った奥津りょうその人である。
『園公秘話』表紙 安藤徳器編
昭和13(1938)年育成社刊
西園寺公望(1849~1940)は、公家出身の文人宰相で、明治3年からの10年間欧州に遊学し、パリのソルボンヌ大学の学士号を得て帰国した。
五年後の1884年、ジャポニズム潮流のなか「古今和歌集」の仏訳本『蜻蛉集』が、公望の逐次訳をもとに文豪テオフル・ゴーチェの娘ジュディットの手によってパリで出版された。
正史に記録されない公望の側面を、安藤徳器(1902~1953)が取材した『園公秘話』は、その『蜻蛉集』の書影を表紙に斜めに配した洒落た装幀となっている。
なお、奇しくも香亭の没した後、公望も興津に坐漁荘を営み、没するまでの大半をそこに過ごしたという。
30
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第133話
高士中根香亭先生 廿四 紅灯点々
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
一体に中根香亭の生前は、自らおよび係累についての多くは語らず、無論筆記せず、さらには他人の筆で逸話を公表されることも極端に好まず、ましてや日記なども存在しない。そのためにか、われら後世の研究者たちにとって、余人に比して没年のさして遠くないにもかかわらず、憶測から生じた記事が存在することがままあるのである。
そこで連載中拙稿では、香亭自身の筆を第一の根拠とし、ついで親しい友人知人のもの、それから、それらの人々の周辺搦手からなるべくその実体に迫るように心がけてはいるが、結局はこれとてまた他人の筆である。その取捨選択は必然的に読者諸賢の裁量に委せねばならぬため、この数回は、一応はある本稿主意からは大分と道が外れるようでも、幕末から昭和前半期ころまでの一般的な社会裏面史、ことに文士や数寄者の世界を知らんとすれば、多少とも紅灯の街を逍遥し、案内せねばなるまいとの言訳から、地の利?を活かし、いざヒヤカシに出陣しようテナ筋立とはいうが、なんのことはない、下駄を履けばすぐの町内のことである。
まずは江戸・東京(都市)の遊興地帯には大別して二種があって)り、その一が花街、二が遊(色)里で、これはいわずと知れた目的を第一としたものらしく、表面上にはすでに存在しないが、以降、時代の趨勢とともに徐々に花街と遊郭の区別が曖昧となりゆくことをも、軟筆の類いを読むためにはよくよく留意せねばならないことをつけたしおく。
さらば次掲一の花街とは、もそっと高見?の位置に置かれるらしく、音曲や舞踊などの粋藝を鑑賞しながらの酒席を仲立ちとした通人の遊び場で、三業地とも呼ばれる。次に芸者(妓)を主軸として語るとすれば、
一、「置屋」地域内の芸者をはじめ見習いの半玉らが籍を置き所属する単位で、通常は一軒家に雑居し、しかして芸者は置屋に寄宿するものと、一本立ちで通いのものがあるが、どちらも置屋に籍を置く。大抵はその中ですでに大年増となり、花を過ぎたものや、余裕のあるものがその女将となり、立場と職掌上から「お母さん」(義母)などとよばれる。
二、「待合」遊客はいったん待合に入ってから芸者を呼ぶが、待合の帳場は必ず検番を通さねばならない。この待合と次項料亭との違いは、プライベートに小さく利用されることが多く、席料をとり座敷を貸すことと、料理をしてはいけないため、仕出しを利用することである。
三、「料亭」特定地域内の座敷を有し、酒食を自前で提供する料理屋で、待合よりは規模が大きく、複数客や団体利用が多い。もちろん個客もあり、料亭に集う遊客連が馴染みの芸者を指名したり、初(うぶ)の場合は適当な芸者を検番を通して紹介してもらうのは二と同様である。
附、「検番」以上の三種(関西では二業のみ)の営業は、風俗営業法によって特定された地域でのみ許可され、各待合と料亭が共同して必ず検番(三業組合事務所)を別に設け、そこで芸者以外にも三業に携わるものの登録と管理をし、主に芸者の出入り召喚と玉代など、それらに関する諸経費を計算請求し代行する。
各待合、料亭などの経費は別勘定である。また、検番にある広間では外部からの専門家による音曲や舞踊の稽古、各種講習会、小振りな温習会などをも催すのである。
いま都内現役で至近な花柳界といえば新六花街をいい、芳(葭)町、新橋、赤坂、神楽坂、浅草、向島があり、辛うじて大塚などがある。湯島は同朋町と上野山下御数寄屋町などを合併して下谷と総称していたが、いまはその縁(よすが)もない。
ちなみに筆者が青少年期までを過ごした本郷西片では、家人から崖下の白山(丸山福山)や、反対側の根津や湯島に下りて遊んではならない、とキツくお達しがあったものである。そのころを回想してざっと数えただけでも、湯島、下谷、根津、白山、本郷、神田(講武所)、柳橋、根岸、ちょっと足を伸ばせば、駒込、深川、大森、品川、亀戸などなどが挙げられたし、山手線外郭に延長するに及べば、至る所といってよいほど花街は存在していたのである。
本道に戻り、野崎城雄編『東京粋書』では、芸妓の年令で廿八歳以上を「老妓」とし、それ以下を「名妓」、さらに半玉以下を「雛妓」と分かち、就中、愛子を絃妓写真二十人中の十一番、雛妓中の第一に置いている。
筆者がこれらのことを知ったのは、前号紹介するところの『園公秘話』によるもので、書中「玉八聞書」の東京粋書なる部分を、江戸雑学の延長として見るもまた一興であろう。
なお、西園寺公望は生涯正妻を持たぬ主義を貫いた人で、語り主の玉八は、公望に落籍されて内室におさまり、実質上の妻となった新橋芸者の玉八こと小林菊子(生没年不詳)のことで、公望との間に一女新子をもうけたが先逝してしまったのだが、本意はそこにあらず、玉八の妹分であった原の愛妾愛子について触れてあるからと知られたい。
―妹芸者愛子の事ども―
春本のお郁さんが妾を訪ねて参つたときもそうでしたね……
随分古いお話ですがオヤ東京粋書がよく御座いましたネ、
妾も一冊持つて居たのですが震災の時焼きましたよ……
仮名垣魯文のいたずらですが、まあ、よくこんな写真が残って居りました。
ドレドレ愛子のことですか?
あの妓は妾の妹分で、柳原前光さんの二号にもなりましたが、旦那取がいやなために森本座の緞帳役者と噂を立てられ、お暇を戴いて芳町から文芸者に出たのです。
……きらくの女将が侠気のある人で、娘を喰物にしてゐた義理のお袋と旦
那に相談つて手を切らせましたが、元を訊せば幕末のそれ勝海舟さんなどと亜米利加に使いした新見豊前守の娘ですが、御維新のごたくで没落して妾の家で預かった妓です。
横浜の原亮三郎さんの二号にもなりましたが惜しいことに早く亡くなりましたヨ。(『園公秘話』)
次なる例文は、その愛子についての『東京粋書』からの引用となる。
蓬莱屋愛子 高名なる玉八の義妹なり、年歯三五(筆註十五歳)バかりにして、嬌眸秀眉殊に愛すべきハ其名に背かずと雖ども、私(ひそか)に恐る漸く其姉姐の風に染み、相変わらず豪勢なる権力家とならんことを、愛子今雛妓の籍にありと雖ども、梅蕾早く香を放ち一番の春信動いて已まざるの評あり、而して余も左もあらんと想像するところなり、斯子現に橋南各小鬘の巨擘なりといふ
柳原伯爵の後、彼女は旦那取りが厭さで暇をとったが、ふたたび葭町から奥津りょうの名で芸者となり、原に落籍されたが、惜しくも早世する。なお、玉八が語った引用文中、「仮名垣魯文のいたずら云々」とあるのは彼女の記憶違いで、蟹廼屋、また愛蟹子、左文と別号した野崎城雄(一八五八~一九三五)のことである。
「町内二様」
一は、筆者寓居の一軒おいて突き当たりの、旧湯島同朋町花街名残の料亭あと。看板紋は「丸に重ね三角井桁」で、写真右下のポールに天二町(天神二丁目)と見える。
二は、右葉に「┬」と標識に見える小路が天神裏通りで、江戸期は本郷から広小路へ抜ける唯一の大動脈であった。その男坂(天神石坂)下から松坂屋方向への通り沿いに、この三月まで暖簾をまもっていたが、ついに閉店した三絃匠である。脇の戸袋には何気に三味線の撥がアシラってある。花柳界華やかなりしころはかなりの需要もあり、近所に同業者三店が競っていた。いかに花街が盛んであったことが解ろう。
「原亮三郎肖像」
自社金港堂の検印に利用された原の自画像であるが、画素が低いためあまりご参考とならなく、お詫び申し上げる。
21
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第134話
高士中根香亭先生 廿五 塩原懐古
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
つい昨日の五月五日上海から戻り、慌ててこの原稿をものしている。というのは、上海音楽学院の招聘により出ていたためである。
この音楽学院は中国でいっとう古く、一九二七年に創設された国立音楽院で、同二九年に国立音楽専科学校と改名され、解放後の一九五六年に現名の上海音楽学院となった伝統と権威ある音楽学校である。なお、東京藝術大学を「藝大」というと同様に、略して「上音」といわれる。
「上海音楽学院音楽学学術論壇第一五七期」なる一連の名目のもと、筆者による講義と音楽会などが三場もたれ、別に浦東にある法華学問寺での筆者演奏会などもあった。
上音では、
一、レクチャー「平安期『仁智要録』と『三五要録』、および江戸期『玉堂琴譜』との融合」
二、「日本伝統音楽と楽器のワークショップ」、
三、「坂田進一音楽会」
など、それぞれが一時間半の授業に相当したかなり充実したもので、音楽学系の主任教授である趙維平先生のもと、民楽系古琴科の戴暁蓮教授以下、音楽学と民楽系の専攻学生と院生、それに愚生相方で現役藝大生の浦田嬢(箏・三絃)が参加し、楽しくも有意義な講演と音楽会を開催できたが、さらに特筆すべきは、拙稿でもたびたび取り上げる浦上玉堂の催馬楽を、中国の学生たちに演奏させ唱わせたことで、おそらくこれは中国音楽界始まって以来の出来事と思われる。
今回、事前に送った玉堂琴譜(前集)からの催馬楽「桜人」と、今様「人者」の二曲のみであったが、上音の学生諸君十名に練習させておき、筆者の上海入りした当日の午後一杯をかけて磨きをかけた。
その成果として、筆者が直接中国の地と関わってより五十年になんなんとするその歳月中、こうしてようやく中国にお返しできたことになる。もともと催馬楽の出自が、中国唐代を中心とする雅楽曲中のメロディー、すなわち名曲のサビを利用してその旋律としたものに、平安庶民の俗謡を歌辞として充てたいわば日中合作の作品である。その悠揚たる歌声が上音にコダマしたのだから、筆者ならずも胸中感極まろうか。
さて、前述お二方の教授についてである。もともと楽器としては筆者と専門を一にする琴の名手である戴教授は、それこそ筆者の青くさいころからの知音であるし、その同期でもある趙教授も、これまた筆者専門の一部でもある音楽学で、古馴染みで楽しい左友?である。ありがたいことに、両先生ともに何かにかこつけて、すでにポンコツ・ガラクタ化したこの役立たずを、ときに駆り立て、奮い立たせて、最後のご奉公をさせるべくお膳立てしてくださるのである。
最近では昨年の十二月はじめ、上音での「当代古琴周」という大きな催しの前座で、筆者は「東皐琴譜の成立について」という題で講演をしたばかりで、ついでに、この五月末には、またこの戴教授と学生たちと共に、東皐心越禅師所縁の杭州で、浙江芸術院主催の「記念東皐心越逝世三二〇周年」というシンポジウムに招聘されている。
これも昨二〇一四年三月のことであった。東京の上野学園(私立音楽学校)における音楽学会出席のため、上音の趙教授が修士博士課程に在籍する三名の院生を引率来日された。
この音楽学会の一部には愚生も参加聴講したが、学会が終わるや否や、すぐさま各自のテーマに沿った資料蒐集に奔走し、筆者はその中のお一人で、寧波大学で教えながら上音の博士過程で研鑽される金女史と国会図書館に行き、その博士論文のテーマである尺八に関する資料の補足閲覧を手助けさせていただいたりした。
ちょうど帰国や買い物にも至便なように、湯島傍らの御徒町に宿をとり、それぞれが一日の勉めを了えて近くの居酒屋で慰労しあい、和やかに成果を語り合ったことである。
就中、一日だけは「全てを忘れ来日記念に観光したい、それも温泉で一泊したい」というので、塩原の安宿を予約し、上海の四方と都合五人の珍道中となったというわけである。
そもそも約一千年の歴史をもつという塩原温泉は、箒川沿いに現在十一の各温泉が点在するいわゆる温泉郷で、古くはさておき、近代の塩原温泉郷が人口に膾炙する契機が、奥蘭田(本連載十四、十五参照)がこの地に別荘を営み「塩渓紀勝」を明治二十三(一八九〇)年に著したことで、以来、多くの文人墨客らが蘭田の筆のあとを慕い、塩原各地の温泉や景勝を経廻りだしたからによる。
ただ、一般庶民を対象としてといいたいところだが、実際には『塩渓紀勝』は全文白文で著された読書人を相手に想定したもので、かなりの智識人でなければ読むことは不可能であったが、以後、国木田独歩の『欺かざるの記』、徳富蘆花の『自然と人生』中の塩原の件、なかでも、尾崎紅葉(一八六八~一九〇三)が塩原に投宿してその文案を練った新聞連載小説『金色夜叉』(一八九七~未完)など、塩原を題材としたものは枚挙するに暇ないほどである。近年の作では、さすがにいまは斜陽化した塩原を懐古した、森本哲郎(一九二五~二〇一四)の旅行記『旅の半空』(一九九七)が秀逸であるが、ここから一気に一世紀を遡り、香亭先生の筆より引用してみよう。
「塩渓日録」
八月十一日、是に先立ち金港堂公司、田辺小島二子著すところの学級教授法の稿本を寄送し、削正を乞う。前月来久しく雨ふらず、暑熱日に加わること甚だ涼爽の地を得、以て業を執らんと欲し、野州塩原温泉の今歳客の稀なるを聞き、游意始めて決す。是の日の平明、田端より汽車に搭じ、午下西那須に達す。
一亭にて餐し、塩原の近況を問うに対えて曰く、数日以来、避暑の客、帽傘相望するに閒地無し。公若し幽棲を愛せば、古巷福渡を過ぎること遠し。但し其の地更に半里程遠しと。乃ち車を買いて発す。
此の地本茫茫たる曠原。前の十五六年、県令三島通庸始めて之を開き、因て三島村と名づけ、今改めて狩野村と曰う。農家数十戸、路をみて相対し、路広二丈余、平直砥の如し。聞くならく新たに墾く原野、大いさ約方四里。隴畝の間に、時に水田を見、古来荒廃の境を、一旦化して田圃と成す。(続)
従前、下谷金杉村の迷花書室を終の窠と定めていた香亭も、日本鉄道鉄路開通の喧噪のため、やむなく本郷駒込曙町に移転はしてみたものの、その後、日に日に募る烟霞癖で全国行脚をするには、この近代重機の権化である機関車を利用せねばならず、渋々心中和解したことであろう。
なお、香亭の「塩渓日録」には日付がないが、明治十九(一八八六)年開業の日本鉄道那須駅が、同二十四(一八九一)年五月に西那須駅と改称された以降の年の、八月十一日から十六日にかけての作と解る。
塩原・妙雲寺門前
「上海音楽学院の一行」2014.3.9
右端が筆者知音の趙教授、残るが3名の院生。筆者はシャッター役のため写らない。後ろの扁額には塩渓禅林とあるが、甘露山妙雲寺という。
『塩渓紀勝』奥玄宝著 読仙書屋刊
明治23年(1890)年私家版
奥三郎兵衛(1836~1897)は、和泉国佐野の人で、蘭田、また玄宝と号し、渋沢栄一と肩を並べる明治期の日本を代表する実業人である。
大阪の琴家で儒医でもあった妻鹿友樵門に町田石谷と共に学び、後に東京に出て成功したため、友樵の男松井友石のよき保護者であった。煎茶人として、また近代塩原温泉郷を紹介した功労者として著名である。
巻頭におかれる「題辞」は、大蔵次官や貴族院議員を歴任した郷純造の揮毫になる。
23
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第135話
高士中根香亭先生 廿六 続塩渓日録
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
稿題からも知れるよう、拙文は自らの楽事に関連した他愛ない覚書で、さらにその重箱の隅をツッツクような澱筆である。読者諸賢、往々にし眉唾ものであることにご用心の上、各自取捨ご選択めされたい。
つい五月のハナに上海であったが、またぞろ同月末には、音楽学院の戴教授と学生たちと共に、東皐心越禅師所縁の杭州へ行き、「記念中日文化交流大師東臯心越逝世三二〇周年―2015中日古琴藝術交流系列活動―」なる一連の琴会とシンポジウムに招聘され、帰国時に長江遊覧船の転覆事故と前後したため、上海虹橋と浦東空港の間に積乱雲が鎮座ましまし、虹橋離陸寸前の滑走路脇で待機すること三時間、危うくいま一歩で空の上のシド?に行くところを助かった。
杭州においては琴会やシンポなどの他に、就中「東皐琴楽頒証伝承儀式」というものが設定してあり、怪訝に思った筆者が訊ねると、豈計らん。これは筆者を心越派正統の伝承者とし、中国の琴家に逆に伝えるという趣旨のもので、ビックリして、「自分は心越派の琴学を長年研究している一個の研究者でこそあれ、その正統を伝えるものでは決してない。そんないい加減なことはできないし、学者として百年後の笑い者にもなりたくない」と真顔で辞退すれば、「いや、伝承者と伝承人とは違うから」と宣うではないか。それで筆者が折れるはずもなく、そこでやむなく、主催者側は何も経緯を知らぬ某教授に白羽の矢を立て、何ということか、証書を頒証させてしまった。
ついては、日本でも伝統藝や小派もろもろの藝界では、同様に曖昧社撰で、いかにも安易適当に家元を名乗ったり、また乗っ取られたりとのニュースがあるが、せめても動物たる人間本来の生活上、必要な本能的生理的欲求のためにするならともかく、せっかく天から「ヒト」のみに与えられた高次元な藝術的嗜好の世界での、精神的弛緩と緩慢からくる名誉欲は、道を求めるものには決してあってはならないことであろう。
左は文頭数日前の出来事である。
音楽好きな読者諸賢にはご記憶の方もあろうか。筆者のまだ若いころ、小泉文夫(一九二七~一九八三)という音楽学者が、とくにFMラジオやレコードなどを媒体に平易に聴者に語りかけ活躍されていた。
もともと彼は哲学の範疇にある音楽美学を学んだ人で、一九七~八〇年代、おりからの民族音楽ブームの火付け役であるが、五十六歳というあまりに早い逝去を惜しむ声が各界から興り、その功績を遺すために彼の名を冠した「小泉文夫記念音楽賞」が設けられ、世界の音楽学者や演奏家、また団体などに贈られてはや二十六回、昨年度の受賞者が二名(一は団体)で、中国上海音楽学院の名誉教授陳応時(一九三三~)先生と、浜松の「楽器博物館」である。
そのどちらも存知よりのため、その東京における授賞式に筆者も参加させていただき、旧交(五月初旬にお会いしたばかりだが)を温めたわけだが、翌日には藝大における陳師の「琴律学」の講義があり、聞けば陳老師も冒頭の杭州における一連の琴会に出席なさるというではないか。
上音で練習の後、左友の知音趙教授らとシコタマ過ごした翌朝、上音から陳老師と筆者、戴教授と学生たちとでミニバスで杭州を目指し、楽しい?三日間もあっという間にすぎ上海に戻り、また業余にはイケナイ友人たちは一次会で帰し、あとは若き学生とのカラオケ三昧となった。
さあ、本道に戻らねばならぬ…。
奥蘭田が塩原の湯を選び、そこに別荘を建てたのは明治二十(一八八七)年、二年後の同二十三年に『塩渓紀勝』を公にして、遍く世に知らしめた。これが近代塩原温泉第一の功労者であることに過言はないが、塩原温泉郷はこれに先立つこと千年以前に開湯されているが、あまりにも秘境にあり、一般客が容易に訪れることはなかった。そこで栃木県令三島通庸(一八三五~一八八八)が那須野ヶ原を開墾し、明治十八(一八八四)年に塩原街道を開通させて別荘を構え、また翌十九年に日本鉄道が敷設されて那須駅からの道が通じ、沿道付近に各界人士の別荘やら温泉旅館が新築されるや、近郷の人々が身近に温泉を楽しめるようになったところ、さらに蘭田の『塩渓紀勝』が追い討ちをかけ、ようやく全国的に知られるようになったのだ。香亭の「塩渓日録」は、蘭田の「塩渓紀勝」ほどではないものの、隆盛途上にある塩原温泉郷のさらなるよい宣伝となったものであるが、惜しくもこの蘭田と香亭とは、直接の面識はなかったようである。
塩原温泉を世に出した奥蘭田の『塩渓紀勝』と所縁のある琴家、もしくはそれに準ずる者を数えると、
妻鹿友樵 ※当時已故
奥 蘭田 友樵懦門
松井友石 友樵男
今泉雄作 井上竹逸琴門
青山碧山 右同 天才髹漆家
町田石谷 友樵琴門
市河万庵(一八三八~一九〇七)
黎庶昌(一八三七~一八九七)
等があり、改めてその多いことに気付くが、考えてみればさもありなん。幕末明治を生きた当時の知識人たちの縦線と横の繋がりは、驚くほどに緻密かつ縦横?である。
『塩渓紀勝』巻末の「詩林」に「游塩原記」の文を寄せ、異彩を放った黎庶昌は、清末の外交官として世界的に活躍した人で、碩学としても著名である。字を蒓斎といい、貴州省遵義出身で鄭珍の門人である。
一八七○年吳江青浦両県知事赴任の後、曾国藩の幕僚となり、桐城派の文章を学び、曽們四弟子と称され、一八七六年に郭嵩燾がイギリス公使として赴任するや、参事官として随行した。ベルギー、スウェーデン、ポルトガル、オーストリアを歴訪し、それらの経験を『西洋雑志』として発表した。明治十四(一八八一)年には、何如璋後任の第二代駐日清国公使として日本に派遣され、二年後には帰国したが、同二十(一八八七)年に再度駐日公使として赴任し、その在任中に中国国内ではすでに散逸してしまった古籍の収集に尽力して『古逸叢書』を編纂し、日中の学会に寄与した一大功績がある。各界人士との人脈と幅広い交流、さらに分け隔てのない人柄から人望厚く、ために公使帰任時には朝野各界の日本人が大挙してこれを送ったという話が伝わり、帰国後は川東道員兼重慶海関督などの要職についた。
その著に、『拙尊園叢稿』六巻、『丁亥入都記程』二巻、『西洋雑志』八巻、『古逸叢書」二百巻などがあるが、我ら礼楽を学ぶものたちにとっては、何といっても『古逸叢書』中の「碣石調幽蘭」(本連載101~103参照)が断トツであり、他に和漢の学者たちに与えた庶昌の学(楽)恩は実に広く深い。
(続)
【上】「塩渓全図」市河万庵
『塩渓紀勝』4巻全編鑑賞のための図版である。
作者は幕臣市川万庵(1837~1907)幕末明治の書家市河米庵の男で名は三兼、通称を昇六、字は叔並である。江川太郎左衛門と高島秋帆に洋式砲術を学び、鉄砲方となり、父の衣鉢を受け篆隷に長じ、篆刻、点茶、弾琴を善くした。維新後は大蔵省に奉職し、新製日本紙幣の文字をものしている。
市題全圖 讀仙書屋
凡例
下塩原一百十七戸
中塩原三十三戸
上塩原三十九戸
湯本塩原八戸
【右上】塩渓第一勝「忍岡春意」
○題辞「花氣趁人」
三条実美(1837~1891)の筆による。『塩渓紀勝』は、塩原の景勝を十八撰びまずは奥玄宝の本文、それぞれの題辞、景色、それから詩文、また所縁のある素材を印材として2頼づつ押捺。しかる後、玄宝こと蘭田の本文が続くという構成である。
【右下】[塩渓十八景之一」第一
○「忍岡春意」
旧幕臣で南画家の川村雨谷(1838~1906)画。大審院判事でもあった。ことに塩原に到る前ぶりが、新たに敷設された上野駅東台山下からはじまるのは興味深く、図右側の階段あたりは今もその名残がある。
花氣趁人
明治己丑夏日梨堂居士題
25
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第136話
高士中根香亭先生 廿七 続々塩渓日録
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
香亭の紀行文「塩渓日録」と蘭田『塩渓紀勝』とはいわずもがな別ものであるが、ここにいとも珍かな『塩渓紀勝』の翻刻本がある。長年求めて得られずにいたところ、数年前東京郊外でのこと、演奏開演までの空き時間があった。そこで会場への道すがら古本屋を眼にしていたので、例のごとく漁書癖がフト頭を擡げ、「何か匂うぞ」との第六感を頼りに立寄ったなら、何と棚の隅っこに、サモ申しわけなさそうに人待ち顔にコレが並んでいるではないか。きっと書精が筆者を呼んだに違いない。
昭和三十一(一九五六)年の冬、当時塩原町の有力者で塩原テレビ共聴組合理事長であった坂内半之助翁の、奥蘭田を顕彰しようとのたっての依頼で、これも町内屈指の名刹甘露山妙雲寺の副住職であった河瀬憲宗(名は明一)師が、蘭田の難解な白文を塩原町民、ことに温泉業者のために苦心し、
「十八景」部分のみを訓読書き下したものである。しかし難字が多いために活字印刷は諦らめ、初印はガリ版手書きの謄写刷で百二十部きりの粗末なものを出したところ、あっという間に払底してしまった。そこで、すべて割愛してあった元版の挿絵を入れ、新たに和紙刷り・大和綴じの体裁とし、資を募り改めて活字版として昭和三十四(一九五九)年の秋に出版されたのが該書ということになる。
憲宗師は曰う。
…塩原来遊の知名、風流の人々に配布し、奥先生の顕彰と塩原の宣伝を兼ねんとし、塩原町当局、観光関係諸団体に呼びかけてその資をつくり、一方明賀屋主人君島五一君並びに三共印刷所主人の御理解ある御協力を得て、こに出版されることになり私も慶びにたえません。而し乍ら寔に杜撰そのもので、先生の名文を傷つけ他の笑いを買い恥をさらすのが積の山ですが、私共の故郷の発展に大きな努力をされ、是の如き比類のない紀文を、遺して下さった奥蘭田先生の遺徳が少しでも、全国のみなさんに理解して頂け、更に塩原の名所古蹟探訪の葉ともなれば幸せです。
いかにも純朴で郷土愛に満ちた地元の篤志家たちによって、蘭田の高雅な原本白文が平易に訓読され、それまでは原本はおろか、塩原名所の紹介文にすら触れることのできなかった地元庶民が、読みかつ理解した上で、以後噛み砕いた自らの言葉をもって、観光に訪れた全国の人々に紹介できるようになったのである。地下の蘭田翁の得意然とした破顔が一瞬間見えるようである。
しかしながら時すでに遅し。正直いって前記一九六〇年代にいったんは隆盛の浪に乗ったかに見えた後の七〇年代以降は、塩原ばかりか、全国の名だたる温泉郷や観光地に翳りが徐々に見えはじめ、ますます衰退の一歩を辿りつつ、老舗旅館も廃業に追い込まれて荒れ果てたまま、関係者たちは必死にその対策に追われているというのが現状である。
前々号でご紹介したわれら上音一行の塩渓探訪においても然り。百年の老舗も軒並み人手に渡るか大手に買収され、東京起点の格安なバスツアー化して、しかも無料のドサ回り劇団のアトラクション付きですらある。その反対に、行き来に見え隠れする小さな旅館群の多くはすでに廃業して久しいらしく、そのまま風化してしまったガラス越しに眼に映る景色は、割れたガラス戸と破れ障子ばかりの痛々しいものであった。
まことに世にある事物歳月上の盛衰は、天意と自然界現象、さらには人才との三者の接点まったき融合からなるもので、これを無視しての経世済民はあり得ず、成就しがたいことと歴史上知られるのである。
次いで河瀬憲宗訓訳『塩渓紀勝』本文の抜書きであるが、上野を発った車窓内外の景色の面白いこと、鉄路が拓けて一両年。今より百三十年ほど以前の蘭田の水茎による当時の風俗が、憲宗の書き下しにより眼前に活き活きと描写される。
明治二十一年戊子四月十七日陰噎、行装既に整う。杉凉荘これに従う。友人建部、小島二子及び男雲樵、送つて東台山下の停車場に到る。旅客麕集囁嚅耳に聒びすし。既にして車掌鈴を振って乗を警む。
十一時四十分汽篴瀏喨、宛転放輪轟々闐々、電掣風馳、林飛び屋奔る。十三分間にして王子邨に抵る。時に天放晴。老嗢幼を抜け、毫客妓を携え、策を杖く者、瓢を提ぐる者、檻を負う者、絃を抱く者、雅なる者俗なる者、大率一百余人一斉に下車す。是京城の人士なり。往いて晩桜を飛鳥、道灌の諸山ら賞するなり。王子を発す。
是より那須に至る輪を停むること十三次。小鉄橋を渡る、麦浪菜氈左右に繽翻す。
赤羽と曰う。軌道岐をなすもの品川諸駅に通ずるなり。又鉄橋を渡る。
長さ二千四百呎(フィート)、荒川是なり。
曰く浦和、埼玉県庁あり。聞けば此駅往日回禄の災に罹り三百余戸悉く烏有に帰すと。今尚焦壁断立、砕瓦山積す。眉を蹙めて過ぐ。
曰く大宮氷川神社あり。道岐れて右に転ず、
曰く蓮田、曰く久喜、左に上野(こうづけ)の諸山を望む。
曰く栗橋、駅を距ること九町許り、昔幕府関をこの駅に設くと譏察行旅に云う。右に伊坂村あり、村端に源義経の妾静女の墓あり。相い伝えいう、静女義経を追慕して奥に下る、途に義経既に没せしと聞き悲泣しこに終ると。村人これを憫んで墓を建て植うるに杉樹を以てす。いわゆる利根川(刀水)これなり。鉄橋を架す、長さ一千五百三十三呎なり。利根川図誌に按ずればこの水源を上野国利根郡文珠嶽に発し蜒蟺数十里、分れて両派となる。一は則ち南流し権現堂川となり、関宿より逆川を容し行徳に至つて江戸川となり堀江を経て海に入る。一は則ち赤堀川となり東関宿を経て絹川、蚕養川を併総常より銚子の口に注ぎ海に入ると云う。
車聡に倚れば、嘱目柳は翠桃は紅、鴎は泛び颿揚り、恰も綱川(こうせん)(筆註網川(もうせん))の活画図の如し。秋景想うべきなり。
北岸の小站は中田郷と曰う。寺あつて光了寺とう。静女の舞衣を蔵す。蓋し寿永二年神泉苑池の上りに雨を祈って静女舞を奏す。後鳥羽帝之を賜う。世に称して螭龍の舞衣と曰う。
源徳純の和歌に曰く。
耶末乃波尒 やまのは×や(○に)
多知麻不曾伝能 たちまうそての
之頭可仁曾 しずかにそ
多難備久区母毛 たなひくくもも
安女登也波奈留 あやめとやはなる
惜しくも綱川は王維所縁の網川が正しいが、かような正誤は一概に訳者の責を問うのみにあらず、小印刷所を介する筆耕・植字、ルビなど校正上の誤読は往々にしてある。また、文末の徳純を後鳥羽帝同時代の人と錯覚せしめるが、徳純(一七七七~一八二五)は新田岩松氏で、上野国新田郡下田嶋村(現群馬県太田市)を宰領地とし、徳川草創期に麾下となった武将で、中興の徳純は和歌および絵画を善くし、養蚕家のため鼠害を防がんと「猫絵」を描くなど領民から敬慕された地頭である。
『塩渓紀勝』訳本1巻
河瀬憲宗訓読訳
1959年秋塩原観光協会刊
奥蘭田先生著 塩溪紀勝
妙雲寺副住職 河瀬憲宗譯
【上】
○詩文「五言古詩」奥玄宝
車未離城去、早教遊意飛。
鶯随騒容杖、蝶坐美人衣。
花麗排紅霧、鐘清出翠微。
登程從此始、一注樂忘歸。 學王右軍書
【中】
○第1顆「花気趁人」
印材は凝灰石。書を善くした旧幕御先手与力で、天皇家、将軍家の印章をも刻した金子蓑香(1815~1892)の作である。
凝灰石 出于忍岡大猷院廟下。質硬而密鐫之難於攻玉
○第2顆「媚景」
古桜樹の印材。大蔵次官、貴族院議員を歴任した郷純造(1825~1910)の作で、同人の書は巻頭をも飾る。
古櫻 忍岡擂盆山產。老朽有蠹蝕。資脆鬆不易刻
【右】
○「塩渓紀勝」本文中途 奥玄宝
上野を発った汽車は王子飛鳥山を経て、荒川を渡り、浦和、大宮、蓮田、久喜、栗橋に至り、静御前の伝説におよぶ。ことに王子駅頭の件や諸駅近辺にまつわる話が面白く、極力ご紹介したい。
往賞晩於飛鳥道灌諸山也、發王子、自是至那須、停輪者者十三次、渡小鐵橋、麦浪菜氈、繽翻左右、曰赤羽軌道成岐者、通品川諸驛也、又渡鐵橋、長二千四百呎、荒川是也、浦和、有埼玉縣廰焉、聞此驛住日、罹回禄之災、三百餘戶悉歸烏有、今尚焦壁斷立、碎瓦山積、蹙眉而過、曰大宮、有水川神社、支道右轉、曰蓮田、曰久喜、左望上
31
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第137話
高士中根香亭先生 廿八 又続々塩渓日録
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
『塩渓紀勝』を読み下した河瀬憲宗は、「後記」で真摯に述懐する。
…冬の閑季を利用してその読み下しを始めてみました。処が案の定、次から次へと詠めない漢字ばかり、その上白文ときているので、途中幾度か擲げだそうかと思いましたが、思い直しては漢和辞典を二、三冊身の周りにおいて、それこそ文字通り「字引と首引き」でやつと読み終わりました。而し漢文につい旧制中学程度の素養しかなく、とても自信がもてませんので、又そのままにしておきました…、
こうした心境には、かく筆者などにも心当たりなきにしもあらず。ただ、多少地の利を得ていたおかげで、通常よりは漢字・漢文に対するアレルギー反応が少なかったように思える幸運があったからによる。
それは、筆者少時は本郷西片に在り、小学生のときから都電
に乗って聖堂の論語素読に出ていた。これがそもそもの湯島聖堂とのご縁の始まりで、その後に入った農学部前にある地元の第六中学では、奇しくも聖堂毎年の孔子祭において「孔子顕彰歌」を合唱する役割が伝統的にあり、筆者が普段通い慣れた聖堂での式典であるため、同級生たちに対して先輩顔をし、何かしら誇らしげに思えたものである。その後専門の学業を了えた後も、なお継続して、といってもその実ダラダラ(と惰性に近いものであったが、経書や各種古典、また華語講座などに通い続け、世間並の諸学校通算教育年限をはるかに上回る、実に六十年になんなんとするに、いまだ薫陶を受けお世話になり続けている。それこそ小学校から大学院までに相当する以上の学び舎、人生大学そのものが小生にとっての聖堂といってよく、元来、聖堂学問所の伝統は世間の学塾とは異なり、必須科目と単位取得も要らず、自ら求め好む講義に出ればそれでよい。そんな江戸期最高学府の「昌平学黌」(試験があるにはあった)の伝統は、いまも活きている(ただし現在は要学費)のだ。しかも、いまなお、聖堂講師の端くれとして聖堂に関わっているのであるからして…。
ただし、右をもって筆者が孔夫子の衣鉢を時代を超えて人に優れて継いでいる、などとは口が裂けても言えるはずもなく、また思いもよらぬことで、ただく通い続けたばかりが事実である。
ここで香亭の「塩渓日録」に戻る心算であったが、諸資料を目賭するうちにもメモせずにおき、すぐにでも忘却しようものを、敢えて想起するままに挙げてみようと思う。賢妻をしてシバシバ(「惚けがはじまったのでは?」、といわしむる今日このごろであるからである。
香亭の烟霞癖による産物『行脚非詩集』なる詩集は、すでにご紹介した通りの漢詩と和歌で構成された私家版小冊子で、明治三十八(一九〇五)年春の刊行であるから、すでに百十年も以前の稀覯本である。前半の漢詩部を「行脚非詩集」、後半の和歌部を「草鞋抄」という。就中、「行脚房痴淑」と遊心で名乗る香亭が、和歌部の初っ端に詠うに、
世をのがれて西の方に赴くとて
都出でさし上る月を見かへれば 心にかるうき雲もなし
道すがら故郷の友にいひ送りける
ゆく先は我だにそこと知られねど 月のすむ里花のよきやま
をりにふれては山深く入ることもあり
をりをりはみやまに入りて鶯の 夏をも志らぬ声をきくかな
この冒頭三首は、当時の香亭の胸中をよく映したものと知られ、また、
路を塩原の方に取りて紅葉を見る
春は花秋はもみぢにあくかれて 心の外のこひもするかな
と、「塩渓日録」では吐露せぬ、糟糠の妻と愛息とに先立たれた悲しさ、常には包む寂しさ、無常感を烟霞癖にこと寄せ、もの言わぬ山水を、亡妻に対する断ち切れぬ情愛に喩え、「恋」と読んだのである。しかして、花も実もある江戸っ子武士・中根香亭の温情ある性質と振る舞いは、真実、一木一草から駕篭かき、人力車夫にまで及んでやまないのである。また高士と謂われる大いなる所以であろう。
興津にて中村秋香大人が松の下庵がりおとなひて宿に帰りけるにあくるあした大人より きのふ帰り給ひし後に来し人の傘もたでぬれたりといふに心づきてと見ればけに静にふり出たり
かへるさの道にや君はぬれにけん雨と志りせば傘かさましをと思へど何のかひかはあらむといひつかはしける
世のうさにぬれまさりにし我が袖を 傘かればとて何にかはせむ
磯におりたちてふどしを洗ふ
志めふりしたふさき洗ふ清見湾 あなこゝろよき旅の空かれ
心友である中村秋香が東海道興津に新たに構えた「松の下庵」へ、主人に誘われ随伴していた香亭であったが、日に日に勝る烟霞癖からも、興津を訪れる機会がまし、旅行の途次に直接中村から庵を借り、逗留することもたびたびあったのである。
この中村もその興津に在るうち、静岡にいた妻に先立たれ、しかも香亭よりも先逝する秋香の晩年は、香亭との心をなによりの支えと拠り所にしていたのだが、豈はからん、香亭の身心もそぼ降る雨以上に、また濡れていたのである。
次にポール・マリー・ヴェルネール(一八四四~一八九六)の人口に膾炙した秋詩の名訳を二例掲げる。
「落葉」上田敏訳
秋の日のギオロンの
ためいきのひたぶるに
身にしみてうら悲し
…
鐘のおとに胸ふたぎ
色かくて涙ぐむ
過ぎし日のおもひでや
…
げにわれはうらぶれて
ここかしこさだめなく
とび散らふ落葉かな
「秋の歌」堀口大學訳
秋風のヴィオロンの
節(ふし)ながき啜泣(すすりなき)もの憂き哀しみに
わが魂を痛ましむ
…
時の鐘鳴りも出づれば
せつなくも胸せまり
思ひ出づる
来し方に涙は湧く
…
落葉ならね身をば遣(や)る
われもかなたこなた
吹きまくれ逆風(さかかぜ)よ
いかがであろうか、ちょっとオセンチとなったが、「もののふ」たるもの、必ずや「ものの哀れ」を知るのである。
次号連載は、図版説明の補遺と、香亭の心友中村秋香との交
間情をもそっと垣みたい。
「香亭洗褌図」片山春帆筆
片山春帆は、本連載第75~76で少しご紹介したことのある、旧幕御鷹匠同心の片山賢の曾孫にあたる明治~大正期の画伯で、該香亭の挿絵図は博文館から依頼されたものである。詳しくは次号に述べよう
25
「小泉文夫賞授賞式における陳応時老師」
2015年5月21日 東京会館にて
(前々号補遺)中央が陳老で、向かって右が愛息ご夫妻、老師の左が筆者と、陳老かつての教え子山寺夫人。この山寺姉は筆者知音の龔一先生の紹介で、まだ本郷小研究所のころの愚門下にしばらくあり、その後大著『碣石調幽蘭の研究』をものし、田邊尚雄賞を受賞された若き学徒である。また師愛息ご夫妻は、湯島男坂下に移転した弊所からなんと徒歩数分の指呼の間?に現在おられる。実に世界は狭いものである。
【坂田進一講演音楽会〈中国文人音楽の世界〉開催のお知らせ】
~上海音楽学院戴暁蓮教授をお迎えして~
1《大阪》12月6日(日)14:00開演(開場15分前)〈オリエント楽友ホール〉阪急中津駅徒歩2分¥ご予約:¥3,500当日:4,000◇お申込み:06-6373-9838こんりん事務所まで
2《滋賀》12月8日(火)19:00開演(開場30分前)〈木之本交遊館〉JR木之本駅下車徒歩10分¥全席無料◆お申込み:0749-82-2167丸三ハシモト株式会社まで
3《東京》12月11日(金)14:00開演(開場15分前)〈湯島聖堂講堂〉JRお茶の水駅下車徒歩3分¥ご予約:¥3,500 当日残席あれば:¥4,000
◆お申込み:メールのみ受付 坂田古典音楽研究所まで
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第138話
高士中根香亭先生 廿九 片山春帆と曾祖父賢
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
 東海道興津の宿は、中根香亭辱知の歌人中邨秋香とともにしばしば訪れた景勝の地で、彼の地に「松の下庵」を構えた秋香を先に送り、さらには香亭自身の終の住処となった因縁の場所でもある。
東海道興津の宿は、中根香亭辱知の歌人中邨秋香とともにしばしば訪れた景勝の地で、彼の地に「松の下庵」を構えた秋香を先に送り、さらには香亭自身の終の住処となった因縁の場所でもある。いかに人生そのものといえる旅程の途次とはいえ、かかる未来の因果を知る由もない香亭である。同宿臨済の古刹清見寺(正しくは巨鼇山清見興国禅寺)の門前に広がる清渚「清見潟(きよみがた)」にて、禿頭姿の香亭が無心にして褌を洗って(前号挿図参照)いる。しかしてこれは大手書肆博文館の委嘱により、片山春帆(一八八〇~一九五五)が想像して描いたものと思しい。というのは、すでに老齢の香亭が禿頭でないことは図版により明々白々であるからして。
しかしながら、ここに拙筆の端にかかったを機に、この春帆の出自である片山家のことを多少なりともご紹介せずばなるまいか。
かくなる筆先転換の伏線は、奇しくもこの春帆こそが筆者の長年追い求めた片山賢自筆の文書を取捨整理し、公刊した『御鷹匠同心片山家日常記抄』を通し、時空を超えて筆者にまで伝染させたそもそもの癖原にほかならない。
数年前、筆者が沖縄首里城における「御座楽(うざがく)復元委員会」本土側ただ一人の委員として在籍中、春帆の遺作「片山春帆民俗芸能記録画帳」が、おきなわ国立劇場から東京の国立劇場に寄託されたことを薄々知りながら、惜しくも僅差の一年前にこれを辞任したことで、より深く追求せなかった筆者怠慢の結果、今一歩のところで原資料にまでたどりつけず、切歯扼腕しつつも「縁中にありて縁なく」、また万策尽きていた。
そのうち、ある契機から幸いにも片山家現ご当主を知るに至り、この停滞感を一気に払拭し、かつて春帆翁が苦心して整理した文書類の調査が改めて叶うようになったのである。
春帆とは無論画号。春雄が本名で、片山家第十一代、丹青を生業とし、明治から大正、また昭和初期にかけて挿絵画家としても活躍した。
その父が第十代の文雄(幼名文太郎)で、春帆の祖父が旧幕最後の雑司ヶ谷組御鷹匠同心見習としてた育っ第九代片山椿助(一八二三~一八九三)名を大路といい、後の組替えで御勘定所書物御用出役、御軍艦取締役組頭、御勘定組頭となる代々三十俵二人扶持の、いわば軽輩家格片山家歴代における出世頭である。
そのまた父が、幕末筆記癖の人として知られる第八代の御鷹匠同心片山賢(一七九八~一八五三)で、幼名を徳蔵、通称は雄八郎、名は賢、字を孟賢、画号を百薬、また雲嶂、和歌では聴雪、俳号を申之。琴号の凹泉をそのまま晩年に使用し、また、中年以降は六代目養祖父の名を継ぎ勇八と改名した。これこそかくいう筆者の重要な研究対象の一人である。
かくも多藝であった賢は、また心越派琴学二流の初学を中年にして学んだが、その一は、浅草真龍寺の蘭室の流れを汲む陸奥守山藩藩医の矢部昌葊(一七七二~?)に手ほどきされ、いま一は、浪速から江戸に下り、本郷・湯島で琴学を中心に誰を下した琴師鳥海雪堂最晩年の伝で、とくに琴学教授の際に師雪堂の語る「琴学上の事柄」と、日常折々の師雪堂の姿を筆記した『鳥海翁琴話』を、筆者青年のころに耽読したことで、幕末期心越派琴学の大要を知ることができたし、そうした琴界内部の生き証人として重要な人物である上に、さらに大岡雲峰と岡田閑林の門で画業を研鑽し、文字通り「琴・書画」を地で行った人なのである。
片山家の初代片山惣兵衛が慶長元和のころに尾張より出でて、徳川家康とともに江戸に移り、以後代々御鷹匠同心の家格となったわけだが、微禄ながら、もともと片山家には代々の歴代当主が、そのころの武家大半がそうであった以上に、家にかかわる文書を大切に後世に遺し伝えるという気風と家訓があり、片山家一族はおおむねその家風に忠実であったようであるが、その詳細は連載中の別稿に述べることとしよう。
拙稿眼目中根香亭は、下谷長者町に曽根得斎の子として生まれ、少時に同町内の中根氏の養子となり、その後養家が隣町の下谷仲徒士町四丁目三十二番地に移居。そこで成人、東奔西走の後、自己念願の癖である小園「迷花書室」をはじめて実現させえたのもその小宅であり、はじめ武士中根から文士香亭として立つこととなった基点も此処である。
その記念すべき処女作が、『慶安小史』という本紙二十丁にも満たぬ小冊子で、香亭自ら序に曰う。
序 (句読改行及び※筆者註)
今を距つ九年前、余は駿河に遷りて幽居し事も無し。
乃ち古今の書籍を輯録し、以て駿河国誌を修せんと欲し、先に其の国人山田長政、由井正雪、堀部金丸等の伝を作す。(※赤穂浪士堀部某)既にして俗累索纏、東西転移、竟に之を果せざるなり。
去歳の冬、余は病に臥し終日間暇。因て旧稿を出し之を閲せば、雨痕漫濾、鼠嚼縦横、残壞居半。就中由井正雪の伝を得るに稍完たり。
是に於いて尋ねて思推し、読み写し一巻となし、且つ之の題名を改めて曰く、慶応小史と。
抑、余の是の書を為すは、其の意駿河国誌を修するに在るのみ、而して今独り之を伝うるは、その素志に非ざるなり。 (※慶安小史のみ)
然と雖も天下の事は、其の期する所を成さざれば、其の期せざる所を成すこと固より多きこと、豈独り是の書のみならん哉。鳴呼、豈独り是の書のみならん哉。
明治九年一月 中根淑撰并書
九年前といえば太陰暦で一八六八年慶応四年(九月八日明治改元)で、香亭
いまだ沼津兵学校に籍がある。
奈良朝編纂の『駿河国風土記』はおき、駿府加番阿部正信の『駿国雑誌』は天保十四(一八四三)年の編纂で、これが香亭のいう『駿河国誌』そのものか、はたまた修訂せんとした『駿河国誌』原本を指すものかは、原稿が失われた現在では判然とせず。また、『明治新撰駿河国誌』公刊は明治三十(一八九七)年のことで、他に昭和の『駿河国新風土記』があるが、この両書は埒外であろう。
河竹黙阿弥戯作の「慶安太平記」が初演されたのは明治三(一八七〇)年三月で、江戸三座の一、森田座でのこと。香亭の『駿河国誌』稿は明治改元の年にはすでに成っていたが、由井正雪事件が題材の『慶安小史』残稿を明治八年に刪定し自家出版版権免許取得したは九年の二月末つ方である。これに先立つ一月にはすでに上木し、香亭が序をものしたのも同一月のことであるから、かなり倉卒の間に公刊したものとみえる。
もっとも序にもあるよう、元原稿の大半を校訂するのみで可としたのであろうが、これが香亭の記念すべき処女出版作となり、以降、香亭は武士の魂である双刀を捨て、隻手にサーベル、隻手にはペンでの生業とはあいなるのである。
 「中根香亭小照」『香亭遺文』より
「中根香亭小照」『香亭遺文』より香亭肖像のうち最も世に知られたものである。常には写真嫌いな香亭だが、該葉を身内にのみ贈呈した。
いかにも謹厳実直そうな中にも肩を張らず、しかも悟道の境地に達したかに見える老先生の清躯かつ端正な風貌の奥に、秘めたる強い意志が認めらるる秀逸なポートレートである。
(右)『片山春帆スナップ』
片山家蔵より
向って右が前号稿末においた挿図の作者片山春帆で、尻端折りに脚絆と地下足袋、懐には丹青と硯、右手に画筆とイーゼル、左手には中折れ帽と画帖を抱えたその出立ちは、いかにも往時の曾祖父御鷹匠同心片山賢の「野先」姿を彷彿とさせる。なお、前号キャプションで春帆を片山賢の孫としたは、曾孫の誤りである。(野先とは各地御鷹場などへの巡視行)
左は、春帆に『御鷹匠同心片山家日常襍記抄』の公刊を勧めた民俗学者の桜田勝徳(1903~1979)である。
(下)『慶安小史』見開きおよび「序」
香亭の処女出版。「中根氏蔵」とあり、私家版と知られる。
21
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第139話
高士中根香亭先生 卅 香亭と竹逸、そして賢
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
実は、本連載中の中根香亭と東皐心越禅師は無関係ではない。というて互いに面識のあろうはずもなく、香亭は越師のことを能く学習し認識するが、無論、越師は香亭のことを知る由もなく、沖天の空にある月を通し、古人今人が時空を超えて憶い念いあう、淡い間柄という意味においてである。
以下、古来愛誦いまもってやまぬ、李白の「把酒問月」である。
把酒問月 酒を把りて月に問う
青天有月來幾時
青天月有りてより来(このかた)幾時ぞ
我今停盃一問之
我いま盃を停めて一たび之に問う
人攀明月不可得
人は明月を攀ずること得べからず
月行卻與人相隨
月行って人と相随う
皎如飛鏡臨丹闕
皎として飛鏡の丹闕に臨むが如く
綠煙滅盡淸輝發
緑煙滅し尽きて清輝を発す
但見宵從海上來
ただ見る宵に海上より来るを
寧知曉向雲閒沒
寧ぞ知らん暁に雲閒に向かいて没するを
白兔搗藥秋復春
白兔薬を搗きて秋復た春
姮娥孤栖與誰鄰
姮娥孤栖して誰と鄰する
今人不見古時月
今人は見ず古時の月
今月曾經照古人
今月は曾経て古人を照らせり
古人今人若流水
古今人流水の若し
共看明月皆如此
共に明月を看る皆此の如し
惟願當歌對酒時
惟願う歌に当たり酒に対するの時
月光長照金樽裏
月光の長く金樽の裏を照らさんことを
李白の絶唱である。
今を生きる人間には、往時の月を眺めることはできぬが、今現に見える月は、かつては古人を照らしていたのだ。また、古人も今人も逝く水のように移ろいゆくが、共に明月を見れば、等しくかくも思いやるのだ。
香亭は、下谷文人仲間の先達で心越派琴流を修めた奇人井上竹逸(本連載30~4参照)の生前、竹逸が折々に書写していた琴事「備忘録」である『竹逸琴話』を借覧し、写し取って編纂加筆した新聞記事を、明治中期の漢詩文の愛読者や新聞を定期購読するようになった新知識層を対象に啓蒙せんとした。
しかして、何とこの竹逸と前号の片山賢(琴号凹泉)とは、鳥海雪堂琴門でともに研鑽しあった良友であったのだから、因果はめぐる。
図例右丁二行目から、(句読筆者責)
一 蘿道翁ことし-庚戌-二十五回忌にあたられたり、大阪にては追悼に二十五回忌を弔ふ、江戸にてハせぬ事なれとも、いせにもするよしなれハ、十二月廿三日が命日なれハ、餅を備へて井上竹逸と足下と二人を招きて像前に琴をひきて、さてぜんざい餅を餐せんとおもふ也。
廿三日に必来れよと約せけれバ、本日に行て、琴を弾て餅をくひぬ、ただし翁常に壁間に心越師と蘿道翁との肖像を、図画の中に合装せしをかけおかるる也。さて此日竹逸は来らず、翁頃日、風邪にて閑居せられ案内せられざりし故也。
嘉永三(一八五〇)年十月二十三日は、伊勢津の豪商で雪堂の琴師であった蘿道二十五回忌にあたり、その門下所縁の門人が集まり、大阪、伊勢でもするので、この江戸でもお偲びしようとて、雪堂千駄木の仮寓において心越師と蘿道の肖像前で、ぜんざい餅を共に食し、越師と蘿道の命日を記念せんものと、せっかく雪堂が凹泉と竹逸を招いたが、ちょうど雪堂が風邪のため案内できず、竹逸は参会できずじまいであったと。
そんな経歴の竹逸が没したため、日本独自に存続し、明治の御一新を辛くも経て、いままさに終焉期に入らんとするその琴流を惜しみ、香亭はなんとかしてこの貴重な琴流の末期を後世に知らしめんとの思いから、出版界の伝をえて「横浜毎日新聞」に「七絃琴の伝来」という記事を連載したのである。時に明治二十三(一八九〇)年六月のことである。
その端書きに云う。
七絃琴の吾が国に行れたるは帰化の僧東皐禅師が伝へたるをもて初めとす、それより明和安永の頃に至り、江戸の雅人頻りに之を学び、寛政文化の間盛んに行はれ、天保に至りやうやう衰へ、近年に及びては井上竹逸翁外一二の人の弾ずるのみなりしが、翁物故してより後は其道殆ど絶えたりといふべし、
先年依田学海君京畿に遊ばれし時浪華に於て七絃琴を聞かれたるよし語られたれば、彼の地には尚之を伝ふものありと見ゆ、
さて竹逸翁未だ世にありし時、凡そ此道に関かること記したる書あれば何くれとなく抄録せられたるを予幸に借り受けて写し置きたり、(句読は原文のママ)
其目録の大略を挙ぐれば
心越禅師肖像、
琴家略伝、
琴学伝授略系、
琴譜の話、
東皐琴譜の話、
閑叟雑話、
弹琴指法、
製琴法、
定徽捷法、
配徽捷径術、
琴絃製法、
絨扣製、
琴社諸友記録 等なり、
是は固より翁が見るに随ひて記し置きたるものなれば、順序もなく入り乱れ、且つは重複したる事も少なしとせず
故に今其書に就きて前後の順序を正し、取るべきは取り捨つべきは捨てさて漢文の中改め難きものは其原文を存じ、然らざるは邦文に書き替へ、努めて蕪雑を除き簡約に就かんことを期す、
然れどもかく許多の材料を集め置きためは偏に竹逸翁の功なり(、)
予は唯此書の滅せんことを恐れて之世に伝えるに過ぎず、
やはり筋金入りの江戸っ子武士とはかくも違うものかな。本連載中、竹逸とその琴弟子となった今泉雄作について少し触れたが、香亭にしろ、竹逸、雄作にしても実に義理堅く、その上情にはあつく人情脆い。
同時代、下級武士の家や町人長屋には鍵など要らぬわけで、たまさか財をなしたり小銭を貯めたりすれば、それこそ「宵越しの金は明日の心配の種」ってなわけである。
重複しようが書かずにはおれぬ。竹逸は例の浅野の殿様を殿中「松の廊下」で抱き止めた梶川与惣兵衛家幕末期の陪臣で、戟剣をも能くし、また渡辺崋山門下四天王の一で、文人画とくに細密画を善くした画人でもある。しかし主家の扶持に甘んじ、また矜持を高く保ち、職業画家とはならずにあったため売り絵は描かず、ほとんどその遺作は巷間にない。
御一新の後、主家は徳川宗主とともに駿府静岡に移るが、その旧主が一たん非常な困窮に陥るや、秘蔵するところの華製の名琴を惜しげもなく鬻ぎ、なにがしかのまとまった金子に換えて駿府に馳せ参じ、旧主に呈したのである。明治初期の人心いまだ殺伐と余裕のない時流の美談として、これを伝聞した世人、ことに江戸っ子連はこぞってその節義と意気を誉め称え、ヤンヤとばかり喝采して喜んだのである。
『鳥海翁琴話』片山凹泉筆
片山凹泉とは賢の琴号である。
嘉永年間賢の最晩年、遅きに過ぎたきらいがあるものの、鳥海雪堂の下、琴と書に耽溺できたのはいかにも幸いで、さらに井上竹逸が良友となった。
「鳥海翁琴話」坂田進一抄写書下し
恥ずかしながら、筆者の29歳そこそこのころのノートである。いまだ結婚する以前のことで、若くもあり時間もあり、図書館に通い該原本を手写したことも懐かしい。昭和53(1978)年10月に写し了えたとある。
その後これにより、日本独自に発展した幕末期心越流琴派を俯瞰する余裕が多少できたのである。
【坂田進一講演音楽会<中国文人音楽の世界>開催のお知らせ】~名手・上海音楽学院戴暁蓮教授をお迎えして~
12月11日(金)14:00開演(13:45開場)〈湯島聖堂講堂〉JRお茶の水駅下車徒歩3分¥当日:¥3,500
◇お申込み・メールのみ受付(☎不可)11月30日(月)締切 坂田古典音楽研究所まで
20
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第140話
高士中根香亭先生 卅一 興津寓居と小雅宛附けたり 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
平生、諸事倹約をモットーとした香亭であったが、居所だけはかなり贅沢にし、秋香の周旋を経て菓子舗伏見直太郎の後園の海に面した二階建て一戸(写真)を借りきり、表面上は悠々自適の生活に入るのである。
忘年の友木村架空に宛てていう。
老夫先般より此地に尻を据え、東京の方を返ってお旅所と致し候、是は少し事情ありての都合に御座候、今居る家は旧冬中村氏に頼み、土地の人に定め置いてもらひたるものにて、から普請にはあれど眺矚は絶景也、離れ家なれども、あひる三羽と四人暮しにて淋しくはないと、去暮乙骨子(太郎乙)に申送たるを以て、そんな事をいひたる詩を寄せ来りたるが、其後其中の一羽行方不明となりたり、是は家族中の不幸とでもいふべきか、
…略…
兎角当所に御遷座後死葬の事多
きはいまいまし、
興津は暖地には相違なけれど、居て見ればやはり風涼し、東京の春寒察するに余りあり。
折角御自嗇奉祈候、余不尽、…
右は明治四十三(一九一〇)年三月四日付のもの、同月二十二日に香亭が妹の頌子に宛てた書では、近親に対してか、その心情を吐露する。
なお、例のごとく改行句読と(細字分)を加えたは筆者の責である。
当興津は平年に比すれば寒気強き方に有之候ひき、是全く今春は西風吹きすさみたる故なるべし、但し一体の上にては暖地に相違なきことは、昨冬より今日まで一度も雪降りたることなきにて相分かり申し候、
御宅(原田氏)御前様にも琴柱さんにも何れも御機嫌よく、何より結構に存じ候、
老夫も追々年取り、ぶしやうになり候へども、身体は先丈夫の方に有之、此丈夫なる内にうまく目を眠りたく存ずれども、自然の定数あるものと見え、注文通りにもなり申さず、唯々楽しんで天命に任せ居り候、
是までの同居西村方(駒込曙町迷花書室)にては、仰せの如くとめ女縁付き、あと手少なくなり、病人は相替らず立ち居出来ず、別して困り候ことに御座候、夫故老夫も当興津を住所として、東京の方は出見世とすることに致し候、
西村にてはかくては道理上すまぬゆゑ、是非とも居てくれと申し候へども、病人の難儀を見て居るもいやなり、且は人手少き中に世話になり居るも気のどくなれば、こなたへ住ふことに致したるなり、夫には友人中村秋香といふ人、当所に別荘といふ程にはあらねど、小さき家(松の下庵)を所有致し居候、毎年冬より春一ぱい位は来て居候ゆゑ、老夫も年に二三ヶ月は共に来り、話し相手ありて双方都合も宜しく、依て旧冬中村氏此地にて家(伏見屋家作)を見付け置きくれたるを以て、それに入りたる次第なり、
然るに中村事、東京より持ちこしの黄疸病よからず、遂に一月廿八日死去したり、
その二三日前、両人の子息も来りたれど、老夫は臨終まで世話致し、二月三日東京にて葬式に付き、前日出京し、且同十三日は養父の五十回忌になり候まま、十日計り東京に居続け居たり、
其間に友人乙骨氏の妻病死するなど、唯ごたごた日を過し、十四日此地に舞ひ戻り候、
旧冬中井敬所(篆刻家にて同斎先生の門人なり)死去してより矢吹秀一(沼津学校出にて陸軍中将男爵) 依田百川及び谷干城の夫人(谷は臺の縁付たる島村の続き合なるを以て此婆さまに二三度面会を致したる也、其御縁を以て墓誌を書かせられたり)等、あの世に旅立ちするもの多く、度々悔みの状を認め申候、
其中にはこちらがくやみの仲間入りにならんかと存じ候へども、前に申す通り天とうまかせ、何事もはかり難く候、
中村は已になくなり候へども、当地は人気のよき処ゆゑ、ともかくも尻をすゑ候つもりにて、煮焼の稽古致し、此程は余程上手になり候、併手の掛りて面倒なるには面口いたし候、…
※蓋とは香亭亡妻の実弟西村正立長女の島村臺子
同妹頌子宛の別便では、
私住所は三四年前の新築ゆゑ、きたなくは御座なく候へども、安ぶしん故土台なく、先月十九日並に昨夜の大風雨等には、折二階ぐらつき、いやな心地致し、住み替へんかとも思ひ候が、引移る上は、いつそ興津をやめて外へ参つても宜しき身の上ゆゑ、そのへんいろいろと考へ申候、…
また翌十四三年十一月の頌子宛の書にはかくもいう。
…されど当地(興津)に少しなりと居りつきたるゆゑ、老夫今更急に右様(駒込曙町に戻る)致さうとも存申さず候、不自由は甚不自由なれど、田舎はゐなかなりに住みよき処もあり、何れへ行きたりとて、極楽浄土のあるべきはず無ければ、先づこの侭に居るつもりに御座候、
さて、前号では「横浜毎日新聞」記事の切り抜きがどこぞに紛れ、やむなく香亭没後に編纂された『香亭遺文』所収の「七絃琴の伝来」冒頭部分、本文引用の箇所からご紹介したようなわけだが、拙稿中の香亭連載はすでに三年越しの三十回を超えたことで、読者利便のため「略年譜」を加えてはとの編輯子の提言により、これを次号に足すこととし、その前段の補足として香亭自身が小雅に与えたとても重要な「附書」をご紹介しよう。
以下、香亭の没する二年前のものを二分割したものである。
…御約束の老夫小事歴中、誤れる件々別紙に書取、汚電覧候、御閑暇之節、御笑読奉希候、艸々
三月朔(明治四十四年)痴 淑
杵邨深契 黄龍下
「別紙」
余は先年来、意外にも屢雑誌記者(岸上質軒ら)の玩物となりて、其事歴紙上に晒すこととなれり、中には誤謬の点も少からざれども、正誤を乞ふべき筋にもあらねば、唯其侭に打過ぎたり、
尊君(小雅)は能く僕の性行を御承知なれど、常に面晤もし難ければ、其真偽も詳にせられざる所あらんと思ひ、茲に専ら記者の誤れる件を書し、併せて聊他事に及ぶ、
御一覧の上は、必ず火に投ぜらるべし、
春風道人(塚越停春)の文は、吾旅行中にて終に之を見ず、先日残花(戸川残花)の筆したる書も未だ見ず、独り明治畸人伝は其本を送り来りし故、之を見るを得たり、依て専ら其書に就きて誤りを弁ず、
僕、小名を造酒といへり、二男なるを以て、宅にて造酒二郎と呼びたることもありしかど、実は二字名なり、崎人伝に幹の字に作りたるは誤れり、漢学は、同書に僕誰やら(清水純斎)の門人の如く記したるは違へり、僕、十七八の頃、羽倉簡堂翁の熟に半年ばかり通ひたれど、其頃翁は聾病みて応対も出来ざる程なりき、
(続)
「中根香亭興津仮寓」『香亭蔵草』より
心友中村秋香と岳陽興津をしばしば訪れていた香亭は、秋香がそこに「松の下庵」を構えたことに触発され、明治42(1909)年の冬、ついに自らも興津に隠棲することを決意し、以来、秋香との交情を楽しみとしたが、時はすでに遅し、翌43年の1月29日、興津海辺の松林において秋香を荼毘に付
すことになるのである。
「題東皐心越禅師肖像」『香亭蔵草』より
拙稿連載中、このところ井上竹逸の薫陶よろしく、香亭が先人東皐心越禅師の事蹟を慕い、新聞に連載した前後を追うが、かく竹逸の臨模した心越像を香亭が模したものが小雅の蔵となり、同じく竹逸渡辺崋山門下同門の椿椿山の模したものも、東京博物館に現蔵されている。
香亭友人の内藤恥叟(1827~1903)は水府の産で、祇園寺の檀家であり、かつて心越自筆の頂相を観たことから、安政以後の寺数度の回禄により、いまだ原物が遺るか否かを憂慮した。
題東皐心越禅師肖像
越禪師肖像晋也被所調定管越此像往昔借井丕竹逸所寫本以墓之然當時不知典原本奚自獲後藤恥嬰過我観之日像原水祇園寺所蔵寺爲吾香花院管連回祿災所有物
件盡亥忍今無有幸得有之焉前冷數眸守寫本以遗小雅杵衬君則此圖是也頃君裝潢之遠郵遞以乞題簽併錄其來由以還之其乾墨狗墓絕無布彩者從逸描寫之舊池
23
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第141話
高士中根香亭先生 卅二 興津寓居と小雅宛附けたり 中
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
ここで前号に引き続き、香亭小雅宛て附けたりの中盤に戻ろうが、例によって()内は筆者責である。
其他浪人儒者生野臨犀の講席にも参じたれど、此人は安積艮斎が狂生と呼び居たる程の人物にて、人の師たる器には非ざりき、
朝川家は親戚なれど、遠方なりし為め、是又一字も教へを受けず、
故に世間の学者と違ひて、同門の友といふ者一人もなし、
大要は有志の友三四人と会読、輪講、作文等をして、互に切磨したるなり、是実は、聖堂流の学問の嫌ひなりし為、斯様な窮屈なる学問をしたるなり、今思へば愚の至りなり、
詩は十五六歳の頃より、大沼枕山の隣家に移り住みたる故、門人には非ざれど、益を得たること甚だ多し、是等は誤て門人といひても辞せざるなり、
右の如く、漢学は総て独修なる故、固陋は免れざれど、明師に就かざりしより、自然、力を用ふること多かりしめ、今日にても書を読むことのみは、余程常人より上手なる様に自信し居るなり呵々、
画は幼少より好みしかど、固よりいふに足らず、中年よりは山崎董詮翁に就きて学びたり、翁は董九如董烈の後を嗣ぎたる人にて、花卉を善くせり、翁、僕に山水を学ばんとならば、這老(董詮自身)にては上達せず、他に良師を求めよ、といはれたれど、画人に珍らしく学問ありし人なるを以て、僕、終身之を師と仰ぎ居たり、
英学は、乙骨太郎乙、小林弥三郎、薗鑑三郎、石橋好一等に学び、幕府の開成所へも少し通ひたり、前の四人は皆友人なれど、益を得たるは此方多し、要するに英学は甚だ未熟なり、
畸人伝に、僕不平ありて陸軍を去りたる様にいへるは誤り、
僕は、当時徴兵課長主任にて、参謀局の亜細亜兵制取調と、諸局より参り(ママ)勢の内務書編纂とを兼ね居て、相応に忙がしかりき、然るに最初の徴兵は、来九年現役を免ずる筈なるに、前の令の侭にては都合あしき件々ある為め、今の山県公其頃卿にて、僕をして之を改正せしめられたり、此時、僕脚気再発して艱み居たるが、強ひて之を拵へ上げ、病勢愈よからず、医師のいはく、縦ひ隊附ならず
乗馬にて出入する軍人などは、断じて已めざれば、此度は快復すとも、終には是が為めに斃るべし、といふ、
依て辞表を出したるにて、山県公も鳥尾子(小弥太、号得庵。子爵、陸軍中将)を以て緩々摂養すべしと懇諭せられ、一局長大山公(巌。公爵、陸軍大将)(徴兵課は一局に属す)竹島某を以て留任を諭されたれど、前の如き事情なるを以て、遂に辞職したるなり、
故に去るに臨み今後兵を取る方法、(当時、地方にては陸軍を甚だ嫌ひ、種々の手段を以て丁員を隠し、兵を取ること誠に困難なりき)
又、課長に小倉の人馬場素彦を挙ぐべきことを進請したるに、皆其言の如くせられたり、
数年の後文部省に出でたる時は、唯奏任御用掛といふ単一なる名目の下に、編輯の業を執り居たり、畸人伝に判任の方が月俸の多き都合ある為め、其の方に勤め居たる様にいへるは、何の間違ひなるか、
さて文部を罷めたるは、十八年諸省大改革の時なり、
其頃は鈴木唯一と僕と英文読本の材料を集め、外山正一之を仕上ぐる約束にて、斯に従事し居たるに、一日出勤して見れば、鈴木は昨日免職になりたる由なり、僕は同功一体の者なる故、独り留るべきいはれなく、又外山と鈴木とは古くより共に箕作門人なるに、独り鈴木を排したるは感服せざる仕方と思ひ、鈴木同様免職せられたしとて、辞し去りたるなり、
四五日前、木村架空来遊一泊して種々快談のをり、話次左の一段を語りて共に笑ひたり、
尊君の如き僕を信ずるの余り、其所見余程買ひかぶりて平を失へる処あり、依て其事を略記して貴覧に入るなり、
今より十五六年前、僕偶依田学海翁を訪ひたる時、翁我に向ひ、足下は久しく独居の姿にあれど、或人中根は外に蓄妾して居る、といへり如何にといふ、僕之に対へて左の如くいへり、
昔し、家翁(養父中根忉雲)予が為めに婚を議けるし時、親類の長島弘道 方今静岡市長の長島弘裕の父 妻(後の香亭妻西村氏)の父と同勤なりし故、西村の女を娶りては如何といひしに、会(たまたま)翁(養父)病に臥し居り、対門(中根家向いの)武島生の婦は妻(すでに亡妻ではあるが)の姉にて、容姿もあり且つ柔順なりし故、翁彼の婦の妹ならば宜しかるべし、病癒れば相談せんといひたり、
三四箇月を経て、妻の姉腸窒扶斯(腸チフス)にて歿し、伝染して父(武島氏)と弟とに及び、父又是にて歿したり、
我方にては、翁の病漸々不良に陥り、翌年二月終に館を捐てたり、
半歳余経て翁の後役出来、僕是に屋敷替して堀田原のどぶの中の屋敷に移りき、(堀田頭は浅草にて甚しき低地なり依田の旧主堀田氏の下屋敷あるを以て此名あり予依田との話し故、殊更ぶといひたるなり) 且つ其年叔母(小娥女史)をも喪ひ、翁の長病以来借財も崇み、母は老衰して家事を厭ひ、更に困難を窮したり、
又其翌年僕除服後、長島来りて前談の緒を開く故、そは一昨年の事にてもあり、未だ結納したるにも非ざれば、縦ひ其女猶家に在りとも、此有様を聞かば承諾はすまじといへば、然らず、東隣の同家外国局を勤むるを以て、奉行江原(ガウハラ)伊勢守屢来れるが、先頃西隣の娘を貰いひたしといへりとて、同家非常の幸福なりとて勧めたれど、事に託して応ぜず、
又姉の迹へ勧めたるも者あれど、是を断りたるは、全く此方へ帰ぎて、
共に艱難を与にする覚悟なりといふ、
僕も母も如是ならば甚だ幸いなりとて、茲に之をふることとなしたるなり、
翌年は僕将軍家の上洛に従ひて半年ばかり不在、翌々年は征長の軍に従ひ二年足らず滯阪、其間山荊(新妻のとき)善く母に事へ、住所もどぶを免れて再び下谷に移り、僕七歳より養はれたる老母を、兎も角も六年間安楽にして見送りたるは、妻の尽力したる為めなり、
僕謂へらく、妻は必ず清淑なるべし、而して夫は何をしても好しといふも理もなければ、妻の尽したる為めには、吾も亦尽す所あるべしと思ひ、終に先生初め諸君の勧めをも峻拒し続絃せざるにて、
独棲の原因此に在れば、妾の有無は弁ずるにも及ばずといひたり、
依田は正直なる人故、さもあるべし、君が談中、吾頻に暗涙を催したり、吾尊嫂(香亭亡妻)の為めに漢文にて伝を作らんといふ故、夫は甚だ迷惑なりとて固く制したり、翁(学海)は筆の利くと同時におまけを書く癖あるを以てなり、
此談は雑誌には関係なけれど、僕の独棲は私情に出たることにて、高潔などいふ立派なる事に非ず、斯様なる内情は屢口外すべき筋にも非ざれば、人の誤認せるも一概には尤められざるなり、
此書は前にも申したれど、御通覧の上は、必ず丙丁に附せらるべし、(前書同日)
香亭の妻となった西村与一右衛門次女の時子は、武家の妻女、貞女の鑑のような人で、不在がちな夫を扶け、貧に負けずよく家庭を護ったが、惜しくも天寿を全うできず、さらに無情にも天は一子彪をも召してしまい、以降、香亭はややもすれば深い悲しみに沈みがちとなり、折に触れ、その心中を慰め続けた秋香も興津に先逝し、以後その人生感にいっそう隠棲味を増す。
(続)
「中村秋香小照」『不尽迺屋遺稿』
明治44(1911)年前川文栄閣刊より
晩年、御歌所寄人に召された秋香は静岡藩士であったため、なにかと旧藩内にはかかわりのある場所が多かった。
『秋香集』
明治40(1907)年6月五車楼刊本
国文学者で歌人の秋香の短歌集である。なお、長歌は刊行されぬままにあったが、その一部のみが近年翻刻されている。
「松の下庵」
前揭『不尽迺屋遺稿』より
秋香が興津に設けた俺は「まつのしたいお」と読ませる。
秋香と仲睦まじく、ともに利用し来たった香亭であったが、前号ご紹介の理由らで、ついには自身も興津を終の住処と定め、理想とした最後の迷花書室(屋)とするのである。
23
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞
中根香亭略年譜 上(天保10~慶応4年) 坂田進一編
前言
拙稿中の香亭連載はすでに三年越し三十回を超えたを機に、愛読者利便のため「略年譜」を加えよう。その根拠とするは、継ぎ接ぎだらけの拙稿を核とすることもちろんだが、先達田中明氏の『中根香亭先生年譜稿』(1996年私家版)によるところが大きい。氏とは十五年近くの以前、興津における香亭事蹟フィールドワークの際、大変お世話になったことも懐かしく、誌上をお借りし、ここに御礼申し上げる次第である。なお、「略年譜」とはいうものの、一回では収まりきらず、明治改元以前でいったん区切り、以降は再度分載せねばならぬこと、また、第一に香亭自身にかかわることを中心に編み、あまりに些末な他事は省略した。
太陽暦 旧暦 天皇将軍 年齢(数え) 香亭事蹟と関連事項
1839年己亥天保10年120代仁孝天皇・12代将軍徳川家慶
1歳2月12日(新暦3月26日)、各務(本姓曽根氏)一郎の第二子として下谷長者町に生まれる。実母は外祖父朝川善庵の長女操【親族交友】各務一郎は幕府御徒目付元締(勘定役)。長兄雷太郎(号震斎)他、兄妹七子
1840年康子天保11年
2歳【親族交友】弟義温(後石上氏)生
1841年辛丑天保12年
3歳
1842年壬寅天保13年
4歳
1843年癸卯天保14年
5歳【親族・交友】妹之瓦生(しが後片山)
1844年甲辰天保15年12.2弘化改元
6歳【親族交友】3.3妹雅楽(うた後原田)生
1845年乙巳弘化2年
7歳下谷御徒町住、御徒士中根幸右衛門(号忉雲)の養子となる
1846年丙午弘化3年
8歳【親族交友】隣家の画家相沢石湖の席画開筵に臨席し、以来画業に興味を抱く
1847年丁未弘化4年 121代孝明天皇即位
9歳【親族・交友】妹縫(ぬい後宮城)生。実父一郎信濃・越後遊歴。12.29石湖没
1848年戊申弘化5年2.28嘉永改元
10歳【親族交友】1.24実父一郎歿(51歳)。冬御徒町火災のため生家各務家焼失す。このころ養父雲尺八の会を盛んに開き、会場の酒茶を周旋する。実兄雷太郎(御徒士興津甚左衛門組70俵5人扶持養子願不許可
1849年己酉嘉永2年
11歳【親族交友】2.7実母操の父(外祖父)朝川善庵没(60歳)。この
ころから馬術・剣道に励む
1850年庚戌嘉永3年
12歳伊庭道場に通いはじめ、伊庭八郎・忠内三郎三・湊信八郎・屋代貞次郎と親交を結ぶ
1851年辛亥嘉永4年
13歳隣家金子半七郎のもと、算術を習いはじめる
1852年壬子嘉永5年 14歳
1853年癸丑嘉永6年13代将軍徳川家定
15歳大姑中根恒(つね号小娥清崎姓)中根家に戻り、以後、恒の影響下読書に専心する。清水純斎に学ぶ(これは香亭自身が否定)南隣家が大沼枕山家のため親しく往来し、沈山に陪従し各時会に参加する。三昧橋畔に転居する【親族・交友】中根家下谷三昧橋畔に転居する
1854年甲寅嘉永7年11.27安政改元
16歳水戸行。7.28実母操(号白蘋)没【親族交友】養父中根氏御徒士二番組頭桧之間150俵高300石高扶持となる
1855年乙卯安政2年
17歳10.2江戸大地震で中根家全焼す【親族・交友】中根氏御徒士吉川一学組。3.24外祖母朝川夫人孝没【主要著作】「撃剣歌」
1856年丙辰安政3年
18歳羽倉簡堂門に学ぶこと約半歳
1857年丁巳安政4年
19歳脚気に罹患し歩行できぬこと約半年、秋には腰が立たず、ここに武技を断念し、学問に専心する【親族・交友】3月実兄雷太郎小普請方改役となる。中根氏御徒士加藤組10.22朝川善庵養嗣子同斎没(44歳)
1858年戊午安政5年14代将軍徳川家茂
20歳生野臨斎の講席に参加す【親族交友】8.13伊庭軍兵衛8代秀業没(号常同子48歳)
1859年己未安政6年
21歳幕府開成所(蕃書調所)に学び、乙骨太郎乙・小林弥三郎・薗鑑三郎・石橋好一らに英学を学ぶ
1860年庚申安政7年3.18万延改元
22歳親類長島弘道より結婚の周旋あり【親族・交友】10.22後の香亭妻の父西村与一右衛門没
1861年辛酉万延2年2.19文久改元
23歳1月実父各務一郎13回忌ならびに実母操7回忌を修す。2月養父中根雲没。9月養父後役が決まり、中根家浅草堀田原に所替す。養父の長患以後借財が嵩み、養母も老衰し家事が困難となり、貧窮を極む【親族・交友】11.5叔母小娥没
1862年壬戌文久2年
24歳喪明長島の結婚話再興し、西村氏次女時子と結婚【親族・交友】1.28兄雷太郎の長女華子生。8.21羽倉簡堂没(73歳)
1863年癸亥文久3年
25歳2.13将軍家茂公の上洛に際し、御徒士12番隊興津組、御旅館勤番として随行、江戸を発ち、3.4京都着。大阪天満東寺町妙福寺に大母尾崎氏の墓を掃う。7.2江戸帰府沈山に詩の添削を請う
1864年甲子文久4年2.20元治改元
26歳長州征伐軍に加わる【親族・交友】生家各務氏長兄雷太郎(時に御作事組頭)没
1865年乙丑元治2年4.7慶応改元
27歳5.16御徒士目付(12番隊興津組)として家茂公の広島遠征軍に加わる。清水純斎詩を呈す5.25大阪入城。天満にて真鍋豊平に一絃琴と歌を学ぶ。同門に麾下の士富田礫川あり【親族交友】4月伴門五郎(伴賀右衛門の養子の子)を中根造酒(香亭)の弟として親類書を提出す
1866年丙寅慶応2年15代将軍徳川慶喜
28歳2.23布衣以下御供の詩作文章を仰せつけられ、大阪城連歌の間にて『中庸』第22章より御前講義(御目見以下では前代未聞)をなす。龍海寺西湖和尚に『南華真経』を講義する。6月監曹(御徒士目付)として広島行。12.28陸軍指図役勤方に転勤(同勤内田有親、頭取江原素六)す。同12月真鍋豊平との暇乞いに際し、豊平自作の琴を贈らる【親族・交友】西湖和尚寂、遺言にて大硯、貫名海屋の山水一幅を贈られる【国内世事】7.20将軍徳川家茂公薨去【主要著作】8月刊真鍋豊平『須磨之枝折』第2篇中、中根貞「作歌「後の月」所収さる
1867年丁卯慶応3年
29歳1月江戸帰還。同歩兵第7連帯指揮官(同勤に川路聖謨外孫戸田金吾)となる。3月聖謨へ面会の書を呈し、数日を経て面会す。中根家堀田原から再度下谷へ移住。7.4養母没。7.17香亭長子早逝。12.29第7連隊に属し長鯨艦で兵庫へ。12.30大阪へ。真鍋豊平を尋ねるも不明【国内世事】10.15徳川幕府大政奉還。12.9王政復古【親族交友】7.4養母没。9.17実妹うた原田元信に嫁ぐ
1868年戊辰慶応4年9.8明治改元122代明治天皇即位
30歳1.1難波橋上にて伊庭八郎(遊撃隊所属)に遇い、諸藩の動静を交換する。1.3鳥羽伏見の戦では、第7連隊歩兵1大隊に属す。夜間鳥羽苦戦により援軍にいく。1.4未明の砲戦で2丸被弾、1は軍服右脇、2は左袖から皮膚を掠めるも、危うく助かる。1.5敗軍となり淀へ退き、6日には橋本へ移る。敗後残兵と大和伊賀を越え、東海道を下り、さらに紀州にから小船にて熊野に至り、順動艦に乗船す。伊庭の弟金田武司、香亭戦死の誤報を中根家にもたらす。2.10江戸着艦。乙骨太郎乙とともに軍事掛附となり、勝海舟に属して官軍の動静を偵察す。海軍に入り奥羽石巻へ至り、金華山に登る。4.15小田原にて脱走者説得。海舟の戦意無きを痛罵し、軍事掛を辞し、海舟の属下を去る。5.11多賀外記に服す。5.15上野彰義隊の戦。別手銃隊多賀組に属し、広尾祥雲寺に駐官軍背後を衝かんとするも多賀邸、祥雲寺急襲され、兵を解散。多賀兵、榎本配下の海軍に投ず。6.25乙骨、海舟を訪問し、香亭らの駿府従行を進言す。7月榎本の軍艦に移る。7.25兵士を率い三加保艦に乗船するも、中島三郎助と激論中、図らず伊庭八郎と出会う。8.19軍艦8隻で品川沖を出帆、三加保艦(艦長宮永扇三)は開陽艦に曳かれる。8.22夜間鹿島灘にて台風に遭い、香亭詩文稿を失す。開陽三加保を切り離す。8.23安房沖にて碇泊、さらに北行す。8.25夜風雨激化。8.26黒生浦にて座礁し、からくも500人ほど上陸。艦大破し、総員上陸後、函館を目指し四散する。夕刻八郎と合流、八郎の自決を止め、木更津行を目指し、隊の後事を本山小太郎に託し、上総各地を経て、単身江戸に入り、神田今川小路の杉田廉卿宅の乙骨を訪ねて行先を相談す【親族・交友】5.15伴門五郎戦死【国内世事】3.13西郷隆盛、勝と会談、江戸開城で合意す。4.11徳川慶喜江戸から水戸へ。3.15川路聖謨自決【主要著作】「戊辰春日東台即事」
24
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第142話
高士中根香亭先生 卅三 興津寓居と小雅宛附たり 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
香亭、伯耆米子の杵村小雅に宛て、健気にもかく愛妻の逝去を知らせる。
淑啓、春来余寒厳候処、道屐御安健なりや否、客年来の御違和爾後、家事に取紛不奉何、甚関心罷在候。
扨、山荊病中は貴意被為懸、度々御訪問を蒙り感荷浅からず、奉深謝候。然るに何分大患の事迚、漸々不起の症に陥り、終に本月四日を以、溘焉永逝仕候。
当初は快復後篤く御礼可申述など申居候ひしが、後には不治と悟り候か、寄り寄り後事申遣し、終焉に及申候。平素薄弱なる故、最初より摂養を忽に致したにも非ず、医師も二三の国手診断投剤致し候事故、治術を誤りたるにも非ず、所謂命数の然らしむる処にて、是等に遺憾は無之候へども、早歳艱難に相従ひたる、即ち糖糠の妻に候間、往時追懐感傷なき能はず。
※幸いに一人の豚犬有之候間、是よりは㷀㷀(ケイケイ)(孤独なうちにも)相依り、不十分ながら、内外家事相営候計画に有之候。
本日は二七日、そこら取片付候処、
自筆(妻女の)にて、団扇に枯柳寒蝉を描きたるもの出で、豚児と両人思はず傷心仕候。
種々の愚痴立て、慚愧の至に堪ず候へども、是此煩悩即禅心の好種子、此情かくては大悟は覚束なくと、自分極めの禅理を御耳に入れ申し候。先は尊恙御容態伺、旁老妻死去御報迄如此。
喪次取込中故、他に及ばず。
勿々不宜
二月十七日(明治二十六年)淑再拝
小雅杵村先覚
また後年、中村秋香は香亭の妻と息子の年忌に際して短歌を贈れば、
中根香亭ぬしのまなむすこ彪氏か心臓麻痺の症にて俄にみまかりけかなしみて香亭ぬしに
あやなくも猶こそ歎け定なき よのことわりはことわりとして
現とはわれたにおもひわかれぬを 夢のゆめとや君はたとらん
彪氏かみまかりしよりやうやう百日にもちかよりぬと思ふにつけて香亭ぬしの心いかにとおもひやるたに袖のつゆなり
なにことをおもふとなしの袖たにも 露けきものを此ころの秋
感激した香亭は秋香に宛てていう。
…前略…
亡荊へ御手むけの尊詠有難く忝なし。僕は随分断念強き方にて情に乏しく。自分にても是が為め、薄情に陥りてはならずと、時々身を省るといふ様なる性格なれば、不幸に遇ひてもあきらめ早く、悲まざるには非ざれども、決して児女の啼を為さざること、殆ど僧徒以上と自信する程なり。
然るに今、尊詠の前書をよみ、未だ御歌に及ばざる中、ふと感涙を催し来り思はず自失せり。
是は豚犬の事まで併せ記されたる故かと、自ら疑ひて思日返したるが、熟考えすればさるわけにもあらず、細かに見れば、いと短文なれども此中三折して、無限の情致を尽くされたる為めなり。
鳴呼、文章といふものはいとあやしきものなり。之をよみて、うるみた目を以て尊詠を見る、いかでか袖をぬらさらむや。
当日は必ず之を牌子前に相供へ申べきなり。
先以、今朝のありのまゝと、己が感傷の何に依て生じたるかを究めたること等、御懇意に任せ、打明けて報ずることかくの如くし。
時下御自愛特に祈る所なり。余は再信に悉すべし。
二月二日(明治四十二年)淑 拝
中村仁兄大雅
文 几
と答礼、さらに続けて二月十日には、
昨今はいかが、おはすらんなど、思ひ出さぬ日とてはなし。
当地まづまづ暖気の方なれど、さりとて朝夕の冷かたは又格別なり。亡妻年回につき御寄贈下されたる尊詠、当日牌子前に手むけ供養せり。外に鎌くらの新保(磐次)氏、より若緑といふ香を送られ、其たゝとう紙に書されたる歌、
春たつと君が引けんわか緑 昔思へばねぞなかれける
是をも共に備(まま)へたり。さてその日僕墓を掃ひて、
思ひきやかくながらへてなき妻の 苔むすはかをとぶらはんとは
先づかやうな事にて、形ばかりの法会ながら、滞りなく其式を終へたり。早速御礼を述ぶべき処、多少右に付ての俗用残り居り、今日までも延引せり。昨日伯州米子(小雅)より、同地製の羊羹をもらひたれば、特にかほりたるふしもなけれど、遠方の物といふだけの名を、小包にて御裾分け致すにつき、略儀ながら、此中に御礼辞を併せしるすこと斯くの如し。
余多く具せず。 匆々
紀元節前一日(明治四十二年)淑 拝
中村仁翁大人
侍執
(内、句読筆者責)
と、いかにも武士(もののふ)の矜持をもってこれに返歌するのである。
香亭夫人時子は、一子彪(号湖城)の結婚を見ずに先逝するが、明治二十七(一八九四)年四月、ようやく媒縁を得て彪は結婚するも、翌年八月に重い脚気を患い、新婦も不治の病に罹ったを機に、やむなく双方合意の離縁とはあいなる。
明治三十(一八九七)年十一月、香亭と因縁のあった三加保(美嘉保とも)艦もと艦長宮永荘正の女ためと彪は再婚するのだが、一年を経ずした同三十二(一八九九)年の八月八日、急性胃炎を発症し、心臓マヒを併発して三十歳の若さで急逝、天に召されてしまうのである。
糟糠の妻を失い、それでも気丈に平静を保ち、
※幸いに一人の豚犬有之候間、是よりは相依り、不十分ながら、内外家事相営候計画に有之候。
など、以下禅気を交えつつ小雅に報告した香亭だが、運命の悪戯か、六年後にはその頼みとした彪をも失う、その心中いかばかりであったろう。
心友中村秋香は興津に庵を構え、
三十五年四月興津にある程ゆくりなく松のした蔭に作りし庵をあかなひ得てうつりすむ左に伊豆の山々右には三保の松原龍華寺山なと松のこのまより見渡すけしきいはんかたなし
磯きよく波ゆたかなりいさこゝに つひのわかよをまつのした庵
晩年の秋香がこの庵を核とし、唯一香亭との交友を楽しみとしたその根底に、異なる境遇にあった二人の来し方がそこかしこに凝結し、打算のありようもない、まったく世評を度外視した、いかにも清淡な心交密なる一齣がこれらの歌に垣間みえる。
情緒纏綿、続けて中村秋香は香亭との交友を歌に綴り詠ずる。
香亭ぬしと松の下庵に語らひくらして
おもしろく今日もくらしつ 心あひの友まつ蔭に語りかはして
(続)
新聞記事「七絃琴の伝来」
明治23年6月3日 (横浜)毎日新聞 中根香亭編
友人島田沼南(三郎)の紹介を得て、香亭が『(横浜)毎日新聞』、明治23(1890)年6月中に、11回にわたり不定期連載した第1回目である。
該連載を見た大島貞益が、「香亭人の参考に供す」なる、先祖から伝わった浦上玉堂にかかわる別記事をも寄せたが、これは『香亭遺文』中には収録されぬままである。
左上◎印部分がその第1回で、この記事を見た小雅が用人を介し香亭と面会せしめたことで、香亭の没するまでもその交わりは続くことになる。
55
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞
中根香亭略年譜 中(明治1~25年) 坂田進一編
太陽暦 旧暦 天皇・将軍 年齢(数え) 香亭事蹟と関連事項
1868年戊辰明治元年9.8明治改元122代明治天皇即位
30歳9月尺八(英国公使パークス通訳)を頼り横浜の永楽屋飯岡氏にて函館行き外人用便船を依頼、同所で田口卯吉と再会し、東京と横浜間を数度往来本山小太郎と伊庭八郎の救出を議す。
一時尺の周旋で外国商館の手代となる。中根家の籍から一時脱す。8.23会津落城、尺に北走を止められ伊庭のみを依頼する。9.14明治新政府、三加保艦脱走者として中根造酒之助(香亭)を官報に加えらる。9.22乙骨太郎乙勝海舟に香亭の助命を嘆願す。同月徳川新封土の駿河に乙骨の従者として赴き、変名して小島村に暮らす。同月阿部邦之助、海舟を説き伏せ中根の脱籍を復す。11.23徳川家兵学校の三等教授方に中根逸郎の名で就任(御役金200両)する
1869年己巳明治2年
31歳この年任地沼津で家塾を開き、田口卯吉らを門弟とする。5月乙骨上京し尺と面会、伊庭本山の函館行を知る。【交友】8月伊庭函館にて戦死(27歳)【国内世事】7.17江戸を東京と改称す。8月徳川家兵学校沼津兵学校と改称
1870年庚午明治3年
32歳次子彪(生日?)生。5月尺氏沼津に来る。この秋上京す。
『慶安小史』の元原稿を書く。10月徳川家兵学校附属小学校
(明治1.12創立)頭取(校長)を兼任す。11月乙骨田口を連れ静岡に移る
1871年辛未明治4年
33歳3月香亭・塚本明毅・渡辺無尽・石橋好一・江原素六らと伊豆を巡遊する。6.6静岡で海舟と会見した後遠州を旅行、ついで横須賀の伊庭軍兵衛を訪問し、伊庭八郎のことと同想太郎を引取ることを約す。静岡に寄り林又七郎塾の想太郎と会談す。同月1週間ほどして想太郎来沼し、香亭家塾に入る(3年間)。塾にて成瀬隆蔵・高橋三九(木村架空実兄)らに万国史や究理学を講ず。9月熱海でたまたま同宿の清人医師の源恬波・梁慧軒と『浴間筆語』を遺す。11.3徳川家小学校を沼津小学校に改組、香亭に代わり鈴木吾一校長となる。12.2陸軍兵学寮2等教授並・中助教9等官となり中根逸郎を淑と改名。【国内世事】12.16沼津兵学校を合併し沼津出張兵学寮と改称、兵部省管轄とする
1872年壬申〇明治5年陰暦12月2日をもって太陽暦12月31日とする
34歳5月沼津出張兵学寮廃止し東京へ移転夏沼津より東京下谷に転居6.28伊庭秀賢没(73歳)東台山下(下谷仲徒町4丁目32番地)に転居 陸軍参謀局に出仕し、兵史徴兵及び東洋諸国軍制を管掌す。『兵要日本地理小誌』を撰述し、はじめて「日本海」と名づけ、また同書の送り仮名の統一を図るも、刊行を急ぐためそのまま上梓すべく準備される。【主要著作】詩文「蔦姫伝」など
1873年癸酉明治6年
35歳1月香亭の稿なり、これを山県有朋が『兵要日本地理小誌』と命名。鳥尾中将(得庵)中根淑の著と明記されぬを不服とし争うもならず。9.5香亭妻の母西村与一右衛門夫人没。【主要著作】『兵要日本地理小誌』・附図「大日本国全図」(陸軍兵学寮刊著者無記名)。詩文「舟入柳塘」、「美人挿花図」、「飯田覚兵衛」など
1874年甲戌明治7年
36歳2.9佐賀の乱鎮定のため参謀官として大阪に赴任、かたがた信太森の大砲射的場を見分す。2.28陸軍歩兵少佐(9等出仕月俸100円)に任官す。このころ鳥尾司令長官と歌会に興ず。た真鍋豊平を訪問するも不明。3月県人募集行。4月伊庭軍兵衛、想太郎を江戸に連れ戻すべく上京す。香亭旧蔵の楠公像、大阪にて紛失す。大阪にて写真撮影す。阪神鉄道開通し、鳥尾と布引瀧を見物す。6.18陸軍参謀局第5課(地図政誌課9等出仕。8.28鳥尾長官から来翰あり、大阪鎮台司令長官免職を知る。8月一絃琴真鍋豊平同門の旧幕臣富田礫川(明治2年浜松へ移住し三方原開墾に従事)没(59歳)。10月帰京の途次名古屋に四条隆謌を訪い、舟で浜松へ出て東京に戻る。【交友】4月伊庭軍兵衛、想太郎を江戸に連れ戻す。【主要著作】詩「文「高麗橋」、「楠公墓再拝」、「得家書」、「由良峡」、「下淀川」、「大「阪城懐古」など
1875年乙亥明治8年
37歳この年陸軍省第1局徴兵第2課長主任・参謀局亜細亜局兵制課長亜細亜兵制取調内務省局編纂などを兼務。山県陸軍卿より最初の徴兵令担当を命ぜらる。明治9年に現役免除とする改正案を上申す。7月『改訂兵要日本地理小誌』中根淑著と改められたを機に、文名一時に挙る。冬脚気再発し軍人を辞すよう医師から勧告され、馬場素彦を後任に推挙し辞職する。同冬根岸御隠殿通(北豊島郡金杉村185)に転居し、書斎を迷花書室(李白「贈孟浩然」とする
1876年丙子明治9年
38歳この年家塾を開く。8月仏書を耽読し、かたがた原坦山師下に参禅す。12月香亭、鈴木唯一・外山正一・乙骨ら浪士5人と計り、神楽坂上の廃社八雲神社跡地を買取り、私立学校を計画海舟の出資を依頼するもならずして止む。【交友】12.6田口卯吉婚儀。【主要著作】2月「慶安小史』(私家版)。8月「日本小【文典』(迷花書室私家版)
1877年丁丑明治10年
39歳◎この年山崎董詮から画を学びはじめ、香亭をもって号としはじむ。 7.25高橋三九西南の役で戦死、香亭「墓誌名」をものす。【親族交友】10.22浅川善庵の長子相田正準没。11.24関雪江没。【主要著作】3月『独学日本地理書』(迷花書室私家版)。12月『日本文典』、『筆法小学』(私家版)など
1878年戊寅明治11年
40歳この年田口卯吉を福地桜痴・栗本鋤雲に紹介する。春矢口謙斎静岡から上京し、先師各務得斎(香亭実父)の墓参し、偶々林鶴梁と遇う。10.9香亭、大槻文彦・片山淳吉・南部義籌・諛小山由清・内田嘉一らと文法会を結成する(後に井上哲次郎・関根正直・那珂通世らが加わり明治15.4.30解散)。葛飾柴又郡、仁右衛門松傍らに隠棲する森本惣兵衛に、一絃琴の手ほどきをうける。【主要著作】12月『作文要訣』(迷花書室私家版)。「詩文「戊寅元旦」、「根岸閑居」、「春日訪栗本鋤雲園中芍薬盛開」、
「中村秋香贈見興津鯛」など
1879年己卯明治12年
41歳この年から小河原長行子爵より嗣子長生の教育を依頼され、毎土曜(以降6年間)経書詩文添削す
1880年庚辰明治13年
42歳1月鳥尾小弥太(得庵)子爵より、大阪にて得た山水画を贈呈さる。本所火災の見舞い途中、図らずも原坦山師と邂逅す。12月文部省出仕となり編輯局勤務(御用掛准判任官)
1881年辛巳明治14年
43歳この年『歌謡字数考』執筆
1882年壬午明治15年
44歳4.30文法会解散(通算56回)。6月文部省御用掛奏任官となる。9月千葉県飯沼村笠上(黒生)に三加(嘉)保艦遭難(明治元年)碑を建立(香亭書)す。11月文部省編輯局小学校教科書の送り仮名統一を協議する
1883年癸未明治16年
45歳4.22小石川伝通院にて高芙蓉100年忌に参加す。夏伊沢修二に依頼し、音楽取調掛にて一絃琴の調査をする。11月明治7年大阪で紛失した楠公像を鳥尾子爵が入手し、これを香亭に贈呈する。【主要著作】詩文「書芙蓉軒遺篆後」など
1884年甲申明治17年
46歳3月横浜杉田村にて梅花観賞す。4月上野にて第2回内国絵画共進会観賞す。8月文部省御用掛准奏任官となる。【親族・交友】10.7朝川同斎夫人没。この年小笠原長生香亭塾を退き、海軍兵学校に入学す
1885年乙酉明治18年
47歳4.19田口卯吉夫人千代没(23歳)。5.16第14回沼津旧友会幹事役(築地八百松)。5月徳川育英会を企画す。香亭、文部省にて鈴木唯一と英文読本の材料を蒐集した後、外山正一の手で完成にいたる。12.28文部省改革により辞職する。この年下谷根岸新坂下の井上竹逸より七絃琴の資料を借覧し写し取る
1886年丙戌明治19年
48歳春に肱を痛め、これよりしばし一絃琴から遠ざかる。3月文学社編集局に勤務す。7月文部省府県訓令で中等教育に採用すべき第1の書に香亭著の『日本文典』選出さる。10月磯部温泉にて湯治する。谷中天王寺五重塔修復募金に寄付する。11月金港堂に勤務しだし、教科書校正を管理する。【親族交友】2.13第9代伊庭軍兵衛没(63歳)。4.3渡辺崋山門下四天王の一で琴客の井上竹逸没(73歳)。11.7田口卯吉再婚(先夫人の妹鶴子)す。【主要著作】『香亭雅談』7月金港堂刊
1887年丁亥明治20年
49歳5月谷中全生庵に伴門五郎碑を建碑し、義捐金を拠出する。9月また磯部温泉に滞在す。「前句源流」を執筆しだす。秋絹本着色「江山無量」を描く。【主要著作】『天王寺大懺悔』4月金港堂刊
1888年戊子明治21年
50歳3.1香亭、藤本真(藤陰)金港堂に紹介する。同月島田三郎の『開国始末』に批評を加える。5.6梅若歌宅演ずる能楽「二人静」を観賞しスケッチする。8.6依田学海と上州を巡り、高崎からは香亭一人で榛名山に登る。8月沼津小学校附属文庫設立を機に、香亭蔵書の半ばを寄贈する。9.28香亭、山田美妙を金港堂に聘し、「都の花」を担当させる。12月埼玉県下を旅行す。【親族・交友】2月金港堂で香亭下に働き、同堂から米国に留学した三宅米吉(号昭軒後に博士帝室博物館総長や東京文理科大学総長など)が帰朝し、金港堂編輯所長となる。5.7伊豆戸田村にて多賀外記没す。9.23清水純斎没。11.3各務家嗣子義長生まれ実家存続す。【主要著作・編纂】10.21「都の花」を創刊し、香亭が発行人となる。同誌に「謡文評釈」を連載する。「12月「都の花」発行部数15,000部となる。
1889年己丑明治22年
51歳1.4西村家の末っ子に益夫と香亭が命名する。1.5またまた磯部温泉に行く。同月新富座観劇。4.27沼津兵学校同遊会に参席のため沼津行。5.25上野にて円山応挙展を観賞す。11月文部省総務局長から「日本文典」の検査委員を命ぜらる。12.14下谷万代軒の文学会に出席
1890年庚寅明治23年
52歳6.3(横浜)毎日新聞に「七絃琴の伝来」連載開始。6月下谷金杉の家を太田氏に売却(旧宅2,300円・地代坪4円・家350円)※このうち迷花書室を含む三分の一ほどを、後の大正年間に中村不折が購入する。同月同金杉村317御行松傍らの借家に移転(2階建て月額8円50銭)す。7月毎日新聞の記事を見た伯耆米子第5代町長杵村源二(次とも号小雅)郎より再度書翰あり、これより生涯を通じての文通始まる。9月一絃琴真鍋豊平『香亭雅談』を読みて交友再開す。旧古河藩主土井家邸宅一部曙町16の地に家屋を新築し移転する。【親族・交友】2月山田美妙金港堂を辞す。5.9長島弘道(義父義兄の長男で養父のもと同僚)没(71歳)。7.11一絃琴家柴田花守没(82歳)。【主要著作・編纂】10月「小説叢書」編輯(金港堂)など
1891年辛卯明治24年
53歳この年から木村架空に一絃琴を教え始める。2月一家して流行性感冒に罹患す。暮春尺振八の母を牛込に訪問す。5.20「都の花」発行を停止処分され、警視庁に出頭する。6月「横浜毎日新聞」に「七絃琴の伝来」連載。12月勤務先の金港堂書籍 会社と改組さる。【親族・交友】6.7中村正直没(60歳)。6.12実家各務家次男を淳と命名す。10.1時宗大沼沈山没(74歳)。【主要著作・編纂】3.30「日本画譜」編纂。『頭書保元』(金港堂刊)。「『新撰漢文読本』。7月「おどけ草紙初輯編纂以降25年7月2輯まで。9.13「百万塔」編纂以降25年7月22号まで。10.1「古今画林」編纂。10月経済雑誌社「大日本人名辞書」に10余名追加執筆し、序文を書く。11月「花のいろいろ」「虫のこゑごゑ」編纂
1892年壬辰明治25年
54歳1月再度流行性感冒に罹患し3月までおよぶ。春「狂句詠詩集」を編纂し序文を書く。10.2「山あそび」紀行(「国の教育」掲載)に出発、同月9日帰宅す。11.27尺振八7回忌記念祭柳橋亀清楼に出席す。11月妻時子風邪の後遺症で20余日間絶食。【親族・交友】3.14妻の里西村宗家鉄三郎没(76歳)。4.2西村熊二戸主となる。7.27原坦山禅師没(74歳)。【主要著作・編纂】5月随筆「塵塚」整理。「百万塔」編纂(金港堂刊)。『頭書平治物語』(金港堂刊)など
58
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第143話
高士中根香亭先生 卅四 小笠原長生 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
中村秋香の詠じる香亭との友誼は、前途を予見しつつもさらに続く。
その心情は細密にして、宛ら情人を慕うようでもある。と感ずるはあながち筆者ばかりではあるまい。
谷津の釣橋ははりかねにてつりた香亭ぬしと共に渡りこゝろみるにいとあやふし
これもまたよわたる道かはりかねの 糸を命のやつのつりはし
一月廿六日ぬしにあはす 書きておくる
わかれての後いかならん只ひと日 みぬたに君は恋しきものを
興津の水はすべて茶に合はす 海辺故にやとて 山より涌出る清水のこゝかしこなるを汲来て味ふに皆ふさはすぬしと共に興津川の水を汲み来て試るにいとよし
このめにはこれをおきつの外に又 にるものもなき流れなりけり
ぬし(香亭)保養館にあり 日ことにゆきかひつゝ
諸共にかくてよはへむ清見潟 なみのよるひるとひとはれつゝ
又東海ほてるの室にてかたる 庭に椶櫚樹(シュロ)多く風にさやく音いとおもしろし
歌かたり芭蕉のよるの雨もあれと 椶櫚の葉の風のゆふまと
ぬしとゝもに江尻散歩の途中
老の坂ともにこえてのゆくて道 われやさきたつ君やおくるゝ
実(げ)にこそ「歌占」そのもの。現今の墓友のハシリとも思しき、両人興津の松原における荼毘の件もこれにて分明となろうか。
ぬし京(東京)にかへらんとて出てたつとき「此後も君水くまは興津川 ひとりなゆきそあやふき淵に」さるは此程常にともに汲来れは也
ひとりはのきみかいさめに沖津川 涙こそまつさしくまれけれ
香亭ぬしとひ来てもの語の序に ことしも冬は興洋(興津沖)に遊ふへしとありしにその夜の夢にぬしと相携へて清見寺に遊ふとみてあくる日の朝
ことしもとちきりおきつの草枕 まつ夢にこそむすばれたけれ
そもそも筆者が中根氏墳墓の在処を知ったは、香亭が実妹原田頌子に宛てた次の文面によるが、調査当初は迂闊にも下谷から染井に移転した泰宗寺にのみ着目し、寺の墓域を捜索しただけに了っていた。然るに、
私方墓所の事御尋ねに御座候が、右は寺へ寄付金致し、永代毎月一度墓掃除を致すことに、只今の和尚の名はにて墓の横に切り付け申し候。御出京の節、御参詣下され有難し。其節御心づきなかりしかは知らざれども、私方菩提所は、ふしぎに染井墓地の入口へ移転致し、私方墓所が入口に近く候まゝ、御都合甚だよろしき事に御座候。御宅にて青山墓所の事、新聞等にて御覧になれば御心配御尤なれど、東京所々の地面の事、案じてははうづ(野方図、際限)なく、先々は如何様なるか分らざる事故、先づその侭にお置きなさるゝが然るべし。
私方のとて、百年の後は分らず候へども、自分の生きて居る間の勤めと思ひて致したることなり。
夫ゆゑ自分は何処で死しても、骨も残さず煙にするやう、皆々さへ頼み置き候ことに御座候。
倅清文院十三年に当り候に付、御茶菓御備へ下され候ひし由、御親切の段誠に有がたく、茲に御礼申述べ候。八月は酷暑ゆゑ、老夫六月に一寸出
京法事営み、其節は操そう早々立戻(興津へ)申し候。出立前日各務片山へもかけ足にて馳せ廻り候。…以下略
十一月十三日(明治四十四年)
興津兄
はら田お頌さま 人々
とあるではないか。
自ら青山を購めぬ主義を貫いた香亭だが、明治二十六(一八九三)年二月四日の妻時子の死を機に、かく「中根氏歴世墳墓」を新設するは、
「祀堂金貳百圓
泰宗寺永井月幹代」
「明治癸巳中根淑建之
毎月一回泰宗寺掃苔」
と、前記頌子宛書簡にある通りで、碑文は補足し読めるものの、その大枚二百円もすでに期限切れか、指呼の間にある寺の現住は、中根の「な」の字も知らず、無論、月一と先約された掃苔のありようはずもない。霊園用員の管理に委せるのみで、写真のよう、楠の大樹下に位置する墓石の風化は激しく、ここ数年を経ずしてまさに碑面剥落の危機にある。
心友秋香を興津の「松の下庵」極近の松林で荼毘に付したに倣い、香亭自身も遺言し、さらには翌日その三保沖に散骨させ、この染井の墳墓の下には在らぬが、その霊魂は最愛の家族とともにここに寄り添う。
さて、中根家の墓所にかく話題がおよんだを機に筆が重くなったが、香亭の主だった事蹟を伝えようにも、拙筆ではいまだその意の半ばをも伝達できぬまま、やむなく香亭自身の文や、他からの引用で正確を期する部分が多くなるわけだが、さりとて、ここにいつまでも香亭に拘泥し、貴重な紙幅を駄筆で汚し撹拌するわけにもいかず、そこで今回より〆の意も含め、香亭数ある門人中、小笠原長生(ながなり、一八六七~一九五八)を抜き出せば、ようやく本連載冒頭108~111部分に立戻ることとなるため、中根香亭旧宅の一部が現書道博物館となった因縁と経緯、しかしてその大団円へと誘えるであろう。
長生は、肥前唐津藩世嗣小笠原長行(ながみち)の嗣子として唐津城で生まれた。
長行の父で唐津初代藩主の長昌が二十八歳で早逝した際、実子長行はあまりに幼く、そこで親族から養嗣子長泰を擁立して第二代藩主とした。
その結果、生来頴敏な質であった長行は江戸遊学の機会を得て、碩儒朝川善庵の門に学んだことで、唐津藩主とならずも後年幕閣に参政し、奏者番、若年寄、老中職の重職を歴任するのだが、そんな因果もあり、長行は我が子長生のため、善庵の外孫香亭をわざわざ指名し、これに少年長生の教育を委託するのである。
長生は師香亭との来し方を『鉄桜漫談』(昭和三年刊)で述懐する。
一代の国士杉浦重剛氏をして、希有の高士と歎称せしめた香亭中根淑先生は、私が十六(十三の誤植)歳から、経書及び文章を以て師事した方である。
私は色々な人物を知ってるが、高士と云ふ点に於ては、先生に上越す人を見た事が無い。併し高士と云ふ意味の中には、潔癖とか隠逸とか、消極分子が多く含まれるやうであるが、先生此の班に漏れず、晩年は自ら有髪の比丘と称し、一根の如意を友として旅から旅へと遊歴し、一身雲水の如く悠々去来に任せてをられた。
先生剣を取つては、小天狗と怖れられた伊庭八郎と雌雄を争ふに足つたのみか、佐賀征討軍の参謀少佐として画策毎に敵の胆を寒からしめたし、筆を握っては錦心繍腸意に随って迸り、天晴一流の文豪と称されたが、家庭的には恵まれない方で、夫人に後れ、令息に先立たれ、晩年は誠に淋しい生活を送られた。
併し禅を修め陽明学に通ぜられた先生は、天命に安んじて静に人生を観じ
都いでゝさし上る月を見かへれば 心にかゝるうき雲もなし
と詠じすてゝ、終に興津の海水堂と云ふ菓子屋の瑣小な離室で、大正二年の初春逝かれたのである。
(続)
「中根氏歴世墳墓」染井墓地
夫人の逝去を機に香亭が新たに設けた墓地に、図らずも先逝する一子彪をも埋葬することとなる。
いまは訪れる人も献花台もなく、左下に心ばかりの小菊を供える。
29
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞
中根香亭略年譜 下(明治26~大正5年) 坂田進一編
太陽曆 旧暦 天皇・将軍 年齢(数え) 香亭事蹟と関連事項
1893年癸巳明治26年
55歳1.21毎日新聞連載「尺振八君の伊庭八郎を救ひたる始末」8回。2.8妻時子(西村氏)54歳病没。5月上総・下総を巡る。9月吉田より富士登山し、富士川を下り沼津へ。10.17尺振八の養嗣遠藤秀三郎の結婚披露宴(亀清楼)に出席す。11月下仁田の山際公園「高崎藩戦死諸士の碑」を撰文す。同月明治座、遠山左衛門尉(先代市川左団次)を依田学海と観劇し、詩作を競う。同月金港堂書籍株式会社と改組す。【交友親族】1.1香亭画の師山崎董詮77歳没。5月真鍋豊平より二代目一絃琴全国取締と遺愛の琴を譲られた富田豊春(渓蓮斎)が来訪す。【主要著作・詩作】「都の花」終刊号(通号109)。「上鋸山」、「次韻梁川星巌旧題」、「題鹿野山」、「下鹿野山息野店会地大震器物傾倒」など
1894年甲午明治27年
56歳2.4時子の一周忌を修す。4.17男彪結婚す。9月「沼津兵学校記念碑」撰文。同月「新保正興碑文」を撰文す。10.10妙義山に登り、磯部、金洞山、善光寺、直江津、三条、信濃川下り、川中島、姨捨、屋代、軽井沢、磯部を経て、10.17帰京す。【親族・交友】4.15向島大火で小沢酔園宅と文庫焼失。4.21海軍少佐原田元信(実妹の夫)59歳没。【主要著作】1月「狂歌一斑」、「俳句妄解」前書
1895年乙未明治28年
57歳春、池上行。同春、駒込龍光寺で三宅観瀾の墓参。3.6酔園を訪問、「桃「源遺事」にしこれを与う。8月男彪重い脚気に、新妻も宿痾のため、やむなく合意の上離婚す。【親族・交友】1月飯島虚心新婦を娶る。伴鉄太郎の子捨吉26歳没。【主要著作】『送仮名大概』金港堂刊、「一絃琴私説」稿、一絃琴歌「神鷹」作詞(富田豊春曲)
1896年丙申明治29年
58歳2月堀越愛古より「俳諧或問」、「五文字豆鉄砲」を借り、写しとる。7.23相模行、赤岩親方と会う。宮の下、道了尊、明神岳、最乗寺など、24日帰京。9月豊平の米寿に際し、寿詩を贈る。10月伊勢、京都行。高山にて紅葉、東山、頼山陽の墓参、神苑、伊勢、松坂、本居宣長墓参、二見浦など。11.29国学者会に参加。【親族交友】2.2川田江67歳没。2.5末広鉄腸49歳没。12.12鈴木竹圃(白藤の孫、桃野原の男で、沼津兵学校教授仲間)66歳没。
1897年丁酉明治30年
59歳3月文部省教科書検定に抗議す。春、関根正直来訪。6月正統論発表。8.2黒磯温泉行、7日帰京。10.22磐城平行、土浦、水戸浜、平、湯本、新滝、勿来関、関本、水戸、25日帰京。11.4中根小娥女史37回忌を修す。11.14森田思軒37歳没。11.28男彪、宮永ため(もと美加保艦艦長宮永荘正女)と再婚す。【親族・交友】1.29西周69歳没。8.12向山黄村72歳没。10.14各務恵(香亭生家当時の長女)近藤重三郎と結婚。12.1箕作麟祥52歳没。
1898年戊戌明治31年
60歳2.6外祖父朝川善庵50年祭を孫の片山尚絅(実妹の夫でもある)に代わり執行、祭文を作る。5.12鹿島行。銚子、潮来、筑波、16日帰京。8.11塩原温泉行。校正しつつ帰途古河にて熊沢蕃山の墓参をし、16日帰京。10.22小沢酔園と山陰、北陸行き。京都、丹波、亀岡、福知山、丹後、福知川下り、由雲洞岩清水、天橋立、ロ大野、峰山、久美浜、豊岡、玄武洞、今津、城崎、姫路、敦賀、金沢、山中、福井、米原大垣など、11.4帰京。初冬、海舟から扁額揮毫を恵る。12.8当時横浜在住の富田渓来訪、琴譜の話題におよぶ。【親族・交友】6.26野口幽谷68歳没。10.13中村秋香、香亭の「俳句妄解にそあることば」を浄書す。11.28山口せん(義弟伴鉄太郎の女)
1899年己亥明治32年
61歳2.4亡妻時子7回忌を修す。2.12上野東照宮における旧幕史談会に参加すあるも、荒井郁之助、山田昌邦と三人中座し、西郷像を拝し、鳥八十楼にて鼎談す。3月風邪で寝込む。5月家屋増築す。5.22馬籠村洗足にて海舟の墓参。6.19上総行。一宮、大東崎、泉、東浪見、御宿、勝浦、安房興津、小湊、誕生寺、鯛の浦、鴨川、和田、稲村、北条など、23日帰京。6.20徳弘太舞『清虚堂一絃琴譜』に香亭作詞「後の月」所収さる。7.2上野東照宮旧幕史談会に参加し、鳥羽伏見の戦前後の話ををする。8.8男彪30歳、急逝胃カタル心臓マヒで急逝す。9.17木村架空に師豊平形見の一絃琴を譲る。11.20一絃琴歌「ことほぎ」作詩、豊春曲。12月信濃大沢村「登岳碑」揮毫す。【親族交友】1.21勝海舟77歳没。4.13香亭一絃琴の師真鍋豊平91歳没。9.18宮永荘正(扇三・仙蔵)68歳没、香亭が墓銘を書す。
1900年康子明治33年
62歳4.11稲毛海岸行、14日帰京。4.20飯島虚心、山本鉄杆、乙骨太郎乙小沢
酔園、木村架空ら友がきと、小金井観桜行。6月本郷教育会へ寄付す。このころ秋香より再婚話出るも、易卦により辞退す。8月渋沢栄一還暦祝賀の、高等商業学校卒業生同窓会の祝文を添削す。8月彪の妻ためを宮永家に戻す。【交友】3.8外山正一53歳没。3.11河田貫堂66歳没。4.5関根正直室通子没。このころ金港堂社主原亮三郎、亮一郎と改名す。12.4黒田久孝56歳没。
1901年辛丑明治34年
63歳11月末、熱海および伊東温泉にて療養す。3.22乙骨太郎乙、山本扞とともに六阿弥陀堂参詣行。5.27伊庭想太郎来訪。6月「伊庭物語」を二六新報に連載(13回)7月末、大磯で療養。8月徳川家達より進講依頼あるも辞退す。11月末、熱海および伊東行。【交友】2.3福沢諭吉68歳没し、「福「沢君伝」を作る。2.8外山正一53歳没。6.21伊庭、星亨(52歳)を刺殺す。8.1飯島虚心61歳没。12.9木村芥舟72歳没。【著作】「史伝私議」執筆。玉置環斎に一絃琴歌「ことほぎ」(曲・富田豊春)を呈す。
1902年壬寅明治35年
64歳4.8~同22湯河原で療養す。3月「前句源流」を「文芸界」に連載す。3.20「一橋「学士会」出席。4.8湯河原にて療養す。6.3文部省国語調査会の求「めで「日本文典」、「送仮名大概」を提出す。7月「俳句妄」を「婦人界」に連載(8回)す。11月金港堂など教科書疑獄により、検定制が以後国定制となる。【親族交友】4.7中村秋香、興津中宿に「松の下庵」を構える。4.19伊庭想太郎無期徒(ず)役と決す。8.7伴鉄太郎74歳没。【著作】1月「伊庭氏世伝」
1903年癸卯明治36年
65歳この年香亭、世事諸役をすべて辞す。6.5駒込曙町宅を西村氏に寄託す。16~8月興津、静岡、三保、秋葉山、二俣、井伊谷、豊橋名古屋(島村家)、美濃桐洞、飛騨、船津小坂、久々野、七尾、和倉、金沢、永平寺(7.16~27)滋賀(藤樹書院)、長浜、養老、内宮、矢矧川、鳳来寺、牛窪、沼津などを周遊し、8月曙町に戻る。10月房総周遊。10~11月奥羽行脚へ。宇都宮白河、福島(各務家)、板谷峠、米沢、上山、鶴脛、山形、最上川、大石田、松嶺(土方家)、酒田(本間家)、平沢、岬峠、象潟秋田、八郎潟、弘前、津軽、盛岡青森、中尊寺、厳美渓、松島、仙台、郡山、会津若松、津川、阿賀野川新潟渋、草津、浅間、沓掛磯部、11.28帰京。12月伊豆、沼津行、興津にて越年。【親族・交友】彪のもと妻、宮永ため再婚す。
1904年甲辰明治37年
66歳1月沼津、箱根、十国峠、2.16帰京。3月西国行、興津、名古屋、月ヶ瀬、奈良、三輪、初瀬、畝傍山、有馬、高野山、芳野山(如意輪寺・徳定上人)、根来寺、大阪、大津、京都、須磨(新保家)、因幡山、米子(杵村家)、松江(片山家)、玉造、出雲大社、石州、大森、浜田、下関、門司、中津、5.2別府、28耶馬渓、日田、筑後川、吉井、久留米、熊本、八代、水俣、大口、鹿児島、宮崎、人吉、球磨川、田原坂、長崎、唐津、佐賀、太宰府、博多、小倉、宮島、尾道、道後、松山、千原岳、西条、多度津、琴平、高松、小豆島、岡山、津山、大阪、名古屋(島村家)、6.5帰京。○7.28各務家実母50年祭執行。7月中山道行、浅間、諏訪、鵞湖、木曾、美濃、多治見、伊勢、松阪、豊田村、岩内、伊賀四十八滝、名古屋(島村家)、8.2帰京。12月興津保養館にて越年。
1905年乙巳明治38年
67歳1.15興津にて自画像に賛し、西村に送り帰京す。3月インフルエンザ罹患、4月下旬快癒す。5月信濃関西行、甲府、長野、名古屋、越前若狭小浜、舞鶴、丹波篠山、京都、大徳寺、大和、伊賀、笠置、四十八滝、6.23帰京。6月塚越停春の「有髪比丘根香」【親族・交友】4.13田口鼎軒51歳没。4.14鳥尾得庵59歳没。6月塚越停春編「有髪比丘根香」、「明治逸士伝」中に新聞連載さる。7.16奥羽行、山形、米沢、赤湯、山寺、立石寺、湯殿山、月山、新庄羽黒山松嶺(土方家)、酒田(本間家約一ヶ月間)、鶴岡、田川、温海、海府浦瀬新潟、佐渡、長岡、妙高山、信濃、南佐久(木内家)、海野口、野辺山韮崎八王子、9.2帰京。12.6相模行、ついで伊豆修善寺にて越年す。【主要著作】『行脚非詩集』4月私家版
1906年丙午明治39年
68歳1月修善寺、吉奈、湯ガ島、河津、蓮台寺、下田、松崎、沼津を巡る。2.8興津、静岡、柴屋寺、森町、三河、3.2帰京。4月「真鍋蓁斎伝」執筆。4.13紀伊行、鎌倉、興津、名古屋、奈良、吉野、如意輪堂、京都嵐山、摂津、和歌山南紀勝浦、橋杭岩、根来寺、那智、、熊野川、新宮、伊勢、4月末帰京。8.2北海道行、仙台、盛岡、青森、函館、小樽、札幌、旭川、宗谷、名寄、室蘭、函館青森浅虫、大鰐、秋田、横手、山形、9.15帰京。12月南伊豆行、天城、沼津、興津にて秋香と合流。【交友】4.15岸上質軒「明治畸人伝」中「中根香亭先生」掲載す。9.4木村信卿67歳没。
1907年丁未明治40年
69歳1月興津の東海ホテル、十文字屋に滞在。2.1秋香の見送りにて興津から帰京す。2月風邪にて一週間寝込む。3月上野博覧会観賞。5.4九州行、吉備路、尾道、先光寺、錦帯橋、鶴見岳、竹田、豊肥道、阿蘇山、博多、小倉(島村家)、京都、神戸、6月帰京。8月房総行、塩田浦など。9月秩父行、野火止平林寺逗留。10月岡崎春石より「漢書」を借り読破す。12.27伊豆伊東にて越年す。【親族・交友】1.17森川恭子(実妹しが子長女)没。10.31伊庭想太郎小菅監獄にて57歳没。【主要著作・作詩】「読漢書」、「読後漢書」
1908年戊申明治41年
70歳1月熱海小林屋に移る。1.20秋香の誘いで日金峠を越え、興津の岡屋に逗留す。2.28松の下庵を訪う。3.1午前帰京。5.3上野国行、館林、足利、黒羽、那須、高崎達磨寺など、20日帰京。12.21秋香と興津へ、十文字屋にて越年す。【交友】4.27「賢歌愚評」に秋香が後書す。7.2秋香夫人清子没。【主要著作・作詩】『歌謡字数考』、「弔佐藤博士」
1909年己酉明治42年
71歳1月興津逗留中、静岡、掛川に出向く。1月秋香の男春二(成蹊大学創立者)とともに帰京す。2.14亡妻17回忌を修す。2月風邪で伏す。酒田、本間光弥来訪す。12.5興津十文字屋へ。○秋香の斡旋で、伏見直太郎の家作を借りる。【親族・交友】1.3乗竹孝太郎50歳没。2.11鈴木唯一65歳没。4.21西村熊二31歳没。6月西村家一時断絶。9.30中井敬所79歳没。11月末、秋香松の下庵へ。11.27依田学海77歳没。12.16矢吹秀一58歳没。12.19谷干城夫人玖満子66歳没、墓碑銘を書す。
1910年庚戌明治43年
72歳1.17秋香病床に臥し、これを毎日見舞う。1.28秋香が没し、諸事周旋、秋香の遺言により翌日興津海辺にて荼毘に付す。2.2上京、翌3日駒込吉祥寺にて秋香の葬儀に参列。2.13養父中根氏の50回忌を執行2.14興津に戻る。3月随筆「酔酩余録」、「零砕雑筆」整理。5月奥羽行、酒田本間家に逗留、家宰土方家、横手、黒沢尻、足利を経て6月末興津着。8月佐久木内家三氏の墓誌名をものす。10月東京へ。11.5法事執行。11月小笠原長生に硯を贈呈す。11.8鎌倉経由で沼津へ。9日、沼津耕雲寺で墓参し、興津へ。11月一節切(尺八)を再習す。同月木村架空来訪。【親族交友】1.28秋香70歳没。2.5乙骨太郎乙夫人継59歳没。3.29小杉温邨77歳没。10.24山田美妙43歳没。11.8島村千雄55歳没。【主要著作・詩作】「六明庵記」、「水さし桶の記」、「晩香書屋記」、「祭幕末三烈士文」、「題「莫雲卿書帖」、「書藏真帖」、「書東壁硯」など
1911年辛亥明治44年
73歳1.1外川残花「日本及日本人」に香亭小伝発表。1.5酒田本間光輝来訪。1月乙骨太郎乙来泊。2月木村架空来泊。4月土方恕平来泊。3.16皇后陛下の興津行幸に際し七絶を賦す。5.26朝日新聞記者上田芳草編「一絃「琴」に香亭の序文を請う。6月初、東京にて亡男彪の13回忌を行い、8日各務、片山両家を訪う。8月架空とともに一絃琴資料を模索研究す。11.18成瀬隆三夫妻来訪。11月最上徳内の墓誌銘(駒込蓮光寺)を撰す。冬、架空来訪。【親族・交友】1.25秋香遺文集「不尽迺舎遺稿」中村春二編公刊。【主要著作・詩作】冬、「興津十詠」
1912年壬子明治45年7月30日大正改元 7月30日明治天皇歿
74歳1.10島田三郎来訪、翌11日ともに静岡に。1月中村春二来訪。2.3流感にて9日間食せず、18日平食に復す。3.10土方恕平見舞に来訪。3月末から4.4志田温泉にて療養(指の痙攣)。4月見舞客多く、各務義長、島田三郎一家、乙骨太郎乙、木村架空など、この間詩稿整理す。◎大正元年11.16沼津行。11.29駒込西村家人看護のため翌2年1.21まで滞留す。【親族・交友】2.14片山尚絅76歳没。
1913年癸丑大正2年
75歳1.8吉野の井上徳定上人へ永別の辞を代筆にて呈す。1.14この日より食せず。この間見舞うもの、土方、西村、島田、島村小笠原、乙骨、由比、成
瀬、杵村、木村など。門人伏見道太郎をして「香亭自叙伝」を口授筆記せ・しむ。1.18小笠原子爵見舞。1.20香亭75歳胃癌にて没す。翌21日、遺言により興津中宿の松原にて荼毘に付す。22日、三保松原沖にて風葬す。2.23中宿小松原にて35日年会。3.3沼津市大火で市役所焼失、よって中根家戸籍烏有に帰す。【主要遺作】『香亭蔵草』2月大日本図書刊(酒田本間
【主要遺作】『香亭蔵草』家出資)
1916年丙辰大正5年
没後3年【主要遺作】『香亭遺文』(新保常磐次編)
32
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第144話
高士中根香亭先生 卅五 小笠原長生 中
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
重言である。香亭の愛情やまぬ金杉村の草盧「迷花書室」と荘園五十畝(約一千五百坪)の約四分の一が、現「台東区立書道博物館」の敷地で、いまも博物館庭先から垣間見える噺家宅や旧御隠殿の一部も含まれる。
しかし、明治十六(一八八三)年七月の日本鉄道開設前後に伴う人家の増加などで、一帯が漸々喧騒の地となるを嫌った香亭が、やむなく書斎と荘園を正式に手放したのが明治二十三年六月のこと、駒込曙町の家新築なるまで、しばしは同じ金杉の御行松傍らの借家住まいとなる。
すでに香亭の去った明治二十五(一八九二)年の二月、旧迷花書室対面に駒込追分から転宅してきた正岡子規があり、前年に東京帝大の哲学から国文へ転科、さらに六月の学年試験に落ちたことで決意し退学。年末には日本新聞社に入社、翌年二月に二三軒先に移住、三月には中根岸在の洋画家中村不折(一八六六~一九四三)と知り合っている。
不折は東西の古典ばかりか書や雑俳にも造詣深く、湯島から中根岸に移り住んだが、かねがね名士香亭の人となりを聞き、旧迷花書室を垣間みもしつつ子規庵に出入りする。
後に三ヶ年の欧州行帰国後の大正四(一九一五)年、諸経緯を知った上で、幸い、まだ三百五十坪ほど遺っていた上根岸の香亭旧盧を居宅とアトリエ用に購入、先主香亭を偲ぶ意から、迷花書室だけは壊さずに利用し、その他は改装したのである。
関東大震災を経て、さらなる和漢書道蒐集品の増加にともない、昭和十一年(一九三六)十一月三日、居宅に隣接して「書道博物館」を創設。これを開放して歴史的重要な書法資料を展示。昭和十八年六月六日、七十八歳で没し、二代館長を男丙午郎(一九〇九~一九九〇)が継ぐが、
惜しくも昭和二十(一九四五)年四月の東京大空襲で居室と蔵は全焼、ここに香亭縁の書斎は烏有に帰す。
筆者学生のころはしばしば台の下を散策がてら、古い書道博物館を見学したりしたが、浅学でそこまでの詳しいことには気づかずにいた。
二代館長没後の平成初め、三代中村初子が苦心運営するも、諸般の事情から資料と博物館の売却話が興り、ひとしきり世の話題となったがいずれもまとまらず、最終的には台東区に寄贈ということで決着した。
さらに前号から続く香亭門人小笠原長生(ながなり)の語る奇しき物語が、これらの伏線となり、ここに「高士中根香亭先生」連載冒頭にたち還り、楽事および小伝一応の完結へと向う。
少年期香亭膝下にあった長生。塾と数校を経て明治十三(一八八〇)年、数え十四歳で学習院に入学。かつて幕閣重鎮にあった父長行(ながみち)が、勝海舟を抜擢庇護し海軍の充実を図ったごとく、夙に日本の将来に海軍の必要性を少年長生に言い聞かせていたし、長くもまた同じ思いの明治天皇は、同十五(一八八二)年、「華族の子弟は努めて軍籍に入るべし」との聖慮を下したため、いつしか長生も海軍兵学校を希望し、近い将来成人の後は、海軍軍人たるべく奉公したいと希うようになっていた。
後に長生は語る。(改行傍線ルビ筆者)
ある時(昭和七年頃)のことであつた。一日、中村不折画伯が尋ねて(長生を)来られて
「今般明治神宮壁画館に日本海々戦を描くことになり、既に略完成したから一遍御覧下すって、忌憚ない御批評を仰ぎたい」
との懇望であつた。
仍(そこ)で三日後に往訪する旨を告げ、約束の日に根岸なる同画伯の邸に往つて見て驚いた。と云ふのは其の邸が香亭中根淑先生の旧盧で、然も通された室は私が十三歳より六年間、毎土曜日の晩四谷の塾から伺つて経書の講義を聴き、文章を訂正して戴いた所で、坐に其の当時の事が偲ばれ、沁々先生が懐かしくなった。
仍で其の訳を不折画伯に話したところ、画伯も微笑をして
「実は私が此処を手に入れました当時、香亭先生のお住居であつたことを承知してましたので、名士の遺物を保存する考から、此の室だけはそつくり其の侭に残し、他の部分を改装したのです」
と答へられたので、私は、画伯の心懸けが何とも言へず嬉しく、改めて感謝の意を表した。
滅多に他に許さぬ杉浦重剛氏が、稀有の高士と折紙を附けた通り、中根先生は高潔清雅真に璧の如き性格の所有主であった。私は各階級の種々な人物を知つてゐるが、高士と云ふ点に於ては先生に及ぶ者を見た事が無い。亡父は其処を見込んだものか、私が十三歳になった際自身先生の盧を訪うて、懇に私の教育を委託した。尤も亡父は先生の外祖父に当る朝川善庵翁に教を受けた関係もあったからである。併し先生は容易に承諾されないで斯う云はれたさうだ。
「手前も以前沼津に居りました時分は、沢山内弟子も置きましたが、御覧の通り只今は世捨人同然で、門弟を取ることなど思ひもよりませぬ。それに近頃の書生は求道の念が薄く育て栄も致しませねば、旁(かたがた)固く御辞退仕ります。御賢息様は伊庭想太郎の塾(伊庭塾文友館)においでなさると承りましたが、伊庭は手前の門人で人物も確りしてをりますれば、それで充分かと存じます」
と容易に承諾の様子がなかったが、先考の熱心に動かされて
「では斯様に願ひませう。御教授申すは土曜の晩だけとし、御賢息がおいでになる節は什麼(どんな)天気であらうと決して乗物に乗られず、徒歩でお通ひになりたい。道を求むるにそれ位の覚悟が無いやうでは、いくら経書を御勉強になつても何の役にも立ちませぬ。それを御承知下さいますか」
かくして長生の入門はようやく許されることとなったのである。
其の中根先生の講義を聴くために根岸の中根先生の許に通った。
四谷から根岸までは相当の道程であるが夫(それ)をテクテクと歩いてゆかされた。中根さんの家から四谷の文友館へ帰るのには芋坂から谷中に出て帰るのだが、その芋坂だつて当時は坂下に団子屋が一軒あつたばかりで極めてさみしい所であつて、ある晩十時頃私が谷中の墓地まで帰ると遠くの方に気味悪い灯がちらちらと見えてゐた。近寄つて見るとそれは新仏の灯であつたが、さうした新仏の灯が所々にちらくしてゐる時は実に気味が悪かった。
ある年の冬だった。而も其の日は大雪であつて根岸から四谷へ帰るのは容易でなかつた。それでも私は歩いて帰らされた。私の小さい足はザクザクと雪の中に埋もれるやうに喰入った。皮膚が赤く凍てるやうだった。漸つと水道橋の所まで帰った時、下駄の鼻緒がぷっつり切れた。仕方がないので私は袴の股立をとり跣足になり、下駄を袴の腰板の所へぶらさげて駆けつた。すると丁度父が二人曳の俥で帰って来るのにぶつかった。家は番町にあったが、其の日は父は駒込の別邸に帰る所であった。
父は私の異様な風態を見下すと車を停めて
―何うしたのか其の風態は―
とたづねた。私は
―唯今中根先生から四谷に帰る所なんです。途中下駄の鼻緒が切れたので斯うして帰ってゐる所なんです。
―と答へた。
父は―さうか―と頷いた。
父の俥は駒込の別邸の方に向かず根岸の方に向けられた。後で聞いた話だが、父は別邸には帰らず直に根岸の中根先生方へ行って
―こんな大雪の日、よくも思ひ切つて歩かせ帰して下すった。私は其の礼に来た―
と云つて心から中根氏に感謝したと云ふ事である。
長行と香亭は立場こそ違え、明治を生きた旧幕臣同士、その面目躍如たる心意気を伝う佳話であろう。
(続)
少年期の「小笠原長生小照」
明治10(1877)年
13歳から香亭門に通う以前、ちょうど11歳ころのものである。
塩原温泉「七絃瀧」 2014年3月9日
該葉は今号副題とは関わりないが、本連載134「塩原懐古」で、古琴に因む「七絃瀧」なるものを見せたいばかり、上海音楽学院で東西古楽を学ぶ面々を誘ったときのものである。
その確たる典拠は定かでないが、瀧はどうやら奥蘭田が紹介する以前からの名所で、瀑布を壁上に懸けた「琴」七絲に見立てた筋が、山間の春いまだ浅く、左に三、四条見える。
21
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第145話
高士中根香亭先生 卅六 小笠原長生 下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
古の文人に倣い、花を愛でつつ晴耕雨読の生活に憧れ、ようやく念願かない迷花書室を終の窯とするはずの香亭。だが案に相違し、却って文明開化の華咲き爛れゆく東京、否、現世に彼の安住の地はなく、駒込そして興津から全国を転々と行脚した。
さあ小笠原長生の述懐にもどろう。
田口卯吉博士、島田三郎氏、伊庭想太郎氏等は皆其の(香亭)門下生である。そうして私が最後の弟子であつた。
私は先生が興津の客舎に病まれて後屢(しばしば)お見舞し、最後は亡くなられる前二日前であったが、先生は微笑を含んで斯く言はれた。
「医者は昨日あたりもう不起(いけな)いと宣告したが、まだ一両日は保つと思ふよ。併しまァ其麼(そんな)ことは何方でも可いが、貴君は今艦長(最新)と云ふ大切な職務を有つてをらるのだから、さう度々来て下さらんでもいゝよ。男と言ふものは道義の為めには泣くべきだが、生死には須く大観して未練らしく泣かぬ方が可いね。だから今日は一つ愉快な談話をして別れようじゃァ無いか」
「面白いですな、やりませう。併し先生お飽きになったらさう被仰つて下さい」
「あァ言ひますとも、そんな心配をされずに、お得意の日蓮論でもおやんなさい。禅天魔位では参らないね。あれは禅に取っては寧ろ攻撃では無くて訓戒なので、禅に徹した者は什麼(どんな)に歓迎するか判らないよ」
相変らず垢抜のした名論が、静に静に説き出された。
私は恰も沙羅林に於ける釈尊最後の説法を聴聞する羅漢の思で、謹聴すること二時間に及んだが、唯々有難く聴きなされ、瀕死の人と対談してゐるやうな淋しい観念など微塵も起らず、何とも言へぬ安らかな気持―と云ったら済まないかも知れぬが実際さうであつた―になってお別れした。
それから二日経つと先生は、集つて(ゐ)る親戚等に向ひ
「今日は愈々逝くことになった」
と、奇麗に体を拭き浄めさせ、床上結跏趺坐して経文を誦しつゝ、光を放たん許りの寂滅を取られたのである。
扨想ひ出の書翰として此処に掲げるのは明治三十五年軍艦浅間に乗組んで、英国皇帝の戴冠式に参列し、帰朝すると直ぐに軍艦千代田の副長に補せられて北清警備の任務に就き、続いて日露戦役中は、大本営海軍幕僚を抑付つて軍務に掌してゐたので、知りつゝも先生に対し無音に打過ぎたのである。
所が三十九年になると、やつと戦役の後始末もついたので、其の歳二月久々で先生を本郷曙町の寓居―元は御自分の邸であったのをうるさいからとて、時々旅行から帰った時は厄介になると云ふ約束で親戚(西村すなわち亡妻の兄弟)に遣られた場所―にお尋ねした。
先生は固より無欲恬淡の方であるから、切(せめ)てはお口に合ふものでもと、色々考へた末、邸内(長生邸)の竹藪から走りの筍子(たけのこ)を探し、それを持参したのである。
所が折悪しく先生は旅行中であったので、之を親戚の人に託して辞し去った。すると間もなく先生は帰京せられ、さうして私の訪問当時不在であった事を深く遺憾とし、病を推して一書を寄せられたが、場合が場合である丈、文意に一人の温さが籠り、懐みを喚起させずには描かないものである。
以下香亭原文のまま(内筆者)
拝啓本年は今日に至る迄雨雪雑至加ふるに悪風吹き荒み従つて春寒厳しく候処倍御健安御起居至祝是事に御座候老夫も先以頑健過光罷在候扨過日は旧盧へ御駕下候ひし由老夫不在にて拝儀を得ず遺憾の至りなり定めて薄々は御承知の事と奉存候が老夫先年家を捨て諸国を遊歴致し居り京城(東京)に居ることは極めて稀にして旧麟も相州に赴き新年になり豆州より駿遠を経巡り去る二日一先づ帰寓仕り候直に一筆差上べき処途中より感冒にて昨日まで打臥し居り心ならず其侭打過ぎ候ひき御来過の節恵まれたる御新著二種枕上にて拝読談片は既に已に読了り方今権力史の半分程まで看過致し候猶其節拝戴の新筍は甚だ珍しければ同棲の者土を覆ひ置き帰寓後早々調理致しくれ賞味仕候処芳脆少しも減ず銘感の至り依て長編(五言古詩)一首を作り候間此際奉供尊電候春光り未だ和暢に至らず国の為尊体御自衛尤も祈る所也
匆々不備
三月八日 淑
小笠原賢台
侍右
二啓老夫遊歴後の詩作年上刊致し候に付一本呈上仕候御閑暇のをり御垂覧奉希候
伊庭氏内子此程病死の由(訃)音到来せしかど老子就蓐中にて何分会葬致しかね残念に存候誠に気のどくなる事に御座候枕頭執筆書字謹まず御判読田奉希候
(以下別紙にて原書漢文)
丙午二月小笠原長生吾寓を過ぎ、新筍数根を恵まる、蓋し雪中劚する所なり時に余旅泊中にあり、
之を知らず、数日の後、偶寓に還り、烹て之を食ふ、芳美頬に溢る。長篇一首を作り以て喜謝す
「時已に春節に入るも
天猶城雪を降らす
旧盧主人あらず
久く客蹤絶ゆ
乍ち門を敲く者あり
風采頗る高雅
自ら言ふ予は笠某
春笋座下に呈すと
識らず主人の家を舎てゝ
湖海の間に放浪するを
識らず主人の雲遊
千里去って還らざるを
曩時国家大兵を興す
聞く卿槊を横へて御営に待し
朝電暮牘画策に忙しと
指を屈すれば三年卿を見ず
卿昨我を訪ひしに我あらず
我偶帰来つて深く怨悔す
幸に嘉貺尚鮮新及り
籃を開けば
龍孫矗として彩を放つ
烹飪箸を下せば香鼻を働き
雪中胎む所果して異あり
予已に之を食うて心愈虚に
全然利を忘れ兼ねて義を忘る
但卿は予と隠顕を殊にし
身は華冑に在って職は軍に在り
願ふ所は林を尽して其服に充て
直節挺々
此君の如くならんことを」
読返す毎に感慨無量!
いざここに至り愚稿を通読すれば、何やかやと疎漏の多きに気づくが、また連載中に訂正の機会もあろうか。
次なる秋香次男坊中村春二の想い出で、いったん香亭先生と離れよう。
夜、興津の松林で先生の遺骸は焼かれた。恰度自分の父(秋香)の遺骸をやいたのと同じ処、~ああそれも今事実となって二老は同じところで荼毘の煙と消えてしまった。そして先生は戒名もつけず、骨は海に流して何も留めない様にとの遺言であつたとやら、月の夜とはいひながら雲幾重にもかさなり、波の音は近く鞺々(とうとう)と岸をかむさむい夜である。葉に覆はれた先生の遺骸は近親の者の口火よりして遂に赤い炎につつまれてしまった。その深奥なる学識と終とは忽ち焔と消えはててしまうのであった。
「香亭先生火化之処」
大正2年(1913)年2月
左方松林の奥で土俗的な設えで荼毘に付さんとする刹那のもう一葉が遣り、富士山を望む正面石の多い浜がそれでないことが解るのだが、そこには少数の友人と近隣の村民、さらに懐いていた子供たちが集い、いかにも純朴な民から慕われつつ逝った、村夫子
然とした香亭の人柄が偲ばれる。
「桃源郷図」中根香亭画
明治42(1909)年夏日
香亭の求めて求めえなかった理想郷。これを五柳先生の「桃源郷」と重ね、仮の宿とし終の翼ともなった興津で描いた香亭渾身の筆致である。画讃の五絶は『香亭蔵草』にも所収される。
寒斎蔵の該山水をもって飾り、止めの記念とする所以である。
桃源図
桃源避暴秦 千載不通津
一旦溪澗水 誤牽饒舌人
15 △目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第146話
東皐心越禅師と琴(きん) 一
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
この四月半ば、東都池之端湖畔に散る桜花を惜しみながら、その余香に浸りかつ琴韻に酔いつつ、羽田から上海虹橋へ渡ったと思われたい。
数月後には、わが積年の念願である『東皐琴譜正本』中国語版が上海音楽出版社から出版される予定で、四十数年間の結晶が中国琴界に提供されんとしているからである。
ころしも拙稿は「高士中根香亭先生」三年越し長丁場の連載を了えたところ。ここにまたぞろ話は長くなろうが、筆の向くまま気の向くまま、本誌愛読者諸賢に不可欠な「藝の糧」たる「君子四藝」(篆刻を数えれば五藝)、「琴碁書画」中の楽事近辺の散策にご同道願おうとする。
四藝第一等に掲げられる琴について、本邦琴学中興の祖と崇められる東皐心越禪師(一六三九~一六九五)を核にし、さて、具体的にどんなもの、如何なる背景があり、しかして士人の胸中に如何ように存在する(した)か等々、気分一新、そこいらをご紹介しつつ、各自自得していただけばと思う矢先、計らずも本誌に「本邦江戸期篆書篆刻考・心越ゆかりの寺を歩く」なる東皐心越禅師(巷間、略して東皐禅師とも心越禅師ともいうが、本稿では越師とさらに略す。中国曹洞宗第三十五世正宗で日本曹洞宗寿昌派祖)の「篆刻・篆書」について、畏友松村一徳氏による連載が掲載されはじめたではないか。無論、これを天佑の好機とすることに吝かでない。
禅者ながら琴癖をもつ越師であった。しかもその東渡に際し、従僧任せの船荷とはいえ、十余面(張とも)ほど携帯した琴はすべて古琴(美術的骨董的価値が高く貴重な古い琴で、名琴の意も含む)で、現代中国語の新琴をも含めて総称する古琴とは異なるのだ。これに明版および清初版の「琴譜」数種を携行してきたほどの、並々ならぬ「琴痴」なのである。
琴曇琴郭で包まれ、さらに長さ一メートル三十センチ、巾二十五センチ、深さ二十センチほどの木製の琴匣により保護された古琴は、一面分の携帯だけでかなりの負荷で、一説に貿易唐船の半分以上が越師の積荷であったといわれるほどであるし、これに加えて仏具・仏典・書籍・文房具・日常の生活用品・諸々の道具類などを想像していただけば、それがいかに大変な量か、容易にご了解なされようものである。
こうした一事からも力説せねばならぬのは、従来、越師をして「ただの唐人帰化僧」、「一介の風流僧」などと、頭陀袋一つを抱え、命からがら我が国に逃れきた軽輩亡命僧であると捉えられてきたことは、まったくの誤解であることである。
そんな越師について深く踏み込む前に、特筆せねばならぬのは、当時の中国にあっては、儒・仏・道の各界求道者は、士人の嗜む君子四藝を各道修行の妨げとはせず、士大夫然として「琴禅一如」、「琴剣一如」どと称し、儒に限定せず、「静座」、「練丹」などの実践とともに、却って琴を学ぶことが行われていたということである。
長崎上陸当初、海外の知音といわしめた何可遠(すでに一六六八年九月、唐小通事御役御免)との琴事を禅余の慰めとしていた越師であったが、翌年九月、興福禅寺にて道元禅師の語録『永平広録』や、根源同一の日本曹洞宗の規範『永平大清規』などを閲し、
…三嘆日、而今水乳喜同調、
とまで驚喜したものの、豈計らん、「清規」では、明確に音曲を厳禁していることをはじめて知るのである。
『永平大清規』中の「吉祥山永平寺衆寮箴規」を引用すれば、
寮中不可談話世間事。名利事。国土之治乱。供衆之矗(粗)細。是名無義語。無益語・雑穢語。無慚愧語。固制止之……
寮中不可置俗典。及天文地理之書。凡外道之経論。詩賦和歌等巻軸。…
寮中不可置管鉉之具。舞楽之器。
とあり、その傍証には、
供養三宝之外ノ笛類琴瑟之類
などと、世俗や名利、国事などを話題にすることはもとより、僧侶間でも口の端にのせる言葉は、後で自らに後悔せぬものを選ぶよう固く戒めているが、さらには仏典以外の経書や詩文を方丈に所蔵して閲覧したり、歌舞そのものを嗜むことをも禁じているではないか。またその頭註には、
管者簫笛之類、絃琴瑟之類也。管舷之具舞楽之器、僧家畢竟為無用之長物、宜禁之、故日不可置也。
とまで、梵唄以外の歌舞音曲、具体的に琴やら瑟などを名指しで禁じているからして、待査を要するが、心底、道元との共感を公言した越師で
はあるものの、日中禅宗規範の異なりに悩んだ(もとより記録せず)すえ、琴事を含めた楽事を表面上は封印せざるをえなかったことになる。
帰国の意志を捨て、背水の陣で長く錫駐し、日本で骨を埋める固い決意で東渡してきた越師である。ならばと日本の宗風に染まるべく、他派禅宗の清規をも参考にふまえて自らの禁則大綱の規範とし、なによりも、向後日本に滞留錫駐するについては、本来の仏事を等閑にしてまで琴事を表面上に出すべきものではないと、自覚自重した上で、越師は日常起居にも十二分に留意したであろうし、はたまた徳川覇府の国禁を破ってまで異国の僧を庇護し、引き取ってくれた恩人徳川光圀公の手前、中国仏教界ではしごく当たり前であった楽事を、心の奥に秘した結果である。かかるがゆえ、日本の内政規範にやや習熟した上で、他の眼の届(きにくい)かぬ水戸藩邸内後楽園の小庵で、たっての願いをうけ、やむなくごくごく内密裡に教えた幕府儒官の人見竹洞(一六三八~一六九六。名は節、字宜卿、通称友元、別号鶴山)と麾下の士八千石の大身杉浦琴川(一六七一~一七一一。初名春生、後正職、号琴川)両人との尺牘や詩文応酬以外に、具体的な琴事を書残さず、また、あえて記録もしなかったのでは、というのが筆者の重要な観点であり、あれほどの琴癖をもった越師自らは琴事を故意に語りもせず、また記録もしなかった証左とする所以である。
以下は、越師以前の琴の本邦への伝来についての簡紹となる。末から唐代にかけ他の雅楽器とともに朝鮮半島を経由し、また、遣隋・遣唐使などによって奈良朝に我が国に琴および琴書が齎せられた、というのが定説である。この伝が平安朝末期、そう、『源氏物語』が成書したころには、琴は廃れていたとされる。
これに先立ち、平安貴族の教養である「詩歌管絃」は、すでに彼等の生活と深く密着したものとなっていて、逆に、これを中心として日常があったと極論することもできようほどのものである。
わが承和年間(八三四~八四八)以降に伝書した『白氏文集』(元槇編、後に白氏自ら編纂)が、貴族間に愛読されることが流行したことから、村上天皇の第七皇子具平親王(九六四~一〇〇九)は、我が朝の詞人才子、白氏文集を以て規範と為す。故に承和以来、詩を言う者、皆な体裁を失わず。
(『本朝麗藻』巻下)
と自注したほど、実際にこの文集は当時の教養人たるもの必須の読み物となっていた。
【上】『東皐琴譜正本』
坂田進一編2001年9月刊
右が『東皐琴譜正本』で、左の三本(他にもある)も『東皐琴譜』ながら、すべて後の異版と抄写本になる。
【下】「放琴案上図」『琴学入門』より
大江玄圃編1787年刊
享保年間、越師三伝の小野田東川(1684~1763)がはじめて帷を下し、以後心越派(流とも)の琴は江戸の市井に広まり主流となる。
東川門下の清隠翁(峡中老人)に学び、五伝となる大江玄圃(1729~1794)は、通称を久川靱負、名は資衡、字を穉圭、時習堂と号した京師の儒者である。
図は心越流正式な弾琴儀を伝える貴重なもので、琴客は鶴警衣(琴服とも)を着用の上、かく席を設えて弾琴したのである。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第147話
東皐心越禅師と琴(きん) 二
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
聰幽蘭 白居易
琴中古曲是幽蘭
為我殷勤更弄看
欲得身心俱静好
自弹不及聽人彈
かく琴癖をもった白楽天(七七二~八四六)の詠うごと、こうした密やかかつ繊細微妙な思想にあやかった本朝のわがやんごとなき公達女房連の間にも、教養の一環として琴を学ぶことが流行したが、時の経過と次掲の事由で徐々に衰退し、惜しいことに、やがてその伝承はいつしか途絶えてしまい、結果的には東皐心越禅師の東渡以降の再伝を待つことになる。
まず第一に、管絃、すなわち雅楽全天候型の合奏中における琴は、音量が非常に小さいことから、通常は二管編成(竹は龍笛が二、篳篥が二、笙も二で、他の絃楽器もこれに准ずる。また大合奏であればこれが四管編成などになる)である場合、琴のみは複数以上、例えば五~十面ほども楽人を要せねばならず、いかにもアンバランスであること。
第二には、琴は難易度が高く、習得に時間がかかり不便であったことなどから、伝来当初から敬遠されだし、比較的早期に管絃合奏から離脱してしまい、かろうじて私的な独奏や他の絃楽器、すなわち箏と琵琶などの絃楽器のみ、しかも書院における小さな合奏などに生き残っていたが、しかしこれも徐々に廃れていく、というのが実情であったのである。
こうした我が国神代から平安朝までの「琴の盛衰」経過数例を、浦上玉堂は古籍から取捨し、自著『玉堂雑記』中に的確に挙げ指摘している。
これを引用してみよう。
○琴(キン)は唐(カラ)にあり。皇国(ミクニ)にあれど其弾法ひさしく絶たり。皇国箏(ミクニコト)は。唐のの遺製ならん歟。
古書にきんのこと。さうのことと云。
凡(スペテ)古登(コト)といへば。糸(イト)ものゝ惣名か。
残夜抄に。琴のこと絶たりといへり。神代に。大国主神(クニヌシノカミ)。天詔琴(ゴト)とりもち給ひしと云々。のりこととは。みことのりと云意(ココロ)にて。神をいのり。神ノ乗りうつり給ふとやらん云ふ。
仲哀天皇。筑紫(ツクシ)の香椎(カシヒ)の宮に座(イマ)して。熊襲の国をうち給はむとせし時。天皇御琴(ミコト)をひかせ給ひて。建内宿祢(タケウチノスクネ)座(ザ)にあり。神のみことをこひまつりし。宿祢(スクネ)曰。我ガ天皇猶その大御琴(ミコト)をあそばせ。琴ひくをあそびといふ。
神楽(カグラ)を神あそびといひ。楽(ガク)をなすをあそびす。又は琴(コト)笛のあそびなといふこれ也。
雄略天皇。吉野の宮に座して。御琴(ミコト)をひき給ひて。童女(ヲトメ)よく舞へるによりて。御歌(ミウタ)よみて給へり。
又清御原天皇。時も同じく御製あり。五節の舞の初とぞ。
ヿ乙女こが 乙女さびすもから玉を 袂(タモト)にまきて 乙女さびすも。
仁賢天皇。播磨国久米郡小楯(ヲダテ)かもとに座(イマ)して。室寿(ムロホギ)し給へる御詞(ミコトハ)に。八絃の琴をしらぶるとて。
ヿ奈々川乎乃(ナナツヲノ)。也川乎乃古止乎(ヤツヲノコトヲ)。之良部太留(シラベタル)。と云々。
唐(カラ)にも琴(キン)は五絃七絃九絃あり。
…略…
○ 応神天皇三十一年。枯野(カシノ)(伊豆国軽野とも)の舩朽廃(フネクチスタレ)。詔(ミコトノリ)して船材(センザイ)を取(ト)らしめて。薪として。塩を焼しめ。清香薫(カン)ハばしく。焱(焼)ざることを奇として。献じけれは。天皇琴に作らしめ給ひ。その音鏗鏘(サヤケク)遠く聞けり。其遺残木は。海人(アマ)のたきさしとなづけ。御蔵(ミクラ)の宝となれりとそ。
〇万葉集五。贈梧桐日本琴於中衛大将藤卿 并に歌二首。大伴ノ淡夢に(此)琴化娘子日。
秋月※【大伴旅人が藤原房前に日本琴を贈る】
余託根遥嶋之崇岳。晞幹九陽之休光。
長帶姻霞逍。遥山川之阿。遠望風波。出入鴈木之間。
唯恐百年之後。空朽溝壑。
偶遭良匠。散爲小琴。不顧質麁音少。恒希在君子左琴。
梧桐ノ日本琴ヲ中衛大将藤卿ニ贈ル 并に歌二首。大伴ノ淡夢(アハンユメ)に(此)琴(コト)娘子(ムスメ)ニ化シテ日ク。
余(ワレ)根ヲ遥嶋之崇岳(巒)ニ託(タクシ)。幹ヲ九陽(キウヤウ)之休光ニ晞(サラシ)。
長(ナガク)姻霞ヲ帶フ山川之阿(クマニ)逍遥シ。
風波ヲ遠望シテ。鴈木(ガンホク)之間二出入ス。
唯恐クハ百年之後。空ク溝壑ニ朽(クチン)。
偶(タマタマ)良匠(リヤウシヤウ)ニ遭ヒ。散(サン)シテ小琴ト爲ル。質麁(シツソ)音少ヲ顧ミズ。恒ニ希(ネカハクハ)在君子左琴。
ヿいかにあらん。日の時に。かもこえ(雁声)しらん人の膝のべ。わが枕(マクラ)せん(或はかんとも)
ヿひざにふす。玉の小琴(コト)のことなれば。いとかくばかり。わかこひんかも。
高橋文屋麻呂。九歳にして嵯峨天皇に仕へ。天皇自ら琴(キン)を鼓(ヒ)く事をおしへ給ひ。其より。能琴(ノウキン)の名。当時に冠たり。仁明天皇琴(キン)をひき。管を弄(モテアソビ)給ふ。人皆古の虞舜と云へり。治部大輔興世書主。琴(キン)を善(ヨク)す。
ヿ新羅の人。沙良真熊(サラマクマ)。新羅琴(キン)を弾(タン)ず。書主伝習て。其の手法を得たり。其頃藤原ノ関雄(セキヲ)も。琴に名ありし。
ヿ掃部頭藤原貞敏(テイビン)。学を好み。琴を善(ヨク)せり。承和六年。美作(ミマサカノ)の掾となり。遣唐使をかね。判官に準(シュン)じ。唐山に行て。劉二郎(リウジ)なる者に逢て。砂金二百両を贈りければ。劉二郎琴曲を授(サヅ)く。劉二郎貞敏に問て曰く。君はもと何人に従ひて。琴曲(キンキヨク)を学得たるや。貞敏答て日。我は累代家に伝へて。更(サラ)に他師(タシ)なしと。劉二郎曰。僕に一女あり。願くは巾櫛(キンシツ)をとらしめんと。貞敏やがて婚(ツマト)す。劉が女。琴(キン)を善くし笛をよくす。明年貞敏東帰(ミクニゝカヘル)。時に。劉二郎紫檀紫藤二木を贈けるを。取帰り琵琶二面を作り得たり。貞敏又琴絃を作る事を。定国といふものより伝へたりき。平安ノ若江家に此伝あり。弼亦(マタ)此伝を得たり。
散位良岑朝臣長松。承和の初。伊予椽を以て遣唐使准判官(ケントウシジュンハウクワン)となる。他の才能なし。只よく琴をひく。此数ヶ条にひく所の琴といふは。和琴の事にてもありなん。小琴(ヲゴト)といへるにめでゝかきつづけつ。
ヿ肥後国益城(キ)群。菅米丸といふ所に。小松内大臣の宮(ミヤ)あり。石室ありて。古琴蔵(キンヲサマル)といひ伝ふ。
厳嶋神庫(イツクシマジンコ)に重平(シゲヒラ)(衡)の琴蔵(キンヲサ)まる。予上卿(シャウケイ)市正といふ神家(シンカ)にて観(ミ)たり。六七百年の物断紋(ダンモン)古りて。雷家(ライカ)などの製なるべし。
平家の時。琴(キン)行はる。
…略…
其後戦争を経(ヘ)て世(ヨ)下り。人亡びて。琴(キン)道地に墜(オツ)。嘆(タン)ずべきことになん。
こうしていったん琴道の衰退した後、鎌倉~室町~安土桃山を経て江戸期に入るわけだが、琴は五山文学などにその影を落とし、宋・明貿易における琴や琴譜の舶載はあるものの、この間約六百数十年、実技実際の伝播はなく、延宝五(一六七七)年の正月、霊元天皇の御代、徳川第四代将軍家綱公治世下、ようやく東皐心越禅師の東渡によって、明朝浙派の琴流が齎来することとなり、折からの文藝興隆と相俟って本邦第二次の琴道復興期を迎える準備が整う。
【上】市野迷庵手抄『東皐琴譜』天明年間
江戸期琴曲伝授の際、通常は刊本を用いず、かく師伝の『東皐琴譜』を手抄した。
市野迷庵(1765~1826)は、神田弁慶橋で質舗を営みつつ、生涯学問に生きた市井著名な考証学者である。
若くして琴を新楽閑叟に学んだが、その同学が後の碩儒松崎慊堂と奥医杉本樗園となる。
【左】書軸「聴幽蘭」丁錫康書
まだ青臭いころの座右の銘として、筆者の琴友で現代中国を代表する琴家龔一(1941~)先生が、とくに友人の海上名書家丁氏をして書かしめ恵与されたものである。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第148話
東皐心越禅師と琴(きん) 三
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
しかして約六百数十年の後、中国曹洞宗の正宗として東渡したのが、東皐心越禅師(以下越師と略)で、平安朝末期にいったん途絶えた琴道が、越師の伝授を承けた幕儒人見竹洞(既出)と麾下大身の杉浦琴川(既出)に継がれ、さらに後、琴川陪臣の小野田東川(既出)に伝えられ、徐々に江戸の巷間に広まり行くことになる。
この越師は、かなりの「琴痴」の「癖」をもった人で、禅人ながらその東渡に際して、江浙一帯の地で学んだ折に蒐集した古琴(古い名琴)、および明清版の琴譜を本邦に携えたが、琴に納まった琴は、おのおの木製の琴箱〈縦130cm横30cm高25cmほど〉に厳重に収まり、これが十面あったなら、それだけで小部屋は一杯になってしまうほど。当然これら琴・譜だけでも越師一人自ら抱えて持参できる量でもなく、そのことだけをもってしても、優に琴痴である証左とすることができる。
想いつくまま数例挙げてみよう。
【古琴】※旧蔵者→現蔵者
一、「大雅」 祇園寺→宮内庁
二、「萬岳松」杉浦家→不明
三、「素王」 人見家→不明
四、「虞舜」 水戸家→宮内庁
五、「聞天」 水戸家→宮内庁
六、「南風」 水戸家→宮内庁
七、「無銘」 水戸家→宮内庁
八、「無銘」 東川→多紀藍渓 天明の大火で焼失
【その他】
「琴裏板」峡中老人→不明
「製絃器」幸田子泉→不明
「紫竹曲笛」 祇園寺
「漁鼓簡板」 不明
【琴譜・琴書】
<明版〉
一、『太古遺音琴経』一六〇九年
二、『太古正音琴譜』一六一一年
三、『松絃館琴譜』 一六一四年
四、『伯牙心法』 一六一八年
五、『新伝理性元雅』一六一八年
〈清版〉
六、『琴学心声諧譜』一六六六年
〈越師自筆譜>
七、「静観吟」 祗園寺
八、「関唯」 祇園寺
九、「琴譜篆体」祗園寺
※「宝物一覧表」参照(『東皐全集』浅野斧山編)
現存九、の書表には琴操譜名が記され、元来その内容であったようだが、後の装潢時に表紙と本文とが入れ替り、本譜は佚す
どうであろう、ここには省略しておくが、他に琴に関するものもあり、もって越師の琴痴ぶりが遺憾なくうかがえるが、驚くなかれ、これらは従であり、主たる仏教本来の諸器物、仏具・経典・法衣・食器・日常器具・文房具・書籍・宝物等々、併せ唐船全体の積荷半分を占めたというから、頭陀袋ひとつ抱えた一介の亡命僧が、命からがら逃れ来たったわけではないこととお解りになろう。
折しも日本は、徳川氏の覇府以来七十年の安泰爛熟期を迎え、まさに諸学藝の花開かんとするとき、夢裏に琴の正伝を得んものと、ここ日東に越師との見えぬ絲を手繰り俟つ人見竹洞(越師の三歳年長)あり、ま杉浦正春(後の正職。越師杭州永福寺錫駐の年に生まる)と、小野田東川(越師小石川後楽園から水戸城三の丸移住の翌年に生まる)の四士それぞれの見えざる絲が、事外絲桐の契りを結ぶことにより、以降、二百五十年におよぶ本邦琴学第二次の隆盛期を迎えることとなるのであるが、先ずはそんな詳細は後稿に委ね。
かく琴癖ただならぬものをもった越師である。満を持して長崎港へ入港したのが、わが延宝五(一六七七)年正月十二日夜半のこと、さあこれからという矢先の翌十三日、思わぬ奉行所地役人や唐通事による厳しい詮議をうけてしまう。
その主たる原因は、越師が中国曹洞宗寿昌派第三十五世の正宗を背負ってきたことに他ならず、すでに日本には道元禅師派下の曹洞宗が厳然として存在するため、いまさら中国曹洞宗の正宗が日本に錫駐、さらには布教するなどとは宋脈が乱れるだけ云々。また、越師を招聘した長崎五ヶ寺の一、興福寺主の澄一道亮(一六〇八~一六九一)は黄檗宗なのであるから、越師もこれに改宗せねば上陸はあいならん、とのキツいお達しである。
そこで、同船の客と越師従僧たちと検討のすえ、先ずは上陸することが肝要と衆議一致、これを方便として、いったんは澄一に対して礼拝し弟子の礼を執り、何とか上陸することができたのである。無論、このことで越師が寿昌派正宗を捨てたわけでは決してない。
かくして、越師の日東第一となった難関を越え、長崎興福寺に錫駐することになったのである。
上陸二ヶ月後の三月十日、日本の長崎において初めて作曲(秋月※)した記念すべき琴操が図版の「安排曲」である。入港の初っ端から越師の前途を暗示するかのような椿事が出来したが、固い決意のもと宗脈正宗を担い、退路を断って来崎した越師でもある。また、「僧中真儒あり」と、碩儒竹洞をして言わしめたほどの越師のことである。思わず雄渾な宋人の歌詞を借り、武士ならずとも大丈夫たる禅人であると、自らを重ねた渾身の作曲となったのである。
その宋人作の詞は、焦竑編、万暦三十四(一六〇六)年刊の明版『焦氏筆乗』に「霜天曉角詞」と題し所収されるが、該書は早くもわが慶安二(一六四九)年には和刻されているので、越師がその明版および和刻本のどちらを参考にしたかは不明なものの、杭州ではなく東渡直後の新作となるのであるから、あるいはこの和刻本を根拠としたのかも知れぬ。
後に徳川光圀(一六二八~一七〇一)公により越師が庇護されたときの「熙春操」とともに、越師自作琴操の双璧として、さらに後、竹洞と琴川により編纂される『東皐琴譜正本』附録「扶桑操」に収録された。
功名大小
功名ノ大小
天已安排了
天已ニ安排シ了(おわ)ル
何用百般機巧
何ゾ用イン百般ノ機巧ヲ
栄休喜
栄ニ喜ブヿ(こと)ヲ休メヨ
辱休悩
辱ニ悩ムヿヲ休メヨ
開先謝早
開クヿ先ナレバ謝スルヿ早シ
此理人知少
此ノ理ヲノ知ルヿ少シ
万事算来由命
万事算来スルハ命ニ由ル
聴自然真個好(聴自然真個好)
自然ニ聴ス 真個好シ(繰返し)
栄枯得失
栄枯得失ハ
天已安排畢
天已ニ安排シ畢ル
何用強心力(原詞=苦労)
何ゾ用イン強テ心力ヲ労スルヿヲ
得一日過一日
一日ヲ得テ一日ヲ過ス
泰来否極
泰来レバ否極ル(『周易』)
機巧終何益
機巧モ終ニ何ノ益アラン
万事付之一笑(万事付之一笑)
万事之ヲ一笑ニ付ス(繰返し)
前程事暗如漆
前程ノ事ハ暗キヿ漆ノ如シ
明版『新伝理性元雅』
1618年刊 越師将来譜 坂田古典音楽研究所蔵
「安排曲」『東皐琴譜正本』
2001年刊坂田進一再編より
琴譜「安排曲」の冒頭部分である。
越師の長崎上陸後、日本における諧音填詞「扶桑操」第一作目の記念すべき操で、後に、越師の「琴譜草稿」(後に「東皐琴譜」と命名)を整稿した琴川が、臣下の東川をして明版明朝体を模して清書せしめた。その好例が該譜である。
右側の詞が越師の筆跡を臨模したもの、左側の琴譜減字譜が明朝体をと、どちらも東川手筆になる清書原稿から起した整版で、当然、「正本」には後の異版にある「唐音(とういん)」ルビは、一切記入されていない。
25
△目次TOP↑
秋月※ 東皐心越が「安排曲」を作曲したのは「維落仲春有十日」の落款から1689年2月10日のこと。詳しくは厳暁星「新発現的人見竹洞致東皐禪師佚簡」2022年参照。太歳紀年法による東皐心越の干支表記習慣と竹洞書簡による裏付けから説得力がある。
ここに言う1677年3月10日作曲説(「維落は「維新」の反語」という解釈による説、坂田進一『東皐琴譜』中文版年譜,2016年刊参照)は根拠が薄い。
瘦蘭齋樂事異聞 第149話
東皐心越禅師と琴(きん) 四
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
丙辰(一六七六)六月、戦乱にある故国を憂えつつも、半ば揚々と杭州城を出帆した越師である。
途中、辛くも処々に「三藩の乱」余波による海戦を避け、ようやく寧波沖の舟山列島普陀山にたどり着けば、なんと戦火をうけて、さしもの観音霊場もすでに荒廃しきっている。
在ること二ヶ月余り。日夕参禅し、耳・船ふたつながらの風の便りを待ち十一月に出航。十二月三十日薩摩沖に至り、除夜は唐津沖にあり、明くる巳年(一六七七)正月(新暦の二月始めに相当)は、日本の海上において寿ぐのである。
舟中元旦 丁巳始此
紫薇頒正朔。年華又亦新。万邦更歳月。四海序芳辰。
浮世因漂泊。空花任隠淪。喜茲紅日近。極目水之浜。
拙稿これ以降は、前号述べるところに準ずるが、「丙辰仲夏自制(浙)泛海漂泊日久。直至今正始到長崎…」(越師詩題)なる七律題などからはおおよそ予期できぬ、大丈夫たる禅者越師の胸中にも、希望とは相反する大きな葛藤がはじまることになる。
上陸以降の越師の長崎錫駐は、延宝五(一六七七)年正月から同九(一六八一)年の春、すなわち天和改元の年までと、足掛け五年間の長きにもおよぶ。しかして、この五年間のことは続稿中に改めてなぞり、必ずやこれを繙かねばならない。何となれば、これなくして、東渡後の日本における越師半生を正しく把握し、評価することは不可能であるからであるが、いまは、ひとまずこれをおき、越師をして「明末義僧」と位置づけた碧眼の文人高羅佩の観点と印象もあることから、引き続き「安排曲」を引用したく、前号稿末の越師作「安排曲」歌辞をご参照いただきたい。
※本稿引用文()および句読筆者責
蓋シ大丈夫ハ四海ヲ以テ家トナシ。流離ニ就キ国ヲ別ツト雖モ亦タ過チト為サザルナリ。
奈カンゾ越ハ幼キ(コロ)従リ薙染シ素ヨリ囂塵ヲ厭フ。林下ニ処スト雖モ恬然トシ株ヲ守ル。
これは、越師の「日本来由両宗明弁」にあるところで、本稿末の原文抜粋と重複するが、果たせるかな、「安排曲」を詠った宋人と、越師の心情は大きく重なるのである。
該琴操は『東皋琴譜正本』附録の「扶桑操」に所収、その後、そこからさらに各師承筋により転写され、「平仄」と「唐音(とういん)」とを補填し、各種異版の『東皋琴譜』に引き継がれることになる。
そんな一例の図版「安排曲」は、幕末を代表する出羽産の琴師鳥海雪堂(一七八二~一八五三)自筆『東皋琴譜十五曲』中の減字譜である。雪堂は、鳥海痴仙とも名乗った琴師(本連載18~「紀州の琴僧古岳上人」、139参照)で、幕末、すでに衰退ぎみにあった後期心越派の琴系を辛くも死守した功労者である。
京阪にて長く帷を下ろした後、晩年に江戸に下り、本郷や湯島などで琴を中心に兵・数・書などの諸学を教授し、雪堂門下の高弟がこれを明治へと繋いだことから、越師の琴系は、後の大正までの約二百五十年間、なお新都東京の巷間において連綿脈々と息づき、明朝伝来の貴重な文人音楽は、なお密やかに奏でられ続けたのである。
該譜は、浪花在時の雪堂が天保十二(一八四一)年の春二月、手ずから書して門下生に与えたもので、実に今を去る百七十五年の時を経ている。しかしてその内容は、小野田東川撰の「初学十六曲」(「仙翁操」含)を踏襲した唐音入りの基本的な撰曲であるが、諸本多少の異同があることに留意せねばならない。
さあ、ここからは話は杭州から長崎航路へ逆戻りし、さらに日本の仏教界、しかも昔日のこととなる。
今次、ざっと東皐心越禅師(越師と略)東渡以降の軌跡、とくに琴を中心とした「楽事」を追うはずの拙稿だが、折角の機会ではある。軌道を修正、楽事外の「諸事」的見聞しつつ漫歩し行くこととする。左道を往くも右道を行くも、結局は同じローマに通ずるからである。しかして、ロートルの想いつくかぎり、また、息切れのせぬよう、ご同道諸賢とともに見聞を広めたく、まずは越師東渡前後の分明ならざる事情についてはこうである。
越師に日記類はもともとなく、代わりに詩稿が遺る。編年体ではなく前後するが、干支を記したものあり、多少は年月を特定できる。
以下、それらの資料を読むについ見落とせない重要な事項が、明末「三藩の乱」上、長崎の「唐館」(いわゆる唐人屋敷)、設置以前の事情、わが国鎖国(後の呼称)政策である。
試みに、それら越師自筆の『詩稿』、「日本来由両宗明弁」、「東渡述志」および、他纂では、もっぱら袛園寺蔵の資料をもとに編纂された『東皐全集』(浅野斧山)、さらに日本の資料をもとに、戦時中の中華視点を交えて編纂した『明末義僧東皐禅師集刊』(高羅佩)所収するところの「年譜」、さらに『華夷変態』に類するいわゆる長崎ものなどを参考に、その側面から確認してみよう。
※傍点および句読筆者責
山衲心越。
因唐山明清剥復。天下大乱。
兵戈未寧。
欲覓避秦無地。
偶有人為予言扶桑之請。
故不揣愚昧。一時浪蹌而行。
若言故国兵戈之乱。仍是生身之所。
豈可一旦而棄之。豈不是大錯矣。
蓋以大丈夫四海為家。
就流離別国亦不為過也。
奈越從幼薙染素厭囂塵。
雖処林下恬然守株。
不期於丙辰六月間。附舶東渡。
於中時多阻滞。言不可悉。
始丁巳正月十三日而到長崎。
即有通事。查点客人貨物。
并有南京寺。託請清僧二位。
彼時通事查問来歷。
幾時出家曾從何处受法等。
情此事合船客衆尽知曹洞嗣法之人。
亦不妨其所問。以直言之矣。
自幼披髮呉門報恩寺。
乃觉浪和尚的派。住杭州永福禅院。
当時通事不悦而言。
南京寺只要請住持之僧。
那箇要汝請付法的和尚来。
彼時通事自去商議了一会。
方来点人起貨船。因抛錨薩摩。
同衆客即趨面鎮台岡野孫公。
所問唐山明清得失之繇。
臨晚至寺。安住月余。
承澄禅師之言。
既此地接待常住之事
必要師徒相称。方堪可託。
越即共同船知己客衆商量此事。
為可為不可。
衆曰。既到此地。且暫相承。
況唐山嗣法到此。一時誰与張揚。
就有因緣。必須時節。
以此設斎集衆。始成師徒之礼。…
(「日本来由両宗明弁」拔粹)
「霜天曉角詞」和刻『焦氏筆乗』
慶安2(1649)年京都刊より
越師作「安排曲」の原詞「霜天曉角詞」は、明人盛仲交編『閲古編』に初出というが、該書は筆者未見である。しかし、当時すでに独歩し、かなり人口に膾炙した宋詞という。
鳥海雪堂自筆「安排曲」
天保12(1841)年
譜末の雪堂識語は、「東皋琴譜十五曲、応逸斎君需、録以贈焉、天保辛丑年春二月、鳥海印」である。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第150話
東皐心越禅師と琴(きん) 五
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
前号稿末に越師の「日本来由両宗明弁」(日本来由とも)抜粋部分の原文をそのまま提示したが、それでは愛読者諸賢に対してあまりに不親切と思われもする。
はなから対訳すればよかったものと思い直し、ここに煩雑ながらも重複を厭わず、改めて読者利便のため対照意訳を試みたのだが、今号では『東皐禅師集刊』中の水戸彰考館本を根拠とし底本とした結果、相反して『東皐全集』所収文とは僅少の差異を生じてしまった。
いずれ折をみて、越師筆原本との異同を正さねばなるまいが、まずはそのままをご紹介し、稿を進めよう。
()内および※、句読筆者責
山衲心越。
山出し坊主の心越である。
因唐山明清剥復。
中華の地でまさに明の世が清に剥ぎ取られようとする、
天下大乱。
その天下の大乱時。
兵戈未寧。
戦闘はいまだ治まらず、
欲覓避秦無地。
穏やかな居所を求めようにもそんなところはない。
偶有人為予言扶桑之請。
たまたま日本からの要請があることを人から聞くにおよび、
故不揣愚昧。
まことに愚昧な拙僧ではあるが
一時浪蹌而行。
僭越にも海を渡ったのである。
若言故国兵戈之乱。
もし自国の戦乱を理由とすれば、
仍是生身之所。
己もまた生身の人である。
豈可一旦而棄之。
どうして一朝にして、これをなおざりにできようか、いやできぬし、
豈不是大錯矣。
また、この決断に間違いなかろう。
蓋以大丈夫四海為家。
確と丈夫(ますらお)たるもの、世界を股にかけて異国に暮すとも、
就流離別国亦不為過也。
あながちこれも過ちではあるまい。
奈越從幼薙染素厭塵。
そんな拙僧であるが、幼きより剃髪し、もともと騒がしい世間を好まぬ質である。
雖処林下恬然守株。
禅林に於いて修行すれども、物事に拘泥せず平々然とし、いたずらに規範を守ろうとするばかり。
不期於丙辰六月間。
ここに思いがけず、ひのえたつ年の六月、(一六七六年)
附舶東渡。
貿易の大船に身を委ねて日本を目指したが、
於中事多阻滞。
途中で障害に阻まれたことなど、
言不可悉。
筆舌には尽くせないほどである。
始丁巳正月十三日而到長崎。
翌年、ひのとみ年の正月十三日、ようやく長崎港に至った。(一六七七年、新暦では二月)
即有通事。
すると唐通事なる役人がいて、
查点客人貨物。
船客の荷物を調べ、
并有南京寺。
華人のための寺、
託請清僧二位。
その委託をうけた清国の僧侶二名もいた。
彼時通事査問来歴。
そのとき、唐通事が(越師の)出自来歴を訊きただし、
幾時出家曾従何処受法等情。
いつ出家し、どこで誰に従って修行し、また法をうけたか、などの事情を取調べだした。
此事合船客衆尽知曹洞嗣法之人。
これらの事情と、拙僧が曹洞宗正宗であることは、同船の乗客すべてが衆知のことであって、(大旨、同船の客は杭州または浙江の人)
亦不妨其所問。
それゆえ彼らは通事に包み隠さず、
以直言之矣。
直言したのである。
自幼披髮吳門報恩寺。
これなる越師は、幼時に蘇州の報恩寺にて剃髪出家し、
乃觉浪和尚的派。
覚浪道盛の曹洞宗に属し、
住杭州永福禅院。
杭州の永福禅寺に錫駐していたものに相違ございませんと。
当時通事不悦而言。
すると通事が難色を示していうには、
南京寺只要請住持之僧。
南京寺(当時三ヶ寺、後に五ヶ寺)は、ただ後任の住職を要請したのであって、
那箇要汝請付法的和尚来。
そのほうのような付法(師が弟子に教法を授けること。その連綿たる正法伝授を付法相承といい、印可して衣鉢を授け、証明の印信を与える)の僧侶は不要であると。
彼時通事自去商議了一会。
その通事が去り、相談することひとたび、
方来点人起貨船。
来かかったものが貨客船を出帆させ、
因抛錨薩摩。
薩摩沖に投錨したのである。(越師一人のみか?)
同衆客即趨面鎮台岡野孫公。
そこで同船の客は、すぐさま長崎奉行岡野孫九郎こと貞明に訴え出て、
所問唐山明清得失之繇。
お奉行さまのご下問に対し、中華明清の戦乱によるところとお答えしたのである。(繇は由)
臨晚至寺。
夕刻、寺(東明山興福寺)に入り、
安住月余。
以来、錫駐すること一月あまり。
承澄禅師之言。
住職澄一禅師のいうには、
既此地接待常住之事。
すでに長崎の当寺において寄宿衣食し続けておるからには、
必要師徒相称。
子弟と称してもかまわぬし、(是非にもいわねばならぬ)
方堪可託。
そのほうが(お上に対しても)なにかと便利であろうと。
越即共同船知己客衆商量此事。
そこで拙僧は同船知己の客たちと事態の可否を相談すると、
衆日。既到此地。
皆がいうことには、すでに長崎、すなわち日本に上陸しているのであるから、
且暫相承。
しばらくはそのまま(興福寺にて)錫駐し相承し続けられるが上策。
況唐山嗣法到此。
ましてや、中華正統の曹洞宗系譜を承け嗣ぐ越師のことである。
一時誰与張揚。
この後、昔の張揚(楊)のような慈悲深い人が現れぬとも限らず、(徳川光圀公を暗示する)
就有因緣。
そうであるならば因縁があり、
必須時節。
それは必ずや熟すことでしょうと。
【上】「唐船」部分
いわゆる「寧波船」である。
その縮尺に「一間に付一寸積」とあるが、越師はこれに似た「南京船」で、はるばる万里の波涛を乗り越えてきたのである。
「覚浪道盛頂相」
越師将来祗園寺蔵
本文引用※「乃ち覚浪和尚的派にして、住杭州永福禅院に住す」の条。
越師法祖父で曹洞宗中興三十三世の正宗覚浪道盛の自画讃で、かかる自らの正統を証明する品を将来した越師の胸中を推量すべし。
「心越禅師の墓」祗園寺
図版左上がそれで、徳川光圀公の手跡を刻した「寿昌開山心大和尚之塔」とあり、いまもって水戸の祇園寺に現存する。
引用した雑誌『禅』の図版は、いまより100年以前の明治40年代、浅野斧山が錫駐し住職していたころのもので、現在のような廟風の覆いはなく、雨ざらしであったことが解るし、墓石の背部、一面の畑の部分に、1927年、茨城中学校が建設されたというわけである。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第151話
東皐心越禅師と琴(きん) 六「東皋琴譜」
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
今年の仲秋節で見上げた月は、一入わが心に残るもので、そのため、「日本来由両宗明弁」をひとまずおいての、例のごと寄り道となる。
それは、越師(東皐心越禅師)の心願を、はからずも琴縁により、その遺志を継ぐかたちで、およそ筆者半世紀にもおよぶ心血を注いだ『東皋琴譜正本』中国版を、ようやく中国にお返しできたからにほかならぬ。
虹橋に降りたち、上海音楽学院の門前に到着するや、専家楼にも入らず、そのまま間髪を入れず、待ちあぐねたマイクロバスに誘導され、その脚で杭州の永福寺に向う。
あやにくの台風の影響下、不順な天候だが、なんとか寺にたどり着き、翌十四日、天籟閣における「琴譜出「版記念式典」を終えたのである。
またぞろ上海へ戻り、十五日仲秋節の音楽会であるが、これはまたの機会ということで、『東皋琴譜正本』の話に立ち戻り、ここに愛読者諸賢にその成立の経緯をご紹介すべく、多少長くも筆者の跋文を参考に供す。
「東皐琴譜新跋」 坂田進一
九月三十日は「心越忌」である。
元禄三(一六九五)年九月三十日、東皐心越禅師の入寂されてより数え、二〇〇一年は三百六年目に当る。この心越忌当日はたまたま東京琴社創立三十一周年の記念演奏会とも重なり、会場において日本琴学中興の祖でもある禅師の遺徳を偲ぶことができた。
真に好し、日本琴界三百年来の悲願であった『東皐琴譜正本』全五卷を新たに編輯復刻し、これまた禅師の御影前にお供えすることができることに、自らの計画でありながら、さらに深大なる琴縁によるものを感じえるのは何と琴人冥利に尽きることであろうか。
ここに縷々と禅師宗脈の履歴を述べる心算は毛頭なく、向きにはぜひ浅野斧山老師の名著『東皐全集』明治四十四年一喝社刊を閲されたい。こと琴に関しては一代の傑僧浅野斧山師も門外漢であり、よって全集編纂にあたり何蠡舟居士に、全集中の琴の項目と禅師略年譜の執筆を依頼された。
東皐心越は禅者である。これを真面目とすることは無論、それ以前に一個の人である。
かく越師の全人的な人間性に風に心惹かれた幕府の御儒者人見竹洞は、越師を称して「僧中真儒あり」と看破し、徳廟の儒官でありながら一家を挙げて越師に帰依したのであるからして、越師はまた一面、まことに人間的な魅力をも兼備した人であったといいえよう。
その禅余に伝えた琴が、本邦平安朝以来六百年の長きにわたり途絶えていた琴道を再興した名誉を担うばかりか、琴を筆頭とする詩文、書画、篆刻の実技は、天和から元禄期にかけてようやく開花し始めた漢学や、文人を志す学者の活きた指針(雛形)であった。
東皐心越禅師は、生前中国で学ばれた琴曲やご自身訂正なされた琴譜、さらには日本渡航の後に諧音された琴曲などを雑多に保管され、いずれ上梓せんものとのご意向であられたが、夙縁の尽きたことを悟られた越師の命を承け、人見竹洞がこれを準備することとなる。しかるに越師の化で思いのほか落胆した竹洞は、あたかも越師の後を追うかのように三ヶ月後の翌年正月に没してしまった。
越師と竹洞の遺命を承け、再び琴譜編纂のことに携った杉浦琴川は、激務の間隙を縫うこと幾星霜、よく遺命を遡り、明清期の名譜『太古遺音』、『琴学心声諧譜』、『松風閣琴譜』などの書式に倣い、ようやく稿を整えたのが越師入寂後十五年を経た宝永七(一七一〇)年秋八月のことである。
しかるに「好事魔多し」とかや、またもや『琴譜』の上梓を見るに至らず、琴川も翌年の正月に急逝し、三たび『東皐琴譜』は遺稿となってしまった。実に千載遺憾なことで、琴川の心情を思えばさぞや無念であったに相違いなく、察するにあまりある出来事である。
琴譜編纂にあたり、諸家の序文を除く琴譜部分を清書した小野田東川は、本来越師、竹洞、琴川三師の意志を継ぎ、当然『東皐琴譜』の上梓に極力尽力すべきであったろうが、故あって杉浦の家を逐われたため、東川は亡君の朋輩三枝某氏の駿河台の屋敷に寄宿し、琴をもって辛うじて糊口を凌ぐ有り様。東川自身の浄書した琴譜稿本は、もはや出入りもかなわぬ杉浦家に副本は人見家にと、侭ならぬ残念を心に抱きつつも、以後十六曲の階梯を設け、宝暦十三年までも長寿を保ち、実質上の江戸期琴学の礎を築き上げることとなる。これを機に漸々と江戸の琴界は隆盛の一歩をたどることとなるや、俄然テキストの需要も高まり、財と力とを併せもつ琴家は曲数を減じて版本(後記参照)としたが、依然としてこの琴川撰の「正本」とされる『東皐琴譜』は正副二、三の写本により伝わるのみで秘籍とされ、一般の琴者間は無論のこと容易く巷間に流布することはなかった。「幻の琴譜」とされる所以である。
さて、編者が琴学に志してよりすでに四十数年(二〇〇一年当時)を経、東京琴社も本年で創立三十一周年を迎える。琴を学びはじめた少年から青年期にかけて、日本の琴学にも多少の興味をもちはじめ、その基礎文献であるところの『東皐琴譜』八方手を尽くし探し求めたが、写本刊本とを問わず『東皐琴譜』は何処にもなく、ましてや琴川撰の「東皐琴譜正本」など、萬金を積んでも求めようがなかったのが当時の実情で、却って文革以前の中国では国策により琴の研究が旺盛に進められ、内部刊行用ではあったがまことに羨むほどの琴書群が陸続と復刻刊行されつつあった。
翻って当時の日本では現在のように完備された古籍目録もなく、ようやく捜しえた菊地遷甫本『東皐琴譜』は日比谷図書館の架蔵であったが補修中。仁木三岳抄写本の『東皐琴譜』にいたっては、現在の赤坂迎賓館に仮住まい中の国会図書館蔵でしかも閲覧不能。両館とも十八歳の成人であることが利用規定であり、八方塞がりの中やむなく歳月を俟ち初めて閲覧したことを想起する。
これら諸々の経緯に鑑み、東京琴社では『日本琴学叢書』を継続復刻中であるが、既刊六種中に『東皐琴譜』の版本全種を網羅し、いささか需要に応報した所以である。すなわち、
一、鈴木蘭園版『東皐琴譜』明和九(一七七二)年刊一巻
二、大江玄甫版『東皐琴譜』天明七(一七八七)年刊一巻題箋「琴学入門」
三、菊地遷甫版『東皐琴譜』寛政九(一七九七)年刊一巻
四、児島鳳林版『東皐琴譜』文政十(一八二七)年刊三巻題箋「琴譜」
の諸版本がこれである。
『東皋琴譜正本』中国版
坂田進一編・上海音楽出版社刊
本年九月仲秋節、越師示寂後320年目にして、ようやく故国中国にお返しすることができた、記念すべき通番第1冊目の琴譜となる。
「出版記念式典」杭州・永福寺2016年9月14日
「禅韵仲秋」と銘打った、永福寺「天籟閣」における「琴譜出版記念式典」開幕直後である。
「琴譜ご開帳」
上海音楽出版社社長の費維耀氏と筆者による献納式。
「筆者弾琴勢」
出版式後半に催された「古琴雅賞会」における、筆者の「安排曲」弾琴模様である。
なお、今号使用の写真4葉は、友人で文筆家兼写真家でもある北京在の唐小松氏の提供による。
【七絃琴コンサート】千葉市美術館11/10~12/18「浦上玉堂と春琴・秋琴」展で12月3日(土)坂田進一先生演奏。
14時から同館にて先着130名、無料。同日正午より整理券配布
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第152話
東皐心越禅師と琴(きん) 七「東皋琴譜の成立」
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
重言である。
この仲秋前日、驟雨一瞬の晴間に杭州の永福禅寺で見上げた籠月は、ところこそ違え、筆者愛誦の唐詩を連想させ、江南の景そのものの一幅の名画と重なった。
泊秦淮 杜牧
煙籠寒水月籠沙 夜泊秦淮近酒家
商女不知亡國恨 隔江猶唱後庭花
コチトラ、実は一見訳知りのようで、この芸妓ならずも、やはり何も知らず唱うに等しい、いわば他国の人である。いにしえの中華文化を慕い学び、古楽や琴譜やら詩文云々といったところで、その何も知らぬ他国の文化を、いかにも知ったような訳知り顔で、それこそ半世紀以上も云々し、研究と称して、演奏し唱ってきたのであるからして、ここにきて何ともはや汗顔の至りだが、これらを総括するにはいまだはやく、もう少し時の猶予を稼がねばならない。
杭州での「東皋琴譜正本出版記念式典」を終え、上海音楽学院(以下上音と略す)の「専家楼」へ帰りようやくホットするが、該楼は筆者にとっても縁深いもので、そんな因縁は稿中にまた触れる機会があろうか。
古い瀟洒な洋館はもと比利時領館(ベルギー領事館、和製漢語では白耳義)の花園住宅と命名された一九二七年建築の歴史的建造物で、一九三四年に該館はベルギー公使公邸となり、戦時下に領事館は閉鎖。終戦直後の一九四五年九月に再び領事館となるも、一九五〇年代は閉鎖されて軍用に供された。
上音は一九二七年創設された国立音楽院である。一九二九年に国立音楽専科学校となり、解放後の一九五六年に正式に上海音楽学院と改組され、漕河から現在地へと移転するが、その上音現在地の淮海中路周辺はもとのフランス租界地で、旧領事館を含む上音の敷地はもと青幇(チンパン)の大物社月笙(一九五一年没)邸であったものが、一九五八年ころに著名音楽家たちの宿舎群となり、旧ユダヤ人倶楽部は図書館となった後、いまは院部班公楼(学院本部事務所)となり旧ベルギー領事館は主に学院事務所や音楽家接待のために利用され、後に外来教授のための専家楼となったというわけである。
さあ、ここからは『東皋琴譜正本』とその成立の経緯にたち戻り、多少長くも筆者跋文の続きとなる。
以下筆者句読()内註
これらにより第一に琴社(東京)内部の需要を満たし、残部は国内外の同心の知音に分ち幾分か閲覧を容易にしてきた。しかるにこの叢書既刊中にはいまだ肝心の杉浦琴川撰の版が欠けたままであった。『日本琴学叢書』計画以前の長き年月を要し、この抄本の善本を求むる努力を常に怠らざることは無論であったが、名にしおう稀籍のこととて、復刻の底本とするに足るものは皆無であったからである。
這個の事情を江戸の琴者間で大いに筆写された次なる諸書、新楽閑叟の『絲桐談』(『絲桐雑記』、『閑叟雑話』とも)ならびに井上竹逸の『竹逸琴話』、さらにはその校訂要約版ともいうべき中根香亭編、明治中期「毎日新聞」連載の「七絃琴の伝来」などは、「琴譜の話」としておおよそ次のようにいう。
「琴譜もと越師の編集なし、宝永中、杉浦正職始めて東皐琴譜五巻を撰し集む、五十七曲を収む、爾後東皐琴譜八卷四十八曲を収む、
又、小野田東川十六曲を一部として初学に授く、
予(閑叟)往年、水戸祇園寺に至り越師の遺物を見る事を得たり、
琴譜は五音の次序をわかつといふこともなく、幾曲をも一ツになし、とちつけてあり、大抵一譜ことに書式大小不一、厚薄打交、これハ全く彼邦にて学れし時の草本に、後来、訂譜諧音の草本とを合せ集めたるなり、編集撰次して巻冊としたるものなし、
楮虚舟といふ者より学れし曲もあるにや、往々、譜尾に其名を録す、また幼時書を学れし手本数冊、ともに一ツ筥に入てあり、
此筥西土より持来るものにて、幼童の時、手沢の旧物とおもはる、
手本ハ幼時の初学より成童の上達に従ひ、諸体にて字形に難易廉密あり、師の児たりし時、字を学れし次第を見るに足れり、
明末板蕩流離の中にて、かゝるものを海外萬里の国まて携給う、偏に父母師長の恩を思ひ給へる故なるへしと、
師の思親引の詞なとをおもひ合せ、感慨の涙を催しぬ、
杉浦正職編集の東皐琴譜五巻ハ、
林祭酒信篤、(林家三代初代大学頭)
野沂、(人見竹洞男桃源)
林信如、(林別家第三代)
天猗等序、(高天猗こと深見玄岱)
并自序、(杉浦琴川)
規戒一則、
凡例、
五音審弁、
字母源流等二章、
合て 一巻、
宮音六首 上卷一巻、
商音廿五曲 中卷一巻、
角音三曲、
徵音一曲、
羽音十四曲、
商角音一曲 下卷
扶桑操七曲附録 一巻
として、全部五巻五十七曲を収む、此書迎噉閣(空空翁書屋の名)所蔵也、
即、琴川子編集の草本也、
衆序ハ皆各の手書真跡にて、
譜の小序跋往々越師の手書、
又琴川の手書にて、
譜ハ東川の手書也、
此書全部人見氏に蔵す、
これハ板下に清書せしめしと見へ、
譜は明朝様に書し、
小序跋等の字ハ、真跡を模写す、
惟、林家天猗自序等ハ、除て不載
(遺失にもあら須、故ありと見ゆ、あやしむへし)
此書、世に伝る事なし、
今こゝに一二を抜抄して考古の一助に備ふ」
など、随所に見える勘誤訂正の墨書跡からも窺える。
此の後、諸家の序文の抜萃と目録が続き、さらに幸田子泉撰の八巻本『東皐琴譜』の目録と、菊地遷甫版『東皐琴譜』に関わる話が続く。
今回復刻する待望の『東皐琴譜正本』は、前述されるところの、
「即ち、琴川子編集の艸本なり、衆序は皆各々の手書真跡にて、譜の小序跋、往々越師の手書、また琴川の手書きにて、譜は東川の手書なり、此の書全部人見氏に蔵す、これは板(版)下に清書せしめしと見え、譜は明朝様に書し、小序跋等の字は、真跡を模写す、惟、林家天猗自序等は、除て不載」
と記述されるところの、小野田東川の手書を髣髴とさせる、明朝活字体そのものの稀覯なる写本である。幸運にも這個を得、時宜に適った復刻の快挙は、唯々、琴縁に因るものと感謝する。
「専家楼」上海音楽学院構内
左手、梢の間に見える3階窓の部分が筆者の常部屋である。40年ほど前に専門家として招聘されてより、研究の寸暇を得ては、ここを拠点に杭州の永福寺跡などを探しに出た。その後、図らずも寺跡は中国仏教協会の手で越師縁の寺として重修される。
「東皐心越禅師の墓」高崎少林山達磨寺
図版中央の苔むす墓石がそれで、水戸の祇園寺から分骨し、越師を達磨寺の開山としたものである。
元来、達磨寺境内は高崎在の水戸藩領の飛び地であったが、幕末に曹洞宗寿昌派が衰退し、達磨寺が日本曹洞宗に改組されようとした明治初期、同寺は黄檗宗となった。
「龔一先生に東皋琴譜正本を献呈」
さらに以前、友人H姉が上海の古琴家龔一先生の通訳を担当したことから紹介され、龔先生から日本編纂の琴譜『東皐琴譜』『玉堂琴譜』など資料の問合せがあり、筆者との文通へと発展し新たな友情が芽生えた。
以降、変らぬ大切な琴友また兄貴分たる存在で、その意味からも早く完全版『東皐琴譜』を中国にお返しすべく頑張ったが、なんと、すでに40年以上の歳月が経過してしまった。
△目次TOP↑
瘦蘭齋樂事異聞 第153話
東皐心越禅師と琴(きん) 八「東皋琴譜の成立」
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
写真は筆者二十八、九歳、その大分以前に『東皐琴譜』正本の刊行を発願していたが、これにさらなる発破をかける契機となったのが、知人を介して紹介された上海の琴家龔一先生から、日本残存の琴譜『東皋琴譜』や『玉堂琴譜』が、「未だ有りや無しや」と問われたことであり、却ってビックリしたものである。以降、わが「琴痴度」に拍車がかかることになるのだが、如何せん、刊行に到るには、さらなる四十年の歳月を要すことになろうとは…、
ここでいわれる児玉空空の迎噉閣本が、国文学資料館寄託の田安徳川家本と同一であるや否やは直ちに断言できぬが、田安本は、麾下の士幸田子泉と同田安藩儒児玉空空両師弟士の旧蔵であったからして、その可能性は高いのである。しかしながら復刻の底本とするにはなお精彩に欠ける。
「衆序ハ、皆各々の手書真跡にて」とは、確かにそうではあるが、林家三世初代大学頭鳳岡と人見竹洞の男桃源、および林別家の三世葛廬序文の筆写体は、書写生の再度にわたる転写の結果、書体の線と輪郭が脆弱
で、
「譜の小序跋、往々越師の手書、又琴川の手書にて」の部分も、忠実に模写した書体と粗略なる書風が混在する。
「譜ハ東川の手書也、…これい板下に清書せしめしと見へ、譜は明朝様に書し、…」
と記述されるものが、今回是非ともに必要な最重要個所であって、これが琴譜の心臓部ともいうべきであろうが、版下用に浄書したものではなく、減字も明朝体ではない。「此書全部人見氏に蔵す、…」とあるが、人見家は幕末の動乱期を経た後、家学である漢学を廃し、その蔵書も散逸したため、這個の琴譜も現在まで存在するや否やは判然とせない。
「惟、林家天猗自序等ハ、除て不載」は、林家の序はあり、高天猗老人の自序のみ割愛してあることは、国文学資料館本と寒斎架蔵本と完全に一致するうえ、書体も同一であること等々、この資料館本と寒斎蔵本とは、姉妹本である可能性が非常に高い。
しかして正本には元来、東川中年以降選定の初学十六曲中にある、「漁樵問答」と「陽関三畳」の二操は所収されぬし、後年補足の唐音のルビも附されぬのである。
ついで、復刻に際する原本と新補の拠本、および関連次項とを示さん。
第一に、題箋の字体は、東皐心越禅師手沢の明朝将来本の、和翻刻本『韻府古篆彙選』より引用整形し、
第二に、見返し本題、補足文、および編者新跋などの書体は、正楷活字体で統一新作した。
第三に、巻頭を飾る「東皐心越禅「師肖像」は、中国版にあたり祇園寺現蔵の禅師の「頂相自画賛」使用のご許可をいただいたが、前版は琴社社友で画家の李女史がこれを臨模したもので、禅師のお姿を宛然眼前に拝する如き秀作であった。
当初の計画では肖像は禅師分に止め、他の三師は除外する予定であったが、幸い竹洞の肖像が旧来地の野州雲龍寺に現存し、現住亀山良玄師ならびに、西場町文化財保存会の小澤隆先生のご快諾をえて、この度の印刷に付するをえた。
ご好意に対して厚く御礼申し上げる。
東川居士のものは『東都嘉慶花宴集』中の「東都嘉慶宴集之図」に既載される。
しかして琴譜編纂第一の功労者琴川一人を残すのみ。諸版の『武鑑』を検索するも見えず、「現在、杉浦本家は絶え果て畢んぬ」、
との菩提寺現住の話しに、一縷の希望も絶滅し、這個肖像が存在の有無如何や、また刊行に間に合うや否やも知られず、よって巻頭丁裏に、杉浦家「九曜紋」を置きてもってこれに代え、顕彰の思いを暫時後事に委ねんとす。
第四に、旧来の書家序文は、不肖寒斎架蔵の、これも『東皐琴譜正本』より転写し、
第五に、第四の序文に続く琴川の自序は筆勢に欠くるため、やむなく正楷活字体を用いた。
第六に、目録から琴譜にかけての本文は、妻鹿家蔵本を利用させていただいた。この妻鹿本により今回の
復刻が可能となったといって過言でない。ご当主妻鹿友弘先生阪大教授には、琴社を代表し衷心より深甚特別なる感謝の意と御礼を申し上げ、地下の友樵師と琴縁に対しては、心より感謝の念を捧げ奉る次第である。
第七に、編者の新戦は解題をも兼ね、巻頭の新目は多少の利便性を有しよう。
第八に、印刷、製本の手配全般に関しては、琴社および絲竹班の面々、就中赤枝美智子女史財界人書道協会(当時)が労を厭わずにあたられ、用紙から校正、製版、雑務に至るまでお世話くださった。さらには、国文学資料館との交渉は岡部明日香早大院博士課程(当時)が担り、図像処理および彩色印刷、罫線、活字写植等は、秋田英美姉デザイナー、妻鹿友美嬢造形大研究生(当時)の諸兄姉が、連日深更におよぶまでご奉仕くださった。
第九に、和紙は山田商会と西野商会、印刷と製本とは東京印刷および博勝堂に外注依頼した。
ここに謹んで前記諸兄姉ならびに、西野商会市毛昭治取締役、東京印刷石田秀明社長、博勝堂渡邊博之社長に対して御礼申し上げる。
なお、序文用寒斎本の体裁は、椿紙大本仕立て、天地の余白も寛く、結構も雄大なる元禄本である。
本文用妻鹿本は、美濃判より多少小さめの断裁、本文用紙は榧漉きの楮紙、表紙は紺紙金振りに絹目の型押しという、まことに上品な装幀で、これが今期復刻本全体を一貫する基調となるが、両本ともに題箋も見返しの本題もなく、版心も丁数も記さぬ。
復刻に際しての本文用紙には、越前の簀の目入り和紙を用い、表紙にはこれも越前の紺紙に原本の金を銀振りに替えて、復刻本であることを表明し、版心を整え丁数を入れ、竹簀目入り和紙に活版凹凸仕上の題箋を附し、藍紺地に唐蔓艸花の西陣彩布をもって巻帙仕立てに仕上たのである。
最後に、前記妻鹿家蔵本を利用させていただくに至る一條の顛末を、ここに記す義務があろう。
本年春(当時)、かねてより計画中であった、幕末から明治中期に活躍され、関西琴壇の雄と称された、大坂の琴家妻鹿友樵師旧蔵の琴と琴譜、琴書と楽書などの調査を行った。
この調査は、妻鹿友一先生のご在世中より、編者の渇望してやまぬ重大事であったが、諸般の事情で実現せぬまま、すでに三十年近い年月が過ぎ去っていた。
「書斎における若きころの筆者」
筆者がちょうど信濃町に住まいしていたときのもので、バイトと散歩を兼ねて、徒歩で九段上の一口坂にあった中国研究所で中国音楽を教えたり、四谷本塩町までヴァイオリンの出稽古に行っていた。
『東皋琴譜』仁木三岳筆写本 国会図書館蔵
『東皋琴譜』正本ではないものの、そのころまでに日本国内の大小図書館で閲覧可能な「東皋琴譜』はごく稀であり、それこそ何ヶ月もかけて手抄したものである。
なお該『東皋琴譜』は、のちに井上竹逸から今泉雄作へと渡り、最後に雄作が上野図書館に寄贈したものである。
佐久間象山28歳のおり、琴の師仁木三岳(二千石高禄旗本)が没し、平生、他人のための墓碑銘を書かぬ主義の象山も、さすがにこの時ばかりは大恩ある師のため、曲げて撰文したといい、現に榻本だけは遺る。
△目次TOP↑
2017年2月
瘦蘭齋樂事異聞 第154話
東皐心越禅師と琴(きん) 九「東皋琴譜の成立」
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
ところが琴縁とは尊いものである。愚門(筆者)に琴を学ぶ伊藤昭氏童話作家(已故)が、たまたま造形美術大学で教鞭を執られた短時日、その受講生中に妻鹿友一先生の令孫友美嬢が、研究生として勉学に励んでおられたのである。しかも講義中、伊藤講師の琴事に話題がおよぶや、
「先生!、わが家にも琴があります」。という学生がいて、帰宅後熟考うるには、
「妻鹿姓を名乗り友字が付けば、大坂の妻鹿友樵師の直系に違いない」と、伊藤師はようやく合点がいったそうな。
そこで話しが弾み、急遽調査行が実現したというわけである。
大阪では、友樵師旧蔵の古琴琴書の調査にはじまり、書画幅の類いを一通り拝見し、大いに眼福の余録にあずかったのであるが、また古琴の鑒定と二、三面の絨扣の新調、琴絃の張り替え、妻鹿家総勢四名に対する琴の初学指法の手ほどき等々、得難くも有意義な数日を過ごさせていただいた。
よみ
さらには、在京の友美嬢は、友樵師遺愛の明琴「鳳鳴秋月」をもって、正式に愚門で琴を学ぶようなられ、簡単な琴の調製法まで意欲的に修めようとしておられる。
友樵師遺愛の他の琴も百余年の長き眠りから醒め、往古を語りはじむるこのごろではある。
今期復刻の『東皐琴譜正本』は前記諸般の事由により、三百年の長きにわたり公刊されぬまま、今日に至った稀籍中の稀籍と、おおかたはご理解いただけたものと思われるが、この書を琴界に公開し、かつまた巷間に呈し、いやしくも同心の学者の容易く閲覧できうるようにせんことについては、僊界の東皐心越禅師、人見竹洞先生、杉浦琴川君、しかして小野田東川居士にも異存はなかろうと思わる。
四先師の魂魄よ
暫し眠りより覚め
平成に於る人間の小事を臠(みそなは)し 嘉(よみ)し賜へ
而して安堵し給へ
䇮再三百年間の長き時日を要したが
吾人は竟に「琴譜」を四師の御霊の前に奉る
斯く玉譜に瑕瑾を残すこと而已躊躇せらるが
庶幾(こひねがわ)くは不才の工作をも寛恕せられ
今『琴譜』を嘉納され賜へ
しかして安堵し給へ
吾人は茲に至り
漸く 日本琴道の原點に立ち返るを得る
喜びを以て琴を撫し弾じやふ
燃れば 愚者大半の人生も
蝸牛角上に於るに等しき
東京琴社三十一年間の微細なる営みも
強ち無益の事にはあらで
又 明日への絲桐の根とも思ほえやう
喜びを以て琴を撫し弾じやふ
巻頭に新目を附し、もって読者の便に供さむ。
平成十三年辛巳歳
中秋心越忌望日
東京本郷台小研究所
於東京琴社瘦蘭斎
坂田進一識
以上が日本版『東皐琴譜正本』の新跋で、次が、昨二〇一六年の仲秋節に、中国版を出版した折の識語および補足の年記である。
二〇一五年乙巳重九当日
為中国版改訳
於東京湯島男陂下弊研究所
該「新跋」をものしたはもはや十六年前のことだが、やや冗長の嫌いあり。ここに重複をいとわず、越師の琴譜上梓発願から成就までの三百年におよぶ経緯と真相とを、年譜を参考に簡潔に整理し箇条書きにする。
「東皐琴譜正本成立と周辺略史」
▲八歳で仏門に帰依した越師、少時江浙一一帯修業のおり琴事に触れる
▲一六七〇年四月八日、越師三十二歳にして印可をうけ、曹洞宗(中国)寿昌派第三十五世の正宗となる
▲一六七一年、杭州永福寺住職拝命
▲禅余、地の文人名士らと、琴を含む文事交友を盛んにすること五年間
▲長崎唐寺の要請に応じ、古琴数面と琴譜をも携行し、一路日本へ
▲一六七七年正月、長崎上陸以降自作の琴操七首に諧音填詞し、「扶桑操」草稿とす
▲通算五年間、長崎錫駐
▲翌年仲秋、日本曹洞宗『永平大清規』中の音曲に関する戒律を知り、以降、表だった琴事を控える
▲一六八一年七月、徳川光圀公の庇護をうけ、江戸は小石川水戸藩邸内後楽園に仮寓、密かに人見竹洞と杉浦正春(当時数え十一歳、後の琴川)に琴の初学を伝授する
▲越師の琴譜集を『東皐琴譜』と命名、上梓を計画するも諸般の事情でならず、竹洞へ後事を託す
▲一六八三年四月、越師水戸城下へ移り、天徳寺改修に備う
▲この間八年間、竹洞への琴学伝授は専ら尺牘応酬による
▲一六九〇年仲秋、越師天徳寺開堂(後の祗園寺)後、寺務繁多から微疾をきたす
▲一六九五年九月晦日、越師入寂
▲三ヶ月後の翌年正月、竹洞落胆し病没。また琴譜の編纂ならず、すでに元服した琴川に委ねらる
▲琴川、幕府要職の傍ら、琴譜を苦心編纂すること十五年、寵愛する側用人東川(越師が水戸へ去った翌年に生まれる)に命じ、琴譜(減字譜)部分は明朝活字体に倣い、越師と琴川の序跋を臨模したものを中核として清書させる
▲一七一〇年秋八月、ようやく原稿が整うも、翌年の正月琴川急逝し、またしても琴譜の上梓ならず
▲この間、杉浦家当主が替わり、時にあやにく東川の男丹下に不祥事あり。若主君の勘気を宥め、東川を庇護する故主君はすでになく、ために東川一家は杉浦家を逐われる
▲琴譜稿本は杉浦家、副本は人見家にと、東川の手元を離れてすでに無く、以後三百年間、琴川撰『東皐琴譜』は「幻の琴譜」として、人間容易に閲覧できず
▲さいわい東川は駿河台在旧主君の朋輩御先手頭三枝氏に助けられ、その役宅の一郭を借り、やむなく瞽者の箏曲階梯に倣い、親しく主君に従学した琴曲を教授し、糊口をしのぐ
▲湯島聖堂昌平黌に近くもあり、寄宿生や礼楽に興味を抱く書生など、おいおい門下生が増し、東川撰『東皐琴譜』「初学十六曲」を定む
▲一七二二年四月、荻生徂徠(東川門)『琴学大意抄』『幽蘭譜』など撰す
▲一七三五年二月、上野宮の言上により、東川は上古絶えたる琴の名手として徳川八代将軍吉宗公の上聞に達し、平安期以後断絶した雅楽中の琴復興を命ぜらる
▲同年秋九月、東川編『雅楽琴譜』
▲一七三八年秋九月、吉宗公下命の雅楽中「琴」の復興なり、江戸城白木書院(故琴川は御書院番組頭歴任)において管絃興業あり、群臣の供覧を許され、東川らに白銀をたまう
▲一七六三年、勤王の魁山県大弐『琴学発揮』、『琴学正音』を撰す
▲師承により、必要に応じ写された『東皐琴譜』抄写本は枚挙に暇なし
▲刊本には以下の四種あり
①一七七二年鈴木蘭園版『東皐琴譜』
②一七八二年大江玄圃版『東皐琴譜』
③一七九七年菊池遷甫版『東皐琴譜』
④一八二八年児島鳳林版『東皐琴譜』
* * * * *
▲二〇〇一年秋九月、越師寂滅後三百六年目にして、坂田進一編『東皐琴譜正本』、東京において公刊
▲二〇一六年七月、越師示寂後三百十五年目、『東皐琴譜正本』上海音楽出版社から中国版公刊、仲秋節に越師所縁の杭州永福寺において出版記念式開催さる
「心越禅師と高僧碩学の交游」
月刊『禅』明治43(1910)年7月
浅野斧山編 一喝社刊
近代における越師顕彰第一の功労者は、無論、明治41(1908)年に祗園寺第22世となった浅野斧山(1866~1912)である。同師につきて連載中また触れようが、先立つ明治35年曹洞宗大学林(現駒澤大学)教授を拝命し、当時、すでに宗門一の硬骨漢と評されていた。
寺に遺る越師遺品に感激した斧山は、やむにやまれぬ報恩心から、倉卒の間に解読選別して『東皐全集』を編纂、開山の鼓吹禅をどうにかして明治の世人に知らしめ、いまひとたび祗園寺を隆盛にせんものとした。
病躯に鞭打ち、各地「青年僧の会」の説教師となり、また雑誌『禅』『和融誌』など精力的に関与寄稿しつつ、翌年の「全集」発行に向け東西奔走し、六月に公刊し終えるや転錫、幾ばくもない翌年47歳の夏六月、その尊い生涯を疾駆し抜けたのである。
心越禪師―高僧碩徳の交游(二) 浅野斧山
▲禅師と永平録
戊午1678仲秋閱永平錄喜懷元祖佩印還鄉標立宗旨
希公為法道元玄,證入寧宗嘉定間。
列座有因分次第,參隨不讓個中禪。
尊宿機關曾逗漏,天童密意若符筌。
時驚雨雷波翻地,日恐歸槎浪拍天。
幸喜龍神重擁護,茲感大慈現乘蓮。
片帆頃刻如飛至,返棹本國築之前。
初創法幢龍象集,始弘至教實開權。
雲興雲湧津梁廣,指示群迷志不遷。
慧日洞明亘今古,慈風常扇德俱傳。
而今水乳喜同調,雖不成詩綴一篇。
▲禅師と鰲山、( 龍泰廿世)
鰲山其徒黙玄(元寂なり)を使して、禪師を長崎に問い、曰く、百尺竿頭轉身去、翁作赤肉舊時容、虛空昨夜夢醒後、黒漆崑崙不見蹤、師之を見て直に微して曰く、百尺竿頭の一句脱酒に任すも、箇の赤肉〓を迸出して、渾崙と石渾崙と旦(しばらく)道へ如何が是の不見蹤、更に不見蹤の處に
向て試に道へ看ん、支無對、乃師依韻して歌ふ、『從識全身堪吐露、本來如幻即真容、時有大地光赫々、有時無處不留蹤』玄回報して曰く越者善詩恐は具眼の師にあらざる乎、鰲山もまた少しく之を怪む、後法華三味塔の銘を読で拍手三歎して曰く、果然此老當時第一の大善知識なり豈起て請せざ
るを得んやと、即夜に同志相議し、基徒普雪を長崎に還す云々。
▲禪師と風外焉智( 賴岳寺)
禪師の長崎に厄に遭ふ聞き、直に往て禮謁し、鰲山等と相議し、また黄門公にに法の外護を約し、再び崎に至て、禪師に告げ、爲に一歳六度、江崎の間を往來し、遂に天徳に請す、禪師初會に風外を請して第一座に充つ、開堂の日、出で問ふ、山門跳て佛殿に入る時如何、師曰、看々、智曰看破了、師棒を行す、智曰霊龍額下の珠を撃碎し、鳳凰五色の髄を鼔出す、師曰長老好生看、智曰從來此漢を豫着す。
▲禅師と今井弘濟(今井小四郎なり)
佐藤市郎兵衛の書、荐りに至る。師のヒ茵無違なるを知り、且つ登蘇山にと上京の本末を審らかにす。遠懐慰を為す。
師東都に赴くの一事、寡君朝廷の執事と之を議す。其の初めや事成り易きがごとし。僕と玄術と共に欣欣期を俟つ。
既にして事、澀滯に涉り、奸邪、隙を構へて之を沮むがごとし。數日して朝廷果然たるを得たり矣。
向に玄術及び僕、師並に素文兄と相約せし旨、崎土に檗僧の徒有り、密かに檗山に白す(曇瑞なり)。是の故に渠、師の箇事を承當するを要して、吾が事を敗らんと欲す。是れ不幸の濫觴なり。
洞家の舊招提、龍泰・萬松等、志洞派を興するを存し、師の東來を聞きて、喁喁誦說す。
於是、遠近の洞僧、雷同して街に滿つ。是れ檗山の徒の怏然として之を悅ばざるの大本なり。
密計已に渠が爲に知れ、洞僧且つ祖右せば、渠安々勃然たらざるを得んや。
茲に鐵牛と稱する者有り、千忌萬猜、邪策を權門に獻じ、禍心を抱て窺覦す。事の澀滯は此に關す矣。
然も其の源頭を究むれば、則ち洞僧の失計なり。何とならば師、唯孤身東來、淡然無聲ならば、渠此嫌疑を起さざるなり。
僕師と密計を泄す勿れと約せしは、元此を慮りし故のみ。
渠師の德の將に振ひ洞僧影從せんとして、連雞の勢を察し、喬木を兩葉に摘まんとせしのみ。
始は瑞聖寺に抵るを以て名となし、渠拒みて受けず。又從ふて遊說し、當路の人をして猜疑の心を起さしむ。
是の故に事、速やかになり難し、且つ唇舌を費やして後に定まるのみ。
目下、事已に蹉跌し、亦た別に深圖を設けて以て本志を遂げんとす。
師、宜しく且つ崎土に歸り、以て時の至るを待つべし。
僕、書を澄師・素文兄に寄せ、備へて此の事の本末を述べ、且つ師の爲に周旋して、以て安頓の趣きを託す。
亦た當に牛公に奉書し、以て師をして憂戚の思ひ無からしめん。寡君も亦た將に深意有らんとす。
羊叔子言有りて曰はく、「世間の如意ならざること十に七八恒なり」と。蓋し此を謂ふなり。
吁(ああ)!僕、師をして幽閒の地を得しめ、安靜に日を度らしめんと欲す。
65
△目次TOP↑
2017年3月
瘦蘭齋樂事異聞 第155話
東皐心越禅師と琴(きん) 十 東皐心越禅師伝補遺(一)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
おりしも「東皋琴譜の成立」が一段落したところ。筆者四十年来の肩の荷が下りた気がし、このところ脱力感甚だしく、タダでさえ怠惰愚鈍質であるのに加え、日夕茫洋とアラヌ方向を眺める自分にフト気づく。
これまで江戸から大正期、日本流琴派の主流として学ばれた「心越流(派)」と、越師の伝記に関しては、浅野斧山編『東皐全集』所収の「東皐心越禅師伝」、「心越禅師略年譜」などを参考に自論を展開してきたが、明治末年に斧山師が越師を紹介するまでは、越師の事蹟などを一般人士が知ることは稀で、あるとすれば専ら「琴事」を中心としたもの、ないしは「文事」に偏る傾向があった。これは越師を「本邦琴学中興の祖」と崇めた新楽閑叟ら琴客の筆によるところが多く、宗教的見地からしても、禅宗内一部の僧侶が越師に興味を示すのみで、当然大勢ではない。
さらには越師を開山とする曹洞宗寿昌派、その本山寿昌山祇園寺と各末寺などが幕末期に衰退しゆくにともない、新生明治期ともなると、さすがに越師の事蹟もようやく忘れさられようとしていた。
明治四十一(一九〇八)年、曹洞宗宗務部は同宗きっての硬骨漢といわれた浅野斧山を、北関東の教勢および祇園寺再生の要として住職として派遣したのである。これは前号キャプションに少しく触れたところで贅言を避けるが、斧山師は荒廃した寺を復旧するため、『東皐全集』を早急に編纂し、仏事を主に必要に応じて諸事を依頼したのである。
先ずは檀徒および各界の人士に越師の事蹟を知らしめ、いまひとたび祇園寺を隆盛にせんものと、門外漢である「琴事」については、越師の琴流を汲む貴族院議員の何礼之に原稿を依頼し、さらにその伝から、越師将来明朝製「如意」の修理を、当時随一の漆工名人といわれた青山碧山に依頼した。当然、この碧山も心越流琴客の一人であったからである。
斧山師箱に墨書して曰う。
此品破損不忍見、
一日謀東京下谷入谷町住、
上品破後不忍見一日阿東京一下卷入格时住青周来的发於己的成田第三日夜柚丹間修覆蓋翕者禅師琴田之疎而岳清巧也聊表根恩意矢
調整四六年九月
青山周平(号碧山)翁欲修覆、
翁欣然諾之、
日夜抽丹悃修覆了、
蓋翁者禅師琴曲之孫、
而兼嗜漆巧也、
故聊表報恩微意矣、
明治四拾参年九月
斧山識之 印 十七代改之
()内筆者
行末の「十七代」は後考を俟つが、この後、すでに百年の時が経過しているため、図版のように、再度「蓮「頭」部が剥離している。
該例を含むこうした斧山師による一連の事業が、幕末以降、近代における越師第一次の紹介事実となり、その約半世紀の後、越師を中国と欧米に向け紹介した功労者が、碧眼の文人と渾名された高羅佩となるわけであるが、これらはすでに本連載61~68回に触れてあるところ、東京の公使館仲間で知音となった孫伯醇か和製の古琴を貽られたことで、俄然越師に興味を抱き、公務の合間に日本で蒐集した越師の資料をもとに、東京で編纂し、戦時中の重慶において、商務印書館から一百部のみを自費出版した『明末義僧東皐禅師集刊』中の「東皐心越禅師伝」では、越師長崎港上岸に関し、「日本来由」などとは多少異なる見解を示したのである。
拙稿連載をものするにあたり、常住座臥、筆者の繙く日本側基本的資料が次掲の書籍である。
全般『越師詩文集』(仮題。未刊抄本)
琴事『閑叟雑話』 新楽閑叟編(『絲桐談』とも。未刊抄本)
全般『東皐全集』 浅野斧山編(一九一一年東京一喝社刊)
全般『明末義僧東皋禅師集刊』 高羅佩撰(一九四四年重慶商務印書館刊私家版百部)
他に解放後の中国出版物としては、
琴事『歴代琴人伝』査阜西編(一九六五年北京中央音楽研究所刊百五十部内部参考資料)
全般『旅日高僧東皋心越詩文集』陳智超編(一九九四年北京社会科学院刊)
などがある。
ただ、ここに便宜上「全般」と示した資料も、概ね「全集」というにはほど遠く、越師残存の詩文の他断簡零墨など、向後の編纂を俟たねばならぬこともちろん、概して越師の生涯の全容に迫ることをえない。
なんとなれば、大半は日本にある資料の写しと異なる手による抄本であって、新資料とてはそれほどになく、唯一、和漢の資料を俯瞰できる
ことがその利便性である。
拙稿この数次連載中、越師が長崎奉行所から東渡の経緯を問われて提出した「日本来由」、その改訂版ともいえる「日本来由両宗明弁」(伝来の臨済・曹洞の禅宗二派のいい)を半ばとしたまま、解語の華ならぬ眼が他に転ろった結果、改めて通覧すれば、杭州・上海・長崎と東海を跨ぎ、いかにも筆は逡巡躊躇、前後は重複するはで極めて読みニクい。
これら筆者が愛読者諸賢に対し改めて慚謝するところであるが、胸中溢れる憶念のためと、只管ご寛恕を乞う次第。いずれ項をまとめ上梓する際には是非とも再編し、一目瞭然たるものとせねばならないとの猛省一方ならぬこのごろではある。
以下、高羅佩「東皋心越禅師伝」より、越師の長崎上陸部分の抜書きで、前記「日本来由」と重複する部分であるが、なるほど、斧山編のものとは多少異った見解を示している。
※本稿引用文()および句読筆者責
…禅師抵岸。訳官既詢悉為曹洞嗣法和尚。不属臨黄。困悩殊甚。
既恐奉行不許登岸。又慮住崎臨黄僧侶。或有異議。因動師自承臨黄。暫棄曹洞。師固辞之。訳官以師不諳日語。告日本官吏。謂師属黄檗派。因得登岸。其後事発。一時集矢於師。
而不知当時実訊官詭詞也。謁澄一於興福寺。遂駐錫焉。…
詢悉とは、問い、かつ詳細を知ることである。越師担当の唐通事は、すでに師が曹洞の正宗であり、臨済正宗(栄西・白隠派下の臨済宗と区別するため)ともいった黄檗宗に属さぬことを知って困窮甚しく、もしもそのままであれば長崎奉行所は許さぬであろうし、また唐寺の僧侶からも異議が出る。さすれば越師の上岸は叶わず、(※畢竟、戦乱の故国へ強制帰国させるも気の毒ならばと)越師に曹洞を捨てて改宗するが良策と勧めたが、越師はこれを固辞。そこで通事(たち)はまだ和語を解さぬ越師をよそに、役人には越師は黄檗宗の人である(偽り?)とし、越師の長崎港上岸が許されたが、後に事は発覚し、一時、越師に批難の矢が集中してしまう。しかし、これは唐通事の詭弁から発したことで、その後澄一和尚に弟子の礼を執り、ようやく興福寺に錫駐することになった、とある。
そうとすれば、唐通事の詭弁とはあるものの、筆者は(※)内のよう、通事咄嗟の善意と捉えたいが、惜しくも唐通事執務上の諸事記録である『唐通事会所日録』は、寛文十三(一六七三)年から貞享四(一六八八)年までの巻数が佚書で、ちょうど越師来日の延宝五(一六七七)年部分が欠落し、その詳細を知るをえず、他資料に拠らねばならないのである。
東皐心越禅師将来「如意」
浅野斧山「箱墨書銘」祗園寺蔵
高羅佩撰「東皐心越禅師伝」部分
『明末義僧東皐禅師集刊』 重慶商務印書館刊
明末義僧東皐禅師集刊
〔小字注〕…山崎二尹。甫建大譯小譯。順治十年。大譯士死。官監補銓。復以彭城仁左、柳屋治左、歐陽總右、何仁右、充小譯部。後接踵起家者。殆十数人。不能盡載。』東皐抵崎時。此輩作譯官。乾隆年間之譯。見袖海編一害(清白史集、昭代叢書、小方壺齋與地叢鈔均載。)著者汪鷗。字翼倉。號竹里。錢塘人。乾隆年間往還長崎。至於長崎中國人生涯。此編殊詳。其事見清畫家詩史。
詢客査貨。備極苛綳。稍涉違礙。卽多方留難。商旅往往以賄求免。而沒收商貨。拘捕旅客。甚或株連及於船主與中國僑商之事。仍數見不鮮。惟譯官。
大多爲中國人。對東渡商。大抵有郷土之情。輒以權宜開方便之門。禪師抵岸。譯官既詢悉為曹洞嗣法和尚。不属臨黃。困惱殊甚。既恐奉行不許登岸・又慮住將臨黃僧侶。或有異議。因勸師自承臨黃。暫無曹洞。
〔大字本文〕師固辭之。譯官以師不諳日語。告日本官吏。謂師屬黄檗派。因得登岸。其後事發。一時集失於師。而不知當時實譯官詭詞也。師旣登岸。謁澄一於興福寺。遂駐錫焉。
〔小字注〕興福寺爲寓崎江浙商入所創建。先是。萬歷年間。有江浮梁人劉覚者來崎。於四十八年(一六二〇)出家。自撰法名日眞圓 結菴市東。時江浙客商及商船主。欲創一寺於崎。便僑商念佛。兼厝旅櫬。爱共鳩貲。卽眞圓隱居之所。建興福寺。其側又媽姐娑堂。擧眞圓為寺之一代。崇禎五年(一六三二)眞圓示寂。如定【釋默子。江西建昌人。】嗣爲二代。如定博識多才。説法之餘。復授日下八以磚之術。今長崎眼鏡橋。卽如定所建。【是橋乃日本拱式構造之始也。】崇禎十四年(一六四一)。如定退職。逸然【釋性融。姓李。杭州仁和人。】嗣爲三代。逸然善畫。負盛名於日本。是時客商復款。重新寺宇。以如定隱居之所。修建東盧庵。植以桃梅。籬以修竹。有流泉怪石之勝。作爲歷代寺主隱居之所。境内有東明八景。頗負名於世。逸然退職。順治十一年(一六五四)隱元嗣爲四代【釋隆琦。姓林。福建福州人。萬曆二十年(一五九二)生。以家貧。十歲掇學。耕樵爲業。後至普陀山禮觀音。於是崇佛心起。歸閔謁鑑源襌師於黄檗山。剃繫受具。後至經山寺。舉爲費隱禪師之嗣。順治九年(一六五二)日本後光明天皇欲創一禪林。命逸然渡中國而聘隱元。順治十一年(一六五四)隱元抵崎。歳六十有三也。始住錫於興福寺。十五年往江戶。謁徳川家綱將軍。蒙寵最厚。藩王羣臣。多歸依。將軍請師建寺於山城之宇治。順治十八年(一六六一)隱元於此創黃檗萬福寺。而爲日本黃檗宗之…
25
△目次TOP↑
2017年4月
瘦蘭齋樂事異聞 第156話
東皐心越禅師と琴(きん) 十一 東皐心越禅師伝補遺(二)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
越師琴伝補遺の筆を執るつい昨日まで、長崎にあったと思われたい。
越師が悶々のうち長崎に錫駐した五年間。唯一琴を通じて「海外の知「音」と心を許した何可遠(諱兆晋)の項を続稿すべく、ただ、すでに用意した原稿と前後するため、彼処に到ろうとしてなお逡巡している。
有り体にいうと、筆者にとっての長崎というその土地柄が、何故か昔から気になるその訳が、越師のことはさておき、研究分野のひとつである「中国伝来の文人音楽」(一に琴学、二に明楽、三に清楽)の窓口が、なべて長崎であることは無論、それ以上に多くの伏線があることに自ら気づくのである。
郷土史家の宮田安先生ご存命中に何度も長崎に足を運ぶうち、先生自ら崇福寺や興福寺、他の寺々、ご自宅書斎はおろか、何家墓所などご案内くださりもし、「吉宗」などご相伴したが、何と崇福寺門前に到るその道すがら、東京在住の何氏末裔と偶然に出会うのである。その不思議な偶然に吃驚したのも三十余年前のこと。
しかしてこれが縁となり、何可遠(続稿)遺愛の「明代古琴」を、筆者が修理することになるのだから…。
《以上琴学・本連載他号参照》
前後する。長崎に明楽を伝えた魏氏の四百年忌に、研究者の一人とし崇福寺の式典に参列し、西山での魏家の墓参を終えるや、これも宮田先生が谷の向こう側の高みを指差し、
「彼処が心田菴です」
と教えてくださるではないか。
《以上明楽・連載46~5参照》
そんなこんなで、わざわざ長崎経由で上海まで行ったことが幾度かあるほどだし、すでに物故された月琴で著名となられた中村キラ師に、聴き取り調査などで大変お世話になったこともよき想い出となっている。
もともと粋筋の人で気っ風のよい姐御肌のキラ師である。諏訪神社に近い簡素なお住まいで、筆者も存じ寄りの、もと駐日オランダ大使の故高羅佩(ヴァン・グーリック。本連載6~68参照)先生から頂戴したという水世芳夫人家伝の「明琵琶」や、天華斎製の月琴、「月琴譜」などを拝見したり、乏しい内からお寿司を振る舞われたり、あるときなどは、筆者が上海に行く飛行機の時間に合わせ、当時の大村空港まで行かれ、そこで上空を通るであろうはずの飛行機を見送りくださるという、往時の花柳界では檀那? を長崎港まで見送る習慣があり、それを踏襲し倣おうとする、そんな義理堅い、実に頭の下がるお人柄であられた。
《以上清楽・連載74~77・92~94参照>
で、いっそのこと事情が許せば、いずれ自分も長崎市内の古家にでも移住し、二胡や月琴でも教えて余生を送っても…、とまで考えたほどだが、如何せん今となっては、自らの残り時間と蓄えはアマリにも僅少で、残念ながら諦めざるをえない。
さて、奇しくも、わが十代から三十代までの箏曲の師でもあり実の祖母とも慕った故米山種刀自の祖母が、かの楠本イネ(慣用)媼となり、その女系を略記すれば、
灑(たき)→稲(いね)→高(ただ)(多賀)→種(たね)→君(きみ)
となる。(敬称略)
母親と早く死別した筆者にとり、種刀自とその愛娘君小母さまのもとに毎週のように堀の内妙法寺裏道を抜け、馬橋の灸裏手の梅里在のお宅に稽古に通えば、それこそ身内のように親身に接してくださり、その折々に伺ったお話と想い出などの尽きることはないが、いまに印象に残る出来事を二、三想起してみよう。
○シーボルトは幕末期の本邦にはじめてピアノを携え、長崎周辺で採譜した俗曲を、帰国後に『日本楽譜』(一八七四年ウィーン再刊)として出版したほど音楽にも大変造詣が深かった人で、これがその情報提供者かつ、三絃の能手で出島に出入りした瀧の心を掴んだ一因でもある。
○その娘のイネも音曲を好んだ人で、彼女が本邦女医の草分けであったことは、読者諸賢の大方衆知するところ。明治十七(一八八四)年の医術開業試験を、すでに五十七歳の稲は受験せず。ために女医第一号免許の栄誉を他に譲り、産婆を開業して後、娘の高(はじめタダ、後にたか、多賀とも)を頼り再上京して医術を廃し、麻布の異母弟ハインリヒ・シーボルト邸で明治三十六(一九〇三)年八月、七十七歳で没し、長崎の海雲山晧臺寺墓地に埋葬された。
○ある日イネ・高母娘の屋敷の軒端に、尾羽うち枯らした座頭が身を潜めているので、見かねて世話をするうち、これが山津(確かに種刀自はそういっておられたが、三代津山か?)検校と判り、その縁で秘曲を学ぶことができた。と少年の筆者はいつも聞いていた。その真偽はともかく、高にとっての医術は長崎を出るための口実で、実は箏三絃の修業をしたかったのだという。
○絶世の美女高は箏・三絃を善くし、シーボルト門第一といわれた秀才三瀬諸淵と結婚するも死別。山脇泰助男爵と再婚し、権大教正の位を得て皇室に出入し、東京大空襲のときには祖母イネ伝来の天明年間製の古箏を抱え、火を避け逃げ回ったという。
○かく音曲に堪能な母のもとに育っ種(明治十六年生、香蘭女学校第一期生)は米山鉄道技師と結婚後、朝鮮その他の鉄道敷設のため諸赴任地で過ごした。傍ら母親譲りの箏曲を薄くしたが、故石川平七早大教授夫人となった愛嬢君女の婚家先馬橋梅里に晩年に身を寄せ、女系伝承の天明箏を愛奏していたし、筆者との稽古や合奏の合間には、いつも百年前の話に次から次と花が咲き、それこそ、上野彦馬写真館と明記した、被布を着たイネが椅子に腰掛け、娘の高や、孫の種が傍らに立つ古いガラス銀板やアルバムを見せられ、すぐ間近にある歴史上の事実に、しばし時の経つのも忘れたものである。
○ある日種刀自がいうのに、
「これは祖母イネ形見の、箏や三絃の絲を切るための絲切り鋏ですが、記念に坂田君に贈呈しましょう」と古い小さな「和鋏」をくださり、
○またあるときは、わざわざ押入の奥から、「これは、母高形見の胡弓で、すでに壊れ、虫に食われてはいますが、坂田君は胡弓も弾かれるので、何かの参考にはなるでしょうから、これをも進呈しましょう」と。
○さらには、
「『ズーフ・ハルマ』もあるはずだから、出て来たらそれをも進ぜます」との数々の温情、しかも、帰りがけには必ず君小母さまは、懐サビシイであろう学生をそれとなく気遣われ、ソット小遣いを包み、さらに手に余高価な参考書があれば、神保町の書店までも同道され、これを購入してくださったりと、枚挙に暇ないほどお世話になったものである。
○また長崎や明治以来の家柄同士の繋がりから、その末裔方で時の名士たちとも同席させていただくことも多く、ある日、長崎学の権威で長崎高商の名物教授武藤長蔵先生のご子息、武藤富雄先生がお見えになるというので、必要だがどうしても入手困難な高羅佩編の琴の資料があり、その訳を話しお願いすると、
「掲載される紀要を探して、コピーして送りましょう」
とのご親切心から、後日、本当に送ってくださった。というのもついこの間の出来事のようである。
「何可遠墓塔」聖寿山崇福寺墓地
今号では何可遠の琴事についてはまだ深入りせぬが、「先考可遠何府君塔」の墓石は、故人の愛した二つのものを尊重し、慰霊のためこれをもって装飾されている。
その第1が「琴」を象ってあること。
第2には周囲に「老梅樹」を刻んであり、ために生前の故人が如何にこれらを好んでいたかが知られようもので、しかして、この「琴」をして来世でも梅花に因んだ名曲、例えば「梅花三弄」や越師将来の「瑶芳引」(梅花とも)などを弾かんことを象徴していよう。
「心田菴茅葺門と石段」長崎市史跡
本文に記したその当時、片渕にある何可遠の別墅「心田菴」は個人の所有で調査したくもできなかったが、2012年に市に寄贈され、整備の後に町内に管理を委託しているという。
一度、係から筆者の研究所宛に菴の音楽に関する問合せをいただいたが、その後は立ち消えとなっていた。
27
△目次TOP↑
2017年5月
瘦蘭齋樂事異聞 第157話
東皐心越禅師と琴(きん) 十二 長崎余情 一
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
越師の琴事を核に、その楽伝を補う心算が、瓊浦に惹かれてわが胸中の筆も流連するか…。二、三といいつつなお想いは尽きず、箏曲や文人音楽などにかこつけた私事で貴重な行間を浪費するはまことに恐縮ながら、これを己だけのものとして彼方に持去るのも忍びず、あえて副題を「長崎余情」として前号を延く次第。
○我が箏曲の師中、種(たね)先生は邦楽界との柵(しがらみ)がなく、ブ厚い角爪で弾く古生田流の悠揚恬淡たる藝質そのままを人にしたようなお方で、さもありなん、山脇男爵令嬢を出自としながら、世が世ならばの我意を通さず、しかも長崎の血を引く万事質素な典型的明治の女性でいらした。
○姉上が夭逝、母堂山脇夫人高嫗が昭和十四(一九三九)年夏に逝去されるや、同年、健気にも女手一つで母堂の「記念誌」を出版された。
該稀覯書を筆者も長く借覧していたが、複写せずにお返ししたため、記憶に曖昧な部分があり、いまに多くの残念がある。
○種師に筆者が就いたのは、師の七十から九十代にかけての足掛け三十余年ほどで、次項と前後しつつ、和田から徒歩で堀之内妙法寺を抜け、梅里の種師のもとに通ったが、師の高齢と、後のちょうど筆者に時間的余裕がなくなったころ、惜しくも百歳を超えられて亡くなられた。
○そんな一九六〇年代半ばのこと、苦楽生の筆者を見かねた楽友H君。彼は杉並和田の杉並療養所(救世軍立。連載中改稿予定)のX線技師で、傍ら藝大の中山先生(愚生は山本正人先生)に就いてコルネットを学ぶ能手であったが、その誘いで面接を受け、バイトとして採用され、当初は通うに遠いため、所内の①古い寮の一階に寄宿し、二階のH君との音楽三昧にも耽っていた。
○後に療養所向いの②立法寺(りっほうじ)和光苑(已にない)に移り、引き続き療養所の一等奥まった⑫霊安室で週に何度かある、お通夜と告別式(キリスト教)でのオルガン奏楽と、学校紹介の新設「横浜ドリームランド」楽隊のバイトと学業の両立と、そこまでは良かったが、勉学の傍ら、横浜の奥地から毎日終電で帰るため疲労困憊、ついに身体の不調をきたし、楽隊は辞めざるをえずゲルピンとなってしまった。因みに当時の体重は四十八キロであった。
○後には大本山小湊誕生寺の大僧正にまでなった立法寺の③佐藤老和尚と大黒さま。月々の部屋代にもこと欠く貧乏楽生に苦言一つなく、剰(あまつさ)え風邪で寝込めば、逆にお見舞金をくださる。その上、筆者の部屋はさまざまな騒音の元凶で、寺の和光苑では練習しようにも鍵盤が置けず、霊安室葬儀のパイトを兼ねた演奏で、天国入口のドア前? で練習を重ねたその成果か、後の音楽家人生に大いに役立ったものである。また、もと救世軍日本司令官であった⑬植村中将の夫人から、「ボーイ、ボーイ!」と可愛いがられた筆者は、英国留学の際に買われた「コンサティーナ」(本連載11参照)を恵与され、これが珍しい英国式手風琴に親しむ契機となったのである。
該オルガンは病院建替えで不要となり頂戴してすでに半世紀。一見鍵盤部はなんともないが、外見は筆者同様?かなりポンコツ化し、いまはオサガリで賢妻が愛奏している。
また、さすがに金管を長時間練習するときなどは、憚ってすぐ目の前の療養所の⑨車庫を閉め切ってお借りするという、そうした周囲の温かな善意に支えられての学楽生活。何とか理想を捨てず、次項を含めて学楽併行し、梅里の種師のもとにも足繁く通っていた。
▽そのころのことで、前号「魏氏明楽」を伝えた家系長崎鉅鹿家墓参の遥か以前の、奇しき因縁話となる。
前号稿頭に「中国伝来の文人音楽」を挙げたが、より正確を期すには以下のように訂正せねばならぬ。すなわち、往古雅楽以外の、
「江戸期中国伝来の文人音楽三種」
一、琴学(明末東皐心越禅師再伝)
二、明楽(明末主に魏之琰将来)
三、清楽(唐館寄留の清人伝承)
なる、なべてが長崎を通じて流行し伝来の音楽を、田邊老先生などの影響を承け、青年期の筆者はすでにこうした楽類に病育に入っていた。
▽当時、こうした音楽を研究する学者はあるにはあったが、概して机上の楽・学であり、そうした中で傲岸にも、唯一筆者のみは資料に準拠した成果と、ある程度の水準で鑒賞に堪えうる演奏力を有す、との自負すら持っていたのだから始末に悪いが、そうし音楽的根拠となったのが、
・和漢洋の古典音楽を学んでいる
・日本学で唐音(とういん)の基礎を知る
・絲竹楽器の基本奏法を知る
・琴学、明・清楽各種の基本資料を有す
などである。
▽寺近辺を逍遥中、立法寺児童公園の脇に⑥鉅鹿(後に転居)という表札を見かけてはいたが、ナ何と! まさかにこれが筆者が学び尋ねる鉅鹿家とは露知らず、指呼数秒の間、同じ2丁目16番地に時を同じくして、しかも同じ空気を吸っていたのだからして、「畏るべし天の配材!」。
▽一見何でもないことのようだが、すでに絶滅した古典音楽を研究するものにとり、伝承された古楽譜と古楽器、さらにはこれを演奏する人間が存在せねばならず、そこから天蚕を手繰るような作業と綿密な考証を経た上で、はじめて「実存の音楽」と結実なるもの。古楽研究にはフィールドワークと原資料は必要不可欠で、一等重要なものとなる。
▽考えてもご覧じろ、萬金を積み、この世のどこを探し求めても「魏氏明楽の実態」に迫ろうものに巡り会うことなどできようはずもなく、それこそ宝籤に当選するより低い確率であったのだ。
もっともこの時は当選しなかったのだが、後々、改めて鉅鹿氏との好(よしみ)を通じ、こうした見えざる赤い糸の摂理を知るにつけ、いかに偶然とはいえ、神ならぬ身ながら天恩を謝し、いまもって感涙に咽ぶところである。
▽何ものも継続すれば、必然的に結果にたどり着こうが、数十年間迂回した上、却って遠い長崎の地において鉅鹿家の四百年忌に導かれ、以来、鉅鹿氏とは楽友以外の左党でも良友? となるにおいておや。
「長廣山立法寺」日蓮宗
もとの⑨杉並療養所(次図参照。現ブース記念病院)の⑧百年古木の多い、鬱蒼たる杜だった側から新たに撮った写真で、眼前の立法寺脇門前地こそ、筆者の暮らした②和光苑跡である。
左手④山門脇が寺が区に貸していた⑤児童公園で、そこに⑦中野駅発療養所行終点のバス停があった。
都会に在りながらチョイとした森林浴気分に浸れるので、よく早朝深夜には付近を散策したものである。
「療養所のオルガン」現弊研究所蔵
療養所⑪チャペルにあった、ヤマハ製7ストップの普及型リードオルガン。葬式の都度⑫霊安室に運んだ。
「杉並療養所と周辺」
1963年 空撮
① 療養所の寮
② 立法寺和光苑(坂田)
③ 立法寺佐藤住職方丈
④ 立法寺山門
⑤ 立法寺児童公園
⑥ 鉅鹿(おうが)家
⑦ 療養所前バス停
⑧ 療養所の社
⑨ 療養所車庫
⑩ 療養所本館
⑪ 療養所チャペル
⑫ 療養所霊安室
⑬ 植村救世軍中将宅
写真中央の烏帽子型の敷地が療養所主要部で、なんでも当時の話では、都内であるにもかかわらず、図の左右と上部(⑦以南除く)を合わせ、そ
の面積は約1万数千坪以上あると。もって距離感が知れようか。
25
△目次TOP↑
2017年6月
瘦蘭齋樂事異聞 第158話
東皐心越禅師と琴(きん) 十三 長崎余情 二
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
▽二〇一三年秋から逐年、鉅鹿家の明楽関係遺品を粗方整理(図版)す歴史的現場に筆者も立ち合い、而して甚(いた)く憶うよう、半世紀以上前の接点でいち早く気づいていれば、その時点でのさらなる原資料の散逸を防ぎ、いまに遺せたものをと。
ただ、いまさらそれを悔やんだところで詮無いことで、まがりなりにも『東皐琴譜正本』に続き、現在、貴重音楽遺産「魏氏明楽」を本国にお返しすべく、上海音楽学院で教えていること、まずはこれをもって好とせねばならぬであろう。同様に因果は巡ろうものであるからして…。
○種師に戻ろう。ご夫君米山氏先逝後、気のおけない愛娘君小母夫妻と、梅里清見寺裏手のしもたやにひっそりと暮され、今もその辺りの光景がわが瞼の裏に焼き付いて離れない。
○青梅街道沿いに昔あった鹽瀬の支店近く路地を一歩入ると、左手に清見寺のお地蔵さんが見え、右がタバコ屋の店先で、通りがかりに見るとはなしに見ると、オジさんが店番している。実は、これが噺家の故三代目三遊亭圓右師で、師匠の古今亭今輔ゆずりの「オバアさんもの」を持ちネタに、婆さんに成りきるため女装し、高座の往還に時たま筆者とスレ違えば、「ニヤリッ!」とされたもの。禿頭の彼はその当時、テレビの石鹸のCMで話題となっていた。
○その先が種刀自の仮寓した石川家で、都会の片隅の路地に面した枝折戸を入れば、左右に丹精した折々の花々が咲き乱れ、出迎えてくれた。
〇酷暑の時など各家に冷房などはない時代であった。上半身裸となり洗面器の水道水でタオル、拭き足らねば水浴びして一丁上がりてなもんで、食事はおろか、小庭に面した廊下に蚊遣りでスイカをいただき、二階の八畳間で練習したりと、家族の温もりに等しいなか、それは楽しい夢のような時間を過ごした。
○あるとき、種刀自がとても嬉しそうに集合写真を見せられ、
「久しぶりに長崎に行き、祖母のお墓参りをしてきました」
という。見れば、そこには巨漢石川先生ご夫妻と一緒に、杖を持った笑顔の刀自が写っていて、当然、介助あってのことではあろうが、あの急で狭い晧臺寺の坂道をどうやって登ったのか?と推量したものである。
○前述のごとく筆者が種師に就いたのは、刀自の七十から九十代にかけての断続的な三十余年である。その後師が百歳を超えられたときには、区役所から表彰されたこともある。九十歳に近いころも、頭脳明晰、身体なお矍鑠かつ健脚で箏を弾かれるのを唯一の楽しみとしておられたが、そのころから外出時には杖に頼りだした。
○ある日、大森山王在のご親戚某邸訪問の御供で「長磯箏」を拝見したときなど、山王の坂道をゆっくりながらも自力で登られたので、総じて坂の街長崎の血を引く女性は健脚、ということで、ようやく前項に合点がいったような訳である。
○種刀自は百歳を超えられて亡くなられたが、その間、家庭の温もりに触れずに暮らす苦楽生にとり、種師母娘の陰日向のない(「愛は表裏あるべからず」ロマ書十二章九節。ラゲ神父訳)温情はなににも代え難く、その摂理を今にして思えば、何と幸運な巡り合わせ、果報者であったことか。それにつけても、遺品や写真などを早々に探し出さねばならぬ。
⦅▽明楽○箏曲。以下清楽・俗曲⦆
時は二〇一七年の三月一日、筆者は久しぶりに長崎寺町晧臺寺墓地の風頭山傾斜地に面し、ここに前々号稿頭へとようやく繋がる次第。
汗ばみつつも同じき急坂を登り、イネの眠る墓に詣で、さらに青息吐息、ようやく瓊浦を眼下に臨む風頭山頂の展望台に出れば、いかにも心地よい雨上がりの涼風である。ツイツイ釣られ、我知らず蛮声を張り上げたも宜なるかな。
「春は三月」
春は三月風頭(かざがしら)
金比羅参りの賑やかさ
野に出て遊ぶ人々の
酒の機嫌で凧(ハタ)揚げる
押すやら引くやら
繰れるやら凧喧嘩
帰りはカラ瓢箪
家の土産は粔籹(おこし)米
該歌は、月琴などを伴奏に唱われた長崎のお座敷に伝わる俗曲で、「清楽」中の名曲「紗窓(さそう)」を、大正年間に長崎の花柳界に出入りした土地ッ子文化人古賀十二郎らの間で替歌に改作し、以来今日まで洒脱なお座敷唄として定着している。
紗窓とは、薄い紗のカーテンがかかった窓のことを指し、その窓の内側にいる美人を暗示するが、題名と次掲する本歌「紗窓」歌辞の唐詩とはまったく関係がないのである。
「江戸期中国伝来三種の文人音楽」の窓口なべてが長崎で、その一種をいまもって俗に「明清楽(みんしんがく)」とは総称するものの、何度か連載中にも触れたよう、本来「明楽(みんがく)」と「清楽(しんがく)」はまったく別もので、厳密に区別されるべきジャンルであるが、遺憾ながら、現在「琴(きん)・箏(そう)」の字を混用し、あたかも「牛・馬」の分別をせないと同様、いたって無頓着な慣用語と成り果(おお)せてしまっている。
かく清朝伝来の俗曲「清楽」中の名曲「紗窓」や「九連環」が、幕末から明治にかけて大流行し、清楽や邦楽にまったくといってよいほど親しみの無い一般庶民、すなわち楽譜を読まない階層にも、こうした旋律が浸透普及していたお陰で、誰しもが暗誦(そら)で「紗窓」の旋律を唱えた、その証左の替歌が関東大震災直後に流行した「復興節」となるわけだ。
元来、詩作内容は曲題に準拠するものだが、何より七絶の名詩かつ歌辞の寸法が、「紗窓」の単純な旋律にピッタシであったという、この二つの理由から紗窓の曲牌を利用したということが解るが、ただ、もとの歌辞は、幕末の長崎を通して盛んに学ばれた「唐音(とういん)」であり、片仮名をもって表記し唱われることは、いまも長崎黄檗宗の唐寺で、看経や梵唄の際に用いられる発音と同様である。
「紗窓」
シュイキャアニョ テー アン フィ シン
誰 家 玉 笛 暗 飛 声
サン ジ チュインフォン マン ロヲ ジン
散 入 春 風 満 洛 城
ツウ エエ キョ チョンウエンツエ リウ
此 夜 曲 中 聞 折 柳
ヲー ジン ポ キイ クウ ヨエンツイン
何 人 不 起 故 園 情
(一、李白「春夜洛城聞笛」)
ラン リン ムイ ツイ ユイ キン ヒヤン
蘭 陵 美 酒 鬱 金 香
ニョ ワン ジン ライ フウ ペイ クワン
玉 杯 盛 来 琥 珀 光
タン スウ チユウジン ネン ツィ ケ
但 使 主 人 能 醉 客
ポ ツウ ヲー チユイズウ ダウ ヒヤン
不 知 何 処 是 他 郷
(三、李白「客中作」)
「魏氏明服」鉅鹿家旧蔵
本家蔵になった、紛れもない魏君山華やかなりしころの明服である。往時これらをして明楽を演奏していたが、ただ、君山が京師に出る以前の「魏氏明楽」は、いまだ鉅鹿氏家庭内部の「家楽」にすぎず、以降も長崎の地では定着せず、まして普及化することもなかった。
「明服衣巾図」『魏氏楽器図』より 弊研究所蔵
すなわち、これらの明服を雛形とし、魏君山高弟の筒井景周『魏氏楽器図』(安永9[1780〕年刊)が編纂、所収したことが解ろう。
「魏氏楽器図粉本草稿」鉅鹿家旧蔵
『魏氏楽器図』には内部の油印本と公刊本の2種があり、その準拠となった大本が該粉本である。
27
△目次TOP↑
2017年7月
瘦蘭齋樂事異聞 第159話
東皐心越禅師と琴(きん) 十四 長崎余情 三
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
さて、清楽「九連還」とともに大流行した「紗窓」である。以降、こうした旋律が徐々に日本化する過程でできた俗曲が、「法界節」やら「春は三月」で、ことに前者は明治二十(一八九〇~)年代から唄われだし、折々の風俗や時事を織り込んで歌詞が続々と新作され、月琴と尺八、胡琴もしくは胡弓(邦楽器)や三味線、また稀に瑤琴(本邦考案の清楽器。この代りに日本の短箏などに金属絃を張り、縦に抱えて歩きながらも弾いた)などの楽器を交えた三、四人編成で流して歩き、全国を行脚する旅回りの「法界節」の小さな一座は明治の三十年代まで流行した。
その「九連還」一節中の唐音、
サン シューナ ライ キャイポー カイ
双 手 拿 来 解 不 開
とある句末の「不開(ポーカイ)」部分が耳につき、次第に「ホーカイ」と訛ったことからできた題名は、音の似た法界坊(一七五一~一八二九)などの説もあるにはあるが、時代が逆行するため明らかに成立しない。
「法界節」
秋の野に
鹿の鳴き声たどりつつ
山路遥かに踏み入れば
ササホーカイ
吹き来る嵐に
散り乱れる紅葉ばの
錦照り添う
牛込の誰が名付けた神楽坂
参詣帰りのホロ酔いに
ササホーカイ
フトすれ違う
解語(ものいう)花の残り香が
カラン コロン
(しん)
東台や
兵(つわもの)どもが夢の痕
辿りゃ小径に束髪の
ササホーカイ
雄叫びならねど
今日も稽古の声がする
レ、ドーランドーでしょか!
(しん)
※東台=上野の山
「九連環」とならんで大流行した前記「紗窓」は、幕末から明治期にかけて清楽が全国を席巻する一因ともなった曲で、その単純明快さのゆえ、一般大衆が無意識に口ずさんだメロディーの一つとご紹介した。
大正十二(一九二三)年九月一日の関東大震災で壊滅的な大被害をうけた際、演歌師添田唖蝉坊(一八七二~一九九四)、一説には唖蝉坊男の知道(さつき。一九〇二~一九八○)が、誰しもが唄えるメロディーとしてこの紗窓に着目し、急遽、東京の復興を応援すべく下記の歌詞を充て、焼土と化した東京の街頭に、ただ一挺のヴァイオリンや月琴を持って立ち、楽譜のない歌詞だけの廉価版冊子の歌本を販売した。
試みに「紗窓」原譜と「復興節」の歌辞を対照(図版五線譜参照)してみようか。
「復興節」
家(うち)は焼けても 江戸っ子の
意気は消えない 見ておくれ
アラマー オヤマー
たちまち並んだ バラックに
夜は寝ながら
お月さま眺めて
(※同様、添田唖蝉坊創作)
エエゾエエゾー
帝都復興
エエゾエエゾー
田舎の父さん 火事見舞い
やって来て 上野の山に
ビックリ仰天し
アラマー オヤマー
こいつぁー 魂消た流行もの
焼けたか焼けねぇのか
どちらを向いても 屋根ばかり
帝都復興 エエゾエエゾー
カカアが亭主に 言うようは
お前さん シッカリしておくれ
アラマー オヤマー
今川焼さえ 復興焼と
改名してるじゃないか
お前さんもシッカリ
エエゾエエゾー
亭主復興 エエゾエエゾー
この春、筆者が丸山の老舗料亭「花月」に遊んだ折、偶々その一角に展示されていた図(図版参照)があった。その奇遇に驚きもしたが、何よりもまず、画中の姉妹、平井連山の中年期の凛とした姿と、いまだ二八のころであろう梅園の華奢な容姿にハッとしたのである。
恐らくは連山の要請で、この画題のもと西山完葉に依頼したものであろうが、「月宮殿」は、後に梅園も自ら編纂した『清楽詞譜』に収めた曲で、唐の玄宗皇帝と楊貴妃の秘話をモチーフとした白楽天の「長恨「歌」を題材とした比較的大曲である。
貴妃の歿後、玄宗はその死を悼むあまり、道士を頼み幽冥異なる仙界に遊び、貴妃と思しき仙女と再び契りを交わし、詩中に「裳羽衣曲」を再現し、抜粋したサワリの歌辞、
八七月七日長生殿
夜半人なく私語の時
天に在りては
願わくは比翼の鳥となり
地に在りては
願わくは連理の枝とならんと
天長く地久しきもありて尽く
この恨みは綿々とし
て尽くる期なからん…
と、玄宗の絶ち難い思慕の情を歌って後半の合奏部へと移行するのだが、大抵は右記前半のみを演奏し、後半部は割愛することが多く、左記する歌辞から入る。
「長恨歌」白楽天
リイ コン カウ チュイジ ツィンイュン
驪 宮 高 處 入 青 雲
スェンロ フヲンヒャウチュイチュイウェン
仙 樂 風 飄 處 處 聞
驪山の離宮は高きにありて
雲に隠れるほど
天上の音楽が風に乗り
そこここから聞こえくる
ワン コヲ マン ウ ニン スウ チョ
緩 歌 慢 舞 凝 絲 竹
ツィンジ キュンワン カン ポ ツヲ
盡 日 君 王 看 不 足
漁陽そのユッタリとした歌や踊り
笛や箏の音も美しく
玄宗は終日眺め飽きず・
イュイヤン ピイ クウ ドン ティ ライ
漁 陽 鼙 鼓 動 地 來
キ ポウ イ シャンイュイイ キョ
驚 破 霓 裳 羽 衣 曲
突如としてそこに
漁陽の陣鼓が地を揺るがし
羽衣の曲を楽しむ日々は
無惨にも砕け散った…・
ちょうど図版にある「賛」の部分が歌辞のサビ部分にあたり、以下後半部へと移行するのだが、それにしても、かく完璞画の一幅の絵画により、瓊浦の良宵は、さらに忘れがたい想い出とったのである。
清楽「紗窓」俗曲「復興節」対照五線譜
1986年6月坂田進一採譜
「月宮殿演奏図」西山完璞画賛
長崎「花月」資料館蔵
西山完璞(1834~1897)また一に完瑛。大坂生れの画家で字を子受、通称は謙一郎である。
父の西山芳園に画法を受け、人物花鳥を能くするも、その遺作は少なく、その端正な画風は得難いものとされた。
後藤松陰門に儒を学び、播州明石藩に仕えた。
△目次TOP↑
2017年8月
瘦蘭齋樂事異聞 第160話
東皐心越禅師と琴 十五 長崎余情 四(附・続長原梅園)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
この三月、長崎風頭山から眼下に興福・晧臺の両古刹と瓊浦を望めば、筆者の胸中去来するもの頻りで、東帰した後も、いまだ心ばかりは彼の地に留連する。
すると夢裡に彼我の境を超え、いましも入港せんとする唐船の甲板には、訳ありげな僧侶と従僧数人、および他の船客が、半ば不安と半ば希望の面持ちで見守るなか、船長の下知のもと、大勢の船員たちが上陸準備に余念なく、ことに主僧たる某禅師は、上陸以降に起こるであろう長崎での新生活と錫駐に胸膨らませている。等々、筆者脳中の一齣は走馬灯のように駆け巡るのである。
かくも越師の事蹟に仮借しながら、江戸期伝来の中国文人音楽としては最後となった「清楽」中の「月宮殿」から、「紗窓」とその日本化したお座敷唄「春は三月」におよんだのだが、しかし、肝心の「九連環」がいまだしものため、今号冒頭には該譜を掲げ、試みに、愛蔵する『清朝俗歌訳』という稀書を参考に、和漢の両歌辞を挙げ、しかる後、瓊浦の美形を心裡に宿しつつ、前に漏らした越師東渡の前後を再度ナゾろうとの心算であるが、果たして如何なることに...。
「九連環」
八九つ輪をくさりし指かねのこと也。これを題にして、云なしたる、流行体のことなり。
一、
看々兮 賜奴的九連環
九呀九連環 双手拿来 解不開(キャイポーカイ)
拿把刀児割
割不断了 也々々呦
[又]
一、
見よ見よ
ワれに賜ひし九連くわん
きうとハ九ツくさりの
ゆびわの事よ
もろ手かけても解ほどかれぬに
かたな取て ワれともはなれぬ
エゝなんとしやう
二、
誰人兮 解奴的九連環
九呀九連環 奴就與他 做夫妻
他們是個男
男子漢了 也々々呦
[又]
二、
たれかこれ
ワが九連環をとかぬか
きうと八九つ
くさりのゆびかねの事よ
ふとした人と夫婦にならん
かの男しう 男よおとこ
エゝなんとしよう
三、
情過河 在岸的妹住船
妹呀妹住船 雖然與他 隔不遠
閉了双門難
難得見了 也々々呦
[又〕
(※以上唐音略)
三、
河わたろう岸におるのハ
いもかふね
妹とハ いもとののれる舟
かれとをくはなれねと
かねて両門とざしたり
さして逢れぬ
エゝなんとしやう
如何にも該歌辞により、「九連環」が日本全国の庶民間で大流行したという、その理由がうかがわれるではないか。
清楽ついでの余勢をもって、こうして越師の行間を借りるうちに図らずも「花月」で邂逅した美形「平井梅園嬢」(後の長原女史。一八二三~一八九八)の人物につき、ここに読売新聞記者の鈴木光次郎編『明治閨秀美譚』(明治二十五年刊)の記事全文を引用し、少しく補足すれば、いまとなっては、地下家伝に類する清楽家系を知るための、多少とも読者諸賢の参考となるであろう。
該記事は、読売新聞社が各界女流名家「十六名媛」から、読者を対象としてその好むところに従い各々投票せしめた結果であり、「十六名媛当選
者」中、日本音楽家として、その最高位の得点に輝いた「長原梅園女史」なる鈴木光次郎の作文である。
なお、拙稿「喫茶と音楽」(本連載第9~第94参照)と多々重複するも、
敢えてそのままとする。
◎日本音楽家
九十五点 麹町富士見町 長原梅園
(4)日本音楽家長原梅園女史
梅園女史は骨董商故長原弥三郎の妻にして、文政六年下谷の黒門町に生まる。
幼にして書画管絃の道を好み、書を篠崎小竹(在大阪)に、画を父均卿に、三絃を杵屋藤吉、清元佐賀次、富本豊多野に、琴(※箏)曲を中村勾当(大阪)に学び、且最も南画に長じて、号を仙姑と呼び、姉連山と並び立て、江戸の女画仙と称せらる。
之より先、禅僧荷塘一圭と云ふものあり。奥州の産にして、出でゝ長崎崇福寺に住す。偶々来遊の清人金琴江(江芸閣、朱柳橋、李少白等と我国に同遊するもの)が、清楽に堪能なるを慕ひ、密かに幕医曽谷長春に其指法を学ぶ。五裘渇の後、二人相携へて江戸に来り、一圭は大工町に、長春下谷に住したり。
此時に当て幕府の禁制厳にして、楽器の如きは、稀に好事家の密弄するに過ざれば、其伎(※技)を学ぶもの纔かに、文人宮沢雲山、守村約(※鴎嶼)、市川米菴、頴川春漁等の数輩に過ぎず。女史素と文雅を好むの癖あるを以て、傍ら此技を修めんと欲し、姉連山と曽谷長春の門に入て之を習ひ、書画音曲を以て西丸、及び薩、土、藝等の諸大侯に出入し、長原家に嫁して後、又姉連山と大阪に赴き、内平野町に在て和清の楽を教へ、明治に至りて門弟数百千を得た
是に於て女史以謂らく、清楽の趣味最も佳なり。今より姉と東西に並立し、以て大に此道を拡張すべしと。乃ち独り東京に来り、富士見町に在て、数百の後進を養ひ、従来愛玩する所の、
提琴(初代清音斎の製作にかる)
月琴(初代天華斎作にて、逸雲、卓文君等の二名器と同時に渡来せるもの)
琵琶(明代のものにて、藤堂侯より賜る所)
の四名器に依て、前赤壁、琵琶行、翠春亭、飲中八仙、桂殿秋、満宮花、獅子序、天仙子、雪花飛、玉台観、歩々嬌、涼洲令、以下数百曲を著し、偶々友人故鏑木渓菴(頴川春漁の門人にして、鏑木雲潭の弟、何れも文人なり)の遺流、偶々渓菴派と称するに依て、人亦之を称して梅園派と云ふに至る。
女史又古器鑑定に能あるを以て、第三(※回)勧業博覧会の開設あるに方り、選ばれて審査官となり、数百の楽器を鑑別して、其名愈々高し。
又、書画を以て、泉、尾、濃、信、両備、播、丹の諸州を徘徊し、岡田半香、後藤松蔭、森一鳳、中西耕石、田能村直入の諸大家は、皆其相識にて、今尚ほ多く其遺墨を蔵し、自から其筆鋒を学んで画ける東坡抱腹の書画は、当時南画の秀群として世に知られたり。
因に記す右の伝記によれば、梅園女史の長所は日本音楽にあらずして、他にあるもの如く思はるれど、本社は投票の結果より、同女史を当選者となせしまゝゆゑ、読者幸ひに咎むること匆れ。(※印、句読筆者)腕
清楽「九連環」俗曲「法界節」対照五線譜
1973年4月 坂田進一採訳譜
1=E♭ 中速
「九連環」
「法界節」(実音A♭)
はるかぜや にわにほころぶ うめのはな
うぐいすとまれや このえだにササホ
そちがさえずりゃ うめがものいうここちする
ホケキョホケキョ
「寒梢帯月図」梅園仙姑画『清楽詞譜』巻一より
長原梅園の代表的著作としては、該『清楽詞譜』二巻(1884刊)と、『月琴俗曲今様手引草』一巻(1889刊)、さらに『月琴俗曲爪音之余興』と、その続編なる四譜がある。
37
△目次TOP↑
2017年9月
瘦蘭齋樂事異聞 第161話
東皐心越禅師と琴 十六 長崎余情 五(附・続々長原梅園)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
東皐心越禅師(越師と略す)の来崎を引きずりつつ、拙稿はそのまま留連し続けている。
清楽の崎陽伝来当初、まだ珍しい外来楽器のひとつであった「月琴」である。
月琴では主に清楽曲牌が弾かれていたのだが、幕末から御一新を経てすでに半世紀になんなんとする明治中期ともなると、清楽先達の大半は崎陽の地を離れざるをえず、皮肉なことにその結果、日本全国にその枝葉は広まることとなる。なかでも鏑木渓庵や連山・梅園姉妹らの有力清楽師の影響力下、清楽は邦楽と折半するほどの勢力を持つに到ったが、さらなる需要もあって邦楽曲、ことに民間の俗曲を月琴用に手付けした曲集が編纂されはじめた。
ただし、その編纂のためには邦楽を熟知していなければならず、その点、知識豊富な梅園女史や渓庵門の富田渓蓮斎などが最適任者であったのである。
長原家に嫁して後、又姉連山と大阪に赴き、内平野町在て和清の楽を教
へ、明治に至りて門弟数百千を得たり。…中略…今より姉と東西に並立し、以て大に此道を拡張すべしと。乃ち独り東京に来り、富士見町に在て、数百の後進を養ひ…(傍線筆者)
と前稿に引用したよう、姉の連山は大阪に残り、梅園のみ東京は麹町富士見町に移居し、清楽と邦楽を教授しだす。
さすが東都一流の骨董商に嫁いだ梅園女史である。その長い藝歴ばかりでは得られようはずもない古楽器四名器をも入手し、寛政十年生まれの二十五歳以上も歳の離れた実姉連山(一七九八~一八八六)刀自とともに、本邦清楽の揺籃期を受け継ぐパイオニア姉妹となったのである。
ここに富士見町在時の明治十七(一八八九)年刊行になる、図版「梅園女史清楽稽古図」をつぶさに観察してみると、文政六(一八二三)年の生れの梅園女史の年齢に関して、該図版が描かれた時と数年の差を勘案しても、束髪に花飾りをあしらい子女を教える姿を見る限り、いまだその色香の褪せぬ容姿は、とてものこと六十五歳を越した老墟には見えず、恐らく該図版は東都移転当初のもので、三十路前後の姿を写したものと思しい。
該図をつぶさに観察してみると、富士見町の梅園邸であろう、前栽を見下ろす二階座敷で、五名の良家の子女風の年若な門弟が座していて、窓側の年嵩から内に順に並び、あるものは譜を畳に置き、またあるものは譜を手に持ち、心なし微笑みつつも、この稽古を楽しんでいる様子である。
この娘たちを相手に、梅園が三種の清楽器を用意し、「月琴」を持ち、かつ唱って指導している。その傍らには「清笛」と「提琴」が置かれるが、この楽器は前稿に引用文中にいう唐渡りの名器ではなく、見るからに一般的な稽古用の楽器のようである。しかし、いかにもこうした清楽稽古の様子から、清楽(月琴)はすでに日本化し、しかも明治新風俗然としていることが見えてくるのである。
後には、すでに清笛や胡琴の名手となった梅園の実子長原春田が成長してあり、母堂梅園を輔けつつ、傍ら文部省音楽取調掛に奉職するという、押すに押されぬ清楽大家となった長原家でもある。
一方、大阪でも連山亡きあとに二代連山をたて、もとの平井家姉妹は、ここにともども明治を代表する清楽一家となりおおせたのである。
ただし、この連山梅園両姉妹は瓊浦で清楽を学んだのではなく、江戸は下谷黒門町で学んだこと、越師と清楽には「唐音」を除いては、直接の関係性はないことなど、読者諸賢におかれては、くれぐれもお忘れなきよう…。
さあ、ここで前稿冒頭を繋ぐため、とても珍しく貴重な音盤をご紹介し
愚門で月琴を学ぶI兄が、先日、珍しいものを入手したとのこと。それは明治末年に長原梅園社中が演奏した清楽レコード(図版参照)
清楽演奏レコード「御所車」長原梅園社中
COLUMBIA PHONOGRAPH CO.
NEW ONDON
GRAND PARIS,1900
清樂 御所車 笛、胡弓
最寄發明・高聲精亮・
1901
で、曲は俗曲の「御所車」である。
一九〇〇年パリ・コロムビアで録音した原盤をロンドンの同社でプレス、さらに一九〇一年に日本コロムビア社が発売した片面盤レコードである。録音を聴けば、その演奏レベルはなかなかのものだが、ラベルに肝心の演奏者個人名はなく、「清笛」と「胡弓」との楽器名だけで、当然のこと清笛は梅園の男で名手春田のものであろうし、また「胡弓」なる音色も日本のそれではなく、また清楽の「胡琴」でもないため、その低い音程から推察して「提琴」であろう。ならばこの音は梅園が唐渡りの名器をもっての演奏か? いやいや、梅園女史は明治三十一(一八九八)年の没であるからして、一九〇〇年録音では辻褄が合わないが、梅園女史の最晩年に外国録音技師が来日し、その二年後にパリで原盤を製作したとなれば、すべて合点できることとなるが、ここに断言を避け、「精査を俟ち」、余行があれば、これ以降の雑誌記事などを勘案し、改めて梅園親子をご紹介するということで、いったん筆は梅園女史から離れ、閑話休題となる。
る。
近年、日中両国間において、頓に研究されるようになった越師の琴事である。この「楽事」を主とした他愛ない記事の拙稿連載も、すでに越師のテーマは十五回を数えて年余にわたるため、ここで諸賢、ことに中途からの愛読者方のため、これらを整理し、再度かいつまんでご紹介することとしたい。
父蒋氏と母陳氏は、次子が授かるよう西湖の観音像に願かけしたところ、霊験あらたかに越師を授かり、そこで報恩のため時期をまち剃髪させたという。
これが後に中国曹洞宗寿昌派第三十五世正宗となる東皐心越禅師である。
「中国における越師前半生の三十八年間」
当歳 俗名蒋興儔
浙江省金華府婺郡浦陽蒋家次男坊に生まる
八歳 蘇州報恩寺にて剃髪
雛僧として仏学と座禅を主に修行に励む
一三歳 さらに銭塘江流域を中心に師を尋ね道を求む
二〇歳 曹洞宗中興祖覚浪道盛に調し日夕参禅
二九歳 覚浪師命で皐亭山に上り翠微闊堂下で参禅研鑽
三三歳 導師翠微闊堂に印可さる
中国曹洞宗寿昌派第三十五世正宗東皐心越禅師
三八歳 杭州の西湖を望む永福寺住職となる
錫駐すること五年間
六月二十日一番南京船で杭州湾を船出 船主彭公尹
おりから越師の道誉を伝聞した、長崎唐寺の一、興福寺住職の澄一道亮(一六〇八~一六九一)から、越師を後任に迎えたいとの邀請をうけ、杭州湾を船出した船は、淡い希望を抱いた越師と従僧らを乗せ、明末清初の「三藩の乱」を避けつつ、わが延宝五(一六七七)年の正月、ようやく長崎港にたどり着くのである。
「梅園女史清楽稽古図」
『月琴俗曲今様手引草』より明治17(1889)年刊
該手引書はその名のごとく、とくに月琴で本邦の俗曲を弾くために編纂されたもので、同じく梅園編の『爪音の余興』(正続)とともに、当時としてはかなり需要があった俗曲集である。
新撰『月琴調』初篇
明治11(1878)年刊
大阪の書肆村井清兵衛発兌の、現存稀なるかなりの珍本で、当然、これも平井連山と梅園姉妹が長く阪府で下帷し清楽普及に尽くした結実である。
愛好家が清楽から離れて、チョットした俗曲を手軽に楽しむため、月琴用の工尺譜が陸続と刊行されはじめるが、該譜が記念すべき刊本俗曲集の嚆矢となる。
27
△目次TOP↑
2017年10月
瘦蘭齋樂事異聞 第162話
東皐心越禅師と琴 十七 長崎余情 六(附・又長原梅園)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
梅園女史からいったん筆を離れはしたが、筆者の終活とて、湯島の小研究所や他所に配備していた古楽器と楽譜、楽書群を整理すれば、もう一幅連山と梅園の合作が出来するではないか。
そこで、又ゾロ越師には「お控え願って」、前回図版が間に合わなかった、月琴俗曲譜『爪音之余興』前・後編と併せて、ここにお目にかける次第。
該軸の図柄は唐数寄の代名詞ともなった幕臣川勝蓬仙(一八二八~一八七五)ばりの唐竹と太湖石をあしらったもの。当時いかにも清楽大家として名をなした姉妹渾身の合作は、清楽愛好家のみならず、名だたる貴顕垂涎の的であった。というのは強ち売り絵ではないため、かなり入手困難であった理由による。
清楽曲牌を出て、月琴で本邦俗曲を弾くために編纂された譜を『今様手引艸』(一八八九刊)とはよくいったもの。その名の通り、過半近くが唱歌からとったもので、俗曲はあまりに下卑たものを捨て、唱歌と交互にするという配慮である。
試みにその目録を列挙してみよう。
上段「唱歌」 下段「俗曲」
一、春のさかり 二、十日えびす
三、庭の朝顔 四、だるまさん
五、あさひの光り 六、金時
七、よし野山 八、花は上野か
九、軒端に匂ふ 一〇、龍田川辺
一一、見わたせば 一二、夕立や
一三、遊べ 一四、淀の車
一五、君が代 一六、我が恋は
一七、おりなす錦 一八、海晏寺
一九、桜か桃 二〇、梅は咲たか
二二、百蓮 二二、露は尾花
二三、仁は人の道 二四、桜見よとて
二五、鏡なす 二六、川たけ
二七、三番叟
二八、千じょうや
二九、新あしかり
三〇、そで香炉
三一、汐くみ
三三、雛鶴
前号でご紹介したよう、該譜は良家の子女たちが学んでしかるべき良俗譜であった。しかし、ために一般清楽、ことに月琴愛好家たちには物足らず、専ら巷間流行の俗曲を弾くため別仕立てに編纂したものが、同じく梅園編の『爪音の余興』(正・続)である。
内題は梅園の手と思しき「(月琴俗曲)爪音の余興」とあり、次丁に梅園十八番の印記が押捺され、その中心には「梅園女史」、両翼に「広寒宮裏音噴下 白玉桿中韵逸涼」なるもので、どうやら楽天癖のしからしむるところらしい。
ここについでなから、明治中期の音楽趣向を知るため、煩雑を厭わず、さらにその俗曲目録を参考のため掲げようが、現代に生きる吾人は、これらのうち、いったいどれほどの俗曲を知るや否や…、
前編「俗曲はやり唄」
一、数へうた 二、大津絵
三、同かへ哥 五、今様
四、琉球ぶし 六、今様酒徳頌
七、梅にも春 八、ゆふぐれ
九、唐詩音度四曲一〇、長き夜
一一、わがもの 一二、春は鶯
一三、夏はほたる 一四、京の四季
一五、まつちやま 一六、待乳山替歌
一七、月見 一八、浅くとも
一九、同替歌 二〇、さみだれ
二一、秋月 二二、春雨
二三、春雨替歌 二四、あら玉
二五、秋霧 二六、御所車
二七、三番叟 二八、なのは
二九、袖の露 三〇、雪
三一、鶴の声
続編「俗曲はやり唄」
一、臥龍梅 二、沖の大船
三、いたこでじま 四、仇なえがほ
五、わすれた節 六、松づくし
七、一夜あくれば 八、安宅松
九、東の四季 一〇、天人羽衣
一一、しのぶ恋路 一二、老松
一三、春のゆふべ 一四、越後獅子
一五、竹づくし 一六、朝妻舩
一七、宇治は茶所 一八、ひなぶり
一九、ほれて通ふ 二〇、京草ざい
二一、秋の千草 二二、ゆかりの月
二三、かねて手管と二四、縁のつな
二五、花のくもり 二六、こすのと
二七、紀伊の国 二八、宇の春
二九、蝶や胡蝶 三〇、北州
該譜の挿絵を描いた長峰秀湖は、三十七歳にして逝った夭折の画家で、安政六(一八五九)年に会津の長峰晴水の子として生まれ、通名を茂吉といった。
松本楓湖門に学び、明治十五(一八八二)年の第一回内国絵画共進会、同二十七(一八九四)年の日本青年絵画協会などで受賞を重ねたが、同二十八(一八九五)年に惜しまれつつ没した人である。
そこで、先ずは正編に置かれた「清楽四人合奏図」の観察である。蘭図の懸かる「床の間」前は、定番の「煎茶具」。「大瓶」に芍薬を活けるは、これも「清楽席」の常套手段である。
中央に設えた「褥」(絨毯)に座した四名、一は「胡琴」の梅園、二は「清笛」の春田、門人二名は「月琴」で、いかにも中流階級らしい上品な「室内楽」合奏の模様である。
図中、唯一吹笛する男性が梅園嫡子の春田であるというのは、その風貌(後出)と有髯から知られるが、ここに胡琴を執る梅園の手勢にご注目あれ。左手で糸巻を握っていることから、春田の笛声に合わせて曲前の調絃をしている最中と解ろうか。また、花瓶の向こうには「提琴」が置いてあり、これは春田創意になるご自慢の新楽器「鳳琴」の可能性もある。
次いで続編「桜下清楽合奏図」である。梅園が東都に再帰したは明治十二(一八七九)年四月のことであるので、畢竟、該図は墨堤辺での観桜会を兼ねた長原社中船中における「清楽席」を描いたものと思しいが、屋上に三人の船頭が長棹をさして船を操り、十人弱の船客が乗り込む中、熟視すればそのうち五人程が卓を囲んで合奏していて、最右側で「胡琴」を拉くのが梅園らしく、しかも、前譜「清楽四人合奏図」中、やはり「胡琴」を拉く梅園の調絃と同様の姿勢で、奇しくもまったく同じ構図であることが解ろう。
梅園の右側で「清笛」を吹くのは門人の女性で、右から三番目は向こう側を向いて「月琴」を弾き、四番目の女性の楽器は不詳である。五番目が男性であるので、おそらくこれが春田であろうが、「司鼓」(通常、先生役が担当する)であろうか?しかし、伏し目がちの姿勢からは、その担当楽器は特定できない。
最左の女性は「茶童役」でもあろうが、口を開けていることもあり、専門の「唱歌役」(必ず卓に向う)ではないにしろ、思わず知らずのうち、もしや演奏中の曲牌にツラレて口ずさむのかも知れず…、
イヤハヤ!、春風駘蕩たる画中かくもの好風景に誘われ、今しも、軽妙洒脱な清楽合奏が聴こえてきそうではある。
「唐竹と太湖石」 連山・梅園共作
連山と梅園姉妹による絵画は、当時から評判で、かなり需要があったようだが、現在に遺るものは僅かである。
そんな扇面を連載中にご紹介したことがあったが、該幅はいかにも清楽家姉妹好みの唐様粧した意匠と設えで、連山は「韓女連山、梅園は「仙姑」と落款している。
 『月琴俗曲爪音之余興』
『月琴俗曲爪音之余興』【上】正・明治19(1886)年刊【下】続・明治22年(1889)刊。
該譜巻頭の挿絵は長峰秀湖(1859~1895)によるもの。その略歴と図柄の説明は本文中に出だす。
19
△目次TOP↑
2017年11月
瘦蘭齋樂事異聞 第163話
東皐心越禅師と琴 十八 上州少林山達磨寺
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
いまを去るちょうど三百五十年、東皐心越禅師が両手に余る名琴と、明清版の琴譜を携えて東渡するさらに半世紀以前のこと、すでに長崎の地には福建からの魏双侯(一六一七~~一六八九)家伝の「明楽」あり、やや遅れて同じく福建から黄檗宗初祖隠元隆琦(一五九二~一六七三)禅師将来の梵唄があって、その後、九州京阪と各地へ伝播するが、ここで長原梅園女史、次いで長崎とは暫しの別れとなる。
長崎を中心とする黄檗宗(臨済正宗)の布教安定期と、中国曹洞正宗である越師の名声とが重なり、一部黄檗僧から越師の存在が疎まれることとなりゆくが、黄檗二世の木庵性(一六一一~一六八四)が、却って他宗の越師を高く評価した事実もある。ただ、そのような宗派間の軋轢を云々するは本稿の主題ではなく、また越師の本懐とするところではあるまいので、これらは省筆せねばならない。
さて、つい十月五日のこと、筆者は黄檗宗関東の要である上州少林山達磨寺で、経文の伴奏に担り、数日の後上海に至り、いまは音楽学院の宿舎にあってこの稿をものしている。
その経文の伴奏に至る経緯である。
毎年、寺恒例の「ダルマ祭り」に少数の門人たちを引き連れ、開山越師の遠忌九月晦日に近いことで琴曲を献納し、続いて三時間にもおよぼうという「喩伽焔口経」による大施餓鬼「音楽法要」に参加するのである。
因みに達磨大師の生誕日も忌日も十月の五日であるという、寺の現住廣瀬正史老師のお話しである。
達磨寺はもともと越師を開祖とする曹洞宗寿昌派の寺であったと書いたが、幕末の寿昌派(全三十三ヶ寺)衰退期に際し、同派大半の寺々が、看経の「明音」(唐音)によったことと、宗派の規範である「寿昌清規」と「黄檗清規」が酷似するために黄檗に改宗したのである。
同様、黄檗に改宗した名利達磨寺の境内で、毎年末年始に催される「だるま市」には、合わせて三十万人の人出があり、張子の「縁起ダルマ」を求める善男善女で賑わうが、そもそもの発端は越師の描いたダルマの「一筆画」があり、これをもとにヒントを得て、時の住職が周辺農家の農閑期の手仕事に最適と、張子のダルマを作ることを奨励したことから、以来伝統行事となったという。
ユダヤ系ドイツ人で、バウハウスで著名となった建築家のブルーノ・タウト(一八八〇~一九三八)が、ナチスの迫害を逃れて日本インターナショナル建築会の招聘で敦賀港に上陸したのが昭和九(一九三四)年五月。その翌日には桂離宮に案内され、その建築美を観ての静かな感動を、いち早く世界に紹介したことで知られる人でもあるが、そのタウトが達磨寺境内の「洗心亭」(もと東京農大教授佐藤寛次の別荘兼茶室紫蜂荘)に仮寓したのである。
ことの成り行きは、はじめ高崎在の建設会社井上工業社長の井上房一郎から相談された俳人浦野芳雄の機転で、浦野が達磨寺住職広瀬大蟲(一八七八~一九六八)和尚と、洗心亭管理人との了解を得た上で実現したのだが、さらにその陰には、井上の義兄唐沢俊樹が内務省警保局長であったことが幸いし、ドイツを脱出したタウトの身の安全を謀り、そのころ日独伊枢軸国三国の関係を強化しつつあった政府当局の手からタウトを護る、という配慮があったのである。
タウトはエリカ夫人と共に、昭和九年八月一日からの二年三ヶ月の間「洗心亭」に滞在し、この間、多くの学生たちに建築指導をしていたが、案に相違し、専門である建築関係の仕事がなく苦悶する中、工芸運動をも啓蒙していた井上たちが、銀座や軽井沢に工芸品店を開き、実際にタウトの作品を世に知らしめるなど、高崎の知識人たちこぞって温かく彼ら夫妻を支援したのである。
こうした由緒のある寺で、愚門O兄の縁から筆者が琴曲を献納し、また喩伽焔口経に絲竹楽器で伴奏をするようにもなったのだが、もともと黄檗の「お経」に楽器の伴奏などがありようはずもなく、いまを去る四半世紀以前、廣瀬老師の、喩伽焔口経に楽器で是非伴奏して欲しいとのたっての願いで、その施餓鬼の実地録音から、筆者が聴き取りを重ね採譜した楽譜を使用している。
そのはじめ、お経の中の極めて重要な旋律と特徴あるものなどから、徐々に曲を足して版を重ね、二〇〇六年の八月にはほぼ全曲に近くなり、本二〇一七年、最後に採譜し残した「上来召請・悉已来臨」を補填し、ここに晴れて全曲訳譜が完成したわけであるが、越師の長崎錫駐時には、図版にあるよう、すでに延宝版の喩伽経が公刊されているので、してみると、この版を越師も見ていた可能性もあろうか…。
我ら音楽家の眼からしてみれば、即興演奏でない限り楽譜があって当然のことで、訓練されたものがこれを視れば、おおよその楽想を瞬時に捕捉することができるし、あとは楽譜に記されない余白を、自己の楽才と経験から読み取る工夫があるのみである。
しかし、明代末期に隠元隆琦によってわが国に齎された中国黄檗宗梵唄の旋律は、無論、現在もすべて暗記による日本にのみ遺る貴重な音楽遺産でもあり、日東の地で約四百年の時を経るうちにも、修行僧が苦心の末にようやく身体を通し覚えてきた経文の旋律である。
地方の寺々から集約され、最終的には宇治の総本山萬福寺で修業し、各地に散った僧侶たちが、またその徒弟・小(雛)僧たちに代々これを教えるうちに、師承によりその旋律に多少の差がでて当たり前のことで、さらに数年に一度、その差を是正すべく本山の講習会で訂正し直すのであるが、それも一時的なことであって、身体で覚え、一度身に染み付いた旋律は、ほとんどのこと、一生涯直ることはなく、師匠の癖やら小節はいまも弟子の中に活き続けているのである。
道教と違い、元来、日本の禅宗では「琴瑟」を不要とし、ましてや看経の伴奏などに打楽器以外の楽器を用いるなど「もってのほか」のことで、一音楽家の観点からすれば、長いお経の旋律を覚えるに際し、「旋律譜」があったほうが覚えやすいし、これを利用したら便利では、と思うこと頻りであるが、止まれ! こうしたことを良いとも悪いともいうのではなく、つらつら思うに、宗派としても、お経を覚えるために、長の年月をかけず、多少とも早くお経の基本となる簡単な旋律を覚えやすくするため、「訳譜」を必要視したこともあるであろうし、実際に「旋律譜」を書き取り試みた僧侶もあろうが、何せ「教外別伝不立文字」を旨とする禅宗である。結果的には今日まで、楽譜を視て覚えるような不埒な考えで唱える梵唄などは必要とせず、専ら修業とひたすら忍耐で覚える方法が第一とされ、しかして、こうして覚えたお経の旋律は、俗人ではなし得ない僧侶の一生の宝として、大切に育て護られている。
【上】『喩伽焰口経』黄檗版より
延宝6(1678)年の版で、本文にある「上来召請・悉已来臨」の部分となる。
その刊行期は越師長崎錫駐時に重なり、当時、儒仏両界の需要から僧俗こぞっての唐音学習熱が興る中、黄檗宗は年々隆盛となるが、越師曹洞の寿昌派はまだ開かれない。
【中】『喩伽焰口経』打ち物譜
平成版黄檗雛僧版より
経文に楽譜は付帯せず、ただ「打ち物」の印だけがある。
⑱【有縁無縁の諸霊供養】
法界の六道、十類の孤魂
面然大士の統べひきいる声聞くのともがら
草により木にまつわってさまよう精魂
行くえ知らぬよるべなき魂
家族眷属、自他先亡、有縁無縁
一切もとろもの諸霊 等衆
〔衆相太鼓〕
惟願。承三寶力。仗秘密言。此夜今時。來臨法會
受此無遮。甘露法食
〔中座〕
上來召請。悉已來臨。大眾慈悲。齊聲嘆悼。
〔大扶座〕
近代先朝、帝主尊栄位。勲戚候王。玉葉金枝貴。
宰執中宮。姝女嬪妃類。夢断華胥。來受甘露味、
國士朝臣。經緯国時世。牧化黎民。未遂忠良志。
失寵懦獄。謫降邊邦地。戀國遊魂。來受甘露味
【下】『喩伽焰口経楽譜』 坂田進一編
平成版黄檗雛僧版より
「喩伽経」を伴奏するための楽器譜である。五線譜ではなく数字譜であるのは、僧侶の唱う経文旋律の高さがその都度変動して音程が定まらず、出た音高の各調子に瞬時に合わせられるからである。
初版はおおよそ四半世紀以前。改訂版を重ね、本2017年にようやく全訳なった。
焰口施食大法要次第
①【出頭半鐘 拝太鼓】
…和尚方が入堂し、達磨大師に対して三度の五体投地の拝礼
…大勢集った僧侶によって不思議な功徳が現れる
『僧宝讚』
①-1
センパウプスギ
僧宝不思議
シンビサンスサンスインイ
身披三事三事雲衣
ヘウブトハイツァノス
浮杯渡海刹那時
フカンインキュンキ
赴感応郡機
カンツォジンテンコンテチュ
湛作人天功德主
ケンツ キャイヘンキャイヘンウウイ
堅持戒行戒行無違
ゴキンキ シュエンヤウチ
我今稽首願遥知
チンシチャンテヒ
振錫杖提携
17
△目次TOP↑
2017年12月
瘦蘭齋樂事異聞 第164話
東皐心越禅師と琴 十九 扶桑操「思親引」
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
この十一月初頭、大阪の「蝸蘆美術館」開催の書道展の開幕式で、祝賀の意で琴曲を弾く機会を与えられた。
この展覧会の内容は、かつて東皐心越禅師が錫駐していた、杭州永福禅寺の重建初代住職で、現在は韜光寺に移られた月真法師と、京都大徳寺瑞峰院の前田昌道住職お二方による「墨跡展」で、日中国交正常化四十五周年記念「禅心墨縁」なる床しき銘をうって開催されたものであったが、十月十五日に筆者が杭州に行った折、永福寺で直接月真法師から是非にと懇望され、筆者秘蔵の唐代製の古琴を持って、祝賀演奏に馳せ参じたものである。
惜しむらくは、マスコミのネタとはならぬまでも、当日の盛大な開幕式は、静かなうちにも在京阪の日中関係者で賑わい、日中両国語が飛び交う和やかな式典であった。
何やら怪しげな中国系の美術品を扱う会社が世に跋扈しては瞬時に消えいくなか、蝸蘆美術館の館長で、同時に美術品を扱う会社社長の上氏は、大阪芸術大学で苦学した後、同地で起業した立志伝中の人で、直接お会いするうちにもひとかどの人物とお見受けしたし、大阪の中心地にかなりの規模の自社ビルを持つほどの実力があり、その社員や従業員たちに対する徹底した教育指導ぶりは、日本人の視点から見てビックリするほど行き届いたもので、そうしたスタッフ一同の立居振舞が一朝一夕に成ったものでないことは一目瞭然である。
で、高楼の控え室に案内されたとき、何気に隣室の応接間を見ると、何やら気になる扁額があるので、係りの方にうかがうと、「どうぞ、ご覧ください」とのことで、改めて拝見したのが、次なる「呉昌碩」の書である。
「蝸蘆」
偈能作篆蝸非凡蟲
共三一蘆景行高風未
登篆宝慙愧吾躬
吳昌碩篆年八十 時在癸亥十月
とあり、昌碩翁が民国十二(一九二三)年にものした、蝸牛の足蹠から篆書が生まれたとの故事から、八十にもなっていまだ至らぬわが身と、老体に鞭打つ文士の気概を詠んだ書と知れたのだが、成程! 上氏があるとき入手したこの書を企業のモットーに掲げ、その美術館命名の意義と精神を忘れぬようにと、合点点頭したようなわけである。ただ、このときの写真を所蔵者の許可なく、そのままここに図版としては出すことはならず、さらに、いま上海でこの原稿をものしているなど、篆書の名筆を愛読者に提供できず、さりとて事後承諾も大いに憚られるところで、切歯扼腕している。止まれっ、そのときの筆者の琴曲解説レジュメ―写しである。
「雁落平沙」『東皐琴譜正本』
杭州重修永福禅寺の初代で現韜光寺住持の月真法師。永福寺の重建以前から月真師の知遇を得てきた日東の一琴客坂田は、清初に永福寺に錫駐した中国曹洞宗寿昌派第三十五世正宗東皐心越(一六三九~一六九五)禅師の音楽方面の研究に長年携わり、そのご縁で、本日の祝賀演奏を担当させていただくこととなった。
心越禅師(さらに越師と略す)は稀代の「琴癖」をも有した文人肌の高僧で、東渡するに際し、中国で学んだ琴譜と古い名琴を十数面(うち数面が宮内庁に現存する)も将来したことで、日本の「琴道」が再興する。
越師は東渡後の日本で自作した七曲と、これを併せて上梓する考えであったが、自身の示寂で果たせず、琴門弟子の手により、ようやく『東皐琴譜』(正本)と命名整稿したのが、一七一〇年秋のことである。かし諸般の事情により、以降三百年間この正本が出版されることはなく、坂田が編纂し二〇一六年に上海音楽出版社が中国版を出版、永福寺にてその記念会が催され、はじめて中国に里帰りさせることができた。
該譜の越師自跋に、永福寺錫駐時の一六七一~六年の間に、琴友とともに校訂したと記している。
こうした一連の事情は、連載中に散見するので、拙稿愛読者諸賢にはすでにご案内のことと拝察するが、昔時、越師が夢見たであろう「日中文化交流」が、こうしたさまざまな人的交流の成果により、かく頻繁、かつ当然のように日常に行われるようになった今日、多少なりとも経緯を知る一隅にいるものとしては、一入嬉しいことである。
浅野斧山「心越禅師略年譜」には、越師の乗船した唐船と船主を曰い、また夢裡にも忘れぬ慈母の逝去を伝える。
大清康熙十(年)辛亥 三十三(歳) 住西湖金華山永福寺
同十五年 丙辰 三十八 出杭州城東渡乗搓 船主彭公尹
本邦延宝五年 丁巳 三十九 正月十三日着長崎港
二月延命密寺請撰法華三味塔銘
十二月廿二日母氏訃音到没後六年
以下、図版中の説明文が小さなため、蛇足であるが、改めて本文中に重記する。
琴歌「思親引」について
明末、杭州永福禪寺中興の祖となったのが東皐心越禅師で、渡日後、徳川光圀(一六二八~一七○一)公の庇護のもと、水府寿昌山祇園寺、上州少林山達磨寺の開山となった、中国曹洞宗寿昌派第三十五世の正宗である。
東皐心越禅師は、中国で学んだ琴譜を東渡に際し将来し、これに渡来後の日本で自作した琴譜(扶桑操)とを併せ、「琴譜集」上梓を計ったが、越師示寂のため果たせず、琴門の人見竹洞(幕儒)と杉浦琴川(旗本)により編纂されたのが『東皐琴譜』の「正本」(五巻)である。
その第五巻目が「扶桑操」で、全七首が収められる中に「思親引」があり、越師自跋の「歳甲子仲冬 越子泣血銘」から、貞享元(一六八四)年仲冬(陰暦十一月)の作と知れるが、三十九歳ではじめて長崎港に上陸した延宝五年(一六七七)年一月十三日で、惜しくもその年四十歳の年末十二月二十二日、母堂陳氏の訃報がようやく越師にもたらせられ、すでに歿後六年を経過していたことを知るのである。この小操により、東渡後の越師は、禅事の傍ら片時も亡き両親のことを忘れずにいたことが解るのである。
なお、歌詩ルビの「唐音」(とういん)は、もともと越師の伝えたものではないため、当然「正本」にはなく、宝暦年間前後、後人によって「正本」以外に補填されたもので、各師承により発音が異なるものである。
唐音を用いる他楽としては、「明楽」、「琴学」、「清楽」があり、また黄檗宗念経の際の唐音などがある。
※該詩の先行作に韓渥(八四四~九二三)の「宿石邑山中」詩があり、越師はこれを参考に引用したものと知れる。韓屋は、又の名を韓屋、の昭宗龍紀元(八八九)年の進士である。
(原詩)
「宿石邑山中」韓渥
浮雲不共此山齊
山靄蒼々望轉迷
曉月暫飛千樹裏
秋河隔在數峯西 (筆者文責)
以下、前稿と多々重複する部分は、読者諸賢のご寛恕を請い、いまだ中途にある越師の「日本来由」にたどり着くべく、駄文遅筆に鞭打とう。
「思親引 五線譜」
延宝5(1677)年の正月に初めて長崎港に上陸した越師。折しも日本では、そのころから黄檗宗の隆盛に従い、第一次唐様文化の浸透でより唐音学習熱が高まりゆくが、当然、曹洞越師の寿昌派はまだ萌芽の裡にある。
琴譜「思親引」詳細は本文にゆずる。
【東皐心越自作琴操】
琴歌「思親引」スゥツィンイン 『東琴譜正本』扶桑操瘦蘭斎打
黄鐘宮音(D) 稍慢速~中速
歳甲子(1684)仲冬越子泣血銘
S.S.1968.9.15.打譜
べ イュンブ ゴン ハイ トヲンツュイ
白 雲 不 共 海 東 斉
トヲンハイ マン マン ワン チェンミィ
東 海 茫 茫 望 転 迷
チョンジ スゥ ツィンジン ブ ツゥ
終 日 思 親 人 不 知
イ ジ スゥ ツィンシ ル\ ズゥ
一 日 思 親 十 二 時
イ ジ スゥ ツィンシ ル\ ズゥ
一 日 思 親 十 二 時
「開幕式における永福念順法師」
月真法師の後任で、重建永福禅寺第二代住持となった念順法師は、仏教界の琴客で筆者の琴友でもあるが、何を想って佇むのか…、その背面に投影されるのが、韜光月真師である。
23
△目次TOP↑
2018年1月
瘦蘭齋樂事異聞 第165話
「上海霊感之城」と「施拉梅尓(セラメイル)」
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
この数年、ほぼ毎月の半分ほど筆者は上海の音楽学院に行っているため、拙稿も彼の地でものすることが多いことは、読者諸賢も連載の端々に散見されておられるはず。
そんな音楽学院での小生の宿舎は、以前ご紹介したような瀟洒な古い洋館で、大抵はその一室で憩い、勉学もし、さらに寝るわけだが、長い一日もようやく終わって深夜ともなり、ことに左手が鼻の高さに来ぬときなど、なかなか寝付かれず、「夜中寝る能わず、起座して名琴を弾ず」とばかり、静かに琴を弾じたり、こうした原稿類や「楽書解題」、編曲などにチョッカイかけ、あわよくば整稿へと目論む。
そうしたうちにも、テレビの連続劇でたまたま彼の高羅佩(ヴァン・グーリック)先生原案の「神探狄仁傑」や、「包青天」(黄門さま風)といった公案もの、時代劇「神医喜来楽」、「康熈微服私訪記」などがあれば、これらを視ながらウツラウツラしだすのだが、さて、午前二時ころともなり、さすがに上海系の局が相次いで放送終了して円い実験画面となるや、翌朝の本放送開始の六時までの約四時間ほどの間、そこで途切れることなく延々と演奏され続けるのが、今号主題に絡む次なる小曲で、イタリアのエンリコ・トセリ(Enrico Toselli. 一八八三~一九二六)の作曲になる「Serenata rimpianto」(Op.6-No.1)である。
邦題を「嘆きのセレナータ」、華題を「悲嘆小夜曲」といい、聴けば大方の読者も「ああ、あれか」と頷かれるような有名な歌曲である。
その原曲原詞の大意はこうである。
若きころの恋の想い出は、密のように甘く果敢ない。夢の醒めたいまも、年少のころの心の痛手は、骨の髄まで沁み通っている。おお光よ、私を再び照らすことなかれ…。
「アイや、しばし俟たれよ!」ここまでは何でもないことなのだが、そのテレビの実験画面「上海─霊感之城」(上海市人民政府新聞弁公室―出品)と銘打った、上海市内の新旧名所場面と市民と俳優たちによる一瞬の寸劇仕立の背景で演奏される、四分ほどの歌を伴わない器楽の小編成のサロン・オーケストラによる編曲ものが、いかにもシュランメル風(Schrammeln)のマッタリした演奏であり、さらには原曲が中庸な速度で、恋人の窓辺の下で男性によって唱われる情熱的な小夜曲(セレナータ)であるに対し、この演奏はほとんど倍速に間延びさせた緩徐楽章に仕上げたロマンチックな曲想である。
すでにこれまで何千回となく聞いてはいるが、毎回、曲の最後まではほとんど行き着かず、しかも「プツッ」と尻切れトンボで切れてしまう。不思議なことだが、最後までかけて、また最初からかけ直せば気持ちが良いものをと、思う間もなくブチ切ってしまい、最後のピチカートまで聴いたことは、十年にホンの数回、偶然のことである。さらに運が良ければ、ごくタマに「わが夢の都ウィーン」や、「シュランメルのマーチ」などのウィーン土着の名曲がかかることもある。
かくして何気に上海人はシュランメル風の演奏を知らず知らずのうちに毎夜聞かされ続けているし、一昔以前の、とくに「上海老克」(サンへ、ロッカラと発音する)という、中華民国時代からの申し子で、ややイナセな江戸っ子に近いニュアンスの階層は、ごく当たり前にこうした音楽を聞いて育っているのだからして、シュランメルと上海は時空と海山隔てながら、とても相性が好いようである。
ちなみに、「Schrammel」(シュランメル・本連載10~14号参照)は、中国語では「施拉梅尓」(セラメイル)と音訳される。
ウィーン子はいう。「木陰で芳醇なワインを傾け、シュランメルを聴けば、それこそが人生至福の時である」というほどの惚れ込みようで、時の皇帝一族から庶民、ブラームス、シュトラウスII世までがシュランメルの虜となり、とくに皇帝フランツ・ヨーゼフI世の息子ルドルフ皇太子(一八五八~一八八九)は、シュランメル兄弟の大のファンでその良きパトロンであったが、惜しくもマイヤーリンクで自殺してしまい、その後、第一次世界大戦勃発からハプスブルグ家の崩壊へと時代は大きく変わり行くことになる。
この「悲嘆小夜曲」の演奏を、テレビ局の掛かりがよほど気に入ったらしく、しかもこの小曲とこの方法を上司が放映を許可し、以来、上海とこの曲は一体不分化して来たわけで、そうこうするもう何年もの以前に筆者が最初にこの録音を聴いたときの驚き、「何と、シュランメル風であることよ」というイメージは、いまも忘れえず、恐らくはウィーン系の小楽団によって演奏される音源であろうと、その後、東方テレビ局の友人に訊ねたり、八法手を尽く探し求めはしたが、いまも音源は曖昧模糊のうちにある。
そのため、結局は筆者自らがこの音源を聴き取り、総譜を書くことになるハメとなるのだが、極力、第一ヴァイオリンに主旋律を歌わせる方法、他は根音となるピアノ伴奏の定旋律、第二ヴァイオリンのピチカート、チエロの対位的な旋律などなど、いかにもサロン・オーケストラで聴くシュランメル風の醍醐味がここに凝縮され詰まっていて、こんな音楽を夜な夜な我が親愛なる上海市民が聞いているというのがミソで、なにやら筆者の内心はとても嬉しくなり、以降、上海人に対する評価は一段と騰がったものである。
しかして、旧臘十二月のこととなるのだが、ちょうど訪滬翌日の六日が小生の生日となり、しかも古稀を迎えた年であるため、彼の地の心友と楽友らが主となり、何と! 坂田進一を冠とする「音楽生活六十七年」と「古稀記念」の「音楽会」を催してくれることとなり、で、「先生のお望みは?」とあれば、せっかくのことであるから、専門からは大分外れはするが、小生が児童のころから好み親しみ、また思いも一入深い、このウィーン下街の伝統音楽「シュランメル」を演奏し、慶祝自他ともに生きようにと、急遽あいなった次第。なおかつ、ここでアワヨクバ「悲嘆小夜曲」をアンコールピースにと目論んだわけも、容易に愛読者諸賢に納得いただけようか。
無論、この地上海にそうしたシュランメルの専門家やファンがいようはずもなく、小生の楽友を日本から招き、音楽学院や交響楽団ホールなどという、シュランメルには似つかわしくない、大仰な会場は極力避け、日本でいえば区民ホール程度の会場で、「老百姓」(一般庶民)のみなさんを聴衆に、気楽にこれを聴いていただこうということで、楽友と協議し準備を重ねたその結果、市内の古い住宅街の黄浦区の工人文化宮と、市郊外新興住宅地の莘庄鎮文化藝術中心とで、これを演奏しご紹介できることになった。
予算も限られるため、シュランメルと表裏一体の「Wienerlied」(ウィーン小唄)は、学院声楽部の主任教授の推薦で、女学生の宋啓航さんに決まり、小生の時間外授業で曲趣やらコツを教えれば、そこはプロの卵である。何とかコツを掴み、シュランメルらしくなり、演奏会当日とはなりゆくが、そんな肝心の演奏会の内容についてはいわずもがな、「子猷訪戴」ならずも、また触れる機会もあろうか…。
上海の心友・楽友のみなさん、本当にありがとう!
ということで、まず今回の寄り道は「これにて一件落着」となる。
「改修おえた専家楼」上海音楽学院
昨2017年は1927年創立の上海音楽学院建校90周年にあたり、とくに古い学内の洋館の内装諸設備と、夏季から重点的に外装を改修しおわり、おまけに夜は、かくライトアップされるようになった。
テレビ「上海─霊感之城」一場面
Shanghai City of Inspiration と英訳されている。
「シュランメル演奏会」黄浦区工人文化宮
2017年12月8日15:00
坂田進一音楽生活67年・古稀記念音楽会と銘打ち、上海の心友や楽友たちが筆者の好きな「シュランメル小音楽会」を開き、これを祝ってくれた。ウィーン小唄を熱唱する宋后航さん、傍らで提琴を拉くのが筆者である。
15
△目次TOP↑
2018年2月
瘦蘭齋樂事異聞 第166話
東皐心越禅師と琴 二十 上海図書館蔵『和文注琴譜』 上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
拙稿は東皐心越禅師(本稿では越師と略す)の琴事にまつわる異聞を考察中であるが、旧臘十二月の「施拉梅尓音楽会」を無事に了え、筆者いまだ上海音楽学院教学中のこと。
民楽系古琴科戴蓮暁教授のお誘いで、「この十三日に、上海図書館において館蔵の貴重な琴譜を展観し、併せて叢書出版記念の座談会があるので、ご都合つけば出席され、ついてはご意見をたまわりたい」とのことであった。
つとに筆者は上海図書館現蔵の『和文注琴譜』なる琴譜に興味を抱いていた。その理由は、その旧蔵者周慶雲(一八六四~一九三三)の著書『琴書存目』(図版参照)最巻末に置かれた『和文注琴譜』の条に、以下のようにあるからによる。
和文注琴譜 鈔本
(※改行および註と読み下し筆者責)
是編巻数無ク ※不分巻合冊
前後序跋無シ
譜ハ凡ソ三十七曲
日本ハ東皋越杜多ノ撰ナリ
※慶雲は日本僧と思った
或ハ称ス東皐心越
※越師別称五種
或ハ称ス三一山人
或ハ称ス懶訥ト 或ハ称ス聖湖野樵
或ハ称ス皋塢山樵ト
自ラ扶桑操二ヲ譜ス
則チ一ニ曰ク煕春操
一ニ曰ク思親引ト
其ノ熙春操ナルハ
君ノ聖ト臣ノ賢トヲ賛頌シ
※とくに徳川光圀公と臣下
国安ラケク民ノ泰ラケクト
礼楽ト文物トノ興盛ノ意ヲ為シ
思親引ハ
其レ親ノ追慕ノ為ニ之ヲ作シ
※父蒋氏母陳氏
音韻纏綿トシテ至性ヲ発キ
末署スルニ甲子仲冬
越師泣血銘ト
※思親引跋
余操モ皆我国唐宋人ノ譜スル所ヲ録シ
※唐宋填詩詞
而シテ以テ訂正ヲ加エ
復タ按字訳スルニ和音ヲ以テス
※各漢字に唐音が表記
毎譜前ニ桂川家蔵ノ印記有り
※桂川甫周の蔵印
慶雲は民国初年ころから家業の傍ら、山陰の兪瘦石と重慶の李子昭に琴を学び、後に三百二十一種の琴書を蒐集し、五十一歳にしてこれを『琴書存目』(一九一四年刊)にまとめあげ、後学のための益書とした。
筆者はこれを読んだことが一因となり、東皐心越禅師の琴系上にある該譜の全容を調査したいと念願しつつ、いまに到るまでその機会がないままであったが、これも天佑、千載一遇の好機であろうかと、一つ返事で参加させていただくことにしたのである。
幸い音楽学院から徒歩圏内の至便なところに位置する上海図書館は、中国第二の規模を誇る近代的大図書館で、現在、徐家淮分館(一八四七年に創設なる中国初の近代図書館)となっている徐家淮蔵書楼をその起源とし、一九五〇年から図書の購入収集をはじめ、国内の多くの蔵書家や学者の寄贈をうけつつ、また国外図書も購入し、当初は約七〇万冊の蔵書規模で一九五二年七月に上海競馬場の付近に開館したが、さらに一九五八年には上海科学技術図書館、上海歴史文書図書館、上海新聞図書館などを合併し、一九九五年には上海科学技術情報研究所を加えて、一九九六年に壮大な新館を建設し、現在地の淮海中路に移転開館したというわけである。
当然のことながら、同館蔵の琴譜・琴書も少なしとせず、そうした琴書を復刻し、昨二〇一七年十月、これらを『上海図書館蔵古琴文献珍萃・抄本校本』なる一連の叢書とし、中華書局から、ごく少部の三百四十セットを刊行し、主なる対象を各地の重点大学や大図書館としたが、考えてもご覧じろ。ごく単純に見積もっても全人口十四億強の人民に対しての供給部数である。世界無形文化遺産に「古琴」が認定されて以降、爆発的にその愛好者数が増加し、いまや中国全土では恐らく数百万人が古琴を学んでいて、楽器や絲、まして琴譜や琴書、入門書、曲集など、また各街のいたるところにある教室などの従事者などを加え数えれば、それに数等倍するであろうか…。
筆者年少のころ、専門業余を問わず、全国規模の「琴会」に集う琴人は、多くても二百人あればよいほどであったことを憶えば、隔世の感一入である。
さて、当日の昼下がり、戴師の車に便乗して音楽学院から三分ばかりで図書館に到着。善本閲覧室に通り、「『上海図書館蔵古琴文献珍萃・抄本校本』出版首発座談会議程」と題した、図書館と中華書局共催の会議椅子に座れば、なんと思いがけずも隣席に、琴友龔一先生の温顔が温かく微笑んでいるではないか。
そうしてまずは、出陳された館蔵四部の「琴譜」を拝見し、上海図書館幹部および出版関係(中華書局)者らがそれぞれ短いスピーチをし、次いで嘉賓の専家(古琴)である龔一先生(国家一級演奏家)と戴教授、そして筆者が、それぞれ一条のお話と演奏をしたのである。
とりわけ日本琴学を研究対象とする筆者である。つとに上海図書館蔵の『和文注琴譜』に興味があり、その全容を見たいものと熱望していたところ、これより以前にその影印版が『琴曲集成』(中華書局刊)中に入って公刊されたことで、その書面を乱視と戦いながらも、やむなく当面の需要を満たしてはいたのだが、これではなんとしても画面が小さく、しかも印刷が粗悪でいかにも見みずらい。
そこで、このたびの『上海図書館蔵古琴文献珍萃・抄本校本』を拝見すれば、A4サイズの紙型で全十冊洋本仕立て、同館蔵の三十三種の貴重な琴書を収録していて、就中『和文注琴譜』を例にとれば、原本全三巻不分巻合冊、三十七曲収録、百六十丁。サイズ縦二六・一cm、横一六・一cmのところ、縦二四・一cm、横一六一cmのやや大きな画面としたため、難なく細部まで読むことができるようになり、いままでの隔靴掻痒の思いからようやく解放され、琴譜(減字)や唐音など細部にわたり分明に見ることが出来るようになった。
『琴書存目』周慶雲編 1914年刊
巻末の「和文注琴譜」部分。
和文注琴譜 鈔本
是編無卷數前後無序跋譜凡三十七曲日本東皋越杜多撰或稱東皋心越或稱三一山人或稱懶衲或稱聖湖野樵或稱皋塢山樵自譜扶桑二則一日熙春操一日思親引其熙春操爲贊頌君臣賢國安民泰禮樂文物典盛之意思親爲追慕其親之作音韻纏綿發乎至性末署甲子仲冬越子泣血銘餘操皆錄我國唐宋人所譜而加以訂正復按字譯以和音每譜前有桂川家藏印記
【左】『和文注琴譜』上海図書館現蔵
実は『東皐琴譜』であるが、もともとの題箋がなく、後に北京で入手した周慶雲が、整理するために便宜上『和文注琴譜』と付した書名である。
琴譜は同書巻頭の「調絃入弄」部分で、原蔵印「桂川家蔵」と旧蔵印「烏程周氏夢坡室所蔵」、現蔵「上海図書館蔵」とある。
「図書館善本閲覧室にて琴譜を拝見」 2017年12月13日
琴譜を手にとり閲覧する筆者。その右側にいるのが戴暁蓮教授で、龔一先生の愛弟子でもある。さらに右端の男性が、今回復刻版叢書主編の一人厳暁星氏である。
「上海図書館における筆者と龔一先生」
兄貴分である龔一先生と筆者の関係は、この一葉がよく現すところだが、すでに両人ともに白髪となってしまった。
31
△目次TOP↑
2018年3月
瘦蘭齋樂事異聞 第167話
東皐心越禅師と琴 廿一 上海図書館蔵『和文注琴譜』 中上
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
読切り連載のため、たびたび重複せねばならぬ拙稿駄文の煩雑さ。さぞかし読者諸賢におかれても困惑難儀されているであろう、との老爺心と猛省もあり、整理の意を含めて、連載中の主題「東皐心越禅師と琴」についてのチョットしたおさらいと、周慶雲命名するところの『和文注琴譜』清国への伝来大略である。はからずもこの「琴譜」も『東皐琴譜』異本の一種であり、これによってこれを見ば、いかに心越派が流行したかの一証左たろうか。
奈良朝に、唐代の雅楽とともに「琴(きん)」(俗称七絃琴、現代中国語では古琴)と「琴譜・琴書」が伝来してより興った我国の「琴道」である。しかし、音量や難易度などの事情から、いち早く「全天候型」の雅楽合奏からは離脱せざるを得ず、以降は貴族の「館」内で嗜まれた「室内楽」や「独奏」に一縷の命脈をたもつが、これも平安朝末の『源氏物語』成書のころにはほとんど衰退し、ついにその伝脈は途絶してしまう。つづく鎌倉、足利、安土桃山各朝における琴は、宋・元・明貿易の文物交流中と、五山の禅文学などに色濃く影を残しながらも、実際琴藝の授受はまったく行われなかった。
かくして琴が断絶して以後、約六百数十年を経た後の明末清初の康熙十五年に杭州湾を船出し、わが延宝五(一六七七)年正月に長崎に入港した渡日高僧の東皐心越禅師(越師と略)が、明代寿昌派の中国曹洞禅とともに琴を携帯したことで、結果的には「琴の再伝」と喧伝されるようになるが、折から徳廟の「礼楽」勃興期で、徳川第四代将軍家綱から後の八代吉宗公の整備期へと繋がるのである。
こうした風潮にあやかり、いやしくも「士人たるもの礼楽を学ばずんばあらず…」とばかり、机上の学習には飽き足らず、「礼」の実儀と、「楽」の実践たる「琴」と、「中国文人趣味」や「四藝」(琴碁書画)の需要とが重なり相乗しあって、文人墨客間に琴を学ぶことが流行し、後には「心越流琴派(流とも)」と呼ばれるまでに隆盛となり、江戸中期から明治中期まで本邦琴学の正統とされ、さらには、心越派流祖として越師を担ぎ上げ、本邦琴道「中興の祖」と崇め奉ったのは同派後学の琴人らのなせる業で、越師が目論んだことでも、ましてや望んだことでもないことは自明の理である。
禅人ながら「琴癖」をもつ生前の越師が直接対面指導したは、水戸藩後楽園邸内で内密裡に教えた僅か二人、幕儒人見竹洞と旗下大身の御曹司杉浦正春(元服後の琴川)のみで、しかもこの両人は禄に支えられた士人であるため、生計のため売文売藝をする必要がなく、琴の門弟はおかなかったのだが、皮肉なことに、杉浦家陪臣で琴川の寵臣であった小野田東川が主君の急逝後、その背景を失い杉浦家を逐われたことで、やむなく生業として駿河台で瞽者の箏曲階梯に倣い、束脩を授受して琴を教授したことにはじまり、却って江戸の巷間に琴道が広まったのであるから、まさに遷界の越師が生前密かに教えた琴道のその後の展開に、禅師も苦笑を禁じ得ないであろう。
東渡に際し越師は本国で学んだ琴曲と、自身携えきたった「琴譜草稿」、および渡日後の自作譜などを併せ、機が熟せば上梓する目論みであったが、すでに自身の命数を悟り、上梓は果たせぬものと、やむなく前記琴門の両人にその編纂を遺命する。
しかし、越師示寂後三ヶ月にして竹洞も逝き、琴川によりようやく十五年の年月を要して整稿命名されたのが、すなわち『東皐琴譜(正本)』であったが、この「正本」はその後も上梓されることはなく、後に心越流興隆期に用いられたテクストは、すべてが「正本」の簡易版が用いられ繙かれ、ただ単に「琴譜」といえば、この簡易版「東皐琴譜」であり、書面題箋に「琴譜」とあれば、刊本写本を問わず、すなわち「東皐琴譜」を指すことが多く、当然のこと、「琴川正本」以外の各種の版は、地域別にそれぞれ多少の差がある。
小野田東川若年期に教授した向柳原杉浦琴川邸における門弟で師の東川より早逝した幸田子泉ら四天王、および東川門中年以降に駿河台で下帷したうちの逸材ら。迎遯閣牛込琴社に集った面々。江東大川端の曇空和尚門。浅草真龍寺蘭室上人門。飯田町の松波西陵らなど、以上が江戸の主たる琴門である。
西では尾張藩医の中村泰翁。洞津藩士の杉浦梅岳。伊勢の永田蘿道。京都の梅辻春樵。また浪花の鳥海雪堂や妻鹿友樵である。
北には江戸から出て北信と出雲崎に伝えた中江杜徴。備前を出て京都を中心にほぼ全国を股にかけ、心越流の皆伝を得ぬまでもひとかどの琴士として名をなし、独自の琴境を拓いた浦上玉堂門などなど、それぞれの時代と師承淵源により、必要に応じて以下の各版に準拠したテクストを用いていたのである。
ただし、一の「琴川撰正本」は巷間に流布せず、秘譜とされてきたことはすでに述べた通りである。
ここに煩を厭わずに代表的各版を列挙してみるが、無論、一から四、以外の抄写本にいたっては、ここに列挙することは不可能である。
抄写本
一、「杉浦琴川撰正本」源五十七曲本
二、「小野田東川撰」十六曲本
三、「幸田子泉撰」四十七(八)曲本
四、「児玉空空撰」三十三曲本
刊本
一、「鈴木蘭園撰」十六曲本
二、「菊池遷甫撰」十六曲本
三、「大江玄圃撰」五曲本
四、「児島鳳林撰」異五十七曲本
さすれば上海図書館の『和文注琴譜』は三、の四十七(八)曲本の系統であることが知れもするが、周慶雲の入手時、「是編巻数無」とすでにあるよう、不分巻であったが、四十七曲本は、本来は三から四巻に分冊であることと、さらにその目録部分を抜書きしてみれば、以下十曲分の紛失欠損部、すなわち、左記四十七曲本の全曲中、二二、「石交吟」から三〇、「憶秦娥」までの太字部分の都合九曲の一分冊が欠けていることが解る。
もともと『和文注琴譜』は、心越流琴派を学んだ将軍家奥医師で蘭法医の桂川月池(一七五一~一八〇九。後述)自筆自用の抄写譜で、元来が二~三冊の分冊と思しいが、その没後の変遷で桂川家を離れ、表紙もないまま不全本となり一冊に綴じて合本してあったようである。
では何故に清末中国の周慶雲が、いうなれば、かく超マイナーな日本の「琴譜」を入手できたのかとの問いに、
一に、清国留学生、または往来者による。
二に、古書肆文求堂の田中慶太郎(一八八〇~一九五一)の手によって晩清北京の地に齎された。
就中、二が愚案の帰結するところで、別に筆者自身が田中同様京都の出で本郷に住まいし、昭和二十九(一九五四)年文求堂閉店のころを多少知ること。長ずるに従い、本郷・湯島・お茶の水と転々とした想い出などと、交友や趣味の範囲も大きく重なり、筆者の同堂に対する思いもひとかどではなく、例えば聖堂、高羅佩・中山両先生、中文・中哲人との交友、中華文藝などなど、筆者の児童から青年期にかけての変遷をそのままナゾルようである。次号では、『和文注琴譜』の清国への経緯大略の根拠を提示してみよう。
『歴代琴人伝(五・上)』
中国音楽研究所・北京古琴研究会共編
1965年内部参考資料
書中、蒋興儔(越師俗名)以下の系譜を受け売りにした中国の研究者たち。
越師の琴師をそのまま荘蝶庵として、連綿いまにいたる。しかして、小野田東川→多紀安元→桂川月池へと琴系は繋がる。
『東皐琴譜』四十七(八)曲本目録
上海図書館現蔵の『和文注琴譜』は本文中三、の「幸田子泉撰」四十七(八)曲本の写本で、桂川月池の手抄本である。
一、調絃入弄(仙翁操)
二、清平楽
三、浪淘沙
四、東風斎著力
五、三才引
六、大哉引
七、秋風辞
八、帰去来辞
九、子夜呉歌
一〇、幽澗泉
一一、久別離
一二、酔翁操
一三、八声甘州
一四、瑞鶴仙
一五、鳳凰台上憶吹簫
一六、太平引
一七、鶴冲宵
一八、南浦月
一九、飛瓊吟
二〇、梅花
二一、偶成
二二、石交吟
二三、滄浪歌
二四、鳳梧鳴佩
二五、鳴鳳朝陽
二六、賀新郎
二七、南薫操
二八、倚蘭操
二九、嵆中散
三〇、憶秦娥
三一、離別難
三二、離別難(同曲異音)
三三、華清引
三四、霹靂引
三五、月当庁
三六、憶王孫
三七、草堂吟(凡四闕)
三八、長相思
三九、相思曲
四〇、竹枝詞
四一、小操
四二、箕山操
四三、熙春操
四四、思親引
四五、安排曲
四六、楽極吟
四七、高山
27
△目次TOP↑
2018年4月
瘦蘭齋樂事異聞 第168話
東皐心越禅師と琴 甘二 上海図書館蔵『和文注琴譜』 中中
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
○まずは、中華民国三(一九一四)年、周慶雲が『琴書存目』を編纂刊行するに際し、のちに『和文注琴譜』と命名する江戸期の琴譜を北京で入手した時期は、晩清、もしくは中華民国初年のことでなければならなく、田中慶太郎最初の清国上海行は、義和団の乱直後の光緒二十六(一九〇〇)年であったこと。
○次に、古籍唐本に関する智識全般の修得を目的に慶太郎が北京に遊学するのが、まさしく清朝最末期の三年間、光緒三十四(一九〇八)年から宣統三(一九一一)年で、前条と併せ、ピタッと両者の点と線が北京で一致すること。
○現時『文求堂目録』掲載の唐本以外、和書のすべてにいたるまでを揃えることは不可能だが、たまたま、寒斎数冊架蔵のうち一番古いと思しき、明治四十(一九〇七)年の『文求堂発売書目』(図版参照)があり、ちょうど慶太郎が前記清国遊学時の初期の「売立て書目」である。こうした日中書画上の接点を通じて、箋の欠けた「琴譜」は、著名鑑識家であり、中年以降琴に没頭し、新旧の琴書を普く蒐集していた周慶雲の眼にとまり、その処をえて収まったと思しいこと。
○慶雲が該『琴書存目』を編纂し、分類紹介するに際し、無題(実は「東皐琴譜」)の書名題箋に困った結果、その内容からやむなく『和文注琴譜』と仮題したのであって、これが当然原題でないことはもちろんのこと、新題箋は、琴譜の傍らに「唐音ルビ」が付されているために題された仮の書名と考察できること。
○晩清の北京にて、慶太郎が実地に学び目賭し、仕入れてのちに分類し、解題を付して売買しだしたこれらの古籍類は、いうなれば彼の書誌学に裏付けされた古籍商としての矜持ある原点であり、ただ単なる古書流通だけの売買に終わらず、いまに古典文化を東京(日本)と中国とに伝えるという、大きな気概も感じられること。
○彼の目録には「琴譜・琴書」が入り、前述『文求堂発売書目』中の琴書としては、古唐本部子部藝術に『琴譜』(※自遠堂琴譜)呉虹編十二巻がある。さらには、田中帰国年の同四十四(一九一一)年『文求堂新旧唐本書目』なる目録では、経部に五点の楽書(略)と子部藝術部には、なんと八点の琴譜が掲載されているではないか。参考までにその譜名と価格のみをご紹介すれば、
『対音捷要琴譜六巻』 拾円
『伯牙心法不分巻』 壱円五拾銭円
『徳音堂琴譜十巻』 弐円
『澄懐堂琴譜不分巻』 四円
『琴学内編廿二巻外編四巻』 弐円
『琴譜諧声五巻』(※琴簫合譜) 壱円五拾銭
『青山琴譜六巻』(※大還閣) 弐円五拾践
『蕉庵琴譜四巻』 壱円五拾銭
惜しむらくは、ここに掲載されるのはただに唐本のみで、和書はその範疇にないのであるからして、所謂『和文注琴譜』がもし文求堂の手中にありとしても、目録中には当然掲載されないこと。などなどである。
大正九(一九二〇)年にロシアに入ったきり、そのまま消息を絶った大庭景秋(一八七二~?)の短文に、洋書の「丸善」と対照した次なる文求堂についての件がある。
北京へ毎年、それも年に一両度必ず買出しに行く日本の書籍商としては、文求堂主人田中慶太郎氏が、唯の一人だと言って可からう。大阪で有名な鹿田(※松雲堂、現中尾松泉堂がその流れを汲む)なども出かけるにはでかけるが、文求堂主人の豪放な遣口には及びもない。北京で「文求堂来(らい)」となると、瑠璃廠の書林は勿論のこと、名家旧家の間でも、それぞれ立派なものを売りに出すので、文求堂の去った後には、北京には珍籍が空しいと言はれる程である。文求堂主人田中慶太郎氏は元哲学館(※現東洋大学)出身で、後更に外国語学校の支那語科を出た人であるから、深い漢学の素養の上に支那語が十分に話せる。而して北京第一流の旅館に陣取つて、区々たる値段の争ひなどはせずに、買ふべしと見込みを着けたものは、数千金を投じて、時には萬金を投じて、頗る大胆に買ひ取ると云った風だ。
そんなだから文求堂の書は、実の処却々廉くはない。しかし其処に主人の識見も存してゐるので、珍籍古籍を購入しようと云ふほどのものが、値段などを論ずべきものではないと云ふのが、彼の主張である。どれ程威張られた処で、今日どんな学者でも、我国亜細亜研究を進める上に於て、文求堂を閑却しては、全く出来ないと云って差支あるまい。毎年発行して学者や得意先に預ける、唐本仕立ての凝った同店の目録は、文求堂の誇りでもあらうし、また我が読書界の福音でもある
蛇足ながら、以下は筆者なりにまとめた「文求堂小史」である。京都で代々続いた「田中屋」(略して田治)は、御所御用達しの和本専門の大書林で、御一新以前、すなわち文久元(一八六一)年からは元号に因んで店名を「文求堂」と改め、唐本をも扱うようになった。
田中治助から治兵衛へと代替わし、治兵衛の男慶太郎は、字を子祥、救堂(文求堂を三字に分解して合字した)と号した学者肌で、かねて書道篆刻を善くし、とくに家業の漢籍書誌学に詳しい才人であった。主著に『羽陵余蟫』、『支那語動字活用法』、翻訳『重論経今古文学年代』、編訳『支那文を読む為の漢字典』などがあり、就中、『羽陵余鱏』には彼の半生に目賭した貴重書籍についての見識が語られている。
明治十三年生まれの慶太郎は、同二十九(一八九六)年、十八歳で東京へ出、井上円了の哲学館(現東洋大学)を経て、明治三十三(一八九九)年に東京外国語学校支那語科(夜間)を卒業すると同時に家業を継ぎ、明治三十三(一九〇〇)年から清国にわたるようになる。
明治三十四(一九〇一)年、京都の店は父に委せたまま、東京本郷文求堂を移転させ、明治四十一(一九〇八)年から同四十四(一九一一)年まで、再び晩清の北京へ遊学し、古籍版本に関する智識を学びがてら、書画を直接売買し、古籍の他、書画文房具を漁り、そうした名品の数々を日本に郵送させて『文求堂目録』にまとめ、日本の漢学者に送付、逆に日本からは和書、とくに漢籍を持って中国の学者相手に売り捌き、以降、年に数度主に北京に買い出しに行きつつ、日清両国(図版参照。すぐのち中華民国、初期の中華人民共和国に到るまで。但し和書は掲載せず)の文人顧客たちを対象にして、書画を頒布できることを生涯無上の喜びとしていたのである。
(文中※筆者註)
「田中慶太郎小照」(1880~1951)
明治33(1900)年30歳ころ、清末の北京にはじめてわたったころの慶太郎。
『文求堂発売書目』
明治40(1907)年刊
寒斎架蔵『文求堂書目』のうち、一番古いと思しき、主人田中慶太郎が清国にわたったときの「売立て書目」である。
「文求堂新社屋」昭和2年竣工
東京に移転後、湯島、本郷と何度か移転する中、1923年の関東大震災で皆無に帰した経験を活かし、1927年に落成した鉄筋製の新社屋である。
23
△目次TOP↑
2018年5月
瘦蘭齋樂事異聞 第169話
東皐心越禅師と琴 廿三 上海図書館蔵『和文注琴譜』 中下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
ようやくここにいたり、前後逡巡しがちな拙筆の端に、晩清北京の周慶雲により『和文注琴譜』と命名された上海図書館現蔵「東皐琴譜」、もともとの筆写愛蔵者である日東琴客の琴事がかかる。
和漢の往昔、いったいに琴を嗜んだ階層には、聖賢君子、王侯貴族、隠者、道釈士、儒者、文人、武士、画家などの多いなか、医家をも少なしとしない。
江戸琴流の正統派心越派では、多紀藍渓、桂川月池、杉本樗園らがその著名な医家の例である。
桂川月池(一七五一~一八〇九)は、将軍家奥医師(御脈)蘭方医頂点の桂川家の第四代で、外科を善くし、また地理学にも詳しかった名医である。江戸は築地の産で、幼名を小吉、諱を国瑞、通称を甫周、号を月池、また公鑑、無礙庵、雷晋、世民などと別号した。その一方で、月池が大の「琴痴」であったことはあまり世に知られない。
蛇足ながら、二十一歳から独逸人ヨハン・アダム・クルムス原著で和蘭語訳された医書『ターヘル・アナトミア』を杉田玄白らと諺解し、ついに『解体新書』として完成させた月池の功績は夙に有名だが、また大槻玄沢らと共に江戸蘭学界の中心的存在であったため、築地の月池邸は文人墨客のサロンとして常時賑わったという。
かく『解体新書』を共訳した他、安永年間江戸参府のオランダ商館長と面談し、寛政四(一七九二)年、ロシア使節団により送還された漂流民大黒屋光太夫らの将軍引見に同席し『漂民御覧之記』を著し、また『北搓聞略』編纂などの他、『魯西亜志』を訳し、『魯西亜封域図』を製作するなど、幕府の北方問題にも大きくかかわったのである。
月池は、父の甫三(一七三〇~一七八三)と前野良沢(一七二三~一八〇三)に医術と蘭学を学び、明和五(一七六八)年に将軍御目見、翌年奥医師拝命。天明三(一七八三)年法眼、寛政五(一七九三)年に再び奥医師、翌六年幕府「医学館」(館長多紀藍渓)教授の蘭方外科教授となったが、ここに月池の医学や世界状勢、また地理などの業績をくどくどしく説くは本稿の趣旨でなく、これらは省いて医家地誌学の詳伝は他に譲るとし、ここでは、専ら「樂事異聞」を追わねばならぬ。
漢方医古方の最高峰で、幕府「医学館」館長、かつ幕府奥医師大先輩の多紀藍渓(一七三二~一八〇一)にも琴癖(本連載第2話二〇〇四年六月号参照)があったことから、藍渓を月池の琴師とする一説もあるほどだが、生業の医家としての逸話は遣っても、側面の琴客としての逸事は伝わりにくいなか、月池自筆自用の愛情やまなかった琴譜が、却って現在、海上千里を隔つ上海図書館に珍蔵されている事実がある。
新楽閑叟(一七六四~一八二七)はこの月池の琴友で、
…友人新楽閑叟…(『指法書跋』)
と月池が親しく認めた人物である。
牛込「迎遯閣」は幕府の奥祐筆篠本竹堂(一七四三~一八〇九)の牙城で、閑叟はここを核に集う琴社の幹部であり、結社は徳川田安家文学で琴師の児玉空空(一七三五~一八一一)を領袖とし、閑叟や竹堂らが琴社内を取仕切り、なお閑叟の編著「雑話」中に、小野田東川(一六八四~一七六三)琴門の逸材としての藍渓や、月池から親しく聞いた琴事に関する記述を遺したことから、現時、そうした消息を補足できるのは閑叟の功績かつ大いなる書福である。
多紀法印、琴を好ミ従事する事多年、其伝を極む。
東川(小野田)没時、琴-越師より伝るもの-、越師(東皐心越)并竹洞肖像、鶴氅(琴服)-越師より伝ふ-、琴案(琴机)抔を贈る。
其琴火(天明大火)に罹る。
法印歎曰、我道(琴道)已矣、
我豈世の無塩をとつてするものならむや。琴の意にかなふなく、終に廃して不弾。-此頃迄ハ琴を作る工もなく華琴の買ものもなかりし也-
…(浦上玉堂件略)…
桂川月池-甫周-話に、
我いまた琴を学ハさる前に、毎に法印と殿中(千代田)に同直する時、休息所に閑坐するに、間々右手を翻復開合をなす。其故をしらす。後、琴を学てしる。これ撥刺輪鎖抔の指法ならんと。
よりて其故を問ハ、法印笑云、予少年の時、指法のよくし難きをもつて、坐臥常にこれをなす。思ハす終にくせとなる。
予、焚琴(天明大火)以来十余年、多務激職、絲桐に従事する事能ハす、今、公等(月池らの)其道を習ふを見る。老者の喜といふへし。
予、所伝数十曲、殊に好む所ハ釈談章(普安咒)なり。若間暇を得ハ、伝ふへしと。然共遂に不果して没す。惜哉。
寛政間、水戸藩邸へ法印を召して、弾琴の事あり。-琴ハ越師の上る舜なり-
尾張亜相公約ありて来り聴給ふ。
其他高貴の家相会こと、今世江戸に珍敷事にて、盛事といふへし。
月池の宅にて、尾州公所蔵の琴を見る。木枯尽て朽たるか如し。断紋あり老龍吟三字銘あり。艸書にて漆を以ておき上ヶにしたる也。至て古物也。相伝ふ、敬公-諱義直尾州家始祖-の遺物にて、慶長中上(家康)より賜ふ所といふ。
また紀州公所蔵の琴二張を見る。共に銘なし。断紋ありて其形、漆色尤も古雅、至てひきよく音響清亮、実に絶品といふへし。
又水戸公の虞舜琴を久しく借りて模造す。
月池性巧にして、よく模写して其真にせまる。
虞舜ハ岳高く、初学拙手にハ弾し易からす。-水戸祇園寺の大雅琴又しかり-
かる器を常に弾する越師の高手、
妙所に至る想像すへし。
いつれも音ハ妙なり。
以上高貴の蔵物中々人間の見る事を得へからさるものも、時ありて月池の力にて、我徒(琴社)皆縱観を得。
諸侯の旧物、木下侯-備中葦守の城主-古琴-無銘-相伝ふ。
其先長嘯子(木下)の遺物なりといふ。
平戸侯の琴、岳の上に白楽の二字銘あり。
長島侯の物-無銘-
其他猶多かるへし、悉く知る事あたハす。
近世琴道漸々ひらけ、年々舶来するものあり。又旧家古刹より捜し出すもあり。華製の古今(新古の琴)一時に江戸へあつまる。
然共殊勝のものハ少なし。
改行句読筆者責 引用文中()内筆者註
右引用文により、月池は藍渓から直接琴を学んだのではなく、千代田城中にて親しく琴談を交わしていたことが知れるのだが、藍渓や月池は職務上、将軍家の玉体に直接触れることができもし、なおかつ徳川御三家ばかりか、全国の諸侯の覚えも目出たく、とくに月池は諸大名家秘蔵の宝物をも借り出せ、しかも月池は倣古の術に長けていたので、これらから模造できたのである。
そうしたお陰を蒙り、一介の御家人が多い牛込琴社の琴友たちでも、貴顕の秘宝や、月池の模琴も眼にすることができたようである。
「雑話」にあるよう、藍渓は、琴師小野田東川門で少年のころから学び、のちに四天王第一とされた名手であり、ために師東川が没した際、東川遺愛の越師伝来の琴(天明の大火で失す)と同鶴鼈衣(琴服)、および越師と竹洞二先師の肖像、東川遺愛の琴案(机)などを遣られたほど矚望された琴人である。
さらには桂川月池の琴友で牛込琴社の新楽閑叟とは、共に迎遯閣に集う良友同志でもあり、そんな月池老人自筆自用の愛惜やまなかった琴譜が、該『和文注琴譜』(実は『東皐琴譜』)というわけである。
『間叟雑話』新楽間叟編著 寛政九(一七九七)年九月未刊
桂川月池の琴友新楽閑叟は、七十俵五人扶持の御徒目付であったが、科挙に倣った聖堂吟味では南畝に次ぐ成績を修めた秀才である。
若年から児玉空空に諸学と琴を学び、月池や牛込「迎遯閣」に集う琴社の面々、また、致仕後には全国を経巡って各地琴客らの琴事を聞書きし、まとめた話が『絲桐談』である。
書中の後編が「雑話」、すなわち『閑叟雑話』で、図版右側が藍渓紹介の「玉堂」末部分(本文では省略)、左側が月池分となる。
29
△目次TOP↑
2018年6月
瘦蘭齋樂事異聞 第170話
東皐心越禅師と琴 廿四 上海図書館蔵『和文注琴譜』 下上
湯島聖堂斯文会講師琴士・作編曲家 坂田進一
東皐心越禅師(越師と略す)によって東漸した近世日本の琴道は、後人をして「心越派」と呼ばれるようになったが、そうした琴学略系譜をはじめて明確に示した文献が、新楽閑叟編の『絲桐談』(未刊)中の「琴家略伝」である。
しかして、これは内部少数の琴人たちが写本で愛蔵する他なく、中根香亭が文人仲間の井上竹逸に借覧して写本し、かつ整稿したものを、明治中期に不特定多数の新知識階層の新聞購読者に対して「七絃琴の伝来」として紹介知らしめたことで、琴界以外の人が越師の事績とその琴系譜が公開されたのである。
その後、越師を開基とする祇園寺住の浅野斧山が、明治最末年に『東皐全集』を公刊し、さらに昭和となって碧眼の文人高羅佩ことヴァン・グーリック先生が、越師を研究したことから、その大著『琴道』が成ったというわけである。
『琴道』は、一九四○年十一月から日本学誌叢「モニュメンタ・ニッポニカ・モノグラフ」で連載したものを、連載完結にともない、翌一九四一年に『琴道』と改題し、羅佩が没頭した日中琴学を、はじめて平易な英文で欧米向けに刊行紹介した力作で、現在中国において盛んに翻訳復刊されてはいるが、惜しむらくは書中の日本、ことに「心越派琴系譜」(図版下参照)は、当時の資料において判明するだけのもので、どれもいまだ完備されたものとはいえず、今日の視点からすれば訂正されるべき項目が多々ある。ただ、こうした先達により、明治・大正以降すでに忘却されていた日本琴学が見直され、現在の研究を牽引してきた功績には計り知れないものがある。
次いで査阜西先生がこれらを現代の中国に紹介したが、現在連載中の拙稿「上海図書館藏・和文注琴譜」と多々関連すること無論である。
さて、和刻『東皐琴譜』をはじめとする明清版通行の各琴譜は、概して記号譜「減字譜」(琴譜)一行をもって記されるが、もしも琴曲に填詩詞の「歌辞」があれば、二行をあてたうちの右側が歌辞、左側に減字(琴譜)が配置され、松風闇に倣った『東皐琴譜』もその例外でない。
杉浦琴川編の『東皐琴譜正本』以外、すなわち、小野田東川以降に編纂された各種異版の『東皐琴譜』もこれを踏襲していて、さらには、「東
麻琴譜正本』でこそ「唐音」は表記されなかったが、以降の異本『東皐琴譜』の歌辞に必ず各版では、そといっていいほど片仮名の「唐音ルビ」が付されていて、桂川月池手抄本も同様であったため、周慶雲はこれを称して「和文注」とよんだのである。
◎一九五八年春のことである。筆者が琴を初学する契機となった出来事でもあるが、戦後初、いまだ日中国交断絶のままのうち、なんとかその閉塞感を打開せんものとの両国国策で、文化人交流という名目下、中国歌舞団の公演が実現した。
そこでその団長として来日したのが古琴家査阜西(一八九五~一九七八)先生で、超多忙な公演の合間を縫って、夙に興味をいだいていた前記日本の琴派「心越派」までを精力的に調査して帰国したことが発端となり、現在にいたるのである。
やがてその成果(図版左参照)が琴界内部に発表されるや、中国国内の古琴家たちは俄然日本の琴派に注目し、江戸時代に流行した心越派を研究、その概要を調べだして以来、この査氏の「琴系譜」を受け売りにした研究者たちが越師の琴師をそのまま荘蝶庵として、連綿いまにいたるというのがどうやら真相に近い。
戦前までの中国「公共機関」に所蔵されていた日本の琴譜は、北京の中央音楽研究所に『東皐琴譜』があり、上海図書館に『和文注琴譜』などがあったが、一部の識者以外にはほとんど知られておらず、また、「日本の琴流なにものぞ」という本家意識が、いまだ根強く中国琴人の間には残ることも事実である。
この『和文注琴譜』は、将軍家奥医師で蘭法の桂川月池(一七五一~一八〇九)自筆の写本であるが、不全本であるところから表紙がなく、そのため題箋に困ったが結果、その内容からやむなく『和文注琴譜』と仮題したので、これが当然原題でないことはもちろん、該書名命名は、琴譜の傍らに「唐音ルビ」が付されているために題された仮の書名であることはすでに述べてある。
東皐心越琴友=
杭州・楮虚舟 馬季翁
長崎・何子遠(可遠)
東皐心越琴門=
人見竹洞(竹洞、鶴山)
杉浦正春(後正職、号琴川)
人見竹洞琴門=
杉浦琴川 (男)人見桃源
杉浦琴川琴門=
小野田東川(延賓)
小野田東川琴門=
甲州屋七兵衛(峡中老人)
寂堂曇空(新豊禅師)
「東川門四天王」
一、幸田子泉(親盈、友之進)
二、多紀藍渓(元堅)
三、設楽純如
四、杉浦梅嶽
久保盅斎
柴野栗山 他
かく略系を俯瞰すれば、日本で越師が直接琴を手ほどきしたものは、儒官人見竹洞および、麾下大身の子弟でいまだ家督以前の少年武士であった杉浦正春の二子のみであって、越師の遷化後にこの杉浦家の家宰となり、浪人して後江戸の間に琴を広めた小野田東川は、越師が江戸から水戸城に移った翌年の天和四(一六八四)年、ようやく誕生したばかりである。
高羅佩撰「日本琴学略系譜」『琴道』1941年4月より
Historical table of the tradition of the Chinese Lute in Japan
I.Naiden:the Inner Tradition
A.Tōkō-zenji
1.Sugiura Kinzen
2.Hitomi Chikudô
3.Hitomi Tōgen
4.Kashuya Shichibei
5.Tochō
6.Komazawa
7.Onoda Tōzen
8.Shimpō-zenji
9.Suzuki Ran-en
10.Shitara Junjo
11.Ranshitsu
12.Andō Ikuji
13.Taki Rankei
14.UrakamiGyokudō
15.Kojima Hyaku-ichi
16.Katsuragawa Getchi
17.Nakamura Tai-ō
18.Kōda Shizen
19.Kodama Kükü
Anyōji Lute Association
20.Shinraku Kansō
21.Suzuki Hyakutō
22.Shinomoto Chikuda
23.Sugimoto_Ka-en
24.Okajima Rampo
25.Yamamoto Tokuho
26.Takakura Yūi
27.Sugiura Baigaku
29.Donkū
29.Nagata Radō
30.Setsudo
31.Inoue Chiku-itsu
32.Mega Yūsō
33.Matsui Yúseki
34.Imaizumi Yusaku
B.
35.Mansō
36.Satō Mosai
II.Geden:the Outer Tradition
A.
1.Chu Shun-shui
2.P'an Wei-ch'uan
(Andō Sei-an)
3.Murai Kinzan
B.
4.FeiCh'ing-hu
5.Kikusha-ni
「(仮)日本琴系譜」1965年査阜西編
拙稿167号の図版は『歴代琴人伝』の表紙で、肝心な内容「江戸琴人略伝」は、1958年春季の「中国歌舞団」訪日の間隙を縫い、かく査阜西がまとめた労作である。
1965年油印の中国音楽研究所と北京古琴研究会共編になる内部参考資料で、就中、清国編の附録に、越師以下の江戸琴人を整理し配置してある。
歷代琴人傳 清
荘臻風 號蝶庵・秣陵人・著琴学心声琴譜
褚虚舟
東皐禪師 蒋興疇、金華浦陽人,出家爲僧康熙間避乱赴日,歸化傳琴。
人見友元(竹洞) 名節,號竹洞,又號鶴山・京師人,業医( -1696)
杉浦琴川 名正職,字惟天,爲幕府旗下士
小野田東川 名国光,字延宝,侍杉浦琴川 晩年教琴糊口(1683-1763)
幸田親益 通称友之助,旗下士,精天文曆学( -1758)
多紀安元 名元徳,字沖明,號兰溪,幕府侍医(1731-1801)
杉浦元凱(梅岳) 名愜,字士容,称郡治 伊勢人,下帷教授(1733-1792)
設樂純如 通称唯右衛門,(井上竹逸云「大番與力也」)
甲州屋 七兵衛・江戸四谷人)(或云学于人見桃源,可疑)
27
△目次TOP↑
2018年7月
瘦蘭齋樂事異聞 第171話
東皐心越禅師と琴 廿五 上海図書館蔵『和文注琴譜』 下中
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
東皐心越禅師(越師)がわが国に伝え、後に「心越派」の琴道として盛んに学ばれた江戸の琴事を核に、他の楽事異聞を綯い交ぜにしがてら、いまは上海図書館蔵『和文注琴譜』について捕渉中であるが、ついてはこの五月、上海から戻ったその翌朝のこと、またゾロ長崎に飛んだ。
頼山陽が清人江芸閣(こううんかく)の為人(ひととなり)を伝聞して夢裡に慕い、是が非でも面晤せんものと、彼の地瓊浦で三ヶ月も待ちぼうけを食った唐船の逸話は知る人ぞしるが、今回はそうした山陽の事蹟を研究顕頌している「頼山陽ネットワーク」(煎茶家石村良雪代表)のお招きで、同会創立九周年と「九州」をかけ、さらには「頼山陽西遊二百年」と銘打った記念会上での特別演奏をするためであった。
花月では「記念会」と「煎茶席」、併せて「清楽(しんがく)席」、「宴席」などが設けられ、就中、短い時間であったが、清楽曲牌中の多少ともまとまった以下の名曲を聴いていただく得難い機会は、長崎の地においては、月琴の名手中村キラ師が逝った後の久方の合奏であったろう。
平成戊戌五月二十三日
長崎「花月」
【清楽席】
演奏
胡琴・月琴・坂田進一
月琴・伊吹清寿
月琴・後藤結希子
一、「韻頭緩」
二、「韻頭連」
三、「月下集」
四、「平板調」
五、「茉梨花」―「水仙花」
六、「漫板流水」
七、「九連環」―「梅が枝」
八、「紗窓」―「春は三月」
以上
右揭曲名中―で結んだ曲は、清楽が伝播し流行した後に日本化した俗曲で、いまも長崎の花街で盛んに唱われる。
今回、山陽と芸閣に因み、ぜひとも月琴で清楽をという会主の意向で、愚門で月琴を学ばれるお二方に同行願った。
そのお一人伊吹兄は三味線現役の名手で、国立劇場の千秋楽を了えたその足での長崎行。また後藤姐は、神楽坂バリバリの花の藝者衆で、研修で花月にも来られたことがあるという。さらには、これまた花月の会に馳せ参じた忘年の門人となられた篆刻家の小田女史と、そのアッシー君ならぬ福岡在で高名な陶芸家石原先生、別に上海から参加された殷氏とそのお仲間など、名うてのツワモノぞろい。無論、多くの煎茶家や来賓がたなどなど、多種多彩な顔ぶれである。
数氏の挨拶とその後の宴会、ドンチャン騒ぎも畢り、花月での会後、「送り三味線」で見送られるが、そこはそれ、顔馴染みの藝者衆と、その晩の約束をし、さらに後の二次会三次会は、機があればのご紹介…。
前日の昼、長崎入りした筆者と後藤姐とで寺町の延命密寺に行き、越師撰「法華三昧塔」を拝し、足を伸ばして古町橋の光栄寺(秋月※光永寺)に詣で、また鳥海雪堂に琴の初学を導いた日蔵上人の墓参をすべく、さらに風頭山に向うが、記憶が曖昧でなかなか見あたらぬ。
実は、随分と昔のまだ筆者青年のころの墓地にたどり着いた記憶がいまに遺り、何でも寺の門前から川を渡り、そのままマッツグに風頭山頂近くの傾斜地の天辺にポツンとあったはずと、何度も右顧左眄、右往左往したのだが、どうにも見当たらぬ。疲労困憊のすえ、この日は諦め翌日の再起にかけようと、晧台寺近くの古書肆「大正堂」に立ち寄った。
老板としばしの漁書懐古談で脚の疲れを癒せば、愚生は花月の唄本「唄の長崎・情緒集」(昭和二十八年発行)を漁り、また姐さんは、昭和初期復刻の長崎古版画から「清人合奏図」を購め、さらに帰路がてら、それに遇う額縁まで購められ、先ずはめでたしメデタシ。
さ、兄の江稼圃(画を善くした)とともに、清朝嘉慶年間(一七九六~一八二〇)を中心に、たびたび唐館に逗留した芸閣兄弟だが、とくに芸閣は、月琴音楽(清楽)を長崎に伝えたほか、江南の煎茶法や、詩文、また画法など、当時の江南文化を将来したことでも知られ、ことに自用の月琴は、何度か連載中にも触れた蘇州製の世にも稀なる逸品で、裏面には芸閣の讃と山陽の月琴詩が刻まれるという、唐館寄留の来舶清人と日本の文人たちとの交流をいまに伝える生の資料で、いかにも風雅な名器である。
こうした筆者の瓊浦にまつわる音楽研究の対象は、ひとり「清楽」のみにはとどまらず、「明楽(みんがく)」と「琴学」、また「黄檗梵唄」などにおよぶことは、愛読者諸賢先刻ご案内の通りで、転んでも只では起きないこと無論のこと。午前中倉卒の間に、長崎高商の名物教授武藤長蔵(一八八一~一九四二)旧蔵の貴重書を閲覧すべく、事前に許可を得ておいた。
後藤姐は早朝の便で帰京され、伊吹兄と、小田女史と石原先生が福岡に戻られるという車に便乗させていただき、途次、松翁軒本店に寄り、片淵在のもと長崎高等商業学校、すなわち現在の長崎大学経済学部の構内車寄せまで送っていただき、運良くその稀覯本と対面すれば、孔が空くほど見つめた本は、心なしか蟲損が目立つ?
シーボルト孫のたか女の一粒種で、わが箏曲の師米山種刀自が、昭和十四(一九三九)年七月、その敬愛した実母たか媼の逝去に際し、葬儀で配布した非売品が『故山脇多賀子に寄寿留』である。
該書は、海内の孤本ともいえる稀覯本で、筆者の青年期、種刀自からこれを長期借覧していたものの、お身内が必要とのことでそのまま返却におよび、複写せずにいたことを悔やんだものだが、それもそのはず、これを四十五年ぶりに手にして胸中懐旧の念一入であった。
ただ、この貴重書閲覧にあたっての写真撮影は許可されたが、論文や書籍に転載は不可とのことで、その写真をここに引用できぬのも惜しいが、奇跡的にも書中に挟まれて遺ったハガキは、種師中年の手になる水茎の跡も麗しい武藤長蔵宛てのもので、こうした小事のなかに、かく長崎に繋がる歴史上のご先祖たちの、現代にいたる長い親交を示す時の経過がうかがえる。
今度はバスで眼鏡橋付近を目指して自由時間で、再会の時刻を決めていったん伊吹兄と別れたのである。
改めて琴曲心越派系譜を填めるべ越師が日東にはじめて釈駐した寺町興福寺のならび、三宝寺上にある光栄寺の墓地へと向うが、何としても見当たらず、徒手にて諦めかけたが『長崎墓所一覧』の一書を頼りに、フト門前で休息中の石工の頭領に尋ねれば、何ともご親切に、「彼処であろう」と山下の道入口までご案内くださり、テッペンを指差してくださるではないか。
しかし時はすでに伊吹兄との再会時刻まであと数分を余すノミ、はたまた再度山上まで歩く元気はなく、何気に「若年の掃苔時には、さして苦もなく、マッツグに墓まで登った記憶があるのですが…」と呟くと、親方にポンと肩を叩かれ、「歳を取られたですバイ」と慰められるではないか。その何とも嬉しい心遣いに、内心元気づけられ、ひとまず待ち合わせの場所に急いだのである。
晧台寺を右折し、龍馬通りと名付けられた商店街小路で昼食とお茶をすませ、やや疲れが回復したところで、まだ帰りの便までには大分と時間があるので、探墓に再挑戦とばかり、今度は、歩けないので搦め手からとばかり、タクって風頭山頂近くの「亀山社中」を目指し、そこから逆に下るという手で捜そうというわけで、今度ばかしはようよう辿り着いた証が図版である。
「延命(密)寺山門前の筆者」 長崎寺町
真言宗医王山延命寺は、元和2(1616)年、備前から本尊薬師如来像を背負って長崎に留錫した龍宜和尚を開基とし、当時流行していた疫病平癒と、船舶の海上安全を祈願するために建立された。
この山門はその後の明暦3(1657)年、越師来崎以前の二世住職尊覚和尚のとき、長崎奉行所立山役所の門を拝領移築したものという。
東皐心越撰「法華三昧塔銘」 同寺
碑文の説明は改めてせずばなるまいが、延宝5(1677)年正月来崎直後、興福寺に錫駐した越師が、隣寺延命前住の勧化にいたく賛同して銘文をものした。
「日蔵上人墓石」風頭山腹
中島川古町橋沿いの真宗大谷派向陽山光栄寺第8世の日蔵和尚は、幕末期の京阪と関東に、からくも心越派の琴系を繋いだ鳥海雪堂の琴初学の師である。
27
秋月※
東皐心越1677年撰 長崎醫王山延命寺法華三昧塔銘【読み下し】
夫れ塔には、如來舍利、阿育王の造れる八萬四千の塔あり。或は如來の髮・毛・爪・齒等の塔あり。或は甎塔・石塔・琉璃瓦塔あり。經中に多寶佛塔あり。未だ法華三昧塔あるを聞かざるは、何ぞや。
是の寺、前住の法印尊覺導師の者は、顯密を堅持し、年並びに八旬、乃ち聖化當來、此の一大事因縁の爲に非ざる無くして、世に出現し、人に佛の知見を開示悟入せしむるなり。
所以に、四方の善信、咸く師の妙法に遇い難きことを慕ひて、甚だ希有なり。遠近の緇素、善を樂しみ施しを好む者、趨然として至らざる無し。
是に因りて、四衆誠を傾け、特に恭請を伸べて、以て法要を示さんことを請ふ。師も亦年邁を辭せず、欣びて衆の爲に此の經を宣揚すること三月餘に及ぶ。
其の住持、阿閣梨覺真公、継述に善くして、當機に得たり。故に緇侶雲の如く臻り、聽衆日に集まり、何ぞ數千人のみに止まらん。施設供養する者五百餘人、豈に靈山の一會に異ならんや。俨然として未だ散ぜず。
況や世尊、昔し猶ほ云はく、「此の經藏、固より能く到る者無し」と。しかるに此の際に於て、浮木の孔に值ひて、幸に耳にして聞くを得るは、皆是れ夙に微勲を借り、大乘の縁に同契するが故なり。
聞きて解を得、解して悟を得、法華三昧に入る者衆し。會に在る緇素、各々瑩潔の石子を以て、經の全部を書し成す。
更に、存没の親屬の名、十萬を餘り、并せて書して共に貯へ、復た石塔を造りて供養す。
經に云はく、「沙を聚めて佛塔を爲せば、皆已に佛道を成ず」と。塔成りて、餘に謂ひて之を記せしむ。予、深く喜び、合掌して讃じて曰く。
如來、昔、耆閣崛山に在し時、萬二千人、倶に無量義處三昧に入る。身心動ぜず、眉間の白毫相の光を放ちて、東方萬八千世界を照らし、靡かざる處無し。
今、此の處に於て大いに法輪を轉じ、所說の經法、斯の瑞に應ず。豈に重ねて其の義を宣べて、記を作すを待たんや。
云はく、「何ぞ能く是の經を得ん」。阿含に云はく、「佛世に出でたまふ時、惟だ四處に塔を起こす」。曰く、生處・得道處・法輪を轉ずる處・涅槃に入る處と。
若し經典の在る處、皆應に塔を起こして供養すべし。當に知るべし、是の處は即ち是れ道場なり。諸佛、此に於て阿耨菩提を得、諸佛、此に於て法輪を轉じ、諸佛、此に於て般涅槃す。
此の三法に由りて秘藏を成し、佛其中に住す。即ち是れ塔の義なり。
蓋し此の經、深奧にして、功德は量り難く、譬喩は無窮なり。聞きて隨喜すれば、皆勝因を獲。
故に淨名に云はく、「日月、何の故に閻浮提を行く。光明を以て衆の暗冥を除かんと欲す」。東は光の始め、西は其の終りなり。終り有り始め有る者は、其れ惟だ聖人か。
未だ心を發せざる者には、其の心を發せしめ、未だ究竟せざる者には、其の究竟をせしめん。
菩薩も亦爾なり、諸衆も然り。一方既に爾らば、諸方も亦爾し。
普く願はくは、盡法界の有情無情・見者聞者、共に法華三昧を證せんことを。
銘に曰く。
延命密寺、地に靈祥を萃め、名は斯く勝概にあり。山號を醫王とす。
琳宮は紺碧にして、珠樹は蒼を纡ぐ。經行は禪窟にして、次第に行を成す。
法印の願は固く、尊覺の行は彰らかなり。顯密を堅持して、嚴として雪霜のごとし。
年、八帙に逢ひ、法、四方に被(およ)ぶ。信心、虔切にして、曷んぞ榮望を企らんや。
衰邁を辭せず、衆の爲に轉揚す。秘奧を宣示し、理事は端詳たり。
字字に瑞を現じ、句句に光を放つ。天華は座に墮ち、天樂は堂に盈つ。
恒に多く乞士あり、愈々金湯を度る。各々至念を發して、梵章を謄寫す。
華言は閃爍とし、玉偈は鏗鏘たり。復た石塔を建て、奉供して覆藏す。
見る者聞く者、功德は量り難く、現存は福を獲、先亡を超拔す。
生生世世、舟航として用ふる所なり。法華三昧は醍醐の妙漿、人人共に契ひ、個個承當す。
人を開示し悟入せしめ、法の實相を渚(あらわ)す。橫に說き縱に說けば、山高く水長し。
說くも說く所無く、究竟は寂常なり。聞くも聞く所無く、遍界は清涼なり。
諸佛、此に於て、法日は輝煌たり。智慧解脫は海の如く汪洋たり。
普天率土、悲願は高昌にして、四恩を總報し、三有を盡償す。
時に歲は丁巳、旦月中に暢ぶ。餘に謂ひて此を記せしむ。
拱手して度を庠(しやう)に以てす。數語を聯綴して、贊襄を作す。
萬古に傳へんことを冀ひ、克く紹(つ)いで永芳ならんことを。
又た衆姓、石に偈を立てて曰く。
法華三昧塔は、衆姓の共に成せる所なり。如此の真三昧、人は當に力を用ひて行ずべし。
天龍は常に擁護し、六合は彌(いよいよ)清からん。惟だ斯の理を悟るを願ひ、檀波、處處に盈たらん。
時に延寶五年六月望旦、法華三昧塔成り、衆姓、石を立てて芳を流す。
漫りに此の偈を書して、以て不朽を識す。
△目次TOP↑
2018年8月
瘦蘭齋樂事異聞 第172話
東皐心越禅師と琴 廿六 上海図書館蔵『和文注琴譜』 下下
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
驚くなかれ。
例のごと、この拙文をものしている上海で、つい一昨日、偶然にも筆者が入手した『東皐琴譜』が図版である。
上海図書館蔵の月池『和文注琴譜』に比すべくもない無名の零本だが、かく同様に幕末明治期、はからずも中国に渡った琴譜もあるにはあるものかな…、かくしてさらに扶桑に戻ることになるとは。
七月の第三週、夏休みで学生たちの少ない上海音楽学院を利用して開催されたのが、「国家藝術基金二〇一八年度・藝術人材培養資助項目・古譜詩歌伝承人材培養.集中授課」なる長たらしい名目の講座で、全国から学者学生が約百人ばかりが集ったのである。
学外の催しだが主催者の計らいで、住み慣れた専家楼を許されたが、東京同様、連日の猛暑でかなりバテテいる。
そうした中、一昨日、昨日と本日(七月十九日)、「明楽」「琴学」、そして「清楽」と連日講義するうちにも、長崎にかかわる想いはイヤ増すばかり。
越師の琴学と魏氏の明楽、幕末伝来の清楽など、そのすべてが長崎を通じて日本に定着した音楽であることはいうまでもなく、それぞれに直接の関係はないが、一究者である筆者にとってのそれは、どれもが不可分であるばかりの理由ではどうもなさそうである。
思案橋
ながさきに立つ薄烟(詠人不知)
実の祖母とも慕った箏曲の師米山種刀自の実母たか(シーボルト孫)は、過ぐる昭和十四(一九三九)年七月十六日の黄昏どきに逝去したが、その母の「想い出集」として編纂した『故山脇多賀子に寄寿留』は、数日後の葬儀で配布されたのみの非売品で、十四年という時局柄からも、多くの制約のある中での印刷出版であったため、後には種嫗自身もただの一冊を秘蔵するばかりで、後に比較的近くにあった筆者でさえもついに架蔵できなかった稀覯書である。
現在、長崎大学経済学部(当時の長崎高等商業学校)図書館所蔵になる同書には、武藤長蔵宛ての種刀自、自筆のハガキが挿んであることで、こうした長崎に繋がるご先祖たちのご縁から、現代にいたる長い歴史上の時間経過がうかがえる。
ある日、種刀自の家に稽古にうかがうと、種畑が「貴君にご紹介した方がお出でになる」と、武藤教授のご長子富蔵先生をご紹介くださった。
すれば当然のごとく、いろいろと幕末や長崎に関する話題に花が咲き、さらには武藤教授と高羅佩ことヴァン・グーリックのことにおよぶではないか。
そこで筆者から「長崎高等商業学校刊の『武藤教授在職三十年・記念論文集』を所蔵なさいますか」とお訊ねすると、富蔵先生は「家(東京)にありますから、今度複写して進呈しましょう」と、いとも気軽に受けあってくださった。
そのお陰もあって、長年求めていたグーリック先生の英文による琴に
関するはじめてのまとまった論文[Chinese Literary Music and its Introduction into Japan」(「中国文人音楽とその日本への導入」)を読むことができ、筆者その後の琴学研究に大いに役立たせていただくことができたのである。
さらに長崎がらみである
少しく前の拙稿連載159話でご紹介した、思案橋にほど近い長崎の名席「花月」の資料館には、「月宮殿演奏図」(仮題)が展示され、ついこの五月にも拝観するをえた。
読者諸賢には、そのモデルとなっ平井連山と長原梅園姉妹を覚えていらっしゃることと思われるが、実は、これと同じ画題のもと、西山完瑛(一に完璞とも、一八三四~一八九七)が、妹とくに梅園を描いた(図版)ところのもう一幅が寒斎一隅にある。
完瑛は大阪四条派の一翼をにない、とくに商家の床の間を飾るに相応しい詩情あふれる絵画をものした明治の画人として知られるが、味気ない寒斎に静かに鎮座するもの言わぬこの才媛が、月琴を抱えて演奏するのは、画題も同じく「月宮殿」で、こちらは両人ではなく梅園女史ただ独りである。
ここで姉妹のお浚いと、ついでに梅園女史の一子春田について補足しよう。
寛政十年生まれの姉連山とは二十五歳違いで、親子ほども歳が離れている梅園は、安政元(一八五四)年の生まれで、明治三十一年に没しているので、
右月琴秘曲月宮殿題
明治戊寅歳立秋 完瑛画併書 印
との讃からすると、描かれたのはちょうど明治十一(一八七八)年の八月で、翌十二年には、梅園女史は大阪の連山のもとを離れ、姉妹が東西に連立して清楽教授の門戸を張るべく、単身東帰して飯田町に移ったころとは、すでに連載中に触れた。
かくして押しも押されもせぬ清楽大家となった梅園女史の一粒種春田の経歴は、不明なことが多く、さらにどうしたことか名家の出でありながらその生没年も不詳である。
しかして、まごうかたなき幕末生まれの春田は、生まれ落ちたときから家楽の清楽を聞き育ち、青年期にはすでにひとかどの清楽家として名声高く、ことに胡琴と清笛の演奏家として成長したが、梅園女史東帰二年後の明治十四(一八八一)年には、はれて東京音楽学校の前身である「文部省音楽取調掛」となり、家伝の「清楽」ばかりか「明楽」までをもその研究対象としていた。
あるとき出仕先で、たまたま長崎の魏氏鉅鹿家伝来の「楽譜・楽器」が四散の危機にあることを知ったことで、その保存を力説上申し、ようやく「魏氏明楽資料」は「取調掛御買上」となり、現代にまで遺るようになった、という人知れぬ影の功績がこの春田にはある。
越師の来崎よりもはやく、明末期に長崎に伝来した「魏氏明楽」である。
現在、「江戸期、長崎伝来の中国文人音楽」などをヒックルメテ模索中の筆者には、当然のごと、春田に対して特別の思いはあるものの、如何せん資料が乏しく苦心している。
そうしたなか、明治期を代表する音楽雑誌の一、『音楽雑誌』第二拾五号(明治二十五〔一八九二〕年)十月号に掲載された「長原春田氏の略伝」という、春田自身が提供した文章を、恐らくは音楽雑誌社の主幹四竃訥治(しかまとつじ)(一八五四~一九二八)が添削した記事「長原春田氏の略伝」中に、この春田と明楽との関わる次なる一節があり、その経緯の一端が知れる。
別本「和文注東皐琴譜」より「扶桑操」
熈々日永照扶桑君聖臣賢儀四方淳風
「長原梅園女史月宮殿弾奏図」 1878年 西山晥瑛画
驪宮高處入青雲 仙樂風飄處處聞
緩歌慢舞凝絲竹 盡日君王看不足
漁陽鼙鼓動地來 驚破霓裳羽衣曲
七月七日長生殿 夜半無人私語時
在天願作比翼鳥 在地願為連理枝
天長地久有時尽 此恨綿綿無絶期
六月琴秘曲月宮殿題
19
△目次TOP↑
2018年9月
瘦蘭齋樂事異聞 第173話
東皐心越禅師と琴 廿七 上海図書館蔵『和文注琴譜』 続
琴士作編曲家湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
瓊浦の美形、もとい景とその奇しき楽事にツイツイ道草留連しがちな拙稿。琴学、明楽、清楽と綯い交ぜの記事となるも、愛読者諸賢、幸いにこれを諒とせられたい。
越師の遷化後、杉浦琴川の手により十五年を経た宝永七(一七一〇)年の秋、漸く整稿された『東皐琴譜(正本)』であったが、無論、この原書に「唐音ルビ」はなく、三百年間原稿は秘蔵されたまま、ついに上梓されることはなく、それ以降に編まれた各種『東皐琴譜』には、おおむね片仮名の「唐音ルビ」が添付され、書名も略して「琴譜」としたものが多い。就中、幕末明治期にはるばる東都から北京に齎せられた桂川月池旧蔵「琴譜」を入手した周慶雲。当時はそうした伝統と越師の来歴を知る由もなく、自著『琴書存目』編纂のため、便宜上これを「和文注琴譜」としたのであった。してみれば、前号冒頭ご紹介の無名「琴譜」も、中国側からすれば、たしかに同様海を渡った「和文注琴譜」であることに相違ない。
ここで前号に続く道に戻り、音楽取調掛に任命され出仕した長原春田(はるた)(一八五九~没年不詳)と明楽とのこととなる。
化政期から幕末にかけ、魏氏伝来の「明楽」はなお数人の高弟やその子弟らによって細々と伝承されてはいたが、折から新来の「清楽」流行に伴い、明楽家の楽識は初期の清楽の受け皿となり、またあるいは生業をも清楽家に転向鞍替えしたため、気息奄々の明楽はもはや単独では成り立たず、絶絃消滅の危機となり、結果的には清楽中に吸収され、清楽器で演奏されるまでに変化し、やがては治期半ばには「明清楽」と一括呼称されるまでになってしまう。
明治十二(一八七九)年、文部省「音楽取調掛」(後の東京音楽学校、現東京藝術大学)が開設され、二年後の明治十四(一八八一)年、音楽取調掛任命出仕の春田は家系が清楽・名家でもあり、自家薬籠中の清楽のみか絶滅期にあった明楽の貴重性を認識し、いち早くその情況を危惧し、保存に尽力したのである。
そうした春田の明・清両楽に対す保存・研究の各分野に深く及ぶ功績は、音楽正史にこそ名が出ぬものの、真の立役者であり、これを風化させずに現代に語り継がねばならぬが、とくに明治中期にまさに絶絃せんとする刹那の明楽に着目し、魏氏明楽器のみか明楽譜を後世にまで遺した第一の功労者となる。
これらの顛末については順次ご紹介中であるが、すでに春田は清楽大家長原梅園(旧姓平井、連山実妹)女史の一子とご案内したが、家学正統の衣鉢を継ぐものとして、当時第一級の清楽家かつ清笛奏者と嘱望され、また彼自身が改良した「胡琴」の腕前は、後の東京音楽学校ヴァイオリン御雇外人教師を唸らせ、終にはその教師は逆に春田の弟子となったというほどの才能の持主であった。
後年、名遂げた春田の『新撰明笛和楽独習之栞』なる明治三十九(一九〇六)年に公刊中の記譜は、数ある清楽譜中のどれよりも正確精緻な笛譜で、その才能のほども偲ばれるが、実際に彼の演奏(本連載161図版参照)をSP盤で聴けば、その工尺譜は参考程度で、何とも加花工夫された華麗な演奏である。
以下、「長原春田氏の略伝」から明楽との接点を示す抜粋である。
…当時の明楽につき、一般に其器の調法、指法、及楽曲の奏法等疑点多く、信を置くに足らず、必ず外に正しき一定の者あることを悟り、常に此が研究を為すこと年久しかりし、会々明治十四年、文部省音楽取調掛に拝命し、大に此楽の疑点を調ぶるの便を得たり、爾後、職務の余暇、内外の楽書に就き学理を研究し、大に悟る所あり、
春田自身かく念い、かつ調査しつつあるところ、偶然にも、
…時に同職員中、菊池武信なる人あり、曰く、我が郷里肥前梁川(筑後柳河・筆者補)に、明の朱春(舜・筆者補)水より直伝を受けし明楽ありて、世々藩楽たり、今其末流を汲むもの数人ありと、氏之を聞き、雀躍して大に喜び、直ちに抱懐する個所を認め、立花家に就き、其取調を請ひしに、碓井潔水氏(梁川明楽伝来師五世の晩孫)の答書を得て、初めて疑点を解することを得たりと雖も、未だ満足の点に至らざりし、
時に人あり、氏に告て曰く、崎陽に鉅鹿という人あり、同氏は明人の帰化せし者の末裔にして、祖を魏氏と云ふ、其四世の孫富(冨)五郎と云ふものあり、号を君山と呼び、明和の頃京師に遊び、此楽を教授する(こと・筆者補)十余年、此人亡びて現世鉅鹿氏に至るまで、断絶せりと雖とも、楽器、楽譜等は今猶依然として、其人の許に存在せりと、氏聞きて昼思夜夢、其楽器、楽譜を縦覧するの便を得んと熱望して止まず、
時なる哉、同職員中、公用を帯びて崎陽に出張する者あり、氏就て其願事を談じ請て其便を求む、幸なる哉、
其後、其伝来の楽器、楽譜、其外付属品等、悉く文部省音楽取調掛に買上と成り、始めて素懐を達することを得たり、と氏の苦心宜しく思ふ可きなり、其詳細は氏の陳述に係る明楽伝来記中にあり、(此文、音楽雑誌第五号より掲載しあり)
茲に、氏の談話中、此明楽取調の事に至るや、常に語て止ざるの不思議なることあり、夫は、氏の採集に係る該楽譜(魏氏朱氏家伝)の何処より来るも、又、百年来中絶せるにも拘らず、其記譜、及び指法等の正しく符合すること、太鼓、小鼓の鼓法に至るまで、一点の差異なく、実に其正斉驚くに堪たり、又、御買上の付属品中に明の万暦年間に画ける明楽合奏の幅あり、氏自ら模写し、楽譜に添へて、家宝品の内に備へ
氏亦明、清楽のみならず、泰西の楽をも研究せり、甞て音楽所勤務中の余暇、教師独逸人フランツ・エッケルト氏に就き、洋笛の指法を学べり
と、同僚の菊池武信の言に触発され、彼の郷里・旧筑後柳河(川)藩には明の朱舜水直伝の明楽(筆者案?)があり、代々藩楽としてあり、現在でもその末流を汲むものが数人存在する。と言うのである。
新収『和文注琴譜』「秋風辞」
琴川撰『東皐琴譜(正本)』成書以降、江戸通行の各版「東皐琴譜」には、唐音ルビが付されるようになり、右から順次「唐音ルビ」「歌辞」「律名」「減字譜」(琴譜)の構成で、判読に便ならしむべく絶対音の和漢「律名」を付すもあり、雅楽を善くした学者がものしたろう該譜では、日本の「十二律名」が充てられている。
これを仔細に見れば、「平平双下盤盤鳧盤上盤」とあり、「平調(E)、平調、双調(G)、下無(F#)、盤渉(B)盤渉、鳧鐘(G♯)、盤渉、上無(C#)、盤渉」となるが、惜しいかな、若干の齟齬がある。
「長原春田(はるた)肖像」(1859~?)
魏氏明楽を後世に遺した大恩人の春田は、また清(明)笛胡琴の名手でもあった。
11
△目次TOP↑
2018年10月
瘦蘭齋樂事異聞 第174話
魏氏明楽資料顛末記(一)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
瓊浦に纏わるというだけの事由で、強いてこれを延引しようとする拙稿ではある。
折しも長原春田と菊池武信が拙筆の端にかかったを機に、これも長崎港に荷揚げされた魏氏将来の明楽器がたどった数奇な変遷をなぞるべく、暫し越師の異聞は連載二七回をもっていったん離れ、然るべきときになお続稿するとしよう。
ただ、「明楽」についてはすでに何度も連載中に触れるため、新副題「魏氏明楽資料云々」と重筆する箇所も多々あるはず。しかしながら敢えて中途講読諸賢の便ならしむため、大方のご寛容を請う次第である。明楽を将来した魏之琰(一六一七~一六八九)は、明朝崇禎年間末(一六四〇年前後、わが寛永末年)を中心に、安南国、東京(トンキン)国、日本(長崎)の三ヶ国を股にかけて往来した儒(学)商で、後に幕府から華籍のまま定住を許され魏氏鉅鹿家の初祖となる。名を之琰、字は双侯、号は爾潜、一字之琰、一に之瑗、排行は九官といった。
魏家はもともと明朝に仕えた士人の家柄でもあり、之琰は少時より乗船して貿易に携わるまでの十九歳まで、家庭や郷里の絆宮(学校)でかなり「楽」を学んだものと推測される。ただし、それらについての詳細は、いま遺憾ながら不詳である。
家学のゆえか、ことに明楽を善した之琰は、わが俗箏を大成した八橋検校(一六一四~一六八五)とほぼ同時代の人といえば理解しやすいか、またこれを欧州と比較すれば、バロック音楽最盛期のリュリ(一六三二~一六八七)とも重なる。
まずは、いわばこうした大の音楽愛好家の之琰が最終的に長崎に定住してより、魏家に珍蔵された明楽楽器群の顛末に向かうべく、之琰の詳しい事績などは後回しとし、春田と武信のことから進筆しょう。
わが「文部省(モンブセイ)音楽取調係」は明治十二(一八七九)年十月に設置され、同十八(一八八五)年に「音楽取調所」と改組されるが、春田が取調掛を拝命して数年が経過するうちに音楽取調所と改組される前年、ちょうど明治十七(一八八四)年のこと、ひょんなことより明楽取調べは劇的にも、しかも比較的早期に展開しいくことになるが、まずはゆるりと加筆する。
…時に同職員中、菊地武信なる人あり、
と前号稿末に引用したよう、事務官として配属されたのがこの菊池武信である。
おそらくは両人勤務中のとあるとき、武信が春田の「明楽取調べ」の現況を仄聞したのでもあろう、武信がいうには、
…曰く、我が郷里肥前柳河に、明の朱舜水より直伝を受けし明楽ありて、世々藩楽たり、今其末流を汲むもの数人ありと、
と、故郷での風説らしきをいうである。
氏之を聞き、雀躍して大に喜び、直ちに抱懐する個所を認め、立花家に就き、其取調を請ひしに、碓井潔水氏(柳河明楽伝来師五世の晩孫)の答書を得て、初めて疑点を解することを得たりと雖も、未だ満足の点に至らざりし、
これを聴いた春田が欣喜雀躍して当然、早速に柳川の立花家に問い合わせたが、時すでに遅しか、舜水伝来の明楽のあろうはずもなく、充分満足のいく回答は得られなかったものとみえる。しかしこれにより、長崎の地以外にも明楽伝承があったことを知るのである。姫路藩の明楽などはその後の調査で徐々に判明するのではあるが…。(引用中の梁川は柳河、春は舜と筆者訂正)
時に人あり、氏に告て曰く、崎陽に鉅鹿という人あり、同氏は明人の帰化せし者の末裔にして、祖を魏氏と云ふ、
其四世の孫冨五郎と云ふものあり、号を君山と呼び、明和の頃京師に遊び、此楽を教授する(こと)十余年、此人亡びて現世鉅鹿氏に至るまで、断絶せりと雖も、楽器、楽譜等は今猶依然として、其人の許に存在せりと、氏聞きて昼思夜夢、其楽器、楽譜を縦覧するの便を得んと熱望して止まず、
いかにも一時は意気消沈した春田であったが、そこはそれ、「拾う神あれば、捨てる神あり」とばかり、誰々と明記こそせぬものの、さらに新たに有力な情報を得た春田である。実は、これを遡る春田が音楽取調掛に入るの以前、明治十二~三(一八七九~八〇)年のころ、すでに清楽の大家富田渓蓮などの提唱により、好古社錚々の面々により、明楽が一時持て囃されたことがあり、識者や一部好事家の間では知られていて、春田はそうした渓蓮、もしくは周辺の人からの情報を得たのであろう。以後、それこそ春田は昼思夜夢、魏氏明楽の楽器と楽譜を縦(ほしいまま)覧、座右に近く置き、閲覧して一学者として研究してみたいとの熱望やまなくなったのである。そうしてこれが春田の原動力となるうちにも、あたかも天運は春田に味方するかのように、
時なる哉、同職員中、公用を帯びて崎陽に出張する者あり、氏就て其願事を談じ請て其便を求む、幸なる哉、其後、其伝来の楽器、楽譜、其外付属品等、悉く文部省音楽取調掛に買上と成り、始めて素懐を達することを得たり、と氏の苦心宜しく思ふ可きなり、其詳細は氏の陳述に係る明楽伝来記中にあり、(此文、音楽雑誌第五号より掲載しあり)
とばかり、春田の熱意と上奏が功を奏して進展。かくして明楽器と楽譜資料は、左掲の人脈を介しつつ、一括して音楽取調所への譲渡にまで発展しゆくのである。
その過程と春田の「明楽伝来記」は続稿に委ねるとし、それらの人々を挙げれば、柳河(川)藩立花家、碓井潔水(柳河藩明楽伝来師五世の晩孫)、長崎鉅鹿家八世篤義、金貸し田口某、篤義周旋人三田村嘉十郎、音楽取調所春田の上司佐原純一となる。
菊池武信訳『大哉神之愛』 明治21(1888)年東京刊
訳者は著名な英文学者、かつ敬虔な基督教徒で、新教の訳本なども多く、はじめ音楽取調係事務官で四年間勤務し、後には教官として四年間教鞭を執った。
ちなみに書名は「おおいなるかな かみのいつくしみ」である。
「魏氏明楽太鼓二種四葉」
①「魏氏遺愛太鼓」東京藝術大学現蔵
藝大資料館に収蔵される、それこそ長原春田が夢にまで見て苦心蒐集した明楽太鼓であるが、惜しいかな、歴年の瑕瑾で左上の象頭彫刻を欠いている。
②「龍架太鼓図」宝暦9(1759)年 魏氏私家版鉅鹿家蔵
魏氏明楽では元来二種の太鼓があり、君山本人編纂の油印本『魏氏楽器』所収図は、①とは異なる形態の舶載品のようである。
本文中の柳河立花帯刀家で実用演奏された同形の太鼓は、御一新後に帯刀家から市内の日吉神社に奉納され現存する。
③「魏氏楽器図」安永9(1780)年公刊
魏君山直弟子の筒井景周が、師の没後その伝が混滅するを惜しみ、編纂した楽器図所収の太鼓で、1の原物を描いたもの。
大鼓圖 鼓法有六。一曰陰陽,二曰連鼓,三曰三拍子,四曰四拍子,五曰五拍子,六曰雷鼓
④「長原春田写図」明治16(1884)年以降稿本
①の音楽取調所新収の楽器を、春田自身、もしくは画生が臨模したもので、すなわち、③④は①の写生である。
大鼓圖 鼓法有六。一曰陰陽,二曰連鼓,三曰三拍子,四曰四拍子,五曰五拍子,六曰雷鼓
傳曰雷鼓ハ毎曲ノ畢二用
15
△目次TOP↑
2018年11月
瘦蘭齋樂事異聞 第175話
魏氏明楽資料顛末記(二)
湯島聖堂斯文会講師琴士・作編曲家 坂田進一
長原春田の音楽取調掛出仕直後の明治十四(一八八一)年当初、菊池武信から明楽の話を聞いたわけではなさそうである。
なぜならば、武信の音楽取調係勤務は、次掲する「菊池武信略年譜」にあるよう、前後二度あって、最初は明治十七(一八八四)年から同十九(一八八六)年までの四年間を事務方として、ついで教員として明治二十二(一八八九)年から同二十五(一八九二)年までの四年間在職したことが知られるからで、武信が最初の事務職在勤中、校内教官室内でもあろうか、常時明楽のことにアンテナを張っていた春田と、明楽云々のことが話題となった折、たまたまこれを傍らで聞いた九州男児の武信が、それならば故郷筑後柳河にいまも存在する。と話したことが発端といえる。
しかして、この時期を特定できる根拠として、「音楽取調係」は、明治十九(一八八五)年の二月から「音楽取調所」と改称され、さらに明治二十(一八八七)年十月から「東京音楽学校」と改組された経緯があり、春田が苦心周旋した「魏氏楽器」や「楽譜」などには、紛れもなく「音楽取調所」の所蔵印があることから、正式な購入時期は音楽取
調所時代が正しいと断定できるのである。
何にしてもぜひ、明楽「蔭の恩人」となった菊池武信(一八五六~一九二二)の略伝なりともここにご紹介して顕彰の模倣ごととし、謝意の代わりとせずばなるまい。
武信、本姓名を島亘といい、音楽の専門家でこそないが、幼少期に郷里柳河で宣教師から英語を学び、長じて横浜でさらにオルガンをも併修しかつ堪能であったという。明治初期の英語学会や基督教界において、多くの翻訳書出版で活躍した人とある。
「菊池武信略年譜」
安政三(一八五六)年十二月十日 当歳
筑後柳河藩士の家に生まれ、幼少期から漢学と剣術を学ぶ
父菊池信一 母きの
本姓名を島亘という
明治二(一八六九)年 十二歳
英学を学ぶ。
同四(一八七一)年 十四歲
藩命により東京遊学
同六(一八七三)年 十六歲
横浜にて一年間英語を学ぶ
同十一(一八七八)年までの五~六年間、宣教師につき英語、一般教養、オ ルガン、聖書を学びキリスト教に傾倒
同十二(一八七九)年 二十二歳
帰郷し、柳河師範学校小学校訓導
十一月菊池家一家六名受洗
柳河教会設立
同十四(一八八一)年 二十四歲
柳河中学校雇教員
同十五(一八八二)年 二十五歳
山門郡拾番学区学務委員
同十六(一八八三)年 二十六歳
福岡県中学二等教諭柳河中学在勤
同十七(一八八三)年 二十七歳
音楽取調係事務員
三月武信と改名
四月島亘から菊池姓に復す
同十八(一八八七)年 二十八歳
プルーマー著『西教弁』訳刊
チャンブル著『海外名哲士鑑』刊
同十九(一八八六)年 二十九歳
東京の警察署に勤務しつつ『英語発音秘訣』を執筆刊行
同二十(一八八七)年 三十歳
女子教育奨励会書記
同二十二(一八八九)年 三十二歳
東京音楽学校教員
ウィーベ著『音楽訓蒙・学理技術』訳文部省刊
同二十五(一八九二)年 三十五歳
福岡 三池炭坑社 三井鉱山勤務
同二十八(一八九五)年 三十八歳
『大哉神之愛』刊行
同三十(一八九七)年 四十歲
三井鉱山英国人鉄道技師ジョン・アーウィンに雇用される
ブランド著『精霊のはたらき』刊
同三十一(一八九八)年 四十一歳
沖縄県中学、沖縄師範学校、沖縄女学校教員
同三十四(一九〇一)年 四十四歲
福岡県中学修猶館教諭心得
同三十五(一九〇二)年 四十四歲
宮崎県都城中学教諭
同三十九(一九〇六)年 四十九歲
鈴木商店大里製糖社勤務
同四十一(一九〇八)年 五十一歲
『True Christianity & true salvation :
a dialogue between a missionary and a true Christian』著
同四十四(一九一一)年 五十四歲
私塾「鵬搏館」開塾
同四十五(一九一二)年 五十五歳
宮崎県北諸県郡都城商業学校教員
大正五(一九一六)年 六十歲
関東都督民政署嘱託兼旅順高等学校教務
大正十一(一九二二)年 六十六歲
都城にて六月二十一~二十二日没
さて、長崎鉅鹿家には、初祖魏双侯とその子弟近親、後の第四代君山(弟に家督を譲ったら遺愛の「魏氏明楽器」が、激動の幕末期を経てなお、明治初年まで大切に保管されていたが、他の唐通事の家系同様、徳川の扶持を離れてからは、その多くは自活のため、東京や京阪の地に新天地を求めていた。
そんな明治十七(一八八四)年の二月、鉅鹿家第八代当主の祐五郎(篤義)は、フトしたことで百五十円を二年間の期限で借財し、当時、そのカタとして「魏氏明楽器」は、債権者田口某に一札取られ、なおかつ、債務は利息が嵩んで市井への売却寸前、二進も三進も行かぬ状況下にあったが、さすがに天網恢々、疎にして漏らさず、ミューズの神か、はたまた弁天さまの神慮によって、何気ない菊池武信一言の情報は、長原春田の明楽調査にまで発展し、春田新任の上司となった佐原純一へと引き継がれ、春田念願の明楽器購入へと道は開かれるのである。
さらには、長崎での負債者祐五郎と債権者と、東京から全権を委託された佐原との間に立ち、その周旋に担った三田村嘉十郎(詳細不詳)があり、主に佐原と三田村との間でやり取りされた電文や書信の記録が東京藝術大学の資料に遣り、実際の譲渡に至るまでの経緯が明らかになりゆく、その過程は次号となる。
「魏氏明楽器」『好古類纂』
明治41(1908)年刊より
①「管楽器」 好古社刊の該図は、油印本『魏氏楽器図』(宝暦9〔1759〕年内部刊)からの借用で、『魏氏楽器図』安永9(1780)年刊本では、「竹」部に類別される。
「巣笙(笙)」「龍笛」「長簫」「醫篥(篳篥)」の四種であるが、「醫篥」の左側「笙」の上側にある「檀板」は、③の「打楽器」部に置かれる。
②「絃楽器」 同様、「絲」部に類別される。
「琵琶」「月琴」「瑟」(14絃)の三種である。
③「打楽器」 同様、「考撃」部に類別される。
「小鼓」「太鼓」「雲鑼」「檀板」の四種となるが、前号すでにご紹介済みの「太鼓」は省略、しかして正式な「魏氏明楽」使用楽器は、以上の十一種となる。
19
△目次TOP↑
2018年12月
瘦蘭齋樂事異聞 第176話
魏氏明楽資料顛末記(三)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
明治十四(一八八一)年に音楽取調掛となった長原春田。その後数年の魏氏明楽調査過程で、楽器はなおも長崎に存在し、しかも、折しも売立寸前の状況下にあることを知り、誰よりもその購入を力説し、おそらく新上司佐原純一と春田とともに起草したものを、天地人三種の上申書とし、音楽取調所長伊沢修二名で、文部卿大木喬任宛に裁可を仰いだのが次掲の伺書である。
(改行句読筆者)
長嵜縣長嵜區鉅鹿篤義所有之明樂器十一品之儀ハ、別紙天號之通、同人祖魏之琰明末之兵亂ヲ避ケ、安南東京両國ヲ經テ、竟ニ寛文六年吾國に來朝帰化、長嵜住居致シ、鉅鹿ヲ氏トシ罷在候後、寛文十三年上京、内裹ニ於テ明樂ヲ奏シ恩賜ヲ忝シ、又數代ヲ經テ安永年間ニ至り、鉅鹿民部ナル者上京、河原御殿御泉水ニ於テ船樂ヲ奏シ、大ニ堂上方ノ愛顧ヲ蒙リタリ
此民部ハ君山卜號シ、専ラ明樂ヲ教授シ、世間大ニ流行スルニ至ラシメタリト。
然ルニ當今ノ篤義ハ祖先ヨリ八代ノ孫ニ候へハ、該樂器ハ祖先歸化ノ年ヨリ算スルモ、既二二百二十年餘ノ古器ニテ、實ニ傳家ノ重寶ト致居候処、近來漸次困窮ニ陥り、何分保存所持難致場合ニ立至リ候へ共、前述ノ如ク由緒モ有之樂器ヲ、徒ニ商估ノ手ニ賣却候モ残念ノ儀ニ付、博物館若シクハ當所へ献納、又ハ買上相願度旨、別紙地號ノ通、三田村嘉十郎ヲ紹介トシ申來候。
右ハ稀有ノ珎品、殊ニ價モ十一品ニテ、几金百五六拾圓位ニテ、不相當ニモ無之候間、當所参考品トシテ購入致度、依テ別紙人號圖面相添、此段至急仰裁可候也。
明治十八年五月廿六日
音樂取調所長
文部權大書記官 伊澤修二 印
文部卿伯爵大木喬任殿
以下、明楽器保存上にかかわる三名の小伝中、確認のため◎印を付してみよう。
佐原純一(一八四一~一九二〇)
もと佐賀藩上士の家系で、藩命により海軍伝習後、蕃書調所で数学を学び、慶応元(一八六五)年、開成所の数学教授手伝方を拝命し、同二年教授出役。三年二等教授となり、御一新後の明治四(一八七一)年、大学南校の数学中助教広訳方(最高位)となり、同七月文部省編輯司となり『百科全書』を担当。
明治五(一八七二)年八等出仕。同六(一八七三)年には共学舎校主となり、英語、仏語、数学、漢文、書道などを教授する。
◎同十八(一八八五)年九月、音楽取調所一等属御用掛出仕。のち七十九歳没。
伊沢修二(一八五一~一九一七)
高遠藩下士の家系。号は楽石。
明治三(一八七〇)年、十九歳で藩の貢進生として大学南校に入学し、同五(一八七二)年文部省出仕。第一番中学幹事、愛知師範学校校長。同八(一八七五)年から師範学科取調べのため神津専三郎らとともに米国のブリッジウォーター師範学校に派遣され、教育学を学んで帰国後東京師範学校勤務、明治十二(一八七九)年同校校長。
◎兼務で音楽取調掛長、体操伝習所主幹など、洋式体操および小学唱歌の創始と普及に貢献する。明治十九(一八八六)年文部省編輯局局長となり、教科書の編集出版行政に従事。同二十一(一八八八)年東京音楽学校初代校長、翌年国家教育社を創立し社長となり、国家教育主義運動を興す。
明治二十四(一八九一)年野に下り、国家教育社に拠り、学制改革運動、義務教育費国庫負担(義務教育)運動などに挺身。同二十八(一八九五)年、台湾総督府随員として学務部の創設し、翌年から学務部長。帰国後、貴族院議員となり、同三十二(一八九九)から東京高等師範学校校長。同三十六(一九〇三)年「楽石社」を創立し、吃音矯正、視話法の普及に尽力した。著書に『教授真法』(一八七五)、『学校管理法』(一八八二)、『教育学』(一八八三)、『視話法』(一九〇一)があり、六十五歳没。一九五八年『伊沢修二選集』など。
大木喬任(たかとう)(一八三二~一八九九)
通称は幡六、民平、号は其次斎。
佐賀藩士から政界に入り、伯爵叙爵。
藩校弘道館に学び、幕末勤王派として活躍し、維新後に参与、東京府知事、民部卿。
◎明治十六(一八八三)年文部卿、参議兼司法卿、参議兼元老院議長などを歴任し、第一次松方内閣文部大臣を務めたのち、枢密院議長に再任される。六十八歳没。
右揭関係上部のお歴々の名を見るにつけ、彼らの下にあって明楽器保護保存の必要不可欠であることを力説し、必要な手続きを熟し、これを上申した春田の名は、世間当然のことながら何処にも遺留されなく、さらには現在春田の履歴さえも不詳なのである。
ただ春田一つの慰めであったろうは、これら明楽資料が音楽取調所に
無事収められたことで、これらを日常勤務の際に左右に置き、心行くまでの調査が可能となり、自身長年の疑問と直接向き合えたことである。しかるに、惜しいかな、その研究成果は音楽学校に遺らなかった。
ここで当時の百五十円から二百円がどの程度の価値であったかといえば、明楽器の評価が明らかとなろうか。
明治十八(一八八五)年当時の勤め人平均年俸が約百七十八円で、大卒の月給が十円、巡査が六円、大工一日の手間賃が四十七銭、日雇い一日分が十七銭とある。してみれば、平成の今日と比較すれば、二十八年の中級会社員年俸平均が約四百~五百万円で、魏家の明楽器はちょうどその位の価格となる。
伊沢が上司大木文部卿に宛てていうよう、「右ハ稀有ノ珎品、殊ニ價モ十一品ニテ、几金百五六拾圓位ニテ、不相當ニモ無之候」と、いみじくもその貴重性と、十一種の楽器価格の妥当性をいっている。
この後、実際の明楽器が音楽取調所に委譲されゆく経緯と実務の一端とが、東京藝術大学に遺された数種の資料によって明らかとなるため、重言も多いが、拙稿では順次これらを解読することとなる。
長原春田が菊池武信の片言から、明楽初期調査にかかるや、折しもその楽器群がいましも売却の危機にあることを知り、そこで、楽器群を保護し、その市中に泯滅するのを防ぐため、これを音楽取調所が購入すべきと、火急速やかなる決済を上申したところ、音楽取調所の対応も速やかにこれを購入する方向に裁決されたというわけで、電信文などを交え、春田上司となった佐原純一が長崎へ自ら往復出張し、現地の鉅鹿祐五郎(篤義)およびその負債人(田口某)との間に立ち、代言人となった三田村嘉十郎(詳細不詳)と直接交渉し、楽器群とその付属品、および追加品などの価格、長崎港から東京までの輸送費などを決めた上で、晴れて日本郵船の玄海丸で運搬することとなるのである。
魏氏「明笛」東京藝術大学資料館現蔵
明製「龍鳳笛」坂田古典音楽研究所蔵
魏氏明楽器で現在まで流伝するものは大変少なく、もしあるとすれば、概ね江戸期に明楽を学んだものの遺品である。
上図魏氏「明笛」のごとく、魏君山遺愛の楽器群は離散せずに音楽取調所へ納入されたので、他に遺留するものとしては、姫路藩や柳河藩などの楽器が離散し、巷間に流入した可能性があるものか、明朝から直接伝来した楽器のみとなる。
弊小研究所秘蔵の稀少な明朝製「明笛二支一対」は、明朝から伝来した明楽器が、かく巷間になおも存在する証左とはなる。
「明制龍鳳笛概図」坂田古典音楽研究所蔵
「龍笛」と「鳳簫」は一本の竹の上下で製作され、前者には「笛膜孔」があって「竹紙」を貼り、後者にはそれがなく、音色は全く異なる。
箱書と該書付が遺り、その長い経歴を語っている。
27
△目次TOP↑
2019年1月
瘦蘭齋樂事異聞 第177話
魏氏明楽資料顛末記(四)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
明治十八(一八八四)年五月廿六日付けで、時の文部卿大木喬任に裁可を仰いだ音楽取調所長伊沢修二の願書は、その火急性の内容に鑑み、これに対して早くも六月三日に文部省は、
書面之趣聞屇候事
と音楽取調所の魏氏明楽器の購入を認めた。
同所の佐原は翌四日、長崎魏氏鉅鹿家とその債権者田口某との代理人三田村嘉十郎宛に、購入が裁可されたことと、ついては楽器代価問い合わせのための電報を打つ。
長崎 佐原純一
鉅鹿氏所有名楽器買上之儀、別紙御伺相来候處、朱書之通裁可相成候ニ付テハ、年度末ニモ有之候間、左按電報差出可然乎相伺候也、
按
鉅鹿氏之明楽器類買上ル至急送付アレ代価運賃共金高報知アレ
明治十八年六月 音楽取調所
佐原純一
長崎港馬町
三田村嘉十郎 殿
すると、三田村からの返信は案に相違し、音楽取調所宛に不都合の理由を挙げた書簡である。
…豫テ相願置候明樂器之義御買上被下候ニ付、早々送付候様本月四日電報ヲ以テ被仰越段々之御高配深ク奉拝謝候。早速本人(鉅鹿)ヘモ申聞候處、無限相と喜ヒ、不取敢送致之積リヲ以テ、債主方(田口)へ受戾之義談入候處、齟齬之次第有之、夫カ爲困難ナル譯ヲ以テ、値増之義申出候得共、一旦百五十円之所ヲ以テ御買上相願置、今更左様之義何分難取次旨ヲ以テ、断然謝絶仕候得共、本人ニ於テモ其辺之不都合い相弁候。私モ實ニ恐縮之到ニ候得共、別策之施方モ無之候ニ付、一應尊所沾申上試呉候様、再三及歎談其情實ニ於テハ、愍然之次第ニ付、左ニ陳述仕候。
一、明樂器代價百五十円ニテ御買上相願候譯ハ、該樂器抵當ニテ十七年二月田口某ヨリ金百五十円借用セシニ、該樂器無異義返却物カ当其田口某ヨリ談候ニハ、之ヲ利付ノ貸金ニ爲シ置テハ追々利子嵩ミ候。右賣渡之證書ニ改度趣ニ付、其意ニ任セ證書ヲ改メタリ。尤二カ年ノ内ニ元金ヲ以テ受戻ス時、該樂器ハ無異義返却スヘキ旨、口上ニテ約定セシヲ以テナリ。
一、前項之通ニ付、今般元金ヲ以テ受戾之義談込候處、別紙約定書之通、元利皆済之上ナラテハ、樂器返却難爲趣返答候ニ付、當初約束之旨ヲ以テ種々及談判候得共、左様之約定八無之段強情申張候由。嘉十郎云ク、此口上ノミノ約定ヲ爲シタルハ、古風トモ拙トモ云フヘシ。
此鉅鹿タルヤ到テ俗事ニ疎ク、殊ニ人次第ノ人物故、全ク欺カレタルナルヘシ。
一、右之次第ニ付元利計算スレハ、貮百○壱円トナルカ故、此金額ヲ以テ御買上願度、尤モ申訳ノ爲メ、樂器十一品ノ外ニ、別紙弐葉圖面之十二品追加仕度ヨシ。
嘉十郎云ク、此追加之樂器一見致候處、圖面朱書之通破損之品有之。迚モ五拾壱円ノ値ウチハ無之、只不都合之幾分ヲ補候造ト可申之見込候。
書外ニ何カアラハ添付可爲致候得共、近來困難打續、所藏物品悉皆賣却シ、可差出モノ一モ無之ヨシ、御推察可被成下候。
一、右値増之義奉願候譯ハ、貮百壱円ニテ御買上御聞濟被成下候ハハ、夫ヲ用途トシ一時他借金ヲ以テ樂器ヲ受戻シ、該品上納之上代價御下渡ヲ待チテ、一時借用ノ口返償ノ積ニ御座候。
右ハ本人ヨリノ情願ニ候得共、自儘之内情公然難相願候ニ付、尊所迠内々奉伺候間、何分可然御指揮被成下度相願候。實ニ庇陰ヲ以テ御買上之御都合ニ相成候。今日ニ到リ如斯不都合申上候ハ、野生ニ於テモ恐縮之到ニ候得共、前陳之次第御明察可然御聞取被成下度、此段特別之御詮議ヲ以テ、右願旨之御聞届候ニ於テハ、右樂器御省へ上納致度、本人之志願ヲ遂候義ニ付、何分共此上尚御高配奉仰候。此段拝願迠申上度、如此御座候。
謹言
六月十一日三 田村嘉十郎
佐原純一様 侍史
どうであろう。これを読めば、いまでさえ固苦しく、諸手続きに無駄な時間を要すお役所仕事であるはずだが、会計年度末ということもあり、意外にもスンナリと裁可されたに比し、魏氏明楽器購入一件は、却って、長崎サイドの事情で、楽器譲渡は一筋縄でいかなかったことが知れるのである。
債権者田口の無法な五十一円の値上げに対し、音楽取調所はこれを諾する方向で、
十八年六月十六日
長崎佐原純一
鉅鹿氏所有明楽器買上価格之儀ニ付、別紙之通申来候間、左按電信差出可然哉相伺候也
按
明楽器追加品トモ弐百円(ママ)ニテ買上ル本月中着スル様至急送付アレ荷造運搬費ノ高電信ニテ報知アレ
音楽取調所
長崎馬町
所三田村嘉十郎 殿
東京本郷区駒込西片町拾番地
佐原純一 殿
親展
六月十一日投郵(消印東京一八・六・一五)
長崎県長崎区馬町
三田村嘉十郎
代理人三田村は恐縮しつつ、礼を述ぶる。
野生儀御放念可被成下候、却況録相願明楽器之儀、御買上被成早々送付ニ付、本日四日夜ヲ以テ被仰越故、御高配御指揮被成下度相願仕候、実ニ庇護ヲ以テ御買上之御都合ニ相成候、今日ニ至リ□□不都合申上候ハ、野生ニ於テモ恐縮之外ニ候得共、前陳之次第御明察ノ故ト成度候ヲ以テ右願旨被御聞届候ニ於テハ、右楽器上納致度、本人之志願ヲ逐候義ニ付、尚御高配奉仰上候、此段願申上御座候
謹言
六月十一日 三田村嘉十郎
佐原純一様
侍史
これに、次なる債務人田口某の計算書が付帯した。
「計算書」
元金百五拾円也
利金五拾壱円也
申上候より関出シ候迠
一拾七ヶ物利子
金弐百壱円也
右之通ニ御座候也
十八年六月七日
田口
鉅鹿様
音楽取調掛
東京本郷区駒込西片町拾番地
佐原純一
(明治十八年六月十一日投郵)
長崎県長崎対馬町
三田村嘉十郎
「由緒書」 文化(1808)5年12月記
もと鉅鹿家蔵。現東京藝術大学蔵
該鉅鹿家の「由緒書」を記したのが、第5代の明生(1742~1823)で、その続編「続由緒書」は、時代の波に翻弄され、やむなく先祖伝来家宝の明楽器を売却するハメとなった第8代鉅鹿篤義(1830~1892)が、明治11(1878)年春に記した覚書である。正・続ともに魏家の基本資料であるため、いずれ連載中にご紹介せねばならない。
長崎五島の名士初村釣百の家に生まれた篤義は、初名を太作といいのちに鉅鹿家第7代祐十郎の娘信の女婿となり、最後の唐通事役小通事末席となった人だが、いみじくも代理人三田村嘉十郎をして、例文中の
「此口上ノミノ約定ヲ爲シタルハ、古風トモ拙トモ云フへシ。此鉅鹿タルヤ到テ俗事ニ疎ク、殊ニ人次第ノ人物故、全ク欺カレタルナルヘシ」
といわしめた、いわば世間知らずの御曹司であった。
15
△目次TOP↑
2019年2月
瘦蘭齋樂事異聞 第178話
魏氏明楽資料顛末記(五)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
そのはじめ、長原春田等の熱いプレゼンにより、音楽取調所と文部省側は、魏氏遺愛明楽器群の音楽的歴史的価値を認め、その真価を充分認識していた。
それ故、長崎側の言い値百五十円でいったん双方合意はしたものの、足元を見た債権者田口某が鉅鹿家の利息分五十一円をさらに追加請求したに対し、本来ならば、ここで買い手の音楽取調所と文部省側としては、田口の言い分を一蹴し破談して然るべきだが、いうなれば「喉から手が出るほど」入手したい貴重な明楽器であり、却ってその反紳士的で商法にも悖る要求を、大局的見地からこれを黙認したという訳である。もしもこの時、音楽取調所がお上の威光を笠に着てこれを不服とし、明楽器買い上げを蹴っていたならば、世界に類のない魏氏明楽器は四散し、現代に遺らなかったのであるからして、よくぞ我慢したことである!。
以下は、東京藝術大学蔵の明治十六(一八八三)年七月から同十八(一八八四)年八月までの会計に関わる『音楽取調掛時代文書綴巻40 会計局各府県往復書類』からの抜き書きである。
鉅鹿氏所有明楽器買上価格之儀ニ付、別紙之通申来候間、左按電信差出可然哉相伺候也
按
明楽器追加品トモ弐百円ニテ買上ル本月中着スル様至急送付アレ荷造運搬費ノ高電信ニテ報知アレ(濁音音トモ全字)
音楽取調所
長崎馬町
所三田村嘉十郎 殿
<Ⅲ>東京本郷区駒込西片町拾番地
佐原純一 殿
親展
〈Ⅳ> 六月十一日投郵
長崎県長崎区馬町
三田村嘉十郎
消印 東京一八六・一五
處、
野生儀御放念可被成下候、却況録相願明楽器之儀、御買上被成早々送付ニ付、本日四日夜ヲ以テ被仰越故、御高配御指揮被成下度相願仕候、実ニ庇護ヲ以テ御買上之御都合ニ相成候、今日ニ至リ□□不都合申上候い、野生ニ於テモ恐縮之外ニ候得共、前陳之次第御明察ノ故ト成度候ヲ以テ、右願旨被御聞届候ニ於テハ、右楽器上納致度、本人之志願ヲ逐候義ニ付、尚御高配奉仰上候、此段願申上御座候、
謹言
六月十一日 三田村嘉十郎
佐原純一様
侍史
元金百五拾円也
利金五拾 遠円也
申上候より関出し候迠
一拾七ヶ物利子
金弐百遠円也
右之通ニ御座候也
十八年六月七日
田口
鉅鹿様
<Ⅵ>音楽取調掛
東京本郷区駒込西片町拾番地
佐原純一
(明治十八年)六月十一日投郵
長崎県長崎対馬町
三田村嘉十郎
□方々御連絡口御放念可被成下、却説録相願明楽器御買上送付ニ付本日夜を以て仰越え奉附候、早速本人へも申聞候而、無限相磊致之積ヲ以テ、債主方へ受戻の義入有処之次第有之、夫カ有タメ困難ナル訳ヲ以テ、直增之義申出有候得共、一旦百五十円と所ヲ以テ御買上相願候置、今更左様之義、何分難儀被御旨ヲ以テ断然仕候得共、本人ニ於テモ其辺之不都合八、相実ニ外ニ策之施方之無ニ付、一応尊所迄申上呉候様再および談其情、実ニ於テハ次第ニ付左ニ陳述仕候、
一、明楽器代価百五十円ニテ御買上相願訳、諸楽器抵当ニテ十七年二月、田口某ヨリ金五十円借用セシニ、其田口某ヨリヲ利付ノ貸金ニ為シテハ、追々利子相右売渡之証書ニ改度赴ニ付、其意ニ任セ証書ヲ改メタリ、尤二ケ年ノ内ニ元金ヲ以テ受戻ス時ハ、諸楽器無異議返却スへキ旨、口上ニテ御定セシヲ以テナリ
〈Ⅶ〉音楽取調所 用箋
音会第七七五号 十八年六月二十三日
長崎 佐原純一
長崎三田村嘉十郎
按電報可然我
按
明楽器何日積出スカ直ク電信ニテ返辞アレ
<Ⅷ〉十八年六月二十五日
長崎 佐原純一
明楽器積出シ候旨等別紙之通長崎三田村嘉十郎ヨリ電報有之候相供関也
第四四号ナガサキ分局
届 モンブセイ ヲンガク トリシラベショ ヲンヂウ
出 ナガサキ ウママチ
ミタムラ カジウロウ
本文 楽器郵船ニ積ミ入レタ
運賃荷造リ共拾壱円八拾九銭
左記が、長崎からの三田村鉅鹿連名の明楽器発送通知と目録である。
<Ⅸ〉目録
一長簫 一但袋入
一龍笛 一但袋入
一篳篥 二但袋入一筒入一
一檀板 一
一笙 二
一月琴 一
一瑟 一
一同柱 十四
一同爪 二揃
一琵琶 一
一太鼓 一
一同紐 二
一同撥子 二本但皮製
一小鼓 一
一同紫檀台 一
一同同撥子 二本
一雲鑼 一
一同紫檀台 一但引出内ニ象牙ノ撥子一本入
一楽譜及び楽品弾秘調 一套 但七冊
一楽器之図 一冊
一楽舞之図 一幅但箱入
〆
追增之分
一龍笛 一但疵アリ
一篳篥 一右同断
一檀板 一右同断
一笙 一但見虫入
一小鼓の撥子 四本
一太鼓 一但背面ニ疵アリ
一同 一但環ナシ
一篳篥 一筒入但筒口ニ疵アリ
一象牙篳篥 一但袋入
一瑟 一
一瑟柱 十二
一同爪 二揃
一木製太鼓撥子 二木(本)
一楽器図判(版)木一枚
〆
右通御座候以上
明治十八年六月廿三日
三田村嘉十郎
鉅鹿篤義 印
第一号
一月琴 一
一琵琶 一
一雲鑼台 一
〆 三桁
第二号
一長簫 及龍笛 一包
篳篥 二本入一包
一笙 一包
一同 一包
一瑟 一包
一同柱 十四入一包
同爪 四組入一包
一小鼓 一箱
一同台 一包
一同断ノ内 一包
一同撥子 六本入一包
一楽譜及図共 一包
一楽舞図 一箱
一龍笛 一包
一篳篥 三本入一包
一笙 一包
一小鼓 一包
一同 一包
一瑟丿柱 十二入一包
一楽器図判木 一枚
〆 二十桁
第三号
一雲鑼 一箱 但此內ニ台ニ用ル木一ツ入
第四号
一瑟 一箱
〆
第五号
一太鼓 一箱
第六号
一太鼓台 一但六本
一同紐并撥子 一包
同撥子 二本
一檀板 一包
一同 一包
〆 五桁
「魏之琰肖像」鉅鹿家蔵
安南と東京(トンキン)、長崎を股にかけて往来し、後に日本に帰化した長崎魏氏鉅鹿家の初祖在魏之琰(1617~1689)は、名は晧、字を之琰、一に之瑗、また双侯、号は爾潜、排行九官といい、福建省福州府福清県の人である。
魏家はもと明朝に仕えた士人の家柄で、その詳伝改了「由緒書」に譲るとし、長崎帰化に際し、明朝伝来の音楽を携えた。これ即ち「魏氏明楽」である。
39
△目次TOP↑
2019年3月
瘦蘭齋樂事異聞 第179話
魏氏明楽資料顛末記(六)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
明和のはじめ、家伝の明楽を善くすることから、魏家第四代を弟に譲り、勇躍京都に出て明楽を広めて一旗揚げようとした君山こと鉅鹿民部。苦節十年、ようやく明楽が世に認められ、姫路藩では式楽たるべく師範として藩の賓客として迎えられ、安定した伝習がはじめられた矢先、パトロンとなり、何かと君山を引き立ててくれた姫路侯酒井忠恭(ただずみ)(一七一〇~一七七二。号宗雅)が急逝したことで、失意のもと京都を引払い、長崎に帰国する。
その後の百数十年、鉅鹿家の五代から八代当主の間で大切に守られていた魏氏明楽器であったが、拙稿ご案内のごとく、幕末明治初期の奇しき因縁を経て、音楽取調所へとその主を替え、東京は上野の杜の奥深く珍蔵されることになり、明治十八(一八八五)年以来の一世紀以上の歳月、いまも音楽学校の倉庫で静かに眠っている。
左揭するは、「魏氏明楽器」計六箱分を長崎港から日本郵船の玄海丸に積み込んだとの音楽取調所の佐原
純一宛ての報告書で、ついては無事落手の際は、楽器代金と荷造り運搬費用など、別紙請求の通り支払われるよう重ねてご高配くだされとの、世話人三田村嘉十郎と鉅鹿篤義連名の礼状である。
こうして魏氏遺愛の「明楽器群」は、長崎の鉅鹿家の元を離れ、はるばる新生東京の音楽取調所へと運ばれたのである。
<Ⅺ>時下向暑之節ニ候處、着御清通奉我賀候展、野生篤瓦全幸ニロロ尊意候、却説明楽器代価追増之義、過日奉願候處、本月十六日電報以テ御買上ニ被成下候旨、被仰越樣義仕候、依テ本日当港口及之郵船玄海丸へ積込、別紙目録之品数、入入記写之通詰合セ、都合六箱御送附仕候間、回着之上六、御查収被成下度奉願候、楽器代金并運搬費及荷造費八、別紙請求可有差出候ニ付、御下金相来候様、御高配奉仰候、右ニ付テハ程々御手数ヲ奉願恐縮之到ニ奉存候、全ク御高庇ニ因り、御買上之運ニ到リ候故、萬々奉拝謝候、先ハ荷物郵送下報上、兼テ御礼申上度、如此御座候、謹言
十八年六月廿三日
三田邨嘉十郎
鉅鹿篤義
佐原純一殿
明楽器目録はすでに前号掲載した。しかしながら、出自を明朝士人の家格とし、しかも白糸貿易で巨万の富を築いて長崎に定住、唐通事の名家となった鉅鹿家には、明楽器の他にも家祖魏双侯伝来の次掲する家宝があったのである。
記
一董其昌之書 十幅 壱箱
一陳言溥之書 四幅 同
一祝枝山之書 壱幅 同
一劉基之書 壱軸 同
一陳白沙之書 壱軸 同
一安南国王書翰 壱軸 同
一唐国家族ヨリノ書翰 三軸 同
一冷泉卿御詠 壱幅 同
一楽舞図 壱幅 同
一九官夫婦絵像 大壱幅 同
一明服入皮箱 壱箱
但 着物 四つ
蚊帳 壱つ
同 石帯 壱つ但石ハナシ
上〆 壱つ
足袋 弐
一菊模様塗箱 壱箱
但 帽子類 拾壱
楽譜 壹套
会付等 五冊ト一枚
一寿章入唐箱但 壱箱
但 寿章 弐つ
小切 四つ此品別ニ致ス
『由緒書』文化五(一八〇八)年当時の目録には、君山以後の魏家に遺されていた楽器類と、決して多くはないがその他の貴重な家宝が列記され、素封家ならではの第一級品文物の内容に驚かされるのは筆者ばかりではなかろう。
ちなみにこのうち、昭和年代まで遺った数点を、長期間筆者は目睹してきたが、惜しくもその後の整理で、現在はさらに少なくなっている。
さ、ここで中途愛読者諸賢のためと、チョット筆休めの意で視点を変え、『由緒書』や文人間の明楽評判記などを整理し、付帯する話題にも触れてみよう。
魏子明が弟に家督を譲り、家伝の音楽や楽器をもって京都に上り、鉅鹿民部と名乗り君山と号して魏家父祖伝来の音楽普及に勉めた結果、徐々に門弟も定着し、その成果もあってか安永元(一七七二)年には近衛相公の命により、京都河原御殿において大勢の貴人が招かれ、泉水に船を浮かべその中で明楽を演奏することとなる。
先生を師とし門人数十人、而して合奏す
筠圃宮氏之が魁たり、其の名諸王公卿に達す(「君山先生伝」)
これらは君山高弟の一人で、京都上流とコネのあった宮崎筠圃(一七一七~一七七四)の引きによるものだが、当日出席した有栖川宮(一六七二年高松宮から改称)は、
珍しなその品多き物の音の 調べにそへてうたふ唐うた
と詠じ、初めて見聞きする魏氏伝来の明楽に実際の唐風を垣間見る。
またこの御殿に招かれ同席したか、もしくはこれを伝聞したか、別に東本願寺法主が君山師弟を枳穀別殿に召し、船を苑池に浮かべて明楽を奏させた。
さらに和歌の師範で冷泉家中興の祖大納言為村(一七一二~一七七四)卿は、
唐歌をうたふ唐声唐ころも 唐人ならで唐めける船
絲竹にあはす唐歌唐ころも 唐人ならで唐めける船
と詠んで、その唐風三昧の中に演奏された明楽を絶賛したことなど、鉅鹿家『由緒書』には、このことを次のように記している。
従堂上様方厚く蒙御懇命、既ニ安永元辰年、於河原御殿御泉水、船楽を奏候節、先年九官上京之節、於内裡、明楽を奏候儀、
其御記録にも有之由、近衛関白様御意被為遊候、都而本朝にて明楽流行仕候儀い、民部より弘り申候、則其節頂戴仕候御詠歌、
有栖川宮様
珎しなその品多き物の音の 調へにへてうたふからうた
冷泉為村
糸竹に阿はすからうた唐衣 唐人ならで唐免ける舟
右民部儀も、晩年ニハ当所(長崎)に帰郷致、寿を以終申候、
『由緒書』では河原御殿での明楽と、東本願寺枳穀別殿における明楽演奏の記事が混同しているようにも取れるが、「君山先生伝」では別記される。
最後の「寿を以て終り申し候」とは、長崎奉行所を通じお上(幕府)に差し出す公文書では、唐通事の家系が安泰であるため「病死」の語は禁句であったためである。
「楽譜」魏氏君山輯
林謙三旧 蔵関西大学現蔵
清楽名家また音楽取調掛として、魏氏明楽器を散逸一歩手前の危機から救い、さらにこれらから明楽を深く研究しようとした長原春田。
その自筆『魏氏楽譜』表題と、春田識語のある和漢「五音十二律図」なる対照表である。
樂譜 全 魏氏君山輯 春田長藏
五音十二律圖
春田識
黃鍾
宮 宮 合 黃鍾 林鐘
季夏
25
△目次TOP↑
2019年4月
瘦蘭齋樂事異聞 第180話
魏氏明楽資料顛末記(七)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
魏氏鉅鹿家初祖となった魏之琰が初めて来峙したのはわが寛文六(一六六六)年といい、これに前後して東京・安南・長崎と貿易各地を訪れるうちにも、ことに瓊浦の風水を慕うようになり、ついにはお上に願い出て長崎定住を許されたのが同十二(一六七二)年のことである。爾来四百五十年という長き年月が経過するうち、之琰が携えきた「魏氏明楽」の伝承は途絶え、貴重な文物の大半もすでに散逸してしまった。
そんななか、奇跡的に楽譜と楽器のみは長原春田らの手により散逸を免れ、世界における貴重な音楽遺産となって今に伝わり、静かに上野の杜で眠っているのだが、そこで、改めて些末な重複を厭わず、魏氏鉅鹿家のルーツをたどるべく、唯一の資料『由緒書』および『続由緒書』を原文のまま、ここにご紹介する所以である。
ついては、上下に厳格な当時、一般に御家流を用いた文書の慣習では、お上や長上に対する部分を一字分空ける闕字、わが国体に憚っての平出改行は、ニュアンスを伝えるためにそのままとし、旧字と俗字体は適宜変換、送り仮名の不統一もママ、新たに句読点を補足するなど、すべて筆者の責となる。
表紙
「第五百三號 共九 十八冊ノ内」
文化五年辰十二月
由緒書
鉅鹿祐五郎
本文
由緒書
一
初代魏之琰字候(正=侯)號爾潜呼名九官儀、唐国福建省福州府鉅鹿郡之産にして、世明朝に仕へ、明末兵乱之砌、嫡子魏永昌を福建へ残し、故ありて安南国へ赴、又東京国へ参り、数年之內其地之王族を後妻とし、其腹に魏高魏貴之二子を生、其後明末之勢ひ不任、心底
日本之御国風を慕ひ、寛文六午年来朝仕、同十二子年、前二子幷召仕魏憙共に四人、長崎住居御免、翌丑年御願申上候而上京仕、不図も於
内裏、明楽を奏し、御神酒御菓子なと頂戴仕、冥加至極難有仕合奉存候、然処右留守中、安南国之太守より旧好を以、軍用銀子拾貫目之無心申来、其書簡に、今所持仕候得とも、貸渡候之儀ハ(者)相分り不申候、延宝七未年 御奉行所牛込忠左衛門様より格別之 御懇命を以、九官ハもと明官之者故、其儘明服相用候様との御事にて、共ハ元服被仰付、地名を以苗字に御定、魏高を鉅鹿清左衛門、魏貴を清兵衛と御改、御祝儀九官へ黄金五版、二子へ御脇差壱腰、大判老枚宛被下置、清兵衛脇差ハ、爾今所持仕候、御目録も別々に御添へ被下置候得共、九官分而已(のみ)見出し、規左之通ニ御座候、
〔付箋〕此脇差養父十郎代、賊難ニ而紛失仕候
薄具 黄金五版引意
侍生牛込勝登頓首
其後弟清兵衛を本家相続相極、九官儀ハ元禄二巳年寿を以て終り申候、
但、兄清左衛門ハ別家爲致置候処、家名相続之者無之、本家へ引取申候、
一
召仕魏憙儀ハ五平次と改、元禄十一卯年東京通詞被 仰付、御扶持方迄被下置、其子孫五左衛門、当時相続仕居申候、
一
来朝之節、持渡書画之内に、其昌筆赤壁前後之賦、相揃所持仕候処、先年福建へ残置候嫡子魏永昌、其後清朝に仕へ居申候処、其比(頃)其昌之書、唐国におゐても難得候故、前後之内、何れも附与致し呉候様、申来候ニ付、前赤壁ハ差遣し、後赤壁ハ此度差上候、 御用物之内に加り居申候、
一
住居被仰付候より、元禄之初迄ハ、唐館も無之、九官儀自分船にて唐商売仕、運上差上、手代之內山口市左衛門、村田伊左衛門と申もの、両人にて右商売筋取計斗居候、近比迄、巨糸之割合と申伝へ、市中之従ひに相成候、白糸商売ハ、規九官自分自分商売之船より、持渡居候白絲を号にて、鉅ノ字に像り候印にて御座候、
一
妻縁、東京王より守護神として彩色之釈迦像送來、爾今所持仕候、
〔付箋〕薩州侯へ献上
一
九官六十之賀、七十之賀共に清朝高官之親類ともより寿章送来、爾今所持仕候、
一
崇福寺檀越ニ相成候付、本堂并媽姐(祖)堂建立仕、規九官之法名崇福院と申候、
右之内、年月等悉く書載不仕处ハ、類焼之比、記録紛失、或只虫はみ、鑿穿行届不申、其外申伝へも御座候得とも、省略仕候、
一
二代鉅鹿清兵衛儀、相続ニ相立、享保三戌年剃髪いたし、名を道偉と改申候、其後 御奉行所三宅周防守樣之砌、願 江府御用唐画所持之ものより差上候様、被 仰聞候ニ付、彩色美人之画奉差上候処、御返し被成候節、御代官所高木作右衛門様より、左之通之御手帋被下置、爾今所持仕候右本幅ハ、則此度差上候、
御用之內に加り居申候、
鉅鹿道偉老高木作右衛門
此度江府 差上候唐画之内、四幅御写留被仰付候、右四幅之内、其元ゟ被差出候美人之彩色絵も加候、此段吃度申渡ニ而は、無之候內意申聞候様、周防守殿被仰聞被付、如此候、
以上、
十一月十八日
右道偉儀、元文三午年寿を以て終り申候、
『魏氏楽譜総譜』第一曲「江陵楽」 坂田進一訳譜
1989年夏に筆者が訳した音楽史上はじめての記念すべき「魏氏明楽総譜」の第一首目で、これが魏氏伝来の明楽が嚆矢の総譜となり、実際に眼前に楽音が広がったのである。何となれば、これ以前の採譜は、すべて刊本『魏氏楽譜』簡易版からの「斉奏譜」(ユニゾン)であったからである。
右下は「上海音楽学院音楽研究所」蔵印。
15
△目次TOP↑
2019年5月
瘦蘭齋樂事異聞 第181話
魏氏明楽資料顛末記(八)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
寛永十二(一六三五)年から、長崎寄留の唐人は市中雑居を許され、比較的自由に安穏と暮らしていたが、年々貿易が盛んになり、従事者も増加すると、取締りと双方の安全対策を容易ならしむるため、疎開地「唐館」を設ける。これが元禄二(一六八九)年のことで、ちょうど「魏氏明楽の祖」魏之琰(一六一七~一六八九)の没年と重なり、貿易隆盛期には二千人にもおよぶ華人が暮らす館内は、宛ら中国そのままであったと。
以下、魏氏鉅鹿家『由緒書』の続きとなるが、本稿を含む拙稿中、引用古文書の大半は、他の活字翻刻書からの孫引きではなく、その都度原文から新たに筆者が読み下し、本文同様、入念な校正を経たものである。就中、第四代の項目が、家楽「魏氏明楽」流行の礎となった鉅鹿民部こと君山を引用した部分とお分かりになろうか。
但、九官代より巡見
御上使抔御越之節ハ、御本使御
定宿之樣ニ相成数度被入候处御奉行所より被召出、格別之御褒詞抔被置候、其後安永五年之出火前迄ハ、不相替御宿仕候、且又、唐造り座舗為見物、御大名樣被為入候儀ハ、数度之儀ニ御座候、
一
三代鉅鹿太左衛門儀、右道偉子にて、
相続に相立、明和六丑年寿を以て終り申候、
但、九官より此節迄ハ朔御礼相勤、御願筋も、小事ハ御広間へ直伺仕候儀、間々有之候得とも、太左衛門病身ニ付、八朔御礼御断申上候後、其儀無御座候、
一
四代鉅鹿太左衛門儀、先太左衛門子にて、相続ニ相立候処、眼疾ニ而、其上嗣子ニ無之、弟私儀を相続ニ相立、剃髪仕、名を道流と改、隠居仕、享和三亥年、寿を以て終り申候、
但、道流兄幼名留五郎と申者有之候処、
家名相続相好不申、上京仕、名を民部と改、君山と号し、明楽之師範仕候処、酒井雅楽頭様より御扶持被下置候従堂上様方、厚く蒙御懇命、既安永辰年於河原御殿御泉水、船楽を奏候節、先年九官上京之刻、於
内裏明楽を奏候儀者、御記録ニも有之由、
近衛関白様御意被爲遊候、都て本朝にて明楽流行仕候儀、民部より弘り申候、則其節頂戴仕候御詠歌
有栖川宮様
珎(めずらし)な その品多き物の音の 調にそへて 宇たふからうた
冷泉爲村様
絲たけに 合す唐うたから衣 から人ならて からめける舟
右民部儀も、晩年ニハ当所へ帰郷致、寿を以て終り申候、
一
五代私儀、兄道流隠居跡、寛政二戌年より当時迄、相続仕、悴清三郎孫百太郎、一緒罷在候、
右之通ニ御座候以上、
辰十二月 鉅鹿祐五郎
続いて、第八代の鉅鹿篤義がものした「続由緒書」となる。
明治十一年春
続由緒書
鉅鹿篤義
続由緒書
一
五代祐五郎文化五年、幕府御用に付、別冊由緒書相添、旧来持伝へ之諸器物併書画等、桁差出候内、十八桁、
徳川将軍家御用ニ相成、其余百八桁ハ、諸侯方御所望ニ付、差上候由、其節董其昌、劉基、陳白沙、陳言傅、祝枝山等之書ハ難得品々ニ付、持伝候様、被仰聞候趣申伝へ候、且又、翌文化六巳年、幕府より右祐五郎へ白銀五拾枚被下置、孫百太郎へハ旧家之訳を以、新規ニ唐通事役被仰付、年々御役料銀三貫目宛被下置候、
一
六代鉅鹿清三郎儀、天保十一子年、寿を以て終り申し候、
一
七代鉅鹿百太郎、後祐十郎と名を改、唐通事相勤、天保十二巳年、寿を以て終り申候、
一
八代私儀、天保十二丑年、父跡相続、唐通事相勤、引続戊辰御一新之際も其儘被召出、明治十年迄、引続漢訳官ニ而、天津上海抔之在勤も被仰付、相勤候得共、病気ニ付、同年辞表差上、依願免官被仰付候、
別冊之内、不都合并当時所持ニ有之其品、無之訳、
一
初之处ニ、福建省福州府鉅鹿郡と有之候
得共、福建省にハ明朝ニも清朝ニも、福州府鉅鹿部と申処無之、則福建省福州府福清県之間違ニ有之候、且又、鉅鹿二字ハ、魏姓之者、皆鉅鹿氏と唱へ候而、宜く妃、魏姓を賜る時ニ、鉅鹿と云ふ地ニ而、賜り候訳故、魏姓之皆、鉅鹿氏ニ有之、陳姓ハ穎川とか、劉姓へ彭城とか、皆此類也、我国にても、伊藤ハ伊豆国之藤原、佐藤ハ土佐之藤原と云ふ例に彷彿たり、
右者、先代先祖死後、早々唐人屋舗出来、唐人と接待之道絶へ、
且、代々九州大名に金貸ニ而暮し候問、数代後誤り候ものと相見へ、拙者養父より初而、唐通事役被仰付、漸く唐国之人と接待之道相開校位之事ニ有之候、東京王より送り候釈迦牟尼之儀ハ、住居構内ニ釈迦堂を建有之候得共、安永五年失火之折、右堂ハ焼失仕、其後釈迦像ハ其儘致し有候を、当家唐造り之家見物として、明和三年、薩州候(侯)御入ニ相成候縁を以て、同侯へ献上仕候処、右釈迦仏、薩州ニ而霊験有之候ニ而、江戸高輪同侯邸中ニ、堂宇御建立有之、諸家様方より御寄附有之、余程美麗なる堂宇ニ有之候由、承り居候得共、当時ハ如何ともに候哉、
【上】「長崎港図」
寛政4(1792)年 作画者不詳 現長崎県立美術館蔵
渾然一体、和漢蘭(わからん)三国文化が咲き誇る、折しも鉅鹿家第5代祐五郎在世当時の瓊浦鳥瞰図である。
左中
中央右から和の千石船、蘭の大船、左に大小唐船の三種外洋船が繋留され、中央下右にオランダの「出島」、左下部の陸上塀内に「唐館」(俗に唐人屋敷)が描かれる。
【右】「唐船図」
唐船とは、いわゆる「ジャンク」である。南京(藍)、杭州と寧波(白)、福州、泉州(緑)、広東(朱)などと色分けされ、長崎へ来港していた。
通常100~500頓、全長2~30m前後の大小の外洋型貿易船で、定員は50~100名。図例は50人乗りの小型船である。
船主以下船頭、各種上下船員らと、手代、大番頭、果ては北京の落第生を名乗る学者クズレら多彩な商人らが乗り込んでいた。
江南や沿岸部の華人にとっての瓊浦は、比較的近くて魅惑にあふれた外地であり、一度に数ヶ月から数年も唐館に居留し、また何十年間にわたり度々来舶するリピーターも多かった。
19
△目次TOP↑
2019年6月
瘦蘭齋樂事異聞 第182話
魏氏明楽資料顛末記(九)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
ここまで読者諸賢とご一緒に明楽の祖魏氏鉅鹿家の『由緒書』と『続由緒書』を見てきたことで、魏氏家系の粗方が知れもし、また、初祖双侯が一家をして家伝の音楽や楽器をもって京都に上り、内裏で演奏した経緯も散見できた。ただ、この内裏演奏だけは惜しくも文献の確証がなく、あくまで家内『由緒書』の口承にとどまるが…。
しかし、魏双侯之琰四世の孫鉅鹿民部こと魏子明が弟太佐衛門規康に家督を譲り、約百年前の初祖のかそけき伝手を頼りに、同様に都上りし、民部と名乗り君山と号して魏家父祖伝来の明楽普及に勉めた結果、徐々に門弟も定着し出し、その成果もあって、安永元(一七七二)年には近衛相公の命により、京都河原御殿において大勢の貴人が招かれ、泉水に船を浮かべて明楽を演奏し、京都の人士の耳目を驚かしたことは、すでに本連載六(179話2019年3月号)でご紹介した通りである。
魏氏末裔鉅鹿家ではこの時の短冊を未だに所蔵し、一九八九~九〇年
当時の明楽資料調査では、筆者はこの短冊や明服、邸宅図などを含めた貴重な遺品の数々を目賭調査し、簡単な資料集をまとめることができたのである。
ここで、魏君山の明楽伝習と切っても切れない恩人姫路藩主酒井雅楽
守忠恭(ただずみ)(一七一〇~一七七二)侯と君山とのことを、改めてご紹介せねばならない。
こうして明和の初年、勇躍京都に出て明楽を広めて一旗揚げようとした君山こと鉅鹿民部ではあったが、そのはじめは唐画や書法などで糊口を凌ぐよりほかなく、苦節十年にして、君山最初の明楽弟子で後に高弟となった宮崎筠圃(一七一七~一七七四)が京都上つ方とコネもあったことから、その引きなどで、ようやく明楽が世に認められるようになったのである。
重複するが、君山と門弟らによる河原御殿と東本願寺枳殻亭における二度の明楽演奏は、京都人士の耳目を驚かせるには十分で、この二つのデモンストレーションを機に、魏氏明楽は京都ばかりか周辺の藩でも評判となり、理解者や弟子が次第に増加し出すのである。
すると、これらの明楽演奏を伝聞した姫路藩主酒井忠恭は藩の正式な式楽とすべく、明楽師範として賓客として君山を迎え、安定した伝習がはじめられた。
後、姫路侯聞きて之を招き、大いに之を嘆美し、即ち賓礼を以て先生を留めて学ぶ、悉く楽器舞衣を製し、且つ諸近臣をして之を習わせしむ、一時の風靡、将に大行せんとす、(「君山先生伝」)
姫路側の記録には、
…舞楽なども、楽人東儀播磨守を聘して諮り、明楽を創めた。
忠恭は、殊に多趣味で…明楽、蹴鞠、茶、…その他に及んだ。譚筆。
…明楽は当時未だ諸家にはなかったが、忠恭は猪狩律斎等を召し抱へ、中根導惇をして専ら楽府の肝煎をなさしめ、家中の子供等を召し、舞の稽古をさせた。譚筆。…(『姫路城史』)
とある。
例文中の譚筆とは『六臣譚筆』のこと。余談だが、魏氏四代を兄君山から譲られ唐大通事となった四男坊の弟太佐衛門規康が、姫路藩お抱えの明楽の師となった君山のもとを訪れた際、お覚えもめでたくしばしば忠恭侯に召されたことが、
忠恭、長崎大通詞に百挺備射を観覧せしむ
と『姫路城史』に記されているので、兄君山と弟規康は仲の良い兄弟であったことも判ろう。
これらを機に、さらに明楽を学ぶものの増加に伴い、教科書たる『魏氏楽譜』が京都の芸香(うんこう)堂から上梓されたのが明和五(一七六八)年正月のことである。
そんな矢先、惜しくも安永元(一七七二)年七月十三日、パトロンとなり何かと君山を引き立ててくれた忠恭候が急逝してしまったことで、君山もいったん京都に戻るが、門弟たちも次第に離れ、安永三(一七七四)年の冬、君山は病を得て失意のうちに愛用の楽器を携えて故郷の長崎へ帰り、あたかも主君となった酒井忠恭の後を追うかのように四十七歳を最後に、これまた病死してしまうのである。
以後歴代の姫路藩主たちもこれに倣い、明楽を多少は実用したので、藩では幕末までこの伝統は続くことになるのである。
なお、姫路藩には「楽隊」なるものが遺っていた。
明治二(一八六九)年改正の『姫路藩知行取調帳』(『姫路城史』)「寄合」の中に「楽隊」が記載され、楽隊取締支配十二人扶持が六名、五十八人扶持が二十九名の都合三十五人の氏名が列記されている。
人数としてはちょうど舞を入れた明楽の編成にピッタリ符合するが、この楽隊が明楽のためのものか、はたまたいかなるものかは明記されておらず、さらに文政十一(一八二八)年の冬十月、四十年前の江戸藩邸における明楽お披露目の家臣中と、この楽隊中で姓が重なるものは僅かに二名のみであるため、今後この楽隊と明楽との関わりは精査されなければならない。
二代藩主となった酒井忠以(ただざね)(俳号宗雅。一七五六~一七九〇)侯は、養父以上に明楽を奨励した風流才子であった。
実は忠恭の孫であったが早逝した父忠仰に代わって忠恭の養嗣子となり、十八歳で家督を継いだのだが、これも三十八歳で早世してしまう。
その後の百数十年、鉅鹿家の五代から八代当主の間で大切に守られていた魏氏明楽器であったが、幕末明治初期の奇しき因縁を経て、音楽取調所へとその主を替え、東京は上野の杜の奥深く珍蔵され、以来百三十余年間、静かに眠っていることは、読者既知の通りである。
ついで「魏氏明楽の伝習」について少しだけ触れてみよう。従来、魏氏明楽の伝習は君山が上京して諸士に教習した伝、その門下の高弟による伝承、およ君山が姫路侯に賓客待遇で抱えられ姫路藩士へ教習したものなどが主たるものとされ、おおむねの系譜もこれらによるものだが、その詳細はほとんど把握されないなか、弊研究所架蔵の『魏氏楽譜歌集』(別写本)に次のようなものがあり、これにより微細ながらも文化年間末年までの他伝の系譜を補足することができる。
魏之琰四世孫、魏皓字子明号君山、俗称鉅鹿民部一旦遊京師、伝朱明氏之楽、弟子数百、入其室者多、後帰崎陽、以安永甲午之冬、終于家焉
安永三(一七七四)年甲午之冬
君山先生弟子
近衛殿下臣
内藤采男
二條御門番与力
早苗彦之進
曇華院宮官人
結城筑後守
遠枢字環中号龍山、俗称十市、蘇緑、或文甫、家先至遠忠、世居大和国十市郡龍山城、回自号曰龍山、住京兆朱雀野、文化中来遊江都、伝朱明氏之明楽、先生得伝、
於内藤早苗結城三氏、蓋為誓約者内藤氏也、後帰京師、以文化乙亥之秋八月八日、終于京師焉、
文化十二(一八一五)年乙亥之秋八月八日
(『魏氏楽譜歌集』)
原刊『魏氏楽譜後序』 宮崎筠圃
魏氏明楽を学ぶ人士が増加したため、その教科書として君山の高弟らにより編纂され、京都の書肆「芸(うん)香堂」から発兌されたもので、これによって明楽が巷間に認識される契機ともなった。
27
△目次TOP↑
2019年7月
瘦蘭齋樂事異聞 第183話
魏氏明楽資料顛末記(十)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
君山最初の明楽の弟子という栄誉を担った宮崎海西(一七一七~一七七四)は、通称を常之進、字は子常、また筠甫と号した。尾張の海西郡に生まれたので海西と号した。父母に従い京都に遷るが、町の大儒伊藤東涯や蘭嵎に学び経書や史学に通じた。詩書画の三絶にも汚れ、加えて楽、すなわち魏君山の明楽に誰よりも早く着目し、これを率先して学び諸家に紹介したのである。師の魏君山とは十一歳の年長であったが、奇しくも没年を同じくする。
明和五年、この海西の『魏氏楽譜』後序(前号図版参照)中、「予初め謂う、是必ず青山五更の属、…」以下、他伝の「明楽」とは異なる「魏氏明楽」は、合奏音楽の優れた旋律、古詩詞から採られた歌辞など、士人として学んで恥じない音楽であることを力説する。
魏君は長崎の人なり、其の曾祖名は双侯字之琰は、明に仕え某官たり、後乱を避け長崎に来り寓し、遂に家とす。
尤も音楽を善くす、故に其の家に伝習し墜ず、以て君に至る。
君音律に妙解し、自ら謂う、此の楽は唯吾が家に之を伝へ終わんぬ、為に泯滅するも亦惜しからず、乃ち楽器を携えて京に入り、之を同好の人に授け、従学者稍進む。
予初め謂う、是必ず青山五更の属、絲竹に合し之を奏する者は、亦喜ぶべし、既にして之を聞かば、即ち大、然らずんば其の歌は、即ち古の詩詞の曲を歌い、其の声は温柔和暢、固より煩手雑絃の比に非ずと雖も、是金石の楽に非ず、要は庸俗の能く擬い量るべきに非ず、即ち従い学び其の一斑を窺うことを得るは、幸いに至るなり。
此楽は歌を主とし、諸々の楽器は皆歌に倚て之に和すのみ、其の雅俗は則ち姑訓を論ぜず、試みに歌声を捨て、唯絲竹を以て之を奏さば、則ち其の体製を覚えず、甚だ異同有り、但、即ち歌曲に之を詳にすれば、則ち毎曲各々一体を存す、故に愈出て愈奇なること測るべからざるなり、古楽に非さると雖も、所謂上は抗うが如く、下は墜曲の如く、析止の如く、木者を稾するが如し、今皆亦美しからざるを知るべし、歌者の上に在り、匏竹の下に在り、人の声を貴ぶなり、吾益々歌声の已むべからざを信ず。
本邦の用る所も亦金石の楽に非ずして、隋唐の遺曲なり、其の声の容易に之を今に奏し伝来すること、何ぞ其の盛んなる。
但、古には必ず歌有りて今復し聞くべからず、固より恨むべきとなす、吾今歌声の妙有るを知り、益々其の亡するを惜しむ。
曰く歌は詩を本とするか、詩は志を言う、今歌う所は既に国音に非ず、自ら其の楽を習う者に非ざれば、則ち茫として其の唱う所の何事かを知るべからず、然らば則ち歌有りと雖も猶無が如くなり。 …後略…
明和戊子(一七六八)三月
海西宮音識
とあり、海西が魏氏の明楽を学ぶ
に至った顛末および魏氏明楽の特異性と、そうした読書人の音楽を自身も学べるという幸いを、素直に喜んでいることが解る。
君山の京都帷下中、君山所有の楽器一組の全てを高弟の筒井景周が模作させていたし、姫路藩でも伝習にあたり一組の楽器と一揃えの舞衣があり、時おり明楽公演をしていた江戸の藩邸にも略式の一組は常備したものと思われる。
これで魏氏明楽の楽器群は都合四組ほどあったことになるが、もちろん他の伝習生も各自専門とした楽器は自前であったはずである。しかしそれらの大半はすでに散逸してしまい、現在ではその中の一組のみ、しかも魏氏鉅鹿家に伝わったものが無事に遺されて、東京藝術大学に所蔵保管され、長原春田や林謙三がこれらを元に研究したことは、読者諸賢既知のことである。
当然、君山はこの魏家に伝わった楽器一組を持って京の都へ上ったと思われるが、故郷長崎へ引き上げるに際し再び君山はこれらの楽器群を持ち帰ったのだから、元のように魏家には楽器が遺ったことになる。
すでにご紹介した『由緒書』写しには、文化五(一八〇八)年の目録があり、これにより君山以後の魏家に遺された楽器類の詳細が判明し、魏之琰は渡日に際して董其昌の書や祝枝山の書などの当時第一級の明代の文物を携帯していたことも解った。
さ、ここで箸休めの意?で、ご紹介したいのは、君山のパトロンとなった酒井侯姫路藩と「魏氏明楽」その後のことで、「魏氏明楽」が当時未だ在世した旧藩宗主たちとの接点の一つであった証左ともなる出来事である。
明治四十(一九〇七)年の十一月の巻、雑誌『歌舞音曲』第八号の、富田渓蓮稿の「富貴與世」欄に「明楽由来」とする記事中、幕末期を生き残った貴重な明楽の話題がそれである。
幕末から明治期にかけての「音楽の玉手箱」で、邦・清両楽界の元老であった、富田渓蓮ならではの文章で、誤字と思われるのみ訂正し、句読点のみ付して、そのままご紹介することにする。
□明楽の我国へ普及したる由来は本誌へ記載せしが、斯道の暫く衰退せるを雅友●松浦翁、男・同黙斎父子が主唱と成りて、再興を図り、明治十二、三年の頃に至りて、忽ち左の同好者を得たり。
○松平晴山公(定敏旧桑名城主)、
●酒井閑亭公(忠績旧姫路城主)、
●三宅巴老公(旧田原城主。渡辺崋山の主君)、
●森田簾士、
○津田旭庵、
●渡辺柳庵、
●駒井竹波、
豊田翠 ◆蒿 ○富田豊春、
尚、此の外にも四、五人ありしが、●印の分は、松浦氏始め皆黄泉の客となり、目下其音を聴く事もなく遺憾なり。
さて、明楽の合奏は什麼なるものなといふに、先ず雅楽と大同小異、唐音をもて唱歌し、古楽(唐)に比ぶれば葉(派)手なれど、高尚優美なり。魏氏君山翁の愛したる楽器を、先年(明治十四年頃)東京音楽学校にて参考品に購入し、保存しあるを、予周旋して借用し、十月十九日より三ヶ日開会せし第四十七回好古会へ出品せり。
□松浦伯爵の社長たる好古社第四十七回古物展覧会は、特に歌舞音曲に関係の古物を陳列するやう力めたり。松浦家よりは、雅楽及び能楽の珍品数点を博物に乞ふて出品せり。七絃琴は市河米庵翁の寄付したる逸品にて、至極結構なり。之に対して予は、唐本松風閣琴譜を出す。
又、同館の三味線は古近江の作(元宗伯爵家にありしかと)にて、是亦頗る美観なりき。其他一々枚挙するに遑ならず。…後略…
蛇足ながら、例文末の「之に対して予は、唐本松風閣琴譜を出す。」の記載部分は、渓蓮辱知である中根香亭が、これまた門人ともなった伯耆米子の杵村小雅のために借覧したという清朝の名琴譜でもある。
林謙三訳「清平調」1943年初秋 『明楽八調について』より
魏氏明楽を研究した先達が、明治期音楽取調掛の長原春田と、大正末年に東京美術学校彫刻科を畢えた林謙三(1899~1976)のお二方であったが、惜しくも明楽実際の復原にまでは到らなかった。しかし、かく訳譜し、机上の案とはいいながらも、その演奏音を夢裡に描いていたのである。
清平調 小石調
雲想衣裳花想容
春風拂檻露華濃
「中根香亭杵村小雅宛書簡」
『香亭遺文』金港堂1916刊より
直に魏氏明楽とは無縁だが、本文末例文中に示したは、香亭が楽友渓蓮に依頼し、小雅のため『松風閣琴譜』を借覧した部分の切り抜きである。
なお、香亭周辺の楽友・琴友らの影響下、『香亭遺文』所収の「酔迷余録」や「零砕雑筆」(松風閣琴譜)など随筆部には、越師やそれにまつわる江戸の琴事が多出し、香亭自身、斯方に並々ならぬ興味を抱いていたことが解る。
○難問に答へて煩惱即菩提に及ぶ
三日發之尊信並に琴譜到着御報の端書何れも接読致候一昨日富田溪蓮横濱より出京來訪に付琴譜の事面話致したれば緩々留め置かれ御寫し取りにて苦しからざる趣ゆゑ右樣御承知有之度候先頃中の來信中未だ御答致さりしもの二件思ひ出したるに任せ左に申述候杜牧之の詩の貴人頭上不曾饒のは仰せの如く許すの義に御座候世間に公道たる所は貴人の頭でも一向かまはぬこいふ所に在る由を申したる也董華亭の史記の文を許したるは千萬なれど小生は動も
17
△目次TOP↑
2019年8月
瘦蘭齋樂事異聞 第184話
越師故郷・浦江再訪などなど[一]
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
初っ端から私事ではなはだ心苦しいが、上海音楽学院(上音)専家楼の昨年度からの修理で、五月からはやむなく至近な東湖賓館の小部屋である。
もともとここは大公館といわれ、青幣の大親分杜月笙(一八八八~一九五一)の邸宅であったものを改装。旧館と商務(ビジネス)楼に振り分けられていて、市内目抜き通りの淮海中路を隔てた対面の便利な位置にある上音と賓館なので、賓館と特約し、欧米著名な音楽家などの宿舎として優待するが、原則、一般の上音招聘教授連はランクの低い商務楼となっている。
筆者が元気であれば、ホテルから学校正門までは徒歩で約五分、ただ、かなり体調をくずし、極度の疲労を感じはじめたこの五月には、緩歩で
十五分もかかるようになりいかにもおかしい。日夕の通学、近隣の街頭を行き交うにも、かなり不便なため六月は休講し、続く七~八月は幸い夏季休暇でもあるので、この三か月の好機?をとらえ、現在、湯島近場の病院で検査しながら専心加療中である。
しかし先の見通しはあまり芳しくなく、病室では座右の資料もままならず、そこで読者諸賢には大変恐縮だが、今号から当分綿密かつ詳細な記事を避け、拙稿本来の筆意に沿いつつも、あまり肩筋を張らない市井の音楽談義、すなわち「楽事異聞」周辺で茶を濁すことをお許しいただきたい。
で先五月のことである。どうやらこの強行軍が筆者不具合の直接要因となったようだが、東皐心越禅師(越師と尊称)の故郷とされる、浙江省金華市浦江県の音楽家協会と同古琴協会の招聘があり、無理を承知の上、上音教学の間隙を縫い、かの地の心越研究の現況を多少なりとも知ろうと出張ったことである。
江戸「心越流」琴派の基本資料である新楽閑叟編『琴家略伝』冒頭の越師の項目では、その生地について以下のように記していて、短文であるので全文引用ご紹介しよう。
東皐禅師名興儔字心越、明浙江金華府婺郡浦陽人、俗姓蒋氏子、崇禎十二年己卯生、-相伝漢蒋翊裔 出家して寿昌無明禅師の法を嗣く 曹洞宗也水戸の寺を寿昌山と号するもここに出つ-
杭州永福寺に住す、乱を避て我邦に帰投す、于時延宝五年丁巳なり、康熙十五年丙辰六月廿四日杭州を出て、明年丁巳正月十五日長崎着岸、一番南京舩主彭公尹載来ル、同八年庚申京師に来り、天和改元辛酉水戸黄門義公--諱光圀-の招により、江戸え来り、水藩下邸に寓居すといふ、元禄五年壬申水戸城下岱宗山天徳寺に住す、同八年乙亥九月晦日寂、于時年五十七、後に天徳寺を川和田へ移し、其旧趾を以て新に寺を建、寿昌山祗園寺と号す、越師を以て開山の祖とす、
遅れて浅野斧山師編『東皐全集』の「東皐心越禅師伝」によると、
師諱興儔。字心越。初名兆隠。別号東皐。明杭州金華府婺郡浦陽蒋氏子。母陳氏。以崇禎己卯八月二十八日生。活甫八歲投呉門報恩寺。礼俗叔蘭石霊公。薙髮受具。十三遊江淛間。謁覚浪晨夕参究。康熙戊申。依師命登皐亭山謁翠微濶堂。堂令看狗子話。師昼夜不臥。日工夫甚勤。毎入室。師将啓口。堂乃喝。如此者七八次。一日又造室。堂徵詰数番。遂喝出。師於喝下。平生疑団釈然氷解。堂印証付偈曰。
無紋印子印虚空。印破虚空継祖風。
吾家種草恒垂秀。灯伝耀後示千鴻。
時年三十二也。 後略…
とあり、両書ともが金華府婺郡浦陽と、いまの所書きにすれば、越師は、浙江省金華府婺郡浦江県浦陽産の人となるが、いまもって生地を断定することができず、後稿でそうした経緯をご紹介できればと思う傍ら、現在、金華市と浦江県それぞれが「越師はオラが土地さが産んだ偉人」とて、故郷争いをしてどちらも譲らない状況である。
実は、一九九〇年代に一度、二〇〇〇年代に二度ほどこの地を訪れたことがある。
この五月のこと、都合四度目の訪問となる機会があった。というのは、かの地浦江県の音楽家協会と古琴協会の協賛で、「琴兮帰来」と銘打つ越師の記念会を催すから、ついてはぜひとも坂田先生を主賓にお招きし、盛大に式典を開催したいとのこと。
その大きな理由として、
一には越師の故郷であること。
一には坂田編『中国版・東皐琴譜正本』が、約三百数十年ぶりにめでたくも越師の故郷浦江県に戻ったことを祝う。
との主旨である。
そこで上音講義の日程を調整し、その間隙を縫って、五月十六日の夜分、我が学生でもある大学院三年生の葉姐を伴い、まずは学校近くの地下鉄「襄陽南路」から「虹橋駅」へ。そこから高速鉄道(新幹線)の滬昆線に乗り替え、約一時間半ほどで義烏までである。義烏はひところ、アパレル・ファッション関係の企業であふれたし、百均製品の集散地としても栄えたで、ご存じの方も多い中都市である。
当初、金華まで行き在来線に乗り換え浦江までと、独りよがりの道程を考えていたところ、間近になって音楽家協会からの連絡で、一つ手前の義烏のほうが都合よく便利であるとの情報を得た。義烏から協会出迎えの車で二十分ほどで浦江に到着。まもなく旧城内にある塔山という小高い丘に建つ、市内第一級の塔山賓館の客となった。
実はこの日の午後、葉姐の修士答弁(口頭試問)が終わるのを待って出かけたので、遅れた到着時間となったが、さらに翌日からの打ち合わせなどがあり、夜も更けてしまったわけである。
「招聘状」浦江県音楽家協会
邀请函
尊敬的坂田先生:
茲定于5月16日~18日在浙江省浦江县挙力“东皋琴乐”回归东皋故里(浦江)系列活動,敬清拔冗参加。浦江欢迎您
浦江县音乐家协会 2019.04.30
「日程表」
“东皋琴乐回归东皋故里”(浦江)系列活劫
行程安排
5月16日嘉寅扱到(浦江塔山寅館)
5月17日上午8:30开幕式曁贈书仪式(浦江县図书悺)
1、領异活;
2、坂田迸一贈书
上午9:30《东皋琴潽》打潽研討会(浦江县図书館)
中国古琴学会会长徐君跃主持
上午10:30徐君趺东皋琴乐传承音乐会(县図书館)
下午 游览仙华山
晚上19:00,“琴兮旧来”音乐会曁銭美紅古琴演奏走亲(东
阳)交流启动仪式(浦江县文図)
5月18日返程
(联系人:銭美紅 申活/微信13758942518)
坂田先生,您好!
请把您要在“琴兮归来”音乐会上的演奏节目,还有您的照片和简介一起发給我们。感謝您的支持!
浦江县音乐家协会 2019.05.09
「蔣氏宗祠」於浦江県黄宅鎮
2019年5月18日、前夜、越師の余徳を偲ぶ音楽会を終え、越師生地とされる蔣氏一族祠前に佇む筆者。
15
△目次TOP↑
2019年10月
瘦蘭齋樂事異聞 第185話
越師故郷・浦江再訪などなど[二]
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
想えば二〇〇四年五月からの拙稿連載中、やむなく前号一回分の穴を空けることになり、ここに愛読者諸賢のご寛恕を乞う。
しかして、重筆・前後不順の「楽事異聞」なるユルイ内容も、なお必要とあればそうもいくまいが、つけても、せっかく越師故郷の浦江まで足を延ばしたからには、も少し蛇足を加えようとの老爺心。
古来、われわれ琴界では、越師は、
金華府婺郡浦陽の人「琴家略伝」
ということになっていて、これは前号ご紹介ずみだが、越師自身の筆記には、
東皐心越、諱興儔、本貫婺郡浦陽蒋氏子 「東渡編年略」
とのみあるだけで、これではいかにも大まかすぎる。
「婺」とは、元来二十八星宿の名の一で、「金華」と関わる語源は、
金星与婺女星争華之地
なる故事を出典とし、これから南朝陳代には東陽郡を金華といい、次ぐる隋代からは連綿と婺(州)を金華と称し、元代の寧越府を経て、再度金華府の称にもどり、明の成化年間、金華府下の金華県を中心とし、西に蘭渓、東に東陽、同じく東に義烏、南に永康、南西に武義、北に浦陽、西西に陽渓の七県を置き、併せて「金華八婺」と呼称したと。しからば、越師生誕崇禎年間はこの後のことで、清初以来、この地の管轄と線引きはたびたび変更され、いまは浦江第一の大鎮・黄宅鎮に併合されている。
現行の市県制度によれば、省→市→県→鎮(郷)→村となり、改めて前記越師の生地をいまの所書きに整理すると、
浙江省金華市浦江県黄宅鎮蒋宅村となり、また巷間、
小小金華府、大大蘭渓県
と俗に揶揄されるよう、越師生地は金華市、浦江県、蘭渓市などが、それぞれに「郷土の知られざる名人」とて、顕彰やら記念事業を、別々に画策している状態である。
五月十六日、浦江県音楽家協会の要請で、上音講義の合間を縫って研究生葉姐と同道し、夜行の高鉄で一つ手前の義烏駅に夜分着いたことは、前号述べた通り。
浦江県内の中心、県政府の近くに塔山なる小高い地の一角に位置する塔山賓館。その幹部が利用するという一号館に旅装を解き、さらにメインとなる翌十七日の打ち合わせなどで夜も更け、早々に就寝した。
明けて八時の朝食後、塔山の麓すぐに位置する浦江県図書館へ徒歩で行くと、まずは八時半開会の「開幕贈書式典」である。
この開幕とは、言わずもがな東皐心越禅師(越師)記念の「琴兮帰来」なる一連の記念会開幕式との謂いで、贈書とは、越師が幼年のおり出家し、浦江を出郷したのが約三百七十年前。以降の幼少・少年青年期のころ、仏道修行の傍ら江南各地で学んだであろう琴譜類を日本に携え、これに新たに日本で作曲した『扶桑操』を併せた琴譜集、すなわち『東皐琴譜』が、海外の琴弟子人見竹洞と杉浦琴川によってようやく編纂された原本は、諸般の事情で三百年間出版されることができなかったが、二〇〇一年、筆者により東京で『東皐琴譜正本』として上梓され、さらにその改訂中国版が十五年後の二〇一六年、上海音楽出版社から中国全土に公刊されたため、これを改めて越師の故郷に里帰りさせるという意味合いから、筆者に白羽の矢があたり、浦江行が実現したことを指すものである。
次いで九時半、同図書館で「打譜検討会」があり、所の古琴家、音楽家、心越研究家、郷土史家などにより、それぞれ発表や意見があるうち、筆者も「東皐琴譜の成立」という題で講演をし、さらに十一時からは記念の「古琴音楽会」が執行され、主として市内の愛好家たちの和やかな演奏があったのだが、肝心の『東皐琴譜』所収の曲はほとんどなく、これを機に「正本」から学びとり、越師の琴学ばかりでなく、宗学をはじめ詩文や絵画、篆刻など、真の意味で総合的研究がなされるよう切望した次第。
「鷲峰亭」にて黄方炎・黄宅鎮鎮長と
越師幼少期から日夕望み親しんだ蒋宅村の官岩山(海抜391m)※。その中腹に「鷲峰亭」(元代創建、文革中破壊、1980年代重修)があり、黄宅鎮幹部連に両脇を支えられ、ようよう登った筆者ではある。
「鷲峰埜樵」越師自刻印譜集(仮題)より
越師はこの「鷲峰亭」から採り、「鷲峰埜樵」と別号自刻、禅余にも忘れがたき故郷を懐旧した。
【上】「東皐心越故里」にて
2018年5月新設
黄宅鎮蒋宅村「蒋氏宗祠」(前号写真。注:越師生家跡ではない)脇のせせらぎ添いの塀を利用した、越師の事績を簡単に紹介するコーナー前で、上音院生の葉琳娜さんと。
今年6月、彼女は修士課程を晴れて卒業、上海歌劇場に就職した。
【下】「浦江県図書館贈書式」
筆者と館長陳偉華女史
13
△目次TOP↑
秋月※官岩→今の官岩山风景区 宋濂《官岩教寺记》、《华光阁记》《重建鹫峰亭记》等に記載
https://www.baike.com/wikiid/3061244923710255606
2019年11月
瘦蘭齋樂事異聞 第186話
越師故郷・浦江再訪などなど[三] 越師在中国の琴事
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
昼食後、浦江琴会のメンツの案内で、越師所縁の「仙華山」へと向かう。
四十年来の琴友で、いまや浙派を代表する大家となった杭州の徐君躍(西湖琴社社長・浙江音楽学院教授・浙江省級非物質文化遺產浙派古琴代表性伝承人)先生と同道し、道観とは別に境内の山の中腹に建つ小さな「心越記念堂」を、すでに四度目の参観をした筆者だが、無論、越師に因む真物が展示されるわけもなく、そのすべては主に日本の祇園寺と達磨寺所蔵資料のコピーであり、いかにも残念である。
仙華山正門には、清末明治年間に日本に留学したことのある、李叔同(一八八〇~一九四二。弘一法師)手跡の「昭霊仙跡」なる扁額と、また山麓の小さな「心越記念堂」前栽には、水戸祇園寺現住小原師の「伝衣鉢」なる建碑もあり、あたかもその仙華山の山懐に抱かれるような大道観は、改修こそしてはあるものの、だいぶ古く、往古は別に仏堂もあり、その一帯で越師は座禅を組み、また琴をも学んだと思われる。
そこで越師は、杭州西湖をこよなく愛した先達林逋(和靖)の作を填詞とし、琴歌「梅花」(又名「瑶芳引」)を東渡後も愛奏したのである。
時丙寅新秋仙華埜樵録
と該譜跋文にはあるが、当然、「丙寅新秋」なる干支は、越師東渡前のものではなく、渡来後の貞享三(一六八六)年を指す。
この年、すでに越師は光圀公の招請で水戸城北三の丸に在り、故地杭州に想いを馳せ、諧音または旧譜を遺失せぬためにも、新たに記録に留めたと断定される所以で、以下、越師の琴歴、ことに中国における曖昧模糊のうちにあるそれを、改めてここに考察する次第。
まず、越師は少年のころより仏道座禅に励み、傍ら「琴書画」三藝の道に親しんだが、そのころの文事歴は自ら語らず、また一切記録せない。なお、仏門における碁は、「機心を養う」とて、忌まれることもあるのに留意されたい。
今号主意の「故国での琴事」につき、越師は頑に師承を語らぬため、民国以来これまでの中国琴界では、清初南京の荘蝶庵(約一六二四~一六六七号蝶庵)を直接の師承とする定説はあるものの、いまもってその確証はない。しかしながら、順治十六(一六五九)年二十一歳のおり、越師は南京を訪れ(越師自筆断片)ているので、その周辺で蝶庵、もしくはその一派との接点があったのやも知れぬ。
さらには、越師が印可を受ける以前、師覚浪道盛(一五五三~一五五九)の命により、皐亭山の翠微闊堂(生没年不詳)の下に参禅したのが康熙六(一六六八)年で、同年すでに蝶庵は没しているし、参禅公案に没頭しているこの時期には、如何に「琴痴」の越師といえども、さすがに琴事に没頭することはなかったのではと推察され、皐亭山参禅前後期に、蝶庵系の琴人との交流中、越師は多く学んだと筆者は見るうち、越師の生涯中、いっとう琴事に耽り、盛んに学んだころは、印可後の杭州永福寺住職としての五年間であったことが明白となり、幸いにも、その証左を筆者編の『東皐琴譜正本』中の琴譜序跋文に散見でき、これを「東皐心越禅師琴学年譜畧」として、中国版同譜巻末に補遺しえた。
これを参考に、越師東渡以前の琴事に限って適宜抜書きしてみれば、多少ながらも越師「琴癖」の一端が見えもし、しかもそこには、今日、越師琴歌の代名詞となったような小曲は見当たらず、却って中曲以上の琴曲であることで、越師琴藝の高き水準がうかがえうるのである。
「東皐心越禅師琴学年譜畧」拔粹
康熙十年辛亥 一六七一 三十三歳
住西湖金華山永福寺
(日)幕臣杉浦正春生(註後改正職【号琴川】編纂琴譜)
八月返婺得流水譜
《辛亥中秋時返婺郡訪永興公後裔得伝其秘之本》(《流水》心越自跋)
(註 永興公主是南朝梁武帝蕭衍長女蕭玉姚)
康熙十二年癸丑 一六七三 三十五歳
秋日於西冷与虚舟老人校訂《鴎鷺忘機》
(註 琴友楮虚舟)
「時癸丑秋日西冷 虚舟老人皐塢山樵同校」(《鴎鷺忘機》心越自跋)
康熙十三年癸丑 一六七四 三十六歳
八月「甲寅桂月于崇山艸堂松石軒」(《高山》心越自跋)
康熙十四年乙卯 一六七五 三十七歳
此間越於書抄永福山房得馬季翁手譜共校無謬手(《雁落平沙》心越自跋)
十二月中旬《中庸》第二十六章諧音
歲単閼嘉平中浣 東臯越杜多諧音(《大哉引》心越自跋)
(註 歳单閼嘉平中浣是卯十二月中)
越師が永福寺から故郷「婺」こと浦江を訪ねたにちなみ、仙華山に戻るとしよう。
境内一角にあるところの名物「麦藁細工」の工芸品売店などを参観し、さらに奥まった茶室に案内され、各種の銘茶をいただき、しばしの疲れを癒し、その晩に開かれる琴会「琴兮帰来」(古琴名家音楽会)の会場である浦江県「文景園」なる立派なホールへ案内される。
アッ!あにはからん、その駐車場で車から降りたときのこと、日本からわざわざ携帯した古琴ケースを、同行者が倒したため、肝心の琴面の漆が傷つき、そのままでは今晩の演奏ができないこととなってしまった。そこで、徐師の愛器を急遽お借りし、何とかその場はごまかしたのだが、実はこの琴こそは、越師がはるばる杭州から日本に携えた王君竹製の一張との姉妹琴であり、明朝萬暦年製の筆者四十数年来の愛琴である。それこそ中国の数ある自称名工といえどもそうそうヤッツケ仕事で修理できるものでもなく、かの玉堂ならずもしばらくは心痛が続きそうではある。(後述)
「蕙花図」徐元白画 筆者蔵
杭州の西湖琴社を興した徐元白(1893~1957)。その男が匡華(1917~1907)で、孫子が君躍(1960~)先生となる。
なお、蘭は一茎一花、蕙は一茎九花(多花)である。
生長烟霞若名中…
墨蘭以助琴興。丙子春徐元白寫於青溪琴社
【右】浦江県仙華山にて
後方の山が仙華山で、山懐にある道観。その前庭
に立つ筆者と上音院生(当時)葉姐。
【下】琴歌「梅花」琴譜と跋文
『東皐琴譜正本』より
越師自らが各地で学び採集し、杭州より携えた自筆琴譜を、琴門の幕儒人見竹洞に編纂を遺命したがならず、竹洞から引継いだ旗本八千石大身の御曹司杉浦正春(後の琴川)が編纂するに際し、家宰小野田東川(百五十石取り)に命じ、明清の名譜に倣い、明朝体活字を模して浄書させしめたものが本来の『東皐琴譜』である。これがため、後の各種異本とは明確に区別されねばならず、とくに筆者が「正本」と名付けて再編復刻したものが『東皐琴譜正本』にほかならぬ。
今般、かくめでたくも、中国版として中国各地、ことに杭州や浦江に里帰りさせたいとの積年の願いが叶ったわけである。
21
△目次TOP↑
2019年12月
瘦蘭齋樂事異聞 第187話
越師故郷・浦江再訪などなど[四]
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
現在、宮内庁三の丸尚蔵館に収納される「琴」は都合七面(張とも)あり、就中、越師将来といわれる古琴が五面現蔵されている。
七面中、残る二面のうち、
一面は、「伝菅原道真公遺愛琴」
一面は、和製無銘の「素琴」
で、越師将来琴ではないため、とまずこの二面は後稿とするが、これら七面のすべては、収蔵以来未調査および未整理のままであったため、いまだ公開されたためしがなかった。
そこで、平成十三(二〇〇一)年から東京文化財研究所の委嘱で筆者らがその調査を担当し、同十六(二〇〇四)年三月、『古楽器の形態と音色に関する総合研究』の一環として、ここにはじめて越師将来古琴の報告書が正式に公開され、これを機に、後に改めて写真撮影し、さらには研究者の要望があれば、該報告書を基本に回答するようになったので、報告書から一面だけだが、越師将来琴をご紹介してみよう。
琴4漆琴「南風」(後銘)
琴式 列子様(式)
伝 なし
旧蔵・官房印 「南風」(小篆)
断文 蛇腹断
徽 蚌徽
雁足 檀木後補
軫 檀木後補
作者 王君竹
胴內墨書銘
龍池内「雲間王君竹造」
「古嬴李藍谷蔵」
箱書 佐藤一斎
「雲間王君竹造」と胴内墨書銘にある王君竹は、明の万暦年間を中心に活躍した琴の名工で、たまたま該報告書の作成者の愛琴と同じ製作者であるため、他の調査対象の古琴よりも多少判明する部分が多い。
万暦丁巳は同四十五(一六一七)年にあたり、明末清初の天下の大勢既に定り、清朝の基礎も固まりつつある時期(秋月※①参照)に相当する。しかし、報告者の琴は昭和年代に中国の師匠筋から伝承したため、次項の佐藤一斎の箱書きとは重ならない。佐藤一斎は箱書きで、東皐心越の来朝と該琴歴は符合するようにも言うが、判然としない。
…心越禅師。師は琴を善くす。其の伝うる所三張、
一に曰く虞舜、
一に曰く聞天、
一に曰く大雅なりと。
並べて、越師の親しく題するに係り、而して此琴独り年代を詳らかにせず。其の由来する所、或いは亦師の伝うる所か。
……参議公(水戸六代藩主徳川治保(秋月※②参照))燕居の時、此琴に接し之を名づけて曰く南風と。且つ親しく之を書し、俾坦(一斎)をして其の由を記させしむ。
王君竹の製琴の遺例は多くはなく、報告者もこれまで他に二、三の事例を管見したのみであるが、明代前・中期にかけての、やや線の細い華奢
な琴式を完全に脱した、洗練された悠揚迫らぬ雄大なフォルムを持ち、音量は豊富、且つ繊細な音響の明代末年製の代表的な古琴であり、明末清初の士大夫階級の間はもとより、民国から解放後にかけてまで大層持て嘲された、明朝璐王製の官琴などよりも高価に売買されたため、よほど入手困難な琴であった。
琴甲(表面)には蛇腹断があるが、裏面には断文がないため、南風の銘を入れた時に、漆の補修をしたことは確実である。その他にも漆の重修痕跡が多い。
第三、第四絃の第六徽下に絃圧による傷痕あり。第六、第九徽の第一舷側に打撲痕あり、漆の填め跡を研磨していない、退光法仕上げである。 天柱は円、地柱は角形である。
岳山が高過ぎたため、削った痕跡がある。
また、岳山には裂傷がある。
(以上『古楽器の形態と音色に関する総合研究』より転載)
前記引用中、「其の由来する所、或いは亦師の伝うる所か」と一斎もいうよう、越師将来琴の可能性が強いのだが、ここに、奇しくもこの「南風」と姉妹琴が日本に存在するのである。
いささか手前味噌に落ちるようだ筆者四十数年来の愛琴がそれで、胴内墨書銘には、
「萬曆丁巳歳雲間王君竹爲
青渓氷壑居士斲於碧霞斎」
とあり、前記「南風」と同じく、越師将来古琴と姉妹琴で、雲間(現松江)の名工王君竹、一六一七年製作の古琴で、しかも、日本にのみ二面が遺留されていることになるのだが、筆者の琴は浦江において緊急に修理を要する事態となり、現在は図版の通り、上海友人で漆の名工Y師の膝下で修理中。ここしばらくは弾奏することはできないが、気をとりなおし、ここで浦江での琴会にもどり、リハーサルへと続くことと相なる。
越師将来古琴「南風」 皇居三の丸尚蔵館蔵
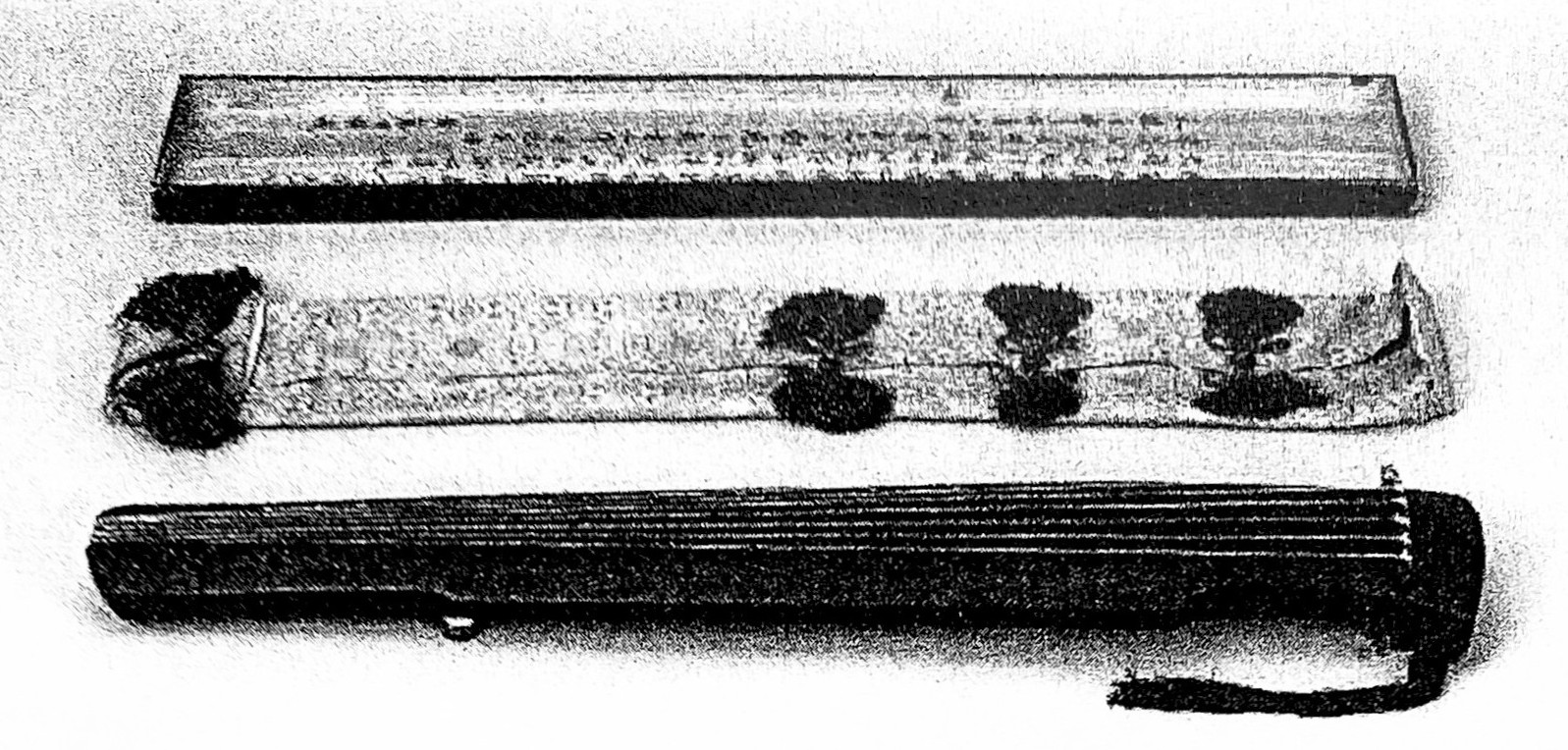 上から箱書、中・琴囊 下・琴面
上から箱書、中・琴囊 下・琴面詳細は、本文を参照されたい。
左は、天保5(1834)年9月、佐藤一斎箱書の部分である。
越師将来姉妹琴「無銘萬暦古琴」 筆者蔵
前号末文、越師故郷の浦江ではからずも傷ついてしまった明朝萬暦年製筆者四十数年来の愛琴は、越師将来琴の姉妹琴である。
23
△目次TOP↑
秋月※①1617年は明末であるが清初ではない。後金が清朝(大清)を名のるは1636年から。
秋月※②参議公に該当し、かつ佐藤一斎に箱書きを命じられるのは徳川治保(1751-1805)でなく、水戸九代藩主徳川斉昭(1800-1860)
2020年1月
瘦蘭齋樂事異聞 第188話
越師故郷・浦江再訪などなど[五]
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
五月十七日午後、浦江県の音楽堂「文景園」控え室で弁当をつかい、リハーサルを終えてあとは本番を待つ。
以下が当日のプログラム写しで、曲目と照らし合わせれば、通行の『東皐琴譜』所収曲はこのうちただの三曲、正本からは十、の一曲のみといういささか寂しい選曲だが、現状ではいかんともしがたい。
琴兮帰来 古琴名家音楽会
節目单
一、《長相思》東皐琴歌 東皐琴筝楽団
二、《瀟湘水雲》琴・銭美紅他
三、《漁歌》古曲琴・徐楽奇
四、《陽関三畳》東皐琴歌・楽団
五、《湖畔楓吟》新曲琴・周享成
六、《浪淘沙》東皐琴歌・陳小剛
七、《流水》琴簫合奏・舞踊 琴・銭美紅 簫・朱建剛 舞・張麗娜
八、《西湖夢尋》創作琴・徐君躍
九、《広陵散》琴琶合奏 琴・銭美紅 琵琶・毛凌燕
十、《雁落平沙》東皐琴譜正本 琴・坂田進一
終幕 尾曲《歌唱祖国》 全員
越師伝来、杉浦琴川編纂本来の『東皐琴譜(正本)』では唐音ルビを用いず、比較的難易度の高い中・大曲を巻首に配置したが、享保・宝暦年間以降、小野田東川がこれらを取捨選択し、江戸市井において初心者のために「初学十六曲」を撰し、はじめて琴譜歌辞の傍らに唐音ルビを補足したことで、難解な琴学を学びやすく教授し出した。
折しも蘐園学派などの唐音学習熱とあいまって、一般学者も学びやすくなり、ことに「初学十六曲」中の琴・坂田進一冒頭に置かれた入門曲四~五曲が、駿河台界隈の聖堂生徒や儒者、文人たちの愛誦するところとなり、以降「心越流(派)琴曲」として確立していく過程で、心越流といえば、かならず唐音で唱われる小曲であるものと、享保期の抄本、宝暦以後の刊本・抄写本類も唐音ルビが附されたため、中華民国以来、中国琴人たちの目には『東皐琴譜』とは、すべて「和文注琴譜」(唐音片仮名ルビつきの琴譜)に類するものとの認識が根底にあるからして、ことにこれから越師を浦江の琴祖として崇めるからには、真摯に①の原譜を基本にして学びとっていかねばならないであろう。
該プログラム中、一、の《長相思》は、『東皐琴譜』から採られた馮延巳の名詞に、越師の諧音校正になるが、北京の李祥霆が打譜(古譜に定拍を与える)し、さらに独自の前奏を加えて編曲したもので、ほとんど原形をとどめない。試みに、
①原譜
②唐音入後譜
③現代打譜
三者三様の楽譜を挙げ、これを比較してみれば、やはり、ごく単純な中に得も言われぬ滋味あふれた旋律と抑揚に裏付けされる①と②が秀逸であると知れるが、学ばねば琴譜から旋律を汲み取ることができず、字面でお伝えできぬのが残念である。
四、の《陽関三畳》は、言わずとも知れた王維の「送元二使安西」をもととした人口に膾炙した名曲だが、杉浦琴川輯の正本には所収されず、後年、心越流として流行するに際し、小野田東川が明清版の琴譜を参考に独自に改編し、「初学十六曲」に加えた小操である。
六、《浪淘沙》は、欧陽脩の詞に越師が諧音校正したもので、他の曲は現在通行中の新・古琴操である。
終幕に《歌唱祖国》を満場の聴衆と大斉唱するのはいかにも赤い中国流だが、最終カーテンコールの席上、思いがけずも浦江音楽家協会から、長年越師と浦江のために尽くした功績への敬意と尊敬の意を含め、浦江在の琴愛好家で、琴製作家斯聞氏自作の琴を各一張づつ、筆者と徐君躍師・銭美紅師に贈呈されたには、実に驚き恐縮した次第であったが、しばし待て! 直前のアクシデントで傷心中の同行院生葉姐が、常々琴を学びたいとの初心を抱いていたことを思い出し、本来筆者へ贈呈されるべき琴を、斯聞師の同意を得た上で、葉姐に進呈することにしたのは、あながち上海に琴二面を持ち帰る不便さの故だけではないこと無論である。
浦江県「琴兮帰来」プログラム
最後の十、で筆者を「東皐琴楽伝承者」とするは誤認で、大いなる妄言である。
「十、《雁落平沙》古琴:坂田迸一(日本“东皋琴乐”传承者)」
いったい、筆者が「心越流の正統な伝承者であると太鼓を敲いて喧伝したこともなければ、斯方研究の第一人者と自慢したこともない」。ゆえに「ただ私は一介の研究者でこそあれ、伝承者では毛頭ない」と訂正すべく何度も提訴したが、筆者の浦江到着以前に印刷されていて刷り直しはならず。
主催側は「琴兮帰来」との大題目の権威づけのため、浦江無辜の民に筆者を心越流正統の伝承者とし、これを皮切りに正統真実の伝承として、地方文化振興の一環として琴を奨励せんとする。これらを遷界の越師はどう見るであろうか。
古琴名家音乐会 暨钱美红古琴演奏走亲启动仪式
为发掘和繁荣东皋古琴艺术,延续东皋艺术和浦江的渊源,提升东皋艺术始于浦江的声望,特举爲“东皋回旧东皋故里”的活動。
东皋心越明未満初浦江人。1676年东渡日本,因琴艺传播的贡献,被誉为日本“近世琴学之祖”。
《东皋琴谱》在我国琴界負有盛名,是东皋心越东渡日本后編撰、整理的琴曲、琴歌集,歌词多为我国历代文学家的作品,上海音乐出版社出版的《东皋琴谱正本(共五册)(精)》由日本东京古典音乐研究所所长坂田进一编写、引进出版,是目前方止法承下来曲目最多(收57曲)、最完整的一份重要乐谱,它的出版开启了我国古谱研究的一个先河,对我国古代音乐史的研究具有重大意义。
东皋心越生于浦江,其琴艺在日本发扬光大,享誉海内外,邀请日本东皋琴乐传承人坂田进一携东皋琴乐回归浦江,作琴学交流,加强中日琴友的交流和学习,是琴界盛事,乃浦江荣幸。
【上右】①《長相思》原譜『東皐琴譜正本』部分
東皐心越禅師伝来。杉浦琴川撰小野田東川浄書
【上左】②《長相思》唐音入り『東皐琴譜』
幕末期湯島在琴師鳥海雪堂。自筆「初学十六曲」より。
筆者坂田書き込みあり
【下左】③《長相思》現代打譜例『和文注琴譜』より 部分
李祥霆改編
13
△目次TOP↑
2020年2月
瘦蘭齋樂事異聞 第189話
越師故郷・浦江再訪などなど[六]
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
いにしえ
いったいに、こたびの浦江行は越師の名を冠した一連の琴会であっ
が、古を大題目としたわりには、本物の古琴や古い琴譜などには短い会期とて一切お目にかかることなく、さらにこの地ならではの「婺劇」、「浦江乱弾」、「浦江道情」などといった、いかにも地方色豊かな戯劇や民間音楽があるものの、そうした音楽関連の古い伝統的な文物にも接する機会も皆無(最終日に少し加えられた)であった。
ましてや現在の浦江に越師所縁の遺物が現存すべくもなく、該行中、筆者は、ただ越師を育んだ浦江現代の景物と熱い人情に触れることができたことを、第一の収穫として心に刻みこみ、これから先は、浦江の古典音楽家や琴人たちの研究と努力の結果如何で、越師ら先人の業績と現代浦江人が時空を超え、現実に音楽的な線上で結ばれることとなるよう、衷心より願ったようなわけである。
さ、翌五月十八日からは、浦江県終了後の訪問地へ向かうべく、かねてより要請をうけていた浙江省最大面積を誇る隣市麗水市の「麗水市古琴協会」会長の晁勝傑師と合流。この晁師は麗水修真国学院「孔子学院」の老師であり、また気功や養生術などにも通じた学者であるが、現在、世界中に創立された孔子学院その他に招かれ、教学にいとまない。
十時には、音楽家協会に依頼してあった『浦江乱弾』関係の資料をいただき、旅寝の塔山賓館を離れ、銭・斯両師送迎の車と晁師の車とで、まもなく旧市内東街にある銭師主宰の「月泉琴社」へ誘われた。
小さな琴社内部を参観し終わるともなく、数少ない「浦江道情」の伝承者である傅興徳老師傅がわざわざ出張り、「漁鼓簡板」を鼓しながら演唱する貴重な一節を聴かせてくださり、耳福・眼福のふたつながら堪能し、望外の至福の時を過ごしたことであった…。が、筆者がこうして漁鼓簡板などの楽曲や楽器に固執する要因はといえば、越師が渡日するに際して、何面もの古琴以外に、漁鼓簡板および、琴律調絃をも兼ねた、越師将来の「紫竹曲笛」(絲竹、崑曲、婺劇などで使用)が祇園寺に遺ることからも、師が幼少より聞き慣れ親しんだであろう、これらの民間音楽と『東皐琴譜正本』所収の琴曲・琴歌には、少なからず関連性があるとみるからに他ならない。
越師故里の黄宅鎮官岩蒋宅村で黄方炎黄宅鎮長らと再度合流、越師の浴びたであろう同じ陽光と風に吹かれて鎮を漫ろ歩きし、蒋氏宗祠や鷲峰亭などを参観したことは、前々号でご紹介した通りで、昼食を喫して浦江の人たちと別れてからは、ひたすら高速道路で四時間ほどの麗水市を目指す。
高速道路の道半ばで、予期せどの大雷雨に見舞われるが、何とかこれを切り抜けて麗水市内までたどり着き、市内蓮都区にあるホテル「万庭大酒店」にチェックインする。
ホテル自慢のバイキング料理に舌鼓をうつほどに、麗水一、二の洞簫吹きである雷徐東氏が合流したので、筆者の希望で、彼に案内され市内の中華書店で地図を求めがてら、ついで別棟のビルにある総支配人の執務室に案内されたのである。
するとそこは書画に溢れた書斎風の贅沢な部屋で、紫焔をとぎれることなく燻らせ、絵筆を握る老板に接待されるうちにも、なんと僧風(当世流行)のナリをした三人の中年オヤジが陸続と参集してくるではないか。しかもかれらそれぞれが洞簫をたしなみ(みな雷氏の生徒らしい)、みながみな杭州の丁森華師傅作の簫を持っていて、これを仔細に見れば、われら琴家が通常吹奏する「琴簫」よりもさらに細い管径のものであることにビックリしついで、珍しくもあるので、お借りして試しに吹奏してみれば、なかなか繊細な良い音が出るではないか。ならばと、彼らと「蘇武牧羊」、「春江花月夜」、「普安呪」その他もろもろの名曲を、簫の合奏で試みれば、遅ればせにやってきた麗水古琴協会副会長周麗萍女史がこれに参戦し、それからは琴簫合奏ということで、数々の琴曲を楽しむこととなり、時のたつのも忘れる。こんなハプニングが時として生じるのも、音楽家ならではの旅中の醍醐味ではある。
翌十九日、市内から三十キロばかり離れた遂昌県石練鎮の「千佛山」を目指す。
そこは、国家AAAA級旅游景区にランク付けされた名勝で、その麓にある三ツ星級のホテル「千佛山酒店」が、その夜の宿舎兼「琴会」会場となる。
このホテルの幹部が前記会長晁氏の学生であった関係で特別な便宜が計られたらしいが、それはおき、鄙の地らしからぬホテル内部の設えは、和風を模した「禅意タタミ室」と銘打ち、かなり凝った部屋で、広くかつかなり贅沢な造りではあった。
市内各地から集った琴友たち五、六十名に紹介され、晩餐を終えると「雅集」がはじまり、三々五々琴を弾き、簫を吹き、日ごろ研鑽の成果を披露し、また茶菓を喫しては、日ごろ抱く琴事上の疑問点や練習方法など腹蔵なく語り合ううちにも、はやくも午前零時をまわってしまう。
「漁鼓簡板」浦江県東街 月泉琴社にて
数少ない「浦江道情」の伝承者 傅興徳 老師傅による演唱。
「蒋氏宗祠外壁」浦江県黄宅鎮官岩蒋宅村
越師生誕の地とされる該村にある、蒋氏一族を祀る廟の外壁に、稚拙に転写された越師自刻印譜からのコピーである。
「麗水市の簫愛好家たちと」
麗水市内中華書店老板執務室における、洞簫吹き雷徐東氏(右から二番目)とその生徒たち。
21
△目次TOP↑
2020年3月
瘦蘭齋樂事異聞 第190話
越師故郷・浦江再訪などなど[七] 麗水から湯島へ
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
浦江や麗水から、今号、唐突にも湯島からの起筆をお許しいただかねばならぬ。というのは、冒頭の写真と本稿は、ここ湯島の高台にある病院でものしたもので、何気にこうして東京に不釣り合いな青空に浮かぶ雲や、眼下のアキバを見ていると、まだ少年であったころの純な気持ちと、それらにつれてこの辺りで遊び廻った想い出に、何とも胸が締め付けられてはキュンとし、さらにこれらを追想し、いま東京と中国を往来しつつ、なお実存する自己の原点と重なるからである。
本郷西片にあった茅屋からは、徒歩か都電、都バスで外に出るよりほかなく、崖下の初音町や柳町、また本郷通りから都電で小学校に通いがてら、帰り道に寄り道し、界隈いたるところに○○をカケまわっていたそのころ、ちょうど湯島聖堂と鉄路を挟んだ対面には、幼心にも印象深い小学校の佇まいにも似た木造の日立の研究所があり、将来、自分もこんなところを拠点に欲しいなどと夢想しつつ、聖堂の論語講座(小学生無料)の帰りしなにアキバに寄り、高架下の電気街で小さな部品を見つけては、小遣いを工夫してバリコン・レシーバーをコサエたり、神保町の古道具屋や東大前の古本屋で訳の分からぬ楽譜を見つけたり、東台、不忍池やアメ横周辺を荒らし、東大の三四郎池でうたた寝したりして喜んでいたものが、中高生となるに従い、多少の智慧が増したものか病膏肩に至り、ってなわけで、いま住む湯島を含めてこの辺りに対する想いには格別なものがあり、一朝一夕には語り尽くせぬも、閑話休題。麗水を簡紹してひとまずこの項を終えねばならぬ。
昨年春の上海音楽学院講義の合間、東皐心越禅師の故郷とされる浦江県についで招聘された麗水市は、浙江省最大の面積をもつ市で、かなり奥まった地のため行く機会とてなかったが、このごろ流行りの高鉄も開通し、従前に比せば行きやすくなった(らしい)。とはいえ、馴染みのない向きには地名を容易に読み間違えやすく、通常、綺麗との意の「麗」字の声調は「第四声」だが、麗水は「第二声」となる。
五月十九日の朝十時、朝食を終え、ホテル前庭一角の人工瀑布を横目に、細い段々を上りきった上部に、これまた人工の「瑶池」があり、その池に面した教学堂ようの楼が、今回の主たる「琴会」会場となり、筆者の「越師の琴事」にかかわる講演、ならびに全体の琴会、また茶会などが開かれ、麗水の会員のほか、さらに南の温州などから、熱心な古琴ファン百人ほどが集ったのだが、帰国後の図書整理と緊急入院などで混乱し、資料がどこぞの箱か見当たらず、麗水市古琴協会や龍泉窯の地などのことは、やむなく後稿に委ねよう。現在、月に二度定期入院する該病院は、寓居からはチャリで三分、緩歩ならば六~七分の町内にあり、従前は「日立病院」(正式名称・小平記念日立病院)という、明治四十三(一九一〇)年創立の「日立製作所」が一九六〇年の創立五十周年に際し、日立創業者の小平浪平(一八七四~一九五一。号晃南)翁を記念し新設した付属病院であったが、二〇一四年四月からは「(大坪会)東都文京病院」と母体組織を替え運営され、施設は居抜きで引き継がれたため、院内の景色は大差なく、待合ロビーや椅子などはあいも変わらぬ落ち着いた空間である。
ここに悪運強くも筆者の手術は成功し、術後の経過も良好。なんとか生かされて、こうしてやり残しの仕事を整理する時間が与えられ、本稿はじめ他の原稿も続けられる元気を与えられた幸運に対し、感謝の意を込め、以下、治療中の該病院と筆者の小さな接点を整理してみたというわけである。
筆者がまだ小石川伝通院わきの蝸牛庵近くに住まいしていたころ、伝通院から大曲に下る安藤坂のマンションにいた生徒の隣室が、ちょうどこの日立病院の院長先生の部屋で、何度かお目にかかったことがある。
しかしある日のことである。ちょうど筆者も午後の同時間帯に都バスに乗っていた春日通りの前方、伝通院バス停の手前で事故がおきてしまった。聞けば、バイクに乗った院長先生のご子息は、数日後に結婚を間近に控えていたための逸り焦る気持ちからか、知らず知らずにわきの車を追い抜いてしまうと、これが無性に気に食わぬと頭にキタ車の運転手は、追いかけざま無法にもバイクをハネ飛ばし、運悪く哀れにも、バラ色の結婚生活を夢に描いていたご子息は亡くなられ、この事故で悲嘆にくれた院長先生は転居されてしまった。
こうした事件後、筆者は本郷三丁目駅真裏にあった小研究所をたたみ、いまの湯島天神男坂下に移っていたが、たまたま当時愚門で学んでいたお茶大院生が、卒業後も引き続き日立コーラス部の伴奏者をつとめていたこともあり、いまもロビーに鎮座するピアノ伴奏での、クリスマス・コンサーを拝聴したり、また、音楽家にとっては致命傷ともいうべき突発性難聴に罹患したときなども、ここの耳鼻科に飛び込んだことが、何とか聴力を取り戻す切っ掛けとなったし、東都文京病院となってからも、眼科にかかったり、また、上海第一の華山医院で治療中の背中の粉瘤が崩れ、始末に負えない処置を、前々回帰国の直後、外科で丁寧に面倒見ていただき大変助かったことなど、それこそ枚挙すればいとまない。
都内でも有数の大病院がここぞとばかりに林立する文京区である。全国の病めるものにとっては、大海の中で見出した灯台の光に、一縷の希望と心身を委ね託す場所柄でもあるが、幸いなことには、湯島男坂下の陋巷音楽家には、天下の東大病院よりも、ココがいっとう近場で使い勝手のよい病院であり、いわば、わが駆け込み寺、希望のハーバーライトなのである。
湯島台の病室からアキバ方面を望む
中央左から二番目の高いビルが、日立本社がお茶の水から移転したダイビルで、かく東都文京病院(旧日立東京病院)から静かにアキバを望めば、「雲は無心にして、以て岫を出ず」ならぬ、わが60年の夢・幻が去来錯綜する。
麗水龍泉「大渓」にて
浙江旅程のすべてを終え、上海帰途のつかの間、案内された青磁で名高い龍泉大渓の川辺でしばし憩うも、「逝く者は斯くの如きか、昼夜を舎てず」と脳裏から離れず…。
古堰画郷「千年樟樹亭」
中央が麗水市古琴協会会長の晁勝傑師で、右隣が副会長の周麗萍女史。
7
△目次TOP↑
2020年4月
瘦蘭齋樂事異聞 第191話
開元琴から雷琴記 玉堂琴へと 鈴木蘭園と三浦蘭阪(上)
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
本連載(二〇〇四年五月)の初っ端に浦上玉堂(一七四五~一八二○)の琴事を取り上げ、以来、折に触れてはその周辺をも経巡ってはい
るが、どうしてどうして一代の琴痴玉堂、ことにその琴趣の深淵にまではなかなか到達しえそうもなく、いまにしてこれらを病床中に読み返せば誤字脱字も多く、いずれ単稿本にでもできるとすれば、その機会には全面改訂せねばならない。
そこで本稿からは視点をかえ、一時、玉堂の琴師となった多紀藍渓はおき、玉堂の楽友となり影響を与えた重要な人物として、京師の儒医鈴木蘭園(一七四一~一七九〇)と、その高弟、河内の三浦蘭阪(一七六五~一八四四)に焦点を当ててみたい。ただし、これとて十二分な資料が手元にあるわけでなく、かなり右顧左眄することとなるは必定、なるべく筆者の姿と足跡を見失わぬように、付かず離れずご陪従あれかし…。
玉堂は生地である備前国岡山池田本藩と支藩岡山新田藩内で、少年のころから夙に楽事に興味を抱き、両藩の書庫といわず周辺郷儒の蔵書から楽書部分を抜き出しては、難解な古楽の楽理を自学していたらしい。
さいわい、玉堂の先達に碩儒熊沢蕃山(了介)があり、礼楽と龍笛や一絃琴などにも堪能であったとあるから、時空を超えて私淑した師匠ともしえたであろうか。
その三浦蘭阪の名を知ったのはかなりの以前のことである。無論、医や本草、また考古や好古方面の人としてではなく、当時の儒学で重んじたところの、楽を学び嗜んだ人としてというに他ならなく、無論、蘭阪は楽家、また専門の楽人として立ったわけではなく、教養としてこれらを学んだのである。
その考古癖を丁寧にナゾッた木崎愛吉編、大正三年郷土史研究会編刊『摂河泉金石文』を参照すれば、
三浦蘭阪(一七六五~一八四三(ママ))
明和二年山城国大山崎の産で、初め社家松田氏、後に坂村の医師三浦懐仙の女婿となって三浦姓を名乗り、名を義徳もしくは一字名で徳、字を季行、また子行、通称を玄純といい、蘭阪、出雲行者、南行存庵、川内古雲行、恬嚢館、酔古堂、南郊惰農などと自号した。
とある。また、医を京都の御典医佐渡法眼に学び、本草学を鈴木蘭園や、小野蘭山(一七二九~一八一〇)らに学び、さらに蘭園からは律学および琴学を学んだが、一絃琴をも善くし、楽友中川蘭窗『板琴知要』のため、南郊惰農なる別号で、次なる序文をものしている。
有其德者必得位其位、苟不得其位則述而待後世、以寓思於絃歌、宣聖猗蘭操非耶、晋孫登鼓一絃琴於蘇門山、雖非同日之論、亦逐其余芳者耳、蘭窓居士鼓板琴以泄其思、著板琴知要
而廣其伝矣、蓋板琴者一絃琴之流也、居士之志招希蘇門之高乎、或欲入猗蘭之室乎、
南郊惰農題(筆者句読)
著に、『衍義傷寒論』『傷寒論逸』『難経正文』『難経辨注』『近古医史』、編に、『律呂弁説』(師蘭園の口述筆記)などの楽書あり、金石にも通じ、考古方面の著述も残している。なお、現在も三浦家は医家として存続しているという。
従来、蘭阪については「琴家略伝」や「本邦琴学伝授略系」(新楽間叟編。未刊)といった、江戸期心越流琴派の系譜にも載らず、多少とも知られた他の琴客に比して、これまでその伝はあまりに知られておらず、当然、その伝も生業の医に偏りがちで、ことに琴癖がありながらその系譜中になかった理由を挙げれば、心越流が盛んなりしころは専ら江戸が中心で、京阪の琴系譜は脆弱であり、一般に趣味の人などを調べるには『京阪著述名家』などに頼っていたからにほかならぬ。
そうした江戸期の琴客たちを調査するなかにも、京師の鈴木蘭園著『律呂弁説』中、蘭阪撰「蘭園先生略伝」その他に接し、就中、三浦徳、また三浦徳季行と明記しあるのを見て、ようやく蘭阪と徳、季行が同一人物と判明したのである。蘭阪の師たる蘭園の口述を筆記した門弟中に三浦徳、季行の名があり、それが蘭阪の別号であると後でようやく知ったようなことで、これがすでに四十年以前のこととなろうか。この門弟たちは独立するに際し師の号蘭園から等しくその蘭字を頂いたらしい。したがって三浦義徳も蘭阪と自号したようである。
この蘭阪の師鈴木蘭園は玉堂に勝るとも劣らぬ琴痴で、著述中よく知られた琴書は『琴学啓蒙』と『雷琴記』の二編のみ。どちらも未刊本で、師蘭園の没後、門人らの講義筆記録をもとに、これを蘭阪が整理し、文化十三(一八一六)年に唯一公刊したものが『律呂弁説』である。
しかして、これまでごく一部の書誌学や本邦医学史を学ぶもの以外には、ほとんど知られない蘭阪の業績とはいえ、それでも次掲する『大阪名家著述目録』にあるデータから粗ましは知ることはできる。
【上】国宝「黒漆七弦(ママ)琴」 東京国立博物館蔵
 法隆寺旧蔵。唐代玄宗皇帝在位時の開元12(724)年に製作され、奈良朝に伝来した古琴。胴内墨書銘に「開元十二年歲在甲子五月五日於九隴縣造」とある。
法隆寺旧蔵。唐代玄宗皇帝在位時の開元12(724)年に製作され、奈良朝に伝来した古琴。胴内墨書銘に「開元十二年歲在甲子五月五日於九隴縣造」とある。当時、蜀(現四川省)の成都近郊九隴県は、琴の名工雷氏一族の本拠地であったため、江戸の琴客間ではこれを俗に「雷氏琴」と推測、そう呼称された。
【下】浦上玉堂自製「玉堂琴」 正宗文庫蔵 昭和12(1937)年製絵葉書より
 「玉堂琴」とは、玉堂が酷愛した「霊和」(雲和説もある)銘の連珠様式の明琴および、その模作琴をも指すが、実は「玉堂清韻」とは前蔵者の「記」であって琴銘ではない。
「玉堂琴」とは、玉堂が酷愛した「霊和」(雲和説もある)銘の連珠様式の明琴および、その模作琴をも指すが、実は「玉堂清韻」とは前蔵者の「記」であって琴銘ではない。玉堂作琴は「雷琴様」が多く、他に十面ほどが現存する。けだし中国では該琴式の遺例は絶無である。
上図法隆寺旧蔵のいわゆる「開元琴」を、鈴木蘭園が拝観して計測した記録『雷琴記』および、蘭園自身の指導のもと、玉堂と琴工とが模作した。
昭和57(1982)年2月、該琴の軫子と繊扣を補足、絲をかけ直し、岡山「鶴鳴館」の「参梅琴会」にて実用、展観した。
【右】鈴木蘭園著『雷琴記』未刊
片山凹泉筆写 国会図書館現蔵
玉堂の楽友となった鈴木蘭園は、明和5(1768)年春季の法隆寺御開帳の際に談判し、ようやく実測した結果を『雷琴記』とし、京阪系の琴人が好んで筆写した琴書となった。
幕末に大阪から湯島に移った鳥海雪堂の自筆本を、琴弟子の御鷹匠同心片山賢(凹泉)が筆写した。(雪堂と賢については本稿19、39、75、76話参照)
【左】同『雷琴記』片山凹泉識語
蘭園稿本から数代後、幕末の琴師鳥海雪堂の筆写本を、雪堂最後期の琴弟子凹泉こと片山賢が嘉永3(1850)年冬に手写した謄写記である。
賢の没後、琴の相弟子井上竹逸に譲与され、同じくこれを竹逸の弟子今泉雄作が師の没後に入手し、貴重な「心越流」を中心とした日本琴学資料の散逸を危惧し、これらを大正4(1915)年の冬、上野一連の文化施設創設期から関わりのあった帝国図書館に、茶道関係書籍とともに一括して寄贈した。
右丁「左琴右書」、左丁「無礙菴」とあるのが、今泉無礙こと雄作の落款印である。
四月二十日平安源龍老和法隆寺記
嘉永三年康成会十月十二日以鳥海師手書
凹泉
13
△目次TOP↑
2020年5月
瘦蘭齋樂事異聞 第192話
開元琴から雷琴記 そして玉堂琴へと[中壱] 蘭阪と蘭園略伝および『雷琴記』
琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一
『大阪名家著述目録』(大正三年三月大阪府立図書館刊)所収するところに、
三浦蘭阪
名義徳 字季行、子行 通称玄純 号蘭阪、出雲行者、南行存庵、恬嚢館、酔古堂 生明和二年 没天保十四年十一月十五日 年七十九 墓河內郡阪村墓地
本姓松田氏来りて懐仙の女婿となる。初め京に出て医を佐渡法眼に本草を鈴木蘭園小野蘭山に学び共に其蘊奥を極め、和漢の書に通ず、又金石文を好み撰述する所多し、
或人物語、衍義傷寒論、雄花艸紙、温古図、川内撫古小識 一、仮初草、近古医史、金石古文模勒帖、九巻類聚、爾雅名物小識 一、傷寒論逸、地志糾謬、治痘小識 一、治痘新書、難経正文、難経弁注、文物古今通志、名物撫古小識 六 天保三年訂刊
とある。
またこれらとは別に、朝日新聞記者の上田芳一郎編『一絃琴』(大正三年五月法木書店刊)所収の小伝で多少補足され、師蘭園の薫陶よろしく、玉堂同様に法隆寺開元琴の模作琴(筆者未見)を愛用、楽書をも多蔵、かくして一絃琴にも傾倒したと
◎三浦蘭坂(ママ)
河内の人、名は義徳、字は季行、出雲行者又は南郊と号す、山城大山崎の社家に生まれて三浦義方(懐仙)の嗣子となる、三浦氏世々医家たるを以て蘭坂亦医を学び、兼ねて鈴木蘭園、小野蘭山の門に学ぶ、故に本草学に精く又国学漢学にも通じ、殊に好古の癖ありて金石文を研究し、名物撫古小識(一巻)、爾雅名物小識(一巻)、河内撫古小識(一巻)等の著あり、又随筆数種あり、是等は皆著者自刻の活字を以て印刷したるものなり、其の友岡田鶴鳴の著したる括嚢軒の記に蘭坂の事を記して、彼未だ曾て書を釈(す)てず、出づるに之を懐にし且歩み且読む、輪に乗るに読書を廃せずといへり、
蘭坂管絃を好み、之に関する書冊を蔵すること幾種なるを知らず、殊に琴を愛し、法隆寺所蔵の開元琴に模して作れる七絃琴あり、又手沢の一絃琴一張あり、子孫之を秘蔵せり、蘭坂一日麦飯真人を訪ひ、其の著『雄花草子』享和二年河内石川紀行に記して曰はく、金剛寺の覚峰(真人)は久しく其の名を聞ければ、夕方近く尋ぬるに、坊に人声あるを聞き、紙に「遊鳥無同友。徘徊迷且啼。園中佳樹在。好許一枝棲」の一詩を認め出るせば、主僧出迎へ大に喜びて座に延きたり、くさぐさの話に殆ど夜を徹す云々と、蘭坂之より一絃琴を真人に学びたるものゝ如し、天保十四年十一月没す、享年七十九
次いで、蘭阪撰の『律呂弁説』巻頭にある、師鈴木蘭園(一七四一~一七九〇)の略伝を挙げ、さらに少し長くはあるが、蘭園の『雷琴記』をナゾッテみよう。さすれば、玉堂と蘭園両者が京師にあっての当初、玉堂は音律の専家然とした長松館の蘭園に強く惹かれたことが解ろうか。
蘭園先生略伝
先生姓ハ源、名ヲ龍、字ハ子雲、蘭園ト号ス。俗称ハ主税、後ニ脩敬ト改ム。
其ノ先近江佐々木氏ノ支族ニ出デ、故ヲ以テ古武器ヲ家蔵シ、世京師ニ在テ商ニ隠ル。
先生頴敏ニシテ読書ヲ好ミ、初メ医ヲ為サント欲シテ、図南浅井翁ニ従ヒ業ヲ受ケ、遂ニ上足ノ弟子為リ。然シテ刀圭ヲ事トセズ、四方ヲ周游シ、学ブ所ニ常師無シ。
東山蓮華王院ノ南、松林中ニト居シ、扁ニ曰ク長松館ト。因テ長松隠士ト称シ、当世諸名家、先生ト結交セザル者無シ。居シテ恒ニ曰ク、学者ハ須ラク六藝ノ囲ニ游ブベシ、典籍章句ニ拘ゝタル者、吾顧スルコト非ザルナリト。
資性強記ニシテ、皇朝典故、経学文章、諸子百家、百般ノ伎藝、撃剣弄数ノ類、所トシテ通暁セザル無ク、其ノ楽ニ於ヒテ最モ力ヲ用イ、声律ヲ妙解シ、律呂ヲ論ゼバ即チ超絶、今ニシテ、古ノ聖人が造律ノ本旨ニ逢ウガ如シ。
故ニ絲管ヲ巧ニシ、殊ニ琴ニ於イテ名ダタルモ、世人ノ或イハ琴家ト為ス者、先生ヲ知ラザル者ナリ。
門ニ於イテ弟子ニ授クニ一事ニ止マラズ、今世自称シ一家ヲ為ス者、往々ニシテ其ノ門ヲ出自トスル者有り。
寛政庚戌ノ年、十月十二日没ス。享年五十。著書若干部、多クハ稿ヲ脱セズ、唯、長沙用薬法、傷寒論脈法觧、琴学啓蒙、雷琴記等、僅カニ脱稿スルノミ。
三浦徳拝撰
蘭阪本草と音律の師は前記のごと鈴木蘭園である。
この蘭園が、明和五(一七六八)年の春、法隆寺の御開帳に際し、役僧とのかなりの強談判の末、ようやく開元琴を拝観し、さらに琴を計測し記録したものが『雷琴記』である。
蘭園の師皆川淇園の序を省き、本文(前号図版参照)を書き下してみよう。
雷琴記
平安源龍撰
明和五年の春、大和の国なる法隆寺、おさめ殿をひらき、昔の宝ともを、人々に見せしむることあり。おほくは上宮太子の御物也。
其中に高麗より奉りし琴のこと有と云ふ。
吾もとより琴を好み、古代の琴を見まほしくおもひしに、是を聞てよろこふこと限りなし。
いさ行てみんとて、友ひとりふたりかたらひたるも、出たつに成て、みなさはり(支障)有てとまりつれは、只ひとり行ぬ。
彼寺に到てみるに、さまさまの宝とも有中に、かの琴聞しよりはみるにまさり、かたへの僧に琴の形うつさまほしきよしを云ふに、よいなりとあれは、ふところにもうけたる筆墨竹はかりなと取いたして、あたりあたりはかりうつしなとするほとに、黄なる衣きたる僧あるか、ふとよりきて、こはなそまさなし(正無し、よくない)ととかむ。
吾初めかたへの僧にこひて、ゆるせしよしをいへと、きゝにたにせす、まつこちとて、御堂の側にゐてゆきて、返す返すくたゝ此ねかひによりてなん、京よりふりはへ(わざわざ)まうて(詣で)きて侍れは、もとより此琴そこ(其許、お主)にしらせたもふとも、いかてか知侍なん。有つる僧のゆるされつれはなん。さらてはいかゝみたりにさるわさもし侍ん。されとことさらにそこ(既出)にきこえふれさりしことのあしとならは、其つみゆるさせたまひて、ねかひのまゝにうつさせたまひてよなと、手をすり、ぬかをさへつき(額を突く、叩頭)て、よろつにこへともきかす。ことあるよしにて出さりぬ。
尚さてやまんことの口おしけれは、ある人に此僧の坊をとふに、弥勒院とおしふ。
扨いきて、つき(従者)ともかたらひて、さまさまいはすれといらへ(返答)もなし。また事有よしにて出ぬ。 (内細字筆者補)
鈴木蘭園述『律呂弁説』部分
文化12(1815)年刊 坂田古典音楽研究所蔵
師蘭園の没後、高弟の筆記録を三浦蘭阪(1765~1844)が校正出版した。
律呂本原一篇。蔡氏所據古説而裁制也。然古說簡奧難通。蔡說亦多誤。是以使後進增生疑惑。今解之辦之。以示後進。學者六世深考篤思。則律呂之道庶幾乎昭明矣。證辧篇。則引原文傍舉諸家之說。羽翼此篇而已。然蔡氏之說既具此篇。故今不別解之。且至章句文義。則先輩有說。故今略之云。
河內 三浦德季行校正
平安 中川故其德再校
「玉堂自作琴と玉堂琴(記)」
昭和8(1933)年売立て目録より
名古屋美術倶楽部の売立て目録にある、玉堂自作の雷琴式(様)の琴および、玉堂自筆「玉堂琴(記)」であるが、「琴記」は、玉堂が酷愛した「玉堂清韻」(記)のある連珠式明琴の説明であって、上にある雷琴式のものとは異なる。
上図の琴は雷琴式で、同様の玉堂模作琴は巷間ままあり、孔子式、連珠式、就中、いっとう多いのが雷琴式である。これまでに何度か玉堂琴として売立てられているが、当然、本文中の明和5年『雷琴記』成立以降の玉堂模作琴と知れる。
17
△目次TOP↑
坂田進一 瘦蘭齋樂事異聞 ©玉堂琴社版 2025.8.3作成
琴詩書画巣 | 古琴の調べ | 中国絵画 | 詩・書 | 中国文人の世界 | 北京信息 | パリ信息 | リンク